
 メインページへ
メインページへ

身のやり場に困ったタウトは、急きょ極東の未知の国日本への亡命を決意。
同年五月三日、 福井県敦賀港に無事上陸、 京都に身をおくことになった。
そして翌日の五月四日、くしくも彼の誕生日、過労と失意のどん底にあったタウトにとって、 生涯忘れえぬものとなったあの桂離宮との衝撃的な出会いを果たすことになる。
筆者は、 かつてその日の桂離宮拝観の様子を、タウトの日記から、観察したことがあるが、本書を著す動機の一つでもあるので、ここにおいても簡単に触れておきたいと思う。
桂離宮の清楚な竹垣、 詰所の前房で來意を告げる。一匹の足痿えた蜥蜴。御殿の清純眞率な建築。深く心を打つ小兒の如き無邪。今日までの憧憬は剰すところなく充された。 ❹❹ (中略) ❹❹ 玄關の間(小さい玄關の間と鑓の間)、 これにつづく古書院控えの間(二の間)、 廣縁、 そこから張出された月見臺の竹縁、 御庭! 泣きたくなるほど美しい印象だ。御庭のたたずまい、 月見臺の前方には斜めに設けられた舟附場。右方には紅の花をつけた躑躅の植込、 ❹❹ 心を和ます親しさである。
「泣きたくなるほど美しい」これが、 有名なタウトの「桂離宮発見」の第一印象である。
さらに彼は桂離宮の細部についても次のように記しているのだ。
タウトは「最初は息づまるばかり」で桂離宮に酔いしれていることがわかる。ところが左方の御庭は嚴しい分化を示しているのだ。背後に無限の精神を蔵しているこの關係の豊かさに、 最初は息づまるばかりの感じであった。池中の岩のうえには龜、 五月の陽光のなかに頭を擡げていたが、 やがてどぶんと水のなかに飛込んだ。
そして、 次の一節が、 桂離宮とのはじめての出会いのまとめとして、 これ以上望むことができぬ程の最高の賛辞となっているのだ。
古書院の間から眺める御庭の素晴らしい景觀。それだのに新書院の前の御庭には、 もうこのような造園術は見られない。藝術的鑑賞のこのうえもない優美な分化だ、 すべてのものは絶えず變化しながらしかも落着きを失わず、 また控え目である。眼を悦ばす美しさ、 ❹❹ 眼は精神的なものへの變壓器だ。日本は眼に美しい國である。
タウトは桂離宮を日本そのものに置きかえて、 その美しさを賛めたたえたのである。
それからほぼ一年後の一九三四年五月七日、 彼はその感動をもう一度体験すべく、 桂離宮を再び訪れることになる。
タウトのそれら二回の訪問をまとめたものに『永遠なるもの』と『画帖桂離宮』があり、 特に前者は桂離宮の訪問記として、 彼の著書『日本の家屋と生活』の終章を飾るものであった。
それでは、 次にその描写をみてみることにしよう。
新緑が目にしみる、 五月の日差しの中、 彼はまず古書院に上がり、 縁側に出て、 庭園全体のほぼ中央に位置する月見台から、 前面に広がる光景をまのあたりにした。
春蝉が鳴き、 ときおり魚がきらりと跳る池の小島で、 亀がのんびり甲羅を干していたという。
私達は今こそ真の日本をよく知り得たと思った。しかしここに繰りひろげられている美は理解を絶する美、 即ち偉大な芸術のもつ美である、 すぐれた芸術作品に接するとき、 涙はおのずから眼に溢れる。
「涙はおのずから眼に溢れる」。
彼が初めて桂離宮を訪れた日の日記の中でも「泣きたくなるほど美しい印象だ」と記されているが、 ここでも同様の記述となっているのだ。
タウトは二回の桂離宮訪問の総合としての印象記にこのような表現を用いなければならないほど、 その美しさに胸を打たれたといっても過言ではないだろう(図2参照)。
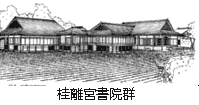
さて、 彼が桂離宮を初めて訪れた日の約二週間後の一九三三年五月二十日、 今度は日光へと足を延した。
この日、 彼は車の中から日光の大自然を心ゆくまで満喫し、 帝国ホテルの建築家であるかのフランク・ロイド・ライトも宿泊したことで知られる金谷ホテルで昼食をとったあと、 今度はバスにのって中禅寺湖を訪れ、 そこで華厳の滝を眺めてからさらにモーターボートで湖を一周した。
そして翌日の五月二十一日、 宿泊したホテルをたって、 展望台からの景色を楽しんだ後、 快い気分で日光市街へ戻り、 軽い気持ちで、 ぶらりと東照宮へ立ち寄ったのである。
ところがタウトは、 そこで突如「すさまじい建築」を目撃することになるのだ。
日光の東照宮へ。木深い杉木立、 そのなかにすさまじい建築がある。左側の社殿(大猷院廟)は東照宮よりも十五年あとに竣工した。金色の唐門、 装飾品のように『美しい』。建築物の配置はすべてシムメトリー、 眩ゆいばかりのきらびやかさ。すべてが威壓的で少しも親しみがない。 第二の社殿(東照宮)、 ❹❹ いかものだ。神馬は厩のなかで頗るご機嫌斜めである、 欄間の三猿(見ざる、 聞かざる、 言わざる)。兵隊の列のような配置、 なにもかも型にはまっている。華麗だが退屈、 眼はもう考えることができないからだ。鳴龍のある堂(本地堂)、 手をたたくと天井に描かれた龍がクルルルと鳴く、 珍奇な骨董品の感じ。 ❹❹ (中略) ❹❹配置はシムメトリー、 これを破っているところもあるが、 しかしそれはなんの意味ももっていない。建築の堕落だ、 ❹❹ しかもその極致である。
彼は、 この日まず始めに訪れた徳川三代将軍家光を祀る大猷院廟については、 「装飾品のように『美しい』もので「眩いばかりのきらびやかさ」であるととりあえずは評価している。
しかし、 その直後、 「すべてが威圧的で少しも親しみがない」と批判するのである。
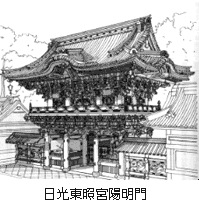 また、 次の東照宮については(図3参照)、 始めからぴしゃりと「いかものだ」と痛烈に非難する。
また、 次の東照宮については(図3参照)、 始めからぴしゃりと「いかものだ」と痛烈に非難する。
さらに「華麗だが退屈だ」と酷評し、 「珍奇な骨董品の感じ」だと罵声を浴びせかけた。
そしてついには「建築の堕落だ ❹❹ しかもその極致である」と結論づけてしまったのであった。
この中で「眼はもう考えることができない」と述べられているのは、 彼の著書『画帖桂離宮』の中でその結論として「眼は思惟する」と書いたあの桂離宮に対比してのことであろう。
このようなタウトの東照宮批判は、 早い時期から知識人の間で衝撃をもって受けとめられていた。
なぜなら彼は桂離宮については最高の賛美をおくったにもかかわらず、 一方の東照宮に関しては、 斬りさくほどの酷評を下したからであろう。
そして、 このタウトの発言はまたたく間に一般の人々にも浸透し、 桂離宮は簡素で美しく、 一方東照宮は装飾過剰で醜いといった固定概念を日本人に深く植えつけてしまったのである。
また、 日光東照宮は、 徳川家康を神として祀るための宮寺として、 茨城県宇都宮日光山麓に、 徳川幕府によって、 一六一六(元和二)年に創建され、 その後一六三六(寛永十三)年に大改築を施されて現在に至っている。
つまり、 この二つの建築は、 ほぼ同年代に建てられたのである。
それでは作者はどうか。
一般に桂と日光の造形があまりに対極的なので、 まったく無関係の人々によって造られたのではないかと考える人が多い。
しかし、 はたしてそうであったのだろうか。
この点について、 むしろ二つの造営をめぐる人々のあいだに、 様々な面でかなり密接な関係があったことがわかる。
例えば、 まず直接的な制作者としては、 狩野探幽がいる。
かれは東照宮と大猷院の彩色工事の総監督であり、 現代風にいえば、 日光のデザイン担当プロデューサーであった。
そして同時に桂離宮桂棚の襖絵も描いている上、 中書院、 笑意軒の襖絵を描いたと伝えられている弟の尚信も日光の絵師のひとりとして、 両方で活躍しているのである。
次に東照宮の陽明門にあげられている額「東照大権現」の字と、 桂離宮の松琴亭に掲げられた額「松琴」の文字は、 どちらも後陽成天皇の筆といわれ、 当時の宮廷を中心とした文化サロンが両方に深く関わっていたことを物語っている。
この後陽成天皇は、 桂離宮を造った智仁親王の実兄にあたり、 造営にあたっては、 大いに相談に応じたと思われる。
また桂の造営にかなり深い影響を与えたと考えられる小堀遠州は、 寛永の頃には伏見奉行のほかに京都御所、 二条城、 大坂城などの作事奉行として将軍家光の側近に仕えていた。
彼と日光の関係については、 一六三六(寛永十三)年四月、 寛永造営の日光東照宮完成に際して、 家光の先発として東照宮の見分を勤めているのである。
このときの遠州の役目の具体的な内容ははっきりしないが、 あるいは将軍家光が東照宮の完成を巡視するにあたって、 その相談役を勤めたのではないかとも考えられる。
一方、 東照宮の総指揮をしたといわれる甲良宗広は、 古い近江大工の名門の出身で、 青年時代には京都の建築界で活躍した。
由緒書によれば、 慶長初年に関白近衛家の門を造営し、 その功によって左衛門尉の号を受けたと伝えられる。
近衛家は当時の京都の貴族のうちでも、 八条宮家と最も深い関係にあり、 中でも近衛信尋は智仁親王の甥にあたり、 二人はかなり親しく交わったといわれる。
信尋は、 親王に招かれて桂離宮で遊んだこともあり、 親王も近衛家の茶会に出席することが多かった。
つまり、 近衛家に取り立てられた甲良宗広は、 八条宮家の極めて身近なところで仕事をしていたことになるのである。
さらに家康亡きあと、 これを東照宮大権現という神格にして、 日光廟を建てる大プロデューサーであったのは、 日光輪王寺の貫主南光坊天海僧正と、 京都金地院住職以心崇伝であるが、 まず崇伝は智仁親王の茶ノ湯の仲間で、 八条宮のために『桂亭記』を選進している。
この離宮を風流、 趣味の極とし、 「徳は三皇を兼ね、 功は五常を過ぐ」とまで絶賛し、 「万夫百工に課して、 流を引き、 山を為し、 華殿を構え、 玉楼を築く」と激賞しているのは、 あながち誇張ともいえないだろう。
また崇伝はのちに詳述するように、 自らの金地院の設計を前述の小堀遠州に託しているのである。
この金地院には、 東照宮と八窓の茶室があるが、 前者は黒と朱の漆塗りに彩色文様を加えた日光に通ずる様式の建築。
また後者は、 遠州独特の窓の多い明るい草庵茶室で、 桂離宮の松琴亭茶室に最もよく似た作風といわれている。
一方、 天海は、 智仁親王の甥にあたる後水尾上皇の実子幸教親王を自分の跡継ぎに欲したこともあり、 両者には近密な関係があったことがおのずと察せられよう。
八条宮三代穏仁親王は後水尾上皇の実子にあたり、 桂離宮書院群新御殿や御幸門、 御幸道等は、 すべて上皇の桂行幸のために造営されたものである。
さらに上皇は、 桂離宮と双璧といわれ、 類似した意匠がみられる修学院離宮を自ら設計したことでも知られる。
このような事情をみてくると、 両者には宮廷と将軍家に共通した建築、 庭園、 絵画、 工芸、 さらに茶ノ湯から和歌、 俳諧、 歌謡、 音曲などのいわゆる「寛永文化サロン」が存在していたことがわかる。
以上のように、 桂離宮と日光東照宮は、 ほとんど同年代に造営された上、 さらに同じ人々が関係して作り出されたものであることが明らかとなる。
にもかかわらず、 両者のあいだには、 対極的とでもいうべき極端に異なる造形が見られることが、 冒頭で触れたタウトの発言以来、 たえず繰り返し指摘され続けてきたのである。
片や庭園建築、 一方は社寺建築という機能上の違いがあることを念頭においたとしても、 桂と日光の意匠表現は、 確かに一見、 何の脈絡もないかのように見える。
同年代、 同関係者によって造営された二建築に、 どうしてこのような大きな差異があるといわれるのだろうか。
また、 両者の造形は今まで指摘されてきたように、 本当に対極的であるのか。
さらには、 タウトがいうように東照宮は本当に醜いのだろうか。
次章以降、 まず各建築ごとにその造営過程を検証した上、 二建築の造形上の相違に関する根本的原因について明らかにしてみたい。
本書には多数の注番号が振られていますが、 HTML化に際して削除しました。