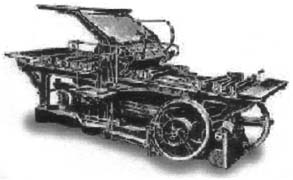

シリーズ アナログ印刷(I)
明治期の写真・印刷と出版事情 ―付・コロタイプ印刷の実際―
[はじめに] 山口須美男
現在私達の生活の中で目にするあらゆる印刷は、写真術の発明により数種類の版式の違う印刷方式が誕生しました。その印刷方法はそれぞれ異なった印刷性能や特長を持っています。具体的にはコロタイプ印刷・原色版印刷・グラビア印刷・オフセット印刷などがあります。
その中でもっとも写真と密接な関係があって、もっとも早期に写真印刷が確立したコロタイプ印刷につて、
写真技術を追いながら、初期の印刷の成果を振り返って見たいと思います。また、この印刷技術を発展進歩させた美術出版にもふれて見たいとおもいます。
150年前にフランスで生まれたコロタイプ印刷も、現在では衰退し、ローコストの印刷が主流となっています。近代の美術印刷の担い手であり、出版文化に貢献した、栄光のコロタイプ印刷の再発見のため実際編を付記しました。
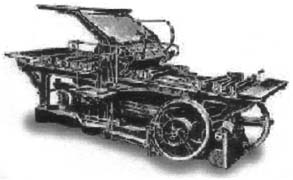

写真技術の歴史
嘉永元年(1848)、長崎に着いたオランダ船によって、黒い不思議な箱が上陸しました。その10年前、1839年にフランスで発明された世界最初の実用的な写真術、ダゲレオタイプ(銀板写真)用の写真機でありました。
ダゲレオタイプとは、フランスの画家ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが発明した写真技法で、銀メッキした銅板に沃素蒸気で処理して表面に沃素銀を形成させて感光性を与え、撮影後(露光後)に水銀蒸気で現像する方式で、ポジの鏡像ができあがります。
上野俊之丞が輸入したダゲレオタイプは、嘉永2年(1849)には、薩摩藩主島津斉彬の手に渡りました。彼が水戸藩主の徳川斉昭に宛てた手紙の中に「印影鏡」という言葉が度々でてきます。斉彬はその中で「鏡ニヨヂューム(沃素)之気ヲウケサセ夫ヨリブロミュム(臭素)之気ヲウケサセ影ヲウツシ夫ヨリ水銀ノ蒸気ニ当テ十分ニ影アラハレ候上硝石精十五倍ノ蒸留水ヲ加洗ヒ……」と、ダゲレオタイプの性能をかなり詳しく説明しています。
しかし、実際に薩摩藩主のダゲレオタイプ撮影が成功するのは、渡来から10年近くたった安政4年(1857)になってからでありました。薬品を自製することを含めて、技術的な問題を解決するのが難しかったと考えられます。市来四郎の手記「島津斉彬言行録」に、明治17年(1884)9月16日に島津斉彬自身が「御手ヅカラモ御試ミ遊バサレタリ……三、四回ニシテ能ク写シ得タリ」とあります。翌9月17日には裃姿の斉彬自身を「三枚奉写」しています。日本人による写真撮影は、こうして大名によって初めて成功しました。日本人が日本人を撮影したダゲレオタイプ(写真)として、大変な貴重品であります。


1841年には、イギリス人ウイリアム・ヘンリータルボットは、1枚のオリジナルだけでなく、現在のように焼き増しのできるネガ・ポジ法を発明しました。このネガ・ポジ法は、紙の繊維の間に感光層を塗り込み、感光後この紙ネガから陽画に焼き付ける方法で、カロタイプと呼ばれました。このカロタイプは露光時間が2・3分と短く、格段の進歩でありました。これが銀塩写真のルーツであります。
このころイギリスのF・S・アーチャーによって、ガラスの原版を用いる湿式コロジオン法(湿板写真)が発明(1851)されたので、ダゲレオタイプは時代遅れの技法になりかけていました。
「註 」 湿式コロジオン法とは、ガラス板の上に感光乳剤と粘着性を持つコロジオンと呼ばれる液を塗布し、湿っているうちに撮影、現像、定着処理を行ないました。露光時間は1分を切りましたが、湿板であるため、撮影現場でガラス板に感光溶剤を塗らねばならず、野外での撮影ではテント式の暗室が必要でありました。
安政元年(1854)に来航したアメリカのペリー艦隊には、ダゲレオタイプ写真家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが乗りこんでいました。彼の役目は帰国後に刊行されるべき報告書の挿図として、日本人の風俗、風景などを撮影することでありました。彼は停泊地の琉球、下田、横浜、函館で400〜500枚のダゲレオタイプで撮影しました。横浜での撮影を見た武州石川郷の名主石川某は「一尺三四寸四方の箱前後ニ覗キ目鏡有之箱の中半分より上ニ合セ鏡を仕掛け写ンと思人を三間斗向ニ立セ置ク其人の姿前の覗目鏡より箱の中え入ル」と、かなり詳しい観察記録を残しています。
函館では松前藩家老松前勘解由、奉行石塚官蔵、用人遠藤又左衛門と彼らの従者たちが緊張しきった硬い表情で撮影されています。ダゲレオタイプは左右逆像になるため、身分の高い侍たちは着物の襟と刀の位置を反対にして撮影されていますが、従者の中にはそのまま逆像に写っている者がいるのが滑稽であります。この時の撮影について函館弁天町の名主小嶋又次郎は「鏡に其侭相移り其場より鏡取候ても移り候もの鏡より不取候由。若哉魔術かとの市中の噂」と驚きの目を見張っています。
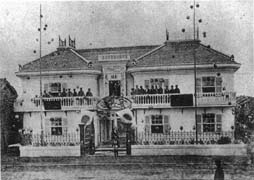 ペリー艦隊と同じころ、ロシアのプチャーチン提督率いるディアナ号が長崎、下田に来航して開国を迫りました。この船に乗りこんでいたアレキサンドル・F・モジャイスキーもまた画家でありましたが、ダゲレオタイプの写真家でもありました。この時、幕府を代表して交渉にあたった勘定奉行川路聖謨は、写真撮影の体験を「早廻りの針五、六分ばかりの内に、顔色、シワ、出来物のあとまでうつる。衣服のいろ目もうつる也。これは子孫へ伝え申すべしと、大悦いたし候」とその感銘を書き残しています。なお、川路聖謨はダゲレオタイプを「写真鏡」と記述しています。従来の「印影鏡」「直写影鏡」などに変わってPhotographyの訳語として「写真」の名称が序々に定着してきました。
ペリー艦隊と同じころ、ロシアのプチャーチン提督率いるディアナ号が長崎、下田に来航して開国を迫りました。この船に乗りこんでいたアレキサンドル・F・モジャイスキーもまた画家でありましたが、ダゲレオタイプの写真家でもありました。この時、幕府を代表して交渉にあたった勘定奉行川路聖謨は、写真撮影の体験を「早廻りの針五、六分ばかりの内に、顔色、シワ、出来物のあとまでうつる。衣服のいろ目もうつる也。これは子孫へ伝え申すべしと、大悦いたし候」とその感銘を書き残しています。なお、川路聖謨はダゲレオタイプを「写真鏡」と記述しています。従来の「印影鏡」「直写影鏡」などに変わってPhotographyの訳語として「写真」の名称が序々に定着してきました。
弘化2年(1845)頃、当時の狩野派の画家で董圓と名乗っていた絵師が、師狩野董川の使いで薩摩藩の江戸屋敷を訪れました。彼はそこで1枚の「銀板写真」を見せられました。その迫真的な描写力に驚いた彼は、誰がどのようにして描いた絵かと尋ねました。その答えは「機械を以って写せり」ということでありました。「妙技あり豈区々毛錐を弄するに忍びんやと筆を折り刷毛を砕き呆然たるもの数日、遂に之を学ばんと決意す」と、彼はのちに書き記しています。
彼のこの゛写真ショック器は、のちに下岡蓮杖と名を変えて、オランダ人の通訳ヒュースケンから写真の手ほどきを受け、安政6年(1859)、開港した横浜でアメリカ人ウンシンからも写真技術を学び、ウンシン帰国の際に写真機と薬品一式を譲り受けました。蓮杖は失敗を繰り返しながら、文久2年(1862)についに湿板写真法により撮影に成功しました。同年中に、野毛に日本で最初の写真館が開業しました。



一方、下岡蓮杖と同じ頃、長崎では上野俊之丞の4男上野彦馬が、写真術の研究をしています。蓮杖は化学や光学には素人で、司馬江漢以来の「写真」の迫真的描写を追及するところから写真術に入っていったのとくらべると、上野彦馬は典型的な蘭学研究者でありました。
彼は安政4年(1857)から、オランダ人医師ポンペが教える長崎海軍伝習所で、主に舎密学(化学)を学んでいます。この時、蘭書中に「ポトガラヒー」の文字を見出して、興味を抱き、津藩の留学生堀江鍬次郎とともに写真術研究に没頭しました。彼の化学の知識が本格的なものであったことは、のちに堀江と共著で出した、津藩の藩校有造校の教科書『舎密局必携』の、第3巻に付録として湿板写真法を紹介した「撮形術・ポトガラヒー」の章が掲載されています。
現像に使うアンモニヤを自製するため、生肉の付着した牛骨を土中に埋め、その臭気のひどさに周辺の人々から抗議か出るなどの大変な苦労の結果、撮影に成功したのは万延元年(1860)の頃でありました。長崎・中島川の河畔に「一等写真師上野彦馬」の看板を掲げて開業したのは、下岡蓮杖と同じ文久2年でありました。
この下岡蓮杖と上野彦馬による肖像写真館の開業によって、ひとまず日本への写真術の渡来と定着の時代は終りました。
下岡蓮杖と上野彦馬が横浜と長崎に開業した文久2年から明治維新にかけて、日本の各地での写真館の誕生は目覚しいものがありました。慶応元年(1865)に、上野彦馬の弟子内田九一、守田来三が大阪で開業、同年に京都では堀与兵衛(真澄)が写場を開いています。翌2年には、ロシア領事ゴスケウィッチから写真を学んだ木津幸吉が函館で開業しています。また、彦馬の弟子であった富重利平が筑後柳川で開業しました。
当時の写真を「キリシタン・バテレンの魔術」「魂を吸い取られる」といった風評がたちました。それに撮影代金がかなり高額だったこともあって、写真館を訪れる人は外国人か金持ちに限られていました。しかし、維新後の「文明開花」の風潮のもとで、写真はその「魁」となりました。写真館が全国各地に出来て、料金も安くなったので、一般庶民も写真に撮られる経験を味わうようになりました。


高見沢茂は『東京開化繁盛記』(明治7年1874)の中の写真の項目には、
「昔人或は鏡を以て不可思議となす、今や其真を写して之を子孫に伝ふことを得るに至る。豈文明の時開化の世と云はざる可んや。……写真の技早く開け、生業をなす者漸く盛んなり」と述べています。
もはや「開化の世」を代表とするものとなり、赤煉瓦造りの偉容を誇る写真館で「不可思議」な技を使う写真師たちは、時代の花形職業としてもてはやされました。
明治初期にもっとも華やかに活躍した一人が内田九一でありました。彼は上野彦馬に写真術を学び、神戸・大阪・横浜を経て、明治2年(1869)に東京に移り、浅草に「九一堂万寿」という看板を掲げて写真館を開業しました。明治8年の突然の死まで、東京随一の写真師の名声を誇っていました。
彼の名声は、なんといっても「御真影」の写真師としての評判が高かったのであります。明治5年(1872)5月、内田は宮内省の命により明治天皇の「一は束帯にして、一は直衣を著御し金巾子を冠したまふ」姿を撮影しました。この時、姿勢を正すため天皇の頭に触れましたが天皇は「写真技術中は、我体と雖も、彼の手中の者なれば、其所為に任すこそ、適当な事なれ、咎むるに及ばず」と意に介さなかったと、石井研堂が『明治事物起源』(下巻、1944)に記しています。
翌年には、軍服を着て椅子に座っている「御真影」を撮影し、同年11月に各府県に配布されました。天皇の生身の体でなく、イメージが呪術的な効果を発揮して人々の意識を支配して行く「御真影」神話の始まりでありました。
まだこの時期には人気役者や芸者の写真などとともに、「写真店」で売られていましたが、東京府知事大久保一翁は明治7年(1874)4月に「聖上御写真複写売買不相成旨……」と布告を出していますが、密売はその後も続いていました。
内田九一とならんで写真の発展に寄与したのは、横山松三郎でありました。横山はエトロフ島の出身で、父の死後、嘉永元年(1848)に函館に来ています。当地のロシア人たちの影響で洋画や写真に興味を持ちますが、文久3年(1863)に函館奉行の官船健順丸で上海に向かいました。帰路、元治元年(1864)に横浜の下岡蓮杖を訪ね写真術を学びました。東京上野池之端に写真スタジオ通天楼を営んだのは明治元年(1868)でありました。
彼のその後の活躍も目覚しく、同3年には、半年に及ぶ強行軍で日光山全域を撮影しました。太政官御用掛蜷川式胤の命で旧江戸城内を撮影し、その写真に着色したのは高橋由一で明治4年に完成しています。同5年には蜷川らの関西地方の古美術調査旅行(壬申検査)に同行し、奈良正倉院御物などを撮影しています。
横山には写真家のほかに画家の一面を持っています。
万延元年(1860)頃にロシア人画家レーマンと出会い、洋画の存在を知って以来、彼は写真とともに画業にも情熱を傾けました。明治6年には通天楼内に画塾を併設し、洋画のほかに石版画も教えています。
横山にとって写真も洋画も対象を迫真的に描く(広義の写真)という意味では、同一のレベルで捕えていました。そのことをよく示しているのは、明治14年(1881)頃に完成された「写真油絵」の技法であります。これは印画紙の感光乳剤の膜の部分だけを残し、裏から油絵具で着色する技法ですが、なまなましい現実感あふれる画像を得ることができます。写真の構図をそのままなぞった絵を描いた高橋由一と同様に、横山もまた写真と洋画との区別がまだはっきりしない時代を生きていたのであります。
横山は華やかな写真家兼洋画家の職を捨て、明治9年に陸軍士官学校の教官となりました。士官学校時代にはフランス人ケレーネの指導を受け、カーボン写真、電気版写真、ゴム印画法、青写真などの実験を重ねています。明治17年(1884)、まだ40才の若さで死去しました。


文久3年(1863)頃、フェリックス・ベアトという写真家が横浜に姿をあらわしました。彼はイタリア生まれの帰化イギリス人で、クリミヤ戦争、インドのセポイの乱、中国のアロー戦争などに写真家として従軍しました。既に、「絵入りロンドンニュース」の特派員として来日していた画家チャールズ・ワーグマンの後を追って、横浜に来たのであります。
ベアトはワーグマンと横浜居留地24番に共同スタジオを構え、日本各地を旅行して風景写真を撮影したり、モデルにポーズをとらせてスタジオで風俗写真を撮影しています。鶏卵紙(感光乳剤の支持体に卵白を使った印画紙)に焼きつけられた写真は、台紙に貼られ、アルバムとして販売されるようになりました。主な顧客は横浜を訪れた外国人旅行者で、彼らのみやげ物として、ちょんまげ姿の侍、力士や芸妓などの珍しい風俗をエキゾチシズムに強調したものであり、富士山、日光、江ノ島などの名所風景典型的な主題でありました。
「註」 鶏卵紙 「コロジオン湿板ネガ」とよばれる現在のネガフイルムで、印画紙に焼き付けるためのネガです。当時使われていた印画紙の多くは「鶏卵紙」と呼ばれる、食塩で溶いた卵白を塗って乾燥後に硝酸銀で処理したもので、柔らかな階調が特徴です。
これを原板(ネガ)にあてて太陽光の下で焼き付けると、水洗と定着だけで処理ができます。当時の肖像写真や風景写真が現在残されている画像は、ほとんどが鶏卵紙であります。また、ガラスがとても貴重であったため、鶏卵紙に焼き付けられた後のネガ原板は、撮影像を掻き落してガラスを再利用しました。
ベアトが作りあげた「横浜写真」は、彼がスタジオを手放した明治10年(1877)以降も、多くの写真家たちによって受け継がれ、ますます発展していきます。ベアトのネガを受け継いだレイムンド・スティルフリートの日本写真社、下岡蓮杖の弟子白井秀三郎の横浜写真社、また、ベアトの助手であった日下部金兵衛、浅草から横浜に移った玉村康三郎などがありました。
彼らのアルバム写真は、一枚一枚繊細な技術で彩色されていて、アルバムの表紙は蒔絵をあしらった豪華なものでした。内容的にはステロタイプの名所風景やヤラセポーズの演出写真がほとんどですが、これらの「横浜写真」によって「東洋の神秘の国」のイメージが全世界に認知されました。また巧みな構図や丁寧な着色技術には、西欧的な遠近法と東洋画の美意識を融合させようという意欲をも感じさせます。「横浜写真」は明治維新以後、世界的に注目されたため、重要な輸出品の一つとなりました。


しかし隆盛を誇っていた「横浜写真」も、明治30年代以降は急速に衰退していきます。写真製版技術の発達で、手間のかかる鶏卵紙彩色写真がすたれたことや明治33年(1900)の郵便規則の改正で私製葉書が認可され、コロタイプ印刷による絵葉書が大流行したのが主な起因であります。
明治16年(1883)5月、浅草の写真師江崎礼二が、新しく輸入したイギリス製スワン乾板で、隅田川で行なわれた海軍の水雷爆発実験を撮影しました。乾板は1871年にイギリスのリチャード・L・マドリックスによって発明されていますが、日本ではこの実験撮影をきっかけに急速に普及しました。爆発によって湧き上がった波頭を瞬間撮影した江崎の写真は、この新技術の優秀さをまざまざと示しました。乾板によって、従来の湿板の暗室処理のわずらわしさや感度の低さはかなり解消されたのであります。
しかし技術的に容易な乾板の普及は、写真師たちにとっては、逆風に遭遇する結果となりました。明治20年代以降、それまでは長期の修業が必要だった写真師に、多少の経験を積めば誰でもなれる時代が訪れました。いきおい各地に次々に写真館が開業し、独占企業だった古株の写真師の地位を脅かすようになりました。そして急速に伸張してきたのが、コロタイプ印刷による写真の複製であります。1枚のネガティブから多数の複製写真がローコストで出来ることから、写真アルバムや観光地、有名社寺の写真絵葉書が流行しました。
また、古典美術の複製も次第に印刷業界に重きをなすに至りました。明治16年(1883)アメリカ帰りの小川一真は、コロタイプ印刷の実用化に道を開きました。
小川一真(1860〜1929)は、武州行田の出身で、小普請組の原田庄左衛門の次男として生まれ、4歳の時、小川石太郎の養子になりました。明治6年(1873)に東京日本橋蠣殻町の報国学校(通称有馬学校)へ入学し、そこで写真好きのイギリス人教師ケンノンからカメラの手ほどきを受け、その関係で浅草に店を構えていた内田九一の写真館に出入りして、写真への関心をさらに深めていきます。報国学校を卒業後、一時群馬県富岡で写真館を経営しますが、激しく動く欧化の波に刺激されて、同13年に上京して、東京築地の外国人居留地内の明治学院に入学しました。その間東京の写真師たちと交流を深め、写真師として独立する事を目指しました。
一流の写真師になるにはアメリカへ行って修行する以外にないと考えて、明治16年に渡米して、ボストン、フィラデルフィアで写真術、印刷術を学び、翌年3月に帰国しました。帰国したもののすぐに写真館を持つことの出来なかった一真に、広告好きで知られた銀座3丁目の天狗煙草で有名な岩谷松平が手を差し伸べてきました。岩谷松平は使い手のないまま横浜港の倉庫で眠っていた機械(カメラ)を取り寄せて、一真に天狗煙草店頭で「写真燈照広告」を実演させ、大変評判となりました。そのようなことがあって、翌年、麹町区(現千代田区)飯田町4丁目に写真館玉潤館を開設し、本格的な写真師としてスタートを切りました。
一真はまた、明治21年(1888)にわが国では初めてのコロタイプ写真製版印刷の実用化に道を開きました。この年の9月には、宮内省では「臨時全国宝物取調局」(岡倉天心、フェノロサらが参加)を設置し、古社寺宝物の調査に着手しましたが、それに先立ち同年4月には奈良方面での調査が行なわれました。一真は写真撮影のため同行を求められ、社寺、仏像の撮影を行ないました。この調査の経験から岡倉らは、明治22年(1889)11月、美術の専門書『国華』の刊行を開始しました。一真は写真製版を担当しコロタイプ印刷を行い、当時としては最高の写真図版を印刷しました。
その後、『国華』の発行所であった国華社は経営にいきずまり、明治38年(1905)に朝日新聞社がこれを引き継ぎ、権威ある古典美術の紹介誌として著名で、発行は現在に及んでいます。最近号の発刊は平成16年7月で通算じつに1305号です。
明治22年(1889)に京橋区日吉町(現銀座8丁目)に小川写真製版所を、築地に写真乾板製造会社を設立し、製版所の中に写真館を併設しました。
一真はそのころ休刊状態になっていた雑誌「写真新報」を引きうけ、同年2月、一真の兄が経営する博文堂(京橋区三十間堀2丁目・現銀座5丁目)から改めて刊行し、写真術普及につとめました。明治24年「濃尾大地震被害地」の撮影、同25年「光線並写真化学」の出版、同29年北海道石見での「皆既日食」の撮影など、精力的に写真・印刷を行なうとともに、写真乾板製造は立派な企業に成長しました。
小川一真の質の高い美術品コロタイプ図版が評価され、明治29年(1896)に日本美術写真に小川一真の最高の印刷技術が駆使されて出来た『真美大観』がいよいよ刊行の運びとなりました。


審美書院発行の美術書
明治の大出版社であった審美書院の『豪華本美術図書』展が京都岡崎にある山崎書店で、平成16年2月に開かれました。゛京から出版文化の発信器をテーマに、明治32年(1899)から41年にかけて出版された、日本ではじめての美術全集『真美大観』全20冊、明治43年完結の『東洋美術大観』全15冊など、明治・大正時代に出版された約100点の豪華美術本の展示がありました。このような貴重図書を手にしてページを繰ると、古き良き時代の素晴らしい印刷技術の高さに瞠目・脱帽しました。
『真美大観』第1冊の奥付によると、その発行は明治32年(1899)5月、京都建仁寺の塔頭禅居庵内に設けられた「日本仏教真美協会」から始動します。これは美術書の発行元(出版社)としては、今日の感覚からするとやや違和感を感じさせる場所であり名称です。
発刊に先立つ明治31年8月、『京都美術協会雑誌』74号の「雑報」欄に「日本仏教真美協会」発足の記事が掲載されています。この記事には「伊藤貫宗、畑道温、北条周篤、奥村明堂、高田自祥、田嶋志一、爾文荷、長山虎壑、前田誠節、後藤文宸、宮崎栴芳、柴田元魯」らが発起人になって禅居庵内に「日本仏教真美協会」を設立し、仏像仏画を撮影して冊子を発行する旨が記されており、さらにその冊子『真美大観』(註・この時点ではまだ「真美偉観」と題されていた)刊行の主眼は、美術品の紹介よりむしろ「美術の嗜好を利用して仏教思想を喚起する」ためにあることが示されています。古美術品写真集の発行元が禅宗寺院内に置かれたのは、それが布教活動の一助として計画されたためでありました。
後日の記事をみると、『真美大観』の販売は「日本仏教真美協会」会員への有料頒布というかたちをとっています。価格は1冊15円50銭、20冊完結をもって210円の予定でスタートしました。これは当時としても「俄か美術家として之を購うの資力あるもの果して幾人かある」と嘆かれるほど高価なものでありました。
明治30年(1897)には宝物調査の進展とその結果を受けて「古社寺保存法」が制定され、同年末より「特別保護建造物」と「国宝」の指定が行なわれました。こうした動向の中、京都では明治27年より臨済・黄檗両宗の機関紙として『禅宗』という雑誌が「禅定窟」から創刊され、その第36号の巻頭に興味深い社論が掲載されています。「寺院の美術を世界の公衆に示すべし」と題された論文には、「今日は日本美術の流行時代也」と前置きして、仏教家は大いに美術を利用し、内外人の仏教思想を呼び起こすべきであるということが説かれています。
その具体化として、ここで初めて寺院の宝物を集めた写真集を出版することが提案されるのであります。前掲の『京都美術協会雑誌』74号の雑報欄に挙げられていた「日本仏教真美協会」設立発起人のうちの一人である「田嶋志一」(1898〜1924)や「奥村明堂」、「爾文荷」が東福寺派宗務所詰、「北条周篤」が嵯峨臨川寺代表であり、同協会の代表である「伊藤貫宗」は、臨済宗金閣寺長老であります。
ここで『真美大観』刊行開始時の担当者の顔ぶれは以下の通りであります。
作品選択 今泉雄作
和文説明 藤井宣正
英文説明 高楠順次郎
同批評的補説 フェノロサ
木版彫刻 森川応翠
同色摺 田村鉄之助
写真製版・印刷 小川一真
編集上全般の整理 田嶋志一
「和文説明」を担当した藤井宣正(1859〜1903)は、『大蔵経冠字目録』や『仏教小史』などの著作がある真宗本願寺派の学僧であり、「英文説明」の高楠順次郎は、インド学・梵語学・仏教学の大家として著名な人物で、明治23年に渡欧し、同30年に帰国しています。この間に「観無量寿経」「南海寄帰内法伝」などの英訳があります。同36年には東京帝国大学梵語学教授となりました。
作品解説者の中にこの藤井や高楠のような仏教学者の名前が見られるのも『真美大観』が何よりもまず、仏教の教化を目的として企画されていたことがわかります。第1冊巻頭には、当時美術行政の権威であった九鬼隆一とフェノロサによる序文が載せられていますが、このうちフェノロサは序文の冒頭に「日本において、東洋の古代美術の精神を観んと欲せば、京畿地方殊に京都の大寺巨刹においてせざるべからず」と述べています。
これらのスタッフにより、仏教美術の写真集が出版されました。仏教関係者にとってみれば、「美術」品写真集はいわば教義の絵解きであり、仏教史の視覚化でありました。しかもそれは印刷による大量生産、大量頒布が可能になっていました。日本で最初の美術作品集が、仏教関係者による内外への布教、仏教教化の方策として企画されたことは画期的なことであります。
また『真美大観』には当時の最高の印刷技術が駆使されました。明治33年のパリ万博に『真美大観』を出品し、「書籍」部門で金牌を受賞しました。
明治35年1月、『真美大観』の発行権は神戸の富豪、光村利藻(1877〜1955)が経営する「関西写真製版印刷合資会社」に移譲されました。これは後の光村原色版印刷所、現在の光村印刷株式会社であります。彼は絵画・刀剣の収集家で多くの画家たちのパトロンとして、自らも当時著名な写真家でもありました。
「日本仏教真美協会」は『真美大観』を刊行するためだけに結成された団体であったため、この時点で解散し、光村のもとで新たに「大日本真美会」が創立されました。
理事長には光村が就任し、理事には雑誌『禅宗』の編集から退いた田嶋志一が就任しています。神戸下山手通りに事務所を構え、その滑り出しは順調でした。
しかし日露の開戦が近付くと、会員である予約購読者は次第に減少していきました。協議の結果、協会の事業を改善拡張し仏教美術以外の画集も刊行することが計画され、明治36年に光村が新たに創設したのが「審美書院」であります。ここからはいわゆる「真善美」の「真美」ではなく、「審美眼」の「審美」の字が用いられるようになりました。おそらく光村は仏教美術以外の画集も扱っていくに当り、「真美」の字に残る宗教色、思想色を排除していこうとの配慮でありました。
以後の「審美書院」は、画家別に作品を編集して『光琳派画集』(明治36〜39年)や『元信画集』(明治36〜38年)、『若冲名画集』(明治37年)などを次々に刊行し、これによって美術出版社の名声を得るようになりました。また、海外へも販路を拡大することが計画され、明治30年代以降の審美書院の刊行物には、田嶋志一の訳による英文版も作られていました。
明治38年、『真美大観』の発行権が光村の事業の失敗で、第十一冊の発行後に手放されました。翌39年1月、『真美大観』の発行権を引き継ぐため、東京市京橋区に「株式会社審美書院」が設立されました。この会社は宮内大臣であった田中光顕が筆頭株主となっていたので、その尽力で多数の政界・財界人が株主となり株式会社として独立しました。当初の資本金は11万円でありました。田嶋志一が審美書院の主幹をつとめ、東京美術学校教授の大村西崖を主筆としました。
大村西崖は、明治36年11月の第10冊以来発行が中断していた『真美大観』の第11冊以降の編集を受け持つようになりました。こうして『真美大観』の作品選択や編集担当は、中断後、前任の今泉雄作から今泉の教え子でもある大村西崖に引き継がれることになりました。大村の主筆就任後、審美書院では彼の解説・編集による流派別画集を次々と出版していきました。 さらに審美書院は宮内大臣田中の許可を得て、正倉院御物の撮影・模写も可能になりました。明治41年1月には宮内省蔵版「東瀛珠光」(正倉院御物図譜) (コロタイプ印刷)を出版しています。
発行元の変遷を経て、『真美大観』は、明治41年5月、第20冊をもって完結しました。膨大な美術品の撮影や編集、製版印刷を通じて、美術図録としてのわが国出版文化の大金字塔を建てました。
ここには日本美術と当時日本国内で所蔵されていた中国美術もとりあげられ、多色摺り木版による着色図版とコロタイプ印刷による白黒写真図版で紹介されています。1冊当り約50枚、全20冊をあわせて984図の絵画、彫刻、工芸、建築作品が掲載されており、これらの図版には1枚ごとに作品解説が付記されています。内訳は絵画が全体の9割を占め、日本・中国を合わせると878図で、彫刻・工芸は104図、建築は第1冊に掲載された2図であります。
『真美大観』完結の同年8月から、審美書院は新たな美術全集『東洋美術大観』の刊行を開始しました。『東洋美術大観』の出版は、審美書院にとって株式組織設立当初から、もっとも重要視していた刊行物でありました。
『東洋美術大観』の編纂と出版は、第1巻の冒頭には、宮内大臣田中光顕による序文が揚げられました。この序文によれば、田中はまず、美術によって「国民の開明」を卜し、理想を高めるべきだとしています。そして日本の美術事情を世界各国と比較して、日本は中国の古画をも保存している東洋で唯一の国であるとし、さらに本書出版は「国家的事業」の達成と記しています。この序文にある「国家的事業」と称したように、官・財・学を捲きこむ大規模事業となっていきました。
明治41年(1908)8月に第1巻の刊行が始まり、大正7年(1918)7月に全15巻が完結しました。第1巻に田嶋志一による緒言が掲載され、ここに『東洋美術大観』の編纂趣旨と方針が説かれています。その一部を揚げると……
「以って優秀卓抜なる絵画彫塑を網羅して、和漢美術の関係を明らかにし、両者の精華を発揮するに於て遺憾なきに近きを得たるにより、之を年代順と流派別とによりて配列し、極めて詳明確実なる美術沿革史を附して、之を東洋美術大観と題し、世に公にするに至れり。」
ここで田嶋が云う通り、『真美大観』の段階では確立されていなかった「絵画彫塑」のジャンル別と「和漢美術」の国籍の区分が本書では明確にされています。編成は第1〜7巻が「日本画」編、第8〜12巻が「支那画」編、第13・14巻が「支那彫刻之部」、第15巻が「彫刻之部(日本彫塑)」となっています。さらに作品図版の配列は明確な通史型構成をとっています。
作品図版には、コロタイプ印刷によるモノクロ写真図版を中心として、着色図版には多色摺り木版が用いられています。木版の一部には金箔や天然群青なども使用され、全体に『真美大観』より華美となっています。ここに掲載された作品写真には、宝物調査時の写真や『真美大観』や審美書院のほかの美術書から援用されているものが多数あり、その他に審美書院主幹田嶋志一自ら全国を飛びまわって、名家を訪れ「撮影」しています。
『東洋美術大観』は大正7年(1918)7月にようやく刊行を終了しますが、写真、用紙その他の材料費や人件費の高騰によって、途中からは予約販売の定価を守るために「1巻を発行する毎に損失を醸すと云う有様」であり、ついには持出しをしてまでの苦難の出版でありました。
さらに大正12年(1923)の関東大震災の際には、審美書院は社屋が半壊して、図版・複製用の版木などを大量に焼失しました。これは美術書の出版社にとって大打撃となりました。また、明治42年から発行されていた雑誌「美術之日本」も、震災後発行が途絶えました。審美書院の出版活動が、この大正12年の震災を契機として実質的にその命運を終えることになりました。
『東洋美術大観』の出版の目的は、かつて仏教関係者によって意図された当初の計画を離れて、内外の購読者を拡大し、「本邦美術の活歴史」つまり「日本美術史」の全体像を、美術名品集の形にした実績は、のちの教育行政や美術出版に、計り知れない成果を結実させました。
その後の審美書院は、六代目社長の野口駿男が「星岡茶寮」(美食倶樂部)の会員だった関係から、星岡茶寮の経営者である便利堂四代目社長の中村竹四郎と懇意になり、昭和14年ころから15年にかけて、経営に疎い野口を補助するかたちで中村が審美書院の常務取締役を兼任することになりました。
数年のあいだ審美書院と便利堂の両社は同じ屋根の下で別々に営業していましたが、やがて戦争が緊迫してきて企業統制が厳しくなり、合同会社「美術書院」を設立しましたが、昭和19年12月2日、審美書院は名実ともに便利堂に合併されました。そして昭和20年5月24日夜から未明にかけての東京大空襲で、写真スタジオとともに全て焼失してしまいました。こうして審美書院は、前身の日本仏教真美協会の発足から数えて47年で幕を下ろすことになりました。



審美書院の出版物
明治32年5月 真美大観
明治36年 元信画集
仝 光琳派画集
明治37年 南宗名画苑
仝 若冲名画集
明治38年 帝室博物館鑑賞録
明治39年 日本名画百選
仝 浮世絵派画集
明治40年 雪舟山水大長巻
仝 支那名画集
明治41年 円山派画集
仝 東洋美術大観
仝 和漢朗詠集
仝 東瀛珠光
明治42年 南画十大家集
明治43年 酣古帖広業画譜
仝 四条派画集

つづく