|
信楽は、滋賀から三重へと続く山中にひっそりとあった。 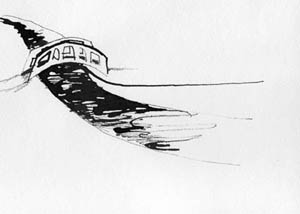 信楽の町全体がひとつの工場のようにシステマティックに運営されている。窯元や陶器の店が古い民家のあいだに点在している。陶美通りと名づけられた川沿いの道を歩くと、一軒気
になる店があった。敷地内には道路を隔てて壁のように松の木の薪が積まれている。「皆川陶器」と書かれた扉の脇に紅葉が赤い。店内には、赤っぽい土の色の
陶器が小さなものから大振りのものまで整然と置かれている。作家皆川隆さんと息子さんの仁史さんの作品だ。どれも炎の色を感じさせる素朴なものである。と
ころどころに表面に緑色がかった釉薬のようなものが目につく。隆さんの妻あさえさんに尋ねると、釉薬は施さないらしい。薪で焚いているので、その灰が降り
かかって溶け、釉薬をかけたようになるのだという。灰のなかに埋めて焚くと、黒っぽい色の陶器になる。手のひらにおさまるくらいの黒っぽい花器は、野の草
が生けられてとても可憐だ。
信楽の町全体がひとつの工場のようにシステマティックに運営されている。窯元や陶器の店が古い民家のあいだに点在している。陶美通りと名づけられた川沿いの道を歩くと、一軒気
になる店があった。敷地内には道路を隔てて壁のように松の木の薪が積まれている。「皆川陶器」と書かれた扉の脇に紅葉が赤い。店内には、赤っぽい土の色の
陶器が小さなものから大振りのものまで整然と置かれている。作家皆川隆さんと息子さんの仁史さんの作品だ。どれも炎の色を感じさせる素朴なものである。と
ころどころに表面に緑色がかった釉薬のようなものが目につく。隆さんの妻あさえさんに尋ねると、釉薬は施さないらしい。薪で焚いているので、その灰が降り
かかって溶け、釉薬をかけたようになるのだという。灰のなかに埋めて焚くと、黒っぽい色の陶器になる。手のひらにおさまるくらいの黒っぽい花器は、野の草
が生けられてとても可憐だ。
高さ1メートル以上、幅3メートルに亘って積まれたたくさんの薪は、登り窯で使用するそうである。窯で焼くのは寝3回ほど、6日間昼夜を問わず3人がかりで行う。夏を避ける。窯の火と太陽の両方から熱が来て、逃げ場がないためだそうである。
信楽は、陶土に恵まれ、古くは紫香楽宮の建立(743年)の際に帰化人から作陶の技術が持ち込まれ、須恵器を焼いた。今に至るまで、盛衰をくりか
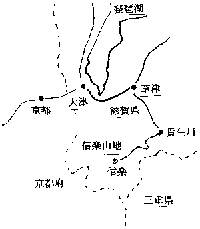 えしな
がら焼き物の町として生きてきた。最近になって良い土が減り、窯元は少し離れた黄瀬の土を使うという。黄瀬の土もまた、高値でありながら質が落ちている、
とあさえさんは嘆く。 えしな
がら焼き物の町として生きてきた。最近になって良い土が減り、窯元は少し離れた黄瀬の土を使うという。黄瀬の土もまた、高値でありながら質が落ちている、
とあさえさんは嘆く。長石のまじった土の、ざらりとした独特の肌合い。生計をたてている人々の労苦と共に、そのあたたかさを感じながら帰路についた。 「関西の人・まち」・目次に戻る |
