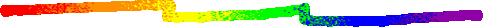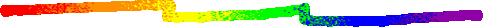My little fantasy
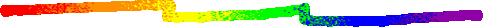
にじのたね
ゆみ子のほっぺたにひとつぶの冷たいしずく。
―あらら、雨?
またポツリ、それからいきなり大きな音をたてて雨がふってきました。肩からぶらさげていた布カバンを頭にあてて、ゆみ子はあわてて雨宿りができそうなところをさがして走ります。何かの店らしい古びた家の狭い軒下に飛び込んだとたん、雨足が急につよくなりました。
―ふうっ!
ゆみ子はぬれた髪の毛を手ではらい、ブラウスのそでとスカートをはたきました。いきおいよく降りだした雨は軒をたたいて溝に流れおちてきます。
―うわぁ、すごい雨!
雨はいい調子で軒をたたきます。いつのまにかゆみ子はカーテンがしまったガラス戸を、雨の音にあわせてたたきはじめます。そして灰色の空を見上げながら、かかとでリズムを踏みました。
ところが・・・、あれっ?
家の奥の方からもうひとつ別の音が聞こえてきます。
ゆみ子はガラス戸に耳をつけてみました。
家のなかから、かすかにシャカシャカという音が聞こえてきます。ゆみ子は音に合せて首をふり、リズムをつけて指先でガラス戸をたたきます。
雨はまだまだやみそうにありません。
いい調子で玄関のガラス戸をたたきつづけていると、とつぜん、少し離れたところにある窓があきました。
ゆみ子はびっくりして玄関脇の植木の間に隠れるようにしゃがみこみます。
そっと顔をあげると、おばさんが窓から顔を出して空をながめていました。
「あらら、雨の音だったのね。ちっとも気がつかなかったわ。ああ、ひさしぶりの雨ねぇ、生きかえるわ」
おばさんは灰色の空にむかってひとりごとを言いました。
やがておばさんは、軒下の植木鉢のかげに、しゃがみこんで小さくなっているゆみ子を見つけました。お店の戸をたたいていたのをしかられるのかと思って、ゆみ子は首をすくめ、ますます体を小さく丸めました。
「あらあら、そんなところにいたら雨にぬれて体が冷えるわ」
「ごめんなさい」
「ごめんなさいって、あら、どうしたの?にわか雨でびっくりしたでしょう。これだけ降っていたらしばらくやみそうもないわね。それにしてもずぶぬれよ。風邪をひくわ。なかにお入りなさい」
おばさんはそう言うと、すぐに窓から顔をひっこめて、入り口のガラス戸をあけてくれました。
おばさんはゆみ子の体をかかえて家の中にいれ、急いで乾いたタオルを渡してくれました。半分カーテンをひいたままの家の中は薄暗くて、ゆみ子はすぐには目がなれませんでした。
−このおうちはふつうのおうちとは違う。ここはやっぱりお店なんだ。
ゆみ子はいぶかしそうな顔であたりをみまわしました。
けれど、店とはいってもそこはちょっと変わった店でした。玄関は広い土間でした。土間から部屋にあがるとそこは板敷きになっていて、壁ぎわは全部棚になっていて、棚の中には糸の束や布がぎっしり詰まっています。
「ちょうどひと休みしようと思っていたところだから、お茶のお客さんは大歓迎よ」
おばさんはおぼんをかかえて奥の台所と店を往復しながら、うれしそうにいそいそと部屋の真ん中にある丸テーブルの上にお茶の用意をはじめます。
髪の毛をふきながら、ゆみ子はめずらしそうにあちこちをみまわします。
板敷きの床には、しわしわの茶色の紙にくるまれたつやつやの白い糸の束がたくさんつみあげられていました。壁きわの本箱のような棚には、いろいろな色の糸の束がぎっしりとつまっていました。天井からはいろんな種類の花束がたくさんぶらさがっています。それから大きいのや小さいのや糸巻きがぎっしり入った箱もありました。板敷きの店の中は乾いたよもぎみたいなにおいがしました。
「ここはお店?おばさんのおうちは何屋さん?」
ゆみ子は不思議そうな顔で聞きました。
「おばさんのおうちはね、もちろん、お店よ。ずっと昔から、おばさんのおばあちゃんの頃からお店なのよ。糸屋さんでしょ、それから染め物屋もするの。それから織物屋さんに仕立て屋さんの時もあるのよ。おばあちゃんがこのお店をやっていた頃は、今よりずっと大きなお店だったのよ。だけど、今はもうこれだけ・・」
おばさんは板敷きのへやをぐるりとみまわしました。
「今日はお休み?」
「ええ、お店はお休み。けれど、おばさんはお休みじゃないの。急いで仕上げないといけない織物があるから、今日はおばさんは織物屋さんよ」
おばさんはそう言って店の奥のはた織り機を指さしました。
「へぇ、おばさんは、今日は織物屋さんなの・・。パタンパタンって聞こえていたのは、はた織りの音だったの?」
「ええ、そうね」
「見てもいい?」
「ええ、いいわよ」
ゆみ子はそろりそろりと機織り機に近づいてみました。
「夕焼けみたい」
ゆみ子は機織り機からぶらさがっている赤い色の織物を目を細めてながめます。
「そう、夕焼けが見える?」
「うん、夕焼けでも、海の夕焼けみたい。ほら、波がきらきらひかってる」
赤い織物をみつめていたら、目がしょぼしょぼまぶしくなってきます。ゆみ子は目を細めました。すると、ゆみ子の耳にどこからか波の音が聞こえてきました。夕焼けの海が目の前に広がって、夕日に照り映えて波がしらがきらきらとまぶしく輝きました。ゆみ子は思わず目をこすります。
「夕焼け色を織るのは、夕焼けのあかね空からもらった色で糸を染めるのよ」
おばさんはにこにこしながらいいました。
ゆみ子は夢からさめたようなぼーっとした目でおばさんの顔をみつめました。
「うん・・、じゃあ、空の色を織るのはお空から色をもらうの?」
「そうよ、もちろん。ニンジン色はニンジンからもらって、ピーマン色はピーマンからもらうのよ」
おばさんは楽しそうに答えます。
「ほんとう?」
「ほんとうよ。おばさんは糸屋さんだし、染め物屋さんで、仕立て屋さんだって言ったでしょう。空みたいな青色で染めた糸はわくわくするでしょう。やさしいピンク色の花の色はほっとするし、やさしい気持ちになるでしょう。だから、きれいだなぁって思ったものから色をいただいて、そこにある白い糸を染めるのよ」
「それからパッタンパッタン織物をして、それで着物を作るの?」
「ええ、そうよ」
「いちご色のお洋服やりんごの色のスカートも作れるの?」
「ふふっ、そうね、きっとおいしそうなお洋服ができると思うわ」
おばさんはにこにこして言いました。
「うわーっ、すてきだね」
ゆみ子はもう一度機織り機の夕焼け色の織物に目をやり、それから、しげしげと白い糸の束をみつめます。そして棚の中におさまっているいろいろな色の糸ながめました。つやつやした糸はどれもこれも不思議な色に輝いて見えました。
「ここにある糸はぜーんぶおばさんが染めたの?」
「ぜんぶってわけじゃないのよ。どの糸もきれいな花やおいしそうな野菜、それから木や葉っぱの色で染めたものだけれど、おばさんのお母さんが染めたものもあるし、おばあちゃんが染めた糸もまだちゃんと残っているわ。おばあちゃんの染めた糸といったら、そりゃあすばらしい。色はちっともあせないし、あんな色が出せたらねぇ」
お茶を入れながら、おばさんはひとりごとのようにつぶやきます。
「さあさあどうぞ。お茶がはいったわ」
おばさんが出してくれたぼたん色の座布団に座って、熱いお茶がはいったお茶碗を両手でだきかかえると、ゆみ子はほっとしたように大きな息をつきました。
「はい、これはおばさんが作ったよもぎのおだんご」
おばさんはきな粉のついたよもぎのおだんごをすすめてくれました。きな粉の香りが口の中に広がって、お餅はとろーりととろけてとってもおいしいおだんごでした。
「きな粉色はきな粉で染めるの?」
ゆみ子はおだんごにかかった黄色いきな粉をしげしげとながめながら聞きました。
「ふふっ、そうよ。きな粉の黄色はあまい味、からしの黄色はからいかな」
「魔法使いみたいだね」
ゆみ子が感心したように言うと、おばさんはたのしそうに笑い、もう1つおだんごを食べました。
気がつくと、窓から明るい日差しがさしていました。
「雨はあがったようね」
おばさんが窓のカーテンをあけると、おうちのなかはいっぺんに明るくなりました。
雨はすっかりあがって、灰色の雲がきれかけてキラキラした光がさしていました。おばさんが店の方のガラス戸をあけると、すうっと気持ちのいい風が吹き込んできます。
「まあ、きれい、ほらほら、見てごらんなさい、大きくてすばらしい虹よ」
おばさんは戸口にたったままふりむいて、ゆみ子に手招きしました。
「うわーっ、おおきな虹だ!」
大きな大きな虹でした。ゆみ子はまぶしそうに目を細めます。
「きれいねぇ」
おばさんはうっとりした顔でため息まじりにいいました。
「大きくてきれいな虹だねぇ。ね、虹の色はどうやって染めるの?」
「虹の色は・・、そうなのよ、ゆみちゃん、虹からもらうのが一番なの」
おばさんはガラス戸にもたれたまま、だんだん薄れていく虹を見つめながら言いました。
「おばさんのおばあちゃんがね・・・」
おばさんはつぶやくようにおしゃべりをはじめます。
ゆみ子は「うん」と声を出してうなづいて、おばさんの顔を見つめました。
「ゆみちゃん、おばさんもね、ゆみちゃんと同じことをおばあちゃんに聞いたよ」
「うん」
おばさんは空の遠くを見ながらゆっくり話しをはじめます。
『おばあちゃん、虹の色はどうやって染めるの?』
『虹の色は、虹からいただくのよ』
おばあちゃんはいつもそう答えたの。
『どうやって?』
そう聞いたけれど、おばあちゃんはそれは色の秘密だからと言って教えてくれなかった。
『早くいかないと虹が消えてしまう』
おばあちゃんは虹が出るといつもそう言って、走り出した。
『おばあちゃん、まって!』
私はいつもそう言って、おばあちゃんのあとを追いかけたけれど、おばあちゃんの姿はいつも途中で見失ってしまう。しばらくすると、おばあちゃんはいつもエプロンにいっぱいの草や花をかかえて帰ってきたわ。そして、その花を煮出していっしょうけんめい糸を染めていた。そうやって染めた糸はそりゃあとくべつにきれいな色だった。つやつやした光があって深い色をしていた。おばあちゃんが草や花で染める糸の色は誰にもまねができない。おばあちゃんの染めた糸で織った布はそれだけでも売れたし、着物に仕立てたら、そりゃあ、いい値段がついた。でも、それが欲しいと言って、このお店も繁盛していたけれど。
だけどね、あの日はおばあちゃんは風邪をひいて寝ていた。なのに、雨あがりの空に大きな虹がかかっているのを見つけると、寝込んでいたおばあちゃんはやっとこさ起き上がって、ふらふらした足どりで虹が出ている方に急いで歩いていこうとした。そうしたら、あっちの方から車が来て・・・、雨が降って濡れた道路の上で車がすべって、おばあちゃんは交通事故にあった。その日からおばあちゃんは寝たまま起き上がれなくなって、それから1週間後におばあちゃんはなくなったの。
おばさんはそっと目をこすり、「ふうう〜」と大きな息を吐き出しました。
空に見えていた大きな虹はだんだんうすくなって、いつのまにか消えていました。
おばさんは、空を見上げてほっと息をつきました。それから、いきおいよく店のカーテンを全部あけました。
雨あがりの光が店の中にまぶしく差し込んできます。
「おばさん、きれいな虹だったね。でっかい虹だったね、ほら、あの虹の中にこんなやさしい桃色もあったわ。それから、ほら、このトマトみたいな色も・・」
ゆみ子は糸の棚の前にとんでいき、ひとつひとつの糸の束を指さしながら言いました。
「ほら、この色とこの色と、それからこの緑色。それから、このうす青色もあった」
おばさんはゆみ子が指さした糸を棚からそっと取り出して、床の上に並べていきました。床の上には、またたくまにたくさんの糸も束が並びました。
「うーん、まだ足りない。ほら、ここにはキラキラひかる感じの青い色。それからここにはすき通った黄色があるともっとすてきな虹になる」
ゆみ子は床の上に糸の束を虹の色の順番に並べていきます。
「うんうん、ゆみ子ちゃん、すてきな虹になってきた。うーん、そうだねぇ、ここにこの色をいれたらどうかしら」
おばさんはゆみ子が並べた糸の間に つやつやの藍色の糸をしのばせます。それはおばさんのおばあちゃんが染めた糸で、おばさんがとても大事にしている糸でした。
「ここはね、広い野原だよ。ここに川が流れていて、野原には花がいっぱい咲いているの。黄色いたんぽぽもあるし、紫のつゆ草もあるの。うーん、それから、ず〜と向こうまでお花にうまった野原なの。それから、この向こうに三角の山が見えて、でっかい虹は山の谷間のここからはえているんだよ。だからここは虹の根っこ。野原に霧みたいな雨が降って、そのなかでいろんな色の小さな花が咲いて、すると、ほら、ここから大きな虹が空にむかって咲くんだよ」
ゆみ子はおしゃべりしながらたくさんの糸の束を並べかえていきます。そして、とりわけきらきら光るおばさんのおばあちゃんの藍色の絹糸の束に手をのばした時、同じ糸に手をのばそうとしたおばさんの手とぶつかりました。重なったふたりの手の上に、突然、冷たい雨粒がポチポチと落ちてきたのです。
「あっ!」
ふたりは同時に声をあげ、ゆみ子は一瞬顔をしかめて目をつむりました。何かに足がからんでふらつき、ふくらはぎに水がはねかえります。ゆみ子はあわてておばさんの手をぎゅっとにぎりしめました。
「草の間に水たまりがあるから気をつけて」
−うん?
ゆみ子がそっと目をあけると、空にはさっき見た虹よりももっと大きな虹が見えていました。
ゆみ子はおばさんとしっかり手をつなぎます。そして、大きな虹がかかった雨あがりの野原を歩きました。あたりの草や木の葉は、雨にあらわれてまぶしいほどキラキラと輝いてみえました。ふたりはしっかり手をつないだまま、黙って歩きました。野原は雨に濡れた草や木の葉がまぶしいほどキラキラ輝き、よもぎのような青くさい匂いがしました。
−なんだかなつかしい。この野原、ずっと昔におばあちゃんに連れられてきたことがあるわ。あの時、いっぱい花と草をつんだ。「染めに使うならお花はつぼみの方がいいの」、そう言っておばあちゃんはせっせと花のつぼみをつんだ。
おばさんはなんだか懐かしいにおいをかいだような気分でした。
「草の中にお花がいっぱい咲いているわ。ほら、みてごらん!なんてきれいなつゆ草だろう」
おばさんは雨にぬれた草むらの中にしゃがみこみ、草のかげにさいているうすむらさきの小さな花に手をさしだしました。雨つゆにぬれた小さな花に指でふれると、花はブルブルとふるえて、雨のしずくがおばさんの手のなかをながれていきました。おばさんが花をつみとろうとした時、二人のうしろで大きな声が聞こえました。
「ああ、その花はダメよ!」
おばさんはびっくりして手をひっこめ、あわててうしろをふりむきました。
背中にかごを背負った野ねずみがたっていました。
「その花はダメよ。ここは私の畑で、その花は私がそだてた虹の花だから」
「まあ、これは虹の花っていう名前なの?」
おばさんはうす紫色の小さな花をしげしげとながました。
「ええ、虹の花という名前。虹の花にはいろんな色があって、紫色のはなかなか咲いてくれないのよ」
「まあ、そうだったの」
「ほら、もっとよくみてごらんなさい。お花がいっぱいあるはずよ」
野ねずみさんはしゃがみこんで草むらのあちこちをそっと両手でよりわけました。
「ほら!」
あちこちの草のかげに小さな花がたくさん咲いていました。
「ここは虹の花のお花ばたけなんだね」
ユミちゃんは、野ねずみさんのとなりにしゃがみこみ、草むらのなかに隠れて咲いている小さな花をながめながらいいました。
「こんなかわいい花で糸を染めたら、どんなにすてきな色になるだろうね。だけど、染めるならつぼみをつまないといけないわ」
おばさんは自分がおばあちゃんと同じことを言っているのに気がつき、はっとしました。
おばさんは虹の花をじっとながめながら、何度も何度もため息をつきました。こんなかわいい花が咲くのに、つぼみのままで摘んでしまうなんて、自分はなんてひどいことを言うのだろうとおばさんは心の中で思いました。
「そう、たまにね、つぼみのうちに摘みとっていく人がいるわ。あなたのおばあさんもそうだった・・」
そう言って野ねずみはおばさんの顔をじっと見つめました。
「だけど、今日はもう来るのが遅かったわ。花はみんな咲いてしまったもの」
野ねずみはそう言って、背中のかごをおろしました。
「ほら、これはみんな虹の花の種」
野ねずみさんはかごをななめに向けて、二人にかごの中をみせてくれました。かごの中には、しわしわの茶色の袋がいくつも入っていていました。
野ねずみはかごの中の袋をごそごそとさわって、やがてひとにぎりの種を出してきました。野ねずみさんがこぶしをひろげると、黒い小さな粒がてのひらの上でころがりました。ゴマ粒みたいに小さな種でした。
「ほんの少しだけれど、種をわけてあげるわ。虹の花がとっても気に入ったみたいだから。あなたもきっといつかすばらしい糸をつくるでしょうね」
野ねずみはおばさんの顔をじっと眺めていいました。
おばさんはゴクンとつばをのみこんで、野ねずみさんの手からひとにぎりの黒い種を受け取りました。
「雨が降ったあとに種をまいて、毎日、朝と晩に水をあげるのを忘れないでね。虹の花は水をやるのを忘れるとすぐに枯れてしまうのよ」
おばさんは虹の種を両手で大事に持って、野ねずみさんの話しにうんうんとうなずきました。
「それから、朝早く、つぼみのうちにつみとるの。そして糸を染めてごらんなさい。さあ、こうしてはいられない。わたしはまだ仕事の途中なの。野原の草が雨で濡れているうちに、種まきもしないといけないし、虹の根もとまで行って、虹の種をとりにいかなくてはいけないの。さっきの虹は素敵だったでしょう。あれだけ大きな虹だったらきっと虹の種もたくさんできているわ」
野ねずみさんはひとりごとのように言うと、また背中にかごを背負い、足早に歩き始めました。
「気をつけて・・」
おばさんは夢をみているようにぼーっとした顔で、野原の草の上を走るように歩いていく野ねずみさんを見送りました。
二人はしばらくの間、野ねずみさんのうしろすがたをじっとながめていました。野ねずみさんの姿が木のかげに消えて、それからゆっくり空を見上げると、もう大きな虹は、どこにも見えませんでした。
ゆみ子は目をこすりました。
目の前で赤や黄色や緑色の虹の色がちかちか輝いていました。ゆみ子はもう一度目をこすり、そっとまわりをみまわしました。
ゆみ子はたくさんの色の糸の束を並べた板の間に、ぺったりと座りこんでいました。
「あらら、ゆみちゃん、ほっぺたにどろがついている」
おばさんも同じように板の間にぺったりと座り込んでいました。おばさんはゆみ子のぽっぺたをそっとぬぐってくれました。
それから、おばさんはポケットから白いハンカチ出しました。そして、ひざの上にひろげ、ハンカチの上でこぶしをそっとひらきます。白いハンカチの上に黒い粒がパラパラと落ちました。
「虹の花の種!」
ゆみ子はびっくりして大きな声をあげました。
「そう・・」
おばさんはうなずきます。
おばさんは種がこぼれないようにハンカチをていねいにたたんでから、ゆっくりと立ち上がり、糸の棚の前にいき、棚の上にハンカチをそっとおきました。
「あらら、今日はすてきな夕焼けだ」
おばさんの言葉にびっくりしてゆみ子が窓にとんでいくと、空はあかね色に染まっていました。
「さて、おばさんは夕焼けの織物を仕上げるわ」
「わたしはピアノの練習にいく日だったの」
ゆみ子は板の間のすみっこにころがっている布かばんを見つけてぽつりとつぶやきました。
「明日、裏庭に花畑をつくるから、手伝ってね」
「うん」
ゆみ子はしっかりうなずきました。
重たいピアノの本が2冊入った布かばんを肩からぶらさげて、ゆみ子はおばさんの家を出ました。ゆっくり歩きながらなんども振り返り、ゆみ子はおばさんに手をふりました。
1
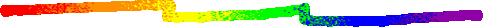
copyright Chie Nakatani 中谷千絵