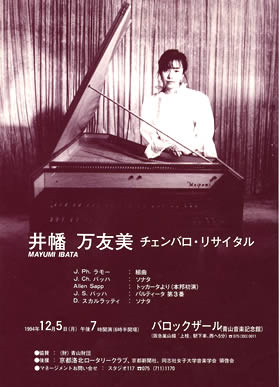|
�@
|
| ��J�EPh�E�����[�@�^�����T���ȏW��1�W |
| �@ |
�t�����X�̍�ȉƃW�����E�t�C���b�v�E�����[�B
�ނ̃`�F���o���̂��߂̑�1�Ԗڂ̋ȏW�́A���R�ȋȂ̗���Ŏn�܂�O�t�ȁA���ɃC�l�K�[���ƌĂ�邻�̓����t�����X�ł悭�g���Ă�����@���ӂ�Ɏg�����A���}���h�A2���q��3���q�̓��荬����N�[�����g�A�₳�����̂��ӂ��T���o���h�T�A�T�T�A���킢�炵�������������R���b�N�ȃ��k�G�b�g�A�����čŌ�͉��t�ҋ������̑�������������Ƃ���Ɍ����W�[�O�ւƑ����܂��B
�t�����X���y�ƌ����Ƃǂ��ƂȂ��y�₩�łӂ�ӂ킵�Ă���C���[�W������̂ł����u���������A�����Ƃ���̋����Ƃ���������ł���I�v�Ƃ��̋Ȃɋ�����ꂽ�l�ȋC�����܂��B
|
| �@ |
| ��J�ECh�E�o�b�n�@�\�i�^
Op,17 No,6 |
| �@ |
�o�b�n�ƌ������n���E�Z�o�X�`�����E�o�b�n�ƂȂ�̂ł����A�ނ̑��q�B�̂������l���͂ƂĂ��D�G�ȉ��y�Ƃł����B
���̂�����1�l���n���E�N���X�`�����E�o�b�n�̃\�i�^�A�ǂ������[�c�@���g�̗l�ȁc�c�B
��1�y�͂̓����f�B�[�Ɣ��t�p�[�g�Ƃ������Ƀ`�F���o���̎����������ĐF�������邩���A������ł����肨�����낳�ł�����̂�������܂���B
�����đ�2�y�͂͂Ђ����琨������B�����f�B�[��������艺������Ƃ��Ă��}�������̂ł��B
|
| �@ |
| ��Allen Sapp �u5�̃g�b�J�[�^�v���
No.1 No.4�i����ȁj |
| �@ |
�A�����J�̍�ȉƃA�����E�T�b�v���B���̃g�b�J�[�^��e�����č����̂��䉏�ōݕĒ��悭�z�[���p�[�e�B�[�ɂ�������������A��܂��̂����������Ē�������A����͂����A���킢�����Ē����܂����B
���̓t�����X�Ō������ς܂�Ă���A�p�[�e�B�[�ł͂��������`�[�Y�Ƀ��C���A���l�̂��藿���A�����ĉ��������y�j�̖{�̒��ł������ڂɂ����������Ƃ̂Ȃ��l�ȗL����ȉƒB�i�Ⴆ�V�F�[���x���N�j���A���̓������Ƃ��ďo�Ă��邨�b�Ɏ��̂��̂��Y�ꂽ���̂ł����B
�����ɓo�ꂷ��2�Ȃ̃g�b�J�[�^�́A�u5�Ȃ̃g�b�J�[�^�v�̂����ł��`�F���o���̖����I�ȕ������g�킹�Ă����ȒB�ł��B
�u�����ԈႦ�Ēe���Ă�́H�v�Ȃ�Č���Ȃ��ʼn������ˁB1��1�̉��͐������̗l�Ɉӎu�������ē����Ă���̂ł��B |
| �@ |
| ��J�ES�E�o�b�n�@�p���e�B�[�^��3�ԁ@BVW827 |
| �@ |
���q����̌�͂����l�A�h�C�c�������y�̕����n���E�Z�o�X�`�����E�o�b�n�̓o��ł��B
�p���e�B�[�^�Ƃ͑g�ȁB����������߂̃����[���l�A�������̏����ȋȂ���o������Ă��܂��B�܂��̓t�@���^�W�A�A�E��ƍ��肪�����f�B�[�̐^�������������鏊�ł���L���܂��B
�����ĕ��ɗh��郌�[�X�̗l�ȃA���}���h�A�����U���I�ȃR�����e�A�����Ƃ藎���������T���o���h�A������Ƃ��錫���s�G���̃C���[�W�̃u���X�J�A�����̓h�W�ȃs�G���̃X�P���c�H�A�Ō�͑��t���Ԃ��Ȃ��W�[�O�ŏI���܂��B |
| �@ |
| ��D�D�X�J�����b�e�B�@�\�i�^ |
| �@ |
�Ō�̓C�^���A�̍�ȉƃh���j�R�E�X�J�����b�e�B�B�ނقǃ`�F���o���ׂ̈ɋȂ������Ă��ꂽ�l�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ɂ��ƃX�J�����b�e�B�̓M�����u���D���ł��ꂪ�����Ď؋��ԍςׁ̈A���M�̊y����Ƃ����ƌ����Ă��܂��B
����䂦���ǂ����A�ނ̍�i�͒e���Ă��ĉ��y�̏�ł́h�V�сh���ӂ�Ɏg���Ă���Ɗ�����͎̂������ł��傤���H
�M�^�[�̃��Y������A���̂Ԃ��肠������A�ƂR�̃����f�B�[��������Ɛ��肾������B�������Ǝv���ƂƂĂ�����������������������A�O���邱�Ƃ̂Ȃ����e�ł��B |
| �@ |