|
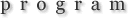
G.Fr.ヘンデル
「第3組曲 二短調」
プレリュード
アレグロ
アルマンド
クーラント
アリアと5つのヴァリエーション
プレスト
D.スカルラッティー
「ソナタ」より
k.420 ト長調
k.308 ハ長調
k.264 ホ長調
●休憩●
J.Ph.ラモー
「クラヴサン曲集」より
喜び
やさしい嘆き
鳥のさえずり
一眼巨人たち
J.S.バッハ
「イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807」
プレリュード
アルマンド
クーラント
サラバンド
ブーレ I&II
ジーグ
|
|
|
|
■G.Fr.へンデル「第3組曲 二短調」
|
| |
ヘンデルはドイツ生まれ、けれども、後にイギリスへと渡りその地で活躍をします。
もともとはドイツのハノーヴァーの宮廷楽長として活躍するはずであったヘンデルですが、その職に就くや否や休暇届けを出しロンドンへとむかいます。そして、その地でデビューを果たしてしまうのです。
一旦は帰国するものの、再び休暇をとりロンドンへ。彼は外国人にもかかわらず、確実にイギリスの国民的作曲家になっていくのです。
さて、この一件でヘンデルは雇い主である選帝候に不義理をするのですが、何の因果かこの選帝候が王位継承確定法によってこともあろうかジョージⅠ世としてイギリス王位を継承することとなるのです。
彼らは和解し、めでたく雇用関係はここイギリスで成就されるわけです。そしてこの雇い主の王女キャロラインの娘たちのレッスン教材として作曲したものを集め出版したのがこの「組曲集」なのです。
その3番目こ位置する「ニ短調 組曲」は情熱的で即興的なプレリュードに始まり、息の長い旋律が折り重なるように登場するアルマンド、少しメランコリックで特徴のあるリズムを持つクーラント、こってりと装飾音の付けられているアリアのテーマ、そして5つのヴァリエーション(変奏)がテーマに比べればシンプルな動きをしながら続きます。
最後はリトルネロ形式によるブレストの終楽章。リトルネロ形式とは、合奏部分が登場し、それが一段落したら、ソロの部分が登場、それが交互に繰り返されていくという形式です。勿論、チェンバロだけで弾き分けるのですが‥‥‥ |
| |
| ■D.スカルラッティー「ソナタ」より |
| |
スカルラツティーはイタリアに生まれ、晩年にはポルトガル、スペインで過ごします。そしてその間、実に555曲のソナタをこの世に残すのです。にも関わらず、このソナタたちの自筆譜は存在しないそうです。
この理由は、当時大きな火災がおこり全て消失してしまったとされる一方、実はスカルラッティーはかなりのギヤンプラーで、借金のかたに自分の書いた楽譜を売り払ったと言う実しやかな噂もあります。
その555曲の中から3曲を選びました。私は気が付くと短調の曲を選ぶ傾向があるのですが(根が暗いのかしら?)、今回はめずらしく3曲とも長調です。
音域がかなり広く、今日弾く楽器では鍵盤が足りないので少々編曲したお茶目なK427、カンタービレ・歌うようなK308、生き生きと元気いっぱいのK264の3曲を。 |
| |
| ■J.Ph.ラモー「クラヴサン曲集」 |
| |
フランス生まれのラモーは「まさにフランス人」と言えるかなりの理論家でした。要するに理屈をこねるのが好き(?)いえいえそんなことを言ってはいけません。その理論好きのおかげで、彼は私たちに有益な理論書を残してくれているのですから。
とは言うものの理論好きのイメージとはうらはらにラモーのクラヴサン(チェンバロのフランス名)曲は快い田園的な色を含ませたチャーミングな曲たちばかりです。
今宵は、1724年に作曲された曲集から、喜びが心からあふれ出るかのごとく始まる「喜び」、苦しい恋煩いをとつとつと伝える「やさしい嘆き」、鳥かご中の鳥たちがいっせいにおしゃべりを始める「鳥のさえずり」、一つ日の巨人たち登場!!彼らがコミカルに動き回る「一眼巨人たち」を。 |
| |
| ■J.S.バッハ「イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807」 |
| |
音楽の父としてお馴染みのバッハはドイツから一歩も出ずして生涯を終えます。
勿論ドイツ国内では何回も引っ越しています。そして、ワイマールという都市にいる時に(ケーテンという説もありますが)彼はプレリュード付きの組曲を6曲作曲しました。それがこの「イギリス組曲」です。
このタイトルの「イギリス」はバッハ自身が付けたものではなく、もともとは、曲集が高貴なイギリス紳士のために作曲されたからとか、力強く厳格な曲の性格を当時のドイツ人の目から見たイギリス人の国民的性格と結び付けた、などの所説による通称だったようです。
さて、それはさておき、今日弾かせて頂くイ短調の組曲は長大なプレリュードで始められ、優しい風情のアルマンド、小さな勇気で向かっていくようなクーラント、スウイングしながら優雅に踊るサラバンド、農夫の踊りのように少し土臭いユーモアを持つブーレⅠ、そして牧歌的なブーレⅡ(その後またブーレⅠを繰り返します)、唐草模様のように旋律が絡み合うジーグへと続いていきます。
この曲の特徴としてプレリュードが兎に角長い……、その長さたるや楽譜のページ数にすると、後に続く舞曲全部の分をあわせたのと同じくらいです。
プレリュードが終わればこの曲の半分が経過したと思ってください。 |
|
