ホーム>このページ(updated September 8th, 2002)
| 2002年6月の本 | |
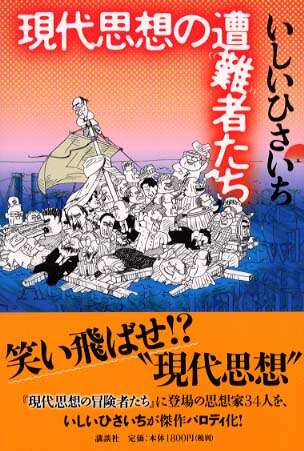 |
いしいひさいち『現代思想の遭難者たち』(講談社、2002年) |
| 『現代思想の冒険者たち』(31巻シリーズ)の各巻には、その巻で取り上げられた思想家に関する小冊子が折り込まれていて、その小冊子に連載されていた石井ひさいち(被災地)の「思想家オチョくり4コマ漫画」が本書の母体になった(書き下ろしも多数あり)。 このオチョくり漫画の大ファンであった私は、それらが編集されて本になるとの知らせをシリーズ最終巻に見つけて以来、ずっとその日を待ちわびていた。その願いが、ようやくこの6月に満たされたのである。当初のタイトル案が『超越論的認識不足』だったらしいが、執筆の苦労(刊行遅延の理由)が偲ばれるエピソードである。 けっこう難しかったりもするが、たとえば、ちょっとでもロールズの思想をかじったことのある人であれば、ロールズをオチョくった「ロールズ・パン」(p.156)を読むだけで大笑いだろう。「ののちゃん」の藤原先生も出演してます(バフチンで)。 | |
| 2002年7月の本 | |
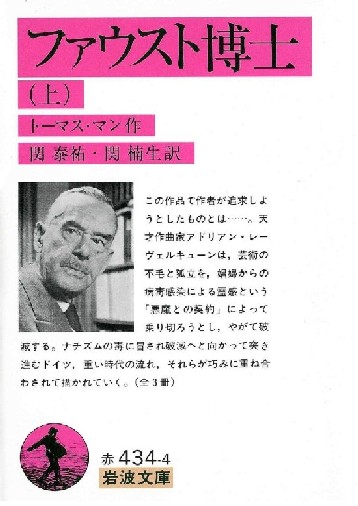 |
トマス・マン『ファウスト博士 上・中・下巻』(岩波文庫、1974年) |
| ゲーテの『ファウスト』を読んで以来、いつかは読みたいと思っていたトマス・マンの『ファウスト博士』。長らく絶版であったが、ようやく昨夏復刊された。とはいえ30年以上も前の翻訳なので、1000ページ近い分量を読むのは大変であった。 「悪魔の助けと釜の下の地獄の火がなければ芸術は不可能」と考える作曲家レーヴェルキューンは、娼婦から意図的に梅毒をもらうことによって創作の霊感を手に入れ、いくつもの傑作を生み出していく。そのレーヴェルキューンが最終的に狂気に陥るまでの人生が、ナチズムによって破局へと向かうドイツの歴史と重ね合わされながら友人によって語られていく。少々複雑な構成の小説である。 ゲーテのファウスト教授は最後の場面で救済されるが、レーヴェルキューンは最後に発狂し、10年の余生を闇の中にさまよい死んでいく。実に暗い、暗い結末。20世紀前半のドイツに対するマンの警句と嘆きが、痛切に響いてくる。 レーヴェルキューンは、ベートーヴェンの第9交響曲のアンチテーゼとして『ファウスト博士の嘆き』(悲哀に寄せる歌)を作曲し、発狂していく。この曲はどのような響きの曲なのだろう、と思わずにはいられない。 | |
| 2002年8月の本 | |
 |
石川達三『人間の壁 上・中・下巻』(岩波現代文庫、2001年) |
| 昭和30年代を舞台とするこの小説では、戦後民主教育の定着を目指す教師達と、教育に対する国家統制を強める自民党との激しい対立を背景に、小学校教師の志野田(尾崎)ふみ子が、民主教育とはいったい何なのか、それをどのようにして実践すべきなのか、その実践を阻もうとする政治に教師はどう向き合うべきなのか、といった点について悩みながら成長していく姿が描かれる。3冊で1200ページ近くにもなるが、石川達三らしい、文体の醸し出す迫力もあって、実に読み応えのある小説になっている。 いろいろと考えさせられることの多い小説だったが、なかでも、とりわけ印象に残った下りは、小学校5年生の浅井吉男が、貧困ゆえに鉄道事故にあって死んでしまう事件。浅井吉男は、25円のノートがたった3円安く買えるというだけの理由で、激しい台風の中を遠くの文房具屋まで買いに行き、その帰りに機関車にはねられて死んでしまう。3円を節約しなければいけないという「貧しさ」が、1人の命を奪ってしまう悲劇。こういった悲劇を日常的に生み出していくものこそが、「貧しさ」なのだろう。そんな貧しさは、この本の至るところで描写されている。 | |
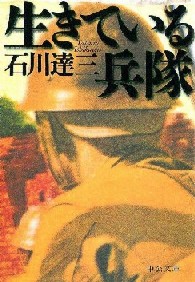 |
石川達三『生きている兵隊』(中公文庫、1999年) |
| これまた石川達三の著作。南京攻略戦に至るまでの日本軍の有り様を書いた作品で、昭和13年に4分の1ほど伏せ字にされて『中央公論』に掲載され、即日発禁とされた。石川は、南京と上海における2週間ほどの従軍取材をもとにして、この作品を書き上げている。 発禁にされたぐらいであるから、当時の軍部にとってよっぽど都合の悪いことが書かれていたのかと思いきや、今読んでみると特にそうとも思えない。日本軍による残虐行為の描写もあるにはあるが(とりわけ小説冒頭の殺人は、むごい)、本書の大半を占めるのは戦場における兵隊の心理状態に関する記述。が、しかし、その記述が戦場で徐々に正気を失っていく人間の有様をニヒリスティックに描いていて、空恐ろしい気分にさせてくれる。そんな兵隊の一人である倉田少尉の独白、「兵隊は戦争にあっては戦うべきものであって反省すべきではないのだ。……」。兵隊はこうやって作られていくのだな。 | |
| 2002年9月の本 | |
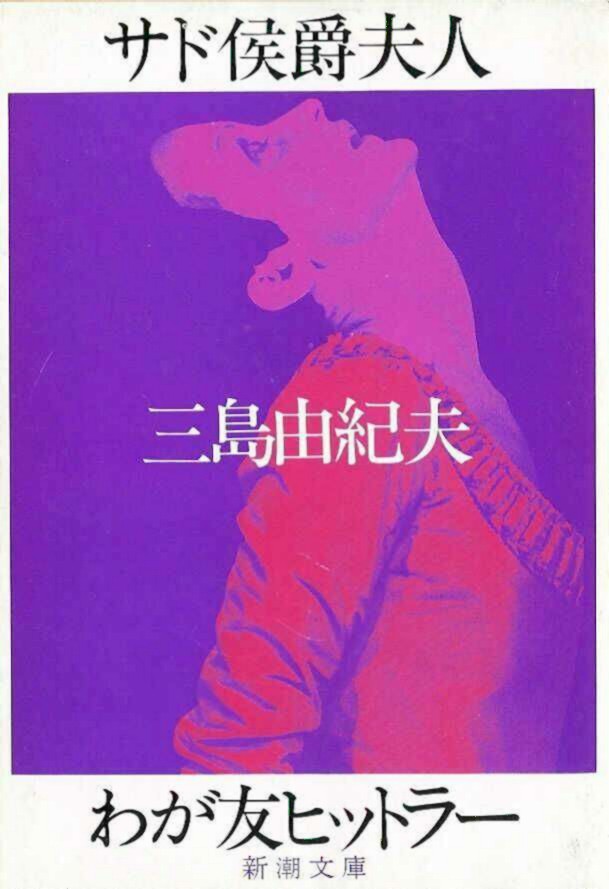 |
三島由紀夫『サド公爵夫人・わが友ヒットラー』(新潮文庫、1979年) |
| レーム事件(1934年6月)の舞台裏を明かす戯曲、『わが友ヒットラー』が面白い。出演は、ヒットラー、レーム、G・シュトラッサー、クルップの4名。このレーム事件というのは、ナチス突撃隊とドイツ国防軍との対立を回避するために、ヒットラーが突撃隊参謀長レームらを中心とするナチス党不満分子を粛正する、という事件。ヒトラーはこの結果、国防軍の支持を得て、ヒンデンブルク大統領の死後に総統の地位へとのし上がっていくことになる。 レームはヒットラーを信じて疑わない単純な軍国主義的人物として、シュトラッサーは社会主義革命の進展を望む教条的な人物として描かれている。クルップは、ヒットラーにうまく取り入ろうとする狡猾巧みな経済人として描かれている。 レームとシュトラッサーが粛正された後、戯曲は、ヒットラーとクルップの二人が交わす会話で幕を閉じる。その会話において、ヒットラーが粛正を正当化しようとして言い放つ台詞が意味深長で恐ろしい。 クルップ 「アドルフ、よくやったよ。君は左を斬り、返す刀で右を斬ったのだ。」 ヒットラー 「そうです、政治は中道を行かなければなりません。」 政治家達が使う「中道」らしき言葉の、いかに胡散臭いことか。騙されないようにしないといけません。 | |