|
ようこそお詣り下さいました。本日は、この行松・専林寺様の鐘楼堂の落慶法要でございます。このようなお目出度い法要に、皆様とともに逢わせて頂きましたご縁を、有り難く存じております。 皆様方とは、おそらく初めてお目にかかるのではないかと思いますので、まずは、自己紹介をさせて頂きます。私は、京都から参りました紫雲寺の伴戸昇空と申します。 私の家内は、柿原・専教寺の娘でございます。ご承知のように、柿原・専教寺のご住職は、このお寺から見ますと孫筋にあたります。その柿原のご住職は、こちらの鐘楼堂建立のお話しがありました当初から、本日の落慶法要を心待ちになさっておられて、そのときには法要準備の一切を引き受けるおつもりだったと伺っております。 ところが、昨年の秋に急な病で床につかれ、本年の3月4日に、浄土にお帰りになりました。法名は、「還相院釋了然」、享年47歳でございました。了然様は、私にとりましては義理の兄にあたります。本日は、その義兄の願いを引き継ぐ形で、お話しさせて頂くご縁を頂戴いたしましたようなわけでございます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 さて、法要というのは「法の要」と書きます。「法の要」というのは、「仏法の要」のことですが、私たち門徒にとりましては、「仏法の要」というのは、「お念仏の教え」を聞くこと、「名号のいわれ」を聞くことでございますね。 嬉しいことがあったとき、悲しいことがあったとき、その嬉しいこと、悲しいことをご縁として、改めて仏様と向き合い、「お念仏の教え」を聞くこと、聞法すること、それが、私たちの法要でございます。 本日は、お同行の皆様が力を合わせて建てられた鐘楼が完成した、その喜びをご縁とする法要でございますので、「梵鐘に聞く」という題で、少し申し上げたいと思っております。その内容はと申しますと、「梵鐘は、時を告げるために鳴るのではなくて、時を止めるために鳴るのだ」という話でございます。 皆さんは、朝から準備でお忙しい思いをなさって、お稚児さんたちのおねりや、お勤めもございましたので、もうお疲れかとは存じますが、どうぞ、しばらくのあいだ、お付き合い下さいますよう、お願い申し上げます。 さて、まずは、この歌を聴いて頂きましょう。
「夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る、 いかがですか。お寺の鐘というと、私たちは、まず、この「夕焼け小焼け」の童謡を思い出すのではないでしょうか。それも、ただ思い出すのではありませんね。懐かしいような、ホッとするような、なんとも穏やかな気持ちになってくる。故郷を離れている人は、故郷を思い出す。違いますかね。 夕焼け空には、浄土のイメージがある。落日の彼方に浄土がある。浄土往生を願って、茜雲の彼方に手を合わせる。そんな人の姿が、昔は、ありましたね。そこに、お寺の鐘が、ゴーンと聞こえてくる。故郷を思い出しなさいと、聞こえてくる。 命あるもの、全ての帰る故郷がある。その故郷へ帰ろう。それが、「お手々つないで皆かえろ、烏と一緒にかえりましょう」なのですね。仏教の言葉で言えば、「一切衆生、悉有仏性」なのです。私たちがこの歌を聴いてホッとするのは、帰る故郷があることを、心のどこかで思い出すからではないでしょうか。 「故郷は何処ですか」と尋ねますとね、皆さんは、たいてい「福井県の武生です」とお答えになりますでしょう。それには違いないのですが、それは、皆さんの「体の故郷」なのですね。私たちの「魂の故郷」は、お浄土なのです。そして、その二つの故郷をつなぐ「心の故郷」として、お寺があるのです。お寺の鐘の音は、娑婆と浄土、この世とあの世をつなぐ音なのです。 大晦日には、あちこちのお寺で除夜の鐘が突き鳴らされます。あの鐘の音を聞きながら、私たちは、行く年を思い、来る年を思い、何とも言えない感慨を抱くわけですが、お寺の鐘の音には、私たちの心を揺さぶる不思議な力があるのですね。 『平家物語』の冒頭にも、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり、娑羅双樹の花の色盛者必衰の理をあらはす…」という有名な言葉があります。「鐘の声に諸行無常の響きがある」というのは、「鐘の音に、お説法が聞こえる」ということですね。 私たち仏教徒は、梵鐘の音に、仏様のお説法を聞いてきたのです。私たちには、耳で聞くことによって、目に見えない世界とつながる力が備わっているのです。目に見えない世界というのは、仏の世界、お浄土のことですね。 まあ、そうは申しましても、梵鐘の音を、耳で聞いている間は、ゴーンという音がするばかりで、お説法は聞こえてきません。そうではなくて、何も考えずに、一心に梵鐘の音を聞いていると、聞いている「私」が無くなって、梵鐘の音だけになっていく。そのとき、その梵鐘の音のなかに、浄土への入り口が開かれてくるのです。 別の言葉で申しますと、一心に梵鐘の音を聞いていると、心の動きが止まってくるのです。心の動きが止まると、そこに、お浄土への入り口が開けてくるのです。 「心の動きが止まると、お浄土の入り口が開けてくる」というのは、「たとえ話」ではございません。どういうことかと申しますとね、「浄土」はどこにあるのかと申しますと、実は、「今、ここに」あるからなのです。 ここは「浄土」ではない、とおっしゃるのなら、それはそのとおりです。それでも、「浄土」は「今、ここに」あるのです。「浄土」は「今、ここに」あるのですが、私たちが、その「今、ここに」いないのです。ですから、「浄土」が感じられないのです。なにか禅問答みたいに聞こえるかもしれませんから、もう少し順序だててお話し致します。 私たちは「今、ここに」いる、と思っています。たしかに身体はここにあります。ですが、心が「今、ここに」ないのです。日常の私たちは、何もしていないときでも常に休みなく頭のなかでオシャベリをしています。常に何かを考えていると言ってもよいでしょう。 「過去」を誇ったり悔やんだり、「未来」に期待したり不安を抱いたりして、決して「今」のこの一瞬にとどまっているということがありません。つまりは、頭のなかで「過去」へ「未来」へと走り回っている私たちは、「今、ここに」はいないということになります。 「過去」は過ぎ去ってしまいました。ですから、「過去」は、いまさらどうしようもありません。「未来」はまだ来てはおりません。ですから、「未来」は、まだどうなるか分かりません。私たちは、そんな「どうしようもない」世界と「どうなるか分からない」世界をうろうろしているものですから、いつまでも心が温まらないのです。そうではなくて、心の温まる世界、「浄土」は、「今、ここに」あるのです。
「時」というものは、「過去」から「現在」を経て「未来」へと続く一筋の流れのようなものと考えられております。しかしこの流れは、「過去」「現在」「未来」という三つの積み木を、このように一列に並べたような関係にはなっておりません。 そうではなくて、「時の流れ」を積み木で表わすとすれば、「過去」と「未来」という二つの積み木がくっついているだけです。そして、この二つの積み木の接点が「現在」に相当するという関係になっております。 たとえばですね。私がこれから「いま」という言葉を声に出して言うとしますね。すると、「いま」の「い」と言ったときには、もう既に「い」と言ってしまったのですから、その「い」という部分は「現在」には無くて、もう「過去」に流れ去っているのです。ところが、「いま」の「ま」という部分はまだ声に出しておりませんから、この「ま」はまだ「未来」にあるのです。つまり、「現在」とは、「過去」と「未来」という2つの積み木がくっついている、この接点にあるということです。 ですから、本当の「今」というのは、「過去」と「未来」という2つの積み木にはさまれた、この「緑色のシート」のようなものです。つまりは、時間の流れからはみだしている世界、時間を超越した世界が、本当の「今」なのです。そして、私たちの日常的な意識とは次元の異なった、「今、ここに」ある広大な世界が、「浄土」なのです。 この「今」という世界には、心のなかのオシャベリがとまったときに、初めて入っていくことができるのです。たとえば、私たちが「現実」と呼んでいる「娑婆」世界は、心のなかのオシャベリによって、こんなふうに「過去」と「未来」にまたがっておりますね。このオシャベリが段々と納まって行ったとき、私たちは自然に、この「今、ここに」ある本来の命の世界、「浄土」に入っていくのです。 「心の動きを止める」というのは、時間を止めるということなのです。時間を止めて、「今」になるということです。「悟る」というのは、この「今」にあり続けることができるようになることです。「仏」の世界は、何処にもなくて、「今、ここに」あるのです。 ところが、現代社会では、この「今、ここに」生きるということが非常に難しくなってしまいましたね。現代は、効率と能率を重んじる競争社会です。ですから、一定時間に、どれだけ多くの仕事を詰め込むかということばかり考えるようになってしまいました。 仕事をこなすことばかりに気を取られて、速くこの仕事を片付けて、次にかかりたいと、追われるように走り続けているのが、私たちです。「速く片付けて、次にかかりたい」というのは、心が「ここ」にないということですから、そうなると、もう「今」を感じることなど、なかなか出来ませんね。 そんな私たちは、日々、忙しい、忙しいと、まるで、忙しいのを手柄のようにして、生きております。たしかに、私たちの生活は、「忙しく、慌ただしい」ものです。ですが、「忙しい」という字は、「立心偏」に「亡くす」と書きます。また、「慌ただしい」という字は、「立心偏」に「荒れる」と書くのです。 「忙しく、慌ただしい」生活は、心を亡くす生活、心の荒れる生活でもあるのですね。そんな「忙しさ、慌ただしさ」に流されている自分を、娑婆の喧噪から救いあげる。日常の時間を止めて、「今」に生きる時を持つ。そのご縁となるのが、梵鐘なのですね。 お寺の鐘は、朝夕の決まった時間に鳴るものですから、梵鐘は時を告げる鐘だと思っていらっしゃる方が多いのですが、そうではないのです。こちらのお寺では、夕方の5時に梵鐘が鳴りますが、その鐘の音を聞いて、「ああ、もう5時や、そろそろ仕事をやめて帰ろうか」というのでは、梵鐘が泣きますよ。 梵鐘は「時を告げる鐘」ではない。梵鐘は、農業放送の時報ではないのです。農業放送の時報と同じだというのなら、梵鐘など要らないでしょう。梵鐘は、時を告げるために鳴るのではないのです。梵鐘は、時を止めるために鳴るのです。 梵鐘の音が聞こえてきたら、仕事の手をとめて合掌する。梵鐘の音を聞くのではなくて、梵鐘の音になるのです。そのとき、時間が止まって、浄土への入り口が開かれてくるのです。梵鐘の音は、その「浄土の入り口に立ちなさい」という、ご催促なのですね。 私たちは、梵鐘の音に「魂の故郷」の歌声を聞くのです。「お浄土」からの懐かしい歌声を聞くのですね。私たちは、根無し草ではない。私たちには、帰っていく故郷がある。私たちはみな、お浄土から生まれてきて、また、そのお浄土へと帰っていくのです。そのことを教えて下さっているのが、「浄土の教え」なのですね。
どういうことかと申しますと、時間を止めると、煩悩の働きが止まるからなのです。たとえば、怒りや、不安や、自惚れや、野心といったものは、煩悩の働きから生まれてくるものですが、怒りは「過去」からやってきます。不安は「未来」からやってきます。自惚れは「過去」からやってきます。野心は「未来」からやってくるのですね。 煩悩のエネルギー源は、「過去」と「未来」にあって、「今」には無いのです。煩悩は、時間のなかでしか生きられないのです。ですから、時間が止まれば、煩悩の働きも止まるのですね。 私たち門徒は、「お念仏」という仏の智慧を頂いておりますが、この智慧はどんな智慧かと言えば、煩悩と争わずに、煩悩の働きを止める智慧なのです。つまりは、時間を止める智慧なのです。 お念仏は、「はからいをはなれ、ただ一心に称える」ものでございますね。「はからいをはなれ」というのは、「自分の頭で考えることをやめる」ということです。たとえば、「お念仏を称えることで救われよう」というのも「はからい」ですし、「お念仏なんか称えて何になるんだ」というのも「はからい」ですね。そういったことを一切考えない。それが「はからいをはなれる」ということです。 「はからいをはなれる」ということは、「心の動きを止める」「頭の中のオシャベリを止める」ということです。ですが、これは、そうしようと思っても、なかなかできることではありませんね。「はからいをはなれよう」とするのも、ひとつの「はからい」ですからね。 そこで、「ただ一心に称える」ということが大切になるのです。お念仏を一心に称えれば、心の動きが止まります。つまりは、頭のなかのオシャベリが止まり、時間が止まるわけです。 「ただ一心に」というのは、「念仏だけを思う」ということです。「お念仏」を称えながら、何かを思ったり考えたりしないということです。よく、「お念仏を称えながら一日を反省する」などとおっしゃる方がおられますが、これは違います。「お念仏」を称えながら「反省」するというのでは、これは「一心」ではなく、「お念仏」と「反省」という二つの心になってしまいます。 ですから、「お念仏」を称えながら、「反省」したり、「我が身の後生」や「先祖の供養」を願ったりしていたのでは、「ただ一心に」というわけにはいきません。「お念仏」を称えながら「反省」するというのは、「お念仏」の入ったコップの中へ「反省」という氷を入れるようなもので、真剣に「反省」すればするほど、心のなかから「お念仏」が出ていってしまいます。 「ただ一心に念仏を称える」というのは、「心」を「お念仏」で満たすということです。もう少し進んで申しますと、それは「お念仏そのものになる」ということなのです。お念仏そのものになったら、そのとき、「お浄土」を感じられるようになり、「浄土の教え」が信じられるようになるのですね。 確かに、現代科学の教育を受けた私たちは、「浄土から生まれて来て、また、その浄土へと帰っていく」と教えられても、なかなか信じられないのです。ですが、信じられないからこそ、お念仏を称えるのです。真宗の奥義を伝える道歌にも、こう歌われています。「信なくば、つとめて御名を称うべし、御名より開く信心の花」と。 信じられなくとも、聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、感じることが出来るようになっていきます。感じるけれど、分からない。分からないけれど、感じる世界がある。その、感じる世界をしっかり受けとめること。それが信じるということなのです。 私たち現代人は、何でも目で見るということにこだわりますけれど、もともと、神や仏というものは、目で見て確かめるものではないのです。神や仏というものは、耳で聞いて、心で感じるものなのですね。 現代は、信仰心というようなものは死に絶えたと言う人もいますが、私は、先日、新聞で、こういう話を読みました。大阪の柏原市にある、四世代同居のブドウ専業農家のお爺さんが亡くなったときの話です。 その農家の最年長者である谷口音三郎さんは、半年ほど自宅で介護を受けて、昨年11月に、89歳で亡くなった。農家の忙しい時期を避けて、しかも、親戚が集まっている場を選ぶかのように亡くなった、大往生だったそうです。 その臨終を看取った人々は、みな心の底から感動した。そのとき、息子さんのお嫁さんは、こう言われたそうです。「もうわたしは、死ぬこと怖くありません。帰る家がある。旅行と同じです」と。 そしてね、家族みんなが感動したのは、ひ孫の小学校5年生の弘美ちゃんが、黙って遺影の横に置いた手紙です。その手紙には、こう書かれていた。「大きいおじいちゃん、大事にしてもらってよかったね。お浄土でおばあちゃんにあいましたか」と。 この記事を読みまして、私も感動いたしました。小学校5年生の子供が、「大きいおじいちゃんは、お浄土へ帰った」と言っているのです。こういう言葉は、ご院さんの話を一回や二回聞いただけでは、なかなか出てきませんね。この家のご家族は、よほど聞法を重ねてこられたに違いない。信心が生きていると思いましたね。 「聞法」の「聞」という字は、「門構えに耳」と書きます。昔は、この「門構え」の「門」は、お寺の門で、お寺の門をくぐって自分の耳でお説法を聞くのが「聞法」だと言われていましたね。ですから、「聞法」と言うと、お寺で聞くお説法のことを思うわけですが、昔は、お寺だけでなく、ご家庭にも聞法の場がありました。熱心な門徒さんのお宅では、ご家族の間で、よく仏法の話をなさったと聞いております。 たとえば、奥さんが、「お父さん、このあいだご院さんがなさった話を、私は、こう聞いたのですが、どうでしょうね」とおっしゃると、ご主人は、「いや、わしは、こう聞いた」というような議論が、日常的にあった。そういうやりとりを傍で聞きながら、子供さんたちが育っていったのですね。 ですが、今はかなり変わってしまいましたね。皆さんのご家庭でも、ご家族で、そういった仏法の話しをなさることは、なかなか無いのではないでしょうかね。皆さんの、子供さんやお孫さんは、「おじいちゃんやおばあちゃんは、亡くなったら、お浄土へ帰っていくのだ」と思っておられるでしょうか。それとも、「死んだら終わりだ」と思っておられるのでしょうかね。 京都と福井では事情が違うかもしれませんが、私は、お通夜の席などで、ご親族の方が「死んだら終わりや」とつぶやかれる声を、よく聞きます。ですがね、皆さん、私たち門徒の頂いている「浄土の教え」というのは、「死んでも終わらない」という教えではなかったでしょうかね。 現代人は、科学に遠慮して、口を濁してしまいますが、本当は、私たちは、死んでも終わらないのです。私たちはみな、お浄土へ帰っていくのです。それが、私たちの「命の真実の姿」なのです。 聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、そのことが心の底から納得できたとき、自ずと「死ぬことへの不安」は解消されます。「死ぬことへの不安」が解消されたとき、初めて、私たちは、本当に生きることができるようになる。心安らかに生きることができるようになるのです。 「死ぬことへの不安」が解消されれば、老いていく日々を楽しめるようになり、病からも学べるようになる。そして、生まれてきたことを、喜べるようになるのです。 「死ぬことへの不安」が解消されたとき、仏教の言葉で「安心(あんじん)」を得たと言います。「安心」を得た人は、心安らかに本当の自分を生きることが出来るようになり、命が輝いてくる。その命の輝きが、世界を照らす光となるのです。「浄土の教え」の本当の意味は、そこにあるのですね。 明治の歌人、正岡子規は、脊椎カリエスで36歳の若さで亡くなりましたが、その亡くなる少しまえに、こう言っています。「私は今まで禅宗のいわゆる悟りという事を誤解していた。悟りという事はいかなる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事はいかなる場合にも平気で生きている事であった」(『病床六尺』)と。 子規は禅宗の信徒さんでしたから「悟り」と言っておりますが、私たち門徒の言葉で「安心」と言っても同じことです。「安心を得た人は、いかなる場合にも平気で生きておれる」のです。思えば、私たちの人生にとって、これほど大切なことはありませんね。 私たちは、帰っていく故郷があると知ったとき、初めて、心安らかに生きることができるようになる。その「魂の故郷」を思い出しなさいと、今日も、お寺の鐘は鳴るのです。 梵鐘の音が聞こえてきたら、仕事の手をとめて合掌する。梵鐘の音を聞くのではなくて、梵鐘の音になるのです。そのとき、時間が止まって、浄土への入り口が開かれてくる。梵鐘の音は、その「浄土の入り口に立ちなさい」という、ご催促なのです。 浄土の入り口に立てば、自ずと、み仏の声が聞こえてくるでしょう。そのことを、こちらの御院様は、こういう歌に詠まれました。「新しき、香のただよえる、鐘楼の、鐘の音に聞く、み仏の声」。「梵鐘を聞く」のではない。「梵鐘に聞く」のですね。 「信心」というのは財産と同じです。親が持っていない「信心」は、子供に伝えることはできません。ですがね、これまた財産と同じで、親から伝えてもらっていなくとも、ご縁があれば、大きな「信心」を、一代で築き上げることもできるのです。 今日の慶き日がご縁となって、皆さんの心のなかに、大きな財産が築き上げられて行きますように、また、その財産が、末永く伝えられて行きますように、心より念じております。 本日は、鐘楼落慶というお目出度いご縁を頂きまして、皆様とご一緒に、心安らかなひとときを過ごさせて頂きました。有り難く存じております。また、ご縁がありましたら、ご一緒に聞法させて頂きたいと念じております。本日は、長い時間、お付き合い下さいまして、本当に有り難うございました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。 |
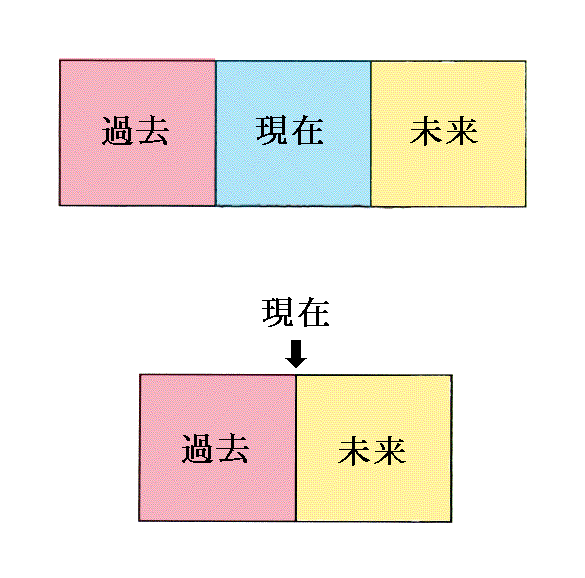 こう申し上げましても、まだお分かりにくいかもしれませんので、ひとつ、目に見えるたとえを使ってご説明いたしましょう。ここに3つの積み木があります。赤、青、黄色、とまるで交通信号みたいですが、赤の積み木には「過去」と書いてあります。青には「現在」、黄色には「未来」と書いてあります。
こう申し上げましても、まだお分かりにくいかもしれませんので、ひとつ、目に見えるたとえを使ってご説明いたしましょう。ここに3つの積み木があります。赤、青、黄色、とまるで交通信号みたいですが、赤の積み木には「過去」と書いてあります。青には「現在」、黄色には「未来」と書いてあります。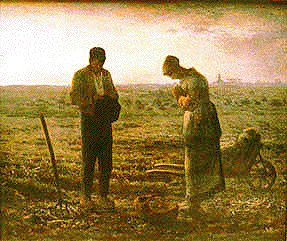 さて、これは、ミレーの「晩鐘」という有名な絵です。夕方、遠くの教会から聞こえてくる鐘の音に、二人の農民が、静かに合掌して佇んでいる。これは、信仰の生活を描いた絵です。この絵をご覧になって、何か心安らかな思いがなさいませんでしょうか。この絵は、時間が止まっているとは思われませんでしょうか。洋の東西を問わず、信仰の生活の核心は、日常の時間を止めるというところにあるのですね。
さて、これは、ミレーの「晩鐘」という有名な絵です。夕方、遠くの教会から聞こえてくる鐘の音に、二人の農民が、静かに合掌して佇んでいる。これは、信仰の生活を描いた絵です。この絵をご覧になって、何か心安らかな思いがなさいませんでしょうか。この絵は、時間が止まっているとは思われませんでしょうか。洋の東西を問わず、信仰の生活の核心は、日常の時間を止めるというところにあるのですね。