前回は、私たちの「現実」を生み出しているのは、他ならぬ私たちの「煩悩」(痴)だということを見てまいりました。しかし、煩悩は「満たされたい」という心の働きなのですから、結局は、煩悩も「救い」を求める心の働きだと言ってもよいかと思います。
ですが私たちは、外から他人の「生命エネルギー」を奪ってくるかぎり、完全に満たされるということはありません。奪ってきた「生命エネルギー」が常にどこからか漏れているからです。そのため、次から次へと外に働きかけ、奪い続けなければならないのです。つまり、煩悩による一時的満足は擬似的な救いでしかないということです。私たちが刹那的・攻撃的になるのはこのせいです。
煩悩も、手段こそ違え、本当は「救い」を求めている心の現われなのです。そうだとすれば、煩悩の強い人ほど、救いを求める力も強いといえるかもしれません。「氷多きに水多し、障り多きに徳多し」(高僧和讃)とか「煩悩即菩提」とかいうのも、この間の事情を表現した言葉ではないかと思います。では、本当の満足を得るにはどうすればよいのか。それは、「大きな生命」との関係を回復することです。今回は、このことについてお話し申し上げたいと存じます。
以前、私たちを「水(生命エネルギー)の半分ほど入ったガラスのコップ」にたとえ、このコップが「満たされていない」のは、「大きな生命」から切り離されて「生命エネルギー」が補充されなくなっているからだというお話しをいたしました。今回はこの「たとえ」に続けて、お話しを進めたいと思います。
「大きな生命から切り離されて」と申しましたが、たいていの場合、完全に切り離されているということはありません。私たちは「ガラスのコップ」というより、氷が張って水を汲み出せなくなった井戸のようなものといった方が、ここでは分かりやすいかもしれません。氷が張った理由は、誕生後の社会的経験や教育といった様々なマイナスの外気にあたったせいです。といっても、人によって多少異なるかもしれませんが、だいたい私たちの心の井戸に張った氷は回りが厚く、中央部はまだほんのわずかに薄氷が張っている程度ではないかと思います。
こうした「たとえ」で考えてみると、ことは意外に簡単なような気もしてきます。この氷を割れば、「大きな生命」とのつながりを回復できるのですから。…問題は、「では、どうやって割るのか」ということです。井戸の氷を割ろうとしたら、小石をぶつけてみるのも一手です。しかし、心の底に張った氷にぶつけることができる小石とは何でしょうか。実は、その小石として用いられていたのが、仏教では「南無(ナム)」、ヒンズー教では「オーム」、キリスト教では「アーメン」といった言葉ではないかと思います。
「ナム」というのは、もともとは「身を屈する」という意味です。漢文では、「帰命、帰敬、帰礼、敬礼、信従」などと訳されています。「オーム(オン)」というのは、本来「そのとうりでございます」という意味の言葉です。これはヒンズー教のみならずバラモン教でもジャイナ教でもヨガでも密教でも様々な意味に解して用いられています。「アーメン」というのは、キリスト教以前からユダヤ教で用いられていた言葉でして、その意味は本来の「オーム」と全く同じものです。多少の形の違いや、時代とともに変化した解釈の違いを別にすれば、これらはもともと同じものだったのではないかと思います。
「この世界の真実」に接して、心の底から「そのとおりでございます」とひれ伏す瞬間、自然に湧き起こる言葉が「ナム」であり、「オーム」であり、「アーメン」なのです。少し解りにくいかもしれませんが、これは逆に言えば、心が「ナム」や、「オーム」や、「アーメン」といった言葉で真に満たされたなら、「この世界の真実」に接するということでもあるのです。心の底に張った氷にぶつける小石として「ナム」や「オーム」や「アーメン」といった言葉が用いられたと申しましたのはこのことです。
「心の底からそのとおりでございますとひれ伏す」というのは、「それを無条件で受け入れる」ということです。つまり、「この世界の真実に我が身を明け渡す」、「自分を捨てる」、「おのれ(エゴ)を無にする」、あるいは「この世界の真実とひとつになる」ということです。それは、「この世界の真実」と溶け合って「永遠の今」になるということでもあります。「永遠の今」とは「大きな生命」の世界のことです。
ところが日常の私たちは、何もしていないときでも常に休みなく頭のなかでオシャベリをしています。常に何かを考えていると言ってもよいでしょう。過去を誇ったり悔やんだり、未来に期待したり不安を抱いたりして、決して「今」のこの一瞬に溶けるということがありません。つまりは、想像の世界で過去へ未来へと走り回る私たちには、肝腎の「今」がないということです。過去へ未来へと右往左往するばかりで心が温まらないものですから、「今」と私たちを隔てている心の氷がだんだん厚くなってゆくのです。「永遠の今」につながるためには、心のなかのオシャベリを止めねばなりません。
「おのれ(エゴ)」とは何か。「永遠の今に溶ける」とはどういうことか。たとえば、山の端に落ちる夕日や空に浮かぶ雲を見つめているときなどに、何もかも忘れて陶然と満たされていたという経験はありませんか。いうなれば、これが「永遠の今に溶ける」ということです。自然と自分との境界が溶け去ってしまい、「見るもの(主体)」とか「見られるもの(客体)」とかいった通常の約束事が無意味になってしまった状態です。ところがです。そのほんの何秒かの後に、頬をつたって涙が流れていることに気づいたとします。このとき、「自分は泣いている」と頭のなかでつぶやくものがいます。これが「おのれ(エゴ)」です。この瞬間に、自然と自分との境界線が復活してしまいます。「永遠の今」を絶えず遠避けているのが頭のなかの様々なオシャベリなのです。
こんなオシャベリを止めるにはどうすればよいのか。…「最も簡単で広く使われている法は、神の御名か、神の存在と、人間の魂がその神にすがっていることとを表わす言葉のいずれかを繰り返し唱える方法である」(A・ハクスレー『永遠の哲学』)。
ハクスレーの言う第一番目の「神の御名を唱える方法」というのは、仏教(真宗)で言えば「念仏を申す」ということになります。これを親鸞聖人は「ただ阿弥陀(アミダ)の三字をとなえる」(『唯信鈔』)こととお示しになっておられます。第二番目の「神の存在と、人間の魂がその神にすがっていることとを表わす言葉を唱える方法」というのは、つまり「南無(ナム)」と唱えることです。ここで「神」というものを擬人化して考えると混乱してしまいます。「神」と言おうと「仏」と言おうと、結局は名状しがたい「大きな生命」のことを言っているのです。いわばこれは不可称・不可説・不可思議世界を象徴する言葉にすぎません。
「念仏を申す」というと、一般には「南無阿弥陀仏(ナム・アミダブツ)」という、いわゆる御念仏を口に唱えることだと考えられております。「南無」とは「無条件で受け入れること」、「阿弥陀仏」とは「時間と空間を超越したこの世界の真実」のことです。ですからこの御念仏の心を一言でいうならば、「この世界の真実とひとつになる」ということになりましょうか。「南無阿弥陀仏」という御念仏は、この心的行為を象徴した言葉なのです。
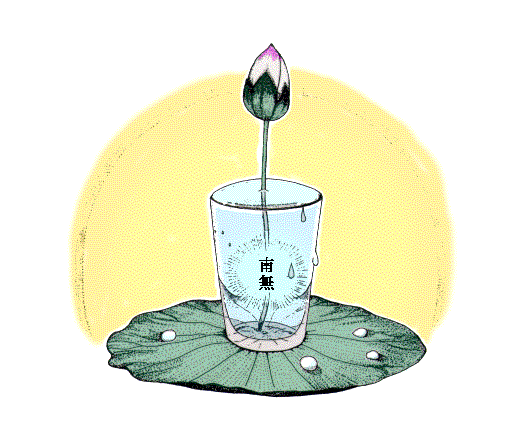 ただ、親鸞聖人は、「弥陀の誓願不思議にたすけまいらせて往生をばとぐるなりと信じて、念仏もうさんとおもいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたもうなり」(『歎異鈔』)とお示しになっておられ、必ずしもこの御念仏を口に出して唱えれば救われるとはおっしゃっておられません。教学的な解釈はひとまずおくとしても、この『歎異鈔』の言葉を「南無阿弥陀仏」にあてはめてみれば、「救い」は心底より「南無」と思う瞬間にあるということになります。心を「南無」の瞬間で満たす。これを別の言葉で言えば、「一念をもって多念を排す」ということになりましょうか。
ただ、親鸞聖人は、「弥陀の誓願不思議にたすけまいらせて往生をばとぐるなりと信じて、念仏もうさんとおもいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたもうなり」(『歎異鈔』)とお示しになっておられ、必ずしもこの御念仏を口に出して唱えれば救われるとはおっしゃっておられません。教学的な解釈はひとまずおくとしても、この『歎異鈔』の言葉を「南無阿弥陀仏」にあてはめてみれば、「救い」は心底より「南無」と思う瞬間にあるということになります。心を「南無」の瞬間で満たす。これを別の言葉で言えば、「一念をもって多念を排す」ということになりましょうか。
六字名号の御念仏を唱えるというのは、「この世界の真実とひとつになる」という思いを象徴的に表現した行為です。…「さらには、この思いをいっそう強く把持せんがために、それをば一語の内に畳みこまんと望むなら、一音節より成る小さき語を選ぶべし、そは二語よりも優れたるなれば。語は短くあるほどますます霊の業にふさわしきものとなる。かくのごとき語は「神(ゴッド)」であり、「愛(ラヴ)」にほかならず。いずれかを選ぶべし、一音節の語にして汝の最も好む語を。しかる後に、その語をば汝の胸に固く付着せしめ、いかなることが生じようとも、胸よりそが離れゆくことのなきようにせざるべからず」(前掲『永遠の哲学』所引『不可知の雲』)。
個人的な経験から申しましても、念仏を象徴としてではなく、心の氷を割るための小石、あるいは頭のなかのオシャベリを止める手段として用いる場合には、「南無阿弥陀仏」という六字、あるいは「阿弥陀」の三字よりも、「南無」の二字(一音節語)を用いる方が適当かと思います。(もっとも、「南無阿弥陀仏」という六字をそのまま用いたいとおっしゃるのなら、それはそれで結構です。)
救われる(満たされる)方法としての念仏は、一種の瞑想行だと言えます。つまりは「念仏行」とでも言うべきものです。「念仏行」とは、ひとことで言えば、「はからいを離れ、ただ一心に念仏申して、浄土に往生する」というものです。
「はからいを離れる」とは「自分の頭で考えることをやめる」ということですが、実践的には二つの思いを捨てることです。そのひとつは、「念仏など唱えて何になるんだ」という思いです。いまひとつは、いささか逆説的ですが、「念仏を唱えることによって救われよう」という思いです。それはともに、自分の頭で「役に立つとか立たない」とか判断している功利的な思いなのです。「はからいを離れる」とは、つまり、「念仏に対する一切の思いを捨てる」ということなのです。
また、「ただ一心に」とは、「念仏だけを思う」ということです。それは、念仏を唱えながら他のことを考えたり願ったりしないということです。たとえば、念仏を唱えながら自分の行いを反省したりすると、それはもう「念仏」と「反省」の二心になるということです。ですから、この「一心」には、「反省」はもとより、「我が身の後生」や「先祖の供養」を願う思いさえも入り込む余地は無いということになります。念仏は、善悪や損得を踏まえた何かの為にする行為ではないのです。親鸞聖人が、「父母の孝養のためとて、一返にても念仏もうしたること、いまだそうらわず」(『歎異鈔』)とおっしゃっているのも、この方向から考えた方が分かりやすいかと思います。
そして最後に「浄土」とは、言うまでもなく「大きな生命」の世界のことです。「大きな生命」との結び付きを回復し、そこに帰る道。これが「念仏行」なのです。
次回は、この「念仏行」の実践法について、いくぶん現代風にアレンジしてお話し申し上げたいと存じます。しかし、まえもってお断りしておかねばならないことが二つあります。
第一に、私自身は様々なご縁によって、自分が救われる(本当に満足できる)道はこれだと信じております。ですが、世界の人々が救われる道はこれしかないとは決して思っておりません。人によって個性も境遇も因縁も様々なのですから、救われる道もまた様々であるに違いありません。にもかかわらずここで「念仏行」をご紹介致しますのは、「念仏行」はどんな人にも開かれた極めて平易な道だと思うからです。もっとも、この一連の手紙をお読みいただいて、「念仏行」をご自身の救われる道とお感じになるか否かは、皆様のお心次第と申し上げるほかありません。
第二に、私の「念仏行」の受け止め方には、やや伝統的解釈とは異なった点があるかもしれません。本来なれば聖典にもとづいてその理由をいちいちご説明申し上げるべきところですが、今回はそういった方法をとっておりません。この点に関しましては、いずれ改めて少しづつお話し申し上げたいと存じます。合掌
〈参考図書案内〉
オルダス・ハクスレー『永遠の哲学』,平川出版社,1988年。
かつて鈴木大拙師は本書を評して、「欧米人の著述によりて東洋人自らが反省の機会を与えられるのもまた時勢であろう」と述べられたことがあります。この書は、真摯に真理を求め解脱をめざす人にとって、格好の手引きとなってくれるものと信じます。
「念仏行」のお話しをさせて頂くのに、仏教徒でない英国人ハクスレーの言葉を引用いたしましたのは、このような「言葉を用いた瞑想法」というものは何も仏教の専売特許などではなく、頭の中のオシャベリを止める方法として人類普遍のものであることをご承知頂いておきたかったからです。私たち人類は3万年前にホモサピエンスとして誕生して以来、ほとんどその構造に変化を見ておりません。つまり私たち人類は、時代や世界の別を越えて、いわば真理を受信するアンテナとして3万年来同じ構造を持っているということです。ですから、「真理がひとつ」である限り、そこへの到達方法に普遍性が見られるのも至極当然のことかと思われます。かつての情報伝達速度が緩慢であった時代はともかくとしても、今や宗教的セクショナリズムの枠を越えて世界を見るべき時がきているのではないかと思います。