[底本]
TLG 2461
URANIUS Hist.
(A.D. 6?: Syrius)
3 1
2461 003
Fragmenta, ed. K. M[u]ller, FHG 4. Paris: Didot, 1841-1870:
523-526.
Frr. 1-31.
5
(Q: 843: Hist.)
"t1a-31"
『アラビア誌(ARABIKA)』
"t1a-4"
《第1巻より》
断片"1a"
Steph. Byz.:"アユアタ(Ayatha)とアユアラ(Ayara)は、〔男性名詞・女性名詞〕いずれにもあらず〔=中性名詞〕、アラビア人たちの集住民だとは、ウーラニオスが『アラビア誌』第1巻の中で。居住民はアユアテーノイ(Ayathenoi)とアユアレーノイ(Ayarenoi)。
断片"1b"
同 :アユアラ(Ayara)は、アラビアの都市、オボデース(Obodes?)に与えられた神託に由来し、その息子アレタスによってそう呼ばれた〔都市である〕。すなわち、アレタスが神託の詮索に出発した。その神託とは、アユアラ(Ayara)という地を探すべし、その地は、アラビア人たちやシュリア人たちのもとで白いを意味するというものであった。そして、アレタスがたどり着いて、横たわっているときに、白いヒトコブラクダに乗って進む白装束の男の幻影が彼に現れた。そしてその幻影が消えると、望楼が現れ、ひとりでに大地に立ち上がったので、そこに都市を建設した。族民はアユアレーノス(Ayarenos)である。
断片2
同 :センノネス(Sennones)は、ガラティア〔プリュギアの東、小アジアの内陸部〕の種族だとは、ウーラニオスが『アラビア誌』第1巻の中で。
断片3
同 :シンガラ(Singara)は、エデッセーあたりのアラビアの都市だとは、ウーラニオスが『アラビア誌』第1巻の中で。市民はシンガレーノス(Singarenos)。
断片4
同 :カトラモーティティス(Chatramotitis)は、エリュトラ海に近い地方。市民はカトラモーティタイ(Chatramotitai)。ストラボーン第16巻〔4章1節〕に……ウーラニオスは『アラビア誌』第1巻の中で彼らのことをカトラモータイ(Chatramotai)と呼んでいる。「カトラモータイとサバイオイ(Sabaioi)とホメーリタイ(Homeritai)とは、駱駝飼である」。
〔サバイオイとホメーリタイについては、村川堅太郎の『エリュトゥラー海案内記』第23節註を見よ。〕 "t5-11"
《第2巻より》
断片5
同 :アイアメーネー(Aiamene)は、ナバタイオイ人たちの領地だとは、ウーラニオスが『アラビア誌』第2巻の中で。族民(ethnikon)はアイアメーノス(Aiamenos)。
断片6
同 :アイアニティス(Ainanitis)は、ナバタイオイ人たちの領地。ウーラニオスが『アラビア誌』の第2巻で。族民はアイアニテース(Aianites)。
断片7
同 :エリュトラ海は、半神エリュトラスにちなむ。しかしウーラニオスは、『アラビア誌』の第2巻の中で〔こう云う〕。海沿いに連なる山並みが、恐ろしく紅く(erythra)て紫色であることにちなむ。だから、太陽の陽光がこの山並みにあたると、海に紅い(erythra)影を投影する。そして山並みが豪雨で氾濫すると、海のなかに一気に流れくだり、海の色がそういうふうになる。
断片8
同 :メーダバ(Medaba)は、ナバタイオイ人たちの都市。市民はメーダベーノス(Medabenos)だとは、ウーラニオスが『アラビア誌』の第2巻の中で。
断片9
同 :モーバ(Moba)は、アラビアの分割地?(moira)。ウーラニオスが『アラビア誌』の第2巻の中で。住民はモーベーノイ"Mobenoi"、女性名詞はモーベーネー(Mobene)。しかし、アルファ(α)とはしっかり結びついていたようだ。というのは、モーアバ(Moaba)〔というの〕があったから。族民はモーアビテース(Moabites)、女性名詞はモーアビティス(Moabitis)。
断片10
同 :パルミュラ(Palmyra)は、シュリアの守備所、これに言及しているのはウーラニオスが『アラビア誌』の第2巻の中で。族民はパルミュレーノス(Palmyrenos)。しかし当人たちは、都市が再建されたとき、自主的にアドリアノポリタイ(Adrianopolitai)と改名した。
断片11
同 :タエーノイ(Taenoi)は、南中地方あたりのサラケーノイ人たちから出た民族だとは、ウールピアノスが『アラビア誌』の中で、またウーラニオスも『アラビア誌』の第2巻の中で。
"t12-20a"
《第3巻より》
断片12
同 :アバセーノイ(Abasenoi)は、アラビアの民族。ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻の中で。「サバイオイ人たちの次に、カトラモータイとアバセーノイである」、そして再び、「アバセーノイ人たちの領地は没薬(smyrna)を産し、香料(thymiama)も(kerpathos)もいくらでも産する。さらにまた、テュロスの紫貝(kochlias)の血の色に似た紫草〔染料〕をも生産する」。
断片13
同 :アダナ(Adana)……幸福のアラビア大陸には、別の都市もあるとは、ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻の中で主張している。
断片14
同 :アトラミタイ(Atramitai)は、幸福のアラビアの民族だとは、ウーラニオスが第3巻の中で。アルテミドーロスは彼らをアルタモーティタイ(Artamotitai)と呼ぶ。
断片15
同 :アコマイ(Achomai)とアコメノイ(Achomenoi)は、幸福のアラビアの民族だとは、ウーラニオスが第3巻の中で。
断片16
同 :ザビダ(Zabida)は、幸福のアラビア大陸にある村。ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻で。
断片17
同 :タムウダ(Thamouda)は、アラビアのナバタイオイ人たちの隣人。ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻で。住民(oiketor)はタムウデーノス(Thamoudenos)。
断片18
同 :ケブラニタイ(Kebranitai)は、幸福のアラビアの民族。ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻で。
断片19
同 :タルパラ(Tarphara)は、〔男性名詞・女性名詞〕いずれにもあらず〔=中性名詞〕、幸福のアラビアの都市。市民がタルパレーノス(Tarpharenos)となるのは、ゾアラ(Zoara)〔の市民〕がゾアレーノス(Zoarenos)、アユアラ(Ayara)〔の市民〕がアユアレーノス(Ayarenos)となるがごとしとは、ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻の中で。
断片20
同 :セーレス(Seres)は、インドの民族で、人間界からは孤立しているとは、ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻の中で。
断片"20a"
Tzetzes Hist. VII, 730:
ウーラニオスが『アラビア誌』の第3巻の中のどこかで言っているところでは、アラビアには葦の聖なる杜(alsos)があり、その葦の中に、王たちと、その妻、兄弟、息子たちだけを埋葬するが、そのほかの者は一切〔埋葬しない〕という。そしてその埋葬法は以下のごとくである。安置しようとする葦の一節に穴をうがち、ここに屍体を置いて、さらに香油を擦りこむ、この葦は伐らないで、再び生長するに任せるのである。
"t21-23"
《第4巻より》
断片21
同 :アッケーノイ(Akchenoi)は、アラビアの民族だとは、ウーラニオスが第4巻で主張しているところで、エリュトラ海の喉元にあたる。
断片22
同 :エドゥマイオイ(Edoumaioi)は、アラビアの民族だとは、ウーラニオスが『アラビア誌』の第4巻の中で。しかし一部の人たちは、イオタ(ι)で〔"Idoumaioi"と〕表記しており、わたしによってはイオタ(ι)で述べられることになろう。
断片23
同 :オボダ(Oboda)は、ナバタイオイ人たちの領地、ウーラニオスが『アラビア誌』の第4巻で、この地の王はオボデース、これをひとびとは神としてあがめ、埋葬した。族民はオボデーノス(Obodenos)だとは、ダカレーノス(Dacharenos)が。
"t24"
《第5巻より》
断片24
同 :モートー(Motho)、アラビアの村、この村でマケドニア人アンティゴノスは、アラビア人たちの王ラビロス(Rhabilos)によって殺されたと、ウーラニオスが第5巻の中で。ここはアラビア人たちの方言で死の場所〔という意味〕である。村人たちは、地元の書式に従えば〔?〕、モーテーノイ(Mothenoi)である。
"t25-31"
《所属不明巻より》
断片25
同 :ブラキア(Brachia)。アラビア海はそういうふうに呼ばれる。で、〔そういうふうに〕呼ばれるようになったのは、ここには浅瀬(blache)が非常に多いからである。たしかに浅瀬に似ている。地名(to topikon)はブラキアテース(Brachiates)。しかしウーラニオスは、彼らをブラキエーノイ(Brachienoi)だと主張した。
断片26
同 :カルナナ(Karnana)は、エリュトラ海に近いミナイオイ人たちの民族の都市。市民はカルナナタイ(Karnanatai)。しかしウーラニオスは、〔地名を〕カルナニア(Karnania)、〔市民を〕カルナニタイ(Karnanitai)だと主張する。
断片27
同 :マンネオース(Manneos)は、河川の中程の地域、ここに居住しているのがアラビア・マンネオータイ(Arabes Manneotai)だとは、ウーラニオスが主張しているところである。
断片28
同 :ニケーポリオン(Nikephorion)。エデッサあたりの都市コーンスタンティナ(Konstantina)はそういうふうに〔呼ばれる〕とは、ウーラニオスによる。族民はニケーポリオス(Nikephorios)だとは、ビュザンティオスによる。
断片29
同 :ニシビス(Nisibis)は、ティグレース〔ティグリス〕河畔の平野にある都市。ピローンは『ポイニキア誌』の中でナシビス(Nasibis)と、アルファ(α)で主張している。しかしウーラニオスはエプシロン(ε)でネシビス(Nesibis)だと。ピローンの主張では、ナシビス(Nasibis)は石碑のことを意味するといい、他方、ウーラニオスの主張では、ネシビス(Nesibis)はポイニキア人たちの方言でまとめられ集められた石を意味するという。しかしストラボーンは、第16巻で、イオタ(ι)で〔ニシビス(Nisibis)と表記している〕。族民はニシベーノス(Nisibenos)。
断片30
同 :ノソラ(Nosora)は、エリュトラ海にある島。ウーラニオスはアラビア人たちの〔欠損であるらしい〕。島民はノソレーノス(Nosorenos)。この書式は地元民のものである〔?〕。
断片31
同 :カラクモーバ(Charakmoba)は、現在の第三パライスティネー〔パレスティナ〕の都市、この都市は、プトレマイオスが『地誌』第5巻、幸福のアラビアの章に書き留めた。また、ウーラニオス(こういったことについては信頼にたる人物。というのは、アラビアの事は精確に記録することに真剣であったから)は『アラビア誌』の中で、モーブウカラクス(Moboucharax)も〔パレスティナ都市〕だと主張している。市民は、前者のカラクモーバ(Charakmoba)のはカラクモーベーノス(Karachmobenos)。後者モーブウカラクス(Moboucharax)の出身者は、モーブウカラケーノス(Moboucharakenos)である。
2002.07.11. 訳了 |
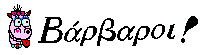 Barbaroi!
Barbaroi!