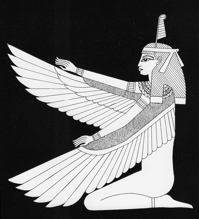第6話
グリュプス(gryps)について

例えばグリュプスという、天のあらゆる有翼類にまさって大きな鳥がいる。これは東の地、オーケアノス河に降り立ち、太陽が水の深みから昇り、光線で世界を輝かせるとき、このグリュプスは自分の翼を広げ、太陽の炎熱を受けとめる、人の住まいする地を焼き尽くさないためである。また別のグリュプスも、日没の方に飛びゆく、自分の翼に刻銘されているとおりである。「進め、光の与え手よ。世界に光を与えよ」〔Cf. 第3バルク6:14〕。
神性においても同様で、2羽のグリュプスがともに行く、つまり、大天使ミカエールと聖なる神の母である、そうして太陽の炎熱、つまり、神の怒りを受けとめる、万人に、「おまえたちをわたしは知らない」〔マタイ25:12、ルカ12:25, 27〕と述べ、その怒りが焼き尽くさないためである。
美しくも、自然究理家はグリュプスについて言った。
註
gruvyは伝承の垢にまみれているが、七十人訳では、不浄の鳥「ペレス」の訳語に当てている(レビ記11:14、申命記14:13)。
「ペレス」はワシ類の総称であると考えられるが(『聖書動物事典』p.308)、「語源に重きを置くことが許されるとすれば、ヘブライ語聖書の《ペレス》は《砕く者》を意味することから、ヒゲワシossifrageすなわち《骨砕き》という名称をよく表していることになるだろう」(『聖書動物事典』p.309-310)。
しかし、グリュプスに関するかぎり、自然究理家が旧約聖書に根拠を置いていないのは確かである。
ヒゲワシ(学名 Gypaëtus barbatus)は、ギリシア語ではfhvnh。アリストテレース『動物誌』第9巻34章では、雛を慈しむ鳥として特記されている。
画像の出典は、『聖書動物事典』p.309。
グリュプスの典拠。—
「またプロコンネソス〔マルマラ島〕の出身でカユストロピオスの子アリステアスは、その作詩した叙事詩に、ポイボス(アポロン)によって神懸りとなり、イッセドネスの国へいったこと、イッセドネス人の向うには一つ眼のアリマスポイ人が住み、その向うには黄金を守る怪鳥グリュプスの群、さらにその向うにはヒュベルボレオイ人(「極北人」)が住んで海に至っている、と語っている」(ヘロドトス『歴史』iv-13)。
「ヨーロッパの北方には、他と比較にならぬほど多量の金があることは明らかである。その金がどのようにして採取されるのかについても、私は何も確実なことを知らないが、伝えられるところでは、一つ眼のアリマスポイという人種が怪鳥グリュプスから奪ってくるのだという」(ヘロドトス『歴史』iii-116)。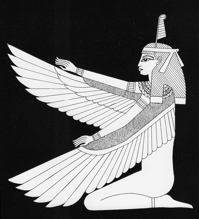
ここから、「護るもの」という、グリュプスのひとつの性格を看取できるかもしれない。
ギリシアのグリュプスが、ヘブライのケルブ(ケルビム)ときわめて関係性が深いことが見てとれる(林俊雄『グリフィンの飛翔』とくに第3章、第4章)。
『聖書動物事典』も、グリュプスとケルブ(ケルビム)との関係性の深さを認めつつ、「2体のケルビムと思われる像の描かれたエジプトの聖なる船、すなわち方舟」の図像を挙げている(p.120)。しかし、そこに描かれているのは向かい合ったマアト女神(右図。画像出典は、『図説・エジプトの神々事典』(河出書房新社)から)の姿である。マアト女神は太陽神(ラー)の妹神である。
この第6話の記述内容から考えて、われわれはギリシア神話のグリュプスではなく、有翼のこのマアト女神を想像するのが正しいかも知れない。