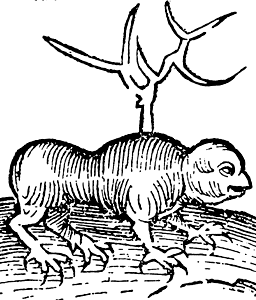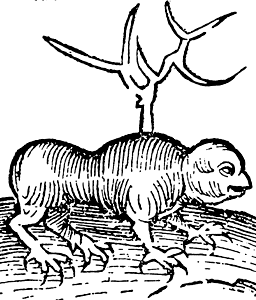第20話
アリライオン(myrmekoleon)について
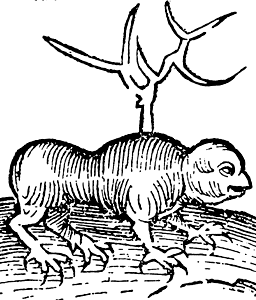
テマンの王エリファズは言った、「アリライオンは肉を摂取できないために滅びる」〔ヨブ、第4章11〕。自然窮理家はアリライオンについて、前肢はライオンだが、後肢はアリだと言った。父親は肉食だが、母親は豆類をかじる、だから彼らがアリライオンを産んだとき、生まれたその子は二つの自然本性を有し、母親の自然本性によって肉を食することができず、また父親の自然本性によって豆類も食することができなかった。かくて、食い物をとることができないので滅びるのである。
このように、二心ある人もまたみな、おのれの生き方全体において定めなき存在である〔Cf. ヤコブ、第1章8〕。〔だから〕二様の生き方をしてはならず〔ベン・シラの知恵、第2章12「禍なるかな、小心で無気力なもの、二股かけた(=二様の生き方をする)罪人」村岡崇光訳〕、まして祈りの時に両義的なことを言ってはならない。二様の生き方をするような両義的で罪深き心にわざわいあれ、と彼〔自然窮理家〕は言っている。美しいのは、「しかり」を「否」、「否」を「しかり」と言うことではなく、「しかり」は「しかり」、「否」は「否」と言うことである〔マタイ、第5章37。ヤコブの手紙、第5章12。参照、第2コリント書、第1章17〕とは、われらが主イエス・キリストのおっしゃったとおりである。
かく美しく、自然窮理家はアリライオンについて言った。
註
「アリライオン(myrmekoleon)」は、旧約聖書でライオンを表す7つの名称のひとつ、ラーヴィーまたはレヴィイヤー〔老いたライオンを意味する — 『聖書動物大事典』p.243, 245〕に(七十人訳で)充てた訳語である。しかし、ここでも、自然究理家の関心は、アリとライオンとの合体という「二心」にあることはいうまでもない。
プリニウスは、インドアリについて、次のように述べる —
「ヘラクレスの神殿内に飾られていたインドアリの角はエリュトラエの見せ物のひとつであった。これらのアリは、ダルダエと呼ばれる北インド地域にある地下の洞窟から金を運び出す。その動物はネコのような色をしており、大きさはエジプトオオカミくらいある。彼らが冬期に掘り上げた金を、インド人たちは夏の暑い天候のときに盗み取る。その頃は暑いのでアリたちは穴に隠れているのだ。しかしアリたちはその人々の臭いをかぎつけて飛び出してくる。その人々は非常に俊足のラクダに乗って退却しているのだが、人々を何度も何度も刺す。この動物たちはそんな速さと激しさを、彼らの黄金に対する愛情に結びつけているのだ」(第11巻111)
この情報源は、おそらく、ヘロドトス『歴史』第3巻102-105 である。
それによれば、この動物は「大きさが犬よりは小さいが狐よりは大きいほど」で、「砂を掻き上げては地下に巣を作り、そのやり方がギリシアで蟻のするのとまったく同様で、形状も酷似している。そしてこの蟻の掘り上げた砂が金を含んでいる」という。おそらくは、野生のモルモットの類をさすのであろう。
メガステネス(ストラボンが引用『地誌』第15巻1章44)によれば、この砂金盗人は、インド東部山岳地帯のダルダイという種族で、おそらく今日のダルディスタン辺の住民らしい。
未検証であるが —
「実際は恐らく、このインドの黄金なるものは、シベリアのレナ川やアムール川が上流の鉱山より運んでいた金の薄被に由来するものと思われるが、この「金を掘り出す蟻」の伝説は古代世界のみならず、チベット、蒙古にもよく知られている」。「この伝説はインド起源のものかもしれない。何故ならサンスクリット語のpipilika〔漢訳教典では「臂卑履也」と音訳される〕は蟻と蟻の集めた黄金の両義を兼ねているからである」(ドゥ・ヨング/塚本啓祥訳『インド文化研究史論集』平楽寺書店、1986.7.、p.206-207)
これも今後の調査を待ちたい。
画像は、『健康の園(Ortus sanitatis)』。博品社の挿絵は、背景の枯木を削除。