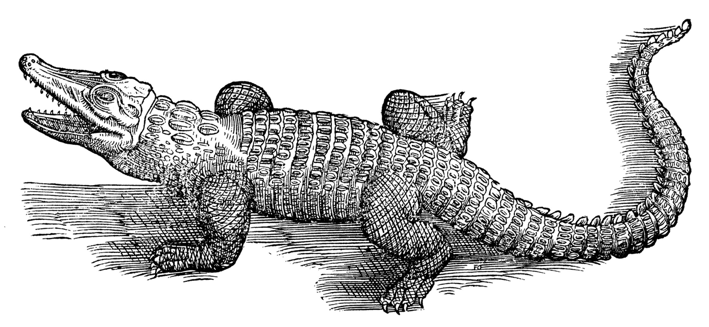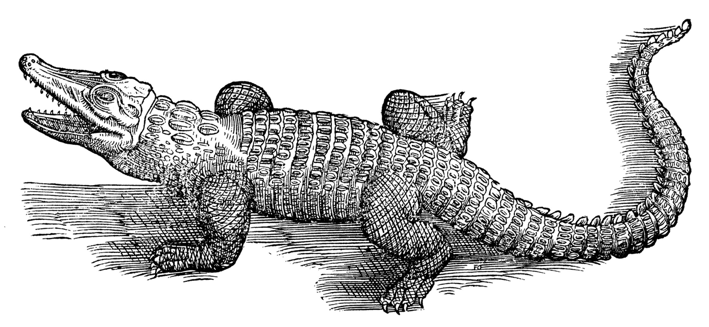第8話
ワニ(krokodeilos)について
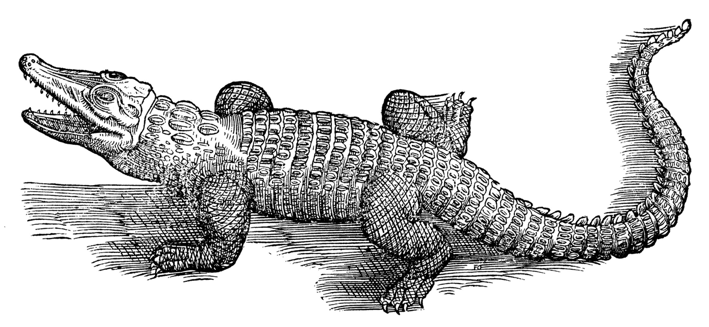
自然究理家はワニについて言った — 水棲で、河川や湖に見出される動物だ、と。前方は臍までライオンのよう、臍から下方はヘビのように見える。誰か人間を手に入れると、これを脚から脊椎まで喰う。しかし頭に近づくと、坐ってこれを嘆く。
このような徳によって見出されるのは、と聖バシレイオスは言う、抜きん出た者たちの多くは、強欲な連中であれ不正な連中であれ、貧しい者たちを貪り食う。しかし、頭、すなわち、裁き手、わたしの言っているのは主なるわれらのイエースゥス・クリストスのことだが(というのは、クリストスはあらゆるものらの頭であるから)、その面前に至ると、義しい裁き手の前に立ったとき、自分たちの邪悪なる行いのゆえに、泣き叫び、自身を嘆くのだが、無益である。なぜなら、ハーデスに悔い改めはあらず、義しい裁き手の前に慰めもないからである。しかしあなたは、憐れまれたいと望むなら、あなたが不正する相手を憐れめ、そうしてワニのようであってはならない。裁き手から聞かないために、「憐れまずして、あなたが憐れみを受けることはないだろう」〔Cf. ロマ11:30-31〕と。
註
P・アンセル・ロビン『中世動物譚』p.53-54から —
文学において、《偽善》を表すきまりの動物は、ワニであった。《ワニの涙》Crocodile's tears という表現は、現在でもなお、うわベだけの悲しみを示すありふれた言い方である。テニソンでさえ、一人前のもの書きになった当初は、恥とも思わずこの陳腐な表現を用いている。
ワニは汝のために涙を流して泣く (『哀歌』第4部1篇)
最近、リリーを編集しているある人が、(ワニが人を食らうときに泣くという)《お話》は、マンデヴィルからとられたものである、と述べているが、それはありえないことだろう。この話は、はじめ『フィシオログス』に出て、それをボーヴェのヴァンサンが引用したらしい。「ワニは人間を見つけ、打ち負かすと、それを食らい、その後、その人間を哀れんで泣くのである」と。紀元400年ころ、アマシアの司教アステリオスが全体的に激しい調子の説教『断食論』でこう記している —「ナイル河のワニをまねるのでなければ、一体、断食というのは何なのか。ワニどもは、自分たちの食べた人間の頭を見て嘆き悲しみ、遺骸を哀れんで泣くという。だがその人間を食べたということを後悔などしていないのだ。ただ、あとに残った人間の頭部には肉が少なく、食べるのに適さないことを嘆いているだけなのだ、と思う」と。さらに時代を遡ると、アエリアヌスの一節がある。ここではもうすでに2世紀に、ワニが涙を流すといわれていることが紹介されている。「テンティラ地方にあるアポロの街の住人は、底引き網でワニを捕える。人びとは、この土地固有の聖なる果実をつける木にワニをつるし、人間をむち打つようにしたたかに打ちすえる。するとワニがすすり泣き涙を流すのだ。その後、人びとはワニを引きずり降ろし、ごちそうとして食べるのである」(『動物の本性について」第10巻21節〉。他方、マンデヴィルにはこうある。「このワニどもは、人を殺し、泣きながらその肉を食う」。おそらく、マンデヴィルはネッカム(『事物の本性について』第2巻101節〉を典拠としたのだろう。いずれにせよ、ワニの涙への言及は、イギリス文学にひんぱんに登場している。
(P・アンセル・ロビン『中世動物譚』p.53-54)
『ローマにいる聖人たちへ』第11章30-32節 —
あなたがたがかつては神に対して不従順であったのに、今では彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同じで、彼らが今あなたがたの(受けている)憐れみのゆえに不従順になったのは、(いずれ)彼ら自身が憐れみを受けるためである。
画像出典、Konrad Gesner『Historiae Animallum』IV。