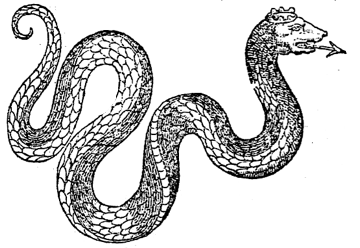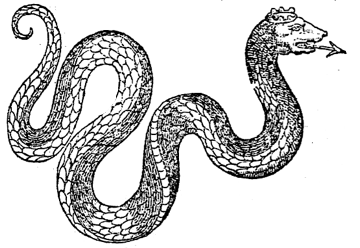第5話
バシリスク(basiliskos)について
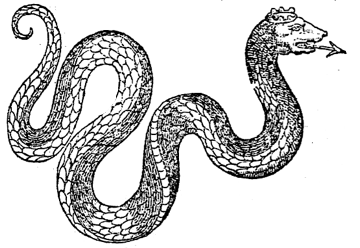
預言者-王(Profhtavnax)ダビデは、詩篇90の中で、主なるわれらのイエースゥス・クリストスの臨在に寄せて言う、「あなたはコブラやバシリスクを踏みつけ、ライオンや大蛇を踏みにじられるであろう」〔詩篇91[90]:13〕。
自然究理家はバシリスクについて言った — じつにしばしば、さまざまな場所で冬の時期になると、ヘビたちはひとつ場所に集まり、冬のせいで餌とするものをまったく持てず、お互いに咬み合い貪り合い、そこでことごとくが命終する。その後、その骨と毒の悪臭のせいで、そこに蛆が湧き、小さなあるものがつくられる、これをバシリスクと〔ひとびとは〕名づける。
で、その動物は、これがいたその場所で、次のような自然本性を有する ˜ これの呼気は、あの隠れ家を乾燥させる。しかしその形相は死で、諸々の都市をも荒れ野にするほどである、と。
この動物について別のことを〔人々は〕言う — 太陽の面前をうろつくこと断じてなく、弓ぞり、後ろ向きである。では、ある知者たちはいったいどうするのか。きれいで新しい鏡を取って、これで太陽の向かい側から、この獣の顔に向けて光線を反射させる、するとこれは自分のいつもの場所に行こうとするが、とつぜん鏡の反射が一挙に落ちかかるので、自分の影を正視できず、すぐに命終する。
解釈。バシリスクは、人殺しの悪魔の顔に解される。そこで、悪魔がやって来て、主なる神がアダムとエウアにお与えになった天国の場所を妬み、有毒のヘビに告げ、当のエウアの耳にこう謂った、「天国の中央にある樹の実について、主なる神はおまえたちに、これを取って喰ってはならぬと謂ったが、これを喰うがいい、そうすればいかなる季節に合わせて食べたらいいか、おまえたちの眼が開かれ、おまえたちは善と悪とを知って、神のごとくなるだろう」〔創世記3:2-3〕、そうして古い神の……〔欠損〕……誡めを干涸らびさせ、[そうして]人間どもの全種族と形相を堕落と滅亡、ハーデスの穴蔵に突き落としてしまわれた。しかし神の知恵、すなわち、主なるわれらのイエースゥス・クリストがは諸天から降りてこられ、肉を通して鏡のようにこの世を照らされ、聖なる神の御子にして神の母であるマリアからこれ〔知恵〕を得られたのであるが、ハーデスまでも下向されたので、悪魔は真実の太陽光線、すなわち、神性の面前に立つことができず、負かされて滅んだのである。
されば、美しくも、自然究理家はバシリスクについて言った。
註
バシリスク basilisk(ギリシア語、basilivskoV)は、《王》を意味するbasileuvVの指小辞であり、はじめは『七十人訳聖書』の中でへビを表す語であった。『七十人訳聖書」の翻訳者たちは、爬虫類のさまざまな名前を翻訳するのにひどく困ったのである。バジリスクという名が採用された理由は、(後にプリニウスが正体を見きわめた)件のへビが、「まるで王冠のごとく、頭部に白い斑点を一つもっている」(『博物誌」第8巻48節〉のが特徴だったからかもしれない。プリニウスの時代までにこのへビは恐ろしいものという評判が定着していた。プリニウスはこう説明を加えている —「それはシュッという音をたててすべてのへピを敗走させる。そしてほかのへビのように、いろいろにとぐろを巻いて体を前方に動かすことなく、その中央部で体を高くもち上げて進む。それは接触によってだけでなく、その呼気によってすら薮を枯らし、草を焼き、岩を砕く。それが動物に及ぼす影響たるや悲惨なものである。かつてその一匹が馬に乗った人の槍で殺された。すると毒素が槍を伝わってのぼってゆき、乗馬者のみでなく、馬をも殺したということが信じられている」。また、別のところではこういっている — 「バジリスクということになると、これを見ただけで、他のへビはみな、恐れ逃げ出す、呼気そして側を通りかかったときの匂いでへビを殺してしまうが、人間の場合は、それに目をつけられただけで命を失ってしまうのである」(ホランド訳、問、第29巻66節)。プリニウスの同時代人、ローマの詩人ルカヌスは、バシリスクが他者を追い払い、砂漠に王として君臨すると述べて《へピの王》という名が正しいとした。アエリアヌスはプリニウスの記述の大部分をそのまま用いたが、これににらまれたものは死ぬ、ということについては何も触れていない。ヒエロニムスが聖書をラテン語に翻訳(『ウルガタ聖書』)した折り、彼は「詩篇」90(91)篇13行でbasiliscusをただ一度用いている。他の箇所では、この同義語regulusを採用して新機軸を打ちだした。regulusは、以前は《へビ》ではなく、単に《小さき王》あるいは《族長》を表す語である。
とかくするうち、新しい伝説ができあがっていった。すなわち、バジリスクはある有毒な爬虫類により雄鶏の卵からかえる、という伝説である。私の知るかぎり、この話が最初に出てきたのはイギリス人ネッカムの著作である。そこにはこうある —「雄鶏が年老いて卵を産むと、それをヒキガエルがひなにかえす。するとバシリスクが生まれてくる」(『事物の本性について』第1巻75節)。一方、ボーヴェのヴァンサンによると、「バシリスクが雄鶏から生まれることがある。というのは、たいへん年老いた雄鶏が卵を産むと、そこからバシリスクが生まれてくるからである。だが、それには多くの条件が整わなければならない。まず、老いた雄鶏が温かい土中深くに卵を産む。そこで雄鶏の助けなく卵がかえる。長時間ののち、ひな鳥が生まれ、強くなる。子ガモがいつもそうするようにである。だが、このひなにはへビのような尾がついている。身体の他の部分は雄鶏のようだ。この誕生を目撃した人によれば、その卵は殻がなく、強い皮である。とても強いため、どんなに強く打ちつけても壊れることはない、ということである。へビあるいはヒキガエルが、この卵をかえすという考えの人もいるが、たしかなことではない。しかしながら、ある種のバシリスクが年老いた雄鶏の卵から生まれるということは、古代人の書き残したものにある」(Spec. Nat., XXI, 24)。あいにくと、ボーヴェのヴァンサンは自分が典拠とした著述家の名をあげてはいないが、おそらくそれはベーダ師(730年)だろう。このくだりから、十三世紀中葉には、バジリスクが雄鶏の卵からかえると考えられていたこと、そのバシリスクは雄鶏の胴体とへピの尾をもっていたこと、がはっきりする。この話は、多分、『七十人訳聖書』の「イザヤの書」59章5節に原型をもつものだろう。そこを逐語的に訳すと「彼らはクサリヘビの卵を割り、クモの巣を張る。その卵を食べる者は、殻の柔らかい卵[ou[rio]をつぶし、その中にバシリスクがいることを知る」となる。次にヒエロニムスの訳をあげておこう。「彼らはグサリヘピの卵を割り、クモの巣を張る。その卵を食う者は死に、あたためられたものはregulus(バシリスク)を生みだす」。
さて『七十人訳聖書』にある殻の柔らかい卵というのは、通常、雌鶏の無精卵を意味するのだが、ここでは雄鶏の卵のことをいっているようだ。というのは、アリストテレースが先にこういっているからである。
(雌鶏の腹中にある)ある時期の卵(これは完成後の黄身と同じように、全体が黄色い)と同じようなものが、雄鶏でも腹を裂いたら下帯(横隔膜)の下(雌鶏で卵のあるところ〉に見つかった例がある。このものは、見たところは全体が黄色であるが、大きさは(普通の)卵くらいであって(奇形として何か凶事の)前兆と考えられている。
(『動物誌』第6巻559b)
このため、バシリスクが時に雄鶏の卵からかえる、ということが推測されていたのかもしれない。同時に、雄鶏といえばバシリスクという連想があったことを覚えておかなければならない。アエリアヌスによれば、雄鶏が時を告げると、バシリスクは衝動的に死ぬ、またリビアの旅人はお守りとして雄鶏を連れて行く(『動物の本性について』第3巻31節)ということである。バシリスクが雄鶏の卵から生まれるという俗説は、エジプトの伝説によって固まったものかもしれない。トマス・ブラウン卿が『俗信論』の中で、エジプトの話として以下の例をあげているからだ —「かの国、エジプトの考えでは、神の使者クロトキはへビを餌としている。その有毒な餌が体内の卵を汚し、時としてひなはへピの姿で生まれてくる」(第3巻5節〉。彼は、このクロトキが雄鶏になり、さらに俗説全体が「イザヤの書」14節にあったように、聖書に過って採用された、といっている。『七十人訳聖書』では、この箇所は「へビの種子からアダーが出」となっているし、他方「ウルガタ』では「へピの根からバシリスクが出」となっている。こうしたいろいろな考え方が混じり合い、雄鶏の卵がへピによってかえされて、バシリスクが生まれる、という俗信ができあがったのかもしれない。先に触れたヒキガエルがへビの代役となった事情は、未だ解明されていない。
(以上、P・アンセル・ロビン『中世動物譚』p.94-97)
画像出典、Konrad Gesner『Historiae Animallum』V。