「当社の会計システム」法人&個人事務所
1.スピード・同時進行形
売掛・回収・経費払い・代理店マージン払い・給与払いは全てスプレッドシートに反映される。
各担当者がどんどん入れていく。
CHATWORK(携帯)で売掛情報・回収情報は幹部全員がリアルタイムに(外出先でも)みられるようになっている。
これは仕組の問題ではなく、権限をどれほど社員に持たせるかである。
一人ひとりが事業部制のような形で経費支出まで任せている。(経費支出稟議制にはしていないしそんな時間もない)
経費支出に関しては、私の分も公開しているので、いかに節約しているかがスタッフにも分かる。
それで歯止めとしている。
私自身は500円以下の経費支出(交通費など)は計上していない。そんなことで時間とられるくらいならもっと儲ければいいからだ。
これもスタッフに姿勢を見せている。
私がするのはEBでの支払オペレーションだけである。(総合振込データ作成はパート)
しかし、全体がうまく回っているかの工場管理のような業務は当然している。
時間も限られているのでぱっぱっと見られるチェックポイントを10ほど儲けている。
2.処理フロー
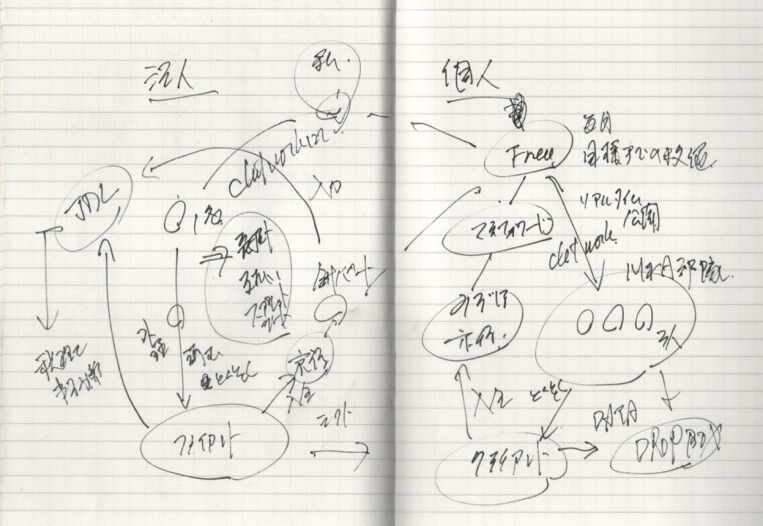
3.チェックポイント
超ハイスピード処理戦略をとると、問題は人がチェックポイントを設ける必要がある。
ここはオフ管理で手作業なので時間はロスする。
これは、持論であるが、全自動にはしない。
AIに任せて全て自動化されました、結果会社はつぶれましたでは話にはならない。
また、会計補助パートへの過度な依存も厳禁している。
自動で進めば、数字に対する意識が低まる。そこをチェックで意識付ける。
(AIも寄り添い機能があるから要注意)
ちょっとだけ紹介すると
・売掛金ー未払い金と現状の営業利益、現状の資金残高のバランス
・常に期末資産予想での納税必要資金の予想
・変動費と固定費のバランス(変動費か固定費かも時勢で変わる
これらはテキストでは習えない。
法人で雇ったパートさんは実践力強く、急成長して、個人会計の方も任すことになった。
4.課題
*ミッション
こういうシステムにするには全員がマネタイズを目指すというミッションを追求しなければ出来ない。
スピードを追求すれば細かいミスは起こる。
それを全員でカバーする気持ちが必要だ。
*学習ツール
勉強材料はどんどん送る。
私自身も同じものを見て勉強する。
勉強している風景もみせて、必要性を伝える。
*人材
スピードについていけないものも出てくる。
当社でも、体調崩して全く働けずに退職に至った人もいた。
こういう時は退職にかかる時間コストはかけていい、精神的コストはかけるな、というのが方針
イレギュラー処理になるので、時間コストはかかる。しかし、職場が暗くならないように、皆で笑って送り出す雰囲気を作ることが大切。
ここを普通の会社の社長は逆にしてしまい、事務所ムードが暗転する。
*互換性
将来の発展形を考えて、システム間に互換性があった方がベターであることは分かるだろう。
会計でいえば、逆に税士事務所の方が遅れているのでマネーフオワードに対応できていない。
(特に京都の税理士は遅れ)
ここが連携できれば、口座の動きとマネーフオワードは連携できているので入力の必要がなくなる。
世の中はそうなっていくだろう。
*デジタルタトウ
少数精鋭でやっているので、皆、スタッフは「自分が倒れたらどうなるんだ」との不安を持ってやっている。
それが責任感にもつながっているのだが、今後忙しい中でもマニュアルの整備が必要である。