|
エッセイ集 終わりのない出立
  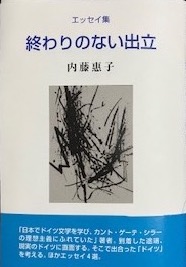
内藤 惠子
Keiko Naito
|
「日本でドイツ文学を学び、カント・ゲーテ・シラーの理想主義にふれていた」著者。到着した途端、現実のドイツに直面する。そこで出合った「ドイツ」を考える。ほかエッセイ4選。
I 出立
/一九四六年のベルリン /『戸口の外で』/ 『幻想』/ 二つの記念碑 / 無駄な死
ドイツの思い出 デーク家 /
ドイツについての話
/
エリカ・ナーゲル夫人のこと
ゲルハルト・リヒター / ドイツの旅 / 求婚広告 / ブルーノ・ワルターの矜持 / ポルシェ
ドイツを考える / 黒い教育学
II 「情緒」/ ー直線と曲線ー
(友人Aとの対話)
III お地蔵様と戦争 / 自主・自律・自己思考
|
2025/10/28 冨岡郁子氏(詩人) 透明なことば 〜『終わりのない出立』(内藤恵子著)を読んで〜
これは私の遺言書よ、といとも簡単に言う彼女の言葉を思うと無造作な読みはできない。ドイツ語教師としての内藤さんを知ったとき、私は彼女が詩を書いて
いるとは知らなかった、お互いにそうだったと思う。詩人としての内藤さんを知ったのはずっと後になって、教師という立場を互いに離れてからだ。
彼女のエッセイに接して心打たれるのは、彼女の根底にある人間に対する揺るぎない信頼である。冒頭で彼女は二つのドイツ語テキストを載せている。本のタ
イトルにもなったカフカの寓話「出立」では、人間が本来持っている知識に対する飽くなき欲求と心が目覚めて行くことの喜びを述べ、マックス・フリッシュの
「捕虜達」では心身ともにどんなに外的権力に侵入されても人間の心の内奥には侵しがたい内発的自我が存在すると語る。彼女の語りは穏やかだが、明晰であ
る。そしてこの二つの信念がエッセイ集を貫いている。その頂点が、ゲルハルト・リヒターについてのエッセイである。「自らが生きた現代史を血とし肉としな
がら、リヒターはいかにそれを芸術表現へと結晶化したか知りたい」と彼女が書くとき、そしてユダヤ人の虐殺の四枚の写真をもとに多層に塗り重ねられた作品
に沈黙や隠蔽ではなく底から響きくるものを彼女が聴きとるとき、この問いは一人の表現者としての彼女がずっと抱えてきた問題であると思った。彼女も日本の
現代史を生きてきた。第二次世界大戦を経験し、敗戦を九歳で迎えている。「お地蔵様と戦争」では空襲の中を逃げた記憶が五感を通して彼女の身体に刻まれて
いる。また彼女がドイツに留学したのは一九六六年から六年間で、それはちょうど東西分裂のドイツが赤軍によって徹底的に顕にされた世代間紛争を経験しなが
ら、どのようにナチスの問題と向き合っていったかの時期であった。彼女がエッセイで語るドイツで知り合った人たちも当然のことながらこのドイツの傷を生き
て来た人々であって、彼女自身が留学の日常生活の中で彼らの寡黙と勤勉さに直に触れることで感じ取っている。彼らは皆、素直で、彼女に対して飾らず、あり
のままに接している。これは内藤さんのお人柄によるものだろうと、やはり私は思う。現代世界の至るところで、この瞬間も繰り広げられる戦争と人間の恐ろし
さを思うと、彼女の言葉は祈りでもある。
このエッセイ集は前年に出版された『しだれて…桜』と一対であると思う。存在の耐え難さがあるからこそだろう、詩集には自然を慕い、抱きとめられたい気
持ちが溢れている。作者は、今、ここにあることを歌っているが、彼女の詩のことばは自由で気取らない。ごまかしも嘘もない。しかも堂々としている。このこ
とばも曇りのない感受性のレンズを通している。それはエッセイ集に私が感じた身体化された思考に支えられているからである。
待てしばし/お前も又静みゆかん
お線香をあげ、お寺の前庭で小金井の森からくる風のそよぎに吹かれながら一緒に黙って座っていたあの時間を思う。
2025/10/11 小寺淑子氏
人間は年齢と共に様々な変化が起きる。肉体的にも精神的にも、良し悪しは別として、自然現象である。こ
の作品とは若い時に出会いたかった。作者の感性の鋭さ、情緒の豊かさ、知性の高さ、全て素晴らしい。それなのに、現在の私は、残念ながらそ
れらの感覚をそのまま受け止める感受性が弱くなっており、様々な情緒が、薄く透けて見える紗のベールから伝わってくる、そんなもどかしさがある。読み返すた
びに、生まれつき哲学的思考力には恵まれず、物事を比較的割り切って処理する私には欠けている素晴らしさが感じられ、魅力的な一冊。
2025/6/18 K.I.氏
エッセイ集では、内藤様の来歴からの世界観と冷静な洞察眼に敬服を覚えつつ、「情緒」では未だに数学アレルギーの私ですが、文学・数学・宗教を横断しなが
ら俯瞰しながらの一文は、全く納得の境地でした。また、ドイツでは十日間ほどの旅行でしか身に覚えが無いのですが、社会層という階層は矢張りどの国にも人
間界には少なからず消しえぬものですね。
2025/6/8 K.IR.氏
一読、ただただ「凄い」という感じです。多くの人に読んで貰いたいと思いました。大変勉強になリました。詩集でも「知的」と書きましたが、エッセイ集も大変「知性」を感じます。ただ脱帽です。最初の「出立」から凄いです。カフカにこんな作品があったのかと驚きました。
「一九四六年のベルリン」、「ドイツの思い出 デーク家」〜、そして最後に近い「お地蔵様と戦争」と凄いものばかり並んでいます。本当に多くの人に読んで貰いたい作品(エッセイ)です。
2025/6/8 A.N.氏
エッセイ集『終わりのない出立』は、ドイツを、世界を公平な目で捉えられ、自問され、賢明な判断をされている秀逸なエッセイと存じました。ど
の御作品も読みごたえのあるもので、深く胸に届き、とても興味深く、拝読させていただきました。どの御作も教えていただきますことばかりで、選ぶことなど
できないのですが、現在の私が是非覚えておきたいと思いました御作品を書かせていただきます。「出立」、「一九四六年のベルリン」、「戸口の外で」、「幻想」、「無駄な死」、「ドイツの旅」、「ドイツを考える」、「情緒」、「ー直線と曲線ー(友人
Aとの対話)」、「お地蔵様と戦争」です。おへそのないカエルを例とした説明になるほどと感心し、思わず笑ってしまいました。
2025年5月12日 神尾加代子氏(詩人)
(前略)
拝読してまず思うことは、端正で清雅な文体の空間を造形しております。口調の流麗さは目をみはるものがある格別なものであります。見るべきものの確認と表現もさることながら、ニヒルともつかないもののあわれがこの知的なエッセイのなかで息をひそめている感がありました。
「エリカ·ナーゲル夫人のこと」、このエッセイでは内容そのものというより自己の言語感覚の自縛の内部での陶酔をこの上なくいたわり、視点をかかわらして
おきたいという高度な次元が感じられました。特にエッセイを拝読して私が学ばせて頂いたのは、個々の内容ではなく、その表現が言葉の網目を通る通り方を知
りぬいて渉味の効いた手練を知り、我が身をきたえようと思うことです。
「ブルーノ·ヴァルターの矜持」。読み手の人の渦をはらんだ内面の情況によって裏ごしされた視点の強さが見るべきものをしっかと見なければという心理を呼
びおこします。かなり重心をもつイメージがこのエッセイの磁場を存在の無限界にいたる辺まで引きつけていると思われます。
前後しますが、「戸口の外で」、これはかなり貴重な本であり、紹介したエッセイも心をふるわせます。著者の思念は人間という存在の心の所産であろうという
考え、科学の目でなく心の目で世界を見るという宇宙の再生に願いをかけた気持ちが伝わって来ました。時代の進歩は人の生き方の進歩に結びつかなかった。
幸福論の物差しも怪しくなりました。物質文明が精神の健康度を狂わせてしまった気もします。そのような時に読むには「終わりのない出立」のエッセイはバイ
ブルでもあります。
2025年5月7日 X氏
ドイツ語辞書を片手にカフカの短篇を読みエッセイを再読しました。クラスの中での内藤さんのお声だけでなくあなたの内面の声も重なって聴こえてきた気がします。
どのエッセイのテーマも重い。特に大戦を経た二十世紀の後も、今もなお終わらないどころか善悪と勝者・敗者とは無関係であるといわんばかりの世界になって筆者の憂いが伝わってくるエッセイには心から私も同感し憂います。
筆者は言葉によって思考に論理(単に明晰なだけでなく、人間の弱さも深く理解されたという意味でしなやかな論理)とエチカを与えてられると思いました。筆者の思考のリズムが感じとれる文章を読むうちに私の背筋が伸びる気がしました。
とりわけ私の好きなエッセイは「ゲルハルト・リヒター」です。筆者が留学されていた時は、筆者が二十代。そして一九六五年から六年間です。この時代はド
イツのみならずフランス、日本でも学園闘争の時代でした。私も高校生そして大学一、二年の頃です。この時に味わったり見聞きした事は、今に至るまで重くひ
びいています。私ですらこうなのです。ドイツで筆者が経験なさったことは、その後深く心に刻まれることになったと想像いたします。
「リヒターがドイツ現代史をいかに生き…表現へと結晶化したか」筆者の問いかけが切実に伝わってきました。完成された作品だけでなく創造されてゆく過程
そのものが作品であるような形に、筆者は問いかけ、考えている。私は心うたれました。なぜ人はイデオロギーにひかれるのでしょうか(そういう人がいるので
しょうか)
2025年5月5日 岡山晴彦氏(詩人)
エッセイ集『終わりのない出立』の中で、とくに「情緒」の項では、日本独特の人の心理や行動まで分け入る「情」、それは中世以来この国の文学や演劇の畑
まで及ぼしてきたことまで思い巡らせ、考えさせられました。このことは後期の著書の中の「ことばへの思い」にも触れられてあります。また詩集『しだれて…
桜』の「間」では、肉体と情緒のはざまで、もがきくるしみ、それでも実存的生き方を貫いてゆく、強靭な生を見ることができました。(略)エッセイの中で、
二か所、詩集の中で一か所「シシュフォス」のことばがありますが、まさに人は「カミュ」の作品でいう不条理の中にあり、それは劫かもしれません。
2025年3月31日 石下典子氏(詩人)
(略)
ドイツのカルチャーも歴史も知り得ないことばかりで、読み進めるごとに納得できたのも、現場で実見した記述だからだと思いました。
書名〈到達することのない旅への出立〉の重要な知恵で、人間本来の知的追求は高齢になろうと保持していていいのだと大変励まされる記述でした。知れば知るほど深淵な世界にたじろぎながらも、歩を進めることで喜びとわくわく感が授かれるのですね。
デーク家でのご夫婦の借家暮らしでは、まるで須賀敦子のエッセイのような冒頭から、世界大戦後のベルリンで起きた不幸な事件に結ばれ、内藤さんが胸を痛めたことと同様にウクライナの現状をも思いました。
驚いたのは宇都宮空襲を経験されていたことです。七月十二日の夜、雨の降る中、避難された方々が詩に書いていましたので、戦後派の私どもも実体を知ることができましたが、あまりに多くの死者と壊滅の県都でしたから、その後の暮らしは想像以上に苦しかったと感じ入ります。
ドイツ語は難しいという定評ですから、高校生時代に関心を持ったことは明晰な頭脳の持ち主である上に、学ぶことが得意な方なのだと思いました。これだけの経歴をお持ちの詩人は少ないです。(以下、略)
2025年3月29日 K.G.氏
(略)カント・ニュートン・ユークリッドの世界、つまり昔の教科書だけを支えにして、文、思考を紬ぎ出していることが一読しただけでわかります。平行線は交わ
らないと信じ込んでいませんか? 頭の中の純粋な世界ですよ。これは中学でお勉強するユークリッド数学です。ニュートンはユークリッド数学を唯一の数学だ
と信じて公式なるものを記述してます。カントもこの世界を基盤に置いてます。だから「絶対時間」と「絶対空間」と絶対を2つも想定しているのです。ものさ
しは「光の速さ」一つで十分。時間も空間も相対的。「光の速さ」にスポットライトをあてると相対性理論ではなく「絶対性理論」です。「現実は、重力で空間
は曲がる」ので平行線は交叉します。
「平行線は交わる」という非ユークリッド数学で記述された式から核兵器や携帯電話が生まれました。GPS機能も同様スマホのメールで「平行線は交わらな
い」と送信している人は、「私は小さい声でしゃべってます」と大声でどなってる人、あるいは「私は今、日本語をしゃべってません」と日本語で言ってる人と
同じです。こういう人達だけでおしゃべりをするのは当人達の世界でまとまって楽しいでしょうが、仲間に入る気にはなれません。
「たまに息抜きを」とか、「人生には遊びも必要だ」とか言う人は、実は思いつめている人でしょう。本当に遊んでいる人は「ヤバイかな、たまにはまじめになろうかな」と不安になることがあります。(以下、略)
2025年3月26日・I . T.氏より
〈昔は良かった〉と郷愁を持って眺める過去は、ともすれば美化された理想の過去であり、それを丸ごとの現実としての未来に置いても、そこには絶対に辿り
着けない。むしろそこを目指して無批判に進めば、容易に過去の国家主義や軍隊文化に取り込まれ、あちこちで悲惨な世界が再生産されるー懐古的ユートピアに
ついて、そんな解説を読んだことがあります。本当にそこらじゅうでそういった回帰運動が起きていて、きっとドイツも日本も例外ではなく、長らく両者を見て
こられた著者にはページに収まりきれない思いや分析がおありでしょう。
ですが提示いただいたように〈出立〉の寓話を〈人間の抑えがたい知的追求の旅への衝動〉として読んだ時、〈辿り着けないこと〉の意味はレトロトピアへの
警戒から逆転します。先が見えず、行く道の保証もなく、途方もない旅であることが、そのまま真の意味で〈幸せなこと〉なのです。以前、NHKのヒューマニ
エンス〈記憶〉の回で、〈記憶は、過去を参照して未来を予測するために形作られる〉という実験結果がありました。理想の過去に耽溺するのではなく、学びの
旅を生き続けることで人は人類の膨大な過去を蓄積し、本当に向かいたい未来をも描けるのではないでしょうか。
2025年3月26日・I . K.氏より 「一九四六年のベルリン」を読んで
一九四六年での一事件「フリッシュの日記」を取り上げた内藤氏の見識から様々のことを想像させて頂いた。
戦前、戦中、戦後のベルリンに関わった人々は、何百万、何千万、いや億の単位になるのではないでしょうか。その人々にはそれぞれの物語があったに違いない。その物語の一コマとしての事実がこの「フリッシュの日記」ということになるのでしょう。
「あなたがロシア兵であったら、この「フリッシュの日記」ということになるのでしょう。
「あなたがロシア兵であったらどうするであろうか。」という内藤氏の問いかけに、果たしてどのような行為が可能であろうか考えてみる。
観念として行動や行為を想い描いたところで事実としての選択は一つ、そしてそれは常に想定を超えている。
「善悪のふたつ、総じてもて存知せざるなり。」と述べられている『歎異抄』の言葉を思い、その時々の選択は常に「その人の業縁による」となれば、「あな
たがロシア兵であったらどうするか」という問いの応えは、その人自身の業縁による。選択という行為になるから、勿論、私自身、こうするかもしれないと思い
描くことは出来るとしても、事実、自分自身の行為は、全く想定は勿論、善悪を超えて為されるに違いない。
存在の闇を何を灯として生き続けるのか。ここから私自身(各自)の物語が始まることになりそうだ。
2025年3月26日・H. S.氏より
内藤恵子さんという方は初めて知りましたが、衝撃的な詩とエッセイで、内に何かを呼び起こされる、というと大げさですが…。(略)カフカの引用されていた
エッセイの冒頭部分に、私の浅学な知識では知り得ないものが世界にはあり、軽く実存などといってはいけないような気持ちになりました。(略)社会性と個の
あいだの問題で、ひどく裂け目があり、そんなタイミングでこの詩に会えたことは暁光でした。
2025年3月26日・O. S.氏より
「エッセイ集」なら私でも大丈夫かなと思って読んでいくと、興味ある内容もあり楽しかったです。一般的で、読みやすく…。特に「ゲルハルト・リヒター」、「求婚広告」、「ドイツを考える」など興味ありました。
「ゲルハルト・リヒター展」は東京でも開催され、感動して観たのを覚えています。その囚人によって撮影されたモノクロ写真も展示されていて大
変ショックでした。「ドイツの思い出 デーク家」では、ドイツ人と日本人は生真面目、几帳面、等と言われ、似ていると思うのですが、誕生日のお祝いの電話
が40年以上も続いたとの事、ずっと忘れないでいる事が愛情や友情の現れで、心打たれます。
★表紙の銅版画についてですが、とても良い作品と思います。この新野耕司氏の個展を観に行ったら私もファンになるかもしれません。強い線が魅力的です。表紙にぴったりです。
2025年3月16日・M.C.氏より
たおやかに美しい装丁を開けると、岩のように強靭な宇宙のようにはるか彼方に届くような言葉たちが並んでいて、うわあ、密度が高いと思った御本でした。
さすが京大でドイツ文学の博士号、シュトゥットガルト工科大学マスターコースで学ばれさらに京都大学で教育学を修められた すごーい先生の御本でした。一
つ一つの言葉を理解しながら、たくさんの光の矢のように流れてくる膨大な読書経験と感動の波をまともに受け止めるには読者も襟を正し、正座して読まないと
いけないと思いました。春の雨の音を聞きながらサーっと読ませていただきました。2度3度と通りすぎた文章を反芻しながら、ああ、すごい先生の心のうちを
みせていただいているのだな…と感動しました。
もう少し自分の言葉で表現が許されるのなら、とても深い深すぎる言葉が並び、完全に理解するには何度も読み返し、人名とか本の名前とかギリシャ神話の神
様の苦悩を自分で理解できるまで調べて、初めて内藤恵子さんの文章を理解できるのだろうと思いました。内藤さんの偉大さは、私がいつも出会って語り合って
きた普通の女性の方たちと比べて、かけ離れた経験から出てきたものだと心を打たれました。
戦時のアメリカ軍の爆撃を覚えておられる幼年時代をお過ごしになり、ドイツ留学を経て京都での教育に携ってこられて、高齢になられても素晴らしい経歴を鮮明に語り、本の形に残されるうらやましい老後だと尊敬します。
どの部分に共鳴させていただいたか、まだまだ何度か読ませていただければどんどん言いたいことは増えるでしょうが、私の思ったことを羅列させてください。
|