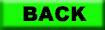梅雨明けということではありませんが、今日は梅雨時の晴れ間が出てまいりまして、いささか気持のいい日。私どもはそういう日を竹日和、「竹が太陽の光を受けて光っているような日」と呼んでいます。素晴らしいですね。普段、この振興協会にご無沙汰しており、柴田理事長に大変ご迷惑をおかけしています。申し訳ありません。皆さま方にもお目にかかることがなかなかできないで申し訳なく思ってます。私もこの歳にしては公職がまだ多く残っており、あちらこちら行って、理事会や役員会が大変多くございます。
今日は、竹文化振興協会が生まれましてから50年。あぁ懐かしいですね。思い出します。そんなことで、本日は是非ということで出席をさせていただいて、こうして皆さん方にお目にかかることができたことを大変嬉しく思っております。どうもありがとうございます。
いいですね、今日のこの呈茶お茶室。本間宗寿先生が竹に携わるお弟子さんたちと一緒に、あんなに素晴らしい柴垣をずっと造られている。しかも、竹をあのように見事に、雰囲気的にお造りいただいて、もうなんともいえない感激をしております。筍まで持って来ていただいて、本当に感激ですね。どうもお手数をおかけしました。あとで皆さんもぜひ一服召し上がって、あの竹の中で日本の素晴らしい一つの自然共生(自然と共に生きる)を是非味わっていただきたいと思います。今日、私はよそから来たものではなくて、この会の名誉会長ということでございますので「お話」をさせていただきます。気楽に、お楽に、聴いてくださいね。お話しましょう。
日本において、竹というものほど素晴らしいものはない。昔からね、松竹梅と言いますでしょう。松は永遠に枯れない永久樹であります。梅は実をたくさん作ってくれて、私たちも日々その実をいただいてご厄介になっていますよね。だいたいにおいて桜はなぜ入らないのか。そう言われますけど桜はちょっと別物なのです。一番大事なのは、松と梅との間、真ん中に、竹があるということです。これを覚えてください。
私がこの協会と関わったのは、ちょうど今から50年前、このような難しい名前の「竹文化振興協会」の名前になる前の「日本の竹を守る会」からになります。
私の祖先の千利休は秀吉から切腹を命じられた。武家で茶家でありましたから、切腹は当然でありました。蟄居閉門ということで、家族はみな会津の若松にお預けの身になったのです。しばらくして、秀吉から赦免ということで許されて、二代目の少庵宗淳が、今私どもが住んでおります本法寺前町に1万坪くらいの土地をいただいて、そしてそこに新しいお茶室を造りました。もう一度、秀吉の下に出仕せよということです。
いわゆる今私たちがおります本法寺前町の千家屋敷には、表千家と裏千家がちょうど半分半分に土地を分けて住んでおります。京都では本願寺さんがありまして、よく「お西さん」「お東さん」と言います。それと同じように、いつのまにか町の人が千家さんは「お表さん」と「お裏さん」と。なんで「お裏さん」と。これは表というのが南の方にある。裏千家はその上、いわゆる北にある。京都では北へあがることを「おあがりやして、おのぼりやして」とかいう。南に行くのを「おくだりやして、おさがりやして」という。ほかの住んでいる方にはなかなか理解できない話です。
三代目の宗旦の時に、千家が二つに分かれた時に、半分半分の屋敷になりました。それでね、千家屋敷の東側には大きな竹藪がありました。ものすごい竹藪でした。子供の時によく竹藪に入って遊びました。その時にはまだリスやいろんな鳥がいて、あんまり竹藪に入ったら危ないようなことを母から注意を受けました。私が5歳頃、丹波丹後の大地震が起こった時に、たしか私は母に抱かれて竹藪の中に入ったのです。茂っている竹藪の中で私が覚えているのは怖いなという気持ちでしたね。竹藪というのは何か出てきそうだなという、そんな気持ちを竹藪の中で思ったことを覚えています。
しかしそれから、父が竹藪の中に入って素振りをしていました。私どももそれを真似して竹藪の中で素振りをする。間隙がありますから、今日もお越しの黒田正玄さんのおじいさんたちによく怒られました。「竹を大事にしておくれや」。「竹の良いのを選んで花入れを作りましょう、茶杓を作りましょう」と。
利休が武家で茶家であって、織田信長や秀吉とともに合戦に出ていく。鎧兜はつけないけれども、表と裏の屋敷には鎧兜があります。でもそういう合戦では、鎧をかぶって直接戦うということではないのです。端午の節句には、いつも鎧兜を飾りますが、その横に我々は檜兜という、要するに檜で作った実に見事な肌飾りです。兜は肌飾りで、そして檜兜を飾りました。
合戦に行っても戦をしない。お茶の道が教えたのは「和(わ)」であります、平和だけではない。平和を創るためには何が大事なのか。「和やかさ」「和み」ですよ。人間の心の中にゆとりがないといけない。今の世の中を見てごらんなさい。ゆとりがない。特にヨーロッパやアメリカは本当にゆとりがない。トランプさんを見てごらんなさい、あの人のゆとりのないこと。思っていたことをすぐ口にする。だからいろんな方と衝突しているのではないですか。
アメリカで有名なコンサルタントのある方(ジェームス)が前から言っているのは、クリティカル、要するに間隙を作りなさいということ。人間同士少しは間隙を作りなさいということです。Book of Teaなどのお茶に関する本を読んで、自分でも気づいたことは、ヨーロッパやアメリカでは間隙、「間(ま)」がないことです。だからすぐ口にしてしまう。関税問題などの経済問題でも、今のトランプ氏は言ったことをすぐに行う。そしてまた、半分撤回してとわけのわからないことをしている。イーロン・マスク氏との蜜えん関係もありましたが、最近では決裂して、マスク氏も多少言い過ぎたようなところがありましたが。アメリカではいつでも衝突が起こっている。私も長いことアメリカで生活していろんなことを知りましたけれど、今のロサンゼルスの移民政策の問題による暴動もそうですよね。
いわゆるクリティカル、「間」をとるということです。日本はそういう「間」がずいぶんうまく取れています。みなさん、「間」といって何を思い出しますか。まず間取りでしょう。自分たちが住んでいる場所で、日本人は「間」を実に大事にしてきました。大和の国が生まれた時から、日本の国というは情(じょう)の国だった。その上で「間」が大事でした。「間」がなかったらぶつかってしまう。問題が起こる。皆さん方の生活の中でも、上手に「間」を取れれば、一家本当に幸せでありましょう。ちょっと「間」を違えたら、愛し合っていたよと言ってもぶつかり合ってそれで終わりです。私たち日本人はそういった「間」の取り方を祖先から色々と学んできた。住んでいる場所でも玄関を入ると、居間、客間(今はマンションに住んでいる人も多いですが)、そして床の間がありました。床の間には、ちょっと掛け物、絵画でも架ける。咲いていた花を竹にちょっと挿してみる。それだけでも、その部屋の中でほっと一息付けるようになる。そして、居間ではおじいさん、おばあさん、父母、兄弟みなが一緒になって、ちゃぶ台を囲んで、みんながいろんなことをわいわい話して生活してきたではないですか。お年よりの方は思い出しませんか。父母やみんなから色んなことを教えてもらいましたよね。自然にしつけができてきました。
「しつけ」は日本で創った言葉です。身を美しく。外来語ではない。きちっとしたことを「間」を持って「間」を取って、その間で自分たちのゆとりの生活をしていく。それをもっとも完璧に教えたのが茶の道であります。単に飲み物のお茶、コーヒー、紅茶をぱっと出したらいいではないか、なんであんなめんどくさいことをしているのか。わざわざお客さんをおもてなしするために、お菓子を出す。お菓子を召し上がってもらっている間にお点前をして、そして一服点てたあと、お菓子を召し上がってもらったあと口に、抹茶を頂戴する。飲み物の中でも、一つの「間」の取り方を教えているではないでしょうか。すぐに「どうぞ、どうぞ、どうぞ」。そのような振るまいはもてなしではありません。やはり心のこもった「間」であります。
日本では「間」とともに大事ことは竹であり、その教えなのです。「なんや。竹や」。そうではないのです。竹がすっと伸びていく。節目を持っている。私はね、70年前にアメリカに行く前に若宗匠という資格を頂戴しました。家元になれるという一つの敬称の称号でございます。私は若宗匠になったお披露目の時、お茶がお好きで私どものお弟子であった吉川英治先生にご挨拶をしていただいた。
感激しましたね。若竹がすくすく伸びていく。あの一節一節、これは大変なことですよ。竹が自分で一生懸命に自分を育てていく。
利休が韮山の竹を切って、初めてそこで自然に咲いている花を持ってきて、そして花生けを作った。これが竹の花入れを用いた最初なのです。そういうことで、韮山の竹で作った3本の茶杓のうち1本(園城寺)は国宝になって、東京国立博物館にあります。大したもんですよね。銘がいちいちついたのです。そして「夜長」「尺八」。3本作ったうちの2本目の「尺八」という竹の花入れが重要文化財になりましたが、これが私共のもとにございます。この「尺八」という花入れを見てますと、私は吉川先生がおっしゃった「若竹の 伸びよ陽の恩 土の恩」、それを想うのです。そういうことを想いながら、私はお茶の道に一所懸命修行しました。
日本中どこにいっても竹があります。竹藪が多い。今でこそ桂の団地ができて竹藪が半分に減ってしまったけど、昔はそれはすごいなというものでした。竹が風で揺らいでいました。私はいつも老ノ坂を通って亀岡に行く時、素晴らしい桂の竹藪を見ますと、「ああいいな」と。私が好きなのは、嵐山の竹藪の中の小径もですね。もう最近はインバウンドが多くてすごいですが、昔はそんなに人もいなくて私はよく行きました。なにかちょっと自分で思ったことがあると、あの道を歩きながら思索をします。いろんなことを考え、そして苦しみから自分がこの竹藪の中で「はぁ、竹のようにすくすくやっていかないといけない」と。あの道が好きなのですよ。
竹というのはなにか勇気を与えてくれる。素晴らしい勇気を与えてくれる。竹というものは日常生活ではなくてはならない。竹から生まれたものをたくさん使っています。扇子にしてもそうです。この頃皆さんあまり持っていませんが、日本人にとって扇子は大事なのです。お茶の関係の方、お寺関係の方は扇子を持っていらっしゃる。私は禅宗でございまして、扇子を出してご挨拶をします。扇子は一つのシンボルなのです。今でこそ立礼ばかりが多いですが、昔はみなさん座って、「間」をとって、「間」をとるために扇子を前に置いて、お互いにご挨拶をするものでした。そうでないと頭がぶつかり合ってしまいます。そうでしょう。今は皆さんだんだん忘れています。外国の方のほうが最近扇子を持っています。扇子で扇ぐということも暑さをしのぐのにいいのかもしれませんが、そういうことは昔からあまりしなかった。扇子は礼儀のシンボルで、それが竹でできているのです。
日本人ならね、そういう礼儀くらいできる人間を育てていってくださいよ、柴田先生。お茶でこそ育てていける。(お辞儀において)構えも大事なのです。今は立礼ばかりで、中国の方のようなお辞儀をして「いらっしゃいませ、いらっしゃいませ」と言う方が多い。「あなた方は中国人なのですか」と言いたくなる。中国の真似をするな。そんな挨拶するなら中国に行ってきなさいと私はいつでもみんなに言っています。そうですよ。もっと日本人らしいお辞儀を行ってほしいものです。日本はこんな情けない国になってしまったのか。
私は80年前、千家の嫡男として戦地へ行った。その中でたった二人、私たちの大学同期から行った者が生きて帰った。私と一緒にペアで後ろに乗せておりました西村晃氏、当時まだ俳優ではなく日大出身でありましたが、生きて帰ったがために俳優になり水戸黄門役で大成功をしました。後ろに乗せて訓練を受けました。第一選抜の試験でわずか2000名の中の一人、その海軍航空隊の搭乗員に選抜されました。昭和18年、土浦の海軍航空隊で試験を受けて予備士官教育を2か月、そのあと、私は戦闘機に乗るはずでしたが、背が大きすぎるということで大型機に行ってくれということで、泣く泣く徳島の航空隊で私は白菊という大変有能な、多様性のある飛行機の方に配属されました。安定性あっていい飛行機でした。戦争が厳しくなって、いろんな飛行機をわずかながらでも造っていましたが、生産力はだんだん下がっていきました。私たちは訓練を受けて、隊員になったのはいいものの、1年半かけるところをわずか10か月。「君たちは死にに来たのだ」と毎日言われ、「君たちの変わりはいくらでもいる」「飛行機は貴重品だ、失敗するな」「君たちは大学出身のインテリだ、分かるだろう。10か月で身につけろ」ということでした。殴られ蹴られの厳しい訓練を受けました。高度1500m以上を上がりますと酸素ボンベが必要ですが、私たちは持っておらず息苦しい中での訓練でした。
そしてグラマンのヘルキャット(戦闘機)ですが、最初は大したことがなかった。初期に南方方面で撃ち落とされた日本のゼロ戦機体のエンジンなどが回収され、いいところを全てグラマンに持って行かれた。私たちが訓練を終えた頃には、改造されたグラマンが来た。もうそれまでのグラマンはのろかったので追撃できましたが、もう空中戦では凄かったのです。私も体験しました。
こんな話は今の自衛隊で訓練を受けている人達にずいぶん話をしました。あなた方はいくら訓練しても弾を打てない。中国や北朝鮮やロシアからスクランブルしても、警告、警告ばかりで威嚇射撃はできない、と思われている。今の自衛隊は軍人ではないので、戦闘はできない。これからはアメリカも頼りにできないのではないでしょうか。皆さん覚悟してください。トランプ政権が続く限り、アメリカはむちゃくちゃになるのではないか。経済も大変です。
今、EUの国々とアメリカとの対立。いくらトランプ氏が戦争を終わらせるといっても、ウクライナとロシアとの戦いはそれくらいでは終わりはしません。その間にイスラエルとパレスチナも。そんなことを言っている間に、中国が海洋制覇、南方方面を航空母艦でうろうろする。太平洋上で日本の領海を通っていく。日本は何もできず無残。アメリカ一辺倒ですが、いざとなったらアメリカは見捨てるのではないでしょうか。
私は国連の大使もやっていますが、アメリカは国連関連の費用を割愛させてくる。自分でお金を出さない。WHOからも脱退もする。アメリカは拠出金を出さない。先日もアメリカ・ニューヨークの国連で大変な議論の輪に入りましたが、もう埒が明かない。これからは単なるコロナのみならずいろんな伝染病がくることもあると思います。エイズ関連の予算も削られている。高等難民事務所も必要ないとなってしまいます。お金ばかりがかかるというのがトランプ氏の言い分です。難民事務所もお金のかからないところへ設置しようと言います。とにかく総会においてもアメリカ、中国、ロシアが「NO」といえば、いくら他の多くの国々が提案しても無駄になる。WHOの事務総長も気の毒な立場です。いったいこれをどうしたらいいのか。世界中が混乱している。たかがアメリカの一人のトップの発言ですが「間」を持たない、いわゆる自分だけのいい分を通していこうというところに、大きな無理難題が出てきてしまう。日本も考えなければなりません。
日本は古事記、日本書紀、新日本書記がある。読まれましたでしょう。そして、万葉集という素晴らしい、単なる歌ではない、天皇から名の知れない人々の歌が選ばれた4500集が書かれている。すごいことです。しかも、中国から来た漢字を日本流の漢字に改めた。分かりますか。こんな素晴らしいことはない。そして、その漢字をもとにして万葉仮名を創った。そしてまたそれをもとにして片仮名を創った。凄いですね。昔大学の先生方と話をしました。
1973年頃だったか、竹博士で京都大学名誉教授だった上田先生は竹がとにかく大事だと言っておられた。知り合いの方を通じて上田先生とお目にかかった。そうすると先生は、「千さんなぁ、日本は古代から素晴らしい知恵と才能を持っている。そういうものがあるからこそ、今日まで日本が来ていることは知っているよね。しかも、その多くを支えているのはやはり自然、自然の中でも竹が大事。それが最近、開発開発で伐採されて竹が少なくなっていく。竹を守らないといけない。千さんなぁ、お茶の方では、竹にちなんだ道具がずいぶん多いやないか。あなたは竹を守る会のリーダーになってもらわないとあかん。」先生がそんなことを言われたので、びっくりしてそんなことを言われても無理ですよと思ったことを思い出します。
万葉集の中に、舒明天皇の「大和には、群山あれど、とりよろふ、天の香具山、登り立ち、国見をすれば、国原は、煙立ち立つ、海原は、かもめ立ち立つ、うまし国ぞ、蜻蛉島、大和の国は」がある。当時の中学校は5年生でしたが、5年間の間にいろんなことを、今の大学以上のことを学びました。その時、この歌についても感動したのですが、ふとなんで奈良には海がないのにカモメが見られるのかと不思議に思って、先生に質問したことがあった。そうすると学校の先生は「あんたよく気が付いたなぁ。それは舒明天皇による、日本の国をつくっていくための一つの理想なのだ。国づくりというのは、それだけの責任と、国づくりに対する努力が必要だ。日本の民がみんな仲良く、手を携えて、助け合っていく。そこに日本の国が生まれていくのではないか。まほろばの大和の国がそれによって今日まで続いてきた。」と。
あなた、考えてみなさい。日本はこれまで外国から侵略されてこなかった。平治の乱、源平の戦いをはじめ内乱こそはあったが、それは為政者が変わるくらいで大したことがなかった。今のケチな政治家とは違うのですよ。もっともっとすごい方々だった。
ケチとは悪い言葉ですが、先日、政治家が集まった場でこのような話をした。「あなた方は何をしているのだ。私たちは大学を出て22~23の頃に徴兵で海軍に行って、特攻戦士、みんな突っ込んでいった。あなた方はそのように国のために死ねるか。死ぬ覚悟でやらないといけない。自分の党利が良かったらいいのか。国民の方がよく知っている。そんな情けない政治をするよりも、国民一人一人が政治した方がいいのではないか、みなが政治をしましょうよ、と。
本当に重箱の隅をほじくりまわすようなことばかりをしている。時間が勿体ない。もっと重要なことを。トランプ大統領に対抗できるような度胸と、もう日本の国を何が何でも守るということで、関税問題でも弱々しくてはいけない。私は外務省参与も長い間しています。私はこの歳になって、いつ死んでもいい。だから言いたいことを言いたい。私たちの仲間は靖国神社の中でどれだけ悔しい思いをしているか。

皆さん、私たちは日本の国を守っていかないといけない。そのためには日本の素晴らしい自然、その中で竹を中心にいろんな植物、また寄ってくる動物に対して、私たちは優しい手を伸べていく。お互いに自然共生の環境を創っていく必要がある。私たちはそれをもとにして、生きているということに対する価値観を、存在感を思わなければならない。いいですか。
こんなことが昔から言われてきました。人間は過去を知らなければならない。過去を知る。過去を知ってこそ今があるのだ。そこから自分の存在価値や居場所を思わなければならない。自分が何をしているのか?自分は何なのか?を自分で明確にする。そういうことによって、自分たちの明日があるのだ。今を大事にしなければ、今を思わなければ明日はない。
私はどこに行ってもFutureという言葉ばかりを聞きます。未来なんて分かりますか。自分には今後何があるか分からない。未来を思うなら、今を大事にしないといけない。どうか皆さん、今を大事にしましょうね。
今を大事にするということは、自分を、家族を守る。そして日本の大事な「間」というものを自分の家の中から、それをはっきりみんなに認知させる。それによって日本人が素晴らしい生き方をしていくことができるのではないか。お茶でね、なんで茶碗を回さないといけないのか。これは単に回すのではないのですよ。正面を避けるために行う。そういうことを身に付けることができていたら、ちょっと半歩下がることができる。人間、いつも前に出よう前に出ようではなく、半歩下がることが大事。それでぶつからない。自分がやはりそれだけ謙虚な気持ちをもつ、自制心をもつ。これを持っていれば、長生きしますよ。
私も102歳にもなって、もう死にたいですよ。仲間もみな待っているのに、お前だけなぜ生きているのかと靖国神社に行ったら怒られますよ。本当にたった一人生き残ってしまいました。でも不思議に元気なのです。これも昔から武家作法やお茶の作法で鍛えられたおかげです。私を切ったら緑の血が出てくるかもしれません。抹茶の色が出てきて。それで長生きしている(笑)。
足腰も未だにいい。日本馬術連盟の会長でもありますし、そしてパリ五輪では(総合馬術団体が)銅メダルを92年振りに取ってきました。これは本当に有難いことです。私はこれで満足して辞めるといったところ、「辞めないでください」と止められました。100歳以上の唯一のアスリート、会長ということです。自分自身、鍛えています。自分を甘やかしたらいけません。休みばかりではなく、不動の姿勢をとる。背骨を正して、顎を引いて。そういう構えが大事ですよ。
竹を守る会、そして竹文化振興協会という大変素晴らしい一つの組織ができました。今日は午後から総会や懇親会もあります。
「若竹の 伸びよ陽の恩 土の恩」。ご清聴ありがとうございました。
※本記念講演は、6月12日に開催され、千名誉会長は、情熱をこめて講演され、多くの参加者に勇気と感動を与えて頂きました。しかしながら、8月14日にご逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表し、心からご冥福をお祈りいたします。