- 級=Q=0.25 mm
文字の大きさを表すのに使う - 歯=H=0.25 mm
字や行の送りに使う - ポイント=pt=72分の1インチ=約0.3528 mm(←米単位。欧/米で異なる)
- パイカ=12ポイントの活字
- 号数
古くからの活版の基準単位で鯨尺に由来する
「トラッキング」で全体に詰めてから、気になるところをさらに「カーニング」するわけですね。
- トラッキング
字間を一律に詰める組み方 - カーニング=くいこみ詰め
各文字の固有の幅よりも送りを詰めて組むこと - レディング
ベースラインと次の行のベースラインの間のこと
- 3色の光源を切り替えて一個の受光素子を用い、1画素を3回で取り込む方式
- 白色光を光源とし、3個の受光素子を用いて1画素を1階で取り込む方式
- 色分解カーブの設定で重要なのはグレーバランスである。一般にYとMはほぼ同じ量なので、YM、C、およびBkという3つの色分解カーブを設定する。
- 網ポジの分解カーブで見ると、YMの網点パーセントに対してCの網点パーセントでは中間部で10%ほど大きくする。
- 日本ではBkをスケルトンブラックといい、C=50%付近から網点を入れ、シャドウ部で75%前後の網点を入れるのが一般的である。
- GCR(Gray Component Replacement=フルブラック)
色領域のCMYの中からグレー成分に相当する量を取り除き、それを墨の網点に置き換えても原理的には同じ色調となる。
カメラやオーディオ製品など全体が黒っぽいものに使用する
YMCのバランスが多少崩れても黒に重点を置くので、ハイライト側からBkが入る - UCR(Under Color Removal=下色除去)
Bk版の下ではBk版以外の色版のインキ量を減らす
GCR以外の普通の写真に用い、シャドウのCMYをグレーにする。 - UCA←→UCR
色版のグレー成分を多くする
- キャラクタライゼーション
それぞれの装置の色を決めている特性をとらえる - プロファイル
特性をデータ化したもの - CMM(Color Matching Method)
異なる装置との色相似のデータ変換方法 - キャリブレーション
各装置の発色を一定に保つ - Macでは・・・ColorSync・・・ライノタイプ・ヘル社
- Win95では・・・KCMS・・・コダック社
印刷再現域はカラーフィルムのそれよりも狭いので、スキャンした画像データは必ず濃度圧縮しなければならない
人の視覚は明るい部分でより敏感なので、明るい部分では暗い部分より階調を豊富にする
- DR(Density Range;濃度域)
- カラーフィルム
DR=2.4〜3.5 約1000階調 - 印刷
DR=1.8〜2.0 約100階調
- カラーフィルム
わかりやすい画像=ヒストグラムの平坦な状態=どの明るさの部分にも情報がまんべんなくある状態
レコーダグリッドのオン/オフによるハーフトーンセルの形成
レコーダグリッド=出力装置の解像度
ハーフトーンセル=線数
- RT(Rational Number;有理数)スクリーニング
角を合わせられる角度のみ使う
モアレが出やすい - ITスクリーニング
無理数、時間がかかる - FMスクリーニング
網点をランダムに塗りつぶす
平網部分や中間的な明るさのフラットな部分で荒れた感じになる - スーパーセル
- 水銀蛍光ランプ(メタルハライドランプ)
水銀ガスによるエレクトロスミネッセンス(electro-luminescence)+蛍光体によるフォトルミネッセンス(photo-luminescence)。現存する光源では最も発光効率が高い。連続光を発する蛍光体を選択できる。温度依存性が非常に大きい。水銀ガス自体の発光(水銀輝線スペクトル、λ=435.8 nm,546.1 nm)が可視域に存在する。 - ハロゲンランプ
黒体輻射による発光。連続光である。blueの成分がRed成分に対して非常に低い。 - キセノン蛍光ランプ
水銀蛍光ランプと同質。水銀蛍光ランプの水銀をキセノンやネオン等の希ガスに入れ替えることにより、欠点であった温度依存性を大幅に取り除くことが可能となった。発光効率が低い。 - LED
エレクトロルミネッセンスによる発光。小型。定電圧駆動可能。応答性良好。発光効率が低い。高価。
- 凸版
最も古くから使われている
活字を使って印刷する - 凹版
エッチング(銅版画)から進化した- グラビア印刷
印刷用のシリンダーに彫刻を施し、凹んだ部分にインクを詰めて印刷する
凹み具合を変えることで濃淡の変化を表現できるので、より広い表現が可能となる
- グラビア印刷
- 平版
リソグラフ(石版画)がもとになった。現在の主流はPS版。- オフセット印刷
油が水にはじかれることを利用した方法
刷版に付けたインクをブランケットに転写し紙に移す
- オフセット印刷
- 孔版
- シルクスクリーン
- プリントごっこ
- 無版
オンデマンド印刷
印刷には「くわえ代」が必要である。
- 巻取り式印刷機
- 印刷サイズで紙の目が決まる
- 枚葉印刷機
- 紙の目が限定される特殊な用紙がある
- インキ校正
何らかの印刷機を使う。多いのは「平台」と呼ばれる色校専用印刷機。フィルム出力されたものから製版する(刷版を作る)。要素が変わることはないが色再現が難しい。 - ケミカルプルーフ
フィルムは出力するが製版しない。安定した再現性があり、広範囲に利用される。
PSの図形処理モデルは下に不透明なインキを敷き、上のマスクを通して見ることを繰り返すもので、色は上に載ったものが生きるようになっている。実際の印刷に使用するプロセスインキは光を透過させるのでオーバープリントの指定などに注意が必要である。
- 校正機より平台機、平台機より輪転機でドットゲインが大きくなる(印刷速度が速い→印圧が高い)
- ドットゲインの量は網点の周長に依存するので、網点サイズが50%の近辺で最も大きくなる
- 各インキメーカーの色見本の印刷物に示されている網のパーセントの値は、実際に印刷される網点サイズより小さい。=見本は正しいあるべき大きさだから、実際の網点サイズはこれより大きくなる。
- カラーパッチ(カラーバー)
トンボの外側に入れる。- ベタパッチ
インキの濃度をチェックする - グレーパッチ
CMYの色の偏りをチェックする - 平網パッチ
ドットゲインが正常かどうかをチェックする
- ベタパッチ
表紙やカバージャケットなどの印刷物の表面に、防水や光沢を目的として表面加工を施すことがある。
- ニス引き
表面を保護するために行われる。水性ニスを印刷面全面に引く方法と、部分的に行うスポットコーディングがある。湿度が高いと印刷面がブロッキングすることがあるので注意を要する。 - ビニール引き
ニス引きより強い効果を求める場合に用いる。塩化ビニールや酢酸ビニールなどと有機溶剤とを混合した溶剤を、コーターで塗布し熱風で乾燥する。 - プレスコート
ビニール引き後に熱プレスするため、「ビニールプレス」とも呼ばれる。ビニール皮膜によりインキ層からの光の反射率が変化することにより、色調が赤浮きするなど色調再現の問題があるので注意を要する。 - ラミネート
通常ビニール貼りと呼ばれる。塩ビ貼り、PP(ポリプロピレン)貼りなど、印刷物の表面に薄い樹脂フィルムを貼りつける方法で、光沢や保護性に優れている。ただし、ビニールプレスと同様、色調再現の問題がある。
- 面付
縦組みの本は折丁の袋の位置が地側になるように面付けする - 折り加工(ここから無断転載)
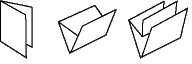
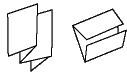
左から 二つ折り、巻き三つ折り、経本折り、巻き4つ折り、観音折り - 丁合
- 製本(ここに製本様式とノドあきのまとめ)
縦組みの本は右綴じの右開き(右へ開く)←→横組みの本は左綴じの左開き- 針金綴じ
- 中綴じ
雑誌やパンフレットなどに多く用いられ、ページ数に限度がある
外折から内折(芯ページ)になるにしたがって左右の仕上がり寸法が小さくなる。 したがって内折ページの版面をノド側に寄せるか、版面の左右寸法を小さくする。目安として16ページ1台で、1mm程度小口の寸法を短くする。 - 平綴じ
厚い製本もできるが、針金綴じの部分(余白)のために、ノドあきは約10mmを必要とする。その分、左右ページの版面は小さくなる。
- 中綴じ
- 接着剤(無線)綴じ
- アジロ綴じ
- 無線綴じ
雑誌や文庫本の製本方式の主流である。ノド側約3mm削られる(ミーリング)ので、その分ノドあきを確保することが必要になる。造本上の強度を確保するために、紙質にもよるが、ベタの絵柄がノドまで入るようなデザインは避けた方がよい。
- 糸かがり綴じ(糸綴じ)
上製本に用いられる。
綴じ方と背の加工は独立していて、使いやすさや耐久性の工夫ができる。
折りの背の部分は削らないので、正規のノドあき寸法でよい。
- 針金綴じ
- 断裁
- 三方断ち
- 天アンカット(文庫本など)
- パーソナライズ=可変データ印刷機能
- ショートラン=小ロット印刷