
この店については、実は、かつてここの常連客であった作家の山口瞳さんやドイツ文学者の高橋義孝さんが、何度かお書きになっている。その他、「この店、この味」的な角度からの紹介記事は新聞、雑誌類にしばしば載った。
昭和十二年の開店以来、店主の沢井ふささんが対したお客は、おそらく延べ百万人前後になるだろう。「安くて、うまくて、居心地がいい」という点について、異論のある人はあるまい。だから、戦前からの常連がいたり、ここ十年ぐらいほとんど一日も欠かさずといった客がいるのである。
にもかかわらず、店主のおばさんという人が、どういう生い立ちで、どんないきさつでここに店を出し、その後、どんな苦労をしてきたか、といった点になると、ほとんどだれも知らない。
浅黒く整った顔立ちは、六十を過ぎたいまでも、若いころをしのばせる。三十年、四十年前はどれほどきれいだったろうか、と思わせるのに、なぜか独身。ご亭主は早くに亡くなったのだろうか、それとも……。おばさんが自らの身の上話をすることはついぞなかった。いつも忙しく立ち働いて、客と雑談する暇がないせいだけでない何かが感じられて、客のほうから質問するのがはばかられた。
たにし亭の三十年来の客である遠藤悟朗さん(五一)=上野動物園勤務、TBSラジオ「全国子ども電話相談室」の月曜日レギュラー回答者=が、この店の四十周年を記念して、何か本を出そうという計画をめぐらすようになったのにしても、おばさんが工夫した料理を広く世間に知らせたいと思う一方、おばさんのことをもっと知りたいという願望があったからだと思われる。

ポン女の学生さんも茶めしを食べに
おばさん自身は、昔、二十年間ぐらい克明につけていた日記は、どこを開いても暗いので、あるとき全部燃やしてしまって、以来、過去は振り返らないことに決めた、というが、今回は、あえて思い出してもらった。だから、この記事の中心は、おばさんの思い出話となるが、その前に、たにし亭とはどんな店か、やはり触れておきたい。
その名の通り、小さい店だ。いつのぞいても盛況で、入れないときが多いから、一度行ってごらんくだいと書くわけにいかないのが、つらいところだ。
国電山手線の目白駅から目白通りを江戸川橋の方に向かって約一キロ、歩いて十分余り。鬼子母神通りとの交差点を越えて間もなくの右手に、赤い字で「おでん」とそめぬいたのれんが下がっている。ここだ。
間口二間、ガタピシの四枚のガラス戸のいちばん左の戸を少し持ち上げるようにして右に滑らせ、首を突っ込むと、おでんの湯気で眼鏡がくもる。奥行き二間程の狭い店内、L字型のカウンターに粗末な丸椅子が十人分。
終戦後間もない昭和二十年の暮れ、強制疎開でこわされた家の古材をかき集めて建てた当時のままである。
以前は年中無休、ここで飲みながら、除夜の鐘を聞く客も多かったが、いまは、日曜、祝日、そして月曜も休み。営業時間も午後六時から十一時までになった。
客層はさまざまである。
開店間もない時間帯は、朝の早い人たち。自らを「一組」と称して、キュッキュッとやり、客同士軽い会話を交わして、「じゃ、お先に」と引き揚げる。
「二組」は、同僚、友人、恋人と連れ立った複数の客が多い。カウンターだけでなく、奥の座敷、小部屋も、予約客とカウンターからあふれた客でいっぱいになる。日本女子大の学生たちもおでんと茶めしを食べにくる。昔はなかったことだ。
「三組」はサラリーマン、学生、湯上がりの近所の商店主など、若い人が多く、談論また風発。
同じ長年の客であっても、一組と三組ではお互い顔も名前も知らないということは、珍しくない。それぞれ、「われこそ、たにし亭の上客」と思いこんでいるから、たまたま一緒になったりすると、案外、反発しあう。笑止。
大半の客が飲んでいるのは、この店独特の「お茶割り」。一合弱の甲種焼酎を、その三分の一ぐらいのほうじ茶で割り、ぶっかき氷を浮かべたものだ。一杯百十円。
お通し(これが実にシャレていて、例えば塩をしたサケの白子の蒸したのにポン酢をかけたものといった具合)は無料。
二級酒百七十円
一級酒二百円(マナーの悪い客は二百二十円)
ビール(大びん)三百円。
刺し身六百円(きわめて上等。食べ残したりする客からは、六百五十円いただくことにしていると、おばさんはいう)
茶めし(みそ汁、つけもの付き)百六十円。
そのほか、季節の料理、おでんなど。勘定を払う段になり、自分の満足度から判断して、もしやおばさん計算違いはないかと心配になること、しばしばである。
個人差はあろうが、お茶割り一杯でほろりとなる。二杯でほぼできあがる。三杯飲んで帰ると、家人に「きょうはたにし亭によってきたんでしょう」といわれる。ウイスキーやビールとは、においが違うらしい。
個人的な記憶では、昭和三十五年前後、このお茶割りが一杯四十円、半分で二十円、二級酒が六十円だった。ポケットに十円玉がジャラジャラ鳴る程度しかなくても心配なくのれんをくぐることができた。お茶割り一杯だけの場合、お通しの原価も計算すると、店の利益は皆無だそうだが、おばさんに粗末に扱われたことはない。

客たちがおばさんを誘って小旅行
作家の大薮春彦さんは、早稲田の学生だった昭和三十二年から三十五年ごろまで、たにし亭に通いつめていた。
「あの店、まだありますか。いやあ、なつかしいなあ。道ひとつ隔てた向かい側に下宿していたんですよ。下宿の飯はおかずがよくないでしょ。腹が減るんで、ほとんど毎晩……。ええ、小説は、そのころからノートに書き出してました。三年のとき『野獣死すべし』でデビューして、以後しばらく行ってたんですが。そうですか、おばさんも元気ですか。思い出集かなんか出すんでしたら、喜んで協力します。ウーン」
電話口の大薮さんは、しばし絶句した後、
「お茶割り、茶めし……。ありがたいお店だったなあ」
と、改めてつぶやいていた。
当時、みんなから「先生」と呼ばれていた常連がいた。徳川夢声に似た容貌でひたすら焼酎を飲む人だった。その先生が、ばったり見えなくなった。焼酎以外口にしなかったので、栄養失調であっさり他界してしまったのだ。飲むときは、やはり何かを食べた方がいいようだ。
たにし亭の客は、おばさん思いでやさしい。最近は、店で知り合った客たちが、おばさんと手伝いの学生を誘って、小旅行をする習慣も定着した。この十一月末には、山形県酒田市の北にある月光川で、サケの溯上を見るグループ旅行をした。その帰りの車中で、おばさんは初めて身の上話をした。
大正三年十二月、大阪の生まれだが、もともとは名古屋市近くのムラの旧家の出だ。祖父はそこの初代村長、村で初めてシルクハットをかぶった人。いろいろの事業に手を出して、没落した。父は苦学して中学を卒業、関西電灯に勤めた後、電気関係の請負工事会社を興して失敗した。母が始めた菓子屋は大繁盛したが、これが誇り高い父にはおもしろくなかったらしい。夫婦げんかが絶えず、離婚。
小学校二年のふささんは、父と二人、東京に来た。山谷の労働者無料宿泊所、木賃宿など、転々と移り住んだ。上京した翌年、関東大震災。掘割に浮かぶ廃船に飛び乗り、隅田川に逃げた。熱風が熱かった。一夜明けて、陸の上は死体の山だった。
不忍池のほとりのバラックにいるとき、二人の妹も父の手に引き取られることになった。ふささんは小学校三年生の身で、母親代わりとなり、家事一切を引き受け、学校には行かず、手内職をした。父はどんな仕事をしていたのか、生活を切りつめて、お金がたまると「特許だ、新案特許だ」と夢中になる発明狂だった。
女衒が来て、三人の娘を売ってくれと切り出したときは、父もさすがに追い返した。
「ねえさん」と呼ぶ客は“四十年もの”
形だけ小学校を卒業してから、女中奉公に出た。実のない味噌汁だけで食べさせられるご飯。しもやけの手が汚いとクビにされたりもした。十五の年から五年間いた本郷の糸問屋では、朝六時から夜十一時まで働かされた。給料の大半は、父と妹たちの生活費になった。髪結い学校に行くために、ようやく蓄えた百八十円も、父に見つかって取り上げられた。無理がたたり、肋膜を患ったが、休む家はなく、神田の職業紹介所や上野の桂庵で次の奉公先を斡旋してもらうほかなかった。
聞いていて息苦しくなるような身の上を、おばさんは、淡々と話した。
みっつ年下の妹も女中をした。画家の古賀春江さんの家に無給で四、五年いて、やめるとき、二百五十円いちどにもらった。これを資金に、妹は、三河島で屋台を出した。二・二六事件の起こる前年、昭和十年である。ふささんも手伝った。
「妹は十九ぐらいだったかな。美人だったから、すごく繁盛して、当時の新聞に出たりしてね。貯金もできたの。それで、二年後にいまの目白に店を開けたの。以上がたにし亭の前史です」
目が弱くなっているおばさん、そこまで語って、目を閉じた。
おばさんの記憶では、目白の開店は、昭和十二年七月二十二日である。ところが、最近、当時の客の一人が訪ねてきて、自分の出征は忘れもしない七月七日、その前夜にここで飲んだと証言した。そんなわけで、開店の日時はあやふやになってしまった。たにし亭には、いまでも、おばさんに対して「ねえさん」と呼びかける客が来るが、これは、姉妹三人でやっていた開店当時を知る人たちだ。
岡山理科大の鎌木義昌教養部長(五七)は、そのころ、早大の学生で近くに下宿していた。
「ぼくは姉さんがいちばんきれいだったと思うな。妹さんは細すぎる印象ですね。若い姉妹がお目当てというのも、先輩連中の中にはおったはずですよ。そうそう、河岸の買い出しに付いて行って、にぎりを食べさせてもらったこともありましたね。貯金ができたからって、店に来る学生を郊外に連れていってくれたり……。そうそう、茶めし……。ええ、当時からありました。安かったなあ」
鎌木さんは、戦後、岡山に戻ったが、いまも家族ぐるみの交際をつづけている。
内緒の酒で出征の常連に送別会
ふささんは、父と仲の悪い二人の妹を、目白に移ってから二年ほどのうちに結婚させ、手伝いの子を一人入れて店を続けた。
で、おばさん自身にロマンスはなかったのか。
「あったのよオ。二十九のときだったかな」
おばさんの目が一瞬だけパッと輝いた。
戦争中のことだ。相手は東大医学部にできた臨時医専の学生。
「わたし、いろんな人に裏切られて、両親さえ信用できない境遇で育っているから、相手を心から信頼することがないのよ。おぼれられない。冷静に見てるの。でも、この人だけは、比較的、信じていた。でも、戦後すぐその人は直腸ガンで死んじゃった」
昭和十八年、九年、統制がいよいよきつくなった。だが、酒、ビール、魚、野菜、一般家庭に比べると、業務用の配給は、質、量ともにましだった。
たにし亭の前には、開店前から空のドカ弁を持った客の行列ができた。開店。おばさんは一人に一本の酒と定量のおかずを出す。客はグビグビと徳利に口を付けて飲み干し、おかずをガバッと弁当箱にあけ、ダダッと外に飛び出し、再び行列の尻につく。中には、女房子どもに並ばせておき、そこに割り込むのもいる。さあ、客同士のけんかだ。おばさんも公平を期さねばならない。二本めまでは許すとして、三本目は、「あんた、もう、ダメッ」。
常連の客が次々に出征して行く日々。内緒で取っておいてあげた酒で送別会。酔って道に寝た学生は、「天皇がなんだ」の一言で目白署に引き立てられた。一週間ほど後、参考人として呼ばれたおばさんは、骨と皮ばかりになったその学生と対面した。
営業できるのは、月のうちの半分、三分の一という状況となり、昭和二十年三月十三日の空襲。階下が店、二階が住居のたにし亭は灰尽に帰した。
再建は二十年の暮れ、二十一年の正月から営業を再開した。焼け野原の一軒家で、コップ一杯五円の“ウイスキー”が、売れた、売れた。
闇で仕入れたアルコールを、メチルが混入していないかどうか、薬屋で分析してもらう。それにカルメラ、酒石酸、サッカリン、本物のウイスキーを少量加えて、水でアルコール分三〇%ぐらいに薄めたのが“ウイスキー”である。
当時、巷には、エチルアルコールを水で薄めただけの“バクダン”が出回っていたが、それにちょっと工夫して、“ウイスキー”にしたところが、たにし亭のおばさんらしいのである。
その年、増加所得税とかで二十万円納税しろと通知が来た。ビックリ仰天、税務署に三ヵ月日参した。
係官も根負けしたのか、ついにおまけしてくれた。税額はなんと六千円。これには、おばさんがあっけにとられた。もっとも、このときの無理で、トリ目になってしまった。
終戦直後の混乱期も薄利の商売
なにしろ、六時起きで、国電の各駅の闇市を回って、アンモニアくさい竹輪などを仕入れて歩き、仕込みをして、それから税務署。夕方から深夜二時ごろまで店をするという毎日だったのだ。
昭和二十二、三年は、密造のカストリ焼酎時代。戦前から、相手がバクチ打ちであれ、朝鮮人であれ、客は客として分け隔てしなかったおかげで、闇の商品の入手は比較的容易だった。口に入るものなら何でも売れた時代、仲間からバカだといわれながら、薄利の商売に徹した。そのころもうけた人たちは、その後、つぶれた。
若き日の山口瞳さんが、この店で、いつも乱れることなく焼酎を三杯、四杯と飲む四十歳ぐらいの男に憧れたのは、昭和二十四、五年ごろだ。
「あるとき、私は、その人に、よくお飲みになりますね、と言った。
『ショッチュウ(焼酎)です』
と、彼は答えた。
別の時に、いまに誰かに表彰されるんじゃないでしょうかと言った。
すると、その人は、落ちついた声で言った。
『ノーメル賞です』
それ以外のことは言わなかった。その事でも、私は彼を尊敬せずにはいられなかった」(文藝春秋刊「酒呑みの自己弁護」から)
おばさんはいう。
「うちにいらしていたころは、山口さん、かわいい顔で、髪がふさふさしてたの。江分利満氏で売り出して以後、写真で見ると、髪がないでしょう。なかなか同一人物と思いにくかった」
昔からうまいといわれるたにし亭の肴だが、おばさんが正規の調理学校で料理を習ったのは、四十五歳を過ぎてからだ。長年おばさんを悩ましつづけてきた父親が、老人性痴呆症で入院して、ようやく自由な時間を得たのだ。
「父の生きているころには、どこの神さま仏さまでもいい、どうか私を三日でもいいから自由にしてください、四日目には死んでもいいからって、お願いしたものだわ」
その父は、十年余り前、ついにあの世の人となった。
「その後の十年、わたしは、一日一日が本当に楽しいの。宝石より大事にして送っているわ」
おばさんは、安らかな表情で、そういいきった。
おばさんの心のこもった料理のうまさ、やさしいもてなしは、五十年の苦難と抱き合わせになっていたことが、納得できた。
本誌・池辺 史生
週刊朝日 1976年12月17日号(122ページ〜126ページ)より
この記事・写真は、著作権者である朝日新聞社の許諾(転載許可期間限定)を得て転載したものです。朝日新聞社に無断でこの記事・写真を転載、送信、出版するなどの行為は禁止されています。
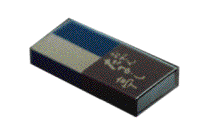
戻る