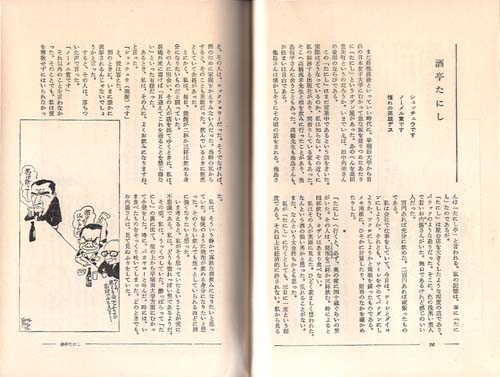
酒亭たにし
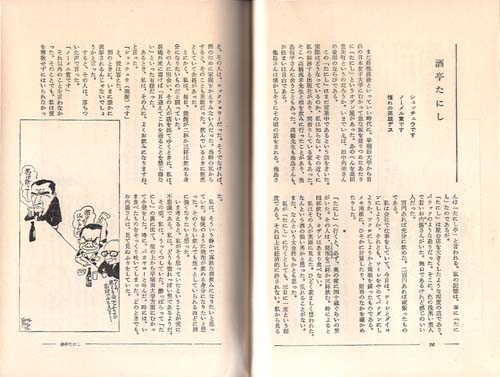
ショッチュウです
ノーメル賞です
憧れの英雄デス
まだ終戦直後といっていい時代に、早稲田大学から目白の日本女子大学にむかって急な坂を登りつめたあたりに「たにし」というオデン屋があった。あのへんを高田豊川町というのだろうか。いまでいえば、田中角栄さんの豪邸のならびである。
この「たにし」はまだ営業中であるという話をきいた。実際はどうなっているのか、私は知らない。その近くに私の勤務する出版社があり、間借りしている家もあった。そこへ高橋義孝先生と酒を飲みに行ったことがあり、池島信平さんに会うこともあった。高橋先生も池島さんも、お住まいは目白である。
池島さんは懐かしそうにその頃の話をされる。池島さんは「たにし亭」と言われる。私の記憶は、単に「たにし」なのであるが。
「たにし」は屋台店を大きくしたような程度の店であり、バラックのような造りだった。そこに、色の浅黒い美人で若いお内儀(かみ)さんがいた。無口であるけれど感じのいい人だった。
百円あれば充分に飲めた。二百円あれば威張ったものである。
私は会社で仕事をしていて、今日は、ツミレとダイコンにしようか、それとも、ツミレはやめてバクダンにしようか、フクロにしようかと策略を練ったものである。メモ用紙に、ひそかに計算したり、財布のなかを確かめたりした。
*
「たにし」に行くと、必ず、奥の席に四十歳ぐらいの男がいた。その人は、焼酎(しょうちゅう)を二杯か三杯飲む。時によると四杯飲む。オデンはあまり食べない。
私はその人が英雄に見えた。ひどく羨ましく思われた。なんという酒の強い男かと思った。乱れることがない。また、なんという大金持ちかとも思った。
私が「たにし」に行くとしても、三日に一度という程度である。それ以上は経済的に許されない。私から見ると、その人は、ロックフェラーだった。そうでなければ、酒のために家庭をかえりみない人だった。当時の私からすると、そのことも英雄だった。飲んでいるときに悠然としていて余裕があった。
とにかく、私は、毎日、焼酎が二杯か三杯は飲める身分になりたいものだと願っていた。
その人に出会い、その人が店を出てゆくときには、私は、森鴎外流に書けば「目迎えてこれを送ることを禁じ得ない」といった有様だった。
あるとき、私は、その人によくお飲みになりますね、と言った。
「ショッチュウ(焼酎)です」と、彼は答えた。
別のときに、いまに誰かに表彰されるんじゃないでしょうかと言った。
すると、その人は、落ちついた声で言った。
「ノーメル賞です」
それ以外のことを言わなかった。そのことでも、私は彼を尊敬せずにはいられなかった。
私は、そういう静かで寡黙な酒飲みになりたいと思っていた。毎晩のように焼酎が飲める身分になりたいと思った。そのくらい飲んでも悠々としていられるほどに酒に強くなりたいと思った。
いま考えると、私がそう思っていたと言うことが実に不思議である。私は、どうも惚れっぽい男であるようだ。
その頃、私は、うっくつしていた。酔っぱらって「たにし」の裏に出て、崖の上から早稲田大学方面にむかって小便をした。時に、バカヤローと叫んだ。時には、いま食べたものをそっくり吐いてしまった。どのときでも、お内儀さんは、見て見ぬふりをしていた。
『酒呑みの自己弁護』 山口瞳著 新潮社 ページ26〜27
昭和四十八年三月三十日 発行
なお、本掲載に付きましては著作権継承者である山口治子さんのご好意で了解頂いております。