(1)生活と人生
ようこそお参りくださいました。お久しぶりでございます。私は、こちらの田畑先生のお招きを頂きまして、京都の紫雲寺からまいりました伴戸昇空と申します。2年前の「歎異抄に聞く会、10周年記念会座」にもお招き頂きましたので、こちらでお話しさせて頂くのは、これで2度目でございます。
本日は、こちらの円徳寺様で毎月お開きになっておられる「歎異抄に聞く会」の150回記念のお集まりとうかがっております。毎月毎月、聞法を重ねられて、150回に至っておられる。これは、よほどのご縁かと存じます。そのような皆様方の記念すべきお集まりに、重ねてお招きを頂きましたことは、まことに光栄なことと存じております。
先日、田畑先生から、この「150回記念会座」の御案内を頂きました。そのなかに、田畑先生がご指導を受けられた細川先生のお言葉が引かれておりまして、「3年前と同じ話をするようでは味わいがない」と書かれておりました。よちよち歩きの私にとりましては、大変重い言葉でございます。果たして、前回と趣の違う話がさせて頂けるかどうか、甚だ心許ない思いもいたしますが、どうぞ、しばらくの間、お付き合い下さいますよう、お願い申し上げます。
さて、本日は、先にご案内申し上げましたように、「仏のまなざしのなかで」という題でお話しさせて頂きます。私たちは、常に、「仏のまなざしのなかで」日暮らしをさせて頂いているわけですけれど、仏法にご縁がないと、なかなかそのことに気づけないものですね。
まあ、仏法にご縁がなくとも生活はできるわけですから、金や地位や名誉を求め、何か美味いものはないか、何か面白いことはないか、健康が大事、生き甲斐が大切といって、「生活」だけが問題になっている間は、なかなかご縁が開けてこないということかもしれません。
ですが、人生は、生活だけでできているわけではないのでして、いずれ、どなたにとっても、生活ではなくて、人生そのものが問題になる日がやってくると思うのです。本当の意味での「人生」が始まるのは、そこからですね。
では、「人生」と「生活」はどう違うのか。この問題をお考え頂くのに、ぴったりの話がありますので、まずは、その話をご紹介いたします。
大正から昭和の初め頃にかけて、大阪城の修理が行われたことがあります。その頃のことです。あるとき、内務大臣だった望月圭介が東京から視察にやってきました。この望月圭介という人は、広島県の出身で、熱心な安芸門徒だったそうです。
お昼時に、一人でぶらりと現場にやってきた大臣は、大工さんたちの前に立って、こう問いかけた。
「毎日御苦労さんですね。あなた方は毎日そうやって、一所懸命に働いていて下さるのだが、一体何のために働いているのかね」と。
妙な質問でしたが、相手は大臣ですから、答えないわけにはいきません。
「そりゃあんた、働かんことには金もらえませんがな」
「なるほど、そりゃそうだ。誰だって働かぬものには賃金はくれんからね。それなら、その金をもらってどうするのかね」
「もちろん、米を買うのだよ」
「なんのために、米を買うのだね」
「そりゃあんた、食うためですがな」
大工さんたちは大笑いですが、大臣はまじめな顔でさらに聞きます。
「なんのために、食うのかね」
「食わなんだら死にますがな」
そのとき望月さんは、ひとこと、こう言った。
「そんなら、食うておったら死なんのかね」
一同唖然として、二の句がつげず、口のなかでモゴモゴと、
「食うておっても死ぬ、食うておっても死ぬ」とつぶやいた、ということです。
いかがですか。笑い話のような逸話ですが、実は、よく味わって頂きたい大切な話なのですね。働いて賃金をもらい、米を買って食べないと死ぬ。そこで問題になっているのは「生活」なのです。ところが、食べていたら死なないのか、という問いかけで問題になっているのは「人生」なのですね。
同じ「死」というものを問題にしながら、大工さんたちは、それを「生活」の危機として捉えている。別に、この大工さんたちだけではなくて、私たちはたいていそうですね。ところが、望月さんは、それを「人生」の危機として捉えているのです。
別の言葉で言えば、かたや、何とか避けたいものとして「死」から目を背けているのに対して、かたや、何としても避けられないものとして「死」を見つめている。いわば、顔を向けている方向が違うのです。仏教の話が解りにくいという本当の理由は、まずは、このあたりにあるのですね。
話を進めます前に、「生活」と「人生」の関係を見ておきたいと思います。ちょっとこちらの図をご覧になってください。
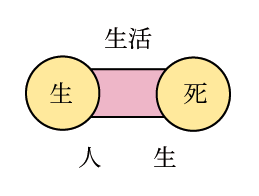 赤い棒の両端に黄色い団子がくっついているような図です。左端の黄色いマルには「生」と書いてあります。「誕生」ですね。そして、もう一方の右端の黄色いマルには「死」と書いてあります。「死亡」です。人生というのは、この左端の黄色いマルから始まって、右端の黄色いマルまでを言います。では、生活とは何かと申しますと、生活というのは、この赤い棒の部分だけを言うのです。
赤い棒の両端に黄色い団子がくっついているような図です。左端の黄色いマルには「生」と書いてあります。「誕生」ですね。そして、もう一方の右端の黄色いマルには「死」と書いてあります。「死亡」です。人生というのは、この左端の黄色いマルから始まって、右端の黄色いマルまでを言います。では、生活とは何かと申しますと、生活というのは、この赤い棒の部分だけを言うのです。
仏法は、人生全体を問題にしています。それも、とりわけ、人生を両端から規定している「生死」を問題にしているのです。ところが、私たちは、そうではない。私たちが悩んだり苦しんだりしているのは、たいてい、人生の問題ではなく、生活の問題なのですね。この赤い棒の部分だけです。そこで、仏法が解らないということになってくるわけです。
「生活」には、「生きたい、生き延びたい、生き残りたい」という欲求しかありません。ですが、「生き延びたい」といっても、寝たきりの病人になっては、いくら長生きしても仕方がない。そこで、「健康が大事」ということになってくる。しかし、いくら健康で長生きしても、それだけでは退屈で仕方がない。そこで、次には、「生き甲斐が大切」ということになってくる。
そのうえ、「生き延びたい、生き残りたい」という欲求だけを握りしめて世界を見れば、当然、「この世は、生き残りを賭けた競争の世界」に見えてしまいます。つまり、「この世は、適者生存、弱肉強食の世界だ」ということになるわけです。
「生活」があって「人生」がない人間を、「修羅」と言います。修羅の行く先には「地獄」しかありません。もちろん、「生活」のない「人生」というものはありませんが、「生活」は「人生」にまで深められる必要があるのです。そうなったときに、初めて、本当の意味での「生活」が始まるのです。
それにしても、私たちの社会は、よくよく「人生」を考えさせないような仕組みになっていますね。
「生・老・病・死」というのは、人生の骨組みです。この「生・老・病・死」を、自分の問題として、苦しみ悩むところから「人生」は始まるのです。
ところが、現代社会ではどうでしょう。子供が産まれてくるとき、病気になったとき、年老いて身体が不自由になったとき、そして死んでいくとき。こういうときは、みんな病院に入っているのですね。
そして、病院から出てきたら、私たちは、どう言うか。「社会復帰」と言うのですね。つまりは、病院の中は社会ではないということです。患者と呼ばれているあいだは、人間扱いされていない。現代社会では、「生・老・病・死」を人生の表舞台から排除しているのです。
テレビを見ても、そうですね。人生を思い出させ、考えさせるような番組は、まず、ありませんね。人生を忘れさせるような番組ばかりです。私たちの社会は、どうして、それほどまでに、人生から目を背けようとするのでしょうかね。
さきほど、「生・老・病・死」は人生の骨組みだと申しましたが、ご承知のように、仏教では、この「生・老・病・死」を「四苦」と呼んでおります。「生まれる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、死ぬ苦しみ」ですね。
ちなみに、この四つの苦しみに、「愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦」の四つを加えて「八苦」と言います。
「愛別離苦」というのは、愛する人と別れる苦しみです。「怨憎会苦」というのは、怨みに思っている憎らしい人とも会わねばならない苦しみです。
ちょっと余談ですが、このあいだ、ある本に、「地獄の苦しみというのは、嫌いな親戚百人と一つの部屋にいることだ」と書いてありました。それなら、極楽の喜びとは何かというと、「姑が死んで息子に嫁が来るまでのあいだ」と言った人がいます。まあ、それほど、身近な人間関係というのは難しいということでしょうね。
さて、その次の「求不得苦」というのは、求めても得られない苦しみです。そして、「五蘊盛苦」というのは、簡単に言えば、我が身に煩悩が沸き立つ苦しみです。「私が、私が」という「我執」に、身も心も苦しむことです。
ですが、私たち一人一人の人生にとって、本質的な問題は、やはり「生・老・病・死」の「四苦」でしょうね。この「生・老・病・死」をしっかり見据えることができれば、残りの四つには、自ずと道が開けるものと思います。
「四苦」というのは「生まれる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、死ぬ苦しみ」のことですが、実際には、これは「死ぬ苦しみ」ひとつに集約されてしまいます。
「生まれる苦しみ」というのは分かりにくいかもしれません。私たちは「産みの苦しみ」とは言っても、「生まれる苦しみ」とは言いませんからね。ですが、「生まれる」ということは「いずれ死なねばならない」ということでもあります。「生まれる」というのは、「死ぬ」ことが約束されているということです。ですから、死ぬことが苦しみである限り、生まれてくることも苦しみなのです。
また、「老いる苦しみ」というのは、ただ歳をとるのが苦しいという意味ではありませんね。たとえば、20歳の者が25歳になっても、別に、苦しくはないでしょう。そうではなくて、「老いる苦しみ」というのは、「死ぬときが近づいてきたと思う苦しみ」「死ぬことへの予感を持つ苦しみ」ですね。
「病む苦しみ」と申しましても、鼻風邪ひとつ引いたくらいで、深刻に苦しむ人もいないでしょう。そうではなくて、大病を患ったときに、「ひょっとしたら、これで終わりかもしれない」と思う苦しみがある。それが、「病む苦しみ」ですね。ですから、「病む苦しみ」というのも、「死への予感を持つ苦しみ」なのですね。
では、「死ぬ苦しみ」とは何か。私たちはよく、「死ぬほどの苦しみ」とか「死ぬより辛い」というようなことを申しますが、かつて死んだという経験を憶えているわけではありませんね。私たちの経験から言えば、死ぬということが、苦しいことなのかどうか、実は、よく分からないのです。かつて死んだときのことを思い出せたら、「死ぬ苦しみ」というのは無いのかもしれませんが、まあ、そういうことは、まずありません。では、「死ぬ苦しみ」とは何かと言えば、それは「死ぬことへの不安」なのですね。
ここ30年ほどの欧米の心理学者の研究によりますと、「死ぬことへの不安」が最も低いのは東南アジアの人々、それについで、欧米の人々、そして、最も「死ぬことへの不安」が高いのが、私たち日本人だったということです。
死を前にすると、日本人がいちばん苦しむ。不思議な気もしますが、それには理由があるのです。欧米の科学技術というものは、もともとキリスト教信仰と抱き合わせになって発展してきたのですが、明治以降、日本は、その宗教的側面を切り捨てて、科学技術だけを導入してきました。そして、ついには、いわば科学を信仰するようになってしまったのです。
その科学の教えでは、「目に見える世界が全て」です。ですが、「目に見える世界が全てだ」ということであれば、たとえば「私」というのは、この、目に見える体のことだということになる。この体が私の全てだということになれば、当然、「死ねば終わりだ」ということになってまいりますね。
世界中探しても「死ねば終わりだ」と思っている民族や文化はめったにありませんが、現代の日本人の大半は、その例外中の例外にあたるのです。ギャラップの世論調査でも、死後の世界を信じる日本人はわずか18%に過ぎません。それに対して、アメリカでは67%もの人々が来世の存在を信じているといいます。
「死ねば終わりだ」と思っている私たちの目には、「死」の先には何も見えません。「死」の先には、底なしの暗闇が広がっているだけです。そんな底なしの暗闇が恐くて仕方がないものですから、私たちは、そこから必死で目をそらせて生きています。「死ぬ」というのは、私たちが一番聞きたくない言葉なのですね。
「死ぬことへの不安」というのは、私たち現代人にとっては、「死んでしまったらお終いだ」という思いから生まれてくる不安です。死ねば、意識がプツンと切れて、それで、全ては御破算になるという恐怖ですね。そんな恐怖に直面していることは、とても耐えられないものですから、私たちは、必死になって「死」から顔を背けている。死から顔を背けて、生活にしがみついて生きているのです。私たちが「人生」を考えないようにして生きているのは、そのためですね。
しかし、「死ぬ」ということは、誰もが避けることの出来ない人生最大の現実です。私たちは、たとえどんなに長生きしようとも、いずれ死ぬのです。お釈迦様でも80歳でお亡くなりになったのです。ですが、そこには「死ぬことへの不安」は無かった。「死ぬこと」は避けられなくとも、「死ぬことへの不安」は解消できる。仏教がめざしているのは、「いのちの真実の姿」を伝えて、この「死ぬことへの不安」を解消することです。
「死ぬことへの不安」が解消されたとき、仏教の言葉で、「安心(あんじん)」を得たと言います。「安心」というのは「安らかな心」と書きます。私たちは、これを「あんしん」と読みますが、「あんしん」と「あんじん」は違います。
「あんしん」というのは、「生活の危機」が解消することです。たとえば、病気になったときの不安、お金が無いときの不安です。こういった不安が解消されると、私たちは安心する。病気が治ると安心する。お金が出来ると安心する。そうですね。それに対して、「あんじん」というのは「人生の危機」が解消すること、「死ぬことへの不安」が解消することなのです。
私たちが聞法するのは、「生活」を「人生」にまで深めて、「安心」を得るためなのです。思えば、「生活」の上に起こってくる様々な問題は、みんな、私たちへの問いかけなのです。私たちは、常に問われているのです。ですが、その、問われていることに気づけるのもまた、仏法を学んできた、聞法してきたお陰なのですね。
問題は、いたずらに生き延びることではない。人生は、サバイバルではないのです。人生で大切なのは、「食べていても死ぬ」という、限りある生命を、如何に生きるかということなのです。食べられる時でも、食べられない時でも、私たちは、常に問われている。その状況のなかで如何に生きているかという、「生き方」を問われているのです。
一度、お考えになって頂きたいのですが、「如何に生きているか」と問われると、私たちは何と応えるでしょうか。 … おそらく、「一所懸命に生きている」と応えるのではないでしょうか。
私たちは、「一所懸命に努力するのは尊いことだ」と教えられてきました。たしかに、それには違いないでしょう。ですが、私たちがみな、「もっと便利な生活、もっと快適な生活」と、物質的に豊かな生活を求めて、一所懸命に努力してきた結果、今、世界はどうなっているのでしょうか。環境破壊が進み、人類絶滅の瀬戸際まできているのです。何かおかしいとは思われませんでしょうか。
そこで一度、「一所懸命」という文字を思い出してみてください。一所懸命というのは、「一つの所」に命を懸けるということ、命懸けになるということですね。そこで、問題なのは、どこに命を懸けているのかということです。私たちが命を懸けてきた「一つの所」とは何だったのでしょうか。「生き方」を問われているというのは、この「一所」を問われているということです。
「人は教育によって作られる」とよく言われますが、私は、教育で一番大切なのは、この「一所」を教えることではないかと思いますね。もしも、子供の頃に、「食べていても死ぬんだ」という、この一言だけでも教えられて育ったら、世界はもっと違っていたと思うのですね。
いかがですか、皆さんは、「食べていても死ぬんだから、しっかりしなさいよ」と言われて育ったのでしょうか、それとも、「食べられないと死ぬんだから、しっかりしなさいよ」と言われて育ったのでしょうか。お考えになってみてくださいね。
私たちはたいてい、「食べられないと死ぬんだから、しっかりしなさいよ」と言われて育ちます。科学万能の現代社会に生きている私たちは、たいてい、「目に見える世界が全てだ」と教えられて育ち、「死ねば終わりだ」と思っていますね。しかし、そういう「生命観」には、「食べていても死ぬんだ」という言葉を受けとめるだけの力がないのです。
ですがね、「いのちの真実の姿」は、そうはなっていないのです。聞法を重ねてこられた皆さんには、よくよくご承知のこととは存じますが、「浄土の教え」では、「死ねば終わりだ」とは説かれていない。「人は、死ねば浄土へと帰っていくのだ」と説かれているのです。
私たちは、「いのちの真実」とは違った思いを握りしめて、「いのちの自然な姿」に背いて生きているから苦しいのです。「死ねば終わりだ」という思いを握りしめて、生活にしがみついて生きているから苦しいのです。
人生には様々な問題が、次から次へと起こってきます。私たちは、そういった問題に、悩み苦しみながら生きているわけですが、次から次ぎから問題が起こってくるということは、とりもなおさず、聞法への御催促を受けているということなのです。
聞法への御催促というのは、「仏の教えを聞きなさい。そして、その問題を、仏の光のなかで見てごらん」という、命の奥底からの呼び声です。どうぞ、その呼び声に耳を傾けて頂きますように。仏の光は、常に私たちを照らしているのです。私たちは、なかなか、その光に気づけないだけなのです。
「仏の光は、常に私たちを照らしている」。このことを、『正信偈』には、「大悲無倦常照我」と書かれていますね。「大悲無倦常照我」というのは、「大悲の光は、倦むことなく、常に我を照らしたもう」と読みます。
もともとは、源信僧都の『往生要集』に出てくる言葉でして、「阿弥陀様の大悲の光は、信心の人を、倦むことなく、常に照らして下さっている。常に照らして下さっているというのは、常に護って下さっているということである」という意味です。
「阿弥陀様は、信心の人を、常に護ってくださっている」のです。ですが、残念ながら、私たちは、たいてい「信心の人」とは言いにくい生き方をしておりますから、この「信心の人」というところが読み取れないのですね。そこで、「信心の人」をいう言葉を飛ばして、「阿弥陀様は、…私を、常に護って下さっている」と理解してしまうのです。
そんな私たちが、護って欲しいと願うのは、どんなときでしょうか。病気になったときとか、お金に困ったときですね。病気になれは、何とか病気が治りますように、お金に困れば、何とかお金が手に入りますように。家内安全、無病息災、交通安全、商売繁盛、武運長久、戦勝祈願。違いますかね。そんな私たちは、心のどこかで、そういう自分にとって都合のよい願いを叶えてくださるのが、仏様の仕事のように思っているところがある。
ところが、実際には、いくら仏様に願ってみたところで、そうそう自分に都合のよいことばかりが起こるわけではない。そこで、「人生、何十年も生きてきたら、この世に神も仏もないことくらい、身を以て分かる」というような、見当違いのことを言う人もでてくるわけです。
ですが、それは違うのです。「常照我」とは、言葉どおり「常に我を照らしたまう」という意味です。「常に我を照らしたまう」とは、どういうことか。それは、こういうことです。ここに懐中電灯があります。これで、こういう具合に、頭の上から私を照らす。これが「常照我」です。
光が私を照らしている。暗闇の中で照らし出された私には、何が見えますか。暗闇の中で照らし出された私に見えるのは、今の今まで見えていなかった、この私自身の姿なのです。「もっと豊かな生活、もっと便利な生活、もっと快適な生活」と、「生きようとする盲目的な意志」に操られて、「生活」に命懸けでしがみついて生きている、そんなお粗末な私の姿なのですね。
ある人が、信心を喜ぶ人に、こう尋ねました。「あんたは、有り難い、有り難いと、お念仏を称えているが、信心の功徳というのは、どんなものかね」と。すると、その人はこう答えたと言います。「お粗末な我が身であると知らせて頂いたことです。ナマンダブ、ナマンダブ」と。
また、念仏者で有名な木村無相さんの詩に、こんな言葉があります。「煩悩具足のぼろ家に、南無阿弥陀仏が住みついて、灯りがついて、ぼろ家のおんぼろが見えまする、南無阿弥陀仏と見えまする」。『念仏詩抄』という詩集に出てくる言葉ですが、この、「灯りがついて、ぼろ家のおんぼろが見えまする」というのは、大慈大悲の光に照らされて、初めて我が身の「愚かさ」が見えましたということでしょうね。
自分の愚かな姿に気づかせてもらうと、安らかな心になる。といっても、これは、「愚か者」とひとこと言われるだけでも腹が立つ、そんな私たちには、なかなか理解しにくいところですが、ひとつ、こんなふうにお考えになってみたらどうでしょう。
たとえば、殺人なり強盗なりの犯罪を犯して、懸命に逃げていた犯人が、時効の寸前に捕まったという話を聞くことがありますね。そんなとき、犯人は、たいてい「捕まってホッとした」と言うそうです。逃げている間は、一瞬たりとも心の安まる時はなかった。何とか生き延びようと必死になっていた。だが、もう、そんなサバイバルのために苦しまなくともよい。
あまり適当な「たとえ」ではないかもしれませんが、仏の光に捕まって、自分の愚かな姿に気づかせて頂いたときに生まれる「安らかな心」は、この、犯人が捕まったときの安堵感に似ていると、お考え頂いたら、さほど、的はずれではないと思います。
私たちにとって一番難しいのは、自分の愚かさに気づくことです。人生を忘れて、生活に右往左往している、そんな愚かな自分の姿に気づくことです。その一番難しいことに気づかせてくださること、それこそ仏の慈悲なのですね。そういう意味では、この「大悲無倦常照我」という言葉も、「大悲とは、倦むことなく、常に我を照らしたもうことなり」と読むべきではないかと思いますね。
自分の愚かな姿に気づかせてもらうと、安らかな心になると申しましたが、本当に、自分の愚かさに気づいたら、「自分を笑える」と思うのですが、いかがですか。本当に自分を笑える人は、人を笑わない。人を責めない。そういう人の傍にいると、ホッとする。心が安らぐ。温かい人というのは、そういう、自分の愚かさを笑える人のことではないでしょうかね。
自分を笑うことをユーモアと言います。温かい人にはユーモアがある。それに対して、他人を笑うことをウイットと言います。ウイットには、棘がある。人を笑うことは簡単ですが、本当に自分を笑うことは難しいのです。自分を笑うには、大きなエネルギーが要るのです。そのエネルギーは、「いのち」の奥底から湧いてくる。その「いのち」の奥底から湧いてくるエネルギーこそ、常に我を照らしたまう光なのです。
大悲の光に照らされて、「生活」が「人生」にまで深められ、ついに「安心」を得たとき、今度は、その「安心」が、生活のなかに、「生き方」となってフィードバックされてくる。心を満たした光が、外へあふれ出てくるのです。ユーモアに、人をホッとさせる明るさがあるのは、そのためでしょうね。
「安心」を得ると、「生き方」が変わります。というのは、私たちは、「死ぬことへの不安」があるから、「死」に背を向けて「生活」にしがみついて生きているのですが、「安心」を得て「死ぬことへの不安」が無くなれば、「生活」にしがみつく必要も無くなります。そこで、自ずと「生き方」が変わってくるわけです。
「生き方が変わる」と言っても、やっぱり、「一所懸命」に生きることに変わりはありません。変わるのは、「一所懸命」の「一所」の方なのです。信仰に生きる人は、その「安心」が、命を支える「一所」となるのですね。
「安心」を得た人は、心安らかに、本当の自分を生きることができるようになり、「いのち」が輝いてくる。その「いのち」の輝きが、世界を照らす光となるのです。「浄土の教え」の本当の意味は、そこにあるのですね。言葉を変えて言えば、「安心」を「一所」として生きること、そのことの大切さを教えているのが「浄土の教え」なのです。
では、この辺で、少し休憩を挟ませて頂くことにいたします。
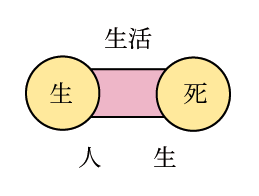 赤い棒の両端に黄色い団子がくっついているような図です。左端の黄色いマルには「生」と書いてあります。「誕生」ですね。そして、もう一方の右端の黄色いマルには「死」と書いてあります。「死亡」です。人生というのは、この左端の黄色いマルから始まって、右端の黄色いマルまでを言います。では、生活とは何かと申しますと、生活というのは、この赤い棒の部分だけを言うのです。
赤い棒の両端に黄色い団子がくっついているような図です。左端の黄色いマルには「生」と書いてあります。「誕生」ですね。そして、もう一方の右端の黄色いマルには「死」と書いてあります。「死亡」です。人生というのは、この左端の黄色いマルから始まって、右端の黄色いマルまでを言います。では、生活とは何かと申しますと、生活というのは、この赤い棒の部分だけを言うのです。