本日は、ご案内申し上げておりますように、「いのちの絆」という題で、お話し申し上げたいと思っております。
これまでにも何度もお話し申し上げてまいりましたように、私たちの「いのち」は、深いところでみんなつながっています。ですから、世界で起こっていることは全て私たち一人一人と無関係ではないのです。それは、たとえば、今年の5月24日に神戸で起きました小学生殺害事件も、私たち一人一人と無関係ではないということです。
今回の話は、この神戸の事件がご縁となって、私たちの「いのち」の真実について改めて考えさせていただいたことが中心になっております。相変わらずの、いささか理屈っぽい話ではございますが、どうぞしばらくの間お付き合いくださいますよう、お願い申しあげます。
さて、皆さんは、現代の若者たちをご覧になって、どんなふうにお感じになっておられるでしょうか。おそらく、「今の若い者は、何を考えているのか分からない」と、お感じになっておられるのではないでしょうかね。
「今の若い者は」と言うようになったら、もう若くない証拠ですが、この言葉はいつの時代にもあったようでして、以前、こんな話を聞きいたことがあります。紀元前3000年頃のメソポタミア文明の遺跡を発掘していたら、楔形文字の書かれた粘土板が出てきた。学者が苦労してその文字を読んでみると、「今の若い者は」と書かれていた、というのです。
本当かどうか知りませんが、そんな話がまことしやかに囁かれているくらい、いつの時代でも、若者には、「何を考えているのか分からない」ようなところがあるものなのですね。ですが、「分からない」ではすまされないこともある。それが、たとえば、今回の事件です。
残念ながら現代社会では、殺人事件そのものは、さほど珍しいものではありません。ですが、今回の神戸の事件は、小学6年生を殺害して死体の一部をさらしものにしたり、犯行声明文を新聞社に送りつけたりしたのが、14歳の中学生だったという点で、きわめて衝撃的な事件でした。
「少年は気が狂っていたのだ」と言う人もいます。実際、やっていることは狂気の沙汰ですから、確かに、犯行当時は普通の精神状態ではなかったでしょう。しかし、私には、この少年が私たちとは全く違った異質な人間だとは思えないのです。少年は、社会という風船の一番薄い場所だった。社会の内側に膨らみ続けている大きなストレスが、その一番薄い場所を突き破って吹き出した。私には、そう思えてなりません。
私たちの社会は大きな問題をかかえている。いわば、少年たちは、私たちがその問題に気づくために、命がけでメッセージを送ってくれたようにも思うのです。少年は私たちに向かって命がけでボールを投げた。私たちは、そのボールをきちんと受け止めねばなりません。今回の法話に、この事件を取り上げました理由は、実はその点にあります。
では、まず話を進めます前に、この少年の心に何が起こっていたのかということを、私なりにまとめておきたいと思います。
少年が自ら書いた「犯行声明文」と「犯行メモ」を読んでみますと、そこには、気になる言葉がふたつ出てまいります。それは、「透明な存在であり続けるボク」という言葉と、「バモイドオキ神」という神様らしきものです。
「透明な存在であり続けるボク」の心のなかに、「バモイドオキ神」という神様が降臨し、少年はこの神様にすがろうとした。私は、ここに、今回の問題の本質を読み解く鍵があると思います。
自分が「透明な存在」だというのは、まるで、そこに誰もいないかのように、人の目が自分を素通りしていく、通り抜けていくと感じている、ということでしょうね。それは無視されているという感覚ではありません。無視されているというのでしたら、他人は自分がそこにいることをちゃんと知っていて、あえて見えないようなふりをしているだけです。しかし、この場合は違います。少年が抱いていたのは、他の人々の意識のなかに自分が存在していないという感覚です。
ちょっと適当な言葉が見あたりませんが、「透明な存在」という言葉で少年が言いたかったのは、誰ともつながれずに孤立して、自分にさえ自分がリアルに見えなくなってしまった、底知れぬ不安とでもいった感覚ではないかと思います。私たちの日常的経験のなかで、それに似た感覚と言えば、おそらく、繁華街や駅の雑踏のなかで感じる孤独感に近いのではないかと思いますね。
皆さんもご経験がおありだろうと思いますが、たとえば、駅のなどの雑踏のなかで立っておりますとね、沢山の人が自分のまわりを通り過ぎていく。それなのに、誰も自分がそこにいることになど関心がない。誰の心にも、自分の姿は写っていない。そんななかで、人の流れのざわめきを聞くともなしに聞いていると、そのうちだんだん自分自身の現実感まで薄れてくる。
よく、地方から出て都会で一人で暮らすようになった人が、都会の孤独を感じると言いますが、それも似たような感覚ではないかと思います。私たちは、そんな感覚を経験することがあっても、ほんの一瞬ですから、たいして問題にはなりませんが、そんな感覚が日常的にずっと続いているとしたら、おそらく大変なことになると思いますね。
少年の育ってきたプロセスに何があったのか、それが少年の心にどんな影響を与えたのか、本当のところは分かりません。ただ、一般的に言えば、厳し過ぎる親に育てられると、この少年のような感覚を持つようになっていきます。「あれもダメ、これもダメ、そんなことも分からんのか、頼りない奴だ、情けない奴だ」と、自分を全て否定され、自分の本当の姿をことごとくはぎ取られてしまえば、誰だって、透明になってしまいます。
私の知り合いに、子供時代にそういう経験をした人がいます。その人は、大人になって運転免許を取って、はじめて車で街に出たときに、非常に驚いたと言います。車線変更をしようとしてウインカーを出したら、まわりの車はちゃんと道をあけてくれた。「他の車には自分が見えているんだ」と感動したというのです。悲しい話ですね。
思うのですが、そんなこともあって、少年は、小さい頃から、母親とも父親とも兄弟たちとも、心のつながりを持てなかったのではないでしょうかね。家族のなかにいて、家族とつながれなかった。親に愛情がなかったというわけではないでしょうけれど、少年は、親の目が自分を素通りしていくように感じながら育った。都会の雑踏のなかの孤独が、家庭のなかにあった。
少年の心は、とほうもない孤独感に押しつぶされそうになっていた。どこにいても、寂しかった。何をしても、虚しかった。何をしても、生きているという実感をともなった喜びが得られなかった。おそらく、そうだったのではないかと思います。
私たちは、他の人々とのつながりを無くすと、自分がそこにいる意味まで無くしてしまいます。少年は、他の人々とつながりたかったのに、つながれなかった。少年はこう言っています。「今までも、そしてこれからも透明な存在であり続けるボクを、せめてあなた達の空想の中でだけでも実在の人間として認めて頂きたい」と。これは、意味を無くした自分に絶望しながらも、最後まで現実世界につながる手がかりを求め続けずにはおれなかった少年の、心の底からの叫びだったと思います。
家族とつながれなかった少年は、友だちとも、先生とも、誰ともつながる手がかりを見いだせなかったのでしょう。外の世界に目を向けるたびに、つながる手がかりを見いだせず、傷つき絶望した少年は、傷だらけになった自分の心を見つめて暮らすようになります。少年の話し相手は、心についた一つ一つの傷だけになっていくのです。
そんな少年の心の暗闇のなかに姿を現したのが、「バモイドオキ神」という神様でした。この神様は、神の仮面を付けた悪魔でしたが、少年には、それを見破る力も、心の余裕もなかった。そして、少年は、その神にすがりつくことで、つまり、その神のために生きるという「物語」にすがりつくことで、自分がこの世に存在する意味を取り戻そうとしたのです。
少年は、この「バモイドオキ神」に受け入れてもらうための手土産として、また自分の忠誠心が並外れていることを示すために、神のためならどんなことでも出来るということを行動で示さねばならないという思いを固めていきます。その「どんなことでもやってみせる」という思いの行き着いたはてが、「人を殺す」という、とてつもない難事業だったのです。
しかし、はたして自分に人が殺せるものかどうか分からない。そこで、少年は2人の少女を襲って試してみます。これが、少年の言う「聖なる実験」でした。そして、自分にはできるという確信を得た。そこで、本番にとりかかった。それが「聖なる儀式」だったわけです。
あまりに暗い話ですので、気が滅入ってしまわれたかもしれません。また、こんな極端な気違いじみた話から、何を学ぶことがあるのかと思われたかもしれません。ですが、ここには、現代社会の根底に横たわっている最も重要な問題が暗示されているように思います。これから、その問題について、少しづつ考えていきたいと思います。
さて、現代社会は子供たちにとって、非常に生きにくい社会です。子供たちにとって、将来に希望を持てない条件が揃っているようにも思えます。親は、口を開けば、「もっと勉強しろ、いい学校に入って、いい会社に入れ」と言いますが、いい学校に入って、いい会社に入れば、幸せになれるのかといえば、とてもそうは思えない現実が社会には満ち満ちています。
一流大学を出たはずの、企業のトップや政治家たちが何をやっているか、新聞やテレビで、よくご存じのことでしょうから、改めて申しあげることはいたしませんが、子供たちも、そういう大人の世界の現実をよく知っているのですね。私たち大人は、どこか惰性で生きているところがありますが、子供は、社会の問題に敏感に反応しているのです。
大人になっても何もいいことはなさそうだ。大人になっても、どうせつまらない人生しか待っていないんだ。でも、どうしていいか分からない。そういうストレスを一時的な刺激のなかで紛らわせようとしている子供たちの口から、共通して出てくる言葉が、「ムカツク、キレル、ダルイ」です。
子供たちは本当にダルイようでして、あちこちで地べたに座り込んでいる姿を見かけます。ああいう子供たちをジベタリアンと言うのだそうですが、何だかとても悲しい言葉に思えます。
しかし、私たちの社会をよく見てみれば、生きるエネルギーが枯渇して、疲労感に苛まれているのは、子供たちばかりではありません。多くの大人たちも、同じように、生きていくエネルギーを無くして苦しんでいるのではないでしょうか。
ある学者は、こう言っています。「多くの人々が生きるエネルギーを枯渇させて、理由なき疲労感を訴え始めている。その背景には、ただ同じことがくり返される日々の中で、『どうせ何をしても無駄』『何のために毎日を生きているのかわからない』という、深い〈むなしさ〉の感覚がある」と。
確かに、そうだろうと思います。昨日も今日も、同じように過ぎていっただけで、何のために生きているのか分からない。何が不満なんだと言われても、よく分からないけれど、何をしていても生きているという実感がない。何か、虚しくて仕方がない。いかがですか。ご自身を振り返ってお考えになってみて、何か思い当たることはないでしょうか。
現代の社会を覆っている、こういう捕まえどころのない、それでいて確実に生きるエネルギーを蝕んでいくような「虚しさ」の感覚は、一体どこから生まれてくるのでしょうか。それは、よく言われるように、「人生の目標を失ったから」でしょうか。それとも、「夢を無くしたから」でしょうか。私は、そうは思いません。私は、「物語を失ったからだ」と思います。突然「物語を失った」などと言っても、お分かり頂けないかと思いますが、それは、たとえば、こういうことです。
以前、ある大手の企業が、定年退職者は平均して数年しか生きていないと知って、驚きました。これは大変だと、あわてて中堅幹部を集めて、定年後の一週間の生活予定表を書かせてみたのです。すると、ほとんどの人が、朝起きて、新聞を読んで、テレビを見ると書いたところで詰まってしまって、あと何も書けなかったというのです。
実際、多くの定年退職者が、肩書きとともに、人とのつながりや自分の居場所もなくして、孤独感や虚しさのなかで、どうしてよいのか分からず、戸惑っていると言われています。どうしてそんなことになるのかと言えば、それは、ほとんどの人に、定年後の生活を支える「物語」が無いからです。
ですが、こう申しましても、「そんな馬鹿なことはない。それなら新たに人生の目標を設定すればよい、夢を持てばよいので、物語など関係ない」とお考えになるかもしれません。しかし、そうではありません。夢や目標を置くにしても、その夢や目標を置く場所、つまり、その夢や目標を支えてくれるものが必要です。その夢や目標を支えてくれるものが、今言っております「物語」なのです。
私たち人類は、いつの時代でも、「物語」に支えられて、目標を立て、夢を描いて生きてきたのです。たとえば、ご存じのように、戦前の日本には、天皇を中心とした皇国神話がありました。日本は、天皇のもとに、大東亜共栄圏の建設から、ひいては万国を統合し、世界を幸せにする役目を担っているという、いわゆる「八紘一宇」の「物語」です。
国民は天皇の赤子として生まれてきて、国家のために有用な人材となり、国家のために死ねば、靖国神社に祭られて神様になる。国民一人一人の夢も目標も、みなこの「物語」に支えられていたのです。
ですが、敗戦によって、この「物語」は、一部の権力者のエゴによって作られ、日本という小さな島国でだけ通用していた、偽りの「物語」だということが分かった。つまり、人類全体を支える真実の「物語」ではなかったということが分かったのです。この時から、日本人は、生きるよすがとなる「物語」を無くしてしまいました。
その時から、日本人は心の底では、いつも「物語」を無くした不安を感じていたのです。ですが、戦後は「腹一杯食べたい」という切実な欲求がありましたし、その後は、バブルがはじけるまで、経済はどこまでも成長するという幻想に目が眩んで、その不安がなかなか意識の表面にまで浮かび上がってこなかったのですね。
ですが、今は違います。バブルの夢がはじけて寝ぼけ眼をこすってみれば、日本はとっくに「物語」を無くして、むちゃくちゃになっている。夢のなかでは、しっかりした大地に立っていたはずなのに、足もとを見れば何も無いことに気づいた。そして、心の底でくすぶっていた不安が一挙に燃え上がってきたのです。
しかし、世界を眺めてみれば、「物語」を無くしているのは日本だけではなかったのですね。アメリカは、民主主義を核にしたアメリカン・ドリームという「物語」をベトナム戦争のなかで無くしてしまいましたし、ソビエト連邦は、共産主義を核にした、みんなが幸せになるはずだった「物語」を、連邦の崩壊とともに無くしてしまいました。結局、歴史が教えてくれたのは、どの「物語」も、大国のエゴの「物語」に過ぎなかったということです。
生きるよすがとなる「物語」を無くしてしまった現代は、先行き不透明な時代ではありません。それどころか、どこまでも透明で、どこまで見渡しても何も確かなものが見えてこない時代です。透明な不安のなかに漂う社会。神戸の小学生殺害事件は、そんな社会のなかで起こったのですね。
社会に「物語」が無かったのですから、社会のなかに浮かんでいる少年の家庭にも「物語」は無かったでしょう。少年は、理屈では説明できなくとも、そのことを肌で感じていたに違いありません。
現実世界に絶望していた少年は、生きる手がかり、生きる力を求めて、心の奥底を探りました。少年が、無意識のうちに求めていたのも、生きるよすがとなる「物語」でした。ですが、出会ったのは、沢山の心の傷から生まれた憎悪と復讐の「物語」、「バモイドオキ神」の物語だったのです。少年は、いわば信者一人だけのカルト教団を作ったのです。
カルト教団といえば、オウム真理教もそうですね。オウム真理教に集まった沢山の優秀な学生たちも、無意識のうちに、生きるよすがとなる「物語」を求めていたのです。日々の生活や研究のなかで、自分は一体何をしているのか分からないという「虚しさ」を感じていた若者たちには、オウムがその「物語」を与えてくれるように思えたのでしょうね。
現代は、かりそめのエゴの「物語」が全て壊れて、生きていることの不安が露になった時代です。そんな現代が必要としているのは、本当の「物語」なのです。こんどの神戸の事件が、私たちに教えてくれているのは、そのことです。
これまで私たちは、「エゴの物語」を生きてきました。ですが、エゴは私たちの「いのち」の本質ではありません。私たちの「いのち」の本質は「一如」にあるのです。私たちにとって本当に大切なのは「エゴの物語」ではなく「一如の物語」なのです。
では、その「一如の物語」について、少しお話ししたいと思います。ここからが、ようやく仏教の話でございます。どうぞ、こちらの図をご覧になってみてください。これは、もうすっかりお馴染みになりました、唯識仏教の心のモデルを簡単にしたものです。この小山のように盛り上がっているのが、私たちの「いのち」の全体像です。
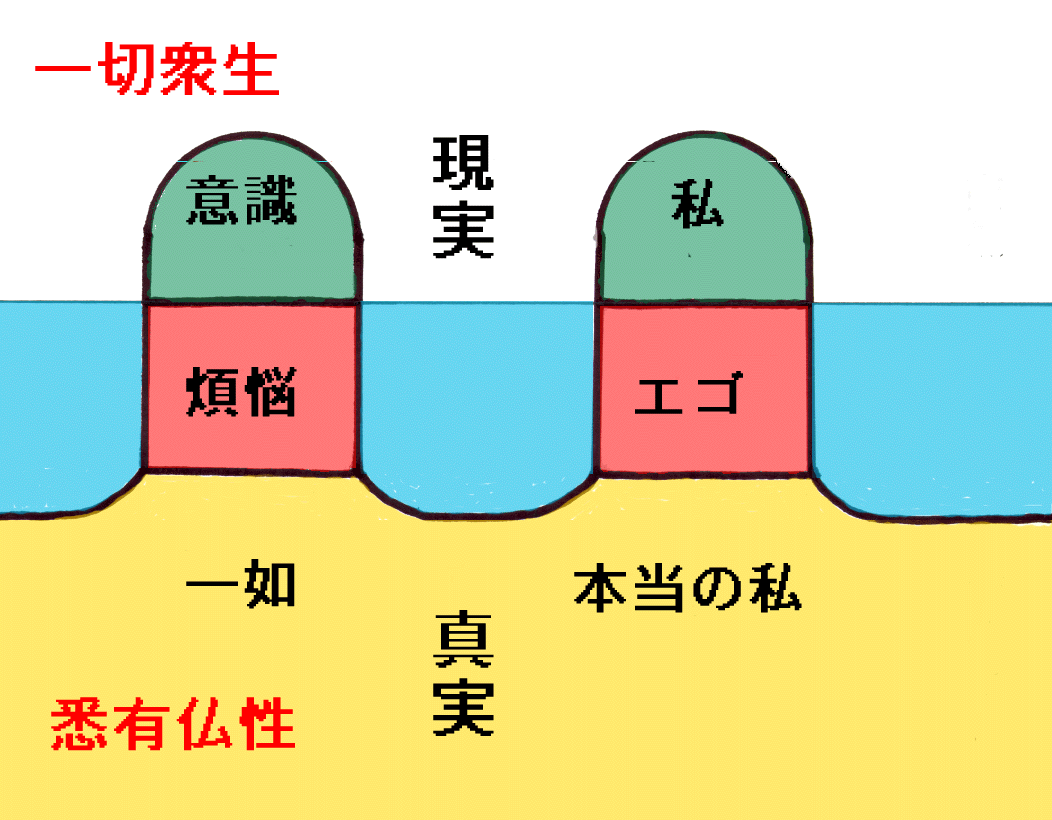 大きく、三つに分かれていますが、一番上が「意識」、二番目が「煩悩」つまり「エゴ」ですね、そして一番下が「一如」です。私たち門徒が「法蔵菩薩」とか「阿弥陀如来」と呼んでおりますのも、この「一如」のことです。前回の話で申しますと、「一如」とは、「本当の自分」のことです。
大きく、三つに分かれていますが、一番上が「意識」、二番目が「煩悩」つまり「エゴ」ですね、そして一番下が「一如」です。私たち門徒が「法蔵菩薩」とか「阿弥陀如来」と呼んでおりますのも、この「一如」のことです。前回の話で申しますと、「一如」とは、「本当の自分」のことです。
私たちはたいてい、この「意識」と「エゴ」の部分だけしか知らずに生きております。ですが、本当は、その下に「一如」の世界がある。私たちはみんな、この「一如」の世界に支えられている。そのことを教えてくれているのが「一如の物語」なのです。
この一番上にある、私たちの「意識」というのは、ちょうど海に浮かんでいる島のようなものです。ですが、本当は、島は海に浮かんでいるわけではありません。たとえば、四国であれ、九州であれ、ハワイであれ、ちゃんと海の底で地球とつながっていて、他の島ともつながっているのですね。
ですが、島がみんなつながっているということは、海に潜ってみないと分かりません。私たちの「いのち」もそうです。「いのち」の奥底を究めた人たちが、私たちの「いのち」の本当の姿を伝えてくださった。みんな「ひとつ」だと伝えてくださった。「一切衆生悉有仏性」と伝えて下さった。それが「一如の物語」、「仏法」なのです。
「一如の物語」は、「物語」と言っても、夢物語でもフィクションでもありません。今も申しましたように、「いのち」の奥底を究めた人たちが、私たちの「いのち」の本当の姿を伝えてくださっているノンフィクションです。いわば、「一如の物語」は、真実世界の旅行記であり、真実世界へのガイドブックなのです。そのガイドブックの最初に書いてあるのが、「一切衆生悉有仏性」という言葉です。
今日は、いろいろお話しいたしておりますが、どうぞこの「一切衆生悉有仏性」という言葉だけでも憶えて帰って頂きたいと思います。目に見える姿形は違うけれど、私もあなたも、草も木も、犬も猫も、みんな仏様に支えられている。みんな、「いのち」の深いところでは「ひとつ」なのだ。みんな「仏様」なのだということです。それが「一切衆生悉有仏性」という言葉の意味です。
目に見える世界が全てだと考えてきた現代人は、そのことを忘れているのですが、私たちが日常意識している目に見える世界は、目に見えない世界に支えられているのです。そして、「いのち」の深いところで、みんなつながって「ひとつ」になっているのです。
私たちは「ひとつ」です。「ひとつ」ですけれど、目に見える現実世界では、みんな違っていますね。姿形も能力も環境も、みんな違います。ですがそれは、互いに比べあい、競いあうためではないのです。互いに学びあい、助け合うためなのです。
いつも申し上げますように、みんながピッチャーだったら野球はできません。みんなが違っているのは、その違っていることで、互いに学びあい、助け合うためなのです。私たちは、そのためにこそ、同じ時代に生まれてきたのです。その学び合い、助け合うための出会いを、仏教では「縁」と言います。
親子の縁もそうですね。私たちは、互いに学びあい、助け合う「縁」があればこそ、この親はこの子を授かり、この子はこの親を授かっているのです。別の言葉で言えば、子供は親を選んで生まれてくるのです。その親からしか学べないことがあるから、その親のもとに生まれてくるのです。親もそうです。その子からしか学べないことがあるから、その子を授かるのです。
ですが、「エゴの物語」のなかで育った現代の私たちは、そうは考えていませんね。子供は親が作るのであって、子供の人格形成は遺伝と環境によって決まると考えています。子供は白紙の心を持って生まれてくるから、親は自分が何もかも書き込まねばならないと考えているのです。
しかし、子供は親を通してやってくるのでして、決して親が作るわけではありません。子供には子供の魂がある。子供の魂は親が作ったものではない。子供には自前の魂があり、その魂は宿業を持っているのです。その宿業が、遺伝と環境を選んで生まれてくるのです。
宿業というのは運命ではありません。宿業とは、生まれ変わり死に変わりしている間に、魂に蓄積された経験の総和のことです。宿業は、自由意志を否定するものではありません。
宿業と自由意志の関係を、もう少し詳しく申しますと、たとえば、こういうことです。ビールを飲んで気分がいいという経験を重ねてきた人がいるとしますね。その人が、仕事から帰ってきて、目の前に冷たいビールと水が置かれていたら、どちらを取るでしょう。きっと、ビールの方に手を伸ばすでしょうね。その人は、自分の自由意志でビールを取ったのです。ですが、それなら水を選ぶこともできたのか、と言えば、そうではないでしょう。それまでの経験から、ビール以外に選ぶ道はなかった。違いますかね。宿業というのは、そういうふうに過去に蓄積された経験をいうのです。
子供は自分の意志で両親を選んで生まれてきます。ですがそれなら、他の親でも選べたのかといえば、そうではない。その子供は、その親を選ぶ必然を持っていた。親もそうです。宿業のなかで、その子を授かる必然を持っていたのですね。
そういう必然に導かれて出会った親と子が、「一如の物語」のなかで、互いの宿業に触れて気づいていく。そこに、「一如」へと続く道が開かれてくるのです。親子の縁は「一如」への縁です。つまり「仏縁」なのです。
親子の縁だけではありません。人の縁は、みな「仏縁」なのです。昔の人は、「袖触れ合うも多生の縁」と言いましたが、人の出会いはみな「仏縁」なのです。ですが、そこに「一如の物語」が無いと、宿業の出会いは、宿業のぶつかりあいに終わってしまうのですね。
神戸の少年の母親は、少年に非常に厳しい人だったと聞きますが、子供を支配するという親子関係は「エゴの物語」から生まれてくるものです。もしも、少年の家庭に「一如の物語」があったなら、そして、この子には、この子の仕事があるのだと気づいていたら、おそらく、あんな結果にはならなかったでしょう。親は子供の運命を支配する人間ではなく、親と子は、互いに学びあって、泣いたり笑ったりできる、「一如」への旅仲間になれただろうと思うのですね。
たしかに、世の中には、完全な親もいなければ、完全な家庭もありません。みんな、傷つきながら育っていくのです。ですが、「エゴの物語」のなかで傷ついていくと、だんだん心の殻が厚くなっていきます。たとえば、手の皮膚の破れたあとがマメになっていくように、心の殻はだんだん厚くなっていくのです。エゴどうしのぶつかりあう世界では、そうしなければ生きていけないのですね。
心の殻が厚くなると、さまざまな出来事や、人の感情で傷つくことは少なくなります。ですが、それと同時に、日々の暮らしのなかで喜びを感じることにも、人の悲しみや苦しみを感じることにも、鈍くなっていくのです。わが子の「いのち」の輝きにさえも、またその悲しみや苦しみにさえも、鈍感になっていくのです。それは、少年の母親だけの問題ではありません。私たちみんなの問題でもあるのですね。
 もちろん、「一如の物語」のなかで生きておりましても、つまり「信心」を持っておりましても、悲しいことや辛いことがなくなるわけではありません。悲しいことや辛いことで、心が傷つくことはいくらでもあります。ですが、その傷の痛みは、「物語」を通して「一如」に吸収されてしまい、その痛みの経験さえも生きるエネルギーになっていくのです。
もちろん、「一如の物語」のなかで生きておりましても、つまり「信心」を持っておりましても、悲しいことや辛いことがなくなるわけではありません。悲しいことや辛いことで、心が傷つくことはいくらでもあります。ですが、その傷の痛みは、「物語」を通して「一如」に吸収されてしまい、その痛みの経験さえも生きるエネルギーになっていくのです。
実際、生きているあいだには、辛いことも悲しいこともありますね。たとえば、大切な人に先立たれるということもあるでしょう。そのとき、「一如の物語」は教えてくれるのです。「死ぬというのは無になることではない。死んだ人は、目に見える世界での姿や形を無くしただけだ。私たちは『いのち』の深いところで、みんなつながっていて、あなたの亡くした愛しい人は、今もあなたとつながっている」と。
その「いのち」の真実につながる「物語」に支えられて、私たちは悲しみから立ち直り、生きる力を取り戻していくのです。ですが、少年には、可愛がってくれたオバアチャンが亡くなったとき、その悲しみを支えてくれる「物語」が無かったのです。
また、少年が「一如の物語」のなかで育っていたら、たとえ、心の奥底をのぞき込むようなことがあったとしても、エゴの怪物に捕まるようなことはなかったと思うのですね。
「物語」を無くしていると、平凡な日々の生活から、「生きているという実感」が得られません。しかし、「生きているという実感」が欲しいのは、誰でも同じです。そこで、人は、無意識のうちに、スリルや、強烈な刺激、あるいは命懸けの状況を求めるようになっていきます。
たとえば、バイクで暴走したり、非行に走ったり、麻薬に溺れたりするのもそうです。また、ホラー映画や、エログロ映画、暴力映画が好まれるのも、強烈なハードロック音楽が好まれるのも、みな同じ理由からだと思います。
たとえば、ホラー映画を見れば、恐怖で身体中をアドレナリンというホルモンが駆けめぐります。その強烈な生理的反応から、「生きているという手応え」を得ようとするわけです。少年がホラー映画を好んだのも、そうだったのではないかと思います。そして、そういう方向で行き着いたはてが、殺人だったのです。
しかし、少年が殺人に走った理由は、それだけではありません。「いのち」の真実につながる「物語」を無くした社会では、なぜ人を殺してはいけないのかが分からなくなっているのです。現代の社会がそうですね。たとえば、いわゆる反抗期に入ったような子供から、突然、「どうして人を殺してはいけないのか」と聞かれたら、私たち親は何と応えるでしょうか。
おそらく、びっくりしてしまって、「何という恐ろしいことを言うのだ。そんなことも分からんのか。馬鹿もん」と怒鳴ってはみたものの、冷静になって考えてみれば、そういう自分だって、「警察につかまるから」といった程度の答えしか思いつかないことに、気がつくのではないでしょうか。少年法を厳しくすればよいという発想が生まれてくるのも、そういう社会だからです。
そんな私たちは、「一如の物語」に耳をすまさねばなりません。「一如の物語」は、教えてくれます。「私たちはみな、生まれ変わり、死に変わりしながら、本当の自分になろうとしている仲間なんだ。『一如』の世界をめざしている同行なんだ。本当の自分には、私もあなたもない。本当の私は、本当のあなたなのだ。あなたを傷つけることは、私を傷つけることなのだ」と。だからこそ、人は人を殺してはいけないのです。
私たちにとって大切なのは「一如の物語」を学ぶことです。「一如の物語」を学ぶ、それは私たち門徒の言葉で言えば、「名号のいわれを聞く」ということです。「名号」とは「南無阿弥陀仏」のことです。
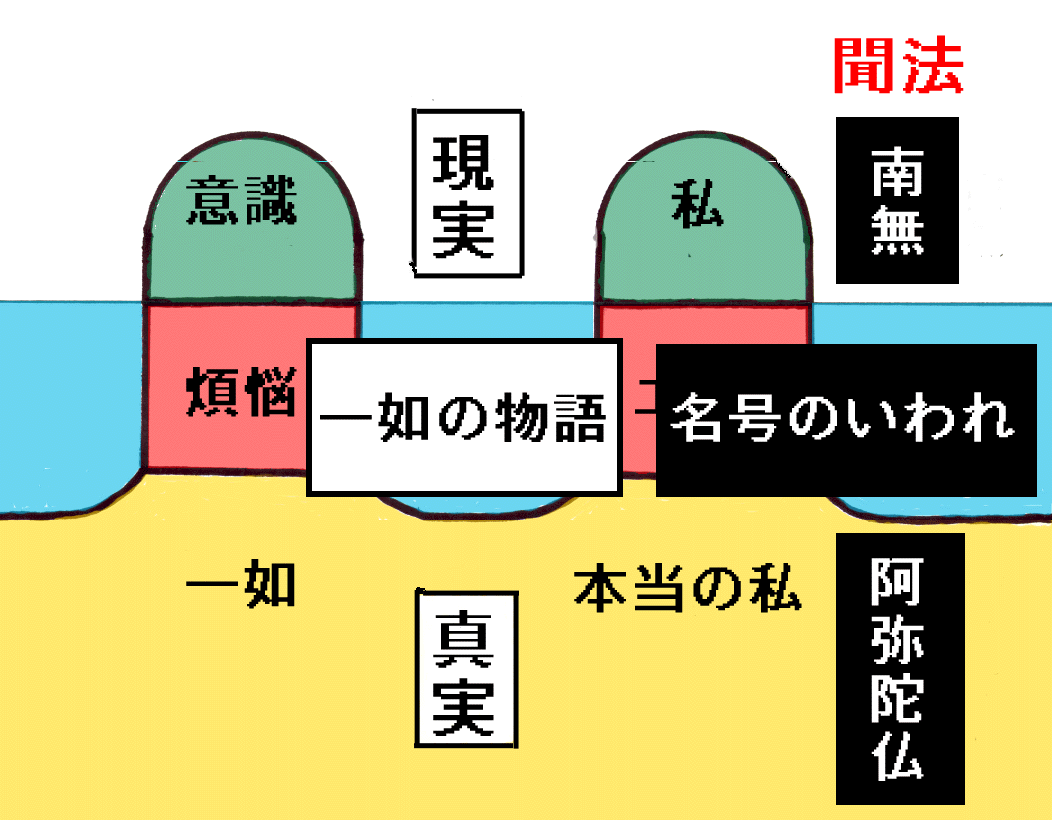 こちらの図で申しますと、「南無」とは私たちの現実のことです。また、「阿弥陀仏」とは「いのち」の真実のこと、「本当の自分」のことです。この現実と真実をつなぐ「物語」、それが「名号のいわれ」です。そして、その「名号のいわれ」を聞くことが、聞法なのです。
こちらの図で申しますと、「南無」とは私たちの現実のことです。また、「阿弥陀仏」とは「いのち」の真実のこと、「本当の自分」のことです。この現実と真実をつなぐ「物語」、それが「名号のいわれ」です。そして、その「名号のいわれ」を聞くことが、聞法なのです。
私たちの心の殻は厚くなりすぎて、自分を閉じ込め、窒息しそうになっています。そんな私たちにこそ、聞法が必要なのです。聞法を重ねて、「一如」に向かって心が開くようになれば、必ず生きるエネルギーが「一如」から流れ込んでくるようになります。
聞法とは、「私」と「本当の私」をつなぐ架け橋です。私たちは、聞法によって世間的に立派な人間になろうとしているわけではありません。そうではなくて、「本当の自分」に気づき、「本当の自分」になっていこうとしているのです。私が私になっていく。それは、私が、世界と「ひとつ」になっていくということです。ですから、「私」が「本当の私」とつながったとき、私が変わり、世界が変わるのです。
たしかに、私たちには、なかなか直接「一如」を体験することはできません。ですが、「一如の物語」に親しんでいると、日常生活での経験が、「物語」を介して「一如」と共鳴を起こすようになります。そして、その共鳴によって、私たちは、「ああ、いま生きている」という無上の喜びを実感するようになるのです。
たとえば、夏の炎天下で仕事をしているときに、爽やかな風が吹いてきたとしますね。仕事の目標やノルマのことしか心にない人なら、風に気づかないかもしれませんし、気づいても、「ああ、気持ちがいい」というだけかもしれません。
ですが、「一如の物語」「仏法」に親しんで育った人には、爽やかな風を受けたという、そんな日常的な経験でさえ、一如と共鳴を起こし、「ああ、いま生きている、生かされている」という無上の喜びを呼び起こすことがあるのです。「極楽の余り風」という言葉がありますが、それはそういう実感から生まれた言葉だと思います。
人生にとって大切なのは、イデオロギーでも経済効率でもありません。人生にとって本当に大切なのは、なんでもない日々の生活のなかで、「ああ、自分はいま生きている」という実感と結びついた、無上の喜びを経験することでしょう。私たちは、そういう「いのち」の実感から、生きるエネルギーを得るのですね。
私たちの社会が生きるエネルギーを無くしているのは、私たちが本当の「物語」を無くしているからです。私たちは本当の「物語」を取り戻さねばなりません。
本当の「物語」とは、現実と真実をつなぎ、私たちの日々の生活に「いのち」を吹き込んでくれる「物語」のことです。それは、「いのち」の真実を伝えてくれる「まことの教え」、つまり、本当の意味での宗教なのです。
私たちの多くは、心の底では、そのことに薄々気づいています。ですから、需要と供給の関係で、雨後のタケノコのように沢山の宗教モドキが生まれてくるのです。また、倫理や道徳の必要を説く人や、生き甲斐論を説く人も出てくるのです。
ですが、エゴの世界の約束事である倫理や道徳からは、本当の救いは得られません。「感謝しろ、仲良くしろ」と言ってみても、自分の心が変わらなければ口先だけに終わってしまいます。「健康が大切、生き甲斐が大事」と言っても、身体が動かなくなってしまえば、それが一体何になるというのでしょうか。
本当の宗教とは、生命の全体像を伝えるヴィジョンです。それは、私たち一人一人の、生まれる前から死んだ後までの、全ての時間をカバーし、全宇宙の空間をカバーして、生命の全体像を伝えるヴィジョンです。
そのヴィジョンのなかで、あたかもサナギから蝶になるように、現実の世界から真実の世界に生まれ変わる。「私」が「本当の私」になる。宗教の言葉で言えば、それは「回心」です。この回心のない宗教は、本当の宗教ではありません。
生命の全体像を伝えるヴィジョンを持ち、私たちを「回心」に導いてくれる宗教。私は、仏教こそ、それだと考えております。と申しましても、それは、現在見られるような、宗派意識で凝り固まった仏教のことではありません。宗派のなかでの先祖供養や御利益祈願にあけくれる気休め仏教ではなく、一人一人の回心をめざす本当の仏教のことです。
私たちに必要なのは、本当の仏教なのです。しかし、そのことに気づいている人は、ごくわずかですから、本当の仏教は、残念ながら、まだ育ってきていません。ですが、そういう時代であればこそ、「一如の物語」「名号のいわれ」を聞く「聞法の場」として、寺というものが、いっそう大切になったと、私は思っております。
私たちは、本当の「物語」を無くしている。そのことを、神戸の少年たちは、全ての命をつないでいる「一如」という、「いのちの絆」を通じて、私たちに伝えてくれたのです。殺された子供たちも、私たちに、そのことを伝えるために死んでいったのです。命をかけて、私たちが気づくための「ご縁」となったのです。私たちは、その「ご縁」を、ちゃんと「仏縁」として受け取らねばなりません。本日お話し申し上げたかったことは、そのことでございます。
本日の話は、ここまででございますが、今回は、教育の問題とか、家族の問題とか、夫婦の問題とかいった、私たちの日常の問題に、具体的には触れることができませんでした。そこで、次回は、そういった問題をも含めまして、「名号のいわれ」を改めてご一緒に聞いていきたいと思っております。
ご縁がありましたら、次回もまたお運び頂きまして、ご一緒に聞法させて頂きたいと存じております。本日は、長い間お付き合いくださいまして、有り難うございました。
紫雲寺HPへ