と申しますのも、昨年末に、こんなことがございました。たしか、12月28日だったと思いますが、庭掃除を終えて、外の石段を洗っておりますと、「こんにちは」と声がする。振り向いて見ますと、四〜五歳くらいの女の子が、三つか四つの弟の手を引いて立っている。
「こんにちは」と答えると、弟の方が、「ここ、神社?」と聞くのです。「神社ではないよ、お寺だよ」と答えると、「ふーん」と首を傾げている。お姉ちゃんが、「お寺だって」と教えるのですが、もうひとつ腑に落ちなかったのでしょうね。今度は、「神様、いる?」と聞いてくるのです。
「神様はいないよ」と答えると、また、「ふーん」と首も傾げている。そこで、お姉ちゃんが、「神様は、いないんだって。仏様だよ」と教えている。すると今度は、「仏様、いる?」と聞いてくるのです。実は、私はここで、言葉に詰まったのです。ですが、「仏様、いるよ」と答えた。
すると二人は、「ふーん、仏様、いるのか」と言うと、向かいのお地蔵様のところに走って行って、手を合わせると、大きな声でお願い事を始めたのです。「お父さんが、死にませんように。お姉ちゃんが、死にませんように。ボクが、死にませんように」。
それを聞いて、正直、驚いたのですが、思い当たることがありました。最近、この近くで、小さな子供二人を残して亡くなったお母さんがいると聞いていたのですが、この子たちが、そうだったのかと。
考え込んでしまいましたね。というのは、子供たちの問いかけに、何も答えられなかった自分に気づいたからです。実際、思いました。「神様、いないよ」「仏様、いるよ」はないだろう、と思いましたね。
では、何と答えればよかったのか。いろいろ考えてみるのですが、浮かんで来るのは理屈っぽい話ばかりです。思えば、今まで、理屈っぽい話ばかりしてきたわけでして、本当は、何も分かっていない自分がいるのです。そのことを、改めて、子供たちに教えられたような気がしております。
子供たちに何と答えればよかったのか、今も分からないまま、またぞろ理屈っぽい話をしようとしております。遠路お運びを頂きました皆様の前に立って、何とも頼りない話でございますが、どうぞしばらくの間おつき合いをお願い申し上げます。
さて、私たちの人生は、わずか数十年ですが、そんな短い間にも、次から次ぎへと問題が起こってきますね。親子、兄弟、親戚や同僚、といった様々な人間関係の問題に、経済的な問題、健康や生き甲斐の問題というように、問題の種がなくなることはない。ふと立ち止まって考えてみれば、生きるというのは悩みや苦しみの連続のようにさえ思えてくるのですね。
そんな人生のなかで、深刻な問題に直面し、闇のなかでもがき続けて万策尽きると、それこそ藁にもすがる思いで、普段は認めてもいない神や仏に頼りたくもなるのです。そして、「仏教なら、こんなときどう考えるのだろう。そんなときには、こうしろと、はっきり教えてくれないものか」と、寺の門をたたく人もでてくるわけですが、なかなか即効性のある答えはないものです。
10年ほど前のことですが、ある大学の先生から、こんな質問を受けたことがありました。「実は、ちょっとお尋ねしたいことがあります。昭和54年に三菱銀行北畠支店に猟銃強盗が入ったとき、犯人に強要されて同僚の耳を切り落とした人がいましたよね。状況から考えれば仕方がなかったとはいえ、耳を切られた人は、切った同僚を許せないと思うのですが、こんな問題を仏教ではどう考えますか」という質問でした。
これは質問をした人自身の問題ではありません。ご自身が耳を切られたわけでも何でもないのです。ですが、何か似たような問題に苦しんでおられたのでしょうね。ただ、私は、この質問に答えられませんでした。
答えが無かったわけではありません。答えならあるのです。ご承知のように、仏典には、「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない。怨みを捨ててこそ息む。これは永遠の真理である」と書かれています。ですが、質問した人は、こんな答えを聞きたかったわけではないでしょう。
「怨みは、怨みを捨ててこそ息む」。有名な言葉です。そんな答えなら、10年前の若い坊さんでも知っていましたし、質問した人も知っていたに違いありません。ですが、怨みを捨てればよいといっても、捨てられない自分がいる。人が本当に苦しんでいるのは、この点でしょう。
どんな問題にも、善悪を基準にした道徳的な答えや、倫理的な答えならあるのかもしれません。ですが、そんな答えをいくら聞いても、苦しみは無くならないのです。善だと知ってもできない自分がいる。悪だと知ってもやってしまう自分がいるのです。私たちが、誠実に生きよう、真剣に生きようとすればするほど、問題になってくるのは、このことではないでしょうか。
私たちは、善だと知ってもできないことがあり、悪だと知ってもやめられないことがある。それは、意志が強いとか弱いとかいった問題ではありません。悪事を為すにも、結構強い意志がいるものです。そうではなくて、私たちのなかに、私たちの自由な意志の働きを妨げているものがある。それを仏教では「煩悩」と「宿業」と言います。
宗教的な伝統を切り捨ててきた私たち現代人には、「煩悩」とか「宿業」なとど言ってみても、ただの言葉のように思われるかもしれませんが、実は、この「煩悩」と宿業」こそ、私たちが人生を受け入れ、救われていく「鍵」になるものなのです。
そこで、前回は、「名号のいわれ」を手がかりにお話しいたしたが、今回は、この「煩悩」と「宿業」というものを手がかりに、私たちの救われて行く道について、ご一緒に考えてみたいと思います。
さて、私たちは、科学万能の時代の流れのなかで、宗教的な伝統を切り捨ててきました。これは、どなたもご承知のことと思います。宗教的な伝統を切り捨てた私たちには、神も仏もない。その結果、私たちに残ったのは、「他の誰よりも自分が可愛い」という思いだけでした。
この、「他の誰よりも自分が可愛い」という心の働きを、仏教では「煩悩」と呼んでいます。現代の言葉で言えば、「煩悩」とは「エゴ」のことです。私たちの心は、この「エゴ」に支配されていて、そこからいろんな問題が生まれてくるのですが、私たちは、なかなかそのことに気づけません。
実際、自分の「エゴ」というものは、なかなか見えないものですね。たとえばですね、子供の躾けでも教育でもそうですね。お考えになってみてくださいね。子供の躾けや教育で、私たち親が、何に一番苦しむかと言えば、結局は「子供が自分の思うようにならない」ということではないでしょうか。
私も親ですから、決して他人ごとではないのですが、「自分の思うようにならない」という悩みの裏には、「自分の思うようにしたい」という心があるわけですね。ところが、「自分の思うようにしたい」というのは、たいてい「自分の都合の良いようにしたい」ということなのです。
考えてみれば、私たちは、自分は変わらずに、自分の都合の良いように他人を変えようとやっきになって、思い通りにならなくて苦しんでいるわけですね。
「自分の都合」というのは、自分の「エゴ」なのですが、私たちは、自分の心を問題とする伝統を切り捨ててきたものですから、他人の「エゴ」は見えても、自分の「エゴ」は、なかなか見えないものなのですね。
自分の「エゴ」が見えるということは、非常に大切なことです。ですが、本当は、「エゴ」が見えただけでは、何にもならないのです。どういうことかと申しますとね、たとえば、痴呆症になったお姑さんの世話をしているお嫁さんがいるとしますね。お嫁さんは、一生懸命に世話はしているものの、内心は嫌だ嫌だと思っている。だれでも、そうだと思いますがね。
ですが、嫌だ嫌だと思っている自分は「エゴ」なんだと気づいて、これではいけないと、さらに熱心に世話をしたとしますね。お姑さんが心の優しい人で、頭がはっきりしていたなら、「すまないね、有り難うね」と感謝のひとつもされるでしょうから、まだ救われるものがある。
ところが、相手は痴呆症なのですから、何にも分からない。財布を盗ったとか、ご飯を食べさせてくれないとか、人を困らせるようなことばかり言っている。するとですね、我慢しても我慢しても、何にも報われない。我慢すれば我慢するほど、苦しくなる。結局は、お姑さんが亡くなるまで、お嫁さんは楽にならない。そうでしょう。自分の「エゴ」が見えただけでは何にもならないというのは、そういうことです。
我慢、我慢と、自分の「エゴ」を抑えようというのは、倫理や道徳の教えです。実際、「自分さえ我慢すれば、丸く治まる」というような、世間的な知恵では、私たちは救われないのですね。
「煩悩の犬、追えども去らず」という言葉がありますが、「煩悩」は、抑えても抑えても無くならない。「エゴ」は無くならないのです。どうしてかと申しますと、「煩悩」は手のひらに着いているゴミのように、払えば落ちるという、柔なものではないからです。
そうではなくて、私たちに時折かいま見える「煩悩」というものは、柱に打ち込んだ釘の頭のようなものでして、目に見えない部分が、柱のなかにしっかり食い込んでいるのです。この、柱のなかにしっかり食い込んでいる部分を「宿業」と言います。
昔は、何かあると「業が深い」とか「業が湧く」とか言いまして、「業」という言葉を日常よく使いましたが、最近は、「業」という言葉も知らないという方が多くなってまいりました。先日も、若い人に「ゴウというのを知っているか」と聞きましたら、「歌手の名前か」と言われてしまいました。
無理もないのですね。若い人だけではありませんはね。お歳をめした方でも、たいてい「業」などというものは、思い出すこともなくなりましたね。日常的に「業」が話題になるようなら、今のような世界には成っていませんものね。
仏教で「業」というのは、歌手の名前ではなくて、「煩悩の働き」のことを言います。「煩悩」に支配されている私たちが、日常生活のなかで、考えたり、したりすること、その全てが「業」なのです。
では、「宿業」とは何かと申しますと、「宿業」とは「前世の業」のことを言います。「宿業」の「宿」とは「前世」のことです。私たちは、生まれ変わり死に変わりして、輪廻転生を繰り返している。そのたくさんの人生のなかで積み重ねてきた「業」が「宿業」なのです。
別の言葉で申しますと、「宿業」というのは、「煩悩の歴史」のことです。例によって図でご説明いたしますと、それは、こういうことです。ちょっと、こちらの図をご覧になってください。
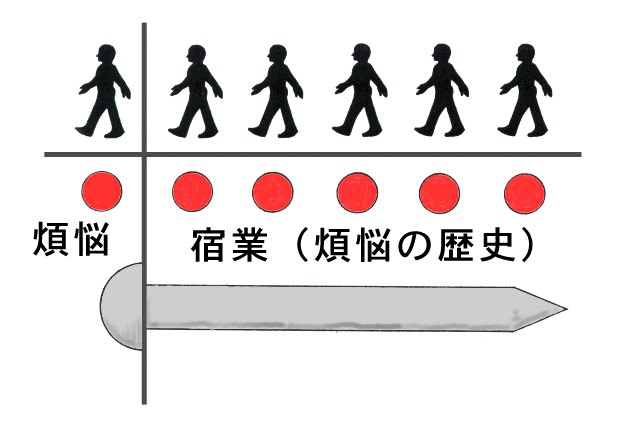 上の段に、何人かの人の絵が、一列に描いてありますね。この一番左の人が、たとえば、現在の「私」です。その後ろに並んでいるのは、過去の私、「前世」の私です。また、人物の絵の下に、一列に並んでいる「丸いもの」は、私の「煩悩」です。
上の段に、何人かの人の絵が、一列に描いてありますね。この一番左の人が、たとえば、現在の「私」です。その後ろに並んでいるのは、過去の私、「前世」の私です。また、人物の絵の下に、一列に並んでいる「丸いもの」は、私の「煩悩」です。
現在の私は「煩悩」に支配されています。ですが、同じように前世の私も「煩悩」に支配されていたのです。「煩悩」には、この「私」を支配しながら働いてきた長い長い歴史がある。その長い長い「煩悩の歴史」、それが「宿業」なのです。
私たちは、この「宿業」を持って生まれてくるのです。ある意味では、この「宿業」こそ、私たちの「人生そのもの」なのです。私たちは、その「宿業」の上に、様々な人生の出来事を受け止めていくのですね。
目に見える「たとえ」で言えば、この「テーブル」が「宿業」で、この「黒板消し」が人生の上に起こってくる出来事だとしますと、私たちはこの「テーブル」を持って生まれてくるのです。この「テーブル」の上に、様々な「黒板消し」を受け止めていく。それが、私たちの人生の本当の姿なのです。
ところが、私たちは、「死ねば終わりだ」と思っておりますから、当然「前世」など考えられません。ですから、私たちは、子供は、何も持たずに手ぶらで生まれてくると考えています。
つまりは、人生とは、ゼロから出発して、いろいろな出来事に出会い、ひとつづつ経験を積み重ねていくことだと考えているわけです。そして、その経験の積み重ねが「人生そのもの」であって、それ以外には何も無いと考えているのですね。
人生には「黒板消し」しかない。「テーブル」なんかないのだ。それが私たちの考え方です。私たちがいろんな経験を積み重ねながら、なかなか人生が深まっていかない、「人生そのもの」が見えてこない理由は、実は、そこにあるのですね。
「これを、どうするか」「あれを、どうするか」と、私たちは、日常生活のなかで、「人生の上」に起こってくる事柄を処理することばかりに関心があって、なかなか「人生そのもの」が見えてこないのです。
特に、商売がうまくいっているときとか、子供が思い通りに育っているとか、事が、自分の都合の良いように運んでいる時には、なかなか気づけないものなのですね。
さきほどの「たとえ」で言えば、「黒板消し」を、自分の思い通りにスイスイと動かせている時には、「テーブル」との間に摩擦が無いようなものですから、なかなか「テーブル」に思い至るということはないのです。
もちろん、人生には、晴れた日ばかりがあるわけではありません。思うようにならないことも、次々に起こってきます。たとえば、手形が落ちなくて金策がつかないとか、子供がグレ始めたとか、さきほどのお嫁さんのように、生きているのが辛いというような状況も起こってくるわけですね。
「黒板消し」を押しても引いても、にっちもさっちも動かないとか、右に押していきたいのに、どんどん左に動いていくとかいうことが起こってくるのです。本当は、そんな時こそ、「人生そのもの」に気づいていくチャンスなのですが、それでも、たいていは気づけないのです。
そんな場合でも、私たちは、たいてい、「努力が足りないのだ、我慢が足りないのだ」と自分を責めたり、「運が悪いのだ、人生ってこんなもんだ」とあきらめて、やり過ごしてしまうのですね。
そんな私たちには、「人生そのもの」が問題になることは、なかなかありません。しかし、「人生そのもの」が問題になるまで、本当の意味での人生は始まらないのです。そして、その、「人生そのもの」を問題とする心を、宗教心と言うのです。
人生はいつ始まるのか。そう聞かれて、あるイスラム教の牧師は、「子供たちが巣立っていき、飼っていた犬が死んだとき」と答えたそうです。子供を育てていく喜びや悩み、飼い犬が与えてくれる慰めのようなもの。ある意味では、そういったものがあるおかげで、私たちは「人生そのもの」と直面せずに済んでいるのですね。
嬉しいことであれ悲しいことであれ、楽しいことであれ苦しいことであれ、私たちの心を引きつけておく事柄が「人生の上」にある間は、なかなか「人生そのもの」が問題になることはありません。
ですが、では、そういったものが全部無くなれば、「人生そのもの」が問題になってくるかと言えば、たいていは、そうはならないのです。というのはですね、私たち現代人は、さきほどの「たとえ」で言えば、「黒板消し」の下に「テーブル」があるという教育を受けてこなかったからなのです。私たちは、人生には「黒板消し」しか無いと教えられてきたのです。
そういう教育を受けてきたものですから、困ってしまうのです。たとえば、自分は退職し、とりたててしなければならないこともない。それでも、身体が動くあいだは、趣味だ旅行だと、経験を求めて動かせる「黒板消し」が、まだあった。ところが、身体が不自由になってしまうと、もう自分で動かせる「黒板消し」は何もなくなってしまいます。
本当は、そこには剥き出しの「人生そのもの」があり、そこから人生が始まるのですが、そうは教えられていないものですから、何も見えてこない。何も見えてこないものですから、しかたなしに、テレビを見て過ごすことになるのです。
本当は、嬉しいことであれ悲しいことであれ、楽しいことであれ苦しいことであれ、人生の上に起こってくる様々な出来事は、それを通じて「人生そのもの」に気づいていく、「人生そのもの」を問うていくための手がかりとして、私たちに与えられているのです。私たち門徒が、日常の生活を大切にするように教えられているのは、そのためなのです。
さきほども申しましたように、「人生そのもの」とは「宿業」のことですが、「宿業」というのは「前世の業」のことですから、考えてみれば、現在の「私」には直接責任が無いはずなのです。しかし、直接責任は無くとも、影響はあるというのですから、現在の私にとっては、「宿業」というのは、たいそう理不尽なものです。
理不尽なことといえば、たとえば、さきほどのお嫁さんのように、お姑さんが痴呆症になったとか、あるいは、一人っ子が自殺したとか、震災で家族を失ったとかいった、どうして自分がそんな目に遭わねばならないのか分からないという苦しい状況がありますね。
ですが、ここが大切なところですから、よくお聞き頂きたいのですが、そういった理不尽な状況そのものが「宿業」ではないのです。世間では、そういった理不尽な状況を「宿業」だと考えるものですから、「宿業」とは「運命」のことだと誤解してしまうのです。
昔はよく、不幸な境遇の人は前世で悪いことをしたからだとか、その反対に、幸福な境遇の人は前世で良いことをしたからだとか言いましたが、本当は、それが「宿業」ではないのです。
そうではなくて、「なぜ自分がこんな目にあわねばならないのか」とか、「どうしてこんなことが起こるのか」といった、理不尽な状況というのは、「自分の外にある闇」です。それに対して、「宿業」というのは、「自分の内にある闇」なのです。
外にある状況を理不尽だと思っているのは「煩悩」です。つまり、「エゴ」ですね。そんな「エゴ」が、自分にとって都合の悪い状況を、いつまで見続けていても、救いが始まるわけではありません。
本当は、「自分の外にある闇」を手がかりとして、私たちの問題意識が、「自分の内にある闇」にまで深まったとき、そこに救いが始まるのです。そのことを教えて下さっているのが、「浄土の教え」「名号のいわれ」なのです。
私たちは、教えを聞き、お念仏を称え、聞法を重ねる生活のなかで、問題意識が「内にある闇」にまで深められていく。「宿業」にまで深められていく。そこに、ようやく救いが始まるのです。問題意識は自然に深まっていくわけではありません。問題意識が深まっていくためには、闇を照らす「教えの光」が必要なのです。
たとえば、高史明さんという方がおられますね。有名な念仏者ですから、ご存じかもしれませんが、あの方は、一人っ子を亡くされました。男の子でしたが、12歳のときに自殺をしたのです。そのことが高さんを打ち砕いた。高さんは、苦しみ抜いたわけですが、そんななかで、『歎異抄』に出会った。そこから、救いが始まったのです。
また、仏教者ではありませんが、以前にもお話ししました、星野富弘さんもそうですね。星野さんは、事故で首から下が動かなくなった。生きていることが苦しくて苦しくて、死にたかった。そんなとき、『聖書』に出会った。そこから、救われていったのです。「教え」によって救われていく姿は、仏教徒であろうとキリスト教徒であろうと、変わりはありませんね。
私たちは、理不尽な状況が変われば、救われるように思いがちですが、そうではありません。高さんの息子さんが生き返ったわけではありませんし、星野さんの身体が回復したわけでもありませんね。そうではなくて、「内にある闇」が「教えの光」に照らし出されて、闇が光に変わっていく。そこに、救いが始まるのです。
話が込み入ってきましたので、このあたりで一度整理をしてみます。まず、私たちが悩み苦しむのは、「なぜ自分がこんな目にあわねばならないのか」とか、「どうしてこんなことが起こるのか」といった、理不尽な状況があるからですね。この理不尽な状況というのは、「自分の外にある闇」です。
仏教は、その「外にある闇」を理不尽だと思っているのは「煩悩」なのだと教えていますが、それだけではありません。私たちは気づいていませんけれど、「自分の内」にも闇がある。「宿業」という闇があるのです。そして、この「宿業」こそ、私たちの苦しみの本当の原因だと教えているのが、仏教なのです。
「宿業」は、自分の力では、どうしようもない理不尽なものです。その、自分の力ではどうしようもないという苦しみから、「生きていることへの底なしの不安」が湧いてきているのです。その「生きていることへの底なしの不安」を紛らわせようとして、私たちは、外の状況を、自分の思い通りにしようと、やっきになって苦しんでいるのです。
私たちには、なかなか気づけませんけれど、仏の目から見れば、私たちが生きている姿は、「宿業」という硯の上で、「煩悩」が墨を摺っているようなものなのです。その「宿業」の硯の上には、「生きていることへの底なしの不安」が黒々と広がっているのです。
私たちの苦しみの本当の原因は、外にはないのです。私たちは、「宿業」という、自分の力ではどうしようもない理不尽なものから湧いてくる、「生きていることへの底なしの不安」で苦しんでいるのです。
ですが、月末の支払いが出来るかとか、子供の成績が下がったとかいった、目の前の事柄で悩んでいる私たちには、なかなか分かりませんね。というのは、「宿業」で苦しんでいるというのは、仏の目から見た私たちの姿でして、私たちの目には、そんな自分の姿が見えていないからなのです。
私たちは「煩悩」「煩悩」と口では言いますが、私たちには、まだ自分の「煩悩」が見えていないのです。「煩悩」が見えていないくらいですから、「宿業」になど気づけるはずがないのですね。
実際、真実の姿というのは見えないものですね。どうして見えないかと申しますと、私たちは、こんなふうにですね、物心ついたときから赤い「煩悩」の色眼鏡をつけて世界を見ているからなのです。
物心ついたときから、ずっとこの赤い色眼鏡をかけているものですから、世界とはこういう赤い色のついたものだと思い込んでしまっている。赤い色というのは「他の誰よりも自分が可愛い」という「煩悩」のことですね。
ですから、この色眼鏡をかけたまま、他の人を見ると、みんな「他の誰よりも自分が可愛い」という赤い色をした生臭いものに見えるのです。たとえば、自分の都合ばかり言っている、勝手な子供とか、気儘な姑とかいうように、見えるわけですね。
ところが、この色眼鏡がずれるときがある。私たちは気づいていませんが、これまでにも、何度か、この色眼鏡がずれたことがあるはずなのです。たとえば、子供の問題で苦しんでいる親御さんがおられたら、思い出して頂きたいのです。
子供は、「親の言うことなんか聞かない。自分はしたいことをして楽しんでいるのだ」と遊び回っている。ですが、「自由だ、楽しんでいる」と言いながら、目は険しくなり、顔が荒んでいる。それは楽しんでいる人の顔ではなく、苦しんでいる人の顔です。そんな顔をご覧になって、一瞬でも、ご自分の苦しさを忘れて、子供さんの深い悲しみをお感じになったことはないでしょうか。
また、痴呆症のお姑さんに苦しんでいるお嫁さんがおられたら、思い出して頂きたいのです。お姑さんはわけの分からないことばかり言って、毎日、人を苦しめている。いつのまにか苦しさを通り越して、憎しみさえ感じている。そのお姑さんの虚ろな目に、一瞬でも、ご自分の憎しみを忘れて、哀れをお感じになったことはないでしょうか。
もしあるというのなら、そのとき、あなたの色眼鏡は下がっていたのです。そのとき、あなたは、仏の目で子供さんをご覧になっていた、仏の目で、お姑さんをご覧になっていたのです。それが、子供さんの真実の姿、お姑さんの真実の姿なのです。
そのとき「煩悩」の赤い色眼鏡を下げてくれたのは、休み無く働いている仏の力、「他力」なのです。信仰の生活とは、その「他力」の働きに気づき続けていくことなのです。ですが、聞法していないと、「名号のいわれ」を聞いていないと、何が起こっているのか分からない。何が起こっているのか分からないから、その大切な経験がうやむやになって終わってしまうのです。
他の人を見ているときに色眼鏡がずれると、その人の真実の姿が見える。では、心の内側を見ているときに色眼鏡がさがると、何が見えるのか。真宗の教えで一番大切なのはここです。
 心の内側を見つめているときに色眼鏡が下がると、何が見えるのかと言えば、それは、私たちの心を支配している「煩悩」の姿です。たとえば、私たちは、「善だ悪だ」と分別しておりますが、その善も悪も、実は「煩悩」によって支えられているのです。ですが、赤い色眼鏡をかけている私たちには、その赤い「煩悩」の姿が見えません。こんなふうにですね。
心の内側を見つめているときに色眼鏡が下がると、何が見えるのかと言えば、それは、私たちの心を支配している「煩悩」の姿です。たとえば、私たちは、「善だ悪だ」と分別しておりますが、その善も悪も、実は「煩悩」によって支えられているのです。ですが、赤い色眼鏡をかけている私たちには、その赤い「煩悩」の姿が見えません。こんなふうにですね。
煩悩の色眼鏡が下がったとき、心の内側を見ているのは「本当の自分」です。その眼差しは、仏の眼差しなのです。その仏の眼差しのなかで、ようやく、自分の「煩悩」が見えるようになるのです。心の奥底に潜むギラリとした「煩悩」のおぞましい姿が見えてくるのです。
 そのギラリとした「煩悩」のおぞましい姿をじっと見つめていると、その背後に横たわる底なしの「宿業」の闇に気づいてくる。自分の力ではどうしようもない、おぞましい自分の姿、「自分の内にある闇」に気づいてくるのです。
そのギラリとした「煩悩」のおぞましい姿をじっと見つめていると、その背後に横たわる底なしの「宿業」の闇に気づいてくる。自分の力ではどうしようもない、おぞましい自分の姿、「自分の内にある闇」に気づいてくるのです。
剥き出しの「人生そのもの」は、つまり「宿業」は、私たちが直視できないほど理不尽なものです。それをしっかり見つめよと教えているのが仏教なのです。そのとき、私たちは初めて夢から醒める。阿弥陀様のおっしゃっている「救われない人間」とは、他の誰でもない、この自分のことだったと気づくのです。
真宗で言う「悪人正機」とは、このことなのです。「悪人正機」というのは「悪人でも救われる」ということではありません。「悪人でも救われる」ではなくて、「悪人こそ救われる」ということなのです。それが「悪人正機」の「正機」という言葉の意味です。
「悪人」の悪というのは、殺人を犯したとか、強盗を働いたとかいった、娑婆の善悪でいう悪ではないのです。そうではなくて、悪人とは、おのれの取り澄ました心の奥底に潜む、ギラリとした「煩悩」のおぞましい姿を見て、その背後にある底知れぬ「宿業」の闇に気づいた人のことを言うのです。「悪人」とは、親鸞聖人のおっしゃっているように、「罪悪深重、煩悩熾盛の凡夫」であるという自覚を得た人のことを言うのです。
私たちも、時には「自分は業の深い悪人だ」などと言うことはありましても、それは娑婆の倫理や道徳で言う善悪を、仏の目から見た善悪と取り違えて、親鸞聖人の口まねをしているだけでしてね、本当は、私たちは、たいてい、「宿業」の闇に気づくどころか、自分の「煩悩」の姿を見たことさえないのです。いかがでしょうか。
つまり、そんな私たちは、まだ悪人ではないのです。そうではなく、私たちは聞法を始めたとき、悪人の候補生となり、聞法を重ねるうちに、念仏往生の正機である悪人の自覚にたどりつくのです。自分は到底救われない人間だ、悪人だと知るわけですね。その時、「宿業」の暗闇の底が抜けて「浄土」への扉が開かれ、私たちは救われていくのです。
お念仏を称え、聞法を重ねる生活のなかで、問題意識が「内にある闇」にまで深められていったとき、そこには「宿業」の深い深い闇が見えてくる。その深い深い「宿業」の闇が見えたとき、ただただ懺悔するしかない、浅ましい、おぞましい、どうしようもない我が身が見えてくる。そして、その懺悔の思いが極限にまで高まったとき、闇は光に変わり、懺悔は歓喜に変わるのです。
思えば、闇のなかにいる「私」に闇が見えるはずがない。「宿業」の深い深い闇が見えるのも、懺悔が歓喜に変わるのも、みんな他力の働きなのです。そのことに気づいていくのが、私たちが救われていく道筋なのです。
しかし、なかなか、闇が光に変わるという経験にまでは至らないものですね。それなら、私たちの信心が偽物なのかと言えば、おそらくそうではないでしょう。そうではないでしょうけれど、いかんせん、その信心の大半は、まだ知識なのですね。
「阿弥陀様は、救われない衆生を救ってくださる」と聞いても、衆生とは、生きとし生けるもののことだと考えている。ですが、衆生という言葉を生きとし生けるもののことだと考えているあいだは、それは知識なのです。そうではなくて、救われない衆生とは、この「私」のことだと気づいたときに、救いが始まるのです。
『歎異抄』に、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人の為なりけり」という言葉がありますが、これは、その気づきをおっしゃったものなのですね。
私たちは、心の底に「宿業」という底知れぬ闇をかかえている。そのことを教えられ、それを信じて、聞法と、お念仏の日々を重ねていく。そうして、信じていたことを、本当に知る、本当に体験するときがくる。そのとき、私たちは救われていくのです。
親鸞聖人の御和讃に、「煩悩具足と信知して、本願力に乗ずれば、すなはち穢身すてはてて、法性常楽証せしむ」(高僧和讃:善導讃)とありますが、ここに「信知」と、わざわざ、「信」だけではなく「知」と示されているのは、そのことなのですね。
「宿業」を知り、「宿業」を阿弥陀様にあずけてしまったとき、「生きていることへの底なしの不安」が無くなります。そこに始まるのが、おおらかな「お任せ」の人生、「生かされて生きる」人生なのです。
傍目には分からないかもしれませんが、そのとき、私たちの人生は大きく変わります。それまでの人生は、さきほども申しましたように、「宿業」という硯の上で「煩悩」が墨を摺っているようなものでしたが、そのときからは、仏の願い、「悲願」という硯の上で「仏」自身が墨をするようになるのですね。
「宿業」を阿弥陀様に取られて、おおらかな「お任せ」の人生、「生かされて生きる」人生がはじまるのです。
35歳で脊椎カリエスで亡くなった明治の歌人、正岡子規は、亡くなる少し前の日記に、こう書いています。「私は今まで禅宗のいわゆる悟りということを誤解していた。悟りという事はいかなる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事はいかなる場合にも平気で生きている事であった」(『病床六尺』)と。
子供さんに苦しむ親御さんも、お姑さんに苦しむお嫁さんも、どうぞお聞き下さいね。仏の目から見れば、「暗闇の底にいるときこそ、光の一番近くにいる」のです。「いろんな問題が次々におこってくるのも、気づけよ、気づけよ、という仏の世界からの働きかけ」なのです。
今現に苦しんでいる私たちの目には、なかなか、そうは見えません。そうは見えませんけれど、南無阿弥陀仏というお念仏を称え、聞法を重ねていくうちに、私たちは、「自分の外にある闇」を「気づきの縁」として考えることが出来るようになってくるのです。
仏の目から見れば、あなたの子供さんは、あなたに伝えることがあるから、グレているのです。あなたのお姑さんは、あなたに伝えることがあるから、痴呆症になっているのです。お念仏を称え、聞法を重ねる生活のなかで、あなたが本当にそのことに気づいたとき、闇が光りに変わるのです。
そのとき、子供さんやお姑さんは、あなたを闇から光へと導くために、グレていた、また痴呆症になっていた、還相の菩薩だったことが分かるのです。その菩薩に、心のなかで手を合わせる生活が始まれば、あなたは変わる。あなたが変われば、世界が変わる。世界が変われば、状況も変わってくると思うのです。
昨年亡くなりましたが、インドで貧しい人々のために生涯を捧げたマザー・テレサという人がいましたね。彼女は、あるとき、「苦しくはありませんか」と聞かれて、こう答えていました。「私は、私のために苦しんでくださっている、病人のなかの神様に仕えているだけです」と。これも同じことを言っているのだと思います。
思えば、年末に、寺の前で出会った子供たちも、私に伝えることがあったから、声を掛けてきたのでしょうね。子供というのは、何か、仏様に近いところがあるように思いますね。
先日も、こんな話を聞きました。神戸震災で、お姉さんを失った小学生の男の子の話です。その子が作文に、こう書いているのです。
「お姉ちゃんが生きていたときには、兄弟喧嘩ばかりして、お姉ちゃんなんか死んでしまえとか、どっか行ってしまえとか言っていたけれど、今はもう、そんなことは言えなくなった。お姉ちゃんは命を懸けて、命の尊さをボクに教えていってくれたのです。だから、もう、死ねなどという言葉は絶対言えない」と。
小学生ですから、難しい言葉は何も使っていませんが、「自分が死ぬことで、理不尽な苦しみをボクに与えることで、命の尊さを教えてくれたお姉ちゃんは、ボクにとって、還相の菩薩だった」と言っているのですね。
子供の目は、仏の目に近いのです。ですが、私たち大人は、社会のなかで長く暮らしている間に、そんな仏のような目で、世界を見られなくなっているのです。だからこそ、そんな私たちは、聞法することで、「仏の目」を身につけていかねばならないのです。
聞法とは、仏の教えを聞くことです。仏の教えを聞くというのは、仏の目から見れば、この私の姿がどう見えるのかを、学ぶことです。それが聞法なのです。
仏の目から見ればどう見えるのか。それを常に問いかけていく生活が、信仰の生活です。仏の目から見ればどう見えるのか。その問いかけが「南無」なのです。そして、その問いかけへの答えが「阿弥陀仏」なのです。「仏の目には、こう見えているよ」という、教えからの応答が「阿弥陀仏」なのです。
「南無」と問いかけ、「阿弥陀仏」と答える。この、「南無」と問いかけ、「阿弥陀仏」と答える生活のなかで、いつしか、「南無」と「阿弥陀仏」がひとつになってくる。「南無」と「阿弥陀仏」が「南無阿弥陀仏」となってくるのです。
「南無」と「阿弥陀仏」が「南無阿弥陀仏」となったとき、そのとき、私の口から出てくる「南無」は、もはや問いかけではない。その「南無」は、「おっしゃる通りです。どうか救ってください」という、凡夫の告白、懺悔の涙です。そのとき、私の口から出てくる「阿弥陀仏」も、もはや応答ではない。その「阿弥陀仏」は、「よくぞ分かってくれた」という、仏の歓喜、悲願の涙なのです。
「南無」が「阿弥陀仏」となったとき、「私の目」は「仏の目」となっている。「仏の目」は「南無阿弥陀仏」。「私の目」も「南無阿弥陀仏」。「南無阿弥陀仏」という六字の名号は、闇から光りへと、救われていく私の姿でもあり、闇が光となった、救われた私の姿でもあるのです。
私たちは、聞法を始めたそのときに、仏の目をもらったのです。南無阿弥陀仏という、お念仏として、仏の目をもらったのです。南無阿弥陀仏という仏の目をかかげ、その仏の目で人生を見ていくこと、それが、念仏に生きるということです。
「名号のいわれ」を聞き、その教えを、頭ではなく、生活全体で受け止めることを信仰といいます。信仰を得ると、人生に拠り所ができます。人生に拠り所があると、日々の生活が充実して、何事にもおおらかになります。それが、信仰の働きです。
しかし、何でもそうですが、そういう信仰が身に付くためには、それなりの時間がかかります。年をとったから、そろそろ信心でもというのでは、なかなか身に付きません。
蓮如上人は、こうおっしゃっています。「仏法には若いうちに親しみなさい。年をとってからでは、足下もおぼつかなくなってお寺にも行けないし、お説教を聞いても眠くなって身に付かないから」と。
信仰は生活の技術ではありませんから、信仰がないと生活できないというものではありません。ですから、世間では、信仰などというものは、年寄りの「慰みごと」であるかのように誤解しておりますが、本当はそうではないのですね。
体が寒いと火のそばによって暖をとりますが、ちょうどそのように、「自分は、これでいいのだろうか。何のために生きてるだろう」と、心が寒くて、魂が疼くときに、その心を温め、魂をほぐしてくれるもの、それが信仰なのです。
本日お話し申し上げたいことは、ここまででございます。長い間お付き合いくださいまして、有り難うございました。ご縁がありましたら、また、ご一緒に聞法させて頂きたいと存じております。どうぞ、皆さん、御達者でお過ごしください。有り難うございました。
紫雲寺HPへ