これはある先生から聞いた話ですが、その先生が、講演をなさっていた時、しきりと欠伸をする人がいた。そこで、先生は、「欠伸が出そうになったら、上唇を左から右へと舐めてみてください。そうすれば欠伸が止まりますから、宜しくお願いします」とおっしゃった。すると、今度は、会場のあちこちで、ペロペロ、ペロペロと唇を舐め始めて、かえって話がしにくかった、ということでございました。ここでは、そういうお気遣いはご無用でございます。どうぞご遠慮なく、欠伸をなさりたい方は、なさっていただいて結構でございます。
本日は、「永代経法要」でございますが、私が皆様の前で初めてお話しさせて頂きましたのも、5年前の「永代経法要」のときでございました。そして、お同行の皆様とご一緒に、現実から真実へと続く螺旋階段を昇ってまいりまして、今回が13回目でございます。
これまで12回お話しさせて頂きまして、どうやらその螺旋階段も一巡りしたように思います。そこで今回は、これまでの「まとめ」に成るような話をさせて頂こうと思っております。どうぞ、これまでの話を思い出して頂きながら、お気楽に、お聞き頂きますように、お願い申しあげておきます。
さて、私たちは真宗門徒でございますが、真宗の教えの要は、「名号のいわれ」を聞きひらき、疑いなく信ずるところにあります。皆様も、何度もお聞きになって、よくよくご承知のことかと存じます。「名号」とは、「南無阿弥陀仏」という六字の名号を申します。この名号ひとつで浄土に往生できる。それが真宗の教え、浄土の教えですね。
伝統的に申しますと、「浄土の教えを聞いて、疑いなく信ずる」というのが、浄土真宗の本筋でございます。ですが、この「信ずる」ということは極めて難しいのですね。『大無量寿経』にも、「この教えを聞いて信じ喜ぶということは、難中の難である。これより難しいことは他には無い」と書かれております。
実際、「弥陀の誓願」とか、「西方浄土」とか申しましても、考えようによっては、とりとめもない話です。御聖教に書かれていると言っても、そんなことは何の証拠にもなりません。疑いだしたら切りがない。おそらく、現代社会で、この「名号のいわれ」を聞いて、「はい、そうですか」と、素直に信じられる人は、ごく希ではないかと思います。
実は、私も、信じられませんでした。以前にもお話しいたしましたが、私は、初めて『大無量寿経』を読みましたとき、疑惑の思いを抱いたまま、動きがとれなくなってしまいました。それでどうしたかと申しますと、どうにもなりません。考えても、考えても、分からないのです。どう読んでみても、信じられない。これを信じることが信心だとすれば、これはもう、紫雲寺も父の代で終わりだな、と思い詰めました。
もしもこのとき、教えに背を向けておりましたら、皆様にお目にかかるご縁もなかったわけですが、疑惑の方が腹にどっしり腰を据えてしまいまして、離れないのです。いわば、どうしても信じられないという思いが、禅宗で言う公案のようなものになってしまったわけです。
そんな思いを腹に抱いて鬱々としておりましたとき、どこでだったか忘れましたけれど、「名号のいわれを信じられるのも、また他力による」という言葉を目にいたしました。この言葉を見たとたんに、目の前がぱっと明るくなりまして、心の底がはじけたように、愉快な気分が沸々と湧いてくる。もう、可笑しくて可笑しくてしかたがない。何もかも分かったという気分です。そのときの体験を、正確にお伝えすることはできませんが、ともかく、何もかも分かったという不思議な気分なのですね。
そんな気分が半日ほど続きました。今になって思えば、禅宗で言う小悟というのも、あんな体験を言うのかもしれませんね。ただ、何もかも分かったと言いましても、では何が分かったのかと言われると、別に何も分かっていないわけです。しいて言えば、分からないことが不安でなくなったということでしょうか。
まあ、そんな体験がありましてから、少し考えが変わり、経典の読み方も変わりました。考えが変わったと申しますのは、ひとつには、信じるということは、感じるということではないかと、考えるようになったことです。たとえば、弥陀の誓願を信じるとは、弥陀の誓願を感じることだと言えば、お分かり頂けるのではないかと思います。
「浄土の教え」は、申しあげるまでもなく、「来世往生の教え」です。ですが、その眼目は「来世」にではなく、むしろ「今生」にあります。「浄土の教え」というのは「この世」で「大慈大悲の光」を身に浴びるための教えなのです。「大慈大悲の光」を身に浴びて、「本当の自分」に出会う。そして、一人一人が命の真実に目覚め、本当の自分を生きることができるようになる。このことを説いているのが「浄土の教え」なのです。
来世で、浄土の光のなかに生まれることを「往生」と申します。それに対して、今生で、浄土の光に触れる体験を「廻心」と申します。「廻心」とは、信心が確立する体験のことです。「体験」である限り、それは「信じる」ことではなく、「感じる」ことなのですね。
「来世往生」は、すでに決まっております。法蔵菩薩の誓願として、すでに決まっているのです。それが私たちの「命の真実」の姿なのです。ですから、私たちにとって、「往生」は、すでに問題ではありません。問題は、それが信じられるか、いや、感じられるかということです。別の言葉で言えば、私たちの信仰の問題は、「往生」にではなく、「廻心」にあるということです。
そこで、今回はこれまでの「まとめ」として、私たちを「廻心」へ導いてくれる道、「行」としての「念仏」についてお話ししたいと思います。「念仏」と申しますと、真宗では、「阿弥陀仏の救済を喜ぶ、報恩謝徳の念仏、御恩報謝の念仏」と言うことに決まっておりますが、それを承知で、私は、「廻心の行」、「安心決定の行」として、お話ししようと思うわけです。
「称名念仏」は「浄土往生の大行」と申しますが、「浄土往生」は、他力の働きです。つまりは、「往生」は阿弥陀様の仕事です。ですが、その阿弥陀様のお働きを、この身に受け止めていくことは、私たち一人一人の仕事なのです。
阿弥陀様のお働きを、この身に受け止めるというのは、「大慈大悲の光」を、この身に感じるということです。「大慈大悲の光」を、この身に初めて感じたとき、その体験を「廻心」と言うのです。禅宗でいう「見性」というのも、これと同じ体験のことです。
では、「大慈大悲の光」は、何処からさしてくるかと言えば、「西方極楽浄土」からですね。「念仏」というのは、今生で、その「浄土の光」を体験するための智慧なのです。そこで、この話は、その「浄土」は何処にあるのかというところから、始めたいと思います。
さて、「浄土」はどこにあるのか。結論から申しますと、実は、「今、ここに」あるのです。ここは「浄土」ではない、とおっしゃるのなら、それはそのとおりです。それでも、「浄土」は「今、ここに」あるのです。
「浄土」は「今、ここに」あるのですが、私たちが、その「今、ここに」いないのです。なにか禅問答みたいに聞こえるかもしれませんから、もう少し順序だててお話し致します。
私たちは「今、ここに」いる、と思っています。たしかに身体はここにあります。ですが、心が「今、ここに」ないのです。日常の私たちは、何もしていないときでも常に休みなく頭のなかでオシャベリをしています。常に何かを考えていると言ってもよいでしょう。
過去を誇ったり悔やんだり、未来に期待したり不安を抱いたりして、決して「今」のこの一瞬にとどまっているということがありません。つまりは、頭のなかで過去へ未来へと走り回っている私たちは、「今、ここに」はいないということになります。こんな私たちの、心のなかのオシャベリを止めるための智慧。それが「念仏」なのです。
私たちは「過去」に生きているわけでも「未来」に生きているわけでもありません。私たちは、本当は「今、ここに」生きているはずなのです。ですが、心が「過去」へ「未来」へとさまよっているのです。
「過去」は過ぎ去ってしまいました。ですから、「過去」は、いまさらどうしようもありません。「未来」はまだ来てはおりません。ですから、「未来」は、まだどうなるか分かりません。私たちは、そんな「どうしようもない」世界と「どうなるか分からない」世界をうろうろしているものですから、いつまでも心が温まらないのです。「念仏」は、こんな私たちが見失ってしまった「今」を取り戻す「智慧」なのです。
こう申し上げましても、まだお分かりにくいかもしれませんので、ひとつ、以前にもご覧頂きました目に見える「たとえ」を使ってご説明いたしましょう。ここに3つの積み木があります。赤、青、黄色、とまるで交通信号みたいですが、赤の積み木には「過去」と書いてあります。青には「現在」、黄色には「未来」と書いてあります。
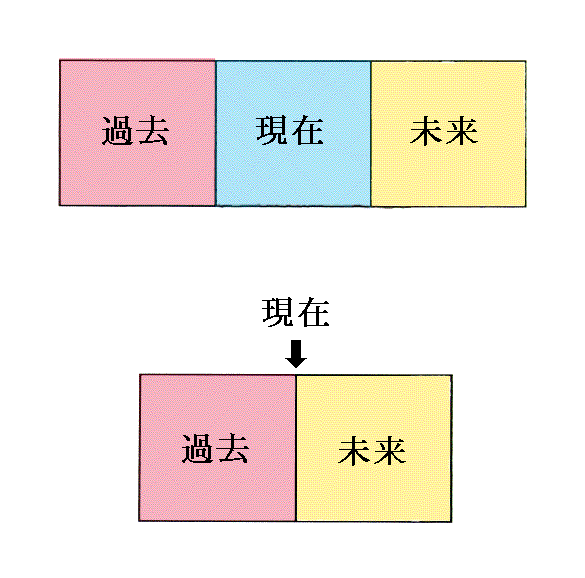 一般に、「時」というものは、「過去」から「現在」を経て「未来」へと続く一筋の流れのようなものと考えられております。しかしこの流れは、「過去」「現在」「未来」という三つの積み木を、このように一列に並べたような関係にはなっておりません。
一般に、「時」というものは、「過去」から「現在」を経て「未来」へと続く一筋の流れのようなものと考えられております。しかしこの流れは、「過去」「現在」「未来」という三つの積み木を、このように一列に並べたような関係にはなっておりません。
そうではなくて、「時の流れ」を積み木で表わすとすれば、「過去」と「未来」という二つの積み木がくっついているだけです。そして、この二つの積み木の接点が「現在」に相当するという関係になっております。
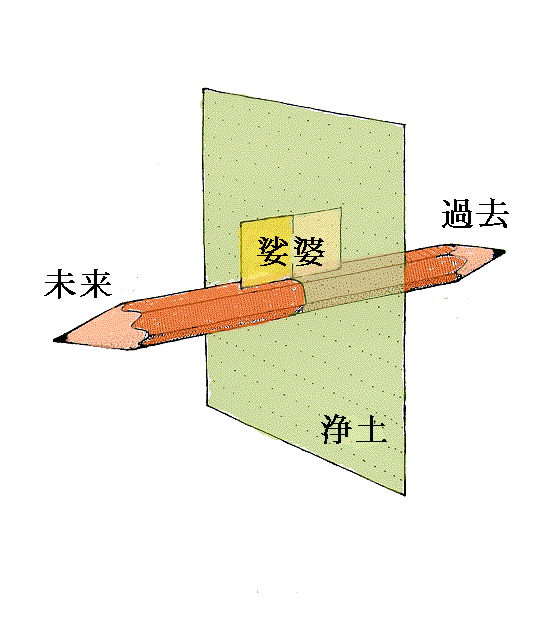 ですから、本当の「今」というのは、「過去」と「未来」という2つの積み木にはさまれた、この「緑色のシート」のようなものです。つまりは、時間の流れからはみだしている世界、時間を超越した世界が、本当の「今」なのです。そして、私たちの日常的な意識とは次元の異なった、「今、ここに」ある広大な世界が、「浄土」なのです。
ですから、本当の「今」というのは、「過去」と「未来」という2つの積み木にはさまれた、この「緑色のシート」のようなものです。つまりは、時間の流れからはみだしている世界、時間を超越した世界が、本当の「今」なのです。そして、私たちの日常的な意識とは次元の異なった、「今、ここに」ある広大な世界が、「浄土」なのです。
この「今」という世界には、心のなかのオシャベリがとまったときに、初めて入っていくことができるのです。たとえば、私たちの「娑婆」世界は、心のなかのオシャベリによって、こんなふうに「過去」と「未来」にまたがっておりますね。このオシャベリが段々と納まって行ったとき、私たちは自然に、この「今、ここに」ある本来の命の世界、「浄土」に入っていくのです。
「心のなかのオシャベリを止める」というのは、「時間を止める」ということですが、これを、例によって、お馴染みになりました「命の構造」の図を使って、ご説明いたしますと、こういうことです。
まずはこの図の説明からいたしますと、これは唯識仏教で言われております「心の構造」を、私なりにアレンジして描き直したものです。小山のように盛り上がっておりますのが、私たちの命の全体像です。上から順に、青、赤、黄に色分けしてありますのは、それぞれ「五感と意識」「マナ識」「アラヤ識」を表しております。
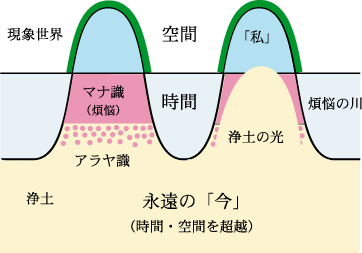 一番上の青色の部分は、私たちの目に見える現象世界ですから、ここは「空間の世界」です。また、一番下の黄色の部分は、阿弥陀仏の世界、「浄土」ですから、ここは「時間も空間も超越した悟りの世界」です。別の言葉で言えば、「永遠の今」の世界です。
一番上の青色の部分は、私たちの目に見える現象世界ですから、ここは「空間の世界」です。また、一番下の黄色の部分は、阿弥陀仏の世界、「浄土」ですから、ここは「時間も空間も超越した悟りの世界」です。別の言葉で言えば、「永遠の今」の世界です。
では、この中間に挟まっている、「煩悩」に支配されている「マナ識」はどうかと言えば、ここが「時間の世界」なのです。たとえば、「煩悩」の働きによって、怒りが過去からやってきます。不安が未来からやってきます。自惚れが過去からやってきます。野心が未来からやってきます。そういうふうに、私たちの心を、過去へ未来へと振り回しているのが、この「マナ識」なのです。
ですから、「心のなかのオシャベリを止める」、「時間を止める」ということは、この「マナ識」の働きを止めるということです。仏の智慧である「念仏」によって、この「マナ識」が止まったら、どうなるのか。「マナ識」が止まるということは、「煩悩」の流れが止まるということです。そうなれば、「浄土の光」が「煩悩の川」を乗り越えて、この「私」にまで届くようになるのです。
阿弥陀如来は、この「浄土」から、常に、私たちに呼び掛けておられるのです。ところが、「煩悩の川」が、騒々しい音をたてて流れているものですから、私たちには、その呼び声が聞こえません。阿弥陀如来の呼び声が聞こえてくるのは、そんな「煩悩」の流れが鎮まったときなのです。
さて、心が一点に集中すると、時間が止まります。たとえば、野球の選手でも、心が良く集中しているときにバッターボックスに立つと、ピッチャーの投げるボールが止まって見えると言いますね。「時間が止まる」というのは、心が「今」にあるということです。
ところが、現代社会では、この「今、ここに」生きるということが非常に難しくなってしまいましたね。現代は、効率と能率を重んじる競争社会です。ですから、一定時間に、どれだけ多くの仕事を詰め込むかということばかり考えるようになってしまいました。
仕事をこなすことばかりに気を取られて、速くこの仕事を片付けて、次にかかりたいと、追われるように走り続けているのが、私たちです。「速く片付けて、次のかかりたい」というのは、心が「ここ」にないということですから、そうなると、もう「今」を感じることなど、なかなか出来ませんね。
ですが、そんな私たちにも、偶然に、「今」を感じるということがあります。たとえば、空に浮かぶ雲を見上げて、いつのまにか我を忘れて感動していた、というようなご経験は、おありではないでしょうか。似たようなご経験は、どなたにも、おありのことと思いますが、「我を忘れていた」というのは、「時間が止まっていた」ということなのです。つまり、そのとき、「今」にいたということです。
もう少し詳しくご説明いたしますと、こういうことです。ここに二つの円が描いてあります。上の円が「雲」、下の円が、たとえば「私」だといたしますと、この「私」は「我」に支配されております。「我」というのは「我執」のこと、つまり「煩悩」のことです。
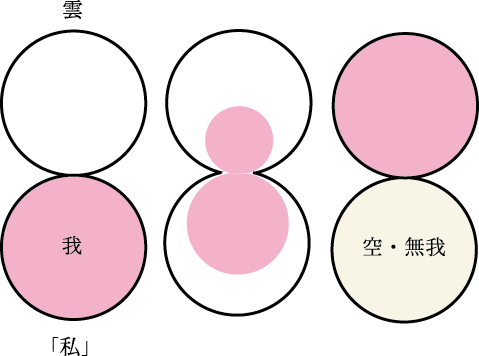 ところが、「雲」という一点に集中しておりますと、「私」は、その「雲」と一体に成ってしまい、「私」の「我」は、「雲」に取られてしまいます。そうすると、「私」のなかは空っぽになってしまいます。つまり、「私」のなかが「空」になり、「無我」になるわけですね。
ところが、「雲」という一点に集中しておりますと、「私」は、その「雲」と一体に成ってしまい、「私」の「我」は、「雲」に取られてしまいます。そうすると、「私」のなかは空っぽになってしまいます。つまり、「私」のなかが「空」になり、「無我」になるわけですね。
「空」とか「無我」というのは、何も無いということではありません。「空」というのも、「無我」というのも、「浄土の光」そのもの、清らかなエネルギーそのもののことです。「我」が明け渡した場所に、「無我」のエネルギーが流れ込んでくるのです。ですから、私たちは自覚しておりませんけれど、そういうときに経験した感動は、「浄土の光」に触れたところから生まれた感動なのですね。
「悟る」というのは、この「今」にあり続けることができるようになることです。「仏」の世界は、何処にもなくて、「今、ここに」あるのです。臨済宗の盤珪禅師が、「仏に成ろうとしょうよりも、仏でおるが造作がのうて、近道でござるわいの」とおっしゃったのは、このことです。また、道元禅師のおっしゃっている「只管打坐」というのも、同じことですね。
座禅も「行」なら、称名念仏も「行」です。そんな「行」としての「念仏」は、心を「今」という一点に集中させるための、焦点と成る言葉です。「念仏」によって、心が「今」という一点に集中すれば、世界が輝いてまいります。言うまでもありませんが、その輝きは、「浄土の光」ですね。
「大慈大悲の光」を身に感じるための「行」、それが「念仏行」です。といっても、何も難しいことをするわけではありません。「念仏行」とは、「はからいをはなれ、ただ一心に念仏申す」という、ただこれだけのことです。
「はからいをはなれ」とは、「自分の頭で考えることをやめる」ということですが、実際には、「念仏など称えて何になるんだ」という思いと、「念仏を称えることで救われよう」という思いを、ともに捨て去ることです。「念仏」を否定するのも肯定するのも、ともに「我が身のはからい」なのです。
また、「ただ一心に念仏申す」というのは「念仏だけを一心に思う」ということです。「お念仏」を称えながら、何か他のことを思ったり考えたりしないで、「心」を「お念仏」で満たすということです。つまりは「お念仏そのものになる」ということなのです。
よく、「お念仏を称えながら一日を反省する」とおっしゃる方がおられますが、これは違います。「お念仏」を称えながら「反省」するというのでは、これは「一心」ではなく、「お念仏」と「反省」という二つの心になってしまいます。
「お念仏」を称えながら「反省」するというのは、「お念仏」の入ったコップの中へ「反省」という氷を入れるようなもので、真剣に「反省」すればするほど、心のなかから「お念仏」が出ていってしまいます。ましてや、「お念仏」を称えながら、「反省」したり、「我が身の後生」や「先祖の供養」を願ったりしていたのでは、「ただ一心に」というわけにはいきません。
落語家の、三代目三遊亭金馬の十八番に、『小言念仏』という話がありますが、あの話に出てくるお爺さんのように、お念仏を称えながら、あれこれ小言ばかり言っているようでは、とうてい「一心」にはなれません。
「ただ一心に念仏申す」というのは「念仏だけを一心に思う」ということです。「お念仏」を称えながら、何か他のことを思ったり考えたりしないで、「心」を「お念仏」で満たすということです。つまりは「お念仏そのものになる」ということなのです。
ちなみに、「念仏行」とは一種の瞑想法だと申しましたが、「浄土教」には、もうひとつ「観仏行」という瞑想法があります。「観仏行」というのは、仏の姿を心に強く「イメージ」する行法です。「観」とは心のなかで何かを観察することを言います。
真宗では「観仏行」はいたしませんが、たとえば、天台浄土教の「常行三昧」では、心のなかに阿弥陀仏のイメージを描き、その仏の相好を観察するという、「観想念仏」(観仏行)が中心になっていました。親鸞聖人も、比叡山におられたころは、この「観仏行」をなさったわけです。
ですが、「念仏行」では、この「イメージ」というものを全く用いず、代わりに「ナムアミダブツ」という名号を用いるのです。「イメージ」というのは映像の世界ですが、「称名念仏」は音声言語の世界です。そこで、このふたつの行法の違いを、少し大脳生理学的に考えてみたいと思います。
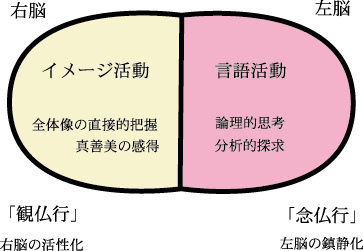 ご存じのように、私たちの大脳は「右脳」と「左脳」という2つの半球からできていて、機能的分業をしています。ごく大雑把に言って、主に「右脳」はイメージ活動を、「左脳」は言語活動を司っています。つまり、「右脳」は全体像の直観的把握や真善美の感得にすぐれ、「左脳」は理論的思考や分析的探求にすぐれているということです。
ご存じのように、私たちの大脳は「右脳」と「左脳」という2つの半球からできていて、機能的分業をしています。ごく大雑把に言って、主に「右脳」はイメージ活動を、「左脳」は言語活動を司っています。つまり、「右脳」は全体像の直観的把握や真善美の感得にすぐれ、「左脳」は理論的思考や分析的探求にすぐれているということです。
こういった「右脳」と「左脳」の機能的分業から見れば、「イメージ」を描く訓練を積むということは「右脳」を鍛えるということになります。つまり、「観仏行」は「右脳」の活性強化をめざしているということです。では、「イメージ」を用いない「念仏行」は何をめざしているのでしょうか。
「念仏行」は「名号」という音声言語を用いているのですから、そのターゲットは明らかに「左脳」にあります。実は、「念仏行」は「左脳」の働きを鎮めることをめざしているのです。私たちの「左脳」には、音声言語を用いたオシャベリが絶えず渦巻いています。この様々なオシャベリを、「ナムアミダブツ」という一つの音声言語に集中することで鎮める。それが「念仏行」なのです。
言葉を代えて言えば、「観仏行」は直接的に「右脳」の活性化をはかっているのに対し、「念仏行」は「左脳」を鎮めることで間接的に「右脳」を活性化しようとしているのです。つまりは、いずれの「行」も、相対的に「左脳」より「右脳」の活性度を高めることをめざしているのです。
どうやら、「浄土」への入り口は「右脳」にあるということのようですが、では、「観仏行」と「念仏行」では、どちらが簡単かと言えば、もちろん「念仏行」の方が、遙かに簡単です。私たちはたいてい、理屈っぽい左脳型人間ですから、苦手な右脳を働かせて「仏」のイメージを観ようとするには、大変な努力がいります。
ところが、「念仏行」は、「名号」を称えるだけです。「ただ一心に名号を称え」、あとは、その「名号」の働きに任せるのです。ですから、「行」そのものには、ほとんど努力はいりません。「念仏行」は、さほどの努力を要せず、「観仏行」と同じ結果に到達する道です。同じ結果とは何かと言えば、仏の世界に触れるということです。
善導大師も、『往生礼讃』のなかで、『文殊般若経』の言葉を引いて、こうおっしゃっています。「懸命に仏のお姿を観ようとはせず、専ら名号を称えれば、その名号の中において、かの阿弥陀仏および一切の仏を見ることができる」(『教行信証』行巻)と。「阿弥陀仏を見る」とは、「智慧の光明を見る」ということ、つまりは、「浄土の光」に触れるということですね。
ところで、「信心」というものは、「聞法」を重ねるうちに深まっていくわけですが、その「信心」の深まり方には二つの方向があります。「二種深信」というのがそれです。「二種深信」とは、善導大師の『散善義』に出てくる言葉ですが、「機の深信」と「法の深信」を言います。
ご承知かとは存じますが、簡単にご説明いたしますと、「法の深信」とは、箸にも棒にもかからない悪人を、念仏ひとつで救ってくださるのが阿弥陀仏の本願だと深く信じること、つまり「名号のいわれ」を深く信じることです。また、「機の深信」とは、その箸にも棒にもかからない悪人とはまさに自分のことだと深く信じることです。
「二種深信」と言っても、信心に二種類あるということではありませんが、私たちの意識の上から言えば、おのずから重点の置き具合というものがあります。
そういうものですから、私はかつて、「阿弥陀様が救って下さる」という一種夢のような話を信じるよりも、現実に即して「自分が悪人だ」と信じる方が簡単ではないかと思っておりました。ところが、そうではないのですね。「機の深信」を究めることは、「法の深信」を究めることより、格段に難しいのです。
どういうことかと申しますと、「自分が浅ましい人間だ」という教えは、「他の誰よりも自分が可愛い」という「煩悩」と、真正面からぶつかるからです。ですから、教養として学ぶことや、他人事として「聞く」ことはできても、自分自身のこととして「聞こえる」というところまでは、なかなかいかないのです。
私たちは、自分では気づいていなくとも、心の何処かに「プライド」を持っています。ですから、自分が「箸にも棒にもかからない悪人だ」とか、「浅ましい人間だ」と、本心から思うことは、なかなかできないものなのです。心の底で「煩悩」が拒否しているからですね。
先日も、かなり聞法を重ねて来られた方が、こうおっしゃいました。「ご院さん、私は自分のことが、どう考えても下品下生やとは思えませんのや。下品上生か、せいぜい下品中生やと思うのですが、どうですやろ」と。思えば、正直な方ですが、「煩悩」というものは、ことほどさように、一筋縄ではいかないものですね。
「煩悩」と真正面からぶつかるというのは、敵陣に真正面から切り込むようなものですから、これは、よほど天分に恵まれた人でないと、成功はおぼつきません。そこで大切になってくるのが、「念仏行」なのです。「念仏行」は、「煩悩」と戦うことなく「煩悩」を鎮める道なのです。
阿弥陀様は、常に私たちに呼び掛けてくださっている。その呼び声が聞こえないのは、私たちが、常に、頭のなかでオシャベリをしているからです。つまりは、心が過去へ未来へと走り回って、「今」という一点に、周波数が合っていないからです。その走り回っている心の周波数を「今」に合わせる、阿弥陀様の呼び声に合わせる、それが「念仏行」なのです。
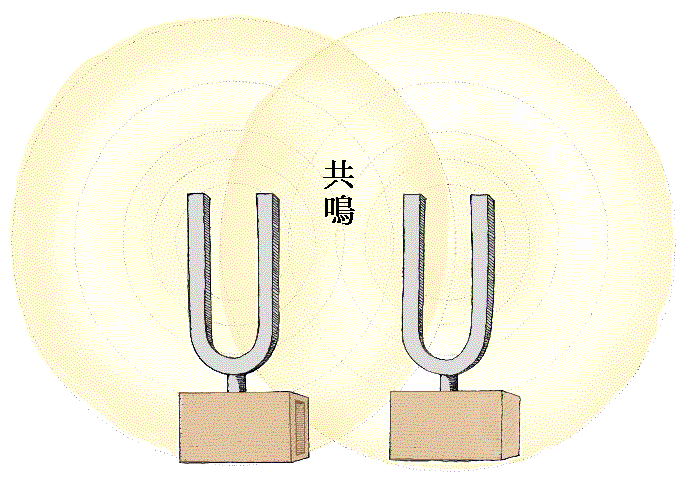
それは、別の「たとえ」で言えば、こういうことです。これは、理科の実験などで用いる「音叉」です。これをバチでたたくと固有の振動数の音を発します。同じ振動数の音叉を二つ並べてその一方をたたくと、もう一方が共鳴して音を発します。こんなふうにです。振動数の違うものなら共鳴を起こしません。
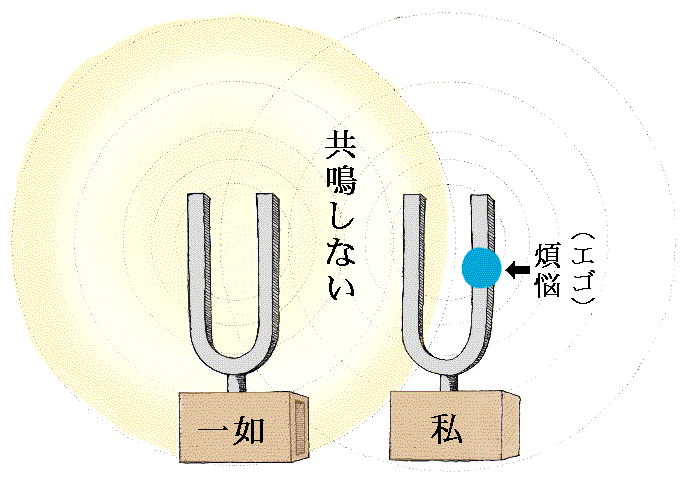 そこで、こちらの音叉が「阿弥陀仏」(一如)、もう一方の音叉が「私」だとしますね。以前にもお話しいたしましたように、人は本来「仏」なのですから、私たちはみな、この「阿弥陀仏」と同じ振動数を持った音叉のようなものです。とは言うものの、「煩悩」が心にくっついて騒いでいるものですから、本来なら起こるはずの「阿弥陀仏」との共鳴が、起きなくなっているのです。こんな具合にです。
そこで、こちらの音叉が「阿弥陀仏」(一如)、もう一方の音叉が「私」だとしますね。以前にもお話しいたしましたように、人は本来「仏」なのですから、私たちはみな、この「阿弥陀仏」と同じ振動数を持った音叉のようなものです。とは言うものの、「煩悩」が心にくっついて騒いでいるものですから、本来なら起こるはずの「阿弥陀仏」との共鳴が、起きなくなっているのです。こんな具合にです。
ですが、「お念仏」を称える生活のなかで、「私」の心にくっついて騒いでいる、この「煩悩」が鎮まっていけば、必ず共鳴が起こります。「信心」というのは、この共鳴のことです。
思えば、「私」の音叉の音は、この「阿弥陀仏」の音叉から賜ったものです。「信心は阿弥陀仏から賜るものだ」と申しますが、それは、このことです。つまりは、「信心」というものは、努力で得られるものではなく、智慧の「念仏」によって、「阿弥陀仏」から賜わるものなのですね。
私たちは「煩悩」に支配されておりますから、そんな私たちが、努力で、つまり「自力」で、仏に成ることは出来ません。私たちに出来ることは、「念仏」という仏の智慧を借りて「煩悩」の流れを鎮め、少しづつ、「他力」の働く場に成っていくことだけなのです。
「念仏往生の本願を信ずる」のが絶対他力の信心と申しましても、「他力」と「自力」は、実際にはそれほど截然と分けられるものではありません。たとえば、「念仏」(行)に重きを置けば「自力」に傾き、「本願」(信)に重きを置けば「他力」に傾くことになってまいります。法然上人にも親鸞聖人にも、この揺れが見られます。
たとえば、親鸞聖人は、法然上人の「信」と「行」のうち、「信」の方面を純化していかれました。三昧発得とか見仏とかいったことは往生とは関係のないこと。弥陀の誓願をたのみ、往生させて頂けると信じて、念仏申さんと思い立つ心の起こる時、すなわち摂取不捨の利益にあずかるのであって、称名念仏の数の功徳で往生が定まるわけではない。
「行」を捨てて「信」を純化しようとすれば、「念仏申す」ということは強調できませんので、「念仏申さんと思い立つ心の起こる時」ということになるのは当然の流れです。
ですが、親鸞聖人晩年の御作である『正像末和讃』には、「弥陀大悲の誓願を、ふかく信ぜんひとはみな、ねてもさめてもへだてなく、南無阿弥陀仏をとのうべし」、「信心のひとにおとらじと、疑心自力の行者も、如来大悲の恩をしり、称名念仏はげむべし」とあり、微妙に風向きが変わってまいります。
思うのですが、「行」のない「信」もなければ、「信」のない「行」もないのではないでしょうか。「行」に支えられて「信」が深まり、「信」に支えられて「行」が正される。いわば、自力と他力の間で揺れを繰り返しながら、不動の位置にまで振幅が収束されていくのが信仰ではなかと思います。
何が「自力」で、何が「他力」なのかは、なかなか私たちの意識では捕らえ難い、甚だ微妙な問題です。ちなみに申し上げれば、伝統的な「他力浄土門」「自力聖道門」という分け方も、あまりに図式的すぎるのではないかと思います。
と申しますのは、実際には「自力」で悟れる道などありえないと思われるからです。たとえば自力聖道門と言われる禅宗でも、「悟り」というものは、自力が鎮静化していき、自力無効となったとき、不意に感得されるものです。他力は常に働いているのです。ですが、その他力の働きに気づけるのは、騒々しい自力の音が鳴り止んだときなのですね。
さて、私たちは、日々、忙しい、忙しいと、まるで、忙しいのを手柄のようにして、生きております。たしかに、私たちの生活は、「忙しく、慌ただしい」ものです。ですが、「忙しい」という字は、「立心偏」に「亡くす」と書きます。また、「慌ただしい」という字は、「立心偏」に「荒れる」と書くのです。「忙しく、慌ただしい」生活は、心を亡くす生活、心の荒れる生活でもあるのですね。
そんな「忙しさ、慌ただしさ」に流されている自分を、娑婆の喧噪から救いあげる。日常の時間を止めて、「今」に生きる時を持つ。それが、「はからいをはなれ、ただ一心に念仏申す」ということなのです。
私たちは、効率と能率のことばかり考えて、一定時間に、どれだけ多くの仕事をこなせるかということに汲々としています。ですが、「量」を考えれば、おのずと「質」は落ちてまいります。「質」というのは、人生の質、生きている事への感動のことです。
日常生活の大半は、ありふれた出来事で占められています。今日することの九割までが、昨日と同じ事なのです。私たちは、その単調な生活を、心を閉ざして走り抜けているだけです。そんな感動のない心は、枯れ果てた井戸のようなものです。
ですが、本当は、走り抜けるのではなく、立ち止まって心を開いたとき、その単調な日々の生活にこそ、豊かな「今」があることに気づくのです。「念仏行」とは、その「今」になるための練習なのです。「今」を無くした枯れ井戸に、「今」を呼び戻す呼び水、それが「念仏行」なのです。
この寺の前には坂道があります。毎日、寺役の行き帰りに、そこを歩くわけですが、私は、その坂道で、「心を開く」という言葉の意味を学びました。暑い夏の日に、てくてくと歩いていたとき、ふと額に照りつける陽を感じ、吹き付ける風を感じたのです。
無意識のうちに、感じることに、全神経を集中させていました。そこへ、風がドンと当たって吹き抜けた。その瞬間、鳥肌が立って、感動が背筋を駆け上がりました。体中にエネルギーが満ちて、陶然と舞い上がり、訳もなく懐かしい「光」を感じました。
寺役に行くことも、寺に帰ることもどうでもよくなって、酔っぱらいのようにふらふらと、光の洪水のなかを歩いていました。そのとき分かったのです。「心を開く」というのは、「今」を全身で感じることだったのです。
花であれ、草であれ、山であれ、川であれ、世界の全てが「今」に満ちている。「光」に満ちているのです。「万法一如」という言葉がありますが、それはこのことです。また、一遍上人が「万法南無阿弥陀仏」(『一遍語録』)とおっしゃっているのも、道元禅師が「万法に証せらる」(『正法眼蔵』)とおっしゃっているのも、このことなのですね。
「今」になるとは、「他力」の働く場になるということです。「他力」の働く場になるというのは、「大慈大悲の光」を、この身に感じることなのです。そのとき、心の底から「ああ、生まれてきてよかった」と思えるようになるのですね。「生まれてきてよかった」。仏法の功徳とは、この一言に尽きるようなものでございます。
さて、本日お話し申しあげたいことは、これだけでございます。長い間、理屈っぽい話にお付き合い下さいまして、有り難うございました。ご縁がありましたら、またご一緒に聞法させて頂きたいと願っております。どうぞ、またお参り下さい。本日は、まことに有り難うございました。
紫雲寺HPへ