私のような若い者が、「歳のとりかた」などと申しますのは、いささか僭越な話ではございますが、どうぞご寛容を頂きまして、しばらくの間、お付き合いくださいますよう、お願いいたします。
私たちはみな、一年一年、歳をとっていきます。若いときには、そんなことはほとんど考えておりませんが、一年一年、順調に歳をとっていけば、いずれは老人になる。当たり前と言えば、これほど当たり前のこともないのですが、私たちの頭のなかでは、それが当たり前のことにはなっていない。
たとえばですね、「長生きしたいですか」とお尋ねしますと、たいていの方は「長生きしたい」とお応えになります。ところが、「歳をとりたいですか、老人になりたいですか」とお尋ねしますと、「歳はとりたくない、老人にはなりたくない」という言葉が返ってくる。皆さんは、いかがでしょうか。
「長生き」したら、当然、「歳をとる」し、「老人になる」のです。ですから、「長生きはしたいが、歳はとりたくない、老人にはなりたくない」というのは、はなから無理な相談です。それでも、私たちは、「歳はとりたくない、老人にはなりたくない」のです。それは、どうしてでしょうか。
それはですね、結論めいたことを最初に申しますと、私たち現代人は、たいてい、歳の取り方を学ばずに大人になるからなのです。「そんな馬鹿な」と思われるかもしれませんが、そうなのですね。というのはですね、歳の取り方を学ぶというのは、宗教教育を受けるということだからです。
私たちは、近代から現代への、科学万能の時代の流れのなかで、宗教的なものを切り捨ててきました。そのことは、どなたもご存じのことと思いますが、その切り捨ててしまったもののなかに、本当は大切なものが含まれていたのです。それは、歳とともに深まっていく生き方、安らかに日暮らしのできる生き方です。
小児科の先生で、松田道雄さんという方がおられました。もうお亡くなりになりましたが、その方が、晩年にお書きになった本のなかで、こういう意味のことをおっしゃっています。「信仰を持っている人には、死への恐怖も、老人問題もない。だが、私は、そういう教育を受けてこなかった」と。
松田道雄さんだけではありませんね。歳をとっていくというのは自然な流れです。その自然な流れのなかで、心安らかに生きておれる。これ以上に大切なことはないと思うのですが、現代社会では、たいていの人が、そういう大切なことを学ばずに歳をとっていきます。
現代社会で幅をきかせているのは、「肉体を養うこと、欲望を満たすことが人生の目標だ」という教えです。ですが、そこには、健康が大事、生き甲斐が大切で、その先がない。
「肉体を養うこと、欲望を満たすことが人生の目標だ」といっても、歳をとれば肉体は衰えていきますし、肉体が衰えていけば、欲望を満たすこともままならなくなっていきます。ですから、私たちは、心のどこかで、「人生が楽しいのは若いうちだけで、老人になったらダメになる」と、思っている。違いますかね。
実際、無理もないのですね。現代は科学万能の時代ですから、そんな現代社会に生きる私たちは、この「目に見える世界」が全てだと考えるようになってしまいました。「目に見える世界」が全てだということなら、たとえば、この「私」という人間は、目に見えるこの「身体」のことだということになります。
目に見えるこの「身体」が私の全てだとすれば、どうなるのか。当然、「死ねば終わりだ」ということになります。前世もなければ、来世もない。「生まれてきたのは偶然で、死ねば終りだ」ということに、なってまいりますね。
ですが、もしも、「目に見えるものが全てだ」「生まれてきたのは偶然で、死ねば終わりだ」というのなら、そんな人生には、「もともと意味も目的もない」ということになってしまいます。
そんな「意味も目的もない人生」を生きる自分にとって、確かに在るのは、目に見えるこの「身体」だけだということになれば、当然、私たちは、無意識のうちにも、その「身体」にしがみついてしまいます。いわば、私たちは「身体」にしがみついて生きているわけです。
そこで、困ったことになるのです。この「身体」というのは、永遠に成長していくというものではありません。ご承知のように、二十歳前後をピークとして、こんなふうに放物線を描いて、徐々に衰えていくものです。
ピークを過ぎてしばらくすると、この衰えに気づき始めます。シワも増えれば、シミもできてくる。怪我をしても、なかなか治らなくなってくる。そのうえ、年を追うごとに、一年が短く感じられるようになってくるのです。
子供のときは、一日が長かったように思うのですが、年をとるにつれて一日が短くなっていくような気がいたしますね。皆さんはいかがでしょうか。月日の経つのは速い、一日があっと言う間に過ぎ去ってしまうとは思われませんでしょうか。
ある学者の研究によりますと、六十歳の人は二十歳の人が感じる一年を四カ月にしか感じていないのだそうです。つまり、六十歳の人にとっては、時間が二十歳の人の三倍も速く流れていくということなのですね。それも、年をとればとるほど、時間は速く流れていくようになるのですね。
どうしてそんなことになるのかと申しますと、こういうことらしいのですね。たとえば柱にかかっている時計は、子供にとっても大人にとっても同じ速さで動いています。ところが私たちはみんな新陳代謝という身体の時計を持っています。子供はケガをしても治るのが速い。身体の時計が速く動いているからですね。
ですが歳をとるにつれて、身体の時計がゆっくりになってくる。そのため、歳をとるほどケガの治りも遅くなる。また、身体の時計がゆっくり動くようになってくると、そとの柱時計がだんだん速く思えてくるのです。そのために、歳をとるほど時間が早く流れるように感じてくるのだそうですね。
ですから、そんな「身体」にしがみついている限り、ピークを過ぎれば、「身体」と一緒に、加速度的に、この坂道を転げ落ちていくことになるのです。とすれば、不安を感じないほうが、おかしいのです。
いつもお話しすることですが、仏教では、「私たちの目に見える世界は、目に見えない世界に支えられている」と教えています。ところが、私たちは、そういう「目に見えない世界」があるという教育を受けてこなかったのですね。
実際、学ぶということは大切なことです。学んでいないと、目の前にあっても見えないということがあります。あまり適切な例ではありませんが、以前、こんな実験の話を聞いたことがあります。
生まれて間もない子ネコの首に、前しか見えないようにメガホンのような形の目隠しを付けて、縦縞模様の描かれた箱に入れて育てます。何ヶ月かたって、成長した子ネコを箱から出して歩かせると、椅子の脚のような垂直の障害物はちゃんと避けて通るのに、水平に出ている棒のような障害物にはぶつかってしまうのだそうです。つまり、縦縞しか見ずに育ったネコには、横縞が見えなくなってしまうらしいのですね。
まあ、言ってみれば、私たちも、この猫のようなものですね。小さい頃から、「目に見える世界が全てだ」と教えられて育ちますと、「目に見えない世界がある」とは、想像することさえできなくなってしまいます。そこで、自分とは、この目に見える「身体」のことだと思いこんでしまうのですね。
先日も、あるところで、「人生は、紙おむつから、紙おむつ」という川柳を目にしました。お作りになったのは、お医者さんだということでしたが、人というものを、この「身体」だと考えれば、そういうことになるのでしょうね。お医者さんらしいと言えば、お医者さんらしい見方です。ですが、それが人生だということであれば、歳をとりたくないと思うのは当然ですね。
歳はとりたくない、老人にはなりたくないと思っているのは、大人だけではありません。子供も、そうなのですね。なかには、「老人になりたくないから、長生きしたくない」という子供までいます。子供らしくない考え方だと思われるかもしれませんが、それはみな、知らぬ間に社会から学んでしまったものなのですね。
現代は、いわば「歳をとることを拒絶している時代」ですが、昔はどんな文化にも、「歳のとりかたのお手本」と言いますか、「人としての完成をめざす教え」がありました。中国文化圏には、たとえば、孔子の『論語』の教えがありました。よくご存じかもしれませんが、こういうものです。
「孔子はおっしゃいました。私は15歳で学問で身を立てようと決心し、30歳で一応のところまで行きました。40歳で惑うことがなくなり、50歳で天命を知りました。60歳で何を聞いても理解できるようになり、70歳になって本当に自由になりました」と。(「子曰わく、吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず」)
四十歳を「不惑」、五十歳を「知命」と呼んだりするのは、ここからとったものですが、ここには、「歳をとりたくない」などという発想は全くないのですね。
また、アメリカ先住民(スー族)には、ワイズマン(賢者)をめざして生きる教えがありました。以前「菩提樹」でもご紹介いたしましたが、もう一度お話しいたします。まずは、こちらをご覧になってください。
0歳〜20歳 ベビー(赤ん坊)
20歳〜40歳 ヤングマン(若者)
40歳〜60歳 マン(大人)
60歳〜80歳 オールドマン(老人)
80歳〜 ワイズマン(賢者)
この年齢の一覧表のようなものは、以前、新聞に載っていたものでして、それには、こういう説明がついていました。
「0歳から20歳までをベビーと呼ぶ。18〜19歳で身体が大きくても心が母親を頼っているうちはベビーだと言う。20歳から40歳はヤングマン、若者と呼ばれる。まだ青い、と言う訳だ。では、どれだけ歩けばマン(一人前の大人)と呼ばれるようになるのか。……40歳から60歳までが正しく「マン」と呼ばれるに相応しい年齢なのだ。60歳から80歳までがオールドマン、老人だ。そして80歳を越えた人はワイズマン、賢い人になる。スー族の歴史は、この賢者が導いてきた」と。
現代の私たちは、60歳で定年を迎えますと、後の人生は「おまけ」のように思っておりますが、スー族の教えでは、そうではないのです。人は60歳で現実という夢から醒る。そして、本当の人(ワイズマン)になるのに、あと20年かかる。60歳を過ぎ、マン(ただの人)からワイズマン(賢者)をめざす。そのためにこそ、それまでの60年があったのだ。何か、生きる勇気が湧いてくるような教えですね。
人は、歳をとるとダメになるのではなく、歳をとっていくにつれて完成されていく。そして、ついには賢者と呼ばれるようになり、聖者と呼ばれるようになる。聖者の「聖」という字は、「耳」という字と「呈」という字からできていますが、「呈」というのは「正しく知る」という意味です。ですから、「聖」という字は、「神の声を正しく聞き知る人」という意味なのです。
以前、こういう話を聞いたことがあります。現代社会では、老人がわけの分からなことを話し始めると、「あっ、いよいよ惚け始めたな」と受けとめます。まあ、最近では「老人力がついた」などと言うそうですが、昔、アイヌのひとたちは、老人の言うことがだんだん分かりにくくなると、「神の言葉」を話すようになったと言ったのだそうです。人は、歳をとるにつれて、だんだん神の世界に近づいていくので、「神の言葉」を話すようになる。そのために、一般の人にはわからなくなるのだというのです。
「人生は、神に成っていくプロセスだ」という社会では、自然に起こってくることを、みなその流れのなかで受けとめていくことができるのです。そんな社会でなら、歳をとることに何の不安もないでしょうね。
かつて、人間にとって最高の教えは「人としての完成をめざす」教えでした。ですが、今は、違いますね。今や、世界中が西洋の近代思想に飲み込まれてしまって、「目に見えるものが全てだ」と考えるようになり、「神も仏もない」世界になってしまった。そして、人間は、自然のごく小さな一部であるにもかかわらず、万物で最高のものだと思い込むようになった。いわば、神様、仏様がなくなって、「人間様」になってしまったわけです。
そういう「人間様」の世界に生まれた私たちは、「肉体を養うこと、欲望を満たすことが人生の目標だ」という教育を受けて、小さいときから競争競争で育っていきます。ですが、以前にもお話しいたしましたように、仏の世界に背を向けて、競争に明け暮れているというのは、「修羅」の姿ですね。話を進めます前に、ちょっとこちらの図をご覧になってください。
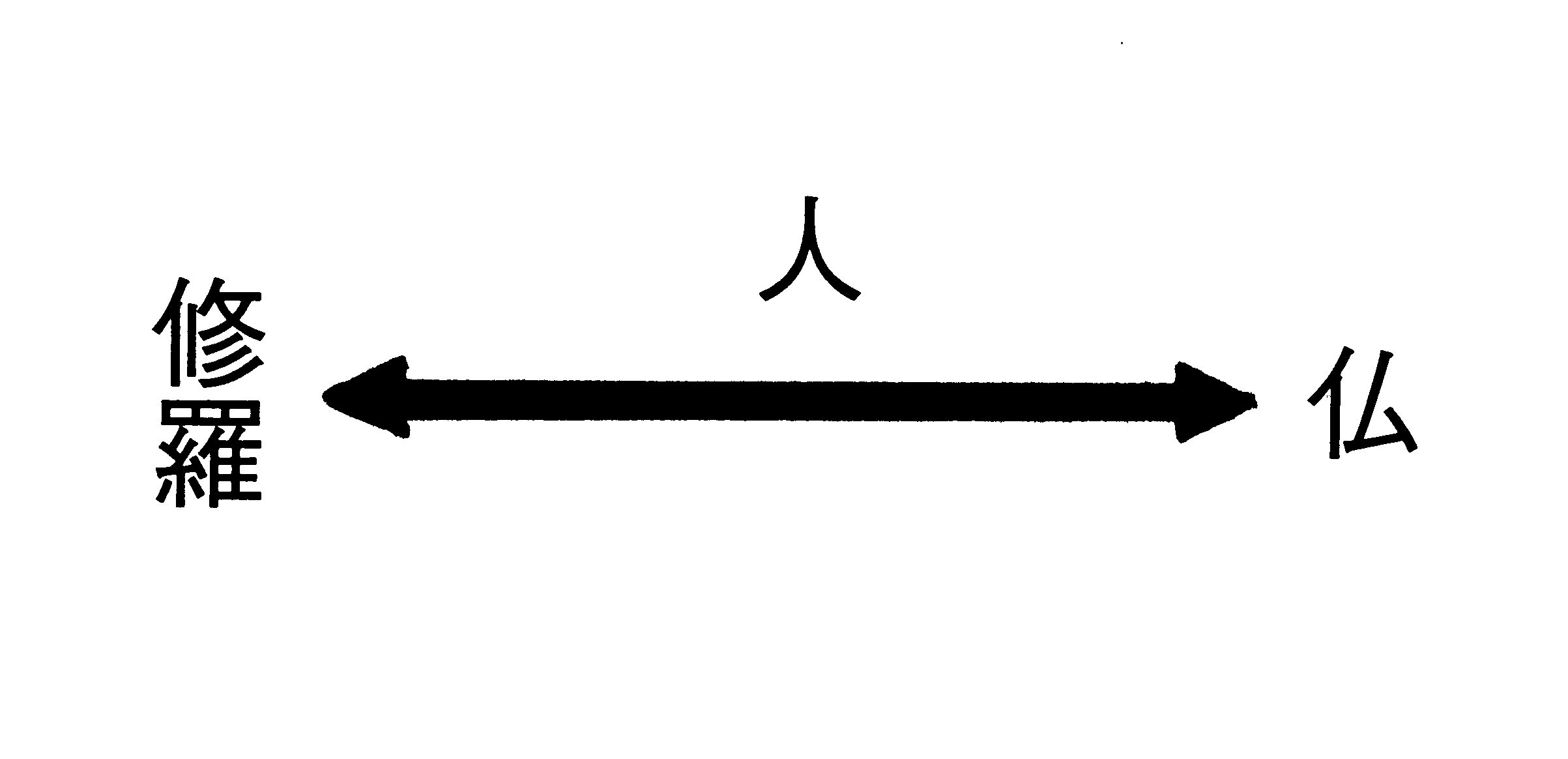 私たちは、この世に人として生まれてきますが、ここに描いてあるように、「人」には「修羅」から「仏」までの幅があるのです。ですが、先ほど申しましたように、「神も仏もない」という現代社会では、こちらの「仏」の世界はないことになる。いわば、私たちは、「仏」の世界を切り捨てたために、「修羅」の世界に閉じこめられてしまったわけです。そういう社会では、こちらの「修羅」の方を向いて生きる道しかなくなるのです。
私たちは、この世に人として生まれてきますが、ここに描いてあるように、「人」には「修羅」から「仏」までの幅があるのです。ですが、先ほど申しましたように、「神も仏もない」という現代社会では、こちらの「仏」の世界はないことになる。いわば、私たちは、「仏」の世界を切り捨てたために、「修羅」の世界に閉じこめられてしまったわけです。そういう社会では、こちらの「修羅」の方を向いて生きる道しかなくなるのです。
私たちは自分が「修羅」の方を向いて生きていても、なかなかそのことに気づきません。以前、ある随筆を読んでおりましたら、こういう言葉が出てきました。「何十年も生きてくれば、この世に神も仏もないことぐらい、経験から分かるものだ」と。
おそらく、金儲けであれ、健康回復であれ、一所懸命に神仏に頼んでも思い通りにならなかったという経験からおっしゃっていることだと思いますが、それは違うのです。自分の思い通りにしようというのは、欲望の満足を目標にしている。つまりは、「修羅」に向かって生きている。「修羅」の方に顔を向けていては、「仏」は見えません。
また、このあいだも、こんな話を聞きました。一代で地位や名誉を手に入れた立志伝中の人とも言える人が、大病を患ったあと、しみじみと、こう言われたといいます。「人生で大切なのは、地位や名誉ではなかった、やっぱり、健康と生き甲斐だった」と。
「そうだ、そうだ、やっぱり健康と生き甲斐だ」と思われるかもしれませんが、それはどうでしょうか。「健康が大事、生き甲斐が大切」というのは、目に見える身体の「健康」が大事、死ぬまで退屈しないための「生き甲斐」が大切ということではないのでしょうか。とすれば、それは握っていた手を持ち替えただけで、「身体」にしがみついていることに変わりはないのですね。
「仏」に背を向けていると、「修羅」の袋小路から出られない。それは、歳をとったら不幸になるという世界です。
確かに、「健康」も大事ですし、「生き甲斐」も大切です。ですが、それが全てではありません。実際、私たちは、健康であって、生き甲斐があっても、どこか満たされないものがある。魂のうずきがある。本当は、そこが大切なところです。
「健康」が大事、「生き甲斐」が大切と言っても、私たちはみな、いずれ病気になって、動けなくなる日がまいります。死の床から、愛しい家族の顔を、見上げる日がくるのです。そんなときにも、まだ「生き甲斐」というものに意味が残っているのでしょうか。
私たちには、「健康」や「生き甲斐」よりも大切なことがあるのです。それは、「身体」にしがみついて、この放物線を生きるのではなく、修羅の世界に背を向けて、「仏」への道を歩み続けることなのです。この道は、歳をとるにつれて深まっていく道です。身体と一緒に衰え滅びる道ではないのです。
私たちが歩むべき道は、こちらの道です。「人として歳をとる」というのは、こちらの方に向かって生きていくことです。本当の幸せへと続く道がそこにある。そのことを教えているのが仏教なのです。
仏教というのは、「仏の説かれた教え」でありますが、それは他ならぬ「仏に成るための教え」です。「仏」とは、インドの言葉で「ブッダ」と言います。ブッダとは、「目覚めた人」のことです。「仏」とは、人間の完成された姿です。人と生まれたものが、人としての完成をめざして生きる。それこそが、人の道ですが、その、人としての完成をめざして生きることを、「仏道を歩む」、「信仰に生きる」というのですね。
私たち門徒にとって、「信仰に生きる」とは、「聞法」と「お念仏」の日暮らしをするということです。「聞法」とは、「仏の教えを聞く」、「仏法を学ぶ」ことです。
仏様の方に顔を向けて、「聞法」と「お念仏」の日暮らしをするうちに、だんだんと仏様に近づいていく。「仏様」とは、これまでにも何度もお話しいたしましたように、「本当の自分」のことですね。ですから、「人として歳をとる」というのは、「本当の自分」になっていくということなのです。
信仰の生活とは、「本当の自分」を求めて歩み続ける旅のようなものです。仏典や信仰の書というのは、みなその旅のガイドブックです。では、その旅の道筋は、どうなっているのでしょうか。ガイドブックを読むだけでは旅をしたことにはなりませんが、今日は、この旅の道筋をたどりながら、「信仰に生きる」とはどう生きることかを、お話しさせて頂こうと思います。
人が本当の人になっていく、その旅の道筋を、たとえば禅宗では「十牛の図」というもので表しています。言葉で聞くより、絵を見た方が分かりやすいということもありますから、この図を借りてお話ししたいと思います。
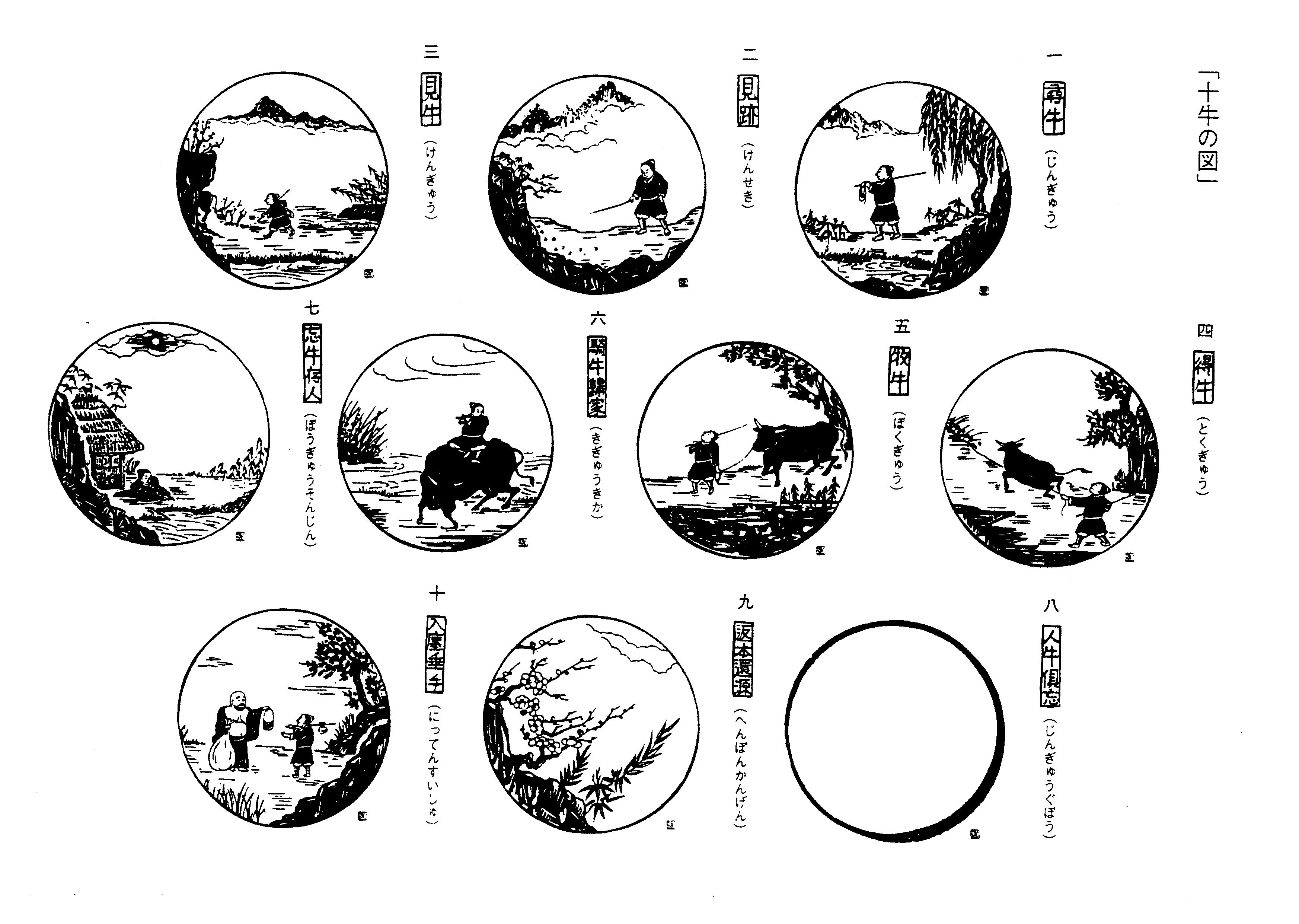
「十牛の図」は、有名な絵ですから、ご覧になったことがおありかもしれませんが、失われた牛を探し求める姿を描いた10枚の絵からなっています。皆さんのお手元の資料に載せておきましたので、そちらをご覧になりながら、お聞き頂きたいのですが、これは、12世紀頃に中国の廓庵禅師の描かれたものです。
第1図は「尋牛」(じんぎゅう)という題の絵です。一人の童が、見失った牛を探しにでかけます。ここで「牛」というのは「仏性」のこと、「本当の自分」のことです。「本当の自分」への旅が始まります。仏の方へ顔を向けたということですね。
第2図は「見跡」(けんせき)です。童が牛の足跡を見つけました。仏法を学ぶことによって、「本当の自分」とは何かという手がかりを得たということですが、ここではまだ、頭で理解しただけです。ここで終われば、教養としての仏教、学問としての仏教です。
第3図は「見牛」(けんぎゅう)です。絵の左端に、牛の尻尾が見えていますね。仏の教えを実践するなかで、「本当の自分」の姿をちらりとかいま見た。それが、これです。その瞬間を、禅宗では「見性」、真宗では「廻心」と呼んでいます。浄土からの光を、木漏れ日のように垣間見た瞬間です。
さらに進んで、第4図から第6図までは、牛を捕まえて馴らし、「本当の自分」とひとつになるまでの世界です。
そして、第7図には牛がいなくなり、第8図では人もいなくなります。これは、「本当の自分」というものも、「本当の自分」とひとつになった「自分」というものもなくなっていく、つまりは、「自分」という思いそのものが無くなっていく世界を表しています。
この第8図は「円相」とも言います。禅宗の和尚さんがよくお描きになりますので、ご覧になったことがおありでしょう。道元禅師は、「仏道をならふといふは、自己をならふなり、自己をならふといふは、自己を忘るるなり」とおっしゃっていますが、その自己を忘れて「無我」になった、「空」になった境地がこれです。
「自分」というものが無くなったとき、命がまっさらになり、命だけが輝いている世界になる。やはり花は花に見え、山は山に見えるが、もとの花や山ではない。全てが命に輝いている。それが、第9図の「返本還源」(へんぽんかんげん)です。
そして、この旅のはてに行き着くのが、第10図の「入廛垂手」(にってんすいしゅ)です。「廛」というのは、人々の行き交う街のこと、「垂手」というのは「手を差しのべる」という意味です。ですから、「街に入って、手を差しのべる」というのが、「入廛垂手」という言葉の意味です。
絵を見ますと、ひとりの翁が、童に手を差しのべています。この翁は、第1図で牛を探しに出た童です。「悟り」を得たあと、再び俗世間に戻ってきて衆生を救う姿が、これだと言われています。
「衆生を救う」というのは、「衆生の顔を仏の方に向けてやる」ということでしょう。とすると、ここに翁と向かい合っている童は、このあとどうなるかと言えば、第1図の童と同じ道をたどることになる。「十牛の図」の終わりは、新たな「十牛の図」の始まりです。童は、翁に出会わないと、翁への道を歩み始めることはありません。このことは、非常に大切なことだと思いますね。
仏教では、仏の世界へ生まれていく姿を「往相」と言います。つまり、自分が「本当の自分」になっていく姿が「往相」です。また、仏の世界から俗世間に戻ってきて衆生を救う姿を「還相」と言います。「十牛の図」で言えば、童が翁になっていく姿が「往相」で、翁が童に手を差しのべている姿が「還相」です。自分が救われ、人を救っていく。それが人として完成された姿だというわけです。
さて、これで一通り「仏道を歩む」という旅の道筋は分かりました。そこで、改めて、ご一緒に考えてみたいのです。この「十牛の図」を見ていると、「仏道を歩む」というのは、非常に難しいことのようにも思えますが、いかがでしょうか。「本当の自分」になるなんて、大変なことだ。「悟る」などということは、自分にはとうてい不可能だと思ってしまいますよね。ですが、「仏道を歩む」、「信仰に生きる」ということは、そんなに難しいことなのでしょうか。
そこで、もう一度、「十牛の図」をよく見て頂きたいのです。この図を、もう少し別の角度から、読み解いてみます。第1図から第7図までは、牛を探し、牛を見つけて、家につれて帰ったが、いつの間にか牛がいなくなったという絵ですね。実はです、ここまでは、まだ「夢」なのです。
何かになりたい、何かを手に入れたいと、走り回っているのは修羅です。何かになれば幸せになれる、何かを手に入れたら幸せになれると思っているのは、修羅の「夢」なのです。夢から醒めたつもりが、まだ夢のなかにいたのです。
「本当の自分」を見つけよう、「本当の自分」になろうと懸命に努力して、やっと「本当の自分」になったと思ったら、「本当の自分」が見あたらない。そのとき、夢から醒めた。それが、第8図の「円相」です。これは、夢から醒めた曇りのない目です。そして、その目に映った世界が、第9図、あるがままの自然の姿です。
目が醒めたら、寝床から起きあがって、平々凡々な日常の生活に戻る。それが、第10図の「入廛垂手」です。この絵の翁こそが、いわば「本当の自分」です。この翁は、何をしているのか。何もしていません。ただ生きているのです。ただ生きているだけなのですが、翁に触れる人がみな救われていく。翁が童に何かを与えているところが描かれているのは、そのことを表したものです。
先に、「仏道を歩むとは、本当の自分になっていくことだ」と申しましたが、実は「なっていく」のではない。「本当の自分」は、どこか遠くにいるわけではなくて、「今、ここに」いるのです。「本当の自分」になっていくと考えるから、難しく思えるので、実際には、「今、ここに」いる「本当の自分」に気づくだけなのです。
では、どうすれば気づけるのかと言えば、なにも難しいことをする必要はありません。仏の方に顔を向けて生きているだけでよいのです。仏の方に顔を向けて生きておれば、気づきはむこうからやってきます。その、むこうからやってくる「気づき」まで、自分で手に入れようとするから、話が難しくなるのですね。
「仏の方に顔を向けて生きる」というのは、一瞬一瞬の「今」を感じ続けて生きることです。それが「信仰に生きる」ということなのです。何か、分かったような分からないような話だと思われるかもしれませんが、もう少し、お付き合いください。
以前にもお話しいたしましたが、私たちは「今、ここに」いる。ですが、修羅の世界の方に顔を向けて生きていると、「今、ここに」いないということになる。
どういうことかと言えば、身体は「ここ」にあっても、心が「今」にないのです。心は、過去を誇ったり悔やんだり、未来に期待したり不安を抱いたりして、決して「今」のこの一瞬にとどまっているということがありません。
つまりは、心が、頭のなかで思考に引きずり回されて、過去へ未来へと走り回っている。そんな私たちは、「今、ここに」はいない、「今、ここに」いる「本当の自分」を見失っているということです。
「今ここにいる自分」こそ「本当の自分」です。「本当の自分」は「仏」です。ですから、「今」をきちんと感じて生きていることが、「仏の方に顔を向けて」生きているということなのです。それが、「目覚めている」ということです。つまりは、第8図の「円相」の世界ですね。
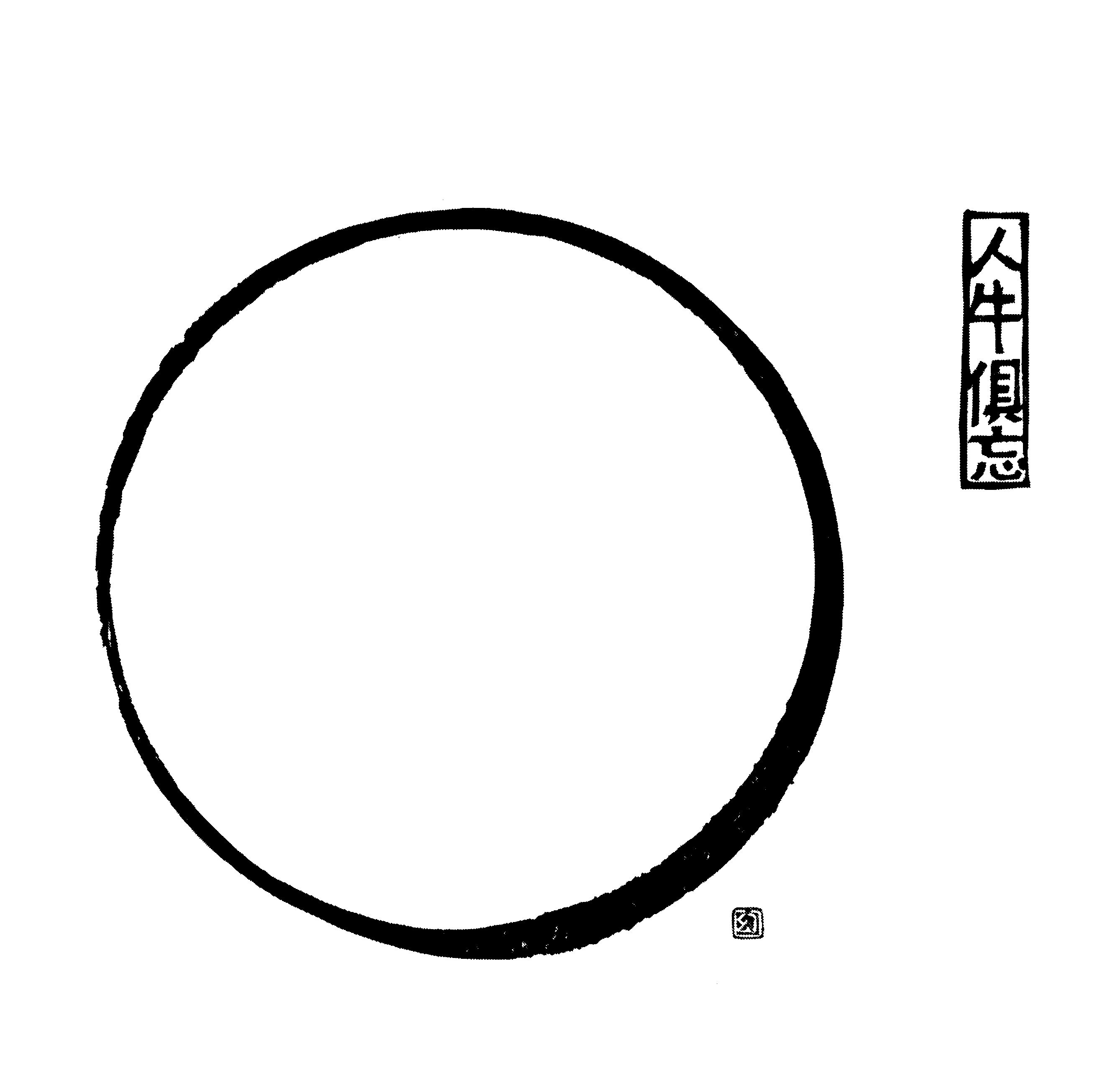 心が「今、ここに」あると、たとえば、お茶を飲んでいるときには、きちんとお茶を味わって飲むことができます。茶碗の手触りを感じ、重さを感じ、お茶のぬくもりを感じ、香りを感じ、口に含んだときの味を感じ、のど越しを感じる。そこには、「今」を感じていること以外に何もありません。
心が「今、ここに」あると、たとえば、お茶を飲んでいるときには、きちんとお茶を味わって飲むことができます。茶碗の手触りを感じ、重さを感じ、お茶のぬくもりを感じ、香りを感じ、口に含んだときの味を感じ、のど越しを感じる。そこには、「今」を感じていること以外に何もありません。
ところが、心が、頭のなかで思考に引きずり回されていると、たとえば、「安物の茶碗で、まずい茶を飲ませよって、礼儀を知らんのか、それとも、人を馬鹿にしとるのか」というようなことになり、お茶ひとつまともに飲めません。
たとえて言えば、頭のなかで考えていることは、「生の自然」ではないのです。思考というものは、分別や欲望で着色された「加工食品」のようなものです。そんな加工食品ばかり食べている心は、本当の自然の味を知りません。
「生の自然」は、今感じていること、つまり感覚にあるのです。「今」を感じるということは、「生の自然」を感じるということです。ですから、心が、「今」を感じているとき、その心には、あるがままの自然の姿が映っています。それが、第9図の「返本還源」(へんぽんかんげん)の世界です。
 以前にも何度かご紹介いたしました、星野富弘さんの詩に、こういうのがあります。「今日は何もしないでいよう、そう思った日ほど、花が私に近づく」。この花を、こう描いてやろう、ああ描いてやろうと、考えている間は、花そのものが見えていない。思考を捨てて、感覚を澄ませば、気づきのほうからやってくるのです。
以前にも何度かご紹介いたしました、星野富弘さんの詩に、こういうのがあります。「今日は何もしないでいよう、そう思った日ほど、花が私に近づく」。この花を、こう描いてやろう、ああ描いてやろうと、考えている間は、花そのものが見えていない。思考を捨てて、感覚を澄ませば、気づきのほうからやってくるのです。
また、こういう詩もあります。「何のために生きているのだろう、何を喜びとしたらよいのだろう、これからどうなるのだろう。その時、私の横に、あなたが一枝の花を置いてくれた。力を抜いて、重みのままに咲いている、美しい花だった」。この詩も、同じことを言っているのですね。
「今」という世界は、光に満ちた世界、仏の世界です。本当に「今」を感じられたら、「今」が輝いてきます。その輝きが心を満たすと、私たちは、満ち足りた幸せを感じます。そして、満ち足り、満ち足りしているうちに、その輝きが、自分の外へあふれ出ていきます。信仰に生きる人のまわりが明るいのは、そのためですね。
このあいだ、河村とし子さんという方のお書きになった『み仏様との日暮らしを』という本を読みました。この河村とし子さんは、クリスチャンだったのですが、事情があって、姑さんと暮らすようになる。姑のふでさんは、小学校も出ていない無学文盲の方でしたが、お念仏一筋の方だった。
そのふでさんは、いつも阿弥陀様に手を合わせて、「あなたがそこにただ居るだけでまわりが明るくなる。あなたがそこにただ居るだけで人々の心が安らぐ。そんなあなたに私はなりたい」と、ひとりごとをつぶやいていたそうです。
ところが、ふでさんは、その願い事そのままの人だった。ふでさんが、そこにただ居るだけでまわりが明るくなる。ふでさんが、そこにただ居るだけで人々の心が安らぐ。ふでさんに触れる人は、みな幸せを感じた。
そんなお姑さんのそばで暮らされた河村とし子さんは、ふでさんから教えを受けたわけでも、躾を受けたわけでもないのに、こんな人になりたいと願われて、とうとう真宗門徒になってしまわれた、という話でした。
信仰に生きるということは、別に何かになるとか、何かをするとかいったことではなくて、仏様の方に顔を向けて日暮らしをするだけ、平々凡々とした生活の一瞬一瞬に、「今」の輝きを感じて生きるだけなのです。
その生活が、人を救い、また、他の人が救われていくご縁となる。信仰の生活には、最初から、往相と還相が、ふたつながらに成就されている。それが、第10図の「入廛垂手」(にってんすいしゅ)の世界、童と翁の世界です。
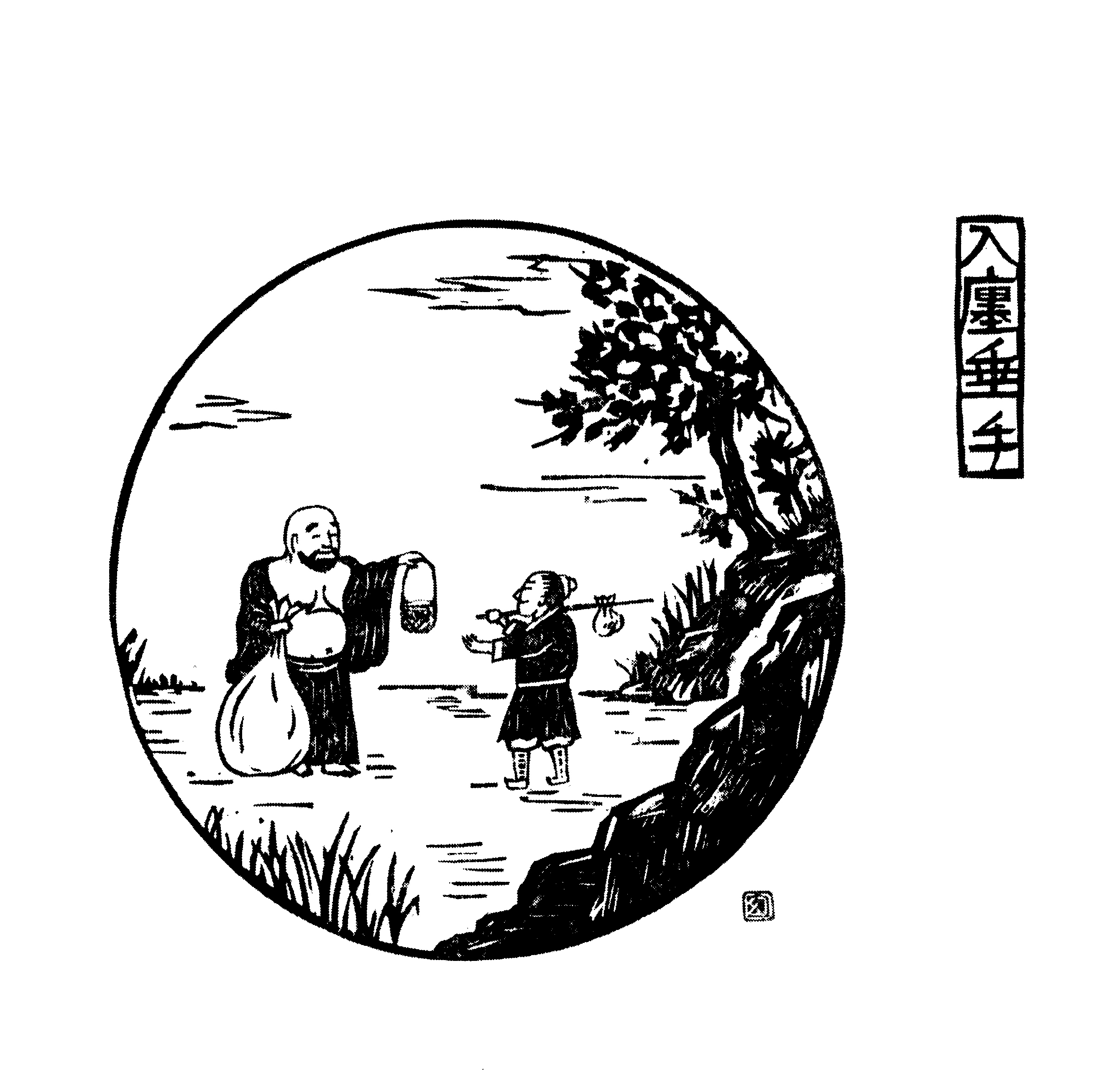 本日の法話の講題は、この絵からとりました。それは、信仰に生きている人の姿が、この「童と翁」のいる絵に集約されていると思ったからです。さきほど、「童は、翁に出会わないと、翁への道を歩み始めることはありません」と申しましたが、もし、童が、老人と出会っていたら、はたして、老人への道を歩み始めたでしょうか。そうではないでしょう。現代の子供たちが、老人にはなりたくないと言っているのを思い出してください。老人は、童の憧れとはならないのです。
本日の法話の講題は、この絵からとりました。それは、信仰に生きている人の姿が、この「童と翁」のいる絵に集約されていると思ったからです。さきほど、「童は、翁に出会わないと、翁への道を歩み始めることはありません」と申しましたが、もし、童が、老人と出会っていたら、はたして、老人への道を歩み始めたでしょうか。そうではないでしょう。現代の子供たちが、老人にはなりたくないと言っているのを思い出してください。老人は、童の憧れとはならないのです。
童が、翁を理想として、こんな人になりたいと思うのは、翁が老人だからではありません。翁が、理想の童、本物の童だからなのです。翁は、一瞬一瞬を、まっさらな目で、初めて見る世界のように見ている。完全に自由で、何をしていても幸せなのです。別の言葉で言えば、翁にとっては、全てが一如との「戯れ」、愉快な「遊び」となっているのです。仏教で「遊戯三昧」というのは、この境地のことです。
仏様の方に顔を向けて生きる日暮らしは、何をしていても幸せという生活です。何をしていても幸せということは、何もしていなくとも幸せということです。
心理学者の河合隼雄さんの本に、こんな話がありました。カウンセリングを受けにこられた方が、「私のように何の生き甲斐もない者が、どうして生きていなくちゃならないんだ」と、言われた。そのとき河合さんは、こう言われた。「生き甲斐があって生きている人は、それは非常に結構な話ですが、生き甲斐があって生きているのは、あたりまえです。生き甲斐も何もなくて生きている人というのは、それはすごいのではないですか」と。
河合さんは学者ですから、それ以上のことはおっしゃいませんが、生き甲斐も何もなくとも平気で生きておれる人というのは、信仰に生きている人だけなのですね。
私たちは、常に、何かしていないと生きておれません。何かしていると気が紛れるのです。ですが、「気が紛れる」というのは、本当に大切なことから目をそらせている、「今」という世界から、心がさまよい出ているということではないのでしょうか。「ただあるだけ」というのは、やっぱり、「すごいこと」なのです。
さて、本日のお話しも、終わりに近づいてまいりました。そろそろ店仕舞いにかかります。
「信仰に生きる」というのは、「仏の方に顔を向けて生きている」という、ただそれだけのことです。「本当の自分」になろうと努力することではないのです。
何かになろうとしていると、合掌していても、肩や肘に力が入ってしまいます。神社仏閣に詣でて、お金が欲しい、健康になりたいと祈願している人の合掌を見ていると、みな肩肘に力が入っています。それは、仏の方に顔を向けている人の合掌ではありません。修羅の合掌です。仏教彫刻でも、肩肘に力の入った合掌をしているのは、奈良の興福寺にある阿修羅像だけですよ。
それでも、「なりたい、なりたい」という思いが消えないときには、河村ふでさんのように、仏様に手を合わせて、「あなたがそこにただ居るだけでまわりが明るくなる。あなたがそこにただ居るだけで人々の心が安らぐ。そんなあなたに私はなりたい」と、おっしゃってみたらどうでしょうか。それも、また、仏の方を向いていることになると思うのです。
大切なのは、「仏の方に顔を向けて生きている」ということです。ですが、私たちは、すぐにきょろきょろしはじめますね。そこで、「お念仏」があるのです。「お念仏」というのは、「南無阿弥陀仏」と称えることですが、「お念仏」を称えるというのは、仏の名前を呼ぶということです。仏の名前を呼べば、仏が戻ってくる、「今」が戻ってくるのです。
私たちは、腹が立ったり、悲しかったりすると、胸が苦しくなりますが、そんな時、よくよく観察してみると、息が乱れていたり、息が止まっている。だから、苦しいのです。「お念仏」を称えていると、その「息」が整ってくる。「息」が整うと、「生き」が整うのです。「生き」が整えば、「今」が戻ってくるのです。「今」が戻ってくると、一瞬一瞬が輝きます。そして、その輝く世界のなかに、気づきがもたらされるのです。
思いますに、信心の功徳というのは、日常のなんでもないことに感動し、喜べるようになるということでしょうね。確かに、日常生活の大半は、ありふれた出来事で占められています。今日することの9割までは、昨日したことと同じなのです。ですが、本当は、たった一度限りの「今」の積み重ね、それが、人生なんですね。「今を感じる」というのは、その、二度と帰ってこない「今」に気づくこと、信仰の生活とは、その「今」に気づき続けながら生きることなのですね。
「身体」にしがみついて、健康だ、生き甲斐だと、歳をとっていけば、不本意ながらも「老人」になってしまう。ですが、仏の方に顔を向けて、「今」を感じながら歳をとっていけば、健康であってもよい、なくてもよい、生き甲斐があってもよい、なくてもよい、何があってもなくても、平気で生きておれる人になる。年齢とは関係なく、「翁」とは、そういう人のことだと思います。
さて、本日お話し申しあげたいことは、これだけでございます。どうぞ、皆さん、歳をとったらダメだとか、若さにチャレンジなどとおっしゃらずに、ご一緒に、肩から力を抜いて、お念仏を称えながら、心安らかに歳をとっていきましょう。
私たちの人生は、「紙おむつから、紙おむつ」ではない。童から翁になる。童から、本物の童になる。本物の童。それが私たちの本来の姿、仏の姿なのですね。
本日は、長い間、お付き合い下さいまして、有り難うございました。またご一緒に聞法させて頂きたいと願っております。南無阿弥陀仏。
紫雲寺HPへ