義兄は脳腫瘍でした。病名を知ったのは昨年の11月でした。初めて診断を受けましたときに、「年内もたないかもしれない、せいぜい3ヶ月というところ」と言われまして、非常にショックを受けました。入院して手術を受けましたが、若い分だけ進むのものも速いわけでして、結局、私たちは命自身の選んだ道を受け入れるしかありませんでした。
無我夢中で過ぎ去った4ヶ月のようにも思いますが、あれほど真剣に「いのち」を見つめて過ごした日々はなかったと思います。思えば、あの4ヶ月は、義兄が私たちにくれた最後の大きな贈り物だったのですね。
義兄は、本年の3月4日に、お浄土に帰っていきました。享年47歳。法名は「還相院釈了然」。決して長い人生ではありませんでしたが、義兄は、今生で為すべきことは全て為し遂げて逝った。仏様の目から見れば、やりのこしたことは何も無かったと、私は信じております。
本日は「永代経法要」でございます。御案内いたしておりますように「悲しむ力…仏のまなざしのなかで」という題で、しばらくお話し申し上げたいと思っておりますが、これも義兄の結んでいってくれたご縁と存じます。
あれから200日ほどたちました。慌ただしい日常のなかで、すでに沢山のことを忘れ始めていますが、折に触れて、涙とともに、思い出されることがあります。仏法にご縁を頂いたお陰で、涙するごとに、その涙の流れ行く先が思い出されるのです。涙の川は、本願の海に流れ込んで行くということをです。本日は、その話をさせて頂こうと思います。
さて、仏教では、私たちの暮らす世界を「娑婆」と呼んでいます。「娑婆」とは、苦しみの世界という意味ですが、最近、新聞やテレビを見ておりますと、つくづく「娑婆」であることを感じますね。
皆さんは、毎日、新聞やテレビをご覧になって、どうお感じになっておられますでしょうか。たとえば、緑十字の薬害エイズ問題、脳死法案問題、東海村の原子力事故、各地の警察官不祥事、雪印乳業の食中毒、三菱自動車のリコール隠し、ストーカー犯罪、保険金殺人、青少年の凶悪犯罪などのニュースをご覧になって、どうお感じになっておられるでしょうか。
みんな、根っこは一つではないのでしょうか。私は、そう感じますね。事件の顔はそれぞれに違いますけれど、そこには共通して欠けているものがある。その欠けているものとは、「人の悲しみを自分の悲しみとして感じる力」です。
これは何も、犯罪的な場面にだけ言えることではありません。この「人の悲しみを自分の悲しみとして感じる力」は、社会の全ての場面で、非常に希薄になっている。「いのち」が非常に軽く扱われるようになっているのは、そのためだと思うのです。
子供の世界でも、例外ではありませんね。大人の世界の病気が、子供たちをも蝕んでいる。この3年の間だけでも、青少年の凶悪犯罪は、私の数えた範囲で100件以上ありました。そのほとんどが、殺人と殺人未遂です。
先月にも大分で、15歳の高校生が隣家の一家6人を殺傷するという事件がありましたが、春には、「人を殺す経験がしたかったのだ」とか、「人の肉がどんな味か食べてみたかった」というような、異常な事件もありましたね。私たちがどんな社会に暮らしているのか、暗澹とした思いさえいたします。
10年前には、何を考えているのか分からない若者たちに対して「新人類」という言葉ができましたが、今や「新人類」を通り越して「脱人類」という言葉まであるのだそうです。確かに、若者たちの言動には、私たちの理解を越えたところが多い。とはいえ、私たちが決して忘れてはいけないのは、そういった子供たちを育てたのは、私たち大人なのだということです。
私たち大人には気づいていないことが沢山あります。分かりやすいところで言えば、たとえば、最近では小学生まで携帯電話を持っているという非難がある。しかし、考えてみれば、子供の欲しがるような新型モデルを次々に発売して儲けているのは大人なのです。
街に出ても、歩いているのは若者ばかりですが、よく見れば、街に並んでいるのは、その子供たちの財布を狙っている店ばかりです。消費を煽って、子供をスポイルし、それで潤っているのは大人なのです。そんな消費文化の大波に流されて、ついには援助交際という少女売春にまで落ちていく子供もいる。
大人に責任のないこととは、とても思えませんね。私たち一人一人が大切なことに気づかないと社会は変わらない、子供は変わらないのですね。「子供には、小言を言う人より、手本になる人のほうが必要だ」と言った人がいますが、本当にそうだと思いますね。
状況はどんどん悪くなっているように思います。それは、「気づけよ、気づけよ」という、仏様からのお催促でもあるのですが、仏様に背を向けて生きている私たちは、なかなかそのことに気づけません。
私たち大人は、どこか惰性で生きているところがありますから、まこと自分自身がつまづかないと気づかない。ひょっとすると、つまづいて倒れていても気づかないのかも知れませんが、そんな大人のおぼつかない足取りを、子供はちゃんと見抜いている。そして、大人の思いもしない方向から、問いかけてくることになる。たとえば、「なぜ人を殺してはいけないのか」と問いかけてくるのです。
3年前に、オウム真理教の事件や神戸の少年の事件がきっかけになって、テレビ討論会が開かれたことがありますが、その席で、14歳の中学生の出した質問が、これでした。「なぜ人を殺してはいけないのですか?」という問いです。ご覧になった方もおられると思いますが、そのテレビ討論会に同席していた、知識人と呼ばれる大人たちは、その問いかけに、うまく答えられませんでした。
あのテレビ討論会があってから、マスコミを通じて、いろんな人が、この問いに答えようとしてきましたが、なかなか「これは」という答えが出てこないのです。
たとえば、ある知識人は、こう言っています。「人を殺してはいけないという絶対的な理由は無いけれど、だからといって、この決まりを破ってもよいということになれば、社会が無茶苦茶になってしまうから」と。
また、ある人は、こう言っています。「私は人を殺してはいけないという感覚を持っているけれど、人を殺してはいけないということの根拠がわかっているわけではない」と。
結局は、「人を殺してはいけないという理由はわからない」けれど、それが社会を維持するための「ルール」なんだ、それが「常識」なんだというところに戻ってきてしまうのです。
もちろん、社会を維持するためには、法律や道徳や倫理といった「ルール」が必要ですし、そういったルールをいちいち思い出さなくとも感覚的に分かっているという「常識」も大切です。ですが、そういったルールは、時代とともに変わるものですし、国によっても違います。つまりは、法律や道徳や倫理は、相対的なものであって、「人を殺してはいけない」ということへの絶対的な根拠にはならないのです。
では、「殺人を禁じる絶対的は根拠はないのか」と言えば、そうではありません。「絶対的な根拠」はあるのです。それは、煩悩を超えた世界、「仏の世界」にあるのです。つまりは、私たちが切り捨ててきた世界にあるのです。現代の知識人に答えられなかったのは、そのためです。
いささか話が難しくなってきましたので、例によって図をご覧になって頂きながら、ご説明したいと思います。これは何度もご覧になって頂いた図ですが、この小山のように盛り上がっているのが、私たちの「いのち」の全体像です。ちょうど、海底から立ち上がって海に浮かぶ島を、横から見たような図です。
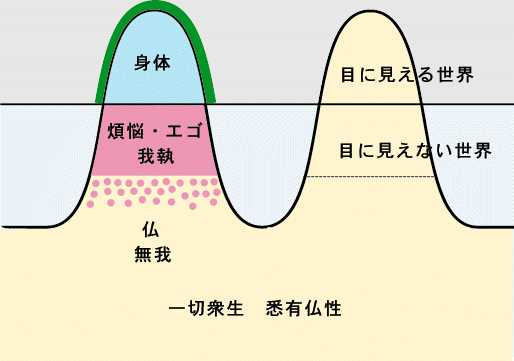
海面から上が「目に見える世界」で、海の上に浮かぶ島の部分は、私たちの「身体」に相当します。そして、海面から下の「目には見えない世界」には、「煩悩に支配されている領域」と「煩悩に支配されていない領域」があります。
「煩悩に支配されている領域」は「我執の世界」「エゴの世界」です。「他の誰よりも我が身が可愛い」という思いは、ここから湧いてきます。そして、その下の「煩悩に支配されていない領域」は「無我の世界」「仏の世界」です。ここは、私たち現代人が切り捨ててきた世界ですね。私たちの「いのち」の全体像は、この「仏の世界」からしか見えないのです。
別の言葉で言えば、「エゴの視点」からは、「いのち」の真実は見えない。そんな「エゴ」を離れた「仏の視点」に立って、初めて「いのち」の真実が見える、ということです。
その「仏の視点」からみれば、私たちはみな、「いのち」の深いところでつながっている。私たちは、「ひとつ」です。目に見える世界では、一人一人がバラバラに生きているように見えても、本当は、みんなが「ひとつのいのち」を生きているのです。あらゆる生き物には、みな、仏様の「いのち」が宿っている。「一切衆生、悉有仏性」というのは、このことですね。
「仏の視点」から見れば、あなたの喜びは、私の喜び。あなたの悲しみは、私の悲しみなのです。あなたを傷つけることは、私を傷つけることなのです。あなたは、私なのです。だからこそ、人を殺してはいけないのです。これは、社会のルールではありません。永遠に変わらない「いのちの真実」です。
いつもお話しいたしますように、私たちは、自分では意識していなくとも、みんな人間としての完成を目指して、生まれ変わり死に変わりしている、「いのちの仲間」なのです。仏教の言葉で言えば、私たちはみな、仏を目指して生きている「菩薩」です。私たち門徒が、互いに「同行」と呼び合っているのは、そのためですね。
ですからね、皆さん。もしも、「なぜ人を殺してはいけないのか」と問う人がいたら、どうぞこのことを思い出して頂いて、「いのちの仲間だから」と、お答えになってください。その一言が、きっと世界を変えていくと、私は信じています。
仲間は、殺し合わない。仲間は、奪い合わない。仲間は、欺き合わない。それが、仲間ですね。私たちが、同じ時代、同じ世界に生まれてきたのは、殺し合い、奪い合い、欺き合うためではないのです。私たちが、同じ時代、同じ世界に生まれてきたのは、互いに助け合い、互いに学び合うためなのです。私たちは「いのちの旅仲間」なのです。「仏教」は、そのことを教えようとしているのです。
しかしです。悲しいことに、私たちには、なかなかこの戒めが守れないのですね。私たちは「自分がされたくないことを、他人にしてはいけない」と思っていますし、「自分が殺されたくないのだから、他人を殺してはいけないのだ」と思っているのです。ですが、実際には、「自分が殺されたくないから、相手を殺す」ということだって、ありうるのです。特に、戦場などでは、そうでしょうね。
戦場と言いますと、このあいだ、中国での戦争体験を集めた本を読みまして、そのなかに、こういう話がありました。当時は、初年兵の教育として、捕虜の試し切りをさせていた。ところが、あるとき一人の僧侶がそれを拒否したのです。「仏教徒としてできません」と拒否したというのです。
まあ、そこには、これだけしか書かれていませんでしたけれど、私は考え込んでしまいました。その僧侶は、「仏の視点」から見て、拒否した。それは、確かに立派だったと思います。ですが、私が考え込んでしまったというのは、その先のことです。
僧侶は拒否した。では、その捕虜は殺されなかったのかと言えば、そうではないでしょう。その僧侶の目の前で、他の兵が、首を斬ったに違いないのです。そのとき、僧侶は、何を感じたか、です。自分は殺さなかったが、それでも結果は変わらなかった。僧侶は、その捕虜の死を、自分自身に無関係なこととは、とても思えなかったでしょうね。
「いのちあるものを殺してはいけない」ということには、絶対的な根拠がある。絶対的な根拠はあるのだけれど、私たちは、それを守れない。守ろうとしても、守れないことがあるのです。仏教で「宿業」というのは、そのことです。
ですがね、そういう悲しい私たちの姿を、じっと見つめるまなざしがあるのです。そんな世界の在り方そのものを悲しむまなざし、仏のまなざしがあるのですね。その仏のまなざしのなかでこそ、宿業の身のままで救われていく世界が開かれてくるのです。加害者も被害者も、ともに救われていく世界が開かれてくるのです。

そういう世界を具体的に知って頂くために、ひとつご紹介したい本があります。『彩花へ…「生きる力」をありがとう』という本です。あの神戸の事件の被害者の一人、山下彩花(あやか)ちゃんのお母さんが書かれた本です。この本は、素晴らしい本でして、ぜひ皆様にもお読み頂きたいと思いますが、そのなかに、お母さんの京子さんは、加害者のA君にあてて、次のような文章を書いておられます。
「今、あなたに会いたいような、絶対に顔も見たくないような複雑な思いでいます。私たちの宝物だった、たった一人の愛娘を、あんなかたちで奪い取ったあなたの行為を、決して許すことはできません。 母であるがゆえに、娘がされたことと同じことをしてやりたいという、どうしようもない怒りと悔しさと憎しみがあります。 その一方で、これもまた母であるがゆえに、どんなに時間がかかってもあなたを更生させてやりたいと願う気持ちがあることも嘘ではありません。 (中略) 罪を罪と自覚し、心の底からわき出る悔恨と謝罪の思いがいっぱいつまった、微塵のよどみもない澄みきった涙を、亡くなった二人の霊前で、苦しんだ被害者の方々の前で流すことこそ、本当の更生と信じます。 それまで、共に苦しみ、共に闘おう。あなたは私の大切な息子なのだから」と。
こういう文章を読むと、「なぜ人を殺してはいけないのか」という質問など、影が薄くなってしまうような気がしますが、この文章に続けて、京子さんは、こう書いておられます。「こんな気持ちは、加害者と被害者という立場を超えた、自分でも説明のつかない感情です。しかし、すべて私の正直な思いなのです」と。
世界というのは、私たち一人一人の心そのものです。「目に見える世界」に意味を与えているのは、私たちの解釈なのです。ところが、その世界を解釈する心を、私たちは二つ持っているのですね。その二つの心というのは、「煩悩に支配されている心」と「煩悩に支配されていない心」です。先ほどの言葉で言えば、「エゴの視点」と「仏の視点」です。
「エゴの視点」から見れば、世界は、誰もが自分の利益を求めて争っている場に見える。「勝つか負けるか、食うか食われるか」の世界に見える。つまりは、「弱肉強食」の世界に見えるのです。
「エゴの視点」から見れば、「やられたら、やりかえす。眼には眼を」という思いしか生まれてきません。京子さんが、「娘がされたことと同じことをしてやりたいという、どうしようもない怒りと悔しさと憎しみがあります」と書いておられるのは、この視点から生まれてきた思いです。
もし、そんな「エゴの視点」からしか世界が見えなかったら、どうなるのか。それはです、私たちが日々、新聞やテレビで見ているような世界になるのです。私たちが「現実」と呼んでいるのは、そんな「エゴの視点」が生み出した世界です。「怖れ」に満ちた修羅の世界です。
それに対して、「仏の視点」から見れば、世界は、「いのちの真実」を学ぶ場に見える。そこでは、私たちはみんな、人間としての完成を目指して、互いに助け合い、互いに学び合っている、「いのちの仲間」です。これは「仏の視点」から生まれる世界です。「共感」に満ちた菩薩の世界です。
京子さんが、A君に対して、「どんなに時間がかかってもあなたを更生させてやりたいと願う気持ちがある」、「それまで、共に苦しみ、共に闘おう。あなたは私の大切な息子なのだから」と呼びかけているのは、まさに、この「仏の視点」から生まれてきた思いですね。
話を戻しますと、ハンマーで頭を砕かれた彩花ちゃんは、医師の予想を覆して、昏睡状態のまま一週間を生き続け、凄まじいばかりの命の底力を見せました。その姿を見つめるなかで、京子さんは、「何が起こっても、人生を恨まず、悲しいことも苦しいことも人生の糧として、懸命に生きよ」と教えるヘッセの言葉に出会い、彩花ちゃんが自分に伝えようとしていたメッセージに気づきます。
彩花ちゃんは、懸命に命を燃やし続けることで、お母さんに、本当の意味での「生きる力」というものを教えようとしていたのです。京子さんがそのことに気づいたとき、昏睡状態の彩花ちゃんの口元に、にっこりと微笑みが浮かんだといいます。そのときのことを、京子さんは、こう書いています。
「『お母さん、よかったね。大事なものを手に入れることができたね。お父さん、お母さん、本当にありがとう」 そう語りかけるかのような、信じがたい笑顔でした。 そして、それから三時間ほど経った午後七時五十七分、彩花はこぼれるような笑顔のまま、悠然と旅立ったのです」と。
京子さんは、最後にこう書いています。「もちろん、最初は憎しみしかありませんでした。彼がやったことに対しては、これからも永久に許すことはできません。 それにしても、私のなかで何かがゆっくりと変わってきたことは事実です。憎いはずの少年が、かわいそうに思えることが多くなり、あんなふうにならなければ誰にも止めてもらえなかったのかと考えると、別の意味で心がつぶされそうでした。 (中略) 少年への思いは、誰に説得されたのでもなく、ごく自然に私のなかに芽生えてきた不思議な感情でした。じっと心の中を凝視したとき、「そうや、彩花が教えてくれたんや」 そう思いました。亡くなってまで、私に教えることを忘れない娘に、ただただ感謝の思いが溢れました。 『ありがとう、彩花。ほんまに、ありがとう』」と。
加害者の少年の「いのち」への共感が、京子さんの前に、憎しみとあきらめを乗り越えて前進する道を開いてくれた。そして、その共感を教えてくれたのは、被害者である彩花ちゃんだった。京子さんは、そう感じたのです。そして、そう感じられたことに感謝が溢れてきた。尊い感情です。誰もが感じられることではありませんね。それは、生きとし生けるものを悲しみ慈しむ「仏のまなざし」のなかでしか、感じることのできない感情だと思います。
また、京子さんは、こうも書いておられます。「私は彩花が『運悪く』、凶悪な殺人鬼に遭遇したとは思えないのです。彩花は、出逢うべくして少年と出逢っているのです。それが、彩花の寿命というものだったのかどうか、適切な言葉は見つかりませんが、彩花が十歳の三月にひとたび人生の幕を閉じることは、やはり彩花自身の命の内側に定まっていたことだろうと思います。 私は、自分を惨めにしないために、無理にそう思い込もうとしているのではありません。これからつづるように、私は彩花に命の深い深い秘密を教えてもらうことになります。 深い眼から見るならば、彩花が瀕死の重傷を負ったことにおいて、少年は『原因』ではなく『きっかけ』にすぎなかったのです。…少年の凶行は彩花の命の力が自ら選択した『きっかけ』にすぎません」と。
「いのちの真実」から言えば、あるいは、こうだったのかもしれません。京子さんに大切なことを伝えるために、彩花ちゃんは命をかけるという約束を持って生まれてきた。そのために、A君も役割を果たすことになっていた。もしそうだとすれば、彩花ちゃんが菩薩であったように、A君も菩薩だった。そう言っても、京子さんには分かってもらえるのではないかと思いますね。
何度も申しますが、私たちはみな、人としての完成を目指して、生まれ変わり、死に変わりしている「いのちの仲間」です。私たちが、同じ時代、同じ世界に生まれてきたのは、互いに助け合い、互いに学び合うためなのです。
だからこそ、私たちみんなが大切なことに気づくために、こういう悲しい役割を自ら選んで生まれてくる「いのちの仲間」がいるのです。私たちみんなが、そのことに気づかない限り、こういう悲しい役割を担って生まれてくる子供たちはなくならないのです。
確かに、私たちは、完全に「エゴの視点」を離れることも、常に「仏の視点」から見ることもできません。しかし、世界を「仏の視点」から見ていくなら、現象世界の奥に「いのちの真実」が見えてくるのです。そのことを、京子さんは、「深い眼で見る」と言っていますね。
その「深い眼」に見えてきたのは、「彩花が人生をかけて私に教えてくれた」、「命の深い深い秘密」です。その「秘密」とは、「命というものの荘厳なまでの輝き」でした。その「いのちの真実の姿」に気づいて、京子さんは、ようやく、「涙に明け暮れしながらも、顔を上げて、強く生きることができるようになりました」。京子さんは、その本の前書きを、こう結んでおられます。「私どもの個人的な苦悩が、多くの人の生きる希望へと転ずることを願います。 (中略) 彩花、『生きる力』をありがとう」と。
この本を読んで思ったのですが、京子さんは、若いころから「仏の視点」に馴染んでおられたようですね。「私は、息子も娘も、偶然にわが家に生まれてきたのではないと思っています」という言葉で始まる子育ての記録を読んでもそう感じましたし、「宿業」とか「因縁」といった仏教用語への正確な理解からもそう感じました。京子さんが、仏教徒かどうかは分かりませんが、いずれにせよ、非常に宗教的な感性に恵まれた方だと思いました。だからこそ、こんな悲しい経験から、これほどまでに尊い感情を紡ぎ出されたのだと思いますね。
エゴの涙は「我」が通らない涙です。我が身の不都合を嘆き憤る涙です。その悲しみが、たとえ気も狂わんばかりの激しい悲しみであろうとも、あるいは、涙も出てこないほどの深い悲しみであろうとも、エゴの涙は、自分の思い通りになるまで乾かない。煎じ詰めれば、玩具屋の店先で駄々をこねている子供の涙と変わらないのです。
たとえば、京子さんの場合で言えば、加害者の少年が同じ苦しみを味わい、彩花ちゃんが生き返ってくるまで、涙は乾かない。それは、私たちにもよく分かる感情です。ですが、その悲しみは、決して癒されることのない感情ですね。世界には、そんな癒されることのない感情が満ち満ちています。
しかし、私たちの「いのち」の奥底には、そういう世界の在り方そのものを悲しむ感情があるのです。そして、その世界を悲しむ感情こそ、本来の「いのち」の感情です。「本当の自分」の感情、仏の感情なのです。私たちは、その仏の悲しみに気づいたときに、初めて、癒され、救われていくのです。
本日の話の最初に、「仏法にご縁を頂いたお陰で、涙の川は、本願の海に流れ込んで行くことが思い出される」と申しましたのは、このことです。 「本願」というのは仏様の願いのことです。仏様は、私たちの悲しみを救いたいという願いをたてられた。その願いが「大悲心」、つまりは「大きな悲しみの心」です。この「大きな悲しみの心」を「本願海」とも言います。「本願海」とは、私たちの本来の「いのち」の願いのことなのです。
私たちは、本来「ひとつ」なのに、バラバラに見える世界に捕らわれている。そして、そんな世界で、損だとか得だとかいって、悲しんだり苦しんだりしているのです。しかし、私たちの「いのち」の奥底には、そんなバラバラに見える世界に捕らわれている「私」を悲しんでいる、本来の「いのち」の感情があるのです。それが「本願海」です。その感情に触れたとき、エゴの涙を流している「私」こそ、悲しまれ慈しまれていることに気づくのです。
私たちの流す悲しみの涙は、本願海に流れ込んだときに「ひとつ」になる。そして、「ひとつ」になったときに、思い出すのです。私たちは孤独ではない、みんな「仲間」だったのだと思い出すのです。そして、この悲しみの涙は、その大切なことに気づかせてもらうために、流させてもらったのだと知るのですね。
そこには、自ずと、「仲間をいとおしむ思い」「生きとし生けるものを悲しみ慈しむ感情」が湧いてくるでしょう。そのとき初めて、人は、孤独な悲しみから解放され、「生きる力」を得るのです。本願海とは、心の闇を照らす光です。その光のなかでこそ、悲しい経験が、生きる力へと変わっていくのです。
何度も申しますように、「いのち」の深いところでは、みんな「ひとつ」です。みんな「いのちの仲間」なのです。私たちは忘れていますが、本来の「いのち」は、そのことを思い出すように、常に願っているのです。つまり、私たちは、常に願われているのです。
実際、京子さんは、彩花ちゃんに願われていたことに気づいたのです。京子さんの心のなかには、感謝とともに彩花ちゃんの「いのち」が輝き続けています。その光は、京子さんの「生きる力」となり、さらには、加害者の少年をも照らし始めるのです。そういう「いのち」の輝く世界に気づいていくこと、それが、「仏の視点」から見るということです。
この本を読んだ感想文が、インターネットにも沢山掲載されています。その全部を読んだ訳ではありませんが、私の読んだ範囲で言えば、「非常に感動したけれど、考えれば考えるほど、京子さんが絶望から立ち直れた理由が分からない」という感想がほとんどでした。おそらく、そうなんでしょうね。「仏の視点」をなくしてしまった現代人には、理解できないのでしょうね。
人生とは、人間として成長し、成熟していくプロセスです。ところが、現代社会では、競争に勝つこと、もっと豊かになること、もっと有名になることを、成長や成熟と考えているようなところがあります。そして、そんな社会には、癒されることのない悲しみが満ち満ちているのです。とすれば、それはとりもなおさず、進むべき方向が間違っているということでもあると思いますね。
以前にもお話しいたしましたが、「人間には修羅から仏までの幅がある」のです。「仏」とは、人間の完成された姿です。ですから、人間として成長し成熟するというのは、「仏」の方に向かって歩み続けるということです。それは、仏の方に顔を向けて、仏のまなざしのなかで、「仏の視点」から世界を見ていくということです。
具体的に言えば、「世界に偶然はない。人生の上に起こってくることには、全て必然があり、自分にとって意味がある」と受けとめることです。それを仏教の言葉で、「宿業」を感じると言います。「宿業」というのは、「あきらめ」を意味する言葉ではありません。そうではなくて、仏のまなざしのなかで、あらゆる人生を肯定していく言葉です。
「仏の視点」から見れば、悲しいことも苦しいことも、全て、私の成長と成熟を支えようとする「いのちの仲間」からのメッセージなのです。人生の上に起こってくることを、全て、人間として成長し成熟する縁として受けとめる。昔の人が、「悲しいことも苦しいことも、全て、仏様のお諭しです。お育てを頂いているのです」と言われたのは、このことですね。
悲しいことも苦しいことも、全て、人間として成長し成熟するための「ご縁」です。ですが、それを「ご縁」と思っているあいだは、まだ知識なのです。仏のまなざしのなかで、「ご縁」が「ご恩」と知られたとき、初めて「生きる力」となるのです。
山下京子さんが、「彩花、生きる力を、ありがとう」と言っておられたのを思い出してくださいね。京子さんは、彩花ちゃんの「いのち」に託されていた「浄土の光」に気づいたのです。彩花ちゃんは、京子さんにとって「還相の菩薩」だった。そのことに気づいたとき、「ありがとう、ありがとう」という感謝の言葉となって溢れてきたのですね。
今生での出会いの「ご縁」が「ご恩」と知られたとき、初めて「生きる力」が湧いてくる。その「生きる力」とは何かと言えば、本当の自分になっていく力です。つまりは、「往相」を生きる力なのですね。
さきほどの中国での戦争体験の話で言えば、僧侶は、捕虜の死によって、我が身の宿業を感じたでしょう。そのとき僧侶は、仏のまなざしのなかに立っていたはずです。そして、その仏のまなざしのなかには、殺された捕虜も立っていたはずなのです。
僧侶は、捕虜の死には深い意味があったことに気づいたでしょう。その大切なことを「いのちの仲間」である自分に伝えるために、捕虜は命を捧げたのだと気づいたでしょう。そして、あるいは、その捕虜こそが仏だったと気づいたかもしれないと思いますね。
大きく見れば、世界に起こっていることは、全て「私」へのメッセージなのです。「私」に大切なことを伝えるために、沢山の「いのちの仲間」が悲しい役割を引き受けて生まれてきているのです。宮沢賢治は、「世界に一人でも不幸な人がいる限り、本当の私の幸せはない」と言ったそうですが、これは、そのことへの気づきを言った言葉だと思います。
私たちは、不幸な人を見ると同情を感じます。ですが、そういう同情は、たいてい「エゴの世界」と共鳴している感情です。私たちは、自分より幸せそうな人に同情を感じることはありませんね。同情するのは、自分より不幸な人に対してです。そのうえ、同情が続くかどうかは、相手の出方次第というところがある。そういう「エゴ」の同情では、本当に人を幸せにすることなどできません。
本当に人を救っていくのは、「いのちの仲間」としての共感です。そういう共感は、「仏の世界」と共鳴するところからしか生まれてこない感情です。「生きとし生けるものを悲しみ慈しむ世界」と共鳴したとき、私たちは本当の意味での同情心、「世界を悲しむ力」を得るのです。現代社会に欠けているのは、この「世界を悲しむ力」です。
ただし、「世界を悲しむ」と言っても、それは外の世界を変えようとすることではありません。外の世界を変えようとするのは「エゴ」の発想です。そうではなくて、変えるべき世界は、私たちの心のなかにあるのです。大切なのは、外の世界を変えようとすることではなく、「エゴの視点」を手放して、自分自身が変わっていくことなのです。
私たちは過去の業縁によって、修羅と仏の間の何処かに生まれてきます。それが「宿業」です。私たちは、今生での人生のスタート地点を自ら選んで生まれてくるのです。そのことに気づいたとき、修羅に背を向けて仏に向かって歩き始めることができるようになるのです。宿業の身を自覚し、そこから仏に向かってスタートする。「宿業を転じる」というのは、そのことです。
「エゴの視点」から流された涙は、修羅の世界に溢れ、悲惨な混乱を生みだすだけです。「仏の視点」から流された涙は、仏の世界を実現して、本当の意味での「生きる力」となり、「多くの人の生きる希望へと転ずる」のです。私が変われば、世界が変わるのです。
私たちは「仏の視点」を回復しなければなりません。「仏の視点」は学ぶことができます。たとえば、「聞法する」というのは、「仏の視点」を学ぶことです。ですが、それだけでは、まだ知識にすぎません。その学んだ「仏の視点」から世界を見ていこうと決意したとき、初めて、「仏の視点」は「生きる力」となるのです。
私たちの心は、煩悩という氷に覆われた池のようなものです。氷を全部取り除いてしまうことはできなくとも、一部に穴を開けて陽の光が射し込む場所を作ることならできるでしょう。「仏の視点」から見ていこうと決意するとは、そういうことです。
とはいえ、私たちは弱いもので、悲しいときや苦しいときには、すぐに「エゴの視点」から見てしまいます。ですが、そういう私たちだからこそ、お念仏が与えられているのです。悲しいにつけ、苦しいにつけ、お念仏を称えることで、「仏の視点」が思い出されてくる。お念仏を称えるごとに、心の暗闇のなかに射し込んでくる光がある。そして、その光のなかで、悲しいことも、苦しいことも、また、生きる力となっていくのです。
私たちは、常に、願われているのです。世界を悲しむ仏のまなざしのなかにいるのです。仏に背を向けて暮らしている私たちにも、その視線を感じることがあるでしょう。ですが、仏の世界を切り捨ててしまっていては、振り向いても何も見えてこないのですね。心のなかに、仏のまなざしに気づく場所を作る。それが、聞法とお念仏の生活なのです。
この世に生を受けた者はみな、遅かれ早かれ死なねばなりません。ですが、仏の目から見れば、人は幾つで逝っても、何もやり残したことはないのです。仏の目から見れば、どんなに短い人生にも意味がある。無駄な人生というものはないのです。そんな仏のまなざしのなかでこそ、人生は生きるに値する価値を持つのです。
さて、本日お話し申し上げたかったことは、これだけでございますが、お話ししながらも、思い出されるのは、義兄の臨終の場面です。3月4日に、義兄が最後の息を引き取ったとき、涙に息苦しくなって、ふと眼を上げると、義兄の寝台を囲むように、何十人もの人が、涙にくれて立ちつくしている。親戚や、寺の総代さんがた、義兄の友人や同僚の顔もある。
さほど大きくもない部屋に、そんなにも多くの人が集まって下さっていることに、そのとき初めて気づきましたが、不思議と、音がしない。あれっと思ったそのとき、人の姿がみなシルエットのようになって、明るい光に包まれ始め、痩せ細った義兄の身体からは、神々しい光が広がっているように感じました。
実際には、それは一瞬のことだったのかもしれませんが、静寂のなかで、みんなの涙を包み込む、柔らかな光があり、仏のまなざしを感じました。そのとき、私は、「今まさに、仏が法を説きたもうている場に出逢っているのだ」と知ったのです。本日は、そのときの柔らかな光の余韻を感じながら、お話しさせて頂きました。まさに、義兄の結んでいってくれた御縁かと存じます。
さて、本日は、長い話にお付き合い下さいまして、有り難うございました。次回は、11月12日の「報恩講」でございますが、今年の「報恩講」には、昭和63年に亡くなりました祖母、正覚院釋尼妙操の13回忌も併せて勤めさせて頂く予定でおります。どうぞ、また、お参り下さいますように。本日は、まことに有り難うございました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
紫雲寺HPへ