義兄が若くして逝きましたことは悲しいことでございましたが、仏法にご縁を頂きましたお陰で、どこかしら安らかな心をもって、この一年を過ごさせて頂いたように思います。
義兄は脳腫瘍という病気で逝きました。病気になれば、何としても治りたい、治したいと願うのが人情です。しかし、病気は、治る場合もあれば、治らない場合もある。私たちはみな、いずれ治らない病気になって帰って逝くわけですが、たとえ病気は治らなくとも、癒されることはできるのです。
私たちはよく、「病気の治癒を願う」と言いますけれど、「治」と「癒」は違うのです。「癒」という字は「病垂れに兪と心」と書きます。「兪」というのは「くり抜く」という意味です。何をくり抜くのかというと、「病垂れと心」が示しておりますように、「心の病」です。「心の病」というのは、「我執」のこと、執着心のことです。
この「執着心」をくり抜くと、心安らかに生きられるようになる。それが「癒される」ということですが、実は、その「心安らかに生きる」ということこそ、まさに仏法のめざしている世界なのです。
そこで本日は、仏法の癒しの世界、信仰の生活について、「安らかに生きる…生老病死を超えて」という題でお話しさせて頂こうと思います。どうぞ、しばらくの間、お付き合いくださいますよう、お願い申し上げます。
仏法にご縁を頂いたということは、本当に幸せなことでございますが、なかなか、この仏法の話というのは、お分かり難いもののようでございまして、彼岸会でも、永代経でも、報恩講でも、お勤めが終わりまして、「これから仏法の話をいたします」と申しました途端に、眠たそうな顔をなさる方が少なくない。なかには、実際に眠ってしまわれる方もおいでですがね。
まあ、仏法が分からなくとも生活はできるわけですから、金や地位や名誉を求め、何か美味いものはないか、何か面白いことはないか、健康が大事、生き甲斐が大切といって、「生活」だけが問題になっている間は、なかなか仏法へのご縁が開けてこないということかもしれません。
ですが、人生は、生活だけでできているわけではないのでして、いずれ、どなたにとっても、生活ではなくて、人生そのものが問題になる日がやってくると思うのです。本当の意味での「人生」が始まるのは、そこからですね。
それにしましても、私たちの社会は、よくよく「人生」を考えさせないような仕組みになっておりますね。人生の骨組みとなっているのは「生・老・病・死」です。「生・老・病・死」というのは、「生まれてくること、年老いていくこと、病気になること、死んでいくこと」ですね。この「生・老・病・死」を、自分の問題として、苦しみ悩むところから「人生」は始まるのです。
ところが、現代社会ではどうでしょう。子供が産まれてくるとき、何処にいるかというと、病院にいるのです。年老いて身体が不自由になったとき、何処にいるかというと、病院にいる。重い病気になったとき、何処にいるかというと、病院にいる。そして死んでいくとき、何処にいるかというと、病院にいるのですね。
そして、病気が治ったりして病院から出てきたら、私たちは、どう言うか。「社会復帰」と言うのですね。つまりは、病院の中は社会ではないということです。患者と呼ばれているあいだは、人間扱いされていない。現代社会では、人生の骨組みであるはずの「生・老・病・死」を、人生の表舞台から排除しているのです。
テレビを見ても、そうですね。人生を思い出させたり、人生を考えさせるような番組は、まず、ありませんね。人生を忘れさせるような番組ばかりです。私たちの社会は、どうして、それほどまでに、人生から目を背けようとするのでしょうかね。今日はまず、このあたりから、ご一緒に考えていきたいと思います。
さて、さきほど、「生・老・病・死」は人生の骨組みだと申しましたが、ご承知のように、仏教では、この「生・老・病・死」を「四苦」と呼んでおります。「生まれる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、死ぬ苦しみ」ですね。
ちなみに、この四つの苦しみに、「愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦」の四つを加えて「八苦」と言います。私たちはよく「四苦八苦する」と言いますが、それは、ここから生まれた言葉ですね。 「愛別離苦(あいべつりく)」というのは、愛する人と別れる苦しみです。「怨憎会苦(おんぞうえく)」というのは、怨みに思っている憎らしい人とも会わねばならない苦しみです。
ちょっと余談ですが、このあいだ、ある本に、「地獄の苦しみというのは、嫌いな親戚百人と一つの部屋にいることだ」と書いてありました。それなら、極楽の喜びとは何かというと、「姑が死んで息子に嫁が来るまでのあいだ」と言った人がいます。まあ、それほど、身近な人間関係というのは難しいということでしょうね。
さて、その次の「求不得苦(ぐふとくく)」というのは、求めても得られない苦しみです。そして、「五蘊盛苦(ごうんじょうく)」というのは、簡単に言えば、我が身に煩悩が沸き立つ苦しみです。「私が、私が」という「我執(がしゅう)」に、身も心も苦しむことです。
これを全部まとめて「八苦」と言うわけですが、私たち一人一人の人生にとって、本質的な問題は、やはり「生・老・病・死」の「四苦」でしょうね。この「生・老・病・死」をしっかり見据えることができれば、残りの四つには、自ずと道が開けるものと思います。
「四苦」というのは、先ほども申しましたように「生まれる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、死ぬ苦しみ」のことですが、実際には、これは「死ぬ苦しみ」ひとつに集約されてしまいます。
「生まれる苦しみ」というのは分かりにくいかもしれません。私たちは「産みの苦しみ」とは言っても、「生まれる苦しみ」とは言いませんからね。ですが、「生まれる」ということは「いずれ死なねばならない」ということでもあります。「生まれる」というのは、「死ぬ」ことが約束されているということです。ですから、死ぬことが苦しみである限り、生まれてくることも苦しみなのです。
また、「老いる苦しみ」というのは、ただ歳をとるのが苦しいという意味ではありませんね。たとえば、二十歳の者が25歳になっても、別に、苦しくはないでしょう。そうではなくて、「老いる苦しみ」というのは、「死ぬときが近づいてきたと思う苦しみ」「死ぬことへの予感を持つ苦しみ」ですね。
「病む苦しみ」と申しましても、鼻風邪ひとつ引いたくらいで、深刻に苦しむ人もいないでしょう。そうではなくて、大病を患ったときに、「ひょっとしたら、これで終わりかもしれない」と思う苦しみがある。それが、「病む苦しみ」ですね。ですから、「病む苦しみ」というのも、「死への予感を持つ苦しみ」なのですね。
では、「死ぬ苦しみ」とは何か。私たちはよく、「死ぬほどの苦しみ」とか「死ぬより辛い」というようなことを申しますが、かつて死んだという経験を憶えているわけではありませんね。私たちの経験から言えば、死ぬということが、苦しいことなのかどうか、実は、よく分からないのです。かつて死んだときのことを思い出せたら、「死ぬ苦しみ」というのは無いのかもしれませんが、まあ、そういうことは、まずありません。では、「死ぬ苦しみ」とは何かと言えば、それは「死ぬことへの不安」なのですね。
ここ30年ほどの欧米の心理学者の研究によりますと、「死ぬことへの不安」が最も低いのは東南アジアの人々、それについで、欧米の人々、そして、最も「死ぬことへの不安」が高いのが、私たち日本人だったということです。
死を前にすると、日本人がいちばん苦しむ。不思議な気もしますが、それには理由があるのです。欧米の科学技術というものは、もともとキリスト教信仰と抱き合わせになって発展してきたのですが、明治以降、日本は、その宗教的側面を切り捨てて、科学技術だけを導入してきました。そして、ついには、いわば科学を信仰するようになってしまったのです。
その科学の教えでは、「目に見える世界が全て」です。ですが、「目に見える世界が全てだ」ということであれば、たとえば「私」というのは、この、目に見える体のことだということになる。この体が私の全てだということになれば、当然、「死ねば終わりだ」ということになってまいりますね。
世界中探しても「死ねば終わりだ」と思っている民族や文化はめったにありませんが、現代の日本人の大半は、その例外中の例外にあたるのです。ギャラップの世論調査でも、死後の世界を信じる日本人はわずか18%に過ぎません。それに対して、アメリカでは67%もの人々が来世の存在を信じているといいます。
「死ねば終わりだ」と思っている私たちの目には、「死」の先には何も見えません。「死」の先には、底なしの暗闇が広がっているだけです。そんな底なしの暗闇が恐くて仕方がないものですから、私たちは、そこから必死で目をそらせて生きています。「死ぬ」というのは、私たちが一番聞きたくない言葉なのですね。
「死ぬことへの不安」というのは、私たち現代人にとっては、「死んでしまったらお終いだ」という思いから生まれてくる不安です。死ねば、意識がプツンと切れて、それで、全ては御破算になるという恐怖ですね。そんな恐怖に直面していることは、とても耐えられないものですから、私たちは、必死になって「死」から顔を背けている。死から顔を背けて、生活にしがみついて生きているのです。私たちが「人生」を考えないようにして生きているのは、そのためですね。
しかし、「死ぬ」ということは、誰もが避けることの出来ない人生最大の現実です。私たちは、たとえどんなに長生きしようとも、いずれ死ぬのです。お悟りを開かれたお釈迦様でも80歳でお亡くなりになったのです。ですが、お釈迦様がお亡くなりになるときには、「死ぬことへの不安」は無かった。「死ぬこと」は避けられなくとも、「死ぬことへの不安」は解消できる。仏教がめざしているのは、「いのちの真実の姿」を伝えて、この「死ぬことへの不安」を解消することです。
「死ぬことへの不安」が解消されたとき、仏教の言葉で、「安心(あんじん)」を得たと言います。「安心」が得られたら、つまりは「死ぬことへの不安」が解消されたら、私たちは、生活にしがみつくことなく、心安らかに生きられるようになる。そのためにこそ、仏法は、「いのちの真実の姿」を伝えようとしているのです。
では、「いのちの真実の姿」はどうなっているのか。それはです、これまでに何度もお話してきたことですが、私たちは「死んでも終わらない」のです。「浄土の教え」では、「人は、死ねば浄土へと帰っていく」と説かれている。「そしてまた、浄土の光を携えて、この世界へと戻ってくる」と説かれているのです。
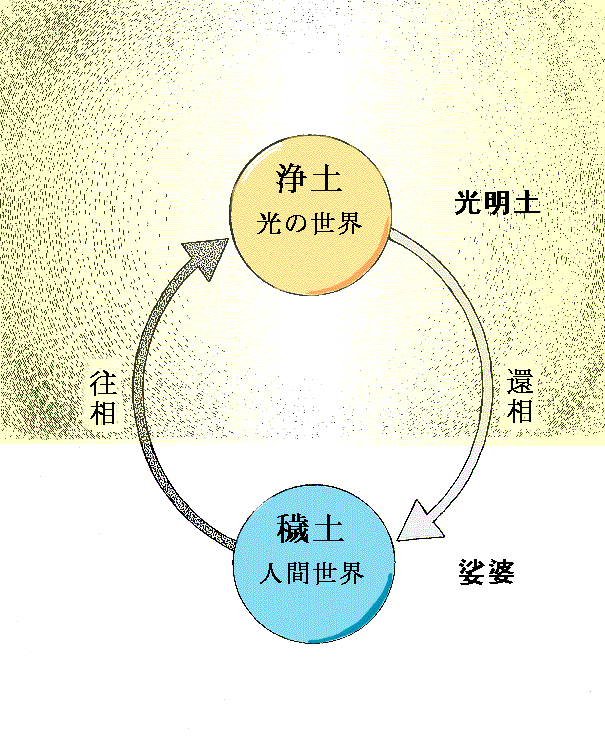
目に見えるように描きますとね、私たちは、この「娑婆(しゃば)」に暮らしている。そして、死ねば「浄土(じょうど)」へと帰っていく。「浄土」というのは「光明土(こうみょうど)」とも言いますように、「光の世界」です。この「娑婆」から「光の世界」へと帰っていく姿を「往相」と言います。
そしてまた、「浄土」の光を携えて、この「娑婆」へと戻ってくる。「娑婆」に光をもたらすために、戻ってくるのです。この、「浄土」の光を携えて「娑婆」へと戻ってくる姿を「還相(げんそう)」というのです。
私たちはみな、「浄土から生まれてきて、またその浄土へと帰っていく」のです。「往相(おうそう)」と「還相(げんそう)」を繰り返しているのです。それが、私たちの「いのちの真実の姿」なのです。「いのち」というのは、そうなっているのです。「そうなっている」ということは、本当は、信じるとか、信じないとかいった問題ではないのですね。
私たちは、何度もそれを経験してきたわけですから、当然「いのち」の奥底では、知っているのです。ですが、忘れてしまっているのですね。その、忘れてしまっていることを、思い出しなさいと教えて下さっているのが、「浄土の教え」なのです。
もう少し、目身見える「たとえ」でお話いたしますね。ここにロウソクがあります。このロウソクが、私たちの身体だとしますね。この世界に生まれてくるために、この身体は、両親が準備します。両親をご縁として、身体を授かるわけです。
そして、この身体に「いのち」が宿る。こうやってお仏壇の蝋燭から火をもらいますと、私のロウソクに火がついて、そして、生まれてくるわけです。この火が、私たちの魂ですね。身体は両親をご縁として授かるわけですが、魂は両親からもらうわけではありません。私たちはみな、一人一人自前の魂があるのです。
そして、生まれてくると、二つの幸せがある。ひとつは、まわりを明るくする。もうひとつは、まわりを暖かくする。子供さんをお持ちのかたは、経験なさったことと思いますが、子供さんが授かったとき、みなさんの心が明るくなり、暖かくなったでしょう。それが「いのち」の本来の働きなのです。
子供を授かるご縁というのは、尊いものですね。子供が授かるのは、その子からしか学べないことがあるから、その子を授かるのです。親は、子供の光に照らされて、初めて我が身の姿が見えるようになるのです。また、子供は子供で、その親からしか学べないことがあるから、その親を選んで産まれてくるのです。親子の出会いにご縁を感じることができれば、本当に大切なことを学べるのですが、なかなか難しいことですね。
さて、それで、このロウソクが燃え尽きてしまったら、この火はどうなるのか。目に見える世界しか信じていない人は、ロウソクが燃え尽きてしまったら、火は消えてしまって、それでお終いだと思っていますが、そうではないのです。光の世界からやってきた、この火は、また、その光の世界へと帰っていくのです。それが、「往相(おうそう)」と「還相(げんそう)」ですね。
「浄土の教え」の核心は、この「往相・還相」にあります。ですが、間違ってはいけないのは、死後の「往相・還相」は、信仰を持っているかどうかとは関わりがないということです。信仰を持っている人も、持っていない人も、「死ねば浄土へと帰っていく」、「光の世界へと帰っていく」のです。だからこそ、「いのちの真実」と言うのです。
お念仏を称える人だけが浄土に往生すると、お考えの方もおられますが、そうではないでしょうね。というのはですね、現在、世界の人口は60億ほどですが、たとえ日本中が門徒さんだったとしても、お念仏を称えているのは1億人ほどでしょう。もしも、お念仏を称える人だけが浄土に往生するのなら、あとの59億人は、いったい何処へ行くのでしょうね。お念仏を称える人も、称えない人も、死ねばみな、光の世界へと帰っていく。だからこそ、浄土の教えは、いのちの真実だと言うのです。
しかしです。信仰を持っている人も、持っていない人も、死ねばみな浄土へと帰っていくというのなら、では、「信仰の生活」とは何かということになりますね。ここが大切なところです。それはですね、「信仰の生活」というのは、この「往相」と「還相」を我が身の現実として生きることをいうのです。
頭で分かるということと、身の現実として生きるということは、全く違います。たとえば、私たちは「いずれ死なねばならない」ということを知っていますね。では、それはいつのことかと言えば、今日ではない、明日ではない、今週ではない、来週ではない、今月ではない、来月ではない、今年ではない、来年ではない、まあ、いつかそのうち、ということになって、一向に切実感がない。こういうのが、頭で分かっているということです。
それに対して、かなりの高齢になって、重い病を患ったりしたときには、そうではありませんね。不安や恐怖で全身が反応する。それが、「いずれ死なねばならない」ということが、身の現実となっているということです。「往相・還相」ということは、いくら頭で分かっても、それだけで「安らかに生きる」ことなどできませんね。
聞法とお念仏の生活のなかで、「わたしたちはみな、浄土から生まれてきて、またその浄土へと帰っていくのだ」ということが、頭ではなく、この「身」全体で分かったとき、「いのち」の火は真っ直ぐに燃えるようになります。揺れたり、またたいたりしていた火が、真っ直ぐに燃えるようになる。それが「安心」を得たということなのです。
この火が真っ直ぐに燃えるようになったとき、まわりを明るくする力、まわりを暖かくする力が、満開になる。私の心が本当に安らかになれば、そのことが、そのまま、他の人の心が安らかになっていくご縁となる。私が本当に救われたら、そのことが、とりもなおさず、他の人が救われていくご縁になるということです。「往相」と「還相」は別にあるわけではありません。「往相」が成就されたとき、自ずと「還相」が成就されるのです。
「往相・還相」を身近に引き寄せて言えば、「お念仏」を喜んでいる姿、仏法を喜んでいる姿、それが「往相」なのです。そして、仏法を喜ぶ人がご縁となって、また仏法を喜ぶ人が生まれてくる、その働きを「還相」というのですね。
別の「たとえ」で言えば、安心を得るというのは、暗闇の中にいると思って怯え苦しんでいたのが、実は、光の中にいるのだと気づいて、安らかな心になることです。
この上に、「常照我(じょうしょうが)」という扁額が掛かっておりますが、これは、「仏様は、常に私を照らしてくださっている」という意味でしたね。たいていは気づいておりませんけれど、私たちは、常に光の中にいるのです。
聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、少しづつ、この「常に我を照らしたまう光」「浄土の光」への感受性が高まってくる。そうすると、今度は、出会った人のなかに宿っている「浄土の光」にも気づけるようになってくるのです。そして、人の「いのち」に託された「還相」の働きに気づくようになってくるのですね。
私たちはみな「浄土」から生まれてきたわけですから、私たちの「いのち」には自ずから「還相」の働きが備わっているはずですが、その「浄土」から持ち帰ってきた「光」は、自分のための「光」ではないのですね。ですから、自分には、その光に気づけない。その光に気づくのは、他の誰かなのです。その光に気づく人との出会い、それが、人と人との縁というものなのですね。
また話が私事に渡りますが、昨年亡くなりました義兄の法名は「還相院・釈了然」といいます。この「還相院」という院号をおくったのは父親です。私には、「還相院」という院号を息子におくった義父の思いが、よく分かるような気がします。義父は、息子の「いのち」に託されていた「浄土の光」を、その臨終のときに、はっきりと感じたのです。
「薄々感じてはおりましたが、やっぱり、あなたでしたか。我が子となって、お浄土の光を届けてくださいましたか。あなたは、私にとって還相の菩薩様でした」と。だからこそ、「還相院」という院号をおくったのです。
私たちはみな、浄土の光を「いのち」に託されて生まれてくるのです。別の譬えで申しますと、浄土からのメッセージを託されて生まれてくるのです。私たちは、出会うごとに、「いのちの真実の姿を思い出しなさい」というメッセージを渡し合うのです。ですがね、その浄土からの便りは、七色の封筒に入っているのものですから、なかなか読んでもらえないのですね。
七色の封筒というのは、私たちの感情のことです。浄土の光、大慈大悲の光は無色透明ですが、この私という煩悩に支配された人間を通して、その光が漏れるときには、屈折して、光に色が着いてしまうのです。
それは、ちょうど、小学校の理科の実験で見せてもらった、プリズムのようなものです。太陽光線は無色透明ですが、三角形の分光プリズムを通すと、赤から紫までの七色の光に分かれましたね。憶えていらっしゃいますでしょうか。私たちは、あのプリズムのようなものなのです。
光に色を着けるのは、私たちの煩悩ですが、その煩悩のお陰で、無色透明で見えなかった浄土の光が、目に見えるようにもなるのですね。ですから、逆に言えば、赤色の光が見えるということは、その奥に、無色透明の光があるという証拠でもあるのです。
たとえば、赤い光が「腹立ち」、青い光が「喜び」、黄色い光が「悲しみ」だとしますとね、誰かと出会って腹が立った、喜んだ、悲しい思いをしたというのは、そういう感情をまとって、大慈大悲の光が、働き出てくださっているということなのです。そのことに、私たちはなかなか気づけませんけれど、腹立ちも、悲しみも、喜びも、その全てが、大切なことへの気づきの縁を秘めているのですね。
たとえて言えば、私たちは、出会うたびに、いろんな色の封筒を渡し合っているのです。ですが、私たちは、その封筒の色に、腹を立てたり、喜んだり、悲しんだりするばかりで、なかなか、その封筒を開けて見ようとはしません。せいぜいが、自分に喜びを与えてくれる好きな色の封筒と、思い出したくもないという嫌いな色の封筒を仕分けるくらいのものですね。
今日、ここにお集まりの皆さんも、おそらく、大切な方を亡くすという経験をなさったことが、おありではないかと思います。そんな皆さんの心の中にも、出会いのなかで届いた手紙が、開かれないまま山のように残っているのではないでしょうか。
開かれないまま残っている手紙の山。私たちの日常の言葉で言えば、それは「思い出」ということになります。「思い出」を、外から眺めている限り、愚痴や繰り言しか湧いてきません。どうぞ、皆さん、その封筒を開いてご覧になってくださいね。
家内の父は、息子からの封筒を開いたのです。開いてみると、赤い封筒も、青い封筒も、黄色い封筒も、なかにはみな、白い紙が入っていた。お浄土からの、ご催促の便りが入っていたのですね。
「あのとき腹が立ったことも、あの時喜ばせてもらったことも、また、あのとき悲しい思いをしたことも、すべては、お浄土からのお諭しでしたか」と、手を合わせて、義父が息子におくったのが、あの「還相院」という院号だったのです。
義兄は47歳で逝きました。若かった。ですがね。人は、幾つで逝っても、何もやり残したことは無いのです。人は、浄土から携えてきた手紙を配り終えると、また、浄土へと帰っていくのです。そこから先は、私たちの仕事です。残された私たちの仕事は、その手紙を、間違いなく読むことなのですね。
子供を授かるご縁というのは、尊いものですね。子供だけではありません。人との出会いにご縁を感じるということは、何よりも尊い経験ですね。人との出会いに偶然はない。人との出会いは、聖なる出会いです。私たちが、わざわざ、この不自由な肉体をまとって娑婆に戻ってくるのは、この、人との出会いを求めてのことですね。
たとえば、重い潜水服を身につけて暗い海に潜るのは、真珠を探すためですね。真珠を見つけたときの感動は、真珠の涙となってあふれてくるのです。ですがね、人に「還相の光」を感じられるのも、また、「浄土の教え」を聞かせて頂いているお陰、「往相」が廻向されているお陰なのですね。
何度も言うようですが、私たちは、「いのちの真実」とは違った思いを握りしめて、「いのちの自然な姿」に背いて生きているから苦しいのです。「死ねば終わりだ」という思いを握りしめて、生活にしがみついて生きているから苦しいのです。
聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、「本当は、そうではないのだ。私たちは、死んでも終わらないのだ。私たちはみな、死ねば浄土へ帰っていくのだ。魂の故郷である浄土へ帰っていくのだ」と、心の底から納得できたとき、「死ぬことへの不安」は解消されます。「死ぬことへの不安」が解消されたとき、初めて、私たちは、本当に生きることができるようになる。心安らかに生きることができるようになるのです。
「四苦八苦」の根本は「死ぬことへの不安」にある。ですから、「死ぬことへの不安」が解消されれば、老いていく日々を楽しめるようになり、病からも学べるようになる。そして、生まれてきたことを、喜べるようになるのですね。
また、これほど憎い人と一緒に暮らさねばならないというのは、よほど、私はこの人に縁があるの違いない。きっと、この人は、私に何か伝えるために生まれてきた人に違いないと、そのご縁を大切に思えるようになるでしょう。
愛しい人との別れでも、これが永遠の別れではない、また「お浄土」で会えるのだと知るでしょう。求めても得られないときにも、ああ、これは今生では私に授かっていないのだと納得できる。「私が、私が」と言ってはみても、本当は、私もあなたもないのだ。みんな「お浄土」への旅仲間なのだと気づけるのではないでしょうかね。
聞法とお念仏の生活のなかで、「死ぬことへの不安」が解消されたとき、「安心」を得たと言います。信仰の生活というのは、この「安心」を得て、心安らかに生きることを言うのです。余計なことを言うようですが、信仰の生活というのは、観光バスでお寺巡りをすることではないのです。
以前、こんな話を聞いたことがあります。ある旅行会社が、全国の有名な「ポックリ寺巡り」のバスツアーを企画したところ、沢山の参加者があった。ところが、帰りのバスのなかで、ひとりのお爺さんがポックリ亡くなった。まさに霊験あらたかだったわけですが、それ以来、この「ポックリ寺巡り」のバスツアーは取り止めになったといいます。お客さんが集まらなくなったのです。
というのはですね、「霊験あらたかなのは結構だけれど、ポックリ逝きたいのは今ではない」ということらしいのです。それなら、いつならよいのかといえば、「もっと年をとって旅行にも行けなくなり、身体が不自由になって、自分のこともできなくなったとき」だといいます。これではどうも、自分の都合ばかり言っているようで、信仰とは程遠いような気がしますね。
そうではなくて、たとえ、寝返りひとつままならず、排便さえも家族や他人に頼るしかないようになっても、その状況を我が身にきちんと受けとめていくことができる。それが信仰の生活ではないでしょうかね。
たとえば、35歳で脊椎カリエスで亡くなった明治の歌人、正岡子規は、亡くなる少し前の日記に、こう書いています。「私は今まで禅宗のいわゆる悟りということを誤解していた。悟りということはいかなる場合にも平気で死ぬることかと思っていたのは間違いで、悟りということはいかなる場合にも平気で生きていることであった」(『病床六尺』)と。
正岡子規は、門徒さんではなくて、曹洞宗の信者さんでしたが、禅宗であろうと真宗であろうと、同じことです。「いのちの真実」に、宗派の違いはありません。仏教だけでなくて、キリスト教であってもそうですね。
このあいだ、ヘルマン・ホイヴェルスという神父さんの書かれた『人生の秋に』という本を読んでいて、こういう詩に出会いました。「最上のわざ」という詩です。お手許にお配りしたプリントに載せておきましたので、どうぞご覧になりながら、お聞きください。
「最上のわざ」
この世の最上のわざは何?
楽しい心で年をとり、
働きたいけれども休み、
しゃべりたいけれども黙り、
失望しそうなときに希望し、
従順に、平静に、おのれの十字架をになう。
若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても、ねたまず、
人のために働くよりも、謙虚に人の世話になり、
弱って、もはや人のために役だたずとも、
親切で柔和であること。
老いの重荷は神の賜物、
古びた心に、これで最後のみがきをかける。
まことのふるさとへ行くために。
おのれをこの世につなぐくさりを少しずつはずしていくのは、
真にえらい仕事。
こうして何もできなくなれば、
それを謙虚に承諾するのだ。
神は最後にいちばんよい仕事を残してくださる。
それは祈りだ。
手は何もできない。
けれども最後まで合掌できる。
愛するすべての人のうえに、神の恵みを求めるために。
すべてをなし終えたら、
臨終の床に神の声をきくだろう。
「来よ、わが友よ、われなんじを見捨てじ」と。
いかがですか。素晴らしいとは思われませんでしょうか。信仰の深まっていく境地というのは、仏教でもキリスト教でも、変わりはありませんね。
「おのれの十字架をになう」というのは、私たち仏教徒の言葉では、「宿業を生きる」とか、あるいは「お任せの人生」と言うところでしょう。また、「まことのふるさとへ行くために」というのは、「お浄土へ帰るために」というのと同じことですね。
この詩には、何も難しいことは言われていないように見えますけれど、実際には、なかなか難しいことですね。たとえば、「楽しい心で年をとり」とありますが、皆さん、如何でしょうか。楽しい心で年をとっておられますでしょうか。「人生、楽しいのは若いうちや。年をとったら、つまらんもんや」という話をよく聞きますが、如何ですかね。
「働きたいけれども休み」。これも、なかなか難しい。「まだまだ若い者には負けない。死ぬまで現役で働く」とおっしゃる方が少なくない。違いますかね。
「しゃべりたいけれども黙り」。これが、またまた難しい。特に、ご婦人方にですね。これは北陸のあるご院さんからお聞きした話ですが、「姑」という漢字は「女偏に古い」と書くのだと思っておりましたら、そうではなくて、あれは、「女偏に十口」と書くのだそうです。一口言えばすむところを、十口言いうのが「姑」だそうです。まあ、何もご婦人方だけではありませんで、私たちはみな、手足が衰えても、口だけは最後まで達者なものですから、「しゃべりたいけれども黙り」というのは、なかなか難しいですね。
「人のために働くよりも、謙虚に人の世話になり」。これまた、たいへんに難しいことですね。恩着せがましく人の世話をすることならできても、卑屈にならず、謙虚に人の世話になることは、まことに難しいことですね。
どれもこれも大切なことですけれど、ただ、こういったことは、そつなく生きていくための処世術ではないのですね。そうではなくて、信仰の生活の中から自然に生まれてくる姿、人としての完成を目指す生き方のなかから自ずと滲み出てくる姿なのです。信仰の生活というのは、キリスト教徒にとっては、祈りの生活ですし、私たち仏教徒にとっては、お念仏の生活ですね。
キリスト教の「祈り」で最も深いのは、「みわざがなされますように」という祈りだと聞きました。「みわざがなされますように」というのは、「全てを、お任せします」という意味です。つまりは、キリスト教の「祈り」もまた、私たちの「お念仏」と同じように、「生かされて生きているいのち」を憶念する祈りなのですね。憶念するというのは、心に深く刻みつけて、常に思い出すことを言います。
この詩にも読み取れますように、「私が、私が」と言っている「私」は、「エゴ」なのです。「私がこれをする、私があれをする」と言うのをやめて、「お任せします。何であれ、起こることが起こりますように」と、全てを受け入れる準備が整ったとき、そこに自然に癒しが始まり、救われていくのです。
「全てを受け入れる」。それは、「私が必要とすることではなく、私に必要なことが起こってくる。私が必要とするものではなく、私に必要なものが与えられる」という、「いのち」への無条件の信頼です。この「無条件の信」を深めていくこと、それが「信仰の生活」なのです。
別の言葉で申しますと、常に「みわざがなされている」ことへの気づきを深めていくこと、「常に我を照らしたまう光」への感受性を高めていくこと、それが「信仰の生活」なのです。
江戸時代の禅僧、良寛和尚に、こういう言葉があります。「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候。死ぬる時節には死ぬがよく候。これはこれ災難をのがるる妙法にて候」。有名な言葉ですが、これも同じ事を言っているのだと思いますね。
これは、無気力で投げ遣りな生き方から生まれた言葉ではないでしょう。「死ぬ時がきたら死ぬのがよいことなのだ」。そう言い切れるのは、「いのち」への無条件の信頼があるからだと思います。
私たちは、生きる理由があって生まれてきたのです。ですからね、乱暴なことを言うようですが、死ぬときが来るまで、絶対に死なないのです。どんな重病にかかっても、それが死ぬときなのかどうかは、私たちには分からないのです。
死ぬ時節は、「いのち」だけが知っている。死ぬときか死ぬときでないのかは、「いのち」にお任せです。そして、もし、それが死ぬときなら、それは、光の世界へと帰るとき、魂の故郷へ帰るときなのです。
最初にお話いたしましたように、「癒し」というのは「心の病をくり抜くこと」なのです。何でも中をくり抜くとホンガラになる。心の場合で言えば、つまりは、ホガラカになるわけですね。
聞法とお念仏の日暮らしのなかで、自然に、「心の病」がくり抜かれていく。そして、ホガラカになっていく。ホガラカに、安らかに、大慈大悲の光の中で、この世界を経験していきましょう。私たちは、そのために生まれてきたのですから。
さて、本日は、ここまででございます。長い時間、お付き合い下さいまして、本当に有り難うございました。また、ご縁がありましたら、ご一緒に聞法させて頂きたいと念じております。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
紫雲寺HPへ