秋は特に行事の多い季節ですから、皆さんも、お忙しいことと存じます。お参りにうかがいまして、そのお宅のカレンダーなどをひょいと見ると、びっしり書き込みがあって、ずっと先まで予定がつまっている。おそらく、皆さんも、そうではないかと思います。
そんなふうに、私たちは常に先のことを考えながら暮らしておりますけれど、本当は、明日のことも分からないのが、人生です。この間、アメリカで同時多発テロ事件が起こりましたときに、改めて思いましたのは、このことです。まことに、「人生、一寸先は闇」です。
ご承知のように、アメリカで4機の飛行機がハイジャックされ、そのうちの2機が国際貿易センター・ビルを破壊し、1機がペンタゴンを襲いました。国際貿易センター・ビルに突っ込んでいく飛行機の映像が、テレビで何度も放送されていましたが、自爆テロというよりも、まるで映画を観ているようでした。
何の躊躇いも感じられない、あまりにも見事な突っ込み方で、かえって現実感が薄いようにさえ思いましたが、飛行機に乗っていた人々も、国際貿易センター・ビルや、ペンタゴンで働いていた人々も、その瞬間まで、そんなことになるとは夢にも思っていなかったに違いありません。
まさに、「人生、一寸先は闇」です。ですが、人生の問題は、「一寸先は闇だ」というところにあるわけではありません。私たちは、「一寸先は闇」どころか、今も闇の中にいるのです。修羅の世界にいるのです。そのことこそ、問題なのです。
今度のテロ事件もそうですが、時代は、ますます人間を修羅の方向に推し進めているようにも思います。このまま進めば、人類に未来はないかもしれません。しかし、どんな未来が待っていようとも、私たちは、人間に生まれてきたことの本分を尽くしていきたいと思います。
そこで、本日は、ご案内いたしておりますように、「人身受け難し」という題で、人間に生まれてきたことの意味と、信仰の生活について、ご一緒に考えてみたいと思います。どうぞ、しばらくの間、お付き合いください。
さて、私たち仏教徒がよく称えます、「仏法僧に帰依し奉る」という「三帰依文」の最初に、「人身受け難し、今已に受く。仏法聞き難し、今已に聞く」という言葉が出てまいります。本日の法話の題は、ここから採ったものです。
その意味は、「人間としてこの世に生を受けることは難しいのに、いま幸いにも、この世に人間として生を受けている。また、たとえ人間に生まれても、仏法を聞くことは難しいのに、いま幸いにも、仏法を聞く身となっている」ということです。
ここには、二つのことが言われています。人間に生まれてきたことへの感謝と、仏法に出会えたことへの感謝です。実は、これが「信仰の生活」の全てです。
人間として生まれてきたものにとって、人間に生まれてきたことに感謝できるということは、最高の幸せではないでしょうか。おそらく、それ以上の幸せはないでしょう。とは言え、そんなことは、人間に生まれてきただけでは、とても、できないことでしょうね。
私たちは、人間に生まれてきたがために、暑さ寒さも感じれば、病気にもなり、年老いてもいく。そして、仕事に苦しみ、人間関係に悩み、愛しい人を亡くし、ついには自分も死んでいくのです。
この紫雲寺では、5年前の平成9年から、いま流行のインターネット上にホームページを開きまして、皆さんにお話ししました法話や、「菩提樹」の原稿を掲載いたしておりますので、それをご覧になった方々から、様々なお便りを頂きます。なかには、「学校の宿題を教えて」などという、はなはだ気楽なものもございますけれど、たいていは、かなり深刻な問題を訴えてこられます。
たとえば、子育ての苦しみとか、家族を亡くした悲しみ、人への怨みや憎しみ、生きていることへの焦りや不安、人生そのものへの虚しさなど、おおよそお手軽な答えなど見あたりそうもない深刻な質問が多いのです。こういった問題に悩み苦しまねばならないのも、みな、人間として生まれてきたがためなのです。とても、感謝などという言葉は出てきそうもありません。
「人身受け難し、今已に受く」と言っても、人間に生まれてきただけでは、感謝はできない。そこで、「仏法聞き難し、今已に聞く」ということが大切になってくるわけですが、その話に入る前に、もう少し、人間に生まれてきたということは、どういうことか、考えてみたいと思います。
人間の「身体」というのは、実に素晴らしいものでして、30兆とも60兆とも言われる膨大な数の細胞が、絶妙なネットワークを形成している。そして、その細胞ひとつひとつに、得も言われぬ神秘的な世界が秘められている。人体の構造や仕組みは、実に、驚異と言うより、奇跡です。
いわば、私たち一人一人が、そんな奇跡を授かっているということです。それだけでも十分、感謝に値すると思いますが、その身体の仕組みのなかで、一番問題になってくるのは、免疫の働きです。
身体は、自分と自分以外のものを識別する能力を持っていて、たとえば病原菌のような自分とは異質な物が身体に入ってくると、すぐにそれを排除しようとします。マクロファージや、ナチュラルキラー細胞などが、その異物に襲いかかって食べてしまうのです。これが免疫の働きです。この免疫の働きのお陰で、身体は健康を維持できるわけです。
ところが、私たちが健康を取り戻そうとして臓器移植をした場合、免疫は、移植臓器を異物として排除しようとするのです。移植された腎臓や心臓を、自分ではないと見分けて、拒絶するわけです。そのために、臓器移植を受けた人は、一生、免疫抑制剤を飲まねばなりません。
私たちが、生きようとする努力を、私たちの身体は拒絶する。これは、考えてみれば不思議なことです。「自分」と「自分の身体」とは、どういう関係になっているのでしょうかね。あるいは、身体が設計された時には、部品交換など予想されていなかったので、身体が適応できないだけなのでしょうかね。
ちなみに、こんな話を聞いたことがあります。究極の臓器移植、首のすげ替え実験の話です。もちろん、人間ではありません。ニワトリです。ある研究者が、一羽のニワトリに、別のニワトリの頭を移植したところ、移植そのものは成功したのですが、ニワトリはほどなく死んでしまいました。そこで解剖して調べてみると、免疫による拒絶反応が原因だった。
ところがです、その拒絶反応が起きていたのは、頭部の方だったのです。つまりは、胴体が頭部を異物だと見て、拒絶したということです。身体は、自分と自分以外のものを識別して、自分以外のものを排除しようとする。それが免疫の働きなのですが、胴体が頭部を「自分」ではないと判断して拒絶したということになると、「自分」とは、一体何なのでしょうね。ひょっとすると、身体にとっての「自分」とは、頭ではないということかもしれません。
私は、科学者ではありませんので、専門的なことは分かりませんけれど、ともかく、身体には、本来的に、自分と自分以外のものを区別して、自分以外のものを排除しようとする働きが備わっている。それを、やや感情的な言葉で言えば、「他の誰よりも我が身が可愛い」ということになります。そうすると、つまりは、身体は利己的なものだということになってくるのでしょうか。
では、この身体を形成している根本は何かと言えば、それは、「遺伝子」だと言われています。お寺で聞くような話ではないかも知れませんが、ほどなく仏法の話に移りますので、もう少しだけ、お付き合いくださいね。
「遺伝子」というのは、ご存じのように、身体を作り出す設計図のようなものです。母親と父親は、それぞれ半分づつ設計図を出し合い、1枚の設計図にして、子供に伝えます。親子が似ているのは、そのためですが、最近は、リチャード・ドーキンスという生物学者の書いた『利己的な遺伝子』という本の影響で、人間が利己的なのは、全て利己的な遺伝子のせいだという考え方が流行っております。
たとえば、男が浮気っぽいのも、親が子供を大切にするのも、戦争で殺し合うのも、全ては、遺伝子が自分のコピーを増やし広めるために、人間を乗り物として利用しているだけだというのです。
しかし、そういう考え方は、利己的な人間社会の現状を踏まえて、その責任を遺伝子に押しつけただけのように思います。むしろ、遺伝子のレベルで言えば、あらゆる生き物は仲間だということになるのです。
たとえば、現代のいろんな人種の遺伝子を比較した研究から、原生人類は、今から20万年ほど前にアフリカにいた、たった一組の男女から枝分かれしてきたということが分かっています。いわば、人類は、アダムとイブから生まれたわけです。
また、現在50万種あるとも言われる陸上の植物も、同じように、今から4億5000万年前頃に、たった1種類の淡水植物から枝分かれしたことが分かっています。
動物も植物も、遺伝子は、同じ4種類の塩基からできていて、これらは全て、地球を構成する物質からできているのです。生き物は、みな、地球の子供なのです。その地球は、宇宙の子供です。つまりは、みんな、「仲間」なのです。
仏教では、「一切衆生、悉有仏性」という言葉で、人間だけではなく、あらゆる生き物は仲間だと言っています。また、仏教には「草木国土、悉皆成仏」という言葉もありますから、まさに、宇宙は仲間だいうことです。
以前にも申しましたが、仲間は殺し合わない、仲間は奪い合わない、仲間は欺き合わないのです。それが、仲間です。私たちはみな、「いのちの仲間」なのです。そのことを教えているのが、仏教です。仏教だけではなくて、おそらく、どんな宗教でも、本質的には同じ事を説いているに違いありません。
とすればです、この間、アメリカで同時多発テロ事件が起こったときに、大統領がなさった演説には、問題がある。ブッシュさんは、こういう演説をなさいました。「このようなことは、神はお赦しになるかもしれないが、私たちは、決して赦さない。必ず関係者を捜し出して、この地上から殲滅する」と。
神の名を出すのなら、これは違うと思うのです。今度のことは、アメリカにも非がないわけではない。もし、あのとき、大統領がそのことに気づいて、「私たちは決して赦せないが、神はお赦しになるだろう。我々は、神の御心に従い、これ以上人命が失われない道を探ってみたい」とおっしゃっていたら、ブッシュさんは歴史に残る大統領になったでしょう。
まあ、現実は、そうではありません。アメリカ議会の武力行使容認決議で、535名いる議員のなかで、反対したのは、バーバラ・リー下院議員、たった一人でした。彼女は、「少し立ち止まって冷静になりましょう」と呼びかけました。歴史に名が残るのは、この人かもしれませんね。
テロを弁護する気など毛頭ありませんが、今回のことは、一部のテロリストたちを何とかすればよいという問題ではないのです。問題は、アメリカによって、そこまで追い詰められている人々がいるということです。
学校のいじめでも何でもそうですが、追い詰めている人には、追い詰められている人の気持ちが分からないのかもしれません。しかし、アメリカには気づいてほしいと思います。ブッシュさんは、さきの演説で、神の名に触れられましたが、宗教の世界は、触れるだけでは、さほど意味がありません。宗教は、それを生きてこそ意味があるのです。
私たちが利己的なのは、身体に原因があるわけでも、遺伝子に責任があるわけでもありません。遺伝子は身体の設計図であり、身体は、生老病死を逃れられない無常のものとして設計されているのです。その無常の身体を、「他の誰よりも我が身が可愛い」と握りしめているものが、私たちの心のなかにある。それこそが、私たちを利己的な行動に駆り立て、悩みや苦しみを生みだしている原因なのです。
私たちの心のなかには、闇がある。修羅の棲む闇があるのです。修羅というのは、戦いを好む生き物のことです。しかし、私たちは、たいてい、そんな修羅の棲む心の闇に気づいていません。ましてや、自分が、戦いを好んでいることになど気づいてはいませんね。むしろ、私たちは、心から平和を願っていると思っているのです。
ですから、国際貿易センター・ビルに突っ込んでいく飛行機をテレビで見ながら、心のなかでワクワクしている「善人」もいれば、「やれ!やれ!もっとやれ! ハイジャックされた他の飛行機はどうしたんだ。この際だ、徹底的にやってしまえ。アメリカのような身勝手な国は平和の敵だ」と叫んでいる「正義の味方」もいるわけです。
アメリカも同じでしょう。正義は自分にあり、自分は善であって、悪を排除すれば、世界が平和になると思っている。ですが、私たちの心のなかに、修羅の棲む闇が残っている限り、世界から戦争の無くなる日は来ないでしょう。
仏教は、この、心のなかの闇を問題にしているのです。いつも申しますように、人間は、「修羅」と「仏」の間に生まれてきます。そして、知らないうちに、修羅へ修羅へと流されて行くのです。ですが、わずかではあっても、自分の心のなかの闇に気づいて、その闇に苦しんでいる人もいる。仏教は、そういう人のためにあるのです。ところが、それがまた、仏教が、なかなか理解されない点でもあります。
さて、話を戻しましょう。私たちは、人間に生まれてきたというだけでは、なかなか、人間に生まれてきたことを喜べるものではありません。人間関係をはじめ、様々なことに悩み苦しまねばならないのも、人間に生まれてきたがためなのです。
そもそも、この身体が、自分と自分以外のものを識別して、自分以外のものを排除することで成り立っているとすれば、人間は、本質的に利己的なものなのでしょうか。私たちが、これほどまでに人間関係に苦しむのも無理はないということになるのでしょうか。
そうではないのです。身体は大切ですが、身体が「私」の本質ではないのです。たしかに、「私」は已に利己的なものとして存在しています。私たちが人生に対して抱く関心は、煎じ詰めれば、全て利己的な関心です。そして、その利己的な関心が満たされないところから、悩みや苦しみが生まれてくるのです。
ですが、その利己的な関心は「私」の本質から生まれてくるわけではありません。利己的な関心の源にあるのは、無常な身体を握りしめて、これが「自分」だと思っている、心のなかの闇なのです。「私」の本質には、利己的なものは何もありません。「私」の本質は「仏」なのです。そのことを教え、その本質に目覚めることを促しているのが、仏教なのです。
しかし、この、仏法の話というのは、分かり難いものですね。まあ、実際、何を言っているのか分からないという話もありますが、仏法の話は、話として聞いている間は、分からないものなのです。人間としての悲しみと申しますか、何らかの内面的苦悩がないと、仏法の話を聞いても、自分の問題として聞こえてこないのです。自分の問題として聞こえてこないから、仏法を求める想いなど湧いてこない。
私たちは、たいてい、「学校を出て、仕事に就き、結婚して、子供ができ、車を買い、家を手に入れ、それなりに幸せに生きられたらそれでよい」と思っています。「辛いことや嫌なこともないわけではないけれど、人生って、そんなもんだ。できることなら、お金の苦労をせずに、死ぬまで快適に暮らせたら、それで結構」と、まあ、そういう生活をしておりますが、そういう生活では、まず、仏法への必要性など感じないものでしょうね。
実際、仏教は、あれが欲しい、これが欲しい、ああ成りたい、こう成りたいという、私たちの世俗的な欲望を満たすための教えではありません。ですから、仏教というのは、本来、「せめて人並みの幸せを、できれば人並み以上の幸せを」と、相対的な世俗の幸せを求めている人の、役には立たないものです。
そのことが分かっていないものですから、「自分が困ったときに、思い通りに救ってくれなかったから、神も仏も信じない」とか、「人生、何十年も生きてきたら、神も仏もいないことくらい分かりそうなものだ」というような、見当違いのことを言う人もでてくるわけです。仏教は、都合良く願いを叶えてくれる教えでもなければ、社会に適応するための教えでもないのです。
仏教は、貧しい人がお金持ちになるための教えではない。名もない人が有名になるための教えではない。病人が健康になるための教えではない。更に言えば、老人が若者になるための教えではない。女が男になるための教えではない。悪人が善人になるための教えではない。そうではなくて、仏教は、人が「仏に成る」ための教えなのです。
「仏に成る」というのは、「本当の自分に成る」ということです。ですがそれは、何かを手に入れて何かに成るということではありません。私たちが既に持っている「いのち」の真実に気づき、「私」の本質に目覚めることを言うのです。
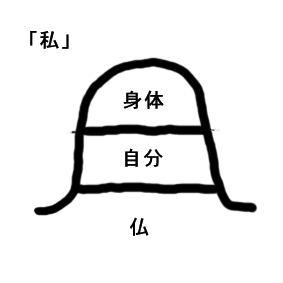
今までに何度もご覧頂いた図がありましたね。私たちの「いのちの全体像」の図です。簡単に描きますと、こんなふうに小山になっている。一番上が「身体」で、その身体にしがみついている「自分」の心がある。そして、その全体を、下から支えている「仏」の心がある。「私」の本質というのは、この「仏」のことですね。
人間に生まれてきた「私」は、仏法に出会うことで、「私」の本質に目覚めていけるのです。そこで、「三帰依文」は、「仏法聞き難し、今已に聞く」と続くのです。
では、私たち真宗門徒が出会っている仏法は、どういう教えかと言えば、それは、「弥陀の本願を信じ、念仏を申さば仏に成る」という教えです。
「弥陀の本願」というのは、『無量壽経』というお経に記されている、阿弥陀如来の誓願を言います。その誓願とは、「誰であれ、清らかな心で(至心に)、私を信じて、私の浄土に生まれたいと念じ、十回でも私の名前を呼ぶならば、必ず、私の浄土に生まれさせよう」というものです。
この阿弥陀如来の誓願を信じて、南無阿弥陀仏という仏の名号を称える。それが、私たちの信仰の内容です。
いかがですか。皆さん。「たった、それだけか?」と思われるかもしれませんが、たった、これだけです。親鸞聖人の時代にも、「本当に、それだけか?」と思われた方々がおられまして、こういう話が伝わっています。
京都におられた親鸞聖人のもとに、関東から門徒の方々が必死の思いで訪ねてこられて、「本当に、それだけですか?」とお尋ねになった。そのとき、親鸞聖人は、はっきりと、こうお応えになっています。「親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なし」(『歎異抄』第2条)と。
「弥陀の本願を信じて、念仏を申さば仏に成る」。言葉にすれば、たった、これだけのことですが、この教えが生活のなかに展開する、教えを生きる、ということになりますと、大変な力となって、人生の様相を変えてしまいます。教えは、人生を、迷いの縁から、悟りの縁へと転じていくのです。
「教えを生きる」ということは、「信仰に生きる」ということ、「信仰の生活」を送るということですが、「世俗の生活」を離れて「信仰の生活」があるわけではありません。とは言え、「世俗の生活」と「信仰の生活」は、違うのです。
私たちは、何をする場合でも、目を外に向けて、将来を予測し、結果に期待しながら行動します。それが「世俗の生活」です。つまりは、「自分」が世界をコントロールしようとする生活、「自分」を信じる生活が、「世俗の生活」です。
それに対して、「信仰の生活」は、目を内に向けて、「仏」を信じ、お念仏の上に世界を受けとめていく生活です。別の言葉で言えば、「信仰の生活」とは、生かされて生きる生活、「お任せと、お与え」の生活なのです。
もう少し詳しく申しますと、こういうことです。目を外に向けて生活していると、世界には、善と悪とがあるように見えます。たいていの人は、善を求め、悪を厭い、できるだけ善いことをしようと思っています。ですから、困っている人を見れば、何とか助けてあげたいと思うわけです。それはそれで、大切なことですね。
ですが、困っている人を助けてあげれば、心のどこかに、感謝を期待する思いもありますね。せめて、「ありがとう」の一言でもないと、不愉快になるものです。それを、感謝もなしに、当然とばかりの態度だったら、今度は、腹が立つ。私たちは、善いことをしても、それで終わらないのです。無意識のうちに、見返りを期待しているのです。
「いや、そんなことはない。人は何とも思わなくとも、善いことをするという、そのことだけで十分なんだ」と言う人もおられるでしょう。そう思えたら結構なことですが、それでも、「自分は善いことをした」という自己満足は残るのではないでしょうか。
私たちは、何をする場合にも、無意識のうちに「自分」の満足を求めているのです。宗教的な修行でも同じです。「今日は、自分の利己的な思いに打ち勝った」などという思いも、結局は、自己満足なのです。つまりは、私たちは、この、どこまでも利己的な「自分」に気づかずに、善だ悪だと言いながら生活している。それが、「世俗の生活」なのです。
それに対して、目を内に向けて生活していると、だんだん利己的な「自分」が見えてきます。自分には、善だ悪だと言っている余地がない。ただただ、悪だと気づいてくるのですね。親鸞聖人は、ご自分のことを、こうおっしゃっています。「欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおく、ひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえず」(『一念多念文意』)と。
ここまで、「自分」を見抜けたら、「自分」には利己的な思いしかないと気づけたら、そんな利己的な「自分」の努力で、利己的な「自分」を超えることなどできないことが、はっきり分かってくるでしょう。いつも申しますように、右手で右手はたたけない、自分で自分は持ち上げられないのです。
利己的な「自分」を超えるとは、人間を超えるということ、つまりは「仏に成る」ということです。「自分」の努力では、つまり「自力」では、此岸から彼岸に渡れないとなれば、已に人間を超えている「仏」の力に頼るしかない。つまりは、「他力」に頼るしかないということです。
「自分」を信じられなくなった「私」にとっては、「仏」を信じる以外に選択肢は無いのです。「私」は、「仏」を信じて、お念仏を称えて生きるしかない。「私」は、全てを「仏」にお任せした。そして、お念仏を称える生活のなかで、起こってくること全てを、「仏」からのお与えとして真剣に生きる。それが、「生かされて生きる」ということ、「信仰を生きる」ということなのです。
「信心」というのは難しいですね。「これが信心だ」と握ってしまうと「自力」になる。「信心」というものは、掌の上に、水を張ったコップを載せて、しずしずと歩くように深めていくものでして、握らないようにすることが大切なのです。握りしめて、その上に胡座をかいてしまうと、信心が害になってしまいます。
しかし、私たちは、人生が自分の思うように流れている時や、自分の努力で何とかなると思っている間は、なかなか、自分が迷いの縁を生きているとは思えないものですね。私たちは、自分の能力や努力が全てだと、どこまでも、自分を信じて生きようとする。そんなふうに、「自分」を信じている間は、「仏」は信じられないでしょうね。
現代社会に生きる私たちは、どこまでも自分を信じて努力するという教育を受けて育ちますので、なかなか仏法への縁が開けてこないのです。おそらく、自力の限りを尽くして、もう駄目だというところまでいかないと、立ち止まれないのかもしれませんが、そのとき間に合うかどうかは分からないのですね。
以前、NHKのテレビで、「ガンと生きる」というシリーズが放送されたことがあります。ご覧になったかもしれませんね。その第1回目でしたか、作家の日野啓三さんのお話しでした。
日野さんは、現在71歳だそうですが、10年前の60歳のときに腎臓と膀胱のガンにかかり、それ以来、ガンや蜘蛛膜下出血で、合計4回もの手術を受けてこられたといいます。その日野さんは、こんなことを話しておられました。
「10年前に初めてガンになったときは、目のまえ真っ暗で、頭のなか真っ白になった。夜に、仏教の本を読んでも全然ダメで、心がおさまらない。そこで、水辺に行きたいと思って、電車で奥多摩渓谷に行った。名もない小さな駅で降り、夏の夕方、崖を下りて谷川の側に座って、水を眺めていた。蝉の声が聞こえ、緑の樹に囲まれているうちに、少し落ち着いた気になった。
けれど、日が暮れてきて、そうだよな、今になって、60歳になって、急に自分が怖くなったから助けてくれって言って、自然に、水でも樹でもいいですけれど、すがりついたって、それは、あんまり虫がよすぎる、と言われたような気がした。都市的・近代的な生活をして、文明にどっぷりつかっていて、いまさら虫がよすぎるよ、と言われた気がした。もともと、そういう生活をしていなきゃ、いざというときに助けてくれませんよ」と。
聞いていて、よく分かるような気がしました。自然だけでなく、仏法でもそうなのですね。いよいよ困ったという時になって、ひとつ仏教でも、と思っても、普段から仏法に親しんでいないと、おそらく何の助けにもならないのではないかと思いますね。
番組の最後に、日野さんは、こういう話をなさいました。「夜、目が覚めて、どうしようもなく、やりきれないときは、このごろね、シベリアの北極圏にいるオオカミのようにね、オオカミの遠吠えのようにね、夜中に一人で、声を出すんですよ。オー、オー、オーってね。
すると、なんか自分の気持ちをね、言葉で言えない、なんかあの、シベリアのオオカミの遠吠えのようなね。すると少し気持ちが楽になります。声を出すほうがいいです。しかも尾を引いて、オー、オー、とね。女房は近所に気兼ねしてやめてくれと言いますけれどね、今でも、ときどきやってます」と。
この話を聞いていましてね、「ああ、これは日野さんのお念仏なんだ」と思いました。「オー、オー、オー」というのがですね。何とも切ないですけれど、これは、「いのち」に呼びかけ、「いのち」を確認しているのだと思いましたね。
私たちが、「南無阿弥陀仏(ナマンダーブ)」と称えるのは、私たちの「いのち」の奥底に眠っている「本当の自分」に、呼びかけているのです。その「いのち」の奥底に眠る、「私」の本質の、秘密の名前、聖なる名前が、「南無阿弥陀仏(ナマンダーブ)」なのです。
名前を知らないと呼びかけることもできません。思えば、「この名をよびなさい」と、名前を教えてもらっているということは、本当に幸せなことなのです。
これは別の話ですが、『鳥の歌』という歌があります。上々颱風という、ちょっと個性的なグループの歌なのですが、その歌の歌詞に、こういう一節があります。「あの日あなたに出会わなけりゃ、どんな夢をだきしめよう、もしも森にさまよったら、誰の名まえを呼んだらいいの」と。
これは、恋歌なんですが、なにか、こう、「迷ったときに呼ぶ名前がある」というところに、共鳴するものを感じますね。「あの日あなたに出会わなければ、どんな人生になっていただろう、もしも道に迷うことがあっても、もう呼びかける名前を知っている」。こういうふうに言い換えたら、なにか、阿弥陀様への恋歌みたいですね。
「南無阿弥陀仏(ナマンダーブ)」というのは、聖なる名前です。かつては、その聖なる名前を、家庭で教えられたものです。「家の宗教」が、しっかりしていたからです。今や、家の宗教と言っても、お葬式のときに多少問題になる程度になってしまいましたが、本来、家の宗教というのは、そういうものではありませんでした。
皆さんも、ご存じだと思いますが、伊藤忠商事という大きな会社がありますね。あの伊藤忠商事の初代創業者は、伊藤忠兵衛という近江の人で、真宗の門徒さんでした。百数十年も前の話ですが、この忠兵衛さんは、亡くなるときに、二代目の忠兵衛を枕元に呼んで、こう遺言なさった。「たとえすべての事業・財産を失うことがあっても、他力安心の信心を失ってはならない」と。これが、「家の宗教」の本来の姿です。
ちなみに、伊藤忠商事では、「商売は忘れても、毎日のお勤めは忘れるな」と、店員全員に『正信偈』の本とお数珠を持たせて、朝夕、店内のお仏壇に向かって、全員でお勤めをすることになっていた。そういう習慣は、戦後まで続いていたそうですが、そういう会社が、日本を代表するほどの総合商社にまで発展したのですから、考えてしまいますね。
誤解のないように申し上げておきますと、仏教は禁欲の教えではありません。仏教は、財産や地位や健康を問題にしませんけれど、それは、お金持ちになってはいけないとか、有名になってはいけないとか、健康になってはいけないとか、そういうことを言っているわけではありません。そうではなくて、そんなことは人生の本筋ではないと言っているだけなのです。
家には、財産ではなくて、人生の本筋としての信心を伝えていく伝統があった。それが「家の宗教」なのです。そして、そういう家の日常生活のなかで、子供は、仏法の話を聞き、「信仰の生活」を身につけていったのです。
そういう家では、正月に門松を立てることもなく、七五三のお参りもせず、葬式で塩をまくこともありませんでした。また、占いも、縁起担ぎも、物忌みもせず、おふだも、お守りも頂かない。およそ世間の行事や習慣には関わらない生活をしていましたから、「門徒物知らず」とか「真宗は、かんまん宗だ」とか悪口を言われることもありましたが、人生の本筋だけは外さなかった。
家の中心にはお仏壇があり、朝夕のお勤めをかかさず、仏法の話を何よりの楽しみとして、仏法にご縁を頂けたのは御先祖のお陰と、喜んで暮らしていたのです。引っ越しのときにも、一番最初に家に入るのは、お仏壇でした。
そういう生活で大切にされた言葉が、「有り難う」「お陰様で」なのです。「有り難う」「お陰様で」という言葉は、生まれ難き人間に生まれ、出会い難き仏法に出会えたことへの感謝の言葉なのです。
しかし、それはたしかに、現代から言えば、まことに信心深い生活なのですが、そういう生活のなかでも、「まことの信心を得る」ということは非常に難しかったのです。というのはですね、「仏法を喜び、仏法を信じる」と言っても、その信心が、「自分」の信心であっては意味がないからなのです。
「自分は仏様を信じている」とか、「自分はお念仏を称えている」とか言っている間は、まだまだ本物ではない。というのは、先ほど申しましたように、「自分」は利己的なものとして存在しているからです。ですから、「自分」の行うことも、口にすることも、考えることも、全て利己的なものなのです。
つまりは、「自分」が信じている限り、それは決して「清らかな心で信じている」ということにはならないということです。同様に、南無阿弥陀仏という名号を称える場合でも、「自分」が称えている限り、それは「清らかな心で称えている」ことにはなりません。
「自分」が、どれほど真剣に信じ、どれほど真剣にお念仏を称えようとも、そこに「自分」という意識が残っている限り、「清らかな心」とは言えないということです。なにしろ、「自分」は、本来、利己的なものとして存在しているのですからね。
勿論、人間には利己的なことしかできないと言っているわけではありません。たとえば、川を流されている子供を見て、自分が泳げないことも忘れて、飛び込んでしまったとかいう話をお聞きになったことがおありでしょう。
実際、私たちは、我を忘れて、他人のために命を投げ出すこともあるのです。ですが、そのときには、文字通り「我を忘れている」のです。つまり、そのとき、「自分」は何も考えていない、「自分」は何もしていないのです。
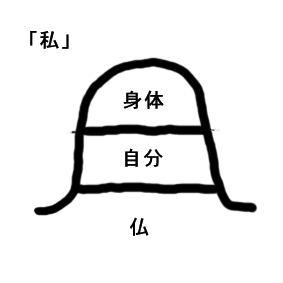
先ほどの図を思い出してくださいね。「自分」が働いていないとき、「仏」が働くのです。「自分は信じている」とか、「自分は称えている」とか言っている間は、「仏」は働かないのです。ただ一心に「弥陀の誓願を信じ、念仏を称える」生活のなかで、いつとはなしに「自分」が消えていく。
そのとき初めて、「仏」が働き出し、念仏の行者は、仏の慈悲を経験するのです。慈悲というのは、利己的なものが全くない感情です。それは、仏の感情なのです。
そのとき、「自分」は消えて、「仏」が「身体」の主(あるじ)となっている。そのとき、お念仏を称えているのは、「自分」ではなくて「仏」なのです。まことの信心を得た人が、「お念仏が出てくださる」と言われるのは、このことなのです。
言葉を替えて言えば、「自分」が「仏」に成ることなど、絶対にあり得ないのです。「自分」が死んで、「仏」となって甦るのです。「信に死して、願に生きん」と言われた方がおられますが、それは、このことなのです。信心のなかで死ぬものは、利己的な「自分」です。「自分」が死ぬと、「自分」に代わって、「本願」が生きてくださる。「仏」が、私の身体の主となって生きてくださるのです。
「仏」を信じているのも「仏」、お念仏を称えているのも「仏」。そうなって、初めて、まことの信心となる。まことの信心というものは、「自分」の信心が挫折を経験しないと、得られないものなのです。
人生に挫折し、「自分」の信心に挫折して、初めて、まことの信心が得られる。人生には挫折したけれど、「自分」の信心に挫折していないと、まことの信心は得られない。人生にも挫折していないという人は、信心からは遠いところにいる。おそらく、そういう人は、仏法には関心が無いでしょうね。
「真宗は、簡単だ、易行だ」と申しますけれど、決して、そうではありません。真宗は、実に難しいのです。「弥陀の本願を信じ、念仏を申さば、仏に成る」。言葉で言えば、たった、これだけの教えですが、その教えを体得することは難中の難で、これより難しいことはないのかもしれません。
その教えを本当に体得した人は、あまり多くはないでしょう。昔は、まことの信心を得た人を、「妙好人」と呼んで、尊敬し、敬愛したものですが、その妙好人と呼ばれた人は、「国に一人、郡(こおり)に一人」と言われるくらい、少なかったのです。
と申しましても、何も、ガッカリさせようとしてお話ししたわけではありません。「信仰の生活」というものは、そこまで深まっていくものだということを、お話ししたかっただけなのです。
「自分は信じる」「自分は称える」というのは、まだ「自力」なのです。「自分は、自分は」と言うのをやめて、「お任せします。何であれ、起こることが起こりますように」と、全てを受け入れる準備が整ったとき、そこに自然に「他力」が働き出すのです。
「全てを受け入れる」とは、いつも申しますように、「私が必要とする事ではなく、私に必要な事が起こってくる。私が必要とする物ではなく、私に必要な物が与えられる」という、「いのち」への無条件の信頼です。この「無条件の信」を深めていくこと、それが「信仰の生活」なのです。
信心を頂いても、悲しいことや苦しいことが無くなるわけではありません。「信仰の生活」のなかにも、悲しいことや苦しいことが起こってきます。ですが、それをもお与えとして、「お念仏」の上に受けとめていく。昔の人が、「悲しいことも苦しいことも、全て、仏様のお諭しです。お育てを頂いているのです」と言われたのも、そのことです。
「弥陀の本願」というのは「仏の願い」のことですが、「仏」というのは、「本当の自分」のことなのです。つまりは、「弥陀の本願」というのは、「本当の自分の願い」のことなのです。
「本当の自分」が、私たちに願っているのです。「本当の自分」の名を呼んで、思い出してほしいと願っているのです。その願いに応えることは、人間として生まれてきた私たちにとって、最も大切な務めであり、一生の仕事なのです。だからこそ、「修行」とは言わずに、「信仰の生活」と言うのですね。
「清らかな心で仏を信じ」、「清らかな心でお念仏を称える」。と言っても、私たちの心は、とても清らかとは言えません。清らかな心というのは仏の心です。最初から、清らかな心だったら、信心もお念仏もないのです。
清らかな心でないからこそ、お念仏を称えるのです。仏の願いは、まさに、そのことにあるのです。清らかな心でない私たちが、お念仏を称えること。それが、仏の願いなのです。どうぞ、皆さん、お念仏を大切になさってくださいね。ご一緒に、お念仏を称える生活のなかで、命の続く限り、仏の願いを実現していきましょう。
さて、話が長くなりまして、申し訳ございません。本日は、ここまでにさせて頂きます。相も変わらぬ理屈っぽい話に、お付き合いくださいまして、有り難うございました。
「人生、一寸先は闇」ですが、また、ご一緒に、聞法させて頂けるよう願っております。どうぞまた、お参りください。有り難うございました。ナマンダーブ、ナマンダーブ。
紫雲寺HPへ