本日もまた、ご縁を頂きまして、仏法の話をさせて頂くわけですが、この仏法の話というのは、聞いても聞いても、なかなかストンと腑に落ちないのですね。
かつて、清水寺の大西良慶貫首も、そのことを嘆いて、こんなふうにおっしゃったそうです。「話がスーッと通るのが通(つう)や。このごろはやたら節(ふし)が多くって、話がなかなか通らない」と。「節というのは、常識のことでしょうか」とお尋ねすると、その通りだと、お答えになったといいます。
仏法は、世間を超えていく道を説いているのですが、私たちの「頭」は、たいてい、世間の常識や価値観にしばられて、身動きとれなくなっています。ですから、聞いた話が「頭」に溜まって、腑に落ちない。つまりは、「頭」が、邪魔をしているから、スーッと通らないのですね。
いつもお話いたしますように、仏教は、心安らかに生きるための教えです。ですから、これまでも、安らかな心を求めて、もっぱら「心」を中心に、仏法の話をしてまいりました。ひとことで言えば、「心」が安らかでないのは、「心」が「頭」に支配されているからです。つまりは、「心」が「頭」とセットになっていることが、苦しみのもとなのです。
本来、仏教では、「心」は、「頭」とではなく、「体」とセットになっていると説かれています。「心と体は分けられない」。仏教の言葉で言えば、「身心一如」です。これが、「いのち」の本来の姿です。
仏法の話は、なかなか腑に落ちないと言いますけれど、「腑に落ちる」というのは、「内蔵にまで、気持ちよく、スーッと通る」ということでしょう。その言葉通り、仏法は、「体」と「心」がセットになっているときに、腑に落ちるものなのです。
そこで、今回は、ちょっと趣を変えまして、「身心一如」(しんじんいちにょ)という題で、「体」を中心に、お話してみたいと思います。はたして、スーッと通るような話ができるかどうか分かりませんけれど、どうぞ、しばらくの間、お付き合いくださいますよう、お願い申し上げておきます。
さて、仏教では、「身心一如」、「体と心は分けられない」と説かれているわけですが、実際、私たちの日常的な経験からいっても、「心」と「体」はつながっていることが分かりますね。
たとえば、興奮すると、手に汗が滲み、腹が立つと、血圧が上がり、恥ずかしいと、顔が赤くなります。こういったことが起こるのは、「心」が「体」につながっているからです。これは、「心から体へ」という流れですが、その反対の例もあります。
たとえば、最近の子供はよくキレるといいますが、その原因は、ジャンクフードやジュースばかり摂っているために、栄養が偏り、血糖値が乱高下することにあるといわれています。
つまりは、「体」の不調が「心」の不調になって現れているのです。ですから、こういう場合には、「体」に目を向けずに、「心」のカウンセリングだけで対処しようとしても、良い結果が得られません。
東洋医学でも、「体」が悪いと「心」が乱れ、「心」が乱れると「体」が悪くなると言われています。たとえば、肝臓が悪いと、怒りっぽくなる。反対に、怒ってばかりいると、肝臓が悪くなる。また、腎臓が弱っていると、恐がりになる。反対に、恐ろしい経験をすると、腎臓を傷めるといいます。「体」と「心」はつながっているのです。
「体と心は分けられない」のです。仏教の伝統のなかには、肉体を不浄なものとして嫌悪する傾向もありますが、それは間違っていると思いますね。「体」は、大切です。実際、お釈迦様でも、病気になられたときには、当時の医療を受けられましたし、出家修行者に対しても、病気のときには、戒律を緩めて、健康の回復に勤めることが認められておりました。
「体」を調えるということは、「心」を調えることにつながります。「体」を調えると言えば、自ずと、健康の話になりますので、この「健康」の話から始めることにいたします。
以前、総理府が調べたところによりますと、「健康に不安を持ち、健康が人生の目的だと考えている人」が、50パーセント以上もあったといいます。「健康が人生の目的」というのは、ちょっと理解できませんけれど、まあ、そういう世相を反映して、テレビでは、連日、健康番組が放送され、実に、さまざまな健康法が、日替わりメニューのように紹介されています。
しかし、そういった健康法は、たいてい、誰かが「頭」で考えたものでして、全部正しいと思っていたら、「体」を壊してしまいます。「健康に良いことは、体に悪い」と言う人もいるくらいですが、健康法で「体」を壊していては、洒落にもなりません。
東洋医学では、私たちが病気になる原因は、「冷え過ぎ」と「食べ過ぎ」にあると言われています。いささか、仏教の本筋から外れるようですが、「体」に対する、先人の知恵を、少し覗いておきたいと思います。
まずは、「冷えは万病の元」ですが、これは、西洋医学から見ても、理にかなった考え方だと思います。私たちは、生きるために、ご飯だとか、野菜だとか、いろいろなものを食べますね。そういった食べ物が消化されて、血や肉になり、活動するエネルギーになる。私たちの体のなかで、食べ物を血や肉やエネルギーに変える化学反応が起こっているのです。
その化学反応を起こしているのは、酵素という触媒作用をもったタンパク質です。体のなかでは、数千種類の酵素が働いている。そういった酵素が働かないと、生命活動が維持できないわけですが、この酵素が最もよく働く温度が、36.5度前後なのです。
私たちの体温が、常に36.5度あたりに保たれているのは、酵素が最も働きやすい温度を維持するためなのです。つまりは、体が冷えると、酵素の働きが鈍くなり、生命活動全体のレベルが下がってしまうというわけです。
そうなると、血液の循環も悪くなり、酸素や栄養の供給も滞り、老廃物の排出もできなくなります。東洋医学では、汚れた血液が体内で滞ることが、病気を引き起こす原因だと考えられていますが、たしかに、血液のなかには白血球や免疫物質が流れておりますから、血液の流れが悪くなると、免疫の働く力も低下してきて、風邪にもかかりやすくなり、病気も治りにくくなります。「冷えは万病の元」なのです。
癌でもそうですね。よく動いて温度の高い、心臓や小腸はめったに癌になりません。癌になるのは、たいてい、動きが遅くて、温度の低い、肺や大腸ですね。
健康のためには、冷えないようにすることが大切なのですが、現代の生活は、クーラーとか、冷たい食べ物や飲み物のせいで、冷え過ぎになりやすいのです。
子供の体温は、大人より高いのが普通ですが、現代の日本には、35度台しかない子供が増えているといいます。鬱になったり、自殺をしたりする子供の体温は、かなり低いそうですが、ボーっと地べたに座り込んでいる子供なども、そうかもしれません。
「心」の問題は、「心」だけでは片づかないのです。「体と心は分けられない」。冷え過ぎは、「体」だけでなく、「心」にも良くないのです。「冷えすぎ」の次は、「食べ過ぎ」についてです。
「人間は、食べる量の四分の一で生きている。残りの四分の三は医者が食べている」。これは六千年前のエジプトのピラミッドの碑文に書かれている文章だそうですが、「食べる量のうち四分の三は食べ過ぎだから病気になる、それが医者の食い扶持になるのだ」という意味です。
日本でも、「腹八分が健康の元」と言われておりますように、食べ過ぎが「体」に良くないことは、昔から、よく知られておりました。実際、癌や、心臓病、肝硬変、糖尿病、高血圧症、肥満などの、いわゆる生活習慣病が爆発的に増えたのは、「飽食の時代」と呼ばれる現代になってからです。
アメリカの栄養学者が、ネズミを使って実験したところによりますと、餌を60パーセントに制限したネズミは、満腹まで食べたネズミの倍以上、健康で長生きしたといいます。「腹八分」であれ「60パーセント」であれ、少食は健康の決め手です。
かつて、厚生省は、栄養素を考慮して「一日30品目の食品を食べよう」などと言っておりましたが、そんな食べ方をしている国は、世界中どこにもありません。まあ、不都合なことが分かったとみえて、最近では厚生省も言わなくなりましたが、まともに30品目など食べたら、確実に、食べ過ぎになって、「体」を壊してしまいます。
厚生省が奨める、一日に摂取すべきエネルギー量は、成人だと、約2000キロカロリー。安静でじっと寝ている状態でも1400キロカロリーが必要だということになっております。ですが、これは、栄養学からみた、理論上の数値でしかありません。
かつて、静岡県の三島にある龍沢寺という臨済宗のお寺で、修行僧の一日に食べたカロリーと使ったカロリーを確かめるという実験が行われたことがあります。その結果、驚いたことに、食べたカロリーよりも、使ったカロリーの方が、ずっと多かった。それなのに、修行僧たちは、体格も立派で、病気もせず、修行に励んでいるというのです。
同じような実験が、京都の圓福寺という臨済宗のお寺でも行われましたが、こちらも同様の結果でした。ひょっとすると、カロリーを中心に考える現代の栄養学は、間違っているのかもしれませんね。
食べ物に関して言えば、残念ながら、現在のところ、環境汚染や、農薬や、食品添加物のために、完全に安全な食品というものはありません。昨年出版された、『食べるな、危険!』という本を読みますと、いかに毒まみれの食品を食べているか、空恐ろしくなります。
ところが、医学博士の西岡一という先生の研究によりますと、唾液には発ガン物質を分解する働きがあって、天然の物であれ人工の物であれ、多くの発ガン物質の毒性は、唾液を30秒間加えるだけで、ほとんど消えてしまうといいます。
とするとです、何を食べるにせよ、よく噛んで食べれば、あまり神経質になることはないということです。西岡先生は「一口三十回」とおっしゃっていますが、よく噛んで食べると、自ずと少食になっていきますから、結局は、「よく噛む」という、昔から言われていることが、少食と健康の決め手というわけです。
寒いと感じたら、冷え過ぎないうちに、用心する。また、物を食べるときには、腹と相談しながら、よく噛んで食べる。ファッションや栄養学を詰め込んだ「頭」で考えるのではなく、「体」のことは、「体」に聞いて調える。結局は、そんな、あたりまえのことが、「いのちの真実」に最も適った健康法なのです。
ところが、快適で贅沢な生活をすることが幸せだという、現代社会の価値観で「頭」がガチガチになっている私たちには、なかなか「体」の声が聞こえてこないのです。そのために、冷え過ぎても感じない、食べ過ぎても感じないのです。
ご馳走を見れば、美味しそうだと思いますし、口に入れると、これがまた、美味しいのですね。ですが、「口に極楽、胃に地獄」という言葉もありますように、「頭」の食欲と、「体」の食欲は違うのです。
また、夏には、毛穴が開いていますから、冷えが「体」の奥深くまで入ります。いったん、「体」に入り込んだ「冷え」は、なかなか抜けません。
それに、現代は、電気のお陰で、明るい時間がうんと長くなりましたが、何万年も、太陽の運行に従って生きてきた私たちの「体」は、明るい時間が長いと「夏だ」と受け止めます。ですから、「体」は、どこかで「夏用」に調整されている。そういうこともあって、現代は、冷え過ぎになりやすいのですね。
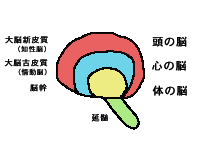 話を進めます前に、ちょっと、こちらの図を、ご覧ください。これは、私たちの「脳」の模式図です。人間の脳は、このように三層構造になっています。
話を進めます前に、ちょっと、こちらの図を、ご覧ください。これは、私たちの「脳」の模式図です。人間の脳は、このように三層構造になっています。
一番内側にあるのが「脳幹」で、延髄をとおして脊髄につながっています。ここでは、内臓の働きや、呼吸などの、基本的な生命活動をコントロールしています。ここは、いわば、「体」の脳です。
その「脳幹」の外側にあるのが、「大脳の古い皮質」で、「情動脳」とも呼ばれています。ここでは、快・不快などの情動をコントロールしています。ここは、いわば、「心」の脳です。
そして、一番外側にあるのが、「大脳の新しい皮質」で、「知性脳」と呼ばれています。ここでは、人間らしい高度な知性や感覚などを司どっています。ここは、いわば、「頭」の脳です。
「知性脳」は、社会に適応して、人間らしく生きるための脳です。人間である以上、社会に無縁で生きていくことはできませんから、「知性脳」がしっかりしていることは必要なことです。ですが、「知性脳」が勝ちすぎるのも、問題です。
たとえばです、仕事でクタクタになっているのに、体力をつけるためにと、ジョギングに飛び出していくなどというのは、「ジョギングは体に良い」と思い込んでいる「頭」の声に、「休もう」という「体」の声がかき消されているからです。
また、病気になったときには、たいてい、食欲が無いものですが、そんなとき、私たちは、「十分な栄養を摂ることが必要だ」と考えて、無理にでも食事をしようとしがちです。
ですが、食欲が無いのは、物を食べれば、体のエネルギーが、消化吸収作用の方にまわされて、病気と闘うための免疫作用にまわされるエネルギーが少なくなってしまうからです。「体」は知っているのです。だから、食欲がわいてこないのです。
「体」のことは、「頭」の声にではなく、「体」の声に耳を傾けねばなりません。「体」は、何が必要かを、知っているのですから。
お釈迦様の時代の出家修行者たちは、「三衣一鉢」(さんね・いっぱつ)と言いまして、「体」に巻く三枚の布と、食事を受ける一つの鉢しか持っていませんでした。「体」は、「三衣」もあれば冷え過ぎにならず、「一鉢」に受ける食べ物で充分だったのです。
「知足」という言葉をご存じだと思いますけれど、あれは、「贅沢なことを言っているとバチがあたるから、このへんにしておこう」というのではないのです。そうではなくて、「体」に聞けば、それで充分に「足りていることを、知る」のです。「頭」にではなく、「体」に聞いて調える。それが、「知足」です。「体」は、何が必要かを、知っているのです。
たとえば、「良薬は口に苦し」という言葉がありますが、本当は、「良薬は口に甘い」そうです。聞いたところによると、肝臓によく効くという「熊の肝(い)」は、非常に苦いものですが、肝臓病の人の口には、美味いと感じるそうです。
漢方医の石原結美(ゆうみ)先生は、どの薬にするか迷ったときには、患者さんに舐めて比べてもらうそうです。すると、必ずどれかを「おいしい」と言う。そのおいしいと感じるものが、その人に効く薬だといいます。まずくて、普段はとても口に出来ないような薬でも、体調を崩して、その薬が体によく効くというときには、「おいしい」と感じられるものだそうです。
人間ではありませんが、犬の場合を考えてみると、なるほどと思います。犬を飼っておられる方はよくご存じのことですが、犬は、体調が悪いと、普段は食べないような草を食べます。犬には、人間のような支配的な「頭」はありませんから、そのとき「体」に必要な草が、本能的に分かるのでしょうね。
また、中国医学では、沢山の漢方薬が用いられています。現代人は、そういう漢方薬を、無数の試行錯誤のなかから、失敗を重ねながら選ばれたもののように考えておりますけれど、そうではないと思いますね。
というのも、原始的な社会の医者であるシャーマンやメディシンマンと呼ばれる人たちは、病人のことを考えながら森を歩いていると、その病人に必要な薬草が、他の植物から、くっきりと浮き出て見えるというからです。どの草が薬になるかを、「体」は知っているのです。
そんな「体」の声を聞く方法として、「O−リングテスト」というものがあります。ご存じかもしれませんが、これは、なかなか面白いものです。まず、手の親指と人差し指の先をしっかり合わせて、輪をつくります。そして、他の誰かが、その指の輪を引っ張って開けようとしたときの、抵抗の強さを覚えておきます。
それから、もう一方の手に、たとえば、なにか薬を持たせて、もう一度、指の輪を開けようとすると、その人にとって効く薬なら、指の輪はさきほどと同じ抵抗を示しますが、効かない薬なら、指の輪は、簡単に開いてしまうというテストです。何故そうなるのかは、分かっていないようですが、これは、日本の医師が発見した方法で、実際に、一部の医療現場でも使われています。
「体」には、「頭」では計り知れない世界があるのです。「体」というのは、つくづく不思議なものだと思いますね。
さて、病気と健康について、「体に聞く」という話を長々としてまいりましたが、改めて申し上げるまでもなく、私たちは、健康を維持するために生きているわけではありません。
たしかに、世の中には、「健康、健康」と、「体」の不調に妙に敏感で、健康に良いことには、やたら実行力のある人も、少なくありませんが、それはどうかと思いますね。
いつもお話いたしますように、「体」が全てだと思って、後生大事にしがみついているのは、「頭」なのです。「頭」は、「体」の健康に執着します。それが極端になって、健康が人生の目的化してしまうと、健康オタクになってしまいます。
「体に聞く」というのは、そういう、「体」にしがみついた、健康オタクになるためではありません。そうではなくて、「体に聞く」ということは、「体」を手掛かりにして、「体」を超えた世界を知るためにこそ大切なのです。
最初に、「頭」は、社会の常識や価値観でいっぱいになっていると申しましたが、社会で生きていくためには、社会の常識や価値観が必要です。「頭」は、社会に適応して生きていくためにあります。いわば、「頭」は、社会との接点です。
ですが、「頭」には、社会の常識や価値観を「ものさし」にして、他人と自分を測り、比較することしかできません。たとえば、他人と比べて、「あいつより上」とか「こいつより下」とか、判断しているのが「頭」です。つまりは、「頭」には、他人と比べた場合の「自分」のことしか分からないのです。「頭」には、相対的な判断しかできないということです。
ところが、「体」は違います。「体」は、ひとりひとり違いますが、「体」にとっては、自分の「体」が全てです。「体」は、他人と比べて悩んだりしません。「体」は、自分にとって、相対的なものではなくて、絶対的なものなのです。
たとえば、「体」に障害があろうとなかろうと、「体」にとっては、それが「体」の現実であるというだけなのです。「体」の障害に悩むのは、社会の価値観に従って、自分を他人と比べて考える「頭」なのです。
「体」は、「いのち」に支えられています。いわば、「体」は「いのち」との接点です。「体」の声に耳をすまして、「体」を、そのまま受け入れることができたら、「体」を支えている「いのちの真実」への気づきが生まれます。「体に聞く」ということで大切なのは、そのことなのです。
以前、テレビで、こういう番組を見ました。アメリカの少女の話ですが、この少女は、通常の10倍の早さで老化する、早期老化症という難病をもって生まれてきました。少女は、現在11歳ですが、早期老化症の患者は、10歳前後までしか生きられないといわれています。
番組のレポーターが、こう質問しました。「こんど生まれてくるとしたら、どうなりたい?」と。すると、少女は、「こんど生まれてくるときにも、また、私に生まれたい。私は、私が好きなの。病気のこともよ」と、応えていました。
老化が進み、しわだらけになって、体中が痛むそうですが、少女は、鏡の前でピアスを付け、「学校の友達と会うのが大好き」と、ニコニコと笑って、登校していきました。帰り道も、友達とおしゃべりするのが楽しいからと、脚の痛みを我慢して、歩いて帰ってくるということです。
ご両親は、少女の病気が原因で、生まれて1年目に離婚したということで、今は、お母さんと暮らしています。お母さんも、最初は苦しんでアルコール中毒になったそうですが、少女の笑顔を毎日見ているうちに、大きく気付くことがあって立ち直ったといいます。
そのお母さんは、こう言っていました。「この子を授かって、幸せです。この子でよかったと、思っています。病気のことも恨んではいません。今は、ただ、いのちいっぱい生きるってことだけね。理解してもらえないかもしれないけれど、人生って、素晴らしいわ」と。
たしかに、他人と比べた自分のことしか分からない「頭」にとっては、理解を越えたことでしょう。ですが、「体」の声に耳をすまし、「体」の現実を受け入れた少女には、「体」の奥に輝いている「いのちの真実」が見えているのです。
私たちには、いずれ、死ぬ日がやってきます。「体」の現実を受け入れるということは、死をも受け入れるということです。癌で亡くなられた、ある同志社大学の先生は、こんなふうに書き残しておられます。
「心に本当の平和を得るためには、死の可能性を直視する必要があります。これは誰もがいつかは直面しなければならないことなのです。私たちの行く先に、何が起ころうとも、それを受け入れていこうという気になったとき、そのときから、怖れず、思いまどわされず、毎日毎日を大事に生きてゆくことができます」と。
たとえそれが、不治の病であろうと、死であろうと、「こんなはずはない。こんなことは間違っている」と、「体」の現実を否定して足踏みしている間は、人生が始まらないのです。「体」の現実を、ありのままに受け入れて、「体」を見つめなおしたときに、初めて、「体」を支えている「いのちの真実」に気づき、生きる道が見えてくるのですね。
さきほども申しましたように、「頭」は、社会に適応して生きるためのものです。「頭」は、社会との接点です。社会は、相対的な世界ですから、社会人としての私たちは、たいてい、「頭」を拠り所として生きています。
しかし、私たちの人生に起こってくる「生・老・病・死」という問題は、相対的な問題ではなくて、一人一人にとっての絶対的な問題なのです。ですが、社会人としてしか生きてこなかった人には、その絶対的な問題をも、相対的な「頭」で考えるしかありません。そこに、大きな苦しみが生まれてくるのです。
たとえば、お腹が痛いというときでも、お腹が痛いと言うだけでは納まらない。いろんなことを考える。「お祖父さんが、お腹が痛いといったときは、胃潰瘍だったな」、「いや、うちは、先祖に癌が多かったから、癌かもしれない」。
病院で、「検査入院でもしますか」などと言われようものなら、もう大変。「やっぱり、そうか」、「検査の結果、悪かったらどうしよう」、「あの医者の顔つきは、何か隠しているようだった」、「家族には、なんと言おうか」、「仕事は、どうしよう」と、とめどもなく、心配になってくる。あれやこれやと、「頭」に振り回されて、わずかな腹痛の、何千倍も悩み苦しんでいる。そんなことは、ありませんかね。
私たちは、常に、「ああだったら、こうだったら」、「ああなれば、こうなれば」と、我が身の現実でないことばかり、「頭」に思い描いて、悩み苦しんでいます。
「ああだっタラ、こうなレバ」。余談ですがね、そんなふうに、「頭」のなかが「タラ」と「レバ」で一杯になったときには、「タラは魚屋、レバは肉屋」と考えて、一息入れる。これは、田中美津という方の本で読んだ言葉です。
また、人生の先行きが気になって仕方がないというときには、「転けても畦道、落ちても田圃」と考えるそうです。
いいですね。この言葉、好きですね。「タラは魚屋、レバは肉屋」、「転けても畦道、落ちても田圃」。皆さんも、悩まれたときには、思い出して頂きたい言葉ですが、まあ、それくらい、私たちは、「頭」に支配されて、悩み苦しんでいるということですね。
「苦しみ」とは、「頭」の思い通りにならないことをいいます。ご承知のように、仏教では、「生・老・病・死」を「四苦」と呼んでいますが、「生・老・病・死」に「苦」を感じるのは、それを「頭」で考えようとするからなのです。
「頭」は、生まれてきた境遇を人と比べ、老いていくことを若者と比べ、病んでいることを健康な人と比べ、死んでいくことを生きている人と比べます。そこから、私たちの、悩みや苦しみが生まれてくるのです。「頭」は、「体」に執着するばかりで、「体」の現実を受け入れようとはしません。
私たちは、そんな「頭」に支配されています。仏法は、その「頭」の支配から解放されて、自由になることを目指しているのです。お釈迦様は、「自らを拠り所とし、法を拠り所として、精進しなさい」と遺言なさいましたが、拠り所とすべき「自分」というのは、「頭」のことではなくて、「体」のことです。「体」は、「頭」から解放されるための拠り所なのです。
「体」は「いのち」との接点です。「頭」ではなく、「体」を拠り所とするところに、「体」を支えている「いのちの真実」が浮かび上がってくる。つまりは、「体」こそが、「いのちの真実」(「法」)を感得する拠り所なのです。
私たち門徒は、毎日、お仏壇の前に座って、手を合わせ、声に出して「お念仏」を称えます。仏様の前に、姿勢を正し、仏様の名前を呼ぶ。「本当の自分」の名前を呼ぶということです。そして、呼びかけ呼びかけするうちに、「息」が調い、「心」が調い、「頭」がおしゃべりを止めて、「身心一如」となっていく。そういう「体」になることが、私たち門徒の修行なのです。「体」です。「体」。
「頭」で、仏法が分かるとか分からないとか言っている間は、何も腑に落ちてこないのです。「頭」が沈黙して、「体と心」がセットになったとき、「体」を支えている「いのち」への気づきが生まれ、「いのちの真実」を説いている仏法が、ストンと腑に落ちる。「身心一如」が説かれているのは、そのことを教えるためだと思います。
さて、「身心一如」という言葉を手掛かりに、「体」の方向から、いろいろお話してまいりましたが、仏法の話は、いつも同じです。「頭」のおしゃべりを止め、「体」の現実を受け入れたら、「いのちの真実」のままに、安らかな「心」で生きられる。ひとことで言えば、これだけです。
一番大切なのは、「頭」が黙るということです。もちろん、私たちは、社会で生きておりますから、四六時中「頭」が黙り込んでしまったら、それは困りますけれど、まあ、現実には、そんな心配はありません。むしろ、四六時中「頭」がしゃべっているということが、問題なのですね。
今日は、「体」の話をいたしましたが、「体」に執着しているのは「頭」です。仏教で、「体は不浄なものだ」と言うのは、「体」に執着する「頭」を戒めているだけです。
「体」は、仏教徒にとっても大切なものです。「身外無仏」という言葉もありますように、「永遠の今」という体験も、「無我」の体得というものも、この「体」を離れたところにあるわけではないのです。
「体」を拠り所として、「いのちの真実」に気づいたら、「いのち」への無条件の信頼が生まれてきます。ですが、「神を信頼せよ。しかしまず、お前のラクダを木につなげ」という、アラブの格言にありますように、「いのち」を信頼するといっても、自分にできることまで放っておくのは、横着なだけです。
「長寿を望まず、無病を期せず、ただ姿勢を正しくする」。これは、金子大栄先生が、96歳でお亡くなりになる前に、おっしゃった言葉です。「いのち」のことは、「いのち」にお任せです。ですが、それは、「いのちの真実」の前に、姿勢を正してこそ言えることだと思います。
私たちは、気付いたときには、「体」を授かっていました。「体」は、「いのちの故郷」に帰るための拠り所として、授かったのです。いわば、「体」は、お浄土からの往復切符です。「体」は、お浄土からの預かり物ですから、いずれは、お返しするときが来ます。どうぞ、そのときまで、お体を大切になさって、気づきを深めていかれますよう、念じております。
仏教は、医学や健康法を説く教えではありませんが、「身心一如」の教えにもとづきまして、「体と心」の健康についても、お話していきたいと思っております。ご縁がありましたら、また、どうぞ、お参りくださいますよう、お願いいたします。本日は、長い時間、お付き合いくださいまして、有り難うございました。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ…。
紫雲寺HPへ