ご承知のように、「お彼岸」は、年に二回、春と秋にあります。春のお彼岸は、春分の日をはさんで前後3日づつの7日間、秋のお彼岸は、秋分の日をはさんで前後3日づつの7日間です。春分の日と秋分の日が、お彼岸のお中日です。
御本山では、この七日間、「彼岸会」が勤まります。また、御本山では、お中日の前日に「永代経」が勤まりますが、この紫雲寺では、毎年、秋のお彼岸のお中日に、「彼岸会」と「永代経」を併せて勤めさせて頂いております。
春と秋に「彼岸会」を勤めるという習慣は、奈良時代にはすでに出来上がっていたようですけれど、実は、この「彼岸会」というのは日本だけの行事でして、インドにも中国にもありません。
ただ、『観無量寿経』というお経様に、「日想観」という瞑想の方法が記されておりまして、春分と秋分に、この「日想観」を行うという習慣は、中国にもありました。
春分と秋分には、太陽は、真東から出て、真西に沈みます。弥陀の浄土は、まさに、その夕日が沈む方向にある。「日想観」というのは、弥陀の浄土を、夕日に重ねて瞑想する行です。
ですが、瞑想というのは、やはり、専門のお坊さんのすることですから、庶民のあいだでは、春分と秋分に落日を拝んで念仏を称え、浄土往生を願うということが盛んに行われるようになります。
その落日信仰で、一番有名なのは、大阪の四天王寺です。四天王寺は、聖徳太子の創建と言われておりますが、その「西の大門」から、お彼岸にながめる落日の方向に、極楽浄土があると考えられました。
「西の大門」から100メートルほど西に、石の鳥居がありまして、そこに掛かっている扁額には、「…このまっすぐ先に極楽の東門の中心がある」と書かれています。春と秋のお彼岸の中日に、人々は「西の大門」に集まり、鳥居の中に沈む夕日に合掌念仏して、極楽往生を願ったのです。
弥陀の浄土は西にある。その浄土に想いを馳せ、浄土への想いを新たにする機会、それが、お彼岸なのですね。
そこで今回は、「あかね雲の彼方へ」という題で、「彼岸」によせて思うことを、少しお話させて頂こうと思います。いささかまとまりのない話ですが、どうぞしばらくのあいだお付き合いください。
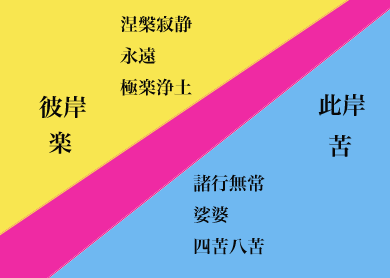 さて、お彼岸というと、ほとんどの方は、お墓参りやご先祖の供養をお考えになるかもしれませんが、もともと、「彼岸」(ひがん)というのは、墓参りや先祖供養を意味する言葉ではありません。「彼岸」というのは、「川の向こう岸」という意味でして、悟りの世界、涅槃の世界、仏の世界を表す言葉です。
さて、お彼岸というと、ほとんどの方は、お墓参りやご先祖の供養をお考えになるかもしれませんが、もともと、「彼岸」(ひがん)というのは、墓参りや先祖供養を意味する言葉ではありません。「彼岸」というのは、「川の向こう岸」という意味でして、悟りの世界、涅槃の世界、仏の世界を表す言葉です。
いっぽう、「川のこちらの岸」は「此岸」(しがん)と言いまして、これは、私たちのいる迷いの世界です。この「此岸」の世界を「娑婆」(しゃば)といいます。
「娑婆」というのは、刑務所の塀の外を言うのではなくて、これはインドの「サハー」という言葉の音を写したものです。「サハー」というのは「忍耐」を意味します。「此岸」は、苦しみに満ちていて、それに耐え忍ばねばならない世界だから、「娑婆」なのです。刑務所の塀の外も、塀の内も、ともに「娑婆」なのです。
こちらの「此岸」は、苦しみの世界です。その「苦しみ」を、仏教では「四苦八苦」といいます。「四苦」というのは、「生・老・病・死」の四つの苦しみです。つまり、「生まれる苦しみ、病む苦しみ、老いる苦しみ、死ぬ苦しみ」です。
この四つの苦しみに、「愛別離苦(あいべつりく)、怨憎会苦(おんぞうえく)、求不得苦(ぐふとくく)、五蘊盛苦(ごうんじょうく)」の四つを加えて「八苦」と言います。私たちがよく言う「四苦八苦」というのは、ここからでた言葉です。
「愛別離苦」というのは、愛する人と別れる苦しみです。「怨憎会苦」というのは、怨みに思っている人や、憎らしい人とも会わねばならない苦しみです。
ちょっと余談ですが、このあいだ、ある本に、「地獄の苦しみというのは、嫌いな親戚百人と一つの部屋にいることだ」と書いてありました。それなら、極楽の喜びとは何かというと、「姑が死んで息子に嫁が来るまでのあいだ」と言った人がいます。まあ、それほど、身近な人間関係というのは難しいということでしょうね。
さて、その次の「求不得苦」というのは、求めても得られない苦しみ。そして、「五蘊盛苦」というのは、我が身に煩悩が沸き立つ苦しみです。「私が、私が」という「我執」に、身も心も苦しむことです。
「苦しみ」というのは、「思い通りにならないこと」をいいます。思い通りにならなくて、苦しくて仕方がない。というのは、つまりは、それだけ、自分の思い通りにしようとしているということですが、いかがですか、皆さん、お心当たりはおありでしょうか。
「あいつが、ああだ、こいつが、こうだ」と、いろいろ文句を言いますけれど、そもそも、我が身ひとつがままならないのに、他人であれ家族であれ、自分以外の人間を思い通りにできると思うほうが、おかしいのです。
まあ、それはともかく、私たち一人一人の人生にとって、本質的な問題は、やはり「生・老・病・死」の「四苦」でしょうね。この「生・老・病・死」をしっかり見据えることができれば、残りの四つには、自ずと道が開けるものと思います。
生まれてきて、順調に生き続けたら、だんだん年老いて、ときには病気にもなり、いずれは死ぬことになる。そんなことは、誰でも知っています。
お釈迦様の説かれたように、この世は「諸行無常」(しょぎょうむじょう)です。「諸行無常」というのは、「あらゆる現象は変化してやまない」という意味です。昇った日は沈む。咲いた花は枯れる。生まれた人は死ぬ。それが「諸行無常」です。
思いますに、「諸行無常」などということは、お釈迦様がお説きにならなくとも、おそらくは誰でも知っていたことでしょうね。ですが、その、誰でも知っていることが、我が身のこととなると、煩悩がからんで、分からなくなってしまいます。
たとえばです、たいていの人は、「年を取りたくない、死にたくない」と思いますでしょう。不老不死を願うのは秦の始皇帝だけではありません。ですが、そんな願いは叶いませんよね。それでも人は、「年を取りたくない、死にたくない」と思う。いくら思っても、思い通りにはなりませんから、苦しくて仕方がない。
お釈迦様が、誰もが知っているはずの、「諸行無常」という言葉でお諭しになったのは、おそらく、そんなときだったのでしょうね。
ちなみに、お釈迦様のころのインドの古い言葉に、パーリ語という言葉がありますが、そのパーリ語で、「無常」を「アニッチャ」といいます。これは、タイで出家修行した日本の方の本で読んだことですが、タイでは今でも、お坊さんたちは、ハエの死骸を見ても、大声で「アニッチャ!(無常)」と叫ぶのだそうです。
「諸行無常」というのは、死ぬことを忘れて欲望を追いかけている人々や、「年を取りたくない、死にたくない」という欲望にとりつかれている人々に、「目を覚ませ!」と諭す言葉なのです。
「此岸」は、諸行無常の世界です。人生の根本である「この身」の生・老・病・死さえ、思うままにならない世界です。それに対して、「彼岸」は、涅槃寂静の世界です。涅槃寂静の世界とは、悟りの世界、仏の世界です。そこは、いわば「永遠の世界」です。
仏教は、この苦しみの世界である「此岸」を離れて「彼岸」に向かえという教えです。「此岸」を離れて「彼岸」に向かうというのは、苦しみの世界を離れて楽になるということですが、以前、こんな話を読んだことがあります。
チベットのお坊さんは、こんなふうに言うそうです。「あらゆる生きものが楽になりたいと思っている。でも楽になるための正しい方法を知らないので、苦しみから逃れられないでいる。仏教はそこで、本当に楽になるための正しい道を教えるのである」と。
子どものころには、科学が発達すれば便利になり、暇ができ、楽になると教えられましたが、そうではなかったですね。便利になればなるほど、忙しくなり、苦しくなってしまいました。
たとえば、昔なら、二泊三日かかった出張を、新幹線や飛行機のおかげで、日帰りでこなさねばならなくなりました。また、手紙で一週間ほどかかった用件が、電話やコンピュータで、あっという間に片づくようになり、一日にこなさねばならない仕事がうんと増えましたね。
科学は、人間の欲望を満たす手段として発達してきました。つまりは、物を増やすという方向に進んできたわけですが、便利な物であれ何であれ、物を増やすことで楽をするというのは、結局は無理なのではないでしょうかね。
お釈迦様は、三衣一鉢(さんねいっぱつ)といいまして、身体にまとう三枚の布と、食べ物を受ける一つの鉢しか持っておられませんでした。それは、何もかも捨てて、「楽」を求められた姿でした。
「いのち」に対する姿勢もそうです。科学は、「いのち」を延ばそうとします。つまり、「いのち」を「増やそう」とするわけですが、仏教は違います。仏教は、「いのち」を充実させようとするのです。
ちなみに、この、「いのち」を充実させるために励むことを「精進する」と言います。「精進」と「努力」は違います。たとえて言えば、「いのち」の流れに逆らって泳ぐことを「努力」と言い、「いのち」の流れに従って泳ぐことを「精進」と言います。
いつまでも若くありたいと、厚化粧や派手な服装をしたりするのが「努力」で、いい年寄りになろうとするのが「精進」だ、と言った方がおられますが、そのとおりでしょうね。
仏教は、「いのち」を充実させる教えです。「いのち」を充実させるというのは、人生に多くのものを詰め込もうという意味ではありません。そうではなくて、死ぬことへの不安が無くなり、安らかな心で生きられるようになるということです。そうなることを、「安心(あんじん)」を得るといいます。それは、つまり、人生を味わって生きるということです。
「安心」を得るというのは、「此岸」で「彼岸」を生きること、「娑婆」で「浄土」を生きること、諸行無常の世界で「永遠の今」と同調することです。
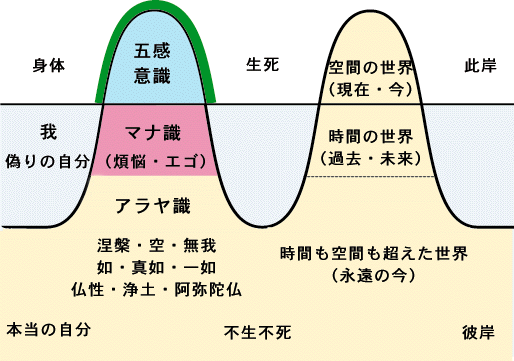 もう一枚の図をご覧になって頂きながら、話を進めます。これは、唯識仏教に基づいた「いのちの全体像」です。これまでに、何度もご覧になって頂きましたが、初めての方のために、簡単に、ご説明いたします。
もう一枚の図をご覧になって頂きながら、話を進めます。これは、唯識仏教に基づいた「いのちの全体像」です。これまでに、何度もご覧になって頂きましたが、初めての方のために、簡単に、ご説明いたします。
「いのち」がこういう形をしているということではなくて、これはいわば、一種の「たとえ話」です。そのつもりで、お聞きになってください。
この小山のように盛り上がっているのが、たとえば「私」です。図全体では、波が並んでいるようにも見えますが、この波ひとつが一人の人間に相当いたします。ちょうど、海底から立ち上がって海に浮かぶ島を、横から見たような形ですね。
ひとつの小山を、上から順に、青、赤、黄に色分けしてありますのは、それぞれ「五感と意識」「マナ識」「アラヤ識」を表しております。「マナ識」「アラヤ識」というのは、唯識仏教の用語ですが、特に憶えて頂く必要はありません。
この水平線から上が、私たちの目に見える現象世界です。つまり、「諸行無常」の世界です。「此岸」というのは、ここのことです。この水平線から上の部分は、死ねば無くなってしまいます。私たちが通常自覚できるのは、ここまでです。
次に、この水平線から下は、私たちには通常はほとんど自覚できない、いわば無意識の世界です。上にあります赤色の「マナ識」というのは、私たちの心のなかで「煩悩」に支配されている領域です。「煩悩」というのは、「他の誰よりも我が身が可愛い」という心の働きのことです。現代の言葉で言えば、つまりは、「エゴ」です。
私たちは、この「エゴ」に「意識」を支配されておりますから、この「マナ識」を「自分」だと思っております。それで、この「マナ識」が「我」と呼ばれるわけですが、それは「本当の自分」ではなくて、「エゴ」に支配された「偽りの自分」なのです。
その下に広がっている黄色の「アラヤ識」というのは、私たちの心のなかで「煩悩」に支配されていない清らかな領域です。ここは、「涅槃寂静」の世界です。「彼岸」というのは、ここのことです。
仏教ではこの領域のことを、いろいろな名前で呼んでおります。たとえば、「涅槃」とか「空」とか、「仏性」「浄土」「阿弥陀仏」とかいうのは、みなこの領域のことです。精神世界の伝統で「永遠の今」というのも、ここのことです。
ここは、「エゴ」に支配されておりませんから「無我」と呼ばれております。この「無我」こそが「本当の自分」なのです。つまりは、「本当の自分」は「仏」だということです。私たちは、みんな「いのち」の奥底で「仏」に支えられているのです。
「仏様」と言うと、私たちは、どこか遠い空の彼方にでもおられるように思っておりますけれど、そうではありません。私たちは、みんな「仏」なのです。「エゴ」に妨げられて、そのことに気づいていないだけなのです。
「此岸」と「彼岸」の間に横たわる川というのは、この「エゴ」に支配された赤い部分、「マナ識」のことです。つまり、「此岸」と「彼岸」の間にあるのは、煩悩の川なのです。
苦しみの世界である「此岸」から「彼岸」に渡れば、楽になる。ところが、その間には、煩悩の川、「エゴ」の流れがあって、邪魔をしていて渡れない。「此岸」と「彼岸」がつながらないのは、間に「エゴ」があって、活発に働いているからです。
「エゴ」は何をしているかと言えば、常に休みなく心のなかでオシャベリをしています。常に何かを考えていると言ってもよいでしょう。過去を誇ったり悔やんだり、未来に期待したり不安を抱いたりして、決して「今」のこの一瞬にとどまっているということがありません。
しかし、「過去」は過ぎ去ってしまいましたから、いまさらどうしようもありません。また、「未来」はまだ来てはおりませんから、まだどうなるか分かりません。私たちは、そんな「どうしようもない」世界と「どうなるか分からない」世界を、「エゴ」に引きずり回されて、うろうろしているものですから、いつまでも楽にならないのです。
では、そんな「エゴ」の活動を止めるには、どうすればよいのか。それは、心の中の時間を止めればよいのです。「エゴ」は、過去へ未来へと、時間の中をさまよっています。言い換えれば、「エゴ」は時間の中でしか活動できないということです。
心の中の時間を止めるというのは、心の中で絶え間なく続いている、「エゴ」のオシャベリを止めるということです。実は、そのためにあるのが、「お念仏」なのです。「お念仏」を称え、心を「お念仏」で満たせば、過去や未来の入ってくる余地が無くなります。そうなると、心の中の時間が止まるのです。
心の中の時間が止まればどうなるのか。心の中の時間が止まれば、現象世界の「今」が、仏の世界の「永遠の今」と同調して、「此岸」のなかに「彼岸」が流れ込んできます。
別のたとえで申しますと、こういうことです。今はどうか分かりませんが、昔のラジオには、放送局の周波数を合わせる「バリコン」というものが付いていましたね。テレビで言えば、チャンネルのようなものです。
あのバリコンを、むやみに動かしても、放送は聞こえてきません。むやみに動かすというのは、心の中の時間が、過去へ未来へと動き回ることです。そうではなくて、バリコンを「今」という一点で止めたとき、浄土からの放送が聞こえてくる。
心の中の時間が止まって、「今」にピッタリと同調したとき、「永遠の今」を感じる。そのとき、「諸行無常」の中にこそ「永遠」があること、「娑婆」の中にこそ「浄土」があることに気づくのかもしれません。
さきほどの図でお分かりになるように、「エゴ」は「意識」を支配して、「他の誰よりも我が身が可愛い」と、「身体」にしがみついています。そのために、私たちは、「自分」とはこの「身体」なのだと思い込んで、「身体」の「死」を恐れているわけです。
ですが、本当は、「死」を恐れているのは、「自分」ではなく「エゴ」なのです。ですから、「エゴ」の活動が止まれば、死ぬことへの不安もなくなり、安らかな心で生きられるようになる。それが、「此岸」で「彼岸」を生きる、「娑婆」で「浄土」を生きる、「安心」を得るということです。
ちなみに、この、「エゴ」の心が「身体」にしがみついているというのは、たとえ話ではなくて、実際、そうなのです。人の顔には、それぞれ特有の印象がありますが、それは、心の在り方が、表情筋をとおして現れているのです。「四十を過ぎたら、自分の顔に責任を持て」と言った人がいますが、顔付きというのは、いわば、顔の筋肉を握りしめている「心」の指跡なのです。
お亡くなりになった方のお顔を拝見するたびに思うことですが、どなたのお顔も同じように穏やかな表情になっています。「心」が「身体」を完全に手放したために、筋肉の緊張が解けているのです。別の言葉で言えば、「我」が取れているのです。まさに仏様のようなお顔です。
この、「エゴ」がしがみついている手が「ほどけ」た状態が、「ほとけ」だと聞いたことがあります。ほどければ、楽になる。ほどけきったら、極楽ですね。仏教がめざしているのは、この「エゴ」の支配から解放されて自由になること、いわば、「ほどけ」て楽に生きることなのです。
さて、仏教は「ほどけ」て楽になる教え、などと言いながら、何とも理屈っぽい話で、ちっとも楽になんかならず、疲れてしまわれたのではないかと思います。理屈っぽい話は、いつものことではありますが、まことに申し訳ないことでございます。
昔の人は、浄土の教えを、こんな理屈で納得していたわけではないのです。ですが、理屈で納得しようとする現代人よりも、遙かに深いところで、腑に落ちていた。それは、おそらく、昔の人は、現代人と違って、もっともっと身体を使って暮らしていたからではないかと思いますね。
仏法というのは、もともと、お釈迦様がその身体を通して体得された「いのちの真理」です。ですから、仏法は、私たちにとっても、身体を通して体得していくものなのです。
身体には、目で見る、耳で聞く、鼻で嗅ぐ、舌で味わう、肌で触れるという、五つの感覚があります。この五感で、つまりは全身で、世界に触れるとき、私たちは、諸行無常の中に、永遠を垣間見るのです。
実際、秋の夕暮れに、田んぼにハサバが立ち並んで、ワラを焼く煙の香りが漂うなかで、西の空に落ちていく夕日を見ていると、まるで時間が止まっているようでした。
都会に住んでおりますと、なかなか、そういう体験をすることは、難しくなりましたが、子どものころに、そういう世界を体験して、夕焼けの空に、何とも言えない、魂の郷愁を感じるのは、戦後まもなく生まれた「団塊の世代」までくらいかも知れませんね。
あかね雲の彼方に、想いを馳せるというのは、今や、贅沢な経験なのかもしれませんが、夕焼けの空に、どこからか、お寺の鐘が響いてくると、懐かしいような、ホッとするような、なんとも穏やかな気持ちになってきます。そんなとき、故郷を離れている人は、故郷を思い出すのではないでしょうか。
童謡の「夕焼け小焼け」に歌われているのは、そんな情景でしょうね。皆さんの、よくご存じの歌ですが、ちょっと、その「夕焼け小焼け」を、お聞きください。
夕焼け小焼けで 日が暮れて、山のお寺の 鐘が鳴る、
お手々つないで 皆かえろう、烏といっしょに 帰りましょう
(由紀さおり・安田祥子「あの時、この歌」第一集、TOCT-5881)
いかがですか。夕焼け空には、浄土のイメージがある。落日の彼方には、浄土がある。浄土往生を願って、あかね雲の彼方に手を合わせる。そんな人の姿が、昔は、ありましたね。そこに、お寺の鐘が、ゴーンと聞こえてくる。故郷を思い出しなさいと聞こえてくる。
命あるもの、全ての帰る故郷がある。その故郷へ帰ろう。それが、「お手々つないで皆かえろう、烏といっしょに帰りましょう」なのですね。仏教の言葉で言えば、「一切衆生、悉有仏性」なのです。私たちが、この歌を聞いてほっとするのは、帰る故郷があることを、心のどこかで思い出すからではないでしょうかね。
お寺の鐘の音は、「娑婆」と「浄土」、「此岸」と「彼岸」をつなぐ音です。あかね雲に、浄土を想い、何も考えずに、一心に梵鐘の音を聞いていると、聞いている「私」が無くなって、梵鐘の音だけになっていく。そのとき、その梵鐘の音のなかに、浄土への入り口が開かれてくる。
一心に梵鐘の音を聞いていると、心の動きが止まってくるのです。心の動きが止まると、そこに、お浄土への入り口が開けてくるのです。
お寺の鐘は、朝夕の決まった時間に鳴るものですから、梵鐘は時を告げる鐘だと思っていらっしゃる方が多いのですが、そうではないのです。梵鐘は、時を告げるために鳴るのではなくて、時を止めるために鳴るのです。
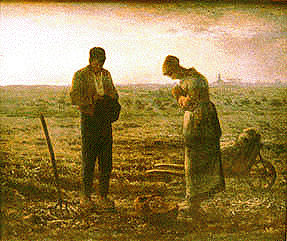 これは、ミレーの「晩鐘」という有名な絵です。夕方、遠くの教会から聞こえてくる鐘の音に、二人の農民が、静かに合掌して佇んでいる。これは、信仰の生活を描いた絵です。この絵をご覧になって、何か心安らかな思いがなさいませんでしょうか。この絵は、時間が止まっているとは思われませんでしょうか。洋の東西を問わず、信仰の生活の核心は、日常の時間を止めるというところにあるのですね。
これは、ミレーの「晩鐘」という有名な絵です。夕方、遠くの教会から聞こえてくる鐘の音に、二人の農民が、静かに合掌して佇んでいる。これは、信仰の生活を描いた絵です。この絵をご覧になって、何か心安らかな思いがなさいませんでしょうか。この絵は、時間が止まっているとは思われませんでしょうか。洋の東西を問わず、信仰の生活の核心は、日常の時間を止めるというところにあるのですね。
私たち現代人は、何でも目で見るということにこだわりますけれど、もともと、神や仏というものは、目で見て確かめるものではないのです。神や仏というものは、耳で聞いて、心で感じるものなのですね。
梵鐘の音が聞こえてきたら、仕事の手をとめて合掌する。梵鐘の音を聞くのではなくて、梵鐘の音になるのです。そのとき、時間が止まって、浄土への入り口が開かれてくるのです。梵鐘の音は、その「浄土の入り口に立ちなさい」という、お催促なのですね。
私たちは、梵鐘の音に「魂の故郷」の歌声を聞くのです。「お浄土」からの懐かしい歌声を聞くのですね。私たちは、根無し草ではない。私たちには、帰っていく故郷がある。私たちはみな、お浄土から生まれてきて、また、そのお浄土へと帰っていくのです。そのことを教えて下さっているのが、「浄土の教え」なのですね。
私たちは、帰っていく故郷があると知ったとき、初めて、心安らかに生きることができるようになる。その「魂の故郷」を思い出しなさいと、今日も、お寺の鐘は鳴るのです。
これは余談ですが、「夕焼け小焼け」という言葉で始まる童謡が、もうひとつあります。「赤とんぼ」です。かつて、その「赤とんぼ」と併せて、紅白のトリに歌われたのが、前回にもご紹介いたしました「どこかに帰ろう」です。
この歌は、前回にはお聞き頂けませんでしたので、この機会に、お聞き頂こうと思います。「赤とんぼ」の歌(歌詞省略)に続けて、お聞きになってみてください。
帰ろう 帰ろう どこかに帰ろう。 帰ろう 帰ろう だれかと帰ろう。
あの日に 帰ろう 子供に帰ろう。 自分に 帰ろう 歌って帰ろう。
(由紀さおり・安田祥子「あの時、この歌」第八集、TOCT-5888)
いかがですか。どこかに帰ろう、自分に帰ろう。やはり、誰もが、どこかに帰っていこうと思うのですね。私たちには、お念仏を称えながら、帰っていく懐かしい世界があります。それが、「いのち」の奥底にある「彼岸」の世界、「極楽浄土」です。
余談ついでに申しますと、「夕焼け小焼け」の作詞者は、明治30年生まれの中村雨紅(うこう)、「赤とんぼ」の作詞者は、明治22年生まれの三木露風、「どこかに帰ろう」の作詞者は、昭和19年生まれの、山川啓介です。
先ほども申しましたが、あかね雲の彼方に、何か懐かしい世界を感じるのは、戦前・戦中生まれの人か、せいぜい戦後の団塊の世代の人までかもしれません。私も、団塊の世代の仲間ですが、そういう意味で、何か次の世代に伝えるものがあるという、責任のようなものを感じますね。
さて、どこでだったか忘れましたが、こういう言葉を読んだことがあります。「人は、たった一つの目的のために生まれてくる。その目的とは、自分自身に出会うことだ」と。
それは、仏教の言葉で言えば、「此岸」から「彼岸」に渡って、「本当の自分」と出会うということ、「仏」と出会うということです。そのことを改めて思い出させもらう機会が、この「お彼岸」なのです。
「娑婆」は、煩悩に支配された暗闇の世界ですが、「闇を呪うよりも、一本のローソクをともした方がよい」という言葉のとおり、私たち自身が「ほどけ」れば、自ずと周りが明るくなるのです。
「ほどけ」ていないと、身体も硬い。身体が硬い人は、呼吸が浅い。呼吸が浅い人が側にいると、それだけで、周りを落ち着かなくする。これは本当ですよ。
どうぞ皆さん、「ほどけ」て、楽になりましょう。仏法は、道徳でも倫理でもなく、社会の優等生になるための教えでもありません。仏法は、自分自身に出会って、楽になるための教えなのです。
社会から捨てられることを恐れて、「生涯現役!」などと言っていないで、そこそこの年になれば、社会なんか捨ててしまって、いい年寄りを目指しましょう。極楽というのは、社会を離れたところに見えてくるのです。
「いのち」の流れに従って精進していると、おのずと、いい年寄りになっていきます。いい年寄りになっていくというのは、仏様に近づいていくことなのです。
日々の生業の中にあっても、立ち止まって生活のすみずみを見つめましょう。物をゆっくり見るだけで、人生の喜びや質が、目に見えて高まります。お念仏を称えながら、ゆっくり見つめて生きる。それが、人生を味わって生きるということです。
さて、話の種も尽きましたので、今日は、この辺で終わらせて頂きます。まとまりのない話に、長い間お付き合いくださいまして、有り難うございました。
次回は、11月14日の「報恩講」です。今日から数えて、ひと月半ほどしか間がありませんが、ご縁がありましたら、どうぞまた、お参りください。
本日は、お忙しいなか、お運び頂きまして、有り難うございました。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ……。
紫雲寺HPへ