この前の春のお彼岸には「浄土の教え」と「念仏行の実践」についてお話しさせて頂きましたが、ご案内申し上げておりました予定時間よりかなり長いお話しになってしまいまして、ご迷惑をおかけいたしました。本日は、余り時間が延びないように心がけますので、どうぞ、しばらくの間、お付き合い頂きたいと思います。
さて、近ごろ、「心の時代」などという言葉が流行っておりますけれど、あれには何かちょっと妙な気持ちがいたします。新聞などに連載されている特集記事などを見ておりますと、心の平安を求めて出家した人や、新興宗教に走る若者たちのことなどが取り上げられておりますが、そういう人は昔からいたのでして、何も今に始まったわけではありませんはね。本当の意味で出家する人などは、むしろ昔の方が多かったと思います。
マスコミの騒いでいる「心の時代」というのをよくよく見てみますと、どうやら、「心」といものが金儲けのタネにできるようになった時代という意味のようなんですね。つまり、宗教や占いや超能力なんかの本がよく売れたり、新興宗教が雨後の竹の子のように生まれたりして、そういったものが商売として十分ひきあう時代になった。それをマスコミでは「心の時代」と呼んでいるように思うのです。しかし、そういう時代というのは、「心の時代」というよりも、むしろ「心が病んでいる時代」と言った方が適切なのではないかと思います。
新聞を見ましても、テレビを見ましても、まあ余りのどかな気持ちになれる記事は出ておりませんね。政界の腐敗、官界の背信、産業界の破綻、教育界の無能、宗教界の堕落、医療機関の非人間性、家庭の崩壊などですね、そんな話題ばっかりのような気がします。それも今に始まったことではありません。昔からそうなんですね。
これまでにも「政界の浄化」とか「教育界の刷新」などとしきりと叫ばれてまいりましたが、そういったことは、まずできないのではないかと思います。と申しますのはですね、あらゆる問題の原因は、社会の仕組みにあるというよりも、むしろその仕組みを運営している人々や利用している人々の「心」にあるからなんです。
仏教では身・口・意の三業ということを申します。「業」というのは「行為」「行い」のことです。「身業」というのは身体で行うこと、「口業」というのは口に言うこと、「意業」というのは心に思うことです。私たちの一切の生活活動は、全てこの3つの業に収まります。つまり、何かをしようと思うことが「意業」で、それが身体的行動に現われるのが「身業」、言語表現に現われるのが「口業」ですから、目に見える具体的な活動は、全て「心」から生まれているわけです。
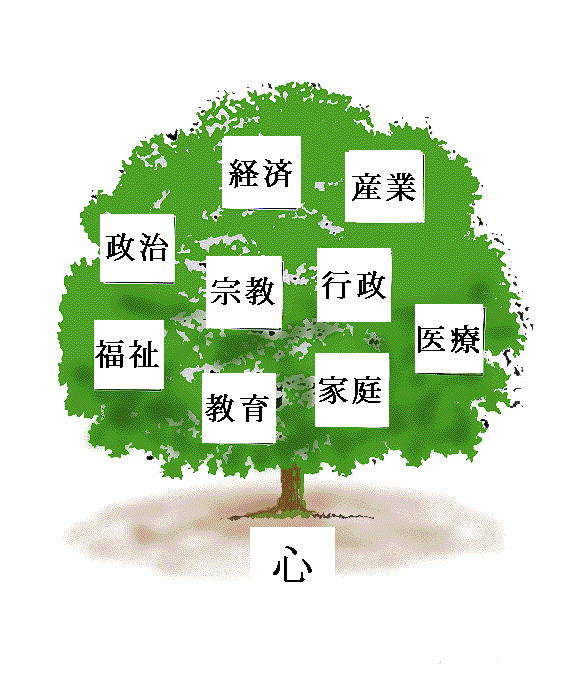 たとえば、この「心」と「具体的な活動」は、木の「根」と「葉」のような関係にあると言えます。ここに木があるとしますね。木の根が「心」です。そして、こんなふうに、「政治」とか、「産業」、「教育」、「宗教」、「医療」、「家庭」などといった、さまざまな葉が茂っています。そして、これらの葉っぱを、ひっくるめて「社会」と呼んでいます。「政界を浄化する」とか「教育界を刷新する」というのは、いわば、この1枚1枚の葉を綺麗に磨こうとするようなものです。
たとえば、この「心」と「具体的な活動」は、木の「根」と「葉」のような関係にあると言えます。ここに木があるとしますね。木の根が「心」です。そして、こんなふうに、「政治」とか、「産業」、「教育」、「宗教」、「医療」、「家庭」などといった、さまざまな葉が茂っています。そして、これらの葉っぱを、ひっくるめて「社会」と呼んでいます。「政界を浄化する」とか「教育界を刷新する」というのは、いわば、この1枚1枚の葉を綺麗に磨こうとするようなものです。
1枚1枚の葉を磨きますと、その時は綺麗になったように見えますが、根っこが傷んでいると、またすぐに汚れてきます。規則を変えたり、管理職を入れ替えたりしても、結局はすぐに元の木阿弥になってしまうのは、具体的な世界を支える根っこ、つまり私たちの「心」が病んだままになっているからなんですね。いわばですね、対処療法だけで、根本治療をなおざりにしているものですから、ちょっとの間は良くなるように見えても、すぐにまた具合が悪くなってくるんです。
そういうことに気づかずに仕組みを変えれば世界が変わるなどと思っているのはですね、毎朝学校に行く時間になるとお腹が痛くなるという登校拒否児童に次々に新しい胃薬を飲ませて、そのうち治ると考えているようなものだと思います。
ですが、この「心の病を癒す」というのはなかなか難しいことなんですね。「心の病」と申しましても、いわゆる精神病のことではありませんが、自分の「心」が病んでいることに、なかなか気づけないという点では同じようなものです。
私たちはみな、「自分の心が病んでいる」とは思っていません。「病んでいる」と思っていないのですから、当然「癒そう」などと思うはずがありません。この「心の病」を癒すのが難しい本当の理由は、ここにあるのです。
すこし寄り道になりますが、以前お話し致しましたように、お釈迦さまが、私たち凡夫は娑婆世界を苦しみの世界とは考えていない、とおっしゃっているのも、このことなんですね。私たちは、娑婆には苦しいこともあるが楽しいこともある、その楽しいことを、もっともと追求していくのが幸せだと考えているんですね。
ところが、この娑婆世界つまり現実世界は「競争の社会」ですから、「幸せ」というものが、すぐに「競争」と結びついてしまいます。また、私たちは、「競争」に勝たなければ「幸せ」になれないという考えを、子供のころからいやというほどたたきこまれて育っていくものですから、何でもかんでも「競争」にして、その「競争」に勝たないと「幸せ」でないというようになってしまいやすいんですね。
しかし、まあ、たとえば「競争」の例として、身近な「かけっこ」を考えてみますね。運動会の「かけっこ」で勝った人は「幸せ」を感じるでしょう。ですが、敗けた人は「不幸せ」を感じるのではないでしょうか。眼には見えなくとも、自分の「幸せ」は、どこかで他人の「不幸せ」と抱き合わせになっている。それが、「競争社会」での「幸せ」というものの本質ではないかと思いますね。
誰かが幸せになれば、他の誰かが不幸せになる。これを社会全体で見れば、「幸せ」と「不幸せ」が差し引きでゼロになる。競争社会がいつまでも本当の意味で「幸せな世界」にならないのは、こんな仕組みになっているからではないでしょうかね。
さて、まあ、それはともかくとしまして、あらゆる「行い、行動」の根本にあるのは「心」であって、現実の「社会」を作り出しているのは、私たち一人一人の「心」だということは、さきほどのこの「木」の絵からも、ほぼお分り頂けたのではないかと思います。つまり、「社会」というものの実体は、私たちの「心」だということです。
「心」が穏やかになれば、自然に「言葉」や「動作」も穏やかになり、「社会」も穏やかになっていきます。「身・口・意」の三業といっても、問題の根本はひたすら「心」にある。だから、「心の病」を癒すことが大切だ。これが仏教の本筋です。
眼に見える世界を生み出しているのは、眼に見えない私たちの「心」です。ですから、私たちの「心」が変われば、「世界」も変わるのです。
ところがですね、私たちは、社会の仕組みを変えれば「幸せ」が得られるように考えがちなんですね。「心」は眼に見えない。ところが「社会の仕組み」は眼に見える。とすると、何かを変えるということになれば、やっぱり「社会の仕組み」の方が眼につく、ということになってしまうんですね。
たとえばこの、社会の仕組みを変えれば「幸せ」になれるという考えを大々的に実行に移したのが「共産主義社会」です。「共産主義」の目指したのは「みんな」が幸せな世界でした。この「みんなが幸せ」という目標は一見間違ってはいないように思えます。ですが、ご承知のように、「共産主義社会」は世界中で崩壊しつつありますね。
その理由は、ちょっと考えれば誰にでも分かります。私たちの「行動」の根本には「心」がある。ところが私たち凡夫の「心」には「煩悩」の火が燃えていて、自分の利益を第一に考えている。この、自分の利益を第一に考えるという「心」をそのままにして、どんなに社会の仕組みを変えてみたところで、「みんなの幸せ」など生まれるはずがない。だから、「共産主義社会」は崩壊していくんです。
「本音」と「建前」という言葉を使って言えば、「共産主義社会」は、「みんなの幸せ」という「建前」から生まれた社会です。それに対して、「資本主義社会」は、「自分の幸せ」という「本音」から生まれた社会です。私たち凡夫の「建前」が「本音」より遥かにもろいということは、誰もが知っていますね。
とはいえ、資本主義社会に暮らす私たちは、資本主義社会が決してバラ色の社会でないことも、よく知っています。資本主義社会も、いずれ共産主義社会のように崩壊するに違いありません。と申しますのは、「本音」も「建前」も「煩悩」から生まれたものだからです。「煩悩」というのは「心の汚れ」のことであって、私たちの「心の真実の姿」ではありません。真実でないものからは、本当の「幸せ」は生まれてきません。
と申し上げただけでは、お分りにくいと思いますので、図を使ってご説明いたします。ちょっと、この図をご覧ください。この「山」のように盛り上がっていますのは、私たちの「心」です。一番上の層が「たてまえ」で、二番目の層が「ほんね」です。「たてまえ」は「みんな」あるいは「全体」というものに重きを置きます。一方、「ほんね」は「自分」あるいは「個人」というものに重きを置きます。
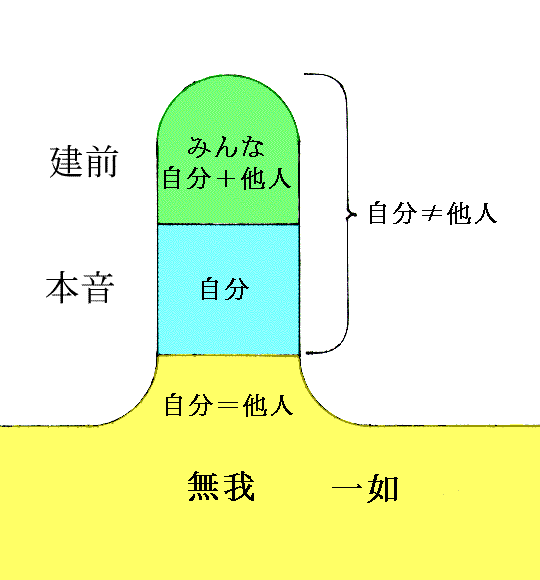 世間では、この「本音」と「建前」を上手に使い分けることができる人を「大人」と呼んでおりますが、世間で言うこの「大人」は「ただの大人」のことです。仏教の言葉で申しますと、「凡夫」のことですね。この凡夫の心に共通して見られる特長が、「本音」と「建前」なんです。
世間では、この「本音」と「建前」を上手に使い分けることができる人を「大人」と呼んでおりますが、世間で言うこの「大人」は「ただの大人」のことです。仏教の言葉で申しますと、「凡夫」のことですね。この凡夫の心に共通して見られる特長が、「本音」と「建前」なんです。
ところで、この「本音」と「建前」は、外見上全く別のものに見えますけれど、実は完全に「同じ心の働き」に裏打ちされているのです。それは、「自分と他人は切り離されている」、「自分と他人は別だ」、「自分と他人は独立した完全に別の存在だ」という心の働きです。
「みんな」とか「全体」とか言っても、自分と他人を区別したうえでの、つまり「自分と他人」という形での「みんな」であり、「全体」なんですね。また、「自分、自分」と言っても、「他人」がいなければ「自分」という言葉すら無意味になりますから、結局、「本音」も「建前」も、「自分と他人を区別する」という心の働きのうえに成り立っているのです。そして、この、「自分と他人は別」という心の働きこそが、「煩悩」の正体なんですね。
この「自分、自分」と言う「本音」の核にあるものを、仏教では「マナ識」と呼んでおりますが、「心」というのはこれだけで終わりではないんですね。この「マナ識」のさらに下に、本性は「空」だと言われる「アラヤ識」があります。
「空」というのは「自他の区別」がない世界、「自分と他人とがイコール」になっていて、「他人」と切り離された「自分」というものが存在しない世界です。「自分」というものが無い。「自分」が無いだけでなく、「他人」も無い。仏教で言う「無我」というのは、この世界のことなんですね。
「自分」も「他人」も無い。全ては一つである。この「全ては一つ」という真実ありのままの世界を、仏教では「一如」と呼んでいます。ついでに申しますと、この「一如」というのは「真如」とか「如」とも言います。「如」とは、宇宙永遠の真理のことです。この「如」が、私たちの住む娑婆世界に現われたとき、それを「如」から「来た」、つまり「如来」と言うんですね。「如来」とは「仏」のことです。ですから、「仏」とは、宇宙永遠の真理が、この世界に働き現われた姿のことを言うのです。
この「心」の絵で申しますと、この「自分」という部分から上が「娑婆」、つまり、私たちの言う「現実世界」です。この娑婆は、「自分」と「他人」が対立している世界です。「自分」と「他人」が対立しているからこそ、損だとか、得だとか、正義だとか、邪悪だとか、勝ったとか、敗けたとか、上だとか、下だとかいった、競争の世界になっているんですね。どんな競争でも、相手がいないとできませんものね。ですが、仏教のめざしているのは、どんな競争とも無縁の、この「無我」の世界なんです。
この「自分」と「他人」との区別のない「無我」の世界を、「本音」という色の着いたガラスを通して見たものが「みんな」という「建前」の世界です。別の言葉で申しますと、「自分イコール他人」という「無我」の世界を、「自他」を区別する目で見ると、「自分と他人」という形での「みんな」というように見える、それを「建前」と言っているということです。「建前」が、ちょっと綺麗に見えるのは、「本音」という色ガラスを通して下の「無我」の世界が映っているからです。
ですから、「本音」が透明になれば、「心」の全体が「無我」、つまり「宇宙永遠の真実」になります。仏教の修行というものは、みな、この「本音」を鍛えて透明にするためにあるのです。
しかしです。「本音」を鍛えて透明にするためにあるのが修行だとは申しましても、この修行は、いくら「努力」してもなかなか上手くはいきません。何故かと申しますと、「努力」というのは、「自分が努力する」というように、「自分」というものが核になって成り立つものなのです。つまり、「努力」というのは、「自力」なんです。「自力」というものは、「自分」と「他人」を区別する娑婆の世界に属しているものなんです。
「本音」から「自分」という色を抜くのが修行の目的です。ですから、「努力」でこれをやろうとするのは、「自分」を握り締めたままこの「自分」を捨てようとしているようなものです。握り締めれば握り締めるほど、目的に反して「自分」が捨てられないのです。本当に「自分」を捨てようと思えば、「努力」という形で握り締めているこの手を開かねばなりません。「努力」すればするほど道は遠くなる。お釈迦さまが苦行をお捨てになった理由のひとつも、ここにあると思いますね。
「浄土の教え」に示されているのもこのことです。なかなか「本音」は自分の力、つまり「自力」では鍛えられない。だから、如来の智恵である「お念仏」にお任せしよう、「お念仏」に鍛えてもらおう、というのが「浄土の教え」です。「お念仏」を唱える生活のなかから、自然に「本音」が鍛えられていく、自然に「本音」から「自分」という色が抜けていく。この「自然に」というのが、「他力」なんです。
さて、どうも理屈っぽい話が続きましたので、このあたりで話題を少し変えまして、あまり肩の凝らないお話しにしたいと思います。
さきほどの「心」の絵をご覧になって、既にお分りかとは思いますが、実は私たちの「心」は根本で「ひとつ」になっています。私たちの「心の本性」は「一如」なんです。言葉を換えて言うと、「私たち一人一人の心というものは、深いところで全てつながっている」ということです。
こういう「心の仕組み」は、学者が頭で考えたものではありません。瞑想に熟達した多数の仏教徒たちが、深い深い瞑想のなかで本当に「心の奥底」まで下りていって確認したことを、まとめたものなのです。
ですが、昔から、「他人の苦しみは、死ぬほどの苦しみでも我慢できる」などという言葉がありますね。また、ちょっと上品ではありませんが、落語にも、こんな話がでてまいります。「俺とお前えは違う人間に決まってるじゃねえか。早ええ話が、お前えがイモ食ったって、俺のケツから屁が出るか」なんてね。まあ、私たち凡夫は、ことほどさように、「自分」と「他人」は別だと考えておりますから、「自分イコール他人」という「無我」の世界が私たちの「心の真実の姿」だなどとは、なかなか思えないんですね。
ところがです。どうやら私たちの「心」は深いところでみんなつながっているらしい。そいう証拠らしいものが、近年、科学の分野でもポツポツと確認されるようになってまいりました。仏教徒は経験的に昔から知っていたことですが、私たち現代人には、この科学で確認されたことも少し覗いておくと理解しやすいかもしれませんから、ちょっとそういうお話しをしておきたいと思います。
さて、まずは、以前にテレビで見た実験のお話しから始めましょう。まず双子の兄弟二人に脳波計を取り付けます。二人は実験の内容について全く知らされていません。兄の方は実験室に残し、弟の方を外に連れ出して、遠く離れた遊園地でジェットコースターに乗せます。ジェットコースターに乗った弟の脳波は、恐怖で激しく振動しました。これは誰もが予想できることでしょう。
ところがです。それと同時に、実験室に残された兄の脳波も、同じ波形を描いて激しく振動し始めたのです。その時、兄は自分の脳波に変化が起きたことを自覚したわけでもありませんし、弟がジェットコースターに乗せられて恐い思いをしているということを察知したわけでもありません。ですが、意識を越えたところで兄の脳は弟の脳波の変化を捕えていたということになります。
とするとです、この二人の「心」は、本人たちの自覚を超えたところで、つながっているということになります。双子は特殊なケースかもしれませんが、こんなつながりは親子の間にも見られます。
昔、ソビエトでウサギの親子を使って行なわれた、いささか乱暴な実験があります。親ウサギに脳波計を付けて、ソビエト国内の実験室に置いておきます。そして、子ウサギを潜水艦に乗せて、太平洋まで連れていき、決められた時間に殺すんです。すると、ちょうどのそ時間に、遠く離れたソビエトにいる親ウサギに付けられた脳波計に異常な揺れが現われたのです。親ウサギがそれを自覚したかどうかは分かりませんが、心の奥底では子ウサギの身に起こった異変を感じとっていたらしいのです。
こんな実験は人間ではできませんが、「何か妙な胸騒ぎがすると思ったら、親しい人が亡くなったという知らせを受け取った」というような話をよく聞きますのは、こういう「心」のつながりがあって、特に敏感な人や、特殊な環境のもとでは、それが自覚できるからかもしれませんね。
次は、世界的に有名な「ニホンザル」の話です。「ニホンザル」の観察から得られた不思議な話はいくつもあるのですが、ここではひとつだけお話し致します。
昭和27年のことです。宮崎県の日南海岸公園にある幸島のニホンザルに餌付が開始され、海岸の砂浜にサツマイモがまかれました。ところが砂浜にまかれたサツマイモには砂や泥がついて、はなはだ食べにくい。猿たちはこの砂や泥に手を焼きました。そのままかじると口のなかが砂だらけになってしまうのですね。
ところが、ある日、生後18ヵ月の若い天才的なメス猿があらわれ、見事にこの問題を解決したのです。彼女はイモを海で洗って食べるということを思いついたのです。この子猿はイモの洗い方を母猿や友達の子猿たちに教え、この「イモ洗い」は徐々に群れのなかに広がってゆきました。
そして6年後の昭和33年の秋のことです。「イモ洗い」をする猿の数がある数量を越えたとき、急に、群れ全体がイモを洗って食べるようになったのです。話はそれだけではないのですね。時期を同じくして、遠く離れた大分県の高崎山の猿たちも、突然、サツマイモを洗い始めたのです。
この現象を知って、日本でも有名なイギリスの生物学者ライアル・ワトソン博士は、ひとつの仮説をたてています。それは、「情報が、ある集団のなかの一定数のものに共有されると、その瞬間に通常の情報伝達手段を越えた何らかの方法によって、その情報は集団全体、あるいは同種の生物全体に伝わるのではないか」というものです。
たとえば、イモを洗うサルが99匹になるまでは、やって見せるとかいった通常の情報伝達によってしか伝わらないのに、イモを洗うサルが100匹を越えたとたんに、現代の科学では説明できないような超常的な方法で、その情報が爆発的に広まって行くということです。
もう少し日常的な「たとえ」で申しますと、「誰かが一度通った道は通りやすい。それも、たくさんの人が通った道は通りやすい」ということになります。たとえば、大量に雪の積もった谷を誰かが雪をかきわけて向こうの丘まで進んだとします。すると次に向こうの丘まで行こうとする人は、先の人がかきわけた道を通って、最初の人よりも楽に行きつけるでしょう。
「救い」も「悟り」もこれと同じではないでしょうか。つまり、誰かが一人悟れば、あとに続く人は少しは楽に悟れるということではないかと思います。お釈迦さまが独力で悟られたことで、後に続く者たちはいくぶんでも悟りやすくなった。また、さきほどの「ニホンザル」の話などから考えますと、「悟った人」「目覚めた人」の数が増え、ある一定の数を超えれば、世界が急激に穏やかになっていくのかもしれませんね。
これに関しては面白い実験の報告があります。科学的実験と言えるかどうか分かりませんが、ある瞑想の団体がアメリカのロードアイランドで行なった、ちょっと変わった実験の報告です。その報告によると、1978年6月12日〜9月12日までの3ヵ月間、瞑想に熟練した300名の人がロードアイランドで瞑想を行なったところ、その期間にロードアイランドでは殺人事件数が前の年に比べて50パーセント、交通事故が48パーセント、自殺が45パーセントも少なくなったというのです。
また同じ団体が1978年10月半ばに行なった実験も報告されています。それによると、約900名の瞑想熟練者を世界各国の紛争地域に派遣してグループで瞑想を行なったところ、彼らが滞在していた間は各地で平和の方向に大幅な進歩が見られたが、グループが帰国すると再び紛争が始まった、ということです。
これらの報告の真偽のほどは分かりませんが、「私たちの心は深いところでみなつながっている」のですから、こういうことが起こっても不思議ではないと思いますね。
「念仏行」も、その他の「瞑想」も、社会を良くするためにではなく、私たちの「心」をこの「アラヤ識」のレベルまで鎮めるためにあるのです。しかし、そんな私たちの心は深いところでみなつながっていますから、この心の深いところで起こる「救い」は自分だけの「救い」ではないのです。言葉を換えて言いますと、「本当に私が救われる道は、同時に他の人々が救われる道だ」ということなのです。
ついでに申しますと、仏教で言う「救い」というのは、「自分と他人」を区別する娑婆で「自分」に都合の良いことが起こるという意味ではありません。もう少し詳しく申しますとね、ちょっと語弊があるかもしれませんが、たとえば、死刑囚でも「仏教」で救われることができます。救われることはできますが、たとえ救われても、やはり死刑は執行されるのです。私たちは、「救われる」というとすぐに「死刑が取り止めになる」というふうに考えてしまいますが、そうではないのです。仏教で言う「救い」は「魂の救い」なのです。魂が「宇宙永遠の真実」、つまり「一如」に目覚めることが「救い」なのです。こういう「救い」を求める人はまれかもしれません。ですが、こういう「救い」に向かって進んで行くのが人類の究極の姿だと、私は信じております。
さて、「アラヤ識」は「一如」です。ですから、そこには「自他」の区別がありません。「人の喜びは、そのまま自分の喜び、人の悲しみは、そのまま自分の悲しみ」というのがこの心のレベルです。「人の喜びは、そのまま自分の喜び、人の悲しみは、そのまま自分の悲しみ」。実はこれは、如来の慈悲の世界なんですね。
かつて「法蔵菩薩とはアラヤ識のことだ」とおっしゃった方がおられましたが、法蔵菩薩の誓願というのは、「心の本性」「一如」の世界に戻れという、慈悲の世界からの呼び掛けですから、まさしく、法蔵菩薩とはアラヤ識のことだと言えます。「お念仏」というのは、この法蔵菩薩の呼び掛けに答える「声」なんです。そして「念仏行」とは、この法蔵菩薩の世界にまで戻るための「行」なんです。
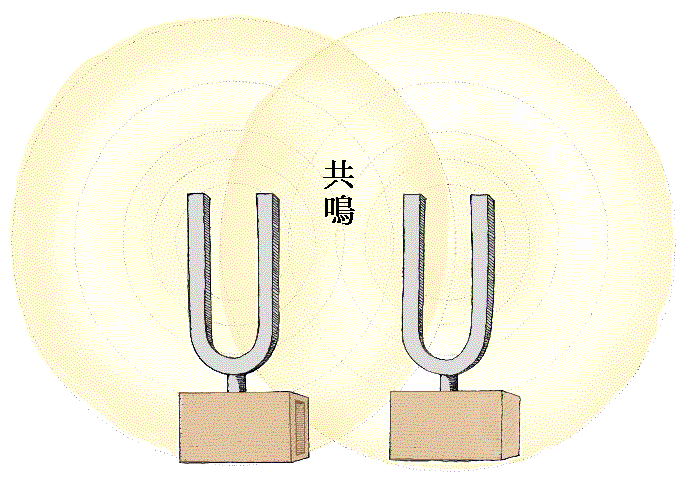 「法蔵菩薩の呼び掛けに答える」というのは、たとえて言えばこういうことです。これは、理科の実験などで用いる「音叉」です。これをバチでたたくと固有の振動数の音を発します。同じ振動数の音叉を二つ並べてその一方をたたくと、もう一方が共鳴して音を発します。振動数の違うものなら共鳴を起こしません。
「法蔵菩薩の呼び掛けに答える」というのは、たとえて言えばこういうことです。これは、理科の実験などで用いる「音叉」です。これをバチでたたくと固有の振動数の音を発します。同じ振動数の音叉を二つ並べてその一方をたたくと、もう一方が共鳴して音を発します。振動数の違うものなら共鳴を起こしません。
人の「心」は本来「一如」ですから、みな同一の振動数を持った音叉のようなものです。ですが、「自分と他人」を区別する煩悩というヨゴレで表面がサビついているので、「人の喜びは、そのまま自分の喜び、人の悲しみは、そのまま自分の悲しみ」というような、本来の「共鳴」が起きなくなっているのです。たとえば、こんな具合にです。
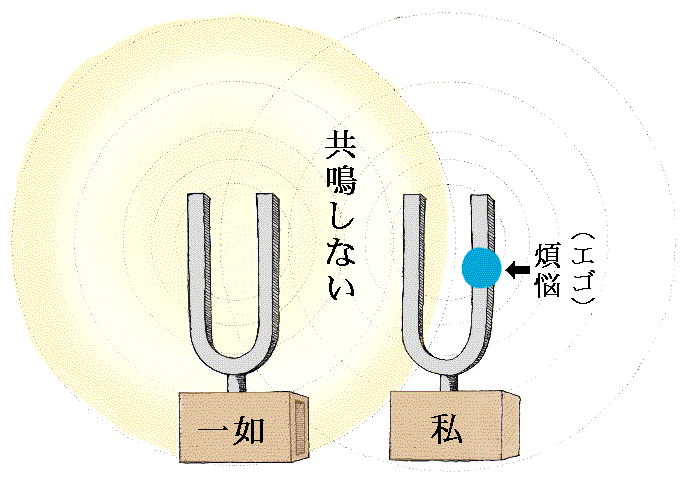 いわば「念仏行」はこのサビ落としなのです。サビを落としながら本来の自分に戻ってゆく。そして、本来の音、つまり「一如」の世界からの音に共鳴できるようになっていくこと、これが法蔵菩薩の呼び掛けに答えるということなのです。
いわば「念仏行」はこのサビ落としなのです。サビを落としながら本来の自分に戻ってゆく。そして、本来の音、つまり「一如」の世界からの音に共鳴できるようになっていくこと、これが法蔵菩薩の呼び掛けに答えるということなのです。
こんなことを申しておりますと、「何を世間離れした綺麗事を言っているのだ、そんな綺麗事で暮らせたら苦労は無い」と、お考えになる方もおられるかもしれません。ですがね、そういう方も、よく考えてみてくださいね。いま、あなたの心に湧いてきた、「そんな綺麗事で暮らせたら苦労は無い」という言葉、それこそが「法蔵菩薩の呼び掛け」なのですよ。「できそうにない。できそうにないけれど、できたらどんなにいいだろう」という、その心の奥底からのささやきこそが「法蔵菩薩の呼び掛け」なのです。
仏教は「綺麗事」を説いているのではありません。さきにも申しましたが、「綺麗事」というのは「建前」のことです。仏教は「綺麗事」ではなく、「綺麗そのものの世界」、つまり「無我の世界」、「浄土の世界」を説いているのです。
その「浄土」をめざす「行」が「念仏行」なのです。私たち仏教徒は「お念仏」によって、何か特別な能力を身につけようとか、何か特別に人間になろうとしているのではありません。ただただ、本当の自分に戻って往こうとしているのです。
私たちは、もともと「ひとつ」でした。「一如」だったのです。ですから、その記憶が心のどこかにあって、私たちは他の人々との心のつながりを求めるのです。他の人々と「ひとつ」になって、あの幸せを取り戻したい。本来の世界に戻りたい、本来の「一如」に戻りたい。そんな私たちの「浄土への旅」は、言葉どおり「魂の故郷への里帰り」なのです。
私たちは、もともと「ひとつ」でした。ですから、そんな私たちにとって一番苦しいのは、「自分はひとりぼっちだ」という「孤独」を感じたときではないでしょうか。
この寺のお同行にも、一人暮らしのお年寄りが何人もおられましてね、「子供たちは近くに住んでいても、滅多にのぞいてくれませんのや。寂しいやら、虚しいやら、何や生きていても張り合いがのうて。みんな、こんなものかね。ご院さん、みんな、歳とったらこんなものかね」と、私みたいな若い坊さんにでもこぼされることがあります。
一人で暮らしているというのは、やっぱり寂しいものですね。ですが、子供たちと一緒に暮らせば幸せか、と言いますと、必ずしもそうでもない。
統計によりますと、日本は高齢者の自殺率が世界一なんだそうですが、自殺をする人の6割が三世代同居家庭のお年寄りだそうです。それも、自殺の原因の第一位は、「寂しいから」というのですね。傍目からは、家族と一緒に暮らせて幸せな人のように見えても、家族の誰とも心のつながりがない。そんな家族のなかで無視されているというのは、一人暮らしの孤独より、もっと苦しいものだろうと思いますね。
これば、決して、お年寄りだけの話ではありません。歳をとっていても、若くても、私たちは、他の人々との心のつながり無しでは生きていけないのですね。
本当は、私たちはみんな、寂しいのです。ですから、みんな、「自分」を認めてもらおう「自分」を認めてもらおうと、やっきになっているのです。「自分」を認めてもらうということで他の人々とつながろうとしているんです。
ですが、この「自分を、自分を」というのは、「自分」と「他人」をどんどん区別していくということですから、「自分」というものにこだわればこだわるほど、「自分」と「他人」との間が離れていくものです。
若くて健康で夢や希望があって、「自分」が何か大きな幸せに向かって進んでいるように感じている間は、遠くにある夢や希望や、目先の刺激にばかり目が向いていますから、自分の心の奥底からの呼び声にまでは気づきません。ちょうど、太陽が出ている昼間には広大な宇宙にまたたく星の光に気づかないようなものです。
ですが、太陽が雲に隠されたり、太陽が西に沈んでいったりすると、それまで見えていなかった星の光に、おぼろげながら気づくのです。太陽を隠す雲というのは、夢や希望が消え去るとか、愛する人に先立たれるとか、定年退職するとか、重い病気になるとか、人生の終盤を迎えるいったような出来事です。私たちの耳に、心の奥底からの呼び声が聞こえてくるのは、こんなときなんですね。
この呼び声は、「魂の故郷に帰っておいで」という、「大きな生命」、「一如」からの呼び声なのです。ですが、私たちは、この「自分」というものをどうしても手放せない。「自分」というものを握り締めたまま、この呼び声を聞くと、「寂しい、虚しい」と聞こえるのです。
人生のなかでの寂しいことも、悲しいことも、全て「魂の故郷」を思い出すためのご縁なのです。そして、その「魂の故郷」に戻るための道が、「お念仏」なのです。静かなところに座り、そっと目を閉じ、「お念仏」を唱えて一心になれば、「自分」というものを握り締めている手から自然に力が抜けていきます。
そしてこの、握り締めている手の平が開いていくにつれて、「自分」も「他人」もない「一如」の世界からの、明るく暖かな光が、その手の平に差し込んでくるのです。そして、自分はひとりぽっちではない、自分は世界の全てと「ひとつ」であるということに気づいていくのです。
さて、それでは、私たち「門徒の教え」に即して、今日のお話しをまとめておきたいと思います。
仏教にはもともと、「これはしてはいけない、あれはしてはいけない」という戒律というものが沢山あります。たとえば「生き物を苦しめてはいけない」とか、「物を盗ってはいけない」とか、「ウソをついてはいけない」といったようなものですね。この戒律が250とか300とかあって、これを守るというのが、もともとの仏教徒だったのですが、真宗にはこの戒律というものが全くございません。
「これはしてはいけない、あれはしてはいけない」という戒律が全く無いのですね。ですが、この「戒律が無い」というところで終わってしまえば、それは仏教でも真宗でもありません。「門徒は何もせんでええから楽や」というのでは、「門徒物知らず」といわれても仕方がありません。真宗には「〜してはいけない」という戒律はひとつもありませんが、「これをしなさい」というのがひとつだけあるのです。それは「お念仏を唱えなさい」ということです。
何故、「お念仏」しか言わないのか。それはですね、「生き物を苦しめる」とか「物を盗る」とか「ウソをつく」とかいう行いは、最初に申しましたように、みな「心」から生まれてきますね。たとえて言えば、様々な行いは、この扇子の1本1本の骨みたいなものです。この骨の根っこは、ここにあるんですね。ここが心です。「お念仏」というのは、ここで全ての骨を押さえているこの「カナメ釘」のようなものです。この「カナメ釘」さえきちんと押さえられていたら、あとは放っておいても、きちんと治まります。ですから、真宗では1本1本の骨については何も言わないのです。
しかし、娑婆世界では、往々にしてこの「カナメ釘」のことを忘れてしまいやすいのですね。ですから、こんなふうに、「カナメ」が無くなって、バラバラになってしまうのです。生活のなかにこの「カナメ」を取り戻す。それが「お念仏を行ずる」ということです。
「念仏行」は、決して自分だけが救われる道ではありません。私たちの心は深いところで全てつながっているのです。ですから、自分だけの救いというものは絶対に無いのです。本当に自分が救われていくなら、同時に他の人々も救われていくのです。
ですが、これまでにも度々お話し申し上げてまいりましたように、お仏壇に向かって、ナマンダブ、ナマンダブと言いながら、先祖の冥福を祈ったり、自分の後生を願ったり、一日の反省をしたり、嫁さんの悪口を言ったりしているのが、「念仏行」ではありません。
「念仏行」というのは、はからいを離れて「一心」になること、「お念仏」そのものになることを言うのです。「お念仏」に任せて、「心」の中のオシャベリを止める。それが「念仏行」なのです。
「欲望」と「他人の思惑」ばかりに振り回され、娑婆の流れに流されている。そんな慌ただしい時間を止めて、娑婆の流れから自分を救い上げる。それが「念仏行」なのです。どうぞ、静かな場所に座って眼を閉じ、自分も他人もない「無我」の世界からの呼び声に、耳を澄ましてみてください。
そんな「お念仏」を唱える生活のなかで、自然に「ほんね」が鍛えられていきます。そして、娑婆のなかでたまった「心」のサビを落としながら、本当の自分に戻っていくのです。どうぞ、そういう「お念仏」を生活のなかに取り戻して頂きたいと思います。
では、本日はここまでにさせていただきますが、最後にちょっと次回の法話の予告を申し上げておきます。
先日、あるお同行のお宅にお参りに行きましたときのことなんですが、「ご院さん、この間の、春のお彼岸の法話を聞かせてもろて、ちょっとガッカリした」とおっしゃるのですね。
「ほう、どういうことでしょうか」と尋ねますと、「私は、お念仏を唱えていたら、死んでから西方極楽浄土へ往生できると思うていたんですが、ご院さんは、西へ西へと進んで行ったら、地球をぐるっと回ってもとの所へ戻って来ると言われた。そんなんなら、死んでからの楽しみが無いんで、なんかガッカリした」と、こうおっしゃる。
私が、「西へ西へと進んで行ったら、地球をぐるっと回ってもとの所へ戻って来る」と申しましたのは、いわば冗談でしてね、そういうことが言いたかったわけではないのです。ですけど、まあ、確かに言葉が足りなかったと思いますので、次回は、もう少し話を進めまして、私たちは「死んだら、それでもう終わりなのか、それとも、終わりでないのか」というお話しをさせて頂こうと思っております。
次回は、10月16日の報恩講でございます。今日から数えましても、ひと月もございませんので、多少慌ただしゅうございますが、どうぞ、お参りくださいませ。お待ち申し上げております。本日は、どうも、長い間お付き合い頂きまして、ありがとうございました。
紫雲寺HPへ