本日は10月16日で、多少日が早うございますが、11月28日の親鸞聖人のご命日のお勤めでございます「報恩講」と、昭和63年11月3日に亡くなりました前前坊守・正覚院釋尼妙操の七回忌を、併わせて勤めさせていただきました。この法要に会うご縁を皆様とともに頂けましたことを、有り難く存じております。
さて本日は、前回にお約束いたしました、「死ねば終わりか、それとも、終わりでないのか」というお話しをさせて頂こうと思っておりますが、まず最初に、皆さんにちょっとお考えいただきたいと思います。……皆さんは、「死んだら、どうなる」とお考えでしょうか。「死んだら、それでもうお仕舞いだ」とお考えなのでしょうか。
「生んでくれと頼んだおぼえもないのに、生まれてきた。いわば、生まれてきたのは偶然だ。また、死にたいと思わなくとも、いずれ死なねばならない。死んでしまったら、それでもうお仕舞いだ」とお考えでしょうか。
「生まれてきたのだから、死ぬまで生きていくしかないのだ。どうせ、死ぬまで生きていくしかないのなら、出来るだけ楽しく生きたい」。私たち現代人は、たいてい、こんなふうに思っているのではないでしょうか。NHKの世論調査を見ても、死後の世界を信じている人は12%しかいないのです。
ですが、もし本当に、「生まれてきたのは偶然で、死んでしまったらお仕舞いだ」と言うのなら、「人生なんて、もともと意味も目的もないものだ」、ということになりはしないでしょうかね。
この間も、あるお通夜の席で、ご親戚の方がですね、「死んだら終わりや、死んでしもたら、みんな終わりになってしまうのや」と嘆いておられましてね、改めて考えさせられました。確かに、亡くなると、もう二度と「今生」では会えなくなってしまいます。ですが、本当に、「私たちは、死んだら、それでもう終わり」なのでしょうか。
私には、どうも、そうは思えないのです。もう少しはっきり申しますと、私自身は、「死んでも終わらない」と信じております。「死んでも終わらない」と言うのなら、どうなると思っているのか。実は、それが、今回と次回の2回に分けてお話し申し上げようと思っていることなのです。
もし、「生まれてきたのは偶然で、死んでしまったらお仕舞いだ」と言うのなら、そこには「面白可笑しく生きたらいいんだ」という一種捨て鉢な思いが残るだけで、いかなる教えも全く意味を持ちません。ですが、もともと仏教は、「死んでも終わらない」という事実を踏まえての教えなのです。
では、その「死んでも終わらない」私たちの人生において、「浄土の教え」はどのような意味を持っているのか。本日のお話しの核心は、この点にございます。
と申しましても、私は何も、「死後の生存」を証明しようとか、私の信じていることを皆様に押しつけようとか思っているわけではありません。どうぞ、お気楽にお聞き頂いて、ご自身でお考えくださいますよう、お願い申し上げておきます。
さて、私たちの肉体が滅びていくことは誰でも知っています。ですから、「死んだら終わりか、終わりでないか」という問題になりますと、たいていは、「魂というものは在るのか、無いのか」という話になってしまいます。そうなると、しまいには、「魂なんてものが在るのなら、ここに出して見せてみろ」などと乱暴なことを言う人もでてくるわけです。
90年ほど前のことですが、この「魂」を「出して見せよう」とした科学者がいました。昔は荒っぽいことをしたもので、死にかけている人を目方計りの上に乗せましてね、死んだ瞬間に、どのくらい体重が減るか確かめようとしたのです。体重が減れば、その減った分が魂の目方だというわけなのです。
何人もの瀕死の病人を目方計りに乗せて計った結果どうなったか。実はです。死ぬと同時に体重がほんの少しだけ軽くなったんですね。人によって違ったらしいのですが、ほぼ3.5グラムから42.5グラムも軽くなった。
この実験をしたのは、イギリスのマクドゥガルという人ですが、当時はオランダでも同じような調査をした人がいたと聞いております。もちろん、最近は、こういう荒っぽい研究をする人はいませんので、この減った体重が、魂の目方だったのかどうかは定かではありません。
魂の目方ということで申しますと、もうちょっと違った実験もあります。皆さんは「体外離脱」という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。「体外離脱」というのは、いわゆる「魂」が、肉体から抜け出してしまう現象を言います。
たとえば、もし皆さんが、ふと気づいたら、身体を抜け出して、上の方から自分の身体を見ていたとか、身体を抜け出して遠くまで飛んでいき、そこで見たり聞いたりしたことが、あとで確かめてみると、本当だった、といったような経験をなさったことがおありでしたら、それが「体外離脱」体験だったわけです。
「体外離脱」は、たいてい偶然に起こります。その起こる確率は100人に1人程度と言われていますが、これを自分の意志で自由に起こせる人も、ごくたまにですけれど、いるのですね。そういう自由に肉体を離れることができる人を、さきほどのような目方計りに乗せて調べた実験があります。
これはオランダの科学者が行なった実験ですが、その報告によると、被験者の魂が肉体を離れている間には、体重が64グラム軽くなっていたということです。
ですが、まあ、たとえ「魂」が在るにせよ、その「魂」に目方があるかどうかとなると、ちょっと首をかしげねばならないような気もしますね。目方があるということになれば、「魂」は物質だということになってしまいます。
私たちの身体は、物質でできております。物質だけでできているかどうかは分かりませんが、まあ、ともかく物質でできている。物質とは何かと、分子から原子へとさかのぼり、ついには、この原子も陽子、中性子、電子という、さらに小さな粒から成っているということが分かった。これが、50年程前までの物質観だったんですね。物質を構成している一番小さな粒は電子だ、というわけです。
ところが、その後、科学は、この電子よりさらに小さな世界を発見したのです。驚いたことに、物質の究極は物質ではなかったのです。物質の究極を追い求めていった結果、そこにあったのは物質ではなくて、様々な波長の電磁波、あるいは光としか言えないような、エネルギーだったのです。
要するにですね、私たちが実際に存在すると考えているあらゆる「物」は、実際には一種の「光」からできているということなのです。とするとです。私たちの身体も物質でできている。物質でできているということは、つまり、光でできているということになるのですね。不思議だとは思われませんか。
私たちは光でできているのですが、それだけではないのですね。人間に限らず、あらゆる生物は常に目に見えないほどの弱い光を身体から出しているのです。この光は特殊な高感度カメラで撮影することができます。日本では東北大学の電気通信研究所で研究されております。以前、テレビで、発芽した大豆から出ているこの光の映像を放送したことがありますから、ご覧になった方もおられると思います。
生きている限り、私たちは常に光を出している。では、死ねばどうなるのか。ある物理学者の研究によりますとね、生物は死亡する瞬間に、通常の1000倍以上もの強力な光を発することが分かったというのですね。
まれには、臨終を迎えた人から、この光が放出されるのを、周囲の人が目撃することもあると言われております。ある報告によりますと、この光は、臨終の人の身体から立ち昇る、ぼんやりとした白いモヤのように見えた、ということです。
私たちの身体は光でできております。その光でできている身体から、臨終に際して抜け出て行く「光」がある。生命というのは不思議なものですね。ひょっとすると、この身体から離れて行く「光」が、私たちの「魂」なのかもしれませんね。
不思議ついで、と言っては何ですが、今日はさらに不思議な話を続けます。仏教の話はいつになったら始まるのか、と思っておられる方もおられるかもしれませんが、これからお話しすることは「浄土の教え」と大いに関係があります。というよりも、科学の時代に生きる私たちにとっては、「浄土の教え」を理解する上で、非常に有益な話ではないかと思います。
その話というのは、「臨死体験」の話です。「臨死体験」というのは、死の淵から生還した人が、あの世とこの世の狭間で得た、様々な不思議な経験のことを言います。
医学的に見て死んだと思われた人が生き返った。心臓が停止し、呼吸が止まり、瞳孔が開いて、脳波が平坦になった。そして、医師が死を宣告した。そういう臨床的には死を宣告された人が、奇跡的に息を吹き返したということが、結構あるんですね。
医学的には5分以上呼吸が止まれば、脳に酸素が行かなくなって、たとえ蘇生しても脳に機能障害が残ると言われております。ですが、実際には、呼吸が止まって12時間も経ってから息を吹き返し、脳には何の障害も無かったという例もあるのです。
その臨床的に見れば死んでいた間に、様々な不思議な経験をした人、こういう人は結構多いらしいんですね。世界最大・最高の世論調査機関でありますアメリカのギャラップ世論研究所が1982年に発表したところによりますと、アメリカ人の成人のうち、約14パーセントが死にかけた経験を持ち、そのうちの35パーセントが「臨死体験」をしている、ということです。これは数で言えば、約800万人に相当します。
では、その「臨死体験」とは、具体的にはどんな体験なのか。臨死体験者の話を総合すると、だいたい次のような体験のようです。
- まず、死を自覚する。「うまく説明できないが、自分は死んだということが分かった」と言うのですね。
- そして、それまでの肉体的な苦痛が消えて、深い安らぎが訪れる。
- 気づいたら、身体から抜け出して、ベッドに寝ている自分の身体を、上の方から見下ろしていた。ベッドの周りで慌ただしく働いている医師や看護婦の姿や、廊下で不安そうに待っている家族の姿が見え、彼らの会話が聞こえた。…これは、さきほどお話しいたしました「体外離脱」と同じ経験のようです。そんなふうにして、しばらく身体の上に浮かんでいた。
- やがて、暗いトンネルに吸い込まれて、ものすごいスピードで進んでいくのが分かった。遠くに、トンネルの出口の光が見えた。
- トンネルを抜けて、言葉では説明できないような、輝く光の世界に入った。そこで、「光の存在」つまり「生命のある光」に出会った。…臨死体験者のなかには、この「光の存在」を「神」だと感じた人もいれば、「仏」だと感じた人もいます。
- その「光の人」は、自分を包み込んで、自分の一生を見せてくれた。人生のあらゆる出来事が、走馬灯のように流れ、細部まで再現された。
- そして、その「光の人」に、「あなたにはまだやらねばならないことがある、帰りなさい」と言われて戻ってきた、と言うのです。
こんな話を初めてお聞きになった方は、何か狐につままれたような気持ちになられたかもしれませんが、「臨死体験者」は、こういったことを実際に経験したと言うのです。
多数の学者が研究した結果、こういった「臨死体験」は、人種や年令、性別、学歴、職業、社会的地位、文化、宗教などに全く関係なく起こり、その体験内容は誰の場合でもほぼ同じものである、ということが分かったのです。
人は臨床的に見て死亡したと判断されても、何時間も経ってから蘇生することがある。また、信仰を持っていたかどうか、あるいは、どういう信仰を持っていたかといったことに全く関わりなく、ほとんど同じ「臨死体験」をする。そこで困ったのは、キリスト教会と一部の医師なんですね。
キリスト教会では、神に背く者、つまり教会に楯突く者、信者でない者は、天国に行けるはずがない、ということになっておりますから、信仰に関係なく、死んだら誰でも明るく輝く光のなかで神に出会うというのでは、はなはだ都合が悪い。
そこで、教会側に立つモーリス・ローリングスという医師が、地獄のような不愉快な「臨死体験」の例を集めようとしたのですが、これが予想に反してかなり少なかった。調査の結果、臨死体験者のなかで地獄のような苦しい経験をしたのは、0.3パーセント、つまり、1000人に3人の割合でしか見つからなかったんですね。
まあ、0.3パーセントでも、いるにはいた。つまり、地獄を経験した人はゼロではなかったわけですが、明るい光を経験した人に比べて極端に少なかった。どういう人が地獄のような苦しみを経験するのか分かりませんが、997対3という、この割合から考えると、たいていの人は明るい光の世界を経験すると考えてよいかと思いますね。
もうひとつ、医師が困ったというのはですね、人は臨床的に見て死亡したと判断されても、「臨死体験」をして蘇生することがあるということになれば、死の判定ができなくなってしまうからです。
アメリカのある心臓病専門医の研究によりますと、神経科の専門医が12チャンネルの脳波計で脳波を測定して、「脳死」と判定されたのち、30分から3時間も経ってから生き返ったという「臨死体験者」の例が、30例ほどあるそうです。
となると、「脳死」を基準にした「臓器移植」など、簡単にはできなくなってしまいます。なにしろ、「臓器移植」には、まだ死にきっていない肉体から臓器を取り出さねばならないのですからね。ですから、さきほどお話ししましたギャラップ世論研究所の発表以後、アメリカではたいていの医師が「臨死体験」を認めるようになりましたが、「臓器移植」を推進していこうとしている一部の医師のなかには、いまだ「臨死体験」の存在そのものを認めないという人もいるようです。
まあ、それはともかく、「臨死体験」に関心をお持ちになった方は、お手元にお配り致しておりますプリントに何冊かの本を紹介しておりますので、そちらをお読み頂くということにして、話を進めたいと思います。
さて、この「臨死体験」の中でもっとも大切なのは「光」に出会ったという経験です。つまり、「臨死体験」の中核を成すのが、この「光との遭遇」なのです。そこで、この「臨死体験」のなかで出会うという「光の世界」に的を絞って、体験者の報告に耳を傾けてみたいと思います。
臨死体験者たちの報告を総合すると、こんな話になります。ちょっと長いのですが、どうぞ情景を想像しながら、お聞きください。
- 暗いトンネルの出口は、夕焼けか、あるいは沈んでいく夕日のようなオレンジ色に見えた。トンネルを出ると、そこは光あふれる場所で、一面黄金色に輝き、光の洪水に遇ったようだった。途方もない量の光で、非常に明るく、強烈に輝いていたのに、少しも眩しくなかった。それはエネルギーの塊のようで、このうえなく素晴らしいものだった。
- どこから光がくるのか分からなかったが、光はあらゆるところにあった。光の届かないような所は、いっさいなかった。全く影を落とさない光だった。両手で小さなお碗を作ってみて気が付いたのだが、手の平の側も、手の甲の側と同じように明るかった。
- その光は、私を包み込み、完全な愛と喜びで満たしてくれた。心が洗われるようで、穏やかな安心した気持ちになった。静かで、平和そのもので、ゆったりと安らかな気持ちだった。とてもよい気分で、完全に愛されている感じがした。深く強い慈悲に包まれているような気持ちがした。これが一晩続いたことなのか、それともほんの一瞬のことだったのかは分からない。そこには時間と距離の感覚が無かった。
- 気がつくと、そこは庭園だった。あらゆるものが強烈な色彩を放っていた。草は鮮やかな緑色で、花々は輝くような真紅、黄色、青に咲き乱れ、茂みには極彩色の鳥がはばたいている。明るい光がすみずみにまで届き、風は全くなく、何もかもが光り輝いていた。聞こえるのは鳥のさえずりと、花々の開く音だけだった。小川がせせらぎ、花や草や木や丘もある田園のなかにいるようだったが、私たちが思っている草や木ではなかった。草木の一本一本が内部から光を放っていた。
- 遠くに町が見えた。建物は明るく輝いていた。人々は幸福で、泡立つ水や噴水があって、光の都とでも呼びたいような、素晴らしい光景だった。美しい音楽が流れ、あらゆるものが輝いていた。言葉では表現できないほど壮大な、美しい光の都市を見た。花園や庭園や広い草原、黄金に輝く城や御殿に至る門を見た。
- ひとつの光が近付いてきた。その光には生命があり、はっきりした個性と人格が感じられた。その『光の存在』は、あらゆるものに浸透し、人を愛で充たすような、美しい強い輝きを放っていた。完全な愛と英知の光だった。私は、その光の生命に完全に包み込まれ、保護されているのを感じて、すっかりくつろいだ気分になった。完全に理解されている、無条件に愛されていると分かった。
- その光の存在が、言葉ではなく私の頭のなかに直接話しかけてきた。それは、『この世界に入る心の準備ができているか』、また『価値のある人生だったか』という意味の質問だった。思ったことが直接伝わってしまうので、何も隠し事はできなかったが、その光の存在は、全てを受け入れてくれて、私に一生を振り返らせた。
- 自分の全生涯が一度に目の前に映しだされ、あらゆる出来事がパノラマのように広がった。そのなかで、私は人生のあらゆる出来事を再体験し、自分の行いが他人にどんな影響を与えたかを知った。意地悪なことをした場面では、相手の悲しみや苦しみが、そのまま伝わってきた。愛情のこもった行いをした場面では、相手の穏やかで幸せな気持ちを感じることができた。なかには見たくない場面もあった。だが、その間、光の存在は一言も非難せず、暖かく見守ってくれて、私が自分の人生を理解する手助けをしてくれた。
- 突然、過去、現在、未来のあらゆる知識が、時間に関わりなく同時に存在しているように思える場所に入った。そこは、言葉では到底表現できないような、あらゆる知識のつまった『学びの場所』だった。一瞬にして、全時代のあらゆる秘密、宇宙、星や月、ありとあらゆるものの持つ意味を悟った。だが、『この知識を持ったまま肉体に戻ることはできない』と言われた。
- 光の存在は、『人生で最も大切なのは、他人を愛することを学ぶことと、知識を身につけることだ。肉体を離れるときに持っていけるのは、この二つだけだ』と言った。私はずっと、この光の存在のそばにいたいと思った。だが、『あなたにはまだやり残したことがあるから戻りなさい』と言われて、戻ってきた。
と、まあ、こういう体験なのですね。さて、皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。これは極めて興味深い体験です。と言うのはですね。この、「臨死体験」のなかで経験する「光の世界」というのは、まさに、私たちが「御経」を通じて知っている「西方極楽浄土」の情景とそっくりなんですね。
トンネルの出口が夕日のように輝いていた。だから、方角で言えば「西」だと考えたのかもしれません。また、トンネルを出ると、そこは非常に明るい「途方もない量の光」にあふれた美しく輝く場所だった。その光は強烈だったが、眩しくはなかった。光の届かない所は一切なくて、影ができなかった。そして、そこには時間と距離の感覚が無かった、というのですから、これは私たちの知っている別の言葉で言えば、「無量光」「無碍光」「無量寿」の世界です。そして、そこに広がっているのは、まるで『大無量寿経』や『阿弥陀経』に説かれている「西方極楽浄土」とそっくりの情景なのです。
そっくりなのは「情景」だけではありません。たとえば、阿弥陀仏の左右に観音菩薩と勢至菩薩を配した「阿弥陀三尊像」というものがありますが、あれは「無量の光」である阿弥陀仏を中央にして、左に「慈悲」の観音、右に「智恵」の勢至を配したものです。
「臨死体験」のなかで出会う「光の存在」は、「愛と知識」というものの大切さを力説していますが、レイモンド・ムーディ博士の研究によると、この「愛と知識」というのは、男女の愛や百科事典のような知識のことではなく、「慈悲と智恵」のことだといいます。とすると、これはまさに、「阿弥陀三尊像」の表わしている世界とよく符号していることになります。
また、「浄土の教え」では、「西方極楽浄土というのは、仏の教えを学ぶのに最も適した場所だ」、「そこで仏の教えを学び、悟りを開く場所だ」と説かれていますが、このことも、「臨死体験者」が「光の世界」のなかにあったと言っている「宇宙永遠の真理を学ぶ場所」というのとよく符号しているように思いますね。
「臨死体験」が科学者によって研究されるようになったのは、ここ20〜30年のことですが、「臨死体験」そのものは大昔からあったに違いありません。私は、この「臨死体験」というものが、「浄土の教え」と大きな関わりを持っていると考えております。もう少しはっきり申しますと、私は、この「臨死体験」と「仏教徒の瞑想体験」を核にして生まれたのが、「浄土の教え」だと考えております。
とするとです。ここに大きな問題が生じてくるように思われるのです。と言うのはですね、「臨死体験」の統計によると、ほとんどの人が「光の世界」を経験するらしいのですが、もし、この「臨死体験」が「死後の世界を垣間見た体験」だとすれば、たいていの人は、死ねばみな、この「慈悲と智恵の光あふれる世界」に迎え入れられるということになるのですね。
「浄土の教え」でも同じようなことが説かれています。初期の頃の「浄土教」では、「浄土への往生」に対して、いろいろ条件が付いておりましたが、中国の「浄土教」を大成した善導大師あたりから、実質的にこの条件が無くなってしまいます。阿弥陀仏の慈悲の力を妨げるほどの「悪」は無いから、どんな悪人でも救われる。いや、むしろ、自力で悟りを開けない悪人こそが阿弥陀仏の慈悲の対象だ、ということになってまいります。いわゆる「悪人正機の説」ですね。
つまり「浄土の教え」でも、「臨死体験」の場合と同様に、善人も悪人も、仏法を大切にする人も、仏法をそしる人も、みんな浄土に往生できるということになるわけです。信じていても、信じていなくても、浄土に往生する。となるとです。「浄土の教え」というもの、あるいは生前の信仰というものには、いかなる意味があるのか、という大問題が生じてくるわけです。
実はです。その答えも、「臨死体験」に見ることができるのです。これは「浄土の教え」の場合の答えでもありますので、よくお聞きください。
「臨死体験」にも、浅い体験もあれば、深い体験もあります。死後の世界にまでは到達しなかった浅い「臨死体験」もあれば、死後の世界に何歩か踏み込んだ深い「臨死体験」もあるのです。「深い、浅い」はどこで区別するのかと申しますと、それは「光の世界」を体験したかどうかです。さきほどからお話し致しております「光の世界」に出会ったという体験は、深い「臨死体験」をした人にしかみられません。
浅い「臨死体験」、つまり肉体から抜け出して、いわゆる「体外離脱」をしたという程度の体験では、その後の人生に余り大きな変化は見られません。ですが、この「光の世界」に出会って「人生を回想した」という深い「臨死体験」をした人には、体験後に極めて大きな変化が現われるのです。ここが大切なところです。
では、何が変化するのか。それはですね。「光に遇う」という深い「臨死体験」をした人は、人格が変わり、生き方が変るのです。どんなふうに変るのか、具体的にちょっと見てみましょう。
まず、「光の世界」を体験した人は、死を恐れなくなります。といっても、生命を粗末にするようになるという意味ではありません。その逆です。臨死体験者は、人生に対して大きな情熱を抱くようになります。あるがままの人生を楽しみ、人生をできるだけ大切にしようとします。
生活は充実し、毎日が新鮮で、生きるのが楽しくてたまらない。宇宙に存在するものは全てつながっているという感じを抱くようになり、日常的なほんの些細なことに喜びを感じるようになります。そして、自分の生き方に対して、これまで以上に責任を感ずるようになり、よりよく生きようとするようになります。
財産や名誉や成功を求めなくなり、競争心が薄れ、物よりも人をはるかに大切に感じるようになります。全ての人間が本来的に平等であるという認識が生まれ、分け隔てなく人を愛するようになります。人生の目標が、利己的な関心から離れ、他人にも何かしてあげたいという気持ちに変るのです。
宗教的な面で言えば、概して特定の宗派にこだわらなくなります。そして、狭い宗派的な世界を離れて、本当の意味で宗教的な生活をするようになるのです。そんな彼らからは特殊なエネルギーがあふれているように、周りの人は感じるようです。そばにいると精神の高揚を感じ、幸せな気分を感じると言います。
アメリカで最も有名な臨死体験者バーバラ・ハリスはこう言っています。
「病院であの体験をしている間に、私は本当の私に出会いました。それは私の人生で一番大事な出来事でした。宗教的にではなく、精神的霊的な意味で、そのときから、私はすっかり生まれ変ったのです。…それまでの空虚感は、私のなかに生まれた何かで満たされました。それは愛としか呼びようがないものでした。といっても、今まで考えていたような愛ではありません。今まで私が考えていた愛は、夫と私に結婚を決意させ、お互いに相手を所有したいという気持ちにさせる、そういう愛でした。その愛のおかげで、私たちは互いに忠実でした。私たちが持っているいろいろなものを愛していました。子供、家、飛行機。所有するものを愛していました。地域社会に溶け込むこと、社会のために働くこと、ガール・スカウトの指導者でいることを愛していました。こういう愛もみな大切なことには違いありませんが、今度のこの愛は、新しい、身体からあふれんばかりの豊かな愛でした。そのことを考えるたびに涙がこぼれるような愛でした」と。
バーバラは「愛」という言葉で表現しておりますが、これはまぎれもなく「慈悲」のことですね。「光の世界」に出会った「臨死体験者」は、その後の人生が大きく変る。ひとたび死を経験して「慈悲」の光を身に浴びた者は、本当にこの「いのち」を生きることができるようになる。実は、これこそが、「臨死体験」の核心であると同時に、「浄土の教え」の核心でもあるのです。
「浄土の教え」では「死ねばみんな浄土に往生する」と説かれています。ですが、それだけではありません。「浄土の教え」は、幸福な死後の世界を約束するためだけの教えではないのです。考えてもみてください。もし、「死ねばみんな浄土に往生する」というだけの教えなら、どうしてわざわざ「浄土の教え」で「救われる」などと言うのでしょうか。「みんなが往生する」というだけのことなら、「救われる」も「救われない」もないでしょう。
「浄土の教え」は死後の世界に重点を置いた教えではないのです。そうではなくて、「浄土の教え」というのは「この世」で「慈悲の光」を身に浴びるための教えなのです。「慈悲の光」を身に浴びて、バーバラが言っているように、「本当の自分に会う」。そして、一人一人が「いのち」の真実に目覚め、本当の自分を生きることができるようになる。このことを説いているのが「浄土の教え」なのです。
「慈悲の光」を身に浴びた者は、本当にこの「いのち」を生きることができるようになる。「浄土経典」の『大無量寿経』に、法蔵菩薩の第33番目の誓願として、「阿弥陀仏の放つ光に包まれたものは、喜びあふれて、おのずから身も心も和らぎ、優しくなる」と書かれているのは、このことなのですね。ですが、「臨死体験」のことだとか、「法蔵菩薩の誓願」だとか、そんなことを知識として頭で知っても、私たちはさほど幸せにはなれません。
経典にもはっきりと書かれています。私たちが「いのち」の真実に目覚め、本当に幸せになるためには、「慈悲の光」に包まれねばならないのです。「臨死体験」でもそうです。大きく人生が変ったのは、実際に「光の世界」を体験した人たちだけです。
では、どうすれば、そんな「慈悲の光」のなかに入ることができるのか。それには二つの道があります。その一つは、「深い臨死体験」を経験することです。しかしこれは、瀕死の重病人にいわば偶然に起こることでして、体験したいと思って体験できることではありません。ですから、この道は私たち一般に広く開かれた道とは言えません。
私たちに開かれているのは、もう一つの道の方です。その道というのは「瞑想」のことです。大昔から、あらゆる宗教の核には、必ずこの「瞑想」が含まれております。それは「浄土の教え」でも例外ではありません。「瞑想」には様々な方法がありますが、私たち門徒に示されているのは、「念仏行」という瞑想方法です。
深い「瞑想」のなかで開けてくる世界は「死後の世界」とつながっていると、私は信じています。ですが、「臨死体験」で、いわば強制的に「光の世界」を経験させられた人は別として、私たちの大半は「死後の世界」などなかなか信じることはできません。何しろ、私たちは科学の時代に生きておりますからね。理解できない確かめようもないことは、なかなか信じられないのです。
とはいえ、私たちは理解できないことは絶対信じられないかというと、そうでもありません。私たちは、確かめようもない途方もなく不思議な話でも、意外に簡単に信じ込んでしまいます。たとえば「ビッグバン理論」です。「ビッグバン理論」というのは、「今から200億年ほど前に、大きさのない特殊な点が大爆発を起こして、宇宙が生まれ、その時はじめて時間と空間というものも生まれた」という理論でして、これが現在の標準的な宇宙論だと考えられております。
こんな、確かめようもない途方もなく不思議な話でも、私たちは簡単に信じられるのに、「死後の世界がある」という話になると、どうして信じられないのか。それはですね、「ビッグバン理論」なら、たとえこれを信じても、私たちの生き方に大して影響がないからなんです。宇宙がどんなふうにして生まれたかなどということは、所詮、私たちの生活には何の関係もない。ですが、「死後の世界」を信ずるということになれば、大問題が起こってくるのです。
私たちの社会は「死ねば終わりだ」という生命観にもとづいて成り立っていますから、「死後の世界」は計算に入っていない。ですから、これを信ずるということになれば、私たちの世界観がひっくりかえってしまうことになります。自然法則も、歴史も、医療も、信仰も、あらゆるものが見直しを迫られることになってくるのです。個人レベルで言えば、生き方を問われることになってくるんですね。
私たちは、死後の世界で「価値のある人生だったか」などと問われることは計算に入れていない。ですから、今更「死後の世界」があるなどと言われても困るわけです。結局、私たちは「信じられない」のではなく、「信じたくない」のです。
私たちの本当の問題は、娑婆が全てだと固執して、娑婆を超えた世界に関心が向かない点にあります。有り体に言えば、私たちの大半は、「光の世界」を云々する以前の段階に暮らしているのです。
ですが、たまたま縁あって、娑婆を超えた「光の世界」の方に顔を向けることができたとします。仏教では、これを「発心を得た」と言います。この「発心を得た者」には、ちゃんと、娑婆をこえた「光の世界」に入る道が用意されております。その道が、「念仏行」なのです。
「念仏行」というのは、前々から常にお話し申し上げておりますように、一種の「瞑想」です。阿弥陀仏の智恵である「名号」の力によって「一心」になる、「念仏」だけに耳を傾ける、「念仏」そのものになる、というのが「念仏行」です。
私は、「念仏行」によって到達する世界は「臨死体験」と同じ世界だと、考えております。と申し上げただけでは、どうしてそういうことになるのかお分りにくいと思いますので、この「念仏行」を「臨死体験」と照らし会わせながら、ご説明してみたいと思います。
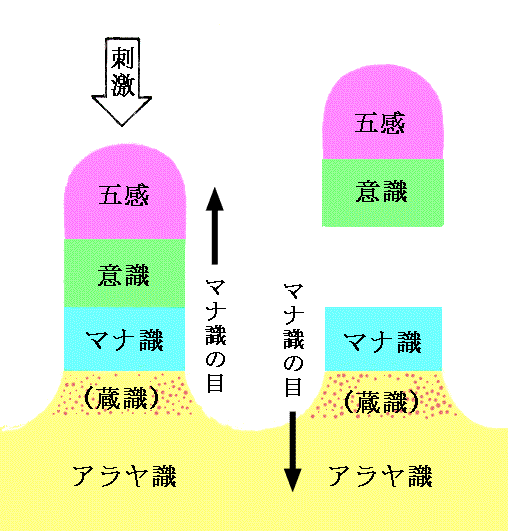 先ず、この絵をご覧ください。以前にもこれと似た絵をご覧頂きましたが、これは「唯識仏教」による「心のモデル」です。山のようになっている心の一番上の層は「五感」でして、その下の層は「意識」です。ここまでの領域は、肉体と結び付いております。そして、その下には、この間もお話し致しました「マナ識」と「アラヤ識」がありますす。「マナ識」というのは、「自分」というものを成り立たせている自我の核になる心でして、「自他を区別する」という「煩悩」によって色付けされています。また、「アラヤ識」は「自他の区別」の無い「光の領域」ですが、ここは「蔵識」とも呼ばれておりまして、私たちのあらゆる経験が蓄積される場所でもあります。
先ず、この絵をご覧ください。以前にもこれと似た絵をご覧頂きましたが、これは「唯識仏教」による「心のモデル」です。山のようになっている心の一番上の層は「五感」でして、その下の層は「意識」です。ここまでの領域は、肉体と結び付いております。そして、その下には、この間もお話し致しました「マナ識」と「アラヤ識」がありますす。「マナ識」というのは、「自分」というものを成り立たせている自我の核になる心でして、「自他を区別する」という「煩悩」によって色付けされています。また、「アラヤ識」は「自他の区別」の無い「光の領域」ですが、ここは「蔵識」とも呼ばれておりまして、私たちのあらゆる経験が蓄積される場所でもあります。
通常、私たちの自我の核であります「マナ識」は外界の「五感」と「意識」に入ってくる膨大な刺激に振り回されておりますから、いわば、「マナ識」の目は上を向いております。ですが、「念仏行」が深まっていくと、肉体に属する感覚が心のなかに入って来なくなる。つまり、この「意識」から上が外れてしまったのと同じようになる。これは「臨死体験」で肉体からの情報が入って来なくなった状態と同じです。こうなると、「マナ識」の目は下を向くようになります。
「マナ識」の下には「アラヤ識」があります。そして、その「アラヤ識」のなかには「私たちのあらゆる経験の記憶」が蓄積されている部分があります。「マナ識」の目は、この部分を通り抜けるときに、「アラヤ識」の「光」のなかで、それまでの人生を回想することになります。
記憶が蓄積されている場所は「アラヤ識」のなかにあるのですから、そこには「自他の区別」がありません。ですから、自分の行為によって他人が抱いた感情も、自分の感情と同じように感じることができるのです。これは、まさに、「臨死体験者」が「パノラマのように人生を回想する」と言っているのと同じ世界です。
「アラヤ識」を更に深く入れば、そこには「人類の記憶」「生命の記憶」「宇宙の記憶」が、過去・現在・未来の区別なく、全て溶け込んでいる、「光の世界」に到達するということになります。
先程はお話ししませんでしたが、「臨死体験」をすると、知能が高まったり、超能力が身についたりすることがあると報告されています。
仏教でも昔から、「瞑想が深まって行くにつれて超能力が現われてくる」と言っています。たとえば「自分や他人の過去や未来の在り方を知る」とか「他人の考えを知る」といった能力です。こういった能力は、瞑想によって「アラヤ識」の奥深く入れるようになると、そのなかに蓄積された記憶を読めるようになる、ということで説明できるのではないかと思いますが、こういった超能力が身につくということもまた「臨死体験」の世界と符号しています。
いかがですか。「唯識仏教」の「心のモデル」で「念仏行」を見てみると、「臨死体験」の世界とうまく符合していることが、よく分ります。つまり、「念仏行」という「瞑想」で到達する世界は「臨死体験」と同じ世界だと考えられるということです。私たちは、「念仏行」によって、「臨死体験」で出会う「光の世界」と同じ「光の世界」に出会う事ができるのです。
皆さんはどう思われるか分かりませんが、さきほども申しましたように、私は、この「念仏行」で垣間見る世界は、「死後の世界」とつながっていると考えております。実は、そう考えているのは私だけではありません。1973年に「超伝導」の研究でノーベル物理学賞を受けたイギリスの物理学者ブライアン・ジョセフソン博士も同じことを考えているようです。
ジョセフソン博士は長年にわたって瞑想を続けていますが、あるインタビューに答える中で、こう言っています。「私は、現実には目に見えない精妙なレベルがあると確信しております。瞑想を通じてそのレベルに触れることもできますし、人が死んだ後に行くのもここではないかと考えています」と。私にとっては、なかなか心強い意見のように思えますね。
「光の世界」に触れた者は、本当の自分に出会うのです。そして、その人その人の本当の姿を生きることができるようになるのです。ある臨死体験者も言っていますが、「そうすることが正しいからそうするのではない」のです。「そうせずにはおれないからそうする」ようになるのです。「臨死体験者」だけでなく、信仰で「光」に触れた人も、やはりそうなるです。
皆さんは、1979年にノーベル平和賞を受けたマザーテレサという人をご存じでしょうか。彼女は12歳の時に、祈りのなかで「光」に触れました。そして、全世界の貧しい人々のために生涯を捧げることにしたのです。テレサは、「そうすることが正しいからそうしたのではなく、そうせずにはおれないからそうした」のです。彼女は現在84歳で、今なお、インドのカルカッタで活動しています。そんなテレサに触れる人は、そのなかに神の光を感じると言います。
「光」を浴びた者は、世界に慈悲の光を放ちます。ですが、それは、みんながマザーテレサのように福祉活動を始めるという意味ではありません。みんながピッチャーでは野球はできません。光り輝く看護婦も、光り輝く病人もいて、世界が輝くのです。一人一人が自分の生まれてきた目的を果たしていくこと、それが世界を照らす光となるのです。
さて、大分長い話になってしまいましたので、そろそろ、私たち「門徒の教え」に即して、今日のお話しをまとめて、締め括りたいと思います。
さて、伝統的に申しますと、「浄土の教えを聞いて、疑いなく信ずる」というのが浄土真宗の本筋です。ですが、この「信ずる」ということは極めて難しいのですね。『大無量寿経』にも、「この教えを聞いて信じ喜ぶということは、難中の難である。これより難しいことは他に無い」と書かれております。
「浄土の教えを聞いて、信を得る」というのは、「話を聞いただけで、光に触れる」ということですから、これはよほど機が熟していないと難しい。親鸞聖人は、法然上人から「浄土の教え」をお聞きになって、信を得られました。ですが、これは、親鸞聖人が、9歳から29歳まで20年間、比叡山で修行なさって、その機が熟していたからです。
法然上人は「瞑想」の達人でした。法然上人は「瞑想」のなかで「光の世界」を体験なさいました。このことは上人ご自身の書き残された『三昧発得記』という文書のなかに出てまいりますから、間違いありません。法然上人は、いわば今生で一度「浄土」への往生を遂げられたのです。親鸞聖人は、その法然上人から放たれている「光」に触れられたのです。
ですが、私たちにとっては、「光の世界」の方に顔を向けること、つまり「発心」を得ることさえ容易ではありません。「発心」は、生まれてきたことの意味、死んでいくことの意味、人生の意味を問うところから生じてきます。ところが私たちは、たいてい、「生まれてきたのだから、死ぬまで生きていくしかない」と考えているのです。これでは、なかなか「発心」とは結び付きません。仏教を学んでも、教養のひとつとして学んでいるようでは、さほど意味がありません。
私たち凡夫は、生まれてきたことの目的に目覚めておりません。ですから、「どうせ死ぬまで生きていかねばならないのなら、出来るだけ楽しく生きたい」という思いを抱くのです。そんな私たちの生き方は、「何とか人生をやりすごそう」としているようにも見えます。別の言葉で言えば、私たちは「生命の重さを持て余している」のです。
「生命を持て余している」から、常に刺激が欲しい。休みが二日も続くと、死ぬほど退屈になってイライラする。そこでテレビを見る。週刊誌を読む。買物に行く。ドライブに行く。映画に行く。ゴルフに行く。旅行に行く。カルチャーセンターに通う。常に何かをしていないとイライラする。そんなイライラを忘れるために何かをする。それが私たちの姿ではないでしょうか。
そんな私たちの人生は、川面に浮かぶ「うたかた」のようにはかないものだと、よく言われます。確かに、私たちの人生は、川面に浮かぶアブクのようにはかないものかもしれません。ですが、川面に浮かぶアブクをよくご覧になってくださいね。川面に浮かぶアブクは無から生まれて無に帰っていくわけではありません。川面のアブクは、川の流れから生まれて、その川の流れに帰っていくのです。
私たちの人生もこれと同じです。私たちは、無から生まれて無に帰っていくわけではないのです。私たちは「光の世界」から生まれて、「光の世界」に帰っていくのです。「一如の世界」から生まれて、「一如の世界」に帰っていくのです。私たちは、死んでも終わらない。死の扉の外には「光の世界」が広がっている。娑婆を超えたこの「光の世界」に心を引かれたとき、「発心を得た」と言うのです。
では、「発心」は得たが「信」を得られない、という私たち凡夫はどうすればよいのでしょうか。実は、そういう私たち凡夫のためにあるのが「念仏行」なんです。真宗には昔からこういう「道歌」が伝わっています。「信なくば、つとめて御名を、称うべし、御名より開く、信心の花」。この歌は、「浄土に往生するという確信が得られないのなら、一心にお念仏を称えなさい。お念仏を称える生活のなかから、自然に確信が得られるようになっていきますよ」という意味です。私たちは「信じられない」。ですが、信じられないからこそ、「お念仏」を称えるのです。
私たちの一生は、はかない「夢」のようなものかもしれません。ですが、「念仏行」によって「光」に会えば、この「夢」が、かけがえのない大切な「夢」であることに気づくのです。「光」に会えば、どうなるのか。親鸞上人は御和讃のなかで、こう詠んでおられます。「本願力にあひぬれば、むなしくすぐるひとぞなき…」。「本願力」とは「慈悲の光」のことです。ですから、この御和讃は、「慈悲の光に遇えば、誰もが充実した人生を送ることができる。生まれてきた目的を果たしていける」という意味です。
「充実した人生を送ることができる」というのは、「生命を持て余す」ことなく、「生命を味わうことができる」ということです。「生命を味わう」とは、「一如を生きる」ということでもあります。
私たち門徒は、互いに「同行」と呼んでいます。「同行」というのは、「浄土への道を一緒に歩む仲間」という意味です。私たちは、「浄土への里帰り」の旅仲間なのです。ですが、旅仲間は門徒だけではありません。「光の世界」は、人類全ての故郷なのです。ですから、世界中の人々が、全て「同行」なのです。
私たちには帰って往く「故郷」がある。私たちは「根なし草」ではない。そのことを、確信をもって思い出す道が、「念仏行」なのです。どうぞ、そういう「お念仏」を、生活のなかに取り戻して頂きたいと思います。
さて今回は、「死んでも終わりではない。その先には光の世界がある、浄土がある」というお話しをさせて頂きました。真宗では、たいていこの「浄土」の話までしか致しませんが、本来の仏教では、もう少し先のことまで説かれております。
そこで次回は、「浄土」から先の話として、「輪廻転生」のお話しをさせて頂くつもりでおります。次回は、春のお彼岸、3月21日でございます。また、どうぞお参りくださいませ。お待ち申し上げております。本日は、どうも、長い間お付き合い頂きまして、ありがとうございました。
◇ 参考文献 (文献の順序は日本での出版年度順です。)
- レイモンド・A・ムーディ・Jr.
『かいまみた死後の世界』、評論社、1977年
- モーリス・S・ローリングス
『死の扉の彼方』、第三文明社、1981年
- マイクル・B・セイボム
『「あの世」からの帰還』、日本教文社、1986年
- レイモンド・A・ムーディ・Jr.
『続 かいまみた死後の世界』、評論社、1989年
- レイモンド・A・ムーディ・Jr.
『光の彼方に』、TBSブリタニカ、1990年
- ブルース・グレイソン+チャールズ・P・フリン共編
『臨死体験』、春秋社、1991年
- カーリス・オシス+エルレンドゥール・ハラルドソン
『人は死ぬ時何を見るのか』、1991年、日本教文社
- カール・ベッカー
『死の体験』、法蔵館、1992年
- ジョージ・ギャラップ・Jr.
『死後の世界』、三笠書房、1992年
- 冨島一晃、『浄土物語』、PMC出版、1992年
- バーバラ・ハリス+ライオネル・バスコム
『バーバラ・ハリスの「臨死体験」』、講談社、1993年
- 中原保、『わたしの臨死体験』、文芸春秋、1993年
- メルヴィン・モース+ポール・ペリー
『臨死からの帰還』、徳間書店、1993年
- 立花隆、『臨死体験』(上・下)、文芸春秋、1994年
紫雲寺HPへ