前回の報恩講のおりには、「私たちは死んでも終わらない、死の扉の外には光の世界がある、浄土がある」というお話しをさせて頂きました。真宗ではたいてい、この「浄土」の話までしか致しませんが、本来の仏教では、もう少し先の話まで致します。そこで今回は、前回の続きということで、「業」と「輪廻転生」のお話しをさせて頂こうと思っております。
まず最初に、伝統的な仏教の考え方をご説明いたしておきたいと思います。本日お話し申し上げます私自身の考え方は、必ずしも、その伝統的な枠組みに従ってはおりませんが、これをご承知頂いたうえでお聞き頂かないとお分かりにくいと思いますので、まず、そのお話しから始めます。
ご承知のように、仏教では、「輪廻」というものを説いております。「輪廻」と申しますのは、実は仏教よりも古いインド古来の考え方でして、生命のある者が、車輪のめぐるように果てしなく生まれたり死んだりを繰り返すことを言います。
時代が下って仏教の誕生したころになりますと、ただ生まれ代わるだけでなく、善い行いをした者、つまり善業を積んだ者は「楽しみの多い世界」に、悪い行いをした者、つまり悪業を積んだ者は「苦しみの多い世界」に生まれ代わると考えられるようになります。その、生まれ代わる世界を、後の仏教徒は6つに分けて考え、「六道」とか「六趣」とか呼んでおります。
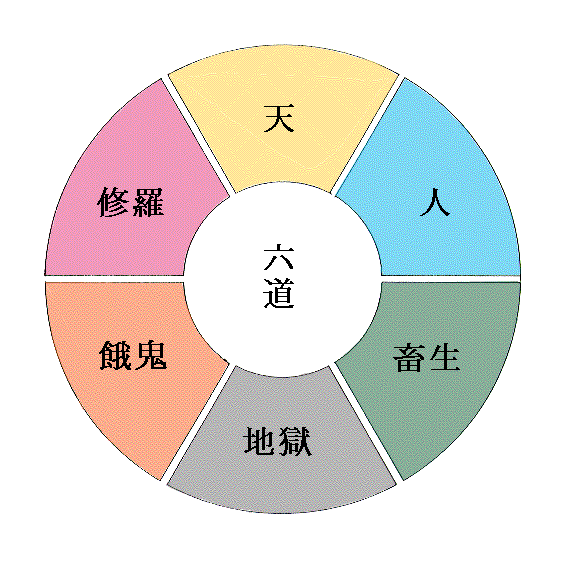 「六道」というのは、ここに示しましたように「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天」という6つの世界のことを言います。そして、この6つの世界を、自分の作った「業」に応じて果てしなく生まれ代わり死に代わりすることを、「六道輪廻」と呼んでいるわけです。ちなみに、「人間」から再び「人間」に生まれ代わることを「転生」と言って、「輪廻」と区別する場合もあります。
「六道」というのは、ここに示しましたように「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天」という6つの世界のことを言います。そして、この6つの世界を、自分の作った「業」に応じて果てしなく生まれ代わり死に代わりすることを、「六道輪廻」と呼んでいるわけです。ちなみに、「人間」から再び「人間」に生まれ代わることを「転生」と言って、「輪廻」と区別する場合もあります。
この6つの世界のどこに生まれ代わるかは、その人その人の「業」、つまり「行い」によって決まります。閻魔様が決めるわけでもありませんし、仏様が決めるわけでもありません。他の誰かが決めるわけではなくて、自分自身の「業」によって自然に決まるのです。つまりは「自業自得」です。
この「六道輪廻」の世界から抜け出すことを「解脱」と言います。「解脱」を得ると、もう二度と再び、この無常であり苦である迷いの世界に生まれることはないのです。つまり、仏教は、この苦しみの世界への「生まれ変わり」を永遠に終わらせるための教えなのです。以上が伝統的な仏教の考え方です。
しかし、科学の時代に生きております私たちにとっては、この「生まれ変わり」という考え方からして非常に馴染みにくいものなのですね。たいていの現代人は、「死ねば終わりだ」と思っておりますから、「生まれ変わり」などというものが本当にあるとは到底思えないのです。なかには、「生まれ変わりなどというのは坊さんの寝言だ」と思っておられる方もおられます。
たしかに、私たちは科学の時代に生きております。科学というものは、「五官で捕らえられないものは存在しない」とみなします。そういう基準をかかげて、つまり「五官という物差し」を振りかざして、科学は過去300年間、「死ねば終わりだ」と教え続けてきたのです。
しかしです。「五官で捕らえられないものは存在しない」と、どうして分かるのでしょうか。「五官を超えたもの」は「五官という物差し」では測れないのです。たとえば30センチの物差しで空気を測ることはできませんね。どうも、「五官で捕らえられないものは存在しない」というのは言い過ぎのような気がします。
本当は、「五官で捕らえられないものは存在しない」と「信じている」としか言えないのではないでしょうか。もし、「信じている」のだと言うのなら、科学も一種の信仰だということになってまいります。
ですが、どうやら、科学者がみな「輪廻転生など寝言だ」と考えているわけではないようです。それどころか最近の科学には、このままで行けば、遅かれ早かれ「輪廻転生」を認めてしまいそうな動きも見えるのです。まずはそういった、科学界の宗教革命ともいえる動きからお話しいたします。例によって、なかなか仏教の話になりませんが、しばらくお付き合い下さい。
「生まれ変わり」ということが欧米で真剣に考えられるようになってきたのは最近のことですが、東洋では昔から言われていることです。たとえばチベットでは、「前世の記憶」が残っている子供は7歳までに前世について話し始めると言われておりますし、また、チベット仏教の最高権威者である歴代のダライラマは子供の持っている「前世の記憶」によって選ばれております。
皆さんも、お聞きになったことがおありかと思いますが、最近、この「前世の記憶」というものが、かなり話題になっております。3歳から5歳くらいの子供たちが、ある日突然、「自分は、この前には、どこどこの町で、こんな生活をしていた」と、前世の記憶を語り始めて、周囲の人々が騒ぎだす。実は、そんなことが世界中で、けっこう頻繁に起こっているのですね。
そんなことが起こると、たいていは親が「そんな嘘を言ってはいけない」とこっぴどく叱って、子供を黙らせてしまうものですから、ウヤムヤになってしまいます。ですが、頑固に「前世の記憶」を話し続ける子供たちもいます。現在では、そういう子供たちを熱心に研究している学者が何人もいるのです。
なかでも有名なのは、アメリカのバージニア大学医学部、精神科主任教授のイアン・スティーブンソン博士です。博士は30年ほど前から、この研究に取り組んでいます。その間に、博士は、世界各地から集められた2千数百件もの生まれ変わりの事例を徹底的に調査して、その研究結果を次々に発表してきました。
スティーブンソン博士の研究の一部は、日本でも、『前世を記憶する子どもたち』という翻訳で出版されておりますので、関心をお持ちの方はご覧になってみてください。
その本によりますと、世界各地から集まってくる事例の99パーセントは科学的に見て疑問が残るが、残り1パーセントの事例については「生まれ変わり」が起っているとしか解釈のしようがない、という結論のようです。
また、「生まれ変わり」は、宗教や、文化や、人種や、教養や、経済状態の違いなどに関係なく、人類全体に普遍的に起こっていて、男性から女性へ、反対に女性から男性への「生まれ変わり」も頻繁に起こっているといいます。
こういったスティーブンソン博士の研究に対して、日本の専門家たちはあまり関心を示していないようですが、アメリカでは、『アメリカ医師会ジャーナル』という権威ある医学誌が、「こういった子供たちを理解するには、生まれ変わりというものが存在すると考える以外にない」、という内容の批評を載せるまでになっています。
「生まれ変わり」というものが存在するらしいということは、「前世の記憶」を持つ子供たちの研究からだけではなく、精神科で行なわれている「催眠療法」の分野でも分かってまいりました。
「催眠療法」というのは、心の病を治すのに催眠術を用いる治療法です。催眠術などと言いますと、何かうさんくさいもののように思われるかもしれませんが、これは現代医学でも立派に認められている技術なんですね。
この「催眠療法」のなかに、催眠術によって意識を過去に導き、心の病の原因になっている過去の出来事を思い出させるという治療法があります。心の奥に抑圧されている過去の苦しい出来事を思い出すと、その病が治ることがあるのですね。そういう目的で意識を過去へ戻す催眠を、特に「退行催眠」と呼んでいます。
私たちは自覚的には思い出せなくとも、過去に経験したことを何でも覚えているらしいのです。理由は分かりませんが、そういう忘れてしまったはずの過去の記憶が催眠中には思い出せるらしいのですね。
ある時、精神科の医師が「退行療法」で患者を治療していた時のことです。「さあ、10歳の頃に戻ってください。…5歳の頃に戻ってください。…3歳の頃に戻ってください」と、だんだん年令をさかのぼって行きまして、「さあ、では、もっと前に戻ってください」と指示したんですね。すると、驚いたことに、誕生以前の記憶にまで戻ってしまったのです。こんなふうにして始まったのが、「退行催眠」による「過去世」の研究です。
この「退行催眠」によって「過去世」にまで戻れるのは、「退行催眠」を受けた人の3%から5%くらいと言われておりますから、誰もが経験できることではないようです。ですが、この研究によって、人間に影響を与えているのは、遺伝と環境だけではないということが分かってきたのです。つまり、現在の問題の原因が「過去世」にあることもある。そういうことが分かってきたわけです。
「退行催眠」の研究で有名な学者には、カナダのトロント大学医学部、精神科主任教授のジョエル・ホイットン博士や、アメリカのマイアミ大学付属病院、精神科主任教授のブライアン・ワイス博士などがいます。そういった研究者の報告から、私たち仏教徒にとって興味深いところを少しだけご紹介いたしておきます。
まずは、私たちの「生まれ変わる」理由です。「退行催眠」の研究によると、私たちは魂の進化のために、目的を持って生まれてくるというのです。たとえば、今生では忍耐を学ぶとか、思いやりを学ぶとかいった目的を持って生まれてくる。そして、ひとつひとつ目的を達成しながら生まれ変わりを繰り返し、完全に学び終わったら、もう生まれ変ってこないというのですね。
この魂の進化のために自分で決めた目的を果たせなかった場合は、また生まれ変ってやりなおすことになる。ちょうど学校の単位を取るように、ダメだった単位は留年してやりなおす。そして、単位を取り終わったら、「輪廻転生」の世界から卒業するというわけです。
また、人生と人生の間には「光り輝く慈悲と智恵に満ちた中間世界」が在って、その「中間世界」で、私たちは次の人生で学ぶことを決め、両親や、職業や、人間関係といった、学ぶ環境をも選ぶというのです。
人は、この「中間世界」で過去の多くの生涯を回想して、次の人生で決着をつけることや罪滅ぼしをすることを選ぶと言われています。そのために、過去の生涯で、何らかの貸し借りのある人々のもとに生まれ変って行くらしいのです。つまり、過去世で縁のあった人々が、ほぼ時を同じくして生まれ変るというのですね。
たとえば、かつて無慈悲な父親だった人が、今生では息子に生まれ変って、自分の間違いを体験するとか、妙に気心の合う親友はかつての娘だった、とかいったことになるというわけです。私たちは、魂を向上させるため、過去の生涯で作った「業」に応じて、自ら選んで学ぶために生まれ変ってくるらしいのです。
ですが、生まれてくるということは、必ずしも楽しいことではなさそうです。ホイットン博士は「誕生の瞬間」を思い出した人のこんな報告を伝えています。「私は分娩室にいて、母とそのまわりにいる医師たちを見守っていました。進行中の全てのもののまわりを白い光がとりかこんでおり、私はこの光と一体でした。それから、『生まれてきますよ』という医師の声が聞こえました。自分は新しい身体と合体しなければならないということがわかりました。今生で生まれてくることには全く気が進みませんでした。光の一部でいるのがとても素敵だったからです」と。
「退行催眠」の研究者には、こういった「誕生の記憶」を専門に研究している学者もいます。アメリカの心理学者ディビッド・チェンバレン博士などがそうです。
チェンバレン博士の研究によりますと、私たちは、「退行催眠」など受けなくとも、ほぼ5歳頃までは、「生まれたときのこと」を憶えているらしいのです。この研究は、『誕生を記憶する子どもたち』という本になって出ておりますので、あるいはお読みになった方もおられるかと思います。
チェンバレン博士によりますと、話ができるようになる3歳前後の子どもに「生まれたとき」のことを尋ねると、たいていは答えてくれるというのです。たとえばですね、母親の子宮のなかでの体験だとか、出産のときの様子、あるいは、そのとき誰が傍にいて何を言ったか、というようなことまで話してくれる、というのですね。念のために、そういった子供たちの話を、親御さんに尋ねたり、病院の記録と照らし合わせてみると、みな本当だったと確認できたということです。
この本に刺激されて、日本でも、ソニー名誉会長の井深大(まさる)さんが主催する「幼児開発協会」や、クモン塾で有名な「公文教育研究会」が調査したところ、たしかにチェンバレン博士の言っているようなことが実際に起っていると分かったのですね。
これまで赤ちゃんは、脳が発達していないから考えたり記憶したりできないとか、言葉が理解できないとか、自分と他人が区別できないとか、まわりで起っていることが理解できないとか言われてきましたが、チェンバレン博士の研究によって、そういった考え方がすべて誤りだということが分かってきたのです。
胎児や新生児は、自分は人間であるというより、何でも知っている賢い「心」そのものだと意識していて、周囲の状況や人々の話の内容を全て理解しているらしいのです。ですが、未熟な肉体のせいで、何もできないことに苛立ちや失望を感じながら、次第にその新たな肉体に馴染んでしまうらしいのです。
たとえば、16歳のときに「退行催眠」で「誕生の記憶」を取り戻したリンダという少女は、こう語っています。「私は生まれたとき、既に自分は賢いと思っていましたし、実際に多くのことを知っていました。ですが、3歳までに、型にはまったつまらない少女に育ってしまいました。周囲の期待にそった馬鹿な子供になってしまったのです。ですから、これから生きなおして、もう一度賢くならねばならないのです」と。
「誕生の記憶」を研究するなかで、チェンバレン博士は、「心と脳は別のものだ」という結論にたどりつきました。そして博士は、人の誕生というものを、「魂が肉体に宿ることだ」と考えるようになったのです。
こういった「前世の記憶」や「退行催眠」による「過去世」の研究を額面どおりに受け取るのはどうかと思いますが、それでも、どうやら科学者たちも「生まれ変わりというものは、お伽話ではなさそうだ」と気づき始めたようではあります。
「退行催眠」の研究者たちの本を読んでおりますと、必ず「業」によって「輪廻転生する」という考え方に行き着きますので、まるで仏教の本を読んでいるような気がしますが、伝統的な仏教の考え方と異なる点も見られます。
「退行催眠」によって意識を過去へ過去へと戻して行くと、いくつもの「過去世」を通って、有史以前の自分や石器時代に洞窟で暮らしていた自分にまで戻るということもあるようです。そして、さらにどんどん時代をさかのぼると、ついには動物だった自分にまで戻ったという例もあるようなのです。しかしです。いったん人間に生まれた者が、また動物に生まれ変わったという例はひとつもないのです。
最初にお話し致しましたように、仏教では「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天」という6つの世界に生まれ変わると説かれています。ところが、「退行催眠」による研究では、今のところ、「地獄」や「餓鬼」や「畜生」や「修羅」に生まれ変わったという経験を持つ人はいないようなのですね。果たして私たちは、死後に「動物」に生まれ変わることがあるのでしょうか。
どうも、科学の時代に生きておりますと、坊さんまで理屈っぽくなっていけませんが、仏教の伝統的な「六道輪廻」説と科学の「進化論」を照らし合わせながら、この点をもう少し考えておきたいと思います。
私は、「生物」というものを、文字どおり「生命+物質」つまり「魂+肉体」だと考えておりますが、現代科学では「生物も結局は物質だ」と考えているようです。ですから、科学で言う「生物の進化」というものは、いわば物質としての「肉体の進化」を扱っているということになります。
一方、仏教の「六道」というのは瞑想体験から生まれたものでして、こちらは、いわば「魂の進化」を扱っているものと言えます。そこでひとつ、この二つの「進化論」を結びつけてお話ししてみたいと思います。と申しましても、これからお話しいたしますのは、仏教の側でも科学の側でも説いていない神話のような話ですので、どうぞお気楽にお聞き頂きたいと思います。
さて、私たちの住んでいる地球が誕生したのは、50億年ほど前だと考えられておりますが、その後ほぼ15億年間、地上に生物はおりませんでした。この、地上に生物がいなかった15億年間は、「生命」つまり「魂」にとっての「暗黒時代」だと言えます。この「暗黒時代」が「地獄」に相当します。
地球に生物が誕生したのは、今から35億年ほど前だと考えられております。私たち人間は約60兆の細胞で出来ていると言われていますが、最初に生まれた生物は、たった1個の細胞で出来た「単細胞生物」でした。
「単細胞生物」の生活は、ただひたすら「食べる」ことでした。際限なく「食べて、食べて」、エネルギーが余ると、つきたての餅を二つにちぎるような仕組みで分裂を繰り返し、無限に殖えていく。これが原始生物の生活だったわけです。この、ひたすら「食べる」ことに集中している段階が、「餓鬼」に相当します。
私たちの常識から言えば、「生きている」ということは「いずれ死ぬ」ということですが、こういった最も原始的な生物には、老化による「死」というものがありません。生存に適した環境にある限り、無限に分裂を繰り返して殖えていくだけで、死なないのです。つまり、「死」というものは、進化の過程で生物に付け加えられたものなのですね。
生物が「死ぬ」ようになったのは、「オスとメス」つまり「性」というものが出来たときだと考えられております。「オスとメス」というものが出来てから、子供を産んで親が死ぬという、私たちにお馴染みの仕組みになったわけですね。それは今から10億年ほど前のことだと言われております。
その後、何億年もかけて、生物は魚類、両棲類、爬虫類、哺乳類へと進化していき、最後に人類が登場します。この「性」というものが出来たことで「死」という現象が生まれてから「人類」が誕生するまでの段階が、「畜生」に相当します。
「畜生」と「人間」の違いは、「死の自覚」にあります。たしかに、人間以外の生物にも、たいてい「死」という現象はあります。ですが、そういった生物にとって「死」というものが「意味」を持つことはありません。たとえば、犬でも猫でも、みな「死ぬべき運命」にあるわけですが、犬や猫は「死」を自覚しているわけではない。夕日を眺めながら、生命の果なさに溜息をつく「犬」などというものは、どうも考えにくいのです。
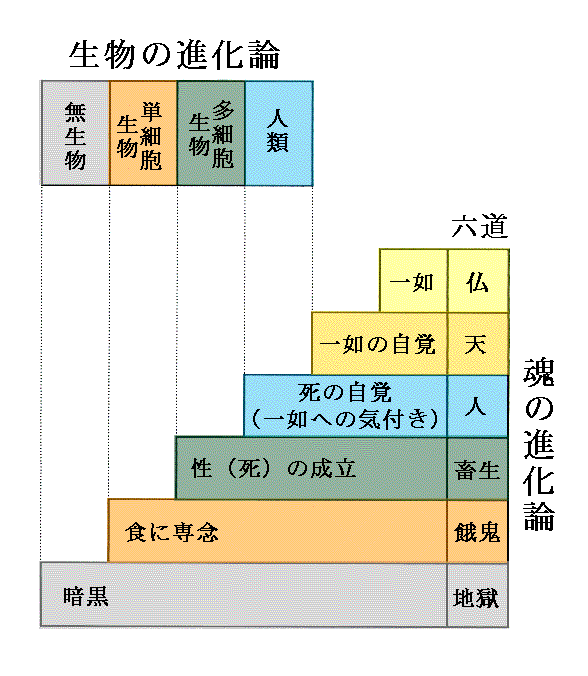 「死」を自覚的に見つめ、「生」の意味を問うことができる唯一の生命体、それが人類だと思います。別の言葉で言えば、進化の途中で付け加えられた「死」というものは、生物が人類にまで進化して、初めて「意味」を持ってきたということです。そういう意味では、「死」は人類のために準備されたものだと言えるかもしれませんね。
「死」を自覚的に見つめ、「生」の意味を問うことができる唯一の生命体、それが人類だと思います。別の言葉で言えば、進化の途中で付け加えられた「死」というものは、生物が人類にまで進化して、初めて「意味」を持ってきたということです。そういう意味では、「死」は人類のために準備されたものだと言えるかもしれませんね。
「死」を自覚したことで、人類は何を得たのか。人類は「死」を自覚することで、「宇宙永遠の真理」つまり「一如」への気づきを得たのです。この「一如」への気づきから生まれたものが、宗教です。
「宗教」というのは、もともとの日本語ではありませんで、明治時代に英語の「レ=リジョン」という言葉を翻訳するために考えだされたものです。「レ=リジョン」というのは「再び結び付ける」という意味です。宗教とは、本来、私たちの「魂」と「一如」との、結び付きの回復をめざすものなのです。生命が何十億年もかけて人類にまで進化してきた目的も、この「一如への回帰」にあると、私は思います。
ちなみに、単細胞生物から人類が誕生するまでの、この35億年の「進化の歴史」を、私たちは何度もおさらいするように繰り返しながら成長していきます。
たとえば、人の卵子は、受精後しばらくは単細胞生物のように分裂を繰り返して成長していきます。そして、受精後32日目から約1週間のあいだに、魚類、両棲類、爬虫類、原始哺乳類と、生物の進化のあとをたどるように姿を変えながら、人間の形になっていくのです。これはまさに「進化」の過程の再現ですね。
誕生してからも、よく似た繰り返しが見られます。誕生すると、子供は、しばらくの間に「光の世界」の記憶を無くし、「食べて育つ」ことが仕事になります。成長期の子供は、食べても食べても、すぐにお腹がすいてくる。ですから、この時期の子供を「ガキ」と言うのですね。
その後、子供はどんどん成長して、8歳〜12歳頃に思春期を迎え、「性」に目覚め始めます。実は、この8歳〜12歳というのは、ちょうど子供が「死」を恐れ始める時期と重なっているのですね。心理学者は、「多感な思春期に死への恐れが芽生える」と、「死への恐れ」を「多感」のせいにしておりますが、そうではなくて、これはまさに、「性」の出現によって「死」が生まれたという進化の流れに呼応しているのだと思いますね。
また、人間の脳は、奥から外側に、順次、「爬虫類の脳」、「原始哺乳類の脳」、「新哺乳類の脳」というように三つの層から成っていて、ここにも進化の過程の繰り返しが見られます。
さて、科学の世界でいう「生物の進化論」は、この「人類」の登場で終わります。人類が登場して幕を閉じるというシナリオは、地球の将来を暗示しているようで、どうも穏やかでありませんが、仏教の側の「魂の進化論」では、「人間」の次の段階として、「天」というものを説いております。
インドの言葉では「天」を「デーバ」と言います。「デーバ」とは、「光り輝くもの」という意味です。「人間」と「天」との違いは、「一如の自覚」にあると思います。
伝統的な仏教では、「天は自分の欲望が充たされる場所だ」と説かれていますが、「六道」というのは、欲望充足の段階ではなく、魂の成長の段階なのですから、そういう考え方は間違いだと思いますね。
お釈迦さまも「トソツ天」という「天」から「人間界」に生まれてこられたと言われております。また、弥勒菩薩の浄土もこの「トソツ天」にあると言われております。私は、「天」というのは「一如の自覚」を得るところ、「自分の魂の目的」を明らかに知るところだと思います。
伝統的な仏教の話を聞いてこられた方々は、「六道」というものを、「死後に行く、どこか別の世界だ」とか、あるいは「私たち人間の様々な心の状態を説明したものだ」とお考えになっているかと思います。また、現代科学を信仰しておられる方々の目には、「六道輪廻」など、「ただのお伽話」のように映っているかもしれません。ですが、「六道輪廻」というのは、闇から光りへの「魂の進化」の流れを表わしたものなのです。
これがひとつの「流れ」であるかぎり、「後戻りはできない」と考えるのが自然だと思いますね。たとえば、皆さんが、家で飼っておられる犬や猫をご覧になって、その犬や猫が、「魂の進化の流れ」をさかのぼって「地獄」に生まれ変わる可能性を持っているとお考えになるでしょうか。私も犬を飼っておりますが、到底、そうは思えませんね。私は、この「魂の進化の流れ」をさかのぼることはないと思っています。つまり、私たち人間は、「地獄」や「餓鬼」や「畜生」に生まれ変わることはない、ということです。
ですが、「人間が地獄に生まれ変わることは無い」などと申しますと、かえって納得なさらない方もおられます。たしかに、実際には、人間世界を見渡してみますと、「絶対地獄に行くに違いない」と思えるような人々もいますよね。ですがね。そういった人々を、自分の心に渦巻く「恐れや、恨みや、憎しみや、嫉み」の思いを離れて、もう一度静かに眺めてみますとね、だんだん、そうは思えなくなってくる。違いますかね?
私たちは、誰かに「恐れや、恨みや、憎しみや、嫉み」の感情をいだいて苦しむと、相手にも同じだけの苦しみを与えて「罰して」やりたくなるのですね。有名な「目には目を」という言葉には、そういった私たちの感情が反映されているのです。人に「地獄行きの切符」を押しつけようとしているのは、誰かを「地獄に押し込もう」としているのは、そんな私たちの心のなかに渦巻く暗い感情でしかありません。
しかし、「六道輪廻」は「魂の進化の流れ」を表わしたものであって、この流れをさかのぼることはない、と申しましても、ちょっとお分りにくいかと思いますので、目に見える「たとえ」を使って、もう一度ご説明いたしたいと思います。
さきほど、「生物」というものは「魂+肉体」で出来ていると申しましたが、もう少し正確に申しますと、私は「魂」が「肉体」を生み出すと考えております。そう考えている理由につきましては、いずれ別の機会にお話し申し上げますので、今回はひとまず、「魂」が「肉体」を生み出すという前提で、お話しいたします。
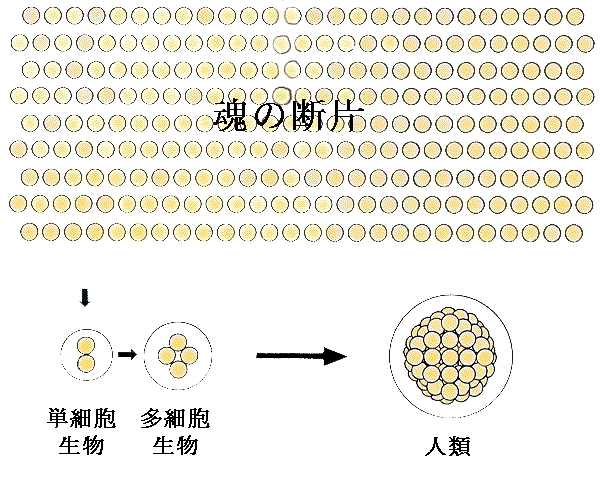 さて、ご覧になりにくいかもしれませんが、ここには小さな円が沢山描いてあります。このひとつひとつの円が「魂の断片」だとお考えください。この、バラバラになった「魂の断片」には、ひとつの方向を持った「流れ」があります。それは、バラバラだったものが徐々にくっついて、「ひとつに成っていく」という流れです。つまりは、「一如をめざす流れ」です。
さて、ご覧になりにくいかもしれませんが、ここには小さな円が沢山描いてあります。このひとつひとつの円が「魂の断片」だとお考えください。この、バラバラになった「魂の断片」には、ひとつの方向を持った「流れ」があります。それは、バラバラだったものが徐々にくっついて、「ひとつに成っていく」という流れです。つまりは、「一如をめざす流れ」です。
では、物語を始めます。まず、地球が誕生して15億年ほどたったとき、二つの「魂の断片」がくっついて、「肉体」を生み出しました。これが「単細胞生物」です。
それから更に25億年ほどたった時、この二つの「魂の断片」に、更に二つの「魂の断片」がくっついて、オスとメスの「性」を持った「多細胞生物」を生み出しました。この「性」というものの出現によって、「死」という現象が生じたわけです。
その後、更に「魂の断片」が雪だるま式にくっついて行き、結び付いた「魂の断片」の数に応じて、様々な形態の生物が生まれ、科学で言う「生物の進化」が進んで行きます。
そして、「魂の断片」が沢山集まって、これだけの固まりになりました。これだけの「魂の固まり」が生み出す「肉体」が人間なのです。たとえば、私たちが体のサイズに合わせて洋服を作るように、「魂」は、その大きさに合わせて「肉体」を生み出すのです。
言葉を変えて申しますと、これだけの大きさになった「魂の固まり」は、人間という「肉体」にしか収まらないということです。別の「たとえ」で申しますと、大人にまで成長すると、もう小学生の頃の洋服には収まらないようなものです。
もう、お分りかと思いますが、私たち「人間」にまで成長した「魂」は、「犬」や「猫」といった動物の肉体には収まりきらないということです。ましてや、「単細胞生物」の肉体には収まるはずもありません。
かくして、「六道輪廻」を、一定の方向を持った「魂の進化の流れ」と見るかぎり、私たち「人間」は、その流れをさかのぼって「地獄」や「餓鬼」や「畜生」に生まれ変わることはない、と考えるのが自然なのですね。
「輪廻」の流れは、魂の成長の流れです。バラバラだった魂の断片が、だんだんとひとつにまとまっていく流れなのです。ですがこの魂の断片は、ジグソーパズルの断片ではありません。ひとつひとつの魂の断片は「一如」の断片なのです。ひとつひとつの魂が「宇宙永遠の真理」そのものなのです。ですが、断片が小さいと、「一如」の姿が鮮明に現われてはこないのです。ですから、人間の大きさにまで成長しないと「一如」への気付きが生まれてこないのだと思います。
このことは「ホログラフ」という立体写真に似ています。ホログラフというのはレーザー光線で写した立体写真ですが、この写真のネガには不思議な性質があるのです。普通の写真ですと、ネガを小さく切り分けて現像すると、それぞれのネガに写っていた部分の映像しかプリントされません。ですが、ホログラフのネガですと、どの断片にも被写体の全体像が写っているのです。
たとえば、花瓶に生けたバラの花を写真にとったとしますね。普通の写真のネガをバラバラにして現像すると、花瓶の一部が写っているものや、バラの一部が写っているようなプリントができあがります。つまり、バラバラにされたネガには、それぞれ全体の一部分しか写っていないということです。全体像を知ろうと思えば、全体の断片をくっつけて、もとの1枚のネガに戻さねばなりません。
ところが、ホログラフのネガですと、どの断片にも花瓶に生けたバラの花が写っているのです。ただ、断片が小さくなるほど映像がぼやけて、鮮明には見えなくなってしまいます。魂の断片もこれと同じではないかと思います。魂の断片が集まって人間を生み出す大きさにまで成長したとき、初めて「一如」の姿が見え始めたのだと思いますね。
さて、日常生活からかけはなれた、それこそ神話のようなお話しを、長々と致してまいりましたが、実は、ここまでが本日お話し申し上げたいことの「まえおき」です。いわば、本日のお料理の「したごしらえ」というわけです。
この「したごしらえ」として二つのお話しを致しました。まず一つ目は、「生まれ変わり」というのはお伽話ではないということです。そして二つ目は、私たち人間は、「地獄」や「餓鬼」や「畜生」には生まれ変わらない、ということです。
お聞き頂いて、あるいはですね、「死ねば終わりだ」という科学の伝統的な考え方と、「六道を輪廻する」という仏教の伝統的な考え方との、両方に楯突いたような話に思われたかもしれませんが、私は、これこそ「浄土の教え」の本筋につながる考え方だと信じております。
それでは、「浄土の教え」のなかで、「業」と「輪廻転生」というものの意味を考えてみようと思います。
「浄土の教え」では、私たちは「お念仏」によって「浄土」に往生すると説かれております。真宗では、この「浄土への往生」に重点をおいておりますから、たいてい「浄土」の話までしかいたしません。ですからご門徒の方々も、そこから先のことはお考えになっておられないかもしれませんね。
ですが、「浄土」に生まれ変わればそれでおしまいかというと、そうではないのです。「浄土の教え」では、私たちは「浄土」からまたこの人間世界に生まれ変わってくると説かれているのです。つまり、「輪廻」があるということですね。
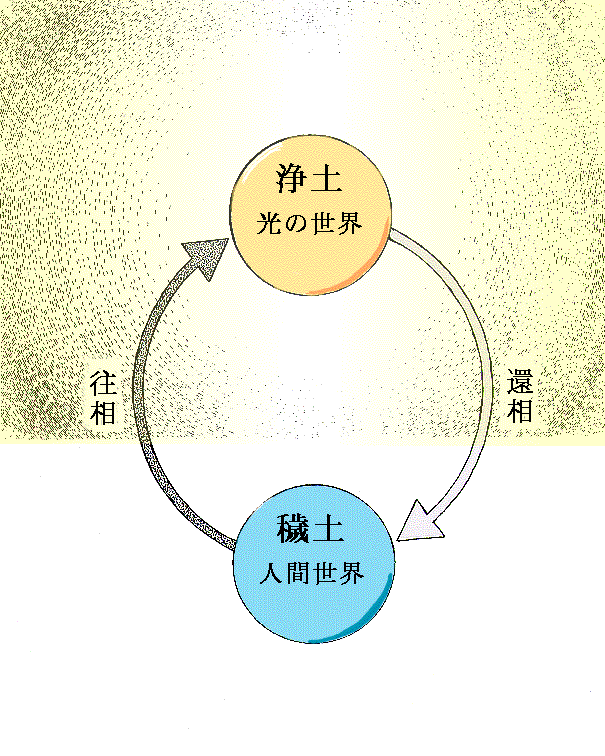 と言いましても、「浄土の教え」で説かれている「輪廻」は、「六道輪廻」ではありません。「浄土の教え」で説かれているのは、「人間世界」と「浄土」という、この二つの世界の間で繰り返される「輪廻」なのです。「人間世界」から「浄土」に生まれることを「往相」と言い、「浄土」から「人間世界」に生まれることを「還相」と言いますが、今回はこの「往相、還相」という言葉を使わずにお話し致します。
と言いましても、「浄土の教え」で説かれている「輪廻」は、「六道輪廻」ではありません。「浄土の教え」で説かれているのは、「人間世界」と「浄土」という、この二つの世界の間で繰り返される「輪廻」なのです。「人間世界」から「浄土」に生まれることを「往相」と言い、「浄土」から「人間世界」に生まれることを「還相」と言いますが、今回はこの「往相、還相」という言葉を使わずにお話し致します。
さて、「六道輪廻」と、「浄土の教え」での「輪廻」の違いは、いわば「閉じている」か「開いている」かというところにあります。「六道輪廻」は「六道」という迷いの世界に閉じ篭められた「輪廻」ですが、「浄土の教え」で説かれている「輪廻」は、「人間世界」と「浄土」という二つの世界で生まれ変わりを繰り返しながら、「一如」へと導かれていく、螺旋状に開いたシステムなのです。
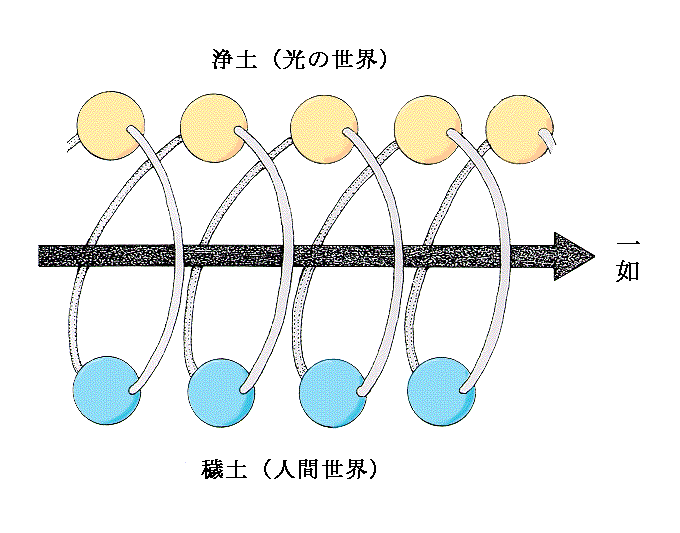 「六道輪廻」の考え方では、「今生で善い行いをすれば幸せな境遇に生まれ変わり、悪い行いをすれば不幸せな境遇に生まれ変わる」と言われています。ところが、経典には、悟った人というのは、「善と悪とを捨てて目覚めた人」だと説かれているのです。つまり、「善悪の世界」は「迷いの世界」だということです。
「六道輪廻」の考え方では、「今生で善い行いをすれば幸せな境遇に生まれ変わり、悪い行いをすれば不幸せな境遇に生まれ変わる」と言われています。ところが、経典には、悟った人というのは、「善と悪とを捨てて目覚めた人」だと説かれているのです。つまり、「善悪の世界」は「迷いの世界」だということです。
ということはです。善悪を基準にしている「六道輪廻」の考え方では、結局のところ、善悪どちらにしても、またまた「六道」という迷いの世界のなかに生まれ変わるということになるのですね。さきほど、「六道輪廻」は「六道」という迷いの世界に閉じ篭められた「輪廻」だと申しましたのは、そういう意味です。
もともと、この「今生で善い行いをすれば幸せな境遇に生まれ変わり、悪い行いをすれば不幸せな境遇に生まれ変わる」という考え方そのものが妙なのです。素直に考えれば、「今生で善い行いをすれば来世で善人に生まれ、悪い行いをすれば悪人に生まれる」となるはずですね。どうして、そうは言わなかったのでしょうか。実は、言わなかったのは言いたくなかったからなのです。
昔の仏教徒が言いたくなかった言葉を補ってみますと、こうなります。「今生で善い行いをすれば、『ごほうび』として幸せな境遇に生まれ変わり、悪い行いをすれば、『おしおき』として不幸せな境遇に生まれ変わる」。こうなのです。こうなのですが、これでは絶対者が支配する「賞罰のシステム」になってしまいます。仏教では絶対者というものを認めておりません。それが分かっているからこそ、この「ごほうび」と「おしおき」という言葉を「伏せ字」にしたのだと思います。
ここには、「善人には幸せを、悪人には不幸せを与えたい」という、私たちの倫理的感情が反映しています。私たちには自他を区別する煩悩がありますので、すぐに他人を裁く絶対者になってしまいます。「六道輪廻」というのは、「宇宙永遠の真理」などではなく、そんな私たちの煩悩が考えだした「賞罰のシステム」なのです。
「六道輪廻」という考え方には「出口」がありません。それは、「輪廻」というものを間違って考えているからです。「輪廻」というのはインドの言葉で「サンサーラ」といいます。「サンサーラ」というのは「流れ」という意味です。「流れ」というものは、川の流れのように必ず一つの方向を持っています。途中でどんなに曲がりくねっていようとも、「自然の力」によって、必ず川は高きから低きに流れるのです。逆向きに流れることは決してないのです。
「六道輪廻」を説いた人々は、流れは「自然の力」で動いているということを忘れて、「善悪の業」という人間の力で動いていると考えたのですね。「輪廻」の輪を回しているのは「善悪の業」という「自力」ではありません。「輪廻」の輪を回しているのは「自然の力」、つまり「他力」なのです。本当の「輪廻」は、まさに「他力のシステム」なのです。
前回にもお話し致しましたように、私たちはみな「光の世界」に帰って行くのです。私たちの死後には、「地獄」や「餓鬼」や「畜生」の世界はありません。私たちは、「人間世界」と「光の世界」という二つの世界の間で「輪廻」を繰り返しているのです。
「神は、紆余曲折のなかにも、必ず真っすぐな筋を通しておられる」という言葉があります。神と言おうと、仏と言おうと、結局は同じことです。私たちは、「自然の力」で動いている大きな生命の流れのなかにいるのです。そしてこの流れは、「一如」という大海へと続いているのです。つまり、この「輪廻」という「他力のシステム」は、私たちを「一如」の大海へと流し込もうとしている「慈悲のシステム」なのですね。
とは申しましても、善悪や喜怒哀楽の渦巻く「人間世界」に生まれてきた私たちには、「輪廻」が「慈悲のシステム」だとはとても思えないのですね。
私たちはみな、それぞれに違った境遇に生まれてまいります。経済的にも社会的にも恵まれた家庭に生まれてくる人もいれば、そうでない人もいる。健康な人もいれば、病弱な人もいる。才能に恵まれた人も、そうでない人もいる。私たちは、あらゆる点でみんな異なっているのです。
私たちは、人間関係に悩むこともあれば、経済的に苦しむこともあります。また、悪どい人が豊かな生活を楽しんでいることもあれば、心優しい人が貧しさにあえいでいることもあるのです。こんな世界に「慈悲」が働いているとは到底思えない。これは、どなたも疑問に思われることだと思います。
伝統的な仏教では、こういった人生の様々な矛盾に「六道輪廻」と「自業自得」という考え方で答えようとしてきました。ですが、すでに私は「六道輪廻」と「自業自得」という考え方は間違いだとお話し致しました。では、この疑問にどう答えるのか。
私は、この疑問に、「浄土の教え」から答えたいと思います。私たちが普通、「浄土に往生する」と言っておりますのは、死後に「光の世界」に帰って行くことです。ですが、「往生」というのは、これだけではないのです。「往生」には、もうひとつあるのです。それは「今生での往生」です。生きている間に「光の世界」につながること、つまり「廻心」を得ることです。私たちにとって大切なのは、こちらの「往生」の方なのです。そこで、「浄土の教え」の核になっているこの「廻心」を中心にお話し致します。
私たちは、「浄土」という「光の世界」から生まれてきたのです。「光の世界」は、私たちの魂が慈悲によって「癒され」、智恵によって「学びを得る」ところです。前世の善業や悪業で傷ついた魂は、「浄土」の慈悲の光のなかで癒されたはずです。ですから、私たちは前世の過ちを「つぐなう」ために生まれてきたのではないのです。私たちは「光の世界」で学んだことを「実践する」ために生まれてきたのです。
「光の世界」は魂の「癒し」と「学び」の場所で、「実践」の場所ではありません。「学び」は「実践」を通してしか実現されません。「実践」するには、「実践の場」つまり「人間世界」へ生まれるしかないのです。
私たちが「光の世界」で学んだこと。それは、「あらゆる魂は、一如をめざす旅仲間、つまり同行だ」ということです。人間だけでなく、虫も魚も、犬も猫も、花も草木も、あらゆる魂は「輪廻」を繰り返すなかで成長し、ついには一如へと帰って行く仲間だということです。仏教で言う「一切衆生悉有仏性」とは、このことです。私たちは、この「学び」を実践するために生まれてきたのです。
私たちの「魂の最終目標」は、あらゆる魂と結び付き、融け合ってひとつになること、つまり「一如」になることです。「自他の区別を離れて、他の魂と融和すること」。そのために、私たちは生まれてきたのです。このことを私たちに思い出させようとしているのが「浄土の教え」なのです。
私たちはみな、目的を持って生まれてきたのです。ですが、さきほど「誕生の記憶」という話で触れましたように、私たちは、誕生してしばらくの間に、新しい未熟な肉体に馴染む過程で、その目的を思い出せなくなってしまうのです。その思い出せなくなった記憶が、「浄土」の懐かしい光を浴びることで蘇るのです。頭にではなく、心に蘇るのです。それが「廻心」です。
「廻心」を得ると、人生の様々な矛盾に対する「疑問」そのものが消えてしまいます。そして、全てはこの「廻心」のためのお膳立てだったと気づくのです。あの苦しかったことも、つらかったことも、喜びも悲しみも、善も悪も、そのどのひとつが欠けても今の「廻心」は得られなかった。そのとき初めて、全てが私を「廻心」に導くための「慈悲」だったと感得できるのです。
「廻心」を得たときに、全ての疑問が氷解し、消えて無くなる。これが「浄土の教え」から得られる答えです。逆に言えば、「廻心」を得るまでは、人生の本当の意味に気づけないということです。
私たちは「廻心」を得るために生まれてきたのです。私たちに「廻心」を得る機会を何度も何度も与えながら、私たちが「廻心」を得る日をいつまでも待ってくれているもの。それが「輪廻」という「慈悲のシステム」なのです。
「廻心」を得ると、死んでも終わらない魂の流れに気づきます。親鸞聖人の御師匠様である法然上人は建暦二年(1212)正月25日に80歳でお亡くなりになりましたが、そのときのこととして、こういう話が伝わっております。病の床に就かれた法然上人に一人の弟子がこう尋ねました。「お師匠さまは、極楽に往生なさるのでしょうか」と。すると法然上人は、「私は極楽浄土からこの世に来たのだから、きっと極楽浄土へ帰って行くだろう」とお応えになった、というのですね。
この場面を、親鸞聖人は高僧和讃で、こう詠んでおられます。「命終その期ちかづきて、本師源空のたまはく、往生みたびになりぬるに、このたびことにとげやすし」。つまりですね、臨終の時が近付いた法然上人は、「浄土へ往生するのはこれで三度目になったが、このたびの往生は殊に遂げやすい」とおっしゃった、ということですね。
大切なのは、この「みたびの往生」というところです。真宗教学では、一度目の往生をインドでの往生、二度目の往生を中国での往生、三度目の往生を日本での往生と、仏教が伝わってきた道筋に合わせて考えておりますが、そうではないと思いますね。
私は、この「みたびの往生」のうち、二度目の往生は「今生での往生」、つまり「廻心」のことだと考えております。法然上人は、この「廻心」という「今生での往生」を得られたとき、初めて、ご自身が「浄土から生まれて、浄土に帰って行く身である」ということに気づかれたのだと思います。つまり、一度目と三度目の往生は、二度目の往生によって自覚されたものだということです。
前回にもお話し致しましたが、法然上人は瞑想のなかで「浄土」に往生され、「慈悲の光」に触れられました。この光は臨死体験者が触れた光と同じものです。光に触れた臨死体験者は死を恐れなくなります。死ねばまたその「光の世界」に帰って行くことを知ったからです。これが「廻心」です。「廻心」というのは、自分が帰って行く「光の世界」の存在を確信することなのです。
「廻心」を得ると、どうなるのか。光に触れた臨死体験者は、どうなったでしょうか。光に触れた臨死体験者は、本当の自分に出会い、その人その人の本当の姿を生きることができるようになったのです。「そうすることが正しいからそうするのではない、そうせずにはおれないからそうする」。そういう生命の流れにそった生活が自然にできるようになったのです。私たちは「廻心」を得て初めて、生命の真実に目覚めるのです。生まれてきた目的を思い出すのです。そして、「生まれてきてよかった」と心から喜べるようになるのです。
ですが、こういうことは頭で知ってもダメなのですね。私たちの頭は、「自他の区別を離れて、他の魂と融和する」と聞くと、「自他を区別してはいけないのだ、他の人々と仲良くしなければいけないのだ」というふうに、倫理的に解釈してしまいます。
「〜してはいけない」とか「〜しなければいけない」というのは、私たちの「努力」を要求する言葉です。「努力」とは「自力」のことです。この間もお話し致しましたように、「自力」というのは「自分の力」という意味ですから、自他の区別を前提にして初めて成り立つものなのです。「自力」というのは、他人と区別された「自分」の利益をはかるための力なのです。
ですから、「自他の区別を離れる」ということは、もともと「自力」では、つまり「努力」ではできないことなのです。「自他の区別を離れる」というのは、「自力」が沈黙したときに自ずと「あらわ」になってくる「他力」の働きなのです。
右手で右手をたたくことができないように、「自力」で「自力」を沈黙させることはできません。「自力」を沈黙させるには、「お念仏」という「他力」が必要なのです。静かなところに座り、そっと目を閉じ、「お念仏」を称えて一心になれば、自然に「自力」が沈黙して、「廻心」への道が開けてまいります。この「お念仏」という「他力」の働きを説いているのが、「浄土の教え」なのです。
私たちはみんな、「一如」をめざす「他力」の流れのなかにおります。「一如」をめざす者を、仏教では「菩薩」と呼んでおります。自覚はしておりませんが、私たちはみんな「菩薩」なのです。私たちは、「浄土の光」を浴びて「廻心」を得ると、初めて、全ての生き物がみな「菩薩」であったことに気づくのです。
人間だけでなく、虫も魚も、犬も猫も、花も草木も、あらゆる魂は、みな「菩薩」だった。そう気づいたとき、何の努力もなく自他の区別が消え去って、あらゆる魂への共感と慈しみに輝く「光の世界」が開けてくるのです。「廻心」を得たあとの世界は、そのまま「浄土」につながっているのです。そして、そんな世界への扉を開ける鍵が、「お念仏」なのです。
さて、本日お話し申しあげたかったことは、これでおしまいです。おそらく、お気づきのことと思いますが、最初に「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天」という「六道」の話をしながら、結局「修羅」については全く触れずにまいりました。
「修羅」というのは「戦いを好み、戦い続ける生き物」のことです。「修羅」とは「動物」のことではありません。「修羅」とは、実は、私たち「人類」のことなのです。
人類は戦う生き物です。だからこそ、人類は地球の王様のようになれたのかもしれません。ですが、それはまた同時に、人類を、より大きなものに向かわせない理由でもあるのです。私たちの多くは、死を自覚しながらも、一如への気づきに欠けています。これが「修羅」なのです。
人間の脳は約140億の細胞から成っていると言われています。ところが実際には、平均的にみて、そのうちの3%しか使われていないのだそうです。もしそうなら、私たちは、まだ「人間」になりきっていないということなのかもしれません。人間を超えるためには、まず人間になりきらねばなりません。
人間になりきる。それは、修羅を離れるということです。私たちが本当の人間になるために、次回は、この「修羅を離れる」というテーマで、お話しをさせていただこうと思っておりす。
次回は9月23日の永代経法要でございます。また、どうぞお参り下さいませ。お待ち申し上げております。本日は、どうも長い間お付き合いくださいまして、有難うございました。
◇参考文献 (文献の順序は日本での出版年度順です。)
- 笠原敏雄編・著
『死後の生存の科学』、1984年、叢文社
- J・L・ホイットン、J・フィッシャー
『輪廻転生』、1989年、人文書院
- イアン・スティーブンソン
『前世を記憶する子どもたち』、1990年、日本教文社
- Z・リッチモンド、K・リッチモンド
『死後生存の証拠』、1990年、技術出版
- ディビッド・チェンバレン
『誕生を記憶する子どもたち』、1991年、春秋社
- ブライアン・L・ワイス
『前世療法』、1991年、PHP研究所
- 片桐すみ子編・訳
『輪廻体験』、1991年、人文書院
- ラリー・ドッシー
『魂の再発見』、1992年、春秋社
- 春秋社編集部編
『誕生の記憶』、1992年、春秋社
- ピーター&メアリー・ハリソン
『前世を忘れない子供たち』、1992年、徳間書店
- ゲイリー・ドーア編
『死を超えて生きるもの』、1993年、春秋社
- ロイ・リッジウエイ
『子宮の記憶はよみがえる』、1993年、めるくまーる
- ブライアン・L・ワイス
『前世療法・2』、1993年、PHP研究所
- サトワント・パスリチャ
『生まれかわりの研究』、1994年、日本教文社
- レイモンド・ムーディー、ポール・ペリー
『死者との再会』、1994年、同朋舎出版
- イアン・スティーブンソン
『前世の言葉を話す人々』、1995年、春秋社
紫雲寺HPへ