前回の春のお彼岸と、その前の報恩講と、2回続けて、「私たちは死んだらどうなるのか」という、「死の先にある世界」のお話しをさせて頂きましたので、今回は、私たちの現実世界に話を戻しまして、「修羅を離れる」というテーマで、お話しさせて頂こうと思います。
前回のお話しの最後に申しましたように、「修羅」というのは「戦いを好み、戦い続ける生き物」、つまり私たち人類のことです。
私たち人類が「修羅」であることは、歴史を見ればよく分かります。皆さんも学校で歴史を学ばれたと思いますが、日本であれ世界であれ、人類の歴史は、実に「戦い」の歴史なんですね。今も世界中で戦争が起っています。世界から戦争が無くならないのは、私たちが「修羅」だからです。
ですが、私たちはたいてい、自分が「修羅」だとは思っていません。「戦いを好む」などと、とんでもない。私たちは、心から「平和を願っている」のです。そう思っておられるでしょう。しかしです、私たちは「平和を願う」と口では言っておりますが、もしも、どこかに平和を願っていない人がいると聞けば、どうなるでしょうか。
「平和を願っていないなどと、とんでもない奴だ。そういう奴がいるから、世の中が少しも平和にならんのだ。平和を乱す悪党はゆるせん。ひねくれた根性を叩き直してやる。つかまえてこい。やっつけてしまえ」ということになりはしないでしょうか。
このあいだのフランスの核実験再開の場合でもそうでしたね。核実験に反対する一部の人たちが、パプア空港を焼き討ちしたり、フランスの列車に爆弾をしかけたりしたのは、ご存じだと思います。
そこまで極端なことはしないにしても、「自分は正しい。悪いのはあいつだ。あいつがいるから悪いんだ。悪い奴はつぶしてしまえ」というのが私たちではないでしょうか。私たちがみんな「修羅」だというのは、そういうことなのです。
以前にもお話し致しましたように、あらゆる問題の根本は、「心」にあるのです。戦争反対を叫ぶ「心」も、実は、戦争という名の「修羅」の都と陸続きになっているのです。戦争反対を叫ぶことが「修羅を離れる」ことではありません。敵対する思い、自他を区別する思いを離れることが、「修羅を離れる」ということなのです。
今回は戦争についてお話ししようというわけではありません。今回は、「修羅」というものを私たちの心の問題として、ご一緒に考えてみたいと思っております。どうぞ、しばらくの間、お付き合いください。
さて、まずは前回のお話しの続きから始めたいと思います。前回の続きで申しますと、「修羅を離れる」というのは、「魂の進化の路をたどる」ということです。
いきなり「魂の進化の路をたどる」などと申しましても、前回は半年も前でしたから、もうお忘れかもしれませんので、少し前回のお話しに戻ります。ちょっと、こちらの図をご覧ください。
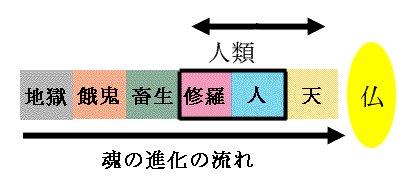 地球の生命は何十億年もかけて人類にまで進化してまいりました。これを仏教の「魂の進化論」で見てみますと、私たち人類は、この図の左から右へ「餓鬼、畜生、人」と三段階進んだところまで来ているわけです。畜生と人の違いは「死の自覚」にあります。
地球の生命は何十億年もかけて人類にまで進化してまいりました。これを仏教の「魂の進化論」で見てみますと、私たち人類は、この図の左から右へ「餓鬼、畜生、人」と三段階進んだところまで来ているわけです。畜生と人の違いは「死の自覚」にあります。
この前にもお話しいたしましたね。畜生である犬や猫でも、みな死ぬべき運命にあるわけですが、犬や猫は「死」を自覚しているわけではない。夕日を眺めながら、生命の果なさに溜息をつく「犬」などというものは、どうも考えにくいのですね。「死」を自覚的に見つめ、「生」の意味を問うことができる生き物は「人類」だけだと思います。
人類は、この死を自覚し、死を見つめることから、「私たちの生命の真実」「宇宙永遠の真理」つまり「一如」への気付きを得たのです。そして、この「一如への気付き」から生まれたのが「宗教」なのです。
ですが、人であればみな一如への気付きを得ているかというと、そうではありません。私たちの多くは、死は自覚していますが、一如への気付きに欠けています。死を自覚していながら一如に気付いていないとどうなるのか。
それはです。この図で言うと、「人」より右側の「天」や「仏」は無いということになります。つまり、「神も仏もない、死ねば終わりだ」ということになるわけですね。
現代人はたいてい、「神も仏もない、死ねば終わりだ」と考えております。私たち現代人にとっては、「現実世界に生きている間の自分が全て」なのです。ですから、たいていは、「生きている間にしたいことをして、せいぜい楽しく一所懸命に生きた者が勝ちだ」ということになってしまいます。
そんな私たちの人生には、「自分の欲望がどれだけ実現できるか」ということしか残っていません。自分の欲望を追求し、自分の欲望を実現することにしか関心がない。これが「修羅」なのです。「修羅」というのは、自分の欲望を実現するために「戦い続ける生き物」のことです。
生命を奪い合う「戦争」だけが「戦い」ではありません。ビジネスであれ、スポーツであれ、「競争」と名の付くものは、全て「戦い」です。先日も、あるビジネス雑誌に、「人生は戦いに始まり、戦いに終わる」と書いてありました。また、「ビジネスマンは企業戦士」「24時間戦えますか」などという、いささか穏やかでないコピーもあるのです。私たちはたいてい自覚しておりませんが、競争社会と呼ばれている私たちの社会は、まさに「修羅」の世界なのです。
現代人のように「目に見える世界が全てだ」となると、どうしても、こうなってしまうのですね。「目に見える世界が全て」なら、私たちは、目に見えるこの「肉体だけでできている」ということになる。「肉体だけでできている」というのなら、当然、「死ねば終わり」です。
また、「目に見える世界が全てだ」ということになれば、目で見て分かるように、あなたと私は違うのです。つまり、自分と他人は別だということになるわけです。
つまりですね、「目に見える世界が全てだ」という考え方からは、必ず、「死ねば終わりだ」という思いと、「自他を区別する」という心の働きが生まれるということです。
「自他を区別する」から、「他人より自分が可愛い」「自分の利益を第一にする」。ですから、他人と争うことになるのです。
「目に見える世界が全てだ」と考えているから、外の世界しか見ようとしません。自分の幸せの原因も不幸の原因も、全て外の世界にあると思い込んでいます。
特に、政治が悪い、社会が悪い、学校が悪い、あいつが悪い、こいつが悪いと、まあ、悪いものは全部、自分の外にある。
私たちの「不幸」の本当の原因は、ここにあるのですが、こまったことに、私たちの眼は、外しか見られないように外を向いて付いているのですね。
さて、「自分の欲望を実現するために戦う」などと申しますと、私たちとは違った荒々しい特殊な人のことのようにお考えになるかもしれませんが、そうではありません。私たちの日常的感覚に合わせて、もっとソフトな言葉で申しますと、「幸せになるために努力する」「満足を得るために努力する」ということになります。これなら、私たちのことだとお分り頂けるかと思います。
ですが、こう申しますと、今度は、「幸せになるために努力して何が悪いのか」とお考えになるかもしれませんので、前以て申し上げておきます。ここでは、「幸せになるために努力する」ことが善いとか悪いとか言おうとしているのではありません。そうではなくて、「修羅」の世界では、本当の幸せは得られないと言おうとしているのです。
「修羅」の世界は「欲望」の世界です。しかし、欲望には限りがありません。これはどなたもご存じのことです。「進学したい、就職したい、昇進したい、結婚したい、車が欲しい、家が欲しい」と、私たちには、「成りたい」「手に入れたい」ものが次から次へと出てまいります。
戦中戦後の大変な時代を経験してこられた方々には、よくお分りのはずですが、満足に食べられない時には、何とか食べたいと思います。ですが、何とか食べられるようになれば、次には、腹一杯食べたいと思うようになるのです。腹一杯食べられるようになると、今度は、うまい物が食べたいということになる。そんな私たちには、「これでもう満足」という日は来ません。つまりは、「成りたい」「手に入れたい」という私たちには、本当の幸せは得られないということです。
仏教では、私たちが幸せになれない原因を「煩悩」と呼んでいます。煩悩には、大きく分けると、先天的に備わっているものと、後天的に備わるものとがあります。仏教では「倶生起の煩悩」「分別起の煩悩」と言っておりますが、こんな言葉は覚えて頂く必要はありません。
先程お話し致しました「自他を区別する心の働き」というのは、「目に見える世界が全てだ」という考え方によって、後天的に備わる煩悩です。それに対して、先天的に備わっている煩悩というのは、以前にもお話し致しました、「生命エネルギー」が漏れ続けているという心の仕組みのことです。この「生命エネルギー」が漏れ続けているという心の仕組みを、仏教では「漏」と呼んでいます。
私たちが「修羅」となって、互いに傷つけ合っているのは、この先天的な煩悩と後天的な煩悩とが手を組んで、私たちの心を支配しているからです。ちょっとその様子を、目に見える「たとえ」を使って、ご説明致したいと思います。
以前にも使った「たとえ」ですが、このコップが私たちの心だとします。水を半分ほど入れておきます。これは、私たちの心が満たされていない姿です。
さて、私たちは食べて寝ているだけでは、なかなか幸せを感じることができません。それで幸せだとおっしゃるのなら、真に結構なことですが、普通はそうではない。腹はふくれていても、心が餓えている。そこで、心を満たしてくれるものを求めるわけです。
心を満たしてくれるものを求めるというのは、先程申しました、「成りたい」「手に入れたい」と思うことです。「成りたい」ものに成り、「手に入れたい」ものを手に入れたら、心が満たされる。このとき感じるのが「幸せ」という感覚ですね。
たとえば、「車が欲しい」と思っていて、車を手に入れた。車を手に入れることで、心が満たされる。このとき感じるのが「幸せ」です。しかし、考えてみると、車で心が満たされるといっても、別に、車が心の中に入ってくるわけではない。車は、車屋のガレージから自宅のガレージに移動しただけです。
「心」というのは目に見えないものですから、その心を満たすものというのも、目に見えないもののはずですね。私たちは、「目に見える物が全てだ」と言いながら、実際には「目に見えないもの」を求めているということになります。
まあ、それはともかく、この「目に見えない何か」を「心のエネルギー」とか「生命エネルギー」とか言います。私たちの身体が食べ物のエネルギーを必要としているように、私たちの心は「心のエネルギー」を必要としているのです。
この水が「生命エネルギー」だとします。この「生命エネルギー」が心に流れ込むと、心が充電されるわけですから、「生きているという実感」を感じます。心が満たされたときに感じる「幸せ」というのは、この「生きているという実感」のことですね。
さて、「手に入れたい」ものを手に入れて、心が「生命エネルギー」で満たされたら、それで永遠に満足かと言うと、そうではない。しばらくすると、またまた心が餓えてきて、「成りたい」「手に入れたい」という思いがわいてくる。
 それはです、私たちの心というものは、落語の「はてなの茶わん」ではありませんが、どこからともなく「生命エネルギー」が漏れているからなのです。こんなふうにです。
それはです、私たちの心というものは、落語の「はてなの茶わん」ではありませんが、どこからともなく「生命エネルギー」が漏れているからなのです。こんなふうにです。
たとえば、食事をして満腹になっても時間がたてばまた空腹になってくるでしょう。食べ物から得たエネルギーが徐々に少なくなっていくからですね。それと同じように、心を満たしていた「生命エネルギー」も少しづつ漏れ続けて、減っていくのです。ですから、私たちは生きている限り常に不満で、常に「成りたい」「手に入れたい」と思い続けることになるのです。
私たちは心の虚しさに堪えられませんから、満たされたいと思っています。「満たされたい」というのは、本当は「救われたい」ということなのです。「満たされたい」というのは、「生命エネルギー」の源である「一如」を思い出せという、「一如」からの呼び声なのです。ですが、「一如」に背を向けている私たちには、そのことが分かりません。
そこに、「自他を区別する」という心の働きが加わってくるものですから、私たちの世界は「修羅」の世界になってしまいます。というのは、「自他を区別」して「自分の利益が第一」という世界では、満たされない心の隙間を満たすために、他人から「生命エネルギー」を奪ってこようとするからです。
それが「競争社会」なのですが、競争というのは何もスポーツや受験や職場での競争のように、誰が見ても競争だと一目で分かるものばかりではありません。日常の何でもない言葉のやりとりにも、「生命エネルギー」をめぐっての奪い合いが見られます。
たとえば、誰かと話しをていて、急に不愉快になったとか、妙に疲れたとかいう経験はないでしょうか。そういう場合には、たいてい、「生命エネルギー」を相手に奪われたと考えて、まず間違いありません。
また、外面(そとづら)が良くて内面(うちづら)の悪い父親などというのは、善い人だと思われたくて外で出血サービスしてきた「生命エネルギー」を、家族を支配することで取り戻そうとしている人なのかもしれません。
以前、バスのなかでこんな光景を見ました。3歳か4歳くらいの子供連れのお母さんが2人、並んで立っていました。片方の子供が、並んで立っているもう一方の子供に、ちょっと触ったのですね。すると、触られた子供が急に泣きだしたのです。
ちょっと触っただけで、何もしていないのですが、その子のお母さんは、「すみません、ごめんなさいね」と、しきりに謝っている。すると、大声で泣いている子供のお母さんは、聞こえよがしに、こう言いました。「泣きな。やられたらやりかえせ。泣いてるからやられるんや」と。
これは作り話ではありません。目の前で見た話です。びっくりしましたね。謝っていたお母さんも、次の言葉が出てきません。硬くなって黙り込んでしまいました。まわりに立っていた人たちも居心地悪そうに顔を背けましたが、私は、思わずその母親の顔を、見つめてしまいました。
心がズタズタに傷ついている人の顔でした。心の中の「生命エネルギー」が底をついている人の顔でした。どういう事情かは分かりませんが、その人は、いつもまわりの身近な人々から「生命エネルギー」を奪われ続けるような環境で育ったのでしょうね。
親からも兄弟からも親戚からも奪われ奪われして、もうこれ以上奪われたら自分がつぶれてしまうというところまできている。ですから、他人に過剰な反応をしてしまうのです。「近付いてくる人は、みんな自分から奪おうとしているのだ。奪われてたまるか」ということになるのです。
こういう母親は、どこから「生命エネルギー」を奪ってくるのでしょうか。実は、自分より弱い、そして自分の支配下にある子供からなのですね。自分が親からされたように、自分も子供から奪ってくる。
子供は、親から離れたら生きていけませんから、奪われ続けても黙って堪えている。この子供の心の中でも「生命エネルギー」が底をついているのです。ですから、ちょっと触られただけでも、「また奪われる」と恐れて、大声で泣くという過剰反応をするのです。かくして、いわば「運命」も遺伝していくのです。
街でも、ちょっと肩が触れただけでも殴られそうな、おっかない人を時々見かけますが、こういう人も、おそらくさっきの親子と同じで、心に「生命エネルギー」のゆとりが無いのでしょうね。
心に「生命エネルギー」のゆとりが無いのは、何も成長の環境に問題があった人たちだけではありません。たとえば、学校でいじめらている子供、お姑さんとうまくいかないお嫁さん、身勝手な夫をもった妻など、「生命エネルギー」を奪われ続けるような状況に陥った人は、皆同じように暗い荒んだ表情をしています。こんなことが起るのも、みんな私たちが「修羅」だからです。
世間ではよく、「心を開け、心を開け」と言いますが、こんな世界では心は開けられないでしょう。目に見えない「生命エネルギー」を無意識のうちに奪い合っている競争社会では、むやみに心を開くと奪われてしまうのです。「生命エネルギー」が奪われるというのは、別の言葉で言えば、「心が傷つく」ということです。
私たちはみな、この世界に生まれ落ちたときには、心は開いておりました。ですから世界が輝いて見えたのです。ところが、この世界に生まれ落ちたら、傷つくことが山ほどある。傷つけば痛いものですから、傷つけられないように、心はだんだん「殻」を作って自分を護るようになっていきます。心を護る貝殻のようなものができるのです。
「生命エネルギー」を奪われてはたまらないから、心を閉じるようになる。ですが、心を閉じてしまうと、肝腎の「生命エネルギー」を取り入れることもできなくなってしまいます。私たちは、本当は、心を開いて「生命エネルギー」を取り入れたいのです。
ですが、先程も申しましたように、私たちの社会では、心を開くたびに逆に奪われてしまうことも少なくないのですね。親切そうな顔をして、「生命エネルギー」をくれるような素振りで近付いてくる人に心を開くと、ひどいめに会うということもある。これでは、エサだと思って貝殻を開いたら、逆に身をついばまれた貝のようなものです。
この人なら大丈夫奪と心を開いたら、やっぱり奪われたということになれば、だんだん用心深くなっていく。「だまされてたまるか」と疑り深くなった私たちは、腹の探りあいで、どんどん人の心の暗い方に目を凝らすようになっていきます。そして、暗いところに目が慣れてくると、その奥にあるもっと暗いところが見えてくるように、私たちは、どんどん人の心の暗い部分へと誘い込まれていくのです。
かくして、「生命エネルギー」をめぐって争えば争うほど、人はここから左側の「修羅」の世界に深入りしていき、どんどん「一如」から遠くなっていくのです。そんな「修羅」の世界で幸せを求めているのは、闇の中で燃えている鬼火を灯台だと思っているようなもの、砂漠の中で逃げ水を追い掛けているようなものです。
ですが、思えば、そんな「修羅」も、「生きているという実感」を求めているのです。本当は、ガムシャラに戦い続けている人ほど救われたいと思っているのかもしれません。「修羅」はただ、それを求める方向が間違っているだけなのです。
「生きているという実感」「人生の手応え」「命の手触り」を得られる場所は、「生命エネルギー」の源である「一如」にあるのです。ここから左ではない。右なのです。
本当に幸せになりたいと思ったら、本当に救われたいと思ったら、「修羅」を離れねばなりません。「心を開く」というのは、本当は「修羅に」向かって開くことではなく、「一如」に向かって開くことを言うのです。
さて、「修羅を離れる」というのは、別の言葉で言えば「彼岸に向かう」ということです。今日はちょうど「お彼岸」ですが、お彼岸というと「ああ、お墓参りをする日だ」と思われる方もおられるかもしれません。しかし、本当は「彼岸」というのはそういう意味ではありません。彼岸というのは「悟りの世界」「一如の世界」のことをいうのです。
仏教は、娑婆を離れて彼岸に到れと教えています。ですがそれは、町を離れて山に篭もれといっているわけではないのです。娑婆は私たちの「心」にあるのですから、たとえ人里離れた山に篭もっても娑婆を離れたことにはなりません。そうではなくて、仏教が教えているのは、私たちの心の中にある「煩悩」を希薄にしていけということなのです。
先程もお話し致しましたように、「煩悩」には二つの種類がありますが、特に私たちを「修羅」にしているのは、自分と他人を区別しようとする心の働きの方です。この心の働きは、他人を犠牲にして「自分」の利益をはかろうとするからです。言葉をかえて言えば、この「煩悩」は「エゴ」なのです。仏教がめざしているのは、そんな「エゴ」からの解放、つまりは「自他を区別する心の働き」そのものの解消なのです。
「エゴ」は「自分」の利益のことしか考えていません。「エゴ」の頭には「自利」しかないのです。そんな「エゴ」の努力を、仏教では「自力」と言います。
他人と区別された自分の利益は、自分の力、つまり「自力」で勝ち取るしかないのです。だからこそ、「エゴ」の支配する娑婆(現実世界)では「自力」つまり「努力」が賛美されるのです。
「自力」と言えば、必ず「他力」という言葉が問題になってまいります。「他力」というのは、世間で考えられているような「他人の力」という意味ではありません。「他力」という言葉には、「自他の区別を消し去って一如へと導いてくれる力」という意味しかないのです。
この「自力」と「他力」という二つの言葉の意味は、仏教を理解するうえで非常に大切ですので、もう一度申し上げます。「自力」というのは「自他を区別して、自分の利益をはかる力」、いわゆる「努力」のことです。それに対して、「他力」というのは、「自他の区別を消し去って一如へと導いてくれる力」のことです。
この図で言えば、「自力」というのは、ここから左向きに働いている力、「他力」というのは、ここから右向きに働いている力のことです。
ご承知のように、仏教は、「悟り」をめざしております。「悟る」というのは「一如に到る」ということです。「悟り」を得るには、滝に打たれたり、山の中を走り回ったり、断食をしたりと、何か身にこたえる修業をせねばならないと、世間では考えられております。
しかしです。この「自力」と「他力」の関係を見ていただくだけでも、「自力では悟れない」、つまり「努力では悟れない」ということが、よくお分りになるかと思います。
浄土真宗は他力の教えだと言われておりますが、なにも真宗だけが他力の教えではありません。自力の教えのように言われている禅宗も、真言宗も、その他の宗派も、本当は、他力の教えなのです。というのも、先程の図で見て頂きましたように、「他力」によってしか、悟れないからなのです。
「自分が救われよう、他人を救おう」と努力しているあいだは、悟れないのです。お釈迦さまがお悟りになったのも、「苦行」という努力をやめられたときでした。
私たちは常に「他力」の中におりますが、そのことに気付くのは「自力」の働きが止まったときだけです。世界には様々な宗教や宗派があり、千差万別のように思われておりますけれど、本当は、どの宗教も宗派も、みな「一如」をめざしているのです。違うのは、この「自力」をどうやって止めるかという、「自力」の止め方なのですね。
何か込み入った話のようにお感じになったかもしれませんが、「自力」と「他力」は、働いている向きが違うということは、お分かり頂けたかと思います。
ちょっと余談ですが、「人事を尽くして天命を待つ」という言葉がありますね。これはいささか妙な言葉ではないかと思います。「人事を尽くす」というのは「自力」の限りを尽くすということ、「天命を待つ」というのは「他力」に任せるということでしょう。しかし、さきほど申しましたように、「自力」と「他力」は反対向きの力なのですから、どうも理屈に合いません。
どこかで読んだ話ですが、「日本人というのは人事を尽くしても天命を待てない国民」なのだそうです。「人事を尽くした上にも人事を尽くす」というのが日本人だそうです。もしそうなら、私はある意味で、「日本人は筋が通っている」と思いますね。
他人と区別された「自分」の利益をはかるには「自力」しかないのです。ですから、自分の利益をはかろうとするかぎり、当然、最後まで「人事を尽くす」しかないわけです。そこには最初から「天命」の出番などないのです。それを知っている日本人の「現実感覚」は、なかなかのものだと思います。
しかし、この「現実感覚」というものは、いわゆるエコノミックアニマルの感覚でして、「修羅を離れる」ために役立つ感覚ではありません。自分の利益、つまり「自利」を追求しているかぎり、「修羅を離れる」ことはできないのです。
言葉の上で言えば「自利」の反対は「他利」です。ですから、ややもすると「自利」は悪で「他利」が善だということになりがちです。人助けこそ仏教の実践だと考える人もいます。
しかしです。「他利」とは他人の利益をはかることなのですから、これもまた「自利」の場合と同様に、自分と他人を区別して初めて成り立つものなのです。つまり本当は「自利」も「他利」も、ともに「エゴ」の表われだということです。そんな「自利」からも「他利」からも、ともに離れるのが仏教の道です。
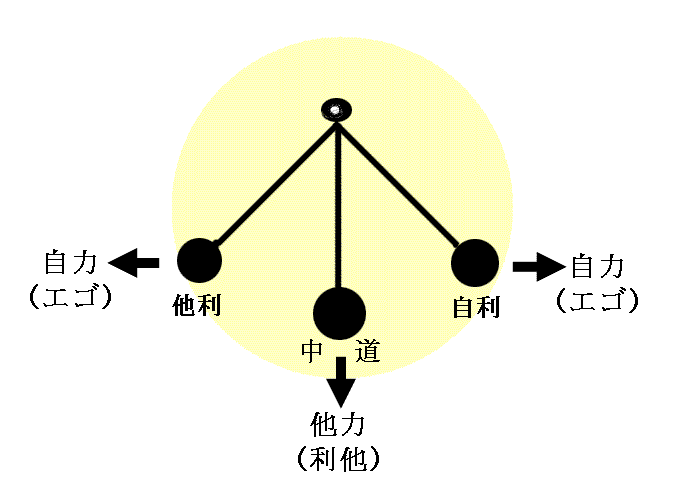 ちょっとこちらの図をご覧ください。たとえて言えば、時計の振り子が右に振れているのが「自利」であり、左に振れているのが「他利」なのです。振り子を動かしているのは「エゴ」です。右にも振れず左にも振れず、静かに止まっている。これが仏教のめざす「中道」なのです。「自」とか「他」とかいった「個」を離れることで「全」になる。それが仏教の「利」です。まことの「利」には「自」も「他」もないのです。
ちょっとこちらの図をご覧ください。たとえて言えば、時計の振り子が右に振れているのが「自利」であり、左に振れているのが「他利」なのです。振り子を動かしているのは「エゴ」です。右にも振れず左にも振れず、静かに止まっている。これが仏教のめざす「中道」なのです。「自」とか「他」とかいった「個」を離れることで「全」になる。それが仏教の「利」です。まことの「利」には「自」も「他」もないのです。
「個」を離れて「全」になるというのは、自分とか他人とかいった「個人」を離れて、「一如」につながるということです。自他の区別を離れて「一如」につながっていくことが、「全て」とつながるということです。
キリスト教でも同じようなことを言っています。「汝自身を愛するが如く、汝の敵を愛せよ」という言葉をご存じでしょう。この言葉だけ聞くと不可能なことを言っているように聞こえますが、そうではありません。これは「神を深く愛すれば、自分も自分の敵もなくなる」と言っているのです。神とは「一如」のことです。「一如」とつながれば、「全て」とつながるのです。
私たちの「心」は深いところで「ひとつ」につながっております。この「ひとつ」につながった世界を「一如」と言うのです。ですから、心の底で「一如」につながっていくことが、全ての人とつながっていく道なのです。
この図で、引力のように、下に向かって引っ張っている力が「他力」です。一方、引力に逆らって右や左に振ろうとする力が「自力」です。私たちは、常に引力に引かれながら、そのことに気付かずに、引力に逆らって立っているのです。ちょうどそんなふうに、私たちは、常に「他力」に引かれながら、そのことに気付かずに、「他力」に逆らって生きているのです。
左右に引っ張るのをやめれば、振り子は引力に引かれて、自然に中央で止まります。「自力」をやめれば、自然に「中道」に帰することになる。ですが、これは「努力」ではできないのですね。「努力」とは「自力」のことだからです。「自力」には左右に引っ張る力しかありません。まことの「利」である「中道」に帰するには、「他力」に任せるしかないのです。
まことの「利」である「中道」に帰す。それは、私たち門徒にとっては、「念仏」に帰すということです。親鸞聖人は、悲嘆述懐和讃でこう詠んでおられます。「小慈小悲もなき身にて、有情の利益はおもふまじ、如来の願船いまさずは、苦海をいかでかわたるべき」と。
これは、自他の区別を離れることのできない私たちには、如来が「一如」の世界からさしむけてくださっている「他力」の船、つまり「念仏」に乗る以外に、まことの「利」に帰する道はない、という意味です。
まことの「利」には善も悪もありません。善悪というものは、自他を区別する社会のなかにしかないからです。念仏には善も悪もありません。いわば、自他の区別をおしすすめる「競争社会」の役には立たないものです。私たちは、何かあるとすぐに、「社会のため、社会のため」と言いますが、外見上社会に役立つ行為が、必ずしも「魂の成長」に役立つとは限らないのですね。
仏教というものは、ある意味で、非社会的なものだと言えます。仏教の目は、本来、外にではなく内に向けられているからです。仏教は、外の世界を変えることではなく、私たちの内にある心を変えることをめざしているのです。
ですから、目の向けられている方向からも、仏教とそうでないものとを見分けることができるように思います。社会に働きかけようとする目は、社会人の目ではあっても、仏教徒の目ではないのです。この点は、社会人である私たちには、なかなか理解しがたいところかと思います。
これは何も仏教だけではありません。本来、あらゆる宗教の目は、外ではなく内を向いているのです。ですが、たいていの宗教人は、宗教人というよりは社会人です。口では「宗教、宗教」と言いながら、目は外ばかり向いているのです。目が外ばかり向いているものですから、自分が頭を下げる神や仏に頭を下げない人がいると、気になってしかたがない。そのうち我慢できなくなって、「ひとつあいつの頭を下げさせてやらねばならん」ということになる。かくして、争いが始まるのです。
宗教の歴史は戦いの歴史です。世界史を見ましても、無数の戦いが宗教の名のもとに引き起こされてきたことが分かります。十字軍では神の名のもとに、一向一揆では仏の名のもとに、おびただしい血が流されました。
現在でも、世界の至る所で宗教紛争が起っています。新聞などでご承知のように、たとえば、
- ボスニア・ヘルツェゴビナ、グルジア、アルメニアでは、《キリスト教徒》と《イスラム教徒》が戦っています。
- 中東では、《ユダヤ教徒》と《イスラム教徒》が戦っています。
- 北アイルランドでは、《カトリック教徒》と《プロテスタント教徒》が戦っています。
- 北インドのカシミールでは、《ヒンドゥー教徒》と《イスラム教徒》とが戦っています。
- それに、宗教を否定する共産主義者と、チベット仏教徒やイスラム教徒も戦っています。挙げていけば切りがないほどです。
神や仏に祈りながら人を殺す。こんなおかしなことはありません。本来、宗教というものは「修羅」を離れるためにあるのです。宗教がめざしているのは「心の平安」なのです。守るべきものが心の平安であるかぎり、血は流されません。守るべきものが心の平安ではなく「物」や「権利」や「プライド」になったときに、血が流されるのです。
「宗教戦争」などという言葉そのものが矛盾しています。さきほどの図で言えば、宗教の道は右、戦争の道は左なのです。左は「修羅」の都へ続く道、右は「修羅」を離れる道です。私たちは、右と左に向かって同時に歩きだすことはできません。
「修羅を離れる」には「菩提心」をおこさねばなりません。「菩提心をおこす」というのは、「一如」に向かって歩み始めたいという思いを抱くことです。宗教はここから始まります。菩提心のない宗教は、ただの教養です。そんな宗教は「修羅」の道具でしかありません。
今に始まったことではありませんが、宗教というものは「修羅」の手垢にまみれてコテコテに汚れてしまっています。近年、若者の宗教離れが激しくなったと言いますが、無理もないと思いますね。そんな手垢にまみれた宗教を見て「きたない」と思うのは正常な感覚だと言わねばなりません。
本当に宗教が理解できたら、戦争はなくなります。ですが、「修羅」である私たちには、「修羅」を否定している宗教というものが、なかなか理解できません。あるいは、理解できないというよりも、理解する気がないといった方が正しいかもしれません。というのは、本当に理解すれば、「修羅」は「修羅」であることをやめねばならないからです。「修羅」には自分が変わる気などありません。「修羅」は、自分が変わるのではなく、自分の都合に合わせて世界を変えようとするのです。
たしかに、「宗教」は「世界の変革」をめざしています。ですが、この変革されるべき世界というのは、外の世界ではなく、私たちの内にある世界のことなのです。
しかし、「修羅」は、外の世界と戦うのが人生だと思っています。「修羅」の目は外を向いていて、その目には、自分の思い通りにしたい外の世界しか映っていません。ですから、宗教というものも「外の世界を変えるための教え」だと誤解するのです。そのため、自分の信じる宗教の理想に合わせて、外の世界を変えねばならないと思い込んでしまうのです。宗教紛争というものは、ここから生まれてきます。
宗教には布教がつきものだと考えられています。しかし、布教というものが宗派の勢力拡大、つまり、何人勧誘したかという地図の上での陣取り合戦を意味するのであれば、そんなものは宗教の皮を被った帝国主義にすぎません。宗教には社会的勢力など持つ必要はないのです。社会的勢力には、必然的に攻めと守りがつきまといます。攻めるのも守るのも争いです。宗教は本来、いかなる争いとも無縁なのです。
あらゆる争いは自分が正しいという思いから生まれます。自分は間違っているという思いから生まれる戦争はないのです。自分が正しいと思ったからこそ、日本は朝鮮や中国に進攻したのです。自分が正しいと思ったからこそ、アメリカはベトナムに爆弾を落としたのです。自分が善であるかぎり、相手が悪なのです。自分を正当化しようとする思い、あらゆる争いはここから生まれます。
親鸞聖人は、悲嘆述懐和讃にこう詠んでおられます。「浄土真宗に帰すれども、真実の心はありがたし。虚仮不実のわが身にて、清浄の心さらになし」と。この聖人と同じように、どうしても正当化できない自分に気付いた人のことを門徒というのです。真宗でいう「悪人の自覚」とは、このことです。
この自覚は、自分が「修羅」であるという気付きです。自分が闇の中にいるという気付きです。信心は、この自覚から始まります。信心とは心にともったともしびです。「自覚された悪人」の心を照らすともしびが信心なのです。このともしびが「一如」への路を照らしてくれます。その道筋には、いかなる戦いもありません。
「戦い」は人の上に立つための道かもしれませんが、決して人を超えるための道ではありません。「戦い」は世界を支配するための道かもしれませんが、決して世界と調和するための道ではありません。
戦後50年を経た今日、「過去の不幸な出来事を反省して、歴史から学ばねばならない」という言葉をよく耳にします。しかし、私たちは過去の歴史から本当に学んでいるのでしょうか。インドのガンジーはこう言っています。「歴史を学べばよく分かる。人間は歴史から何も学ばなかったということが」と。戦後の歴史を見ると、どうもガンジーの言葉が気に掛かりますね。
私たちは、よく「反省」という言葉を使います。反省というのは、たいてい、過去の行いがうまくいかなかったのは何故かと考えることを言います。お寺の掲示板などに、「路を見よ。つまずいたら、振り返って、歩いてきた路を見よ」という言葉がよく書かれていますが、これが反省ですね。私たちは決して反省していないわけではないのです。それなのに、大切なところで何も変わっていないように見えるのはどうしてでしょうか。
それはですね、以前にもお話し致しましたように、私たちは赤い色眼鏡をかけて世界を見ているからなのです。赤い色眼鏡というのは、「序列主義」と「物質主義」という、「修羅」の世界の価値観のことです。そんな色眼鏡をかけたままいくら振り返っても、本当のところが見えるわけではありません。
たとえばです。つまずいて振り返っても、赤い色の石につまずいていたら、そんな石は赤い色眼鏡をかけた目には見えないのです。「修羅」がいくら振り返っても、本当のつまずきの石を見付けることはできません。振り返ってもダメなのです。色眼鏡がはずれていないと、振り向いても、「やっぱり、あいつが悪い」ということになるのです。
真実を知りたいと思ったら、色眼鏡をかけた頭で反省することではなく、色眼鏡を外すこと、つまり、自分の「心」が変わることが大切なのです。ですが、それは「自力」つまり「努力」ではできないことなのですね。「努力」とは「エゴ」の力だからです。
では、そろそろ、本日のまとめに入りましょう。先程もお話しいたしましたように、仏教では、娑婆を離れて彼岸に到れと教えています。ですから、仏教は現実を否定しているようにお考えの方もおられます。ですが、それは違います。娑婆を離れて彼岸に到れといっても、仏教は「現実」を否定しようとしているわけではありません。現実を否定しているのは、仏教ではなくて、むしろ私たちの方なのです。「現実を否定している」と言って分かりにくければ、「今の自分に不満を抱いている」と言えばどうでしょうか。
私たちは常に、「今の自分」ではないものに「成りたい」、「今の自分」が持っていないものを「手に入れたい」のではないでしょうか。本当の現実は「今の自分」にあります。ところが私たちは、「成りたい」「手に入れたい」という欲求の方を自分の現実だと考えがちです。「今の自分」という現実を否定し、「成りたい」「手に入れたい」という欲求を肯定しているのが私たちです。
仏教はちょうどその逆です。仏教は「今の自分」という現実を肯定し、「成りたい」「手に入れたい」という欲求を否定しているのです。つまりは、「成りたい」「手に入れたい」という思いで仏様や神様に手を合わせる「ご利益祈願」を否定しているのが仏教だということです。
仏教がめざしているのは心の平安ですが、「今の自分」に不満を抱いているかぎり、心の平安は得られません。「成りたい」ものになっていない、「手に入れたい」ものを手に入れていない「今の自分」、この「今の自分」を否定しているかぎり、自分は常に惨めです。
では、「成りたい」ものになり、「手に入れたい」ものを手に入れれば、それで心の平安を得られるかというと、決してそうではありません。娑婆に生きる私たちの欲求には、かぎりがないからです。何かを手に入れたら、次は他のものが欲しくなるのです。「衣食足って礼節を知る」という言葉がありますが、これも結局は、「食べられたら、次は、誉められたい」というだけのことではないのでしょうか。
自分は変わらずに外の世界を変えようとするのが「エゴ」です。自分が変わること以外なら何でもしようとするのが「エゴ」です。「エゴ」は努力家です。努力で「成れない」「手に入らない」と分かれば、神や仏にすがってでも「成ろう」「手に入れよう」とするほど、「エゴ」は努力家なのです。
「エゴ」には、「成りたい」「手に入れたい」しかありません。そのために、果てしない努力を続けているのが「エゴ」なのです。思えば「エゴ」とは悲しいものです。もうそろそろ、そんな「エゴ」を解放してやってはいかがでしょうか。「エゴ」を解放する。それは、外の世界を変えようとする努力をやめること、つまり「何もしない」ということです。
「修羅」の世界の中心に向かって走っていた私たちが「一如」に向かって方向転換するためには、まず立ち止まらねばなりません。「何もしない」とは、まずは、そういうことを言うのです。「一如」の世界からの声を聞くには、立ち止まって耳を澄まさねばなりません。それは、ただぼんやりと無気力に何もしないということではなく、積極的に日常の時間を止めるという意味で、「何もしない」ということなのです。
積極的に「何もしない」というのは、自分というものを握り締めていた手を開く、自分を明け渡すということです。それは、「宇宙永遠の真理」「一如」へと運んでいこうとする「他力」に任せるということです。「他力」に任せるというのは、「魂の進化」の流れに身をまかせるということです。
「一如」につながれば、満腹になった人が食物に手を出さないように、本当に「何もしない」で満たされている世界が広がってきます。中国の道教ではこの境地を「無為」と呼び、真宗では「自然法而」と呼んでいます。
ユダヤ教にも「安息日」といって何もしない日があります。安息日というのはレジャーのための休日ではありません。安息日というのは、一日何もしないで神の声に耳を澄ます日なのです。ユダヤ教徒は、この日のために他の6日間を働いて過ごすのです。
「一如」は、私たちに常に、「そっちじゃない、こっちだ」とささやきかけています。その声が聞こえないのは、私たちが頭のなかでいつもオシャベリをしているからです。自分と話すのに熱中していたら、一如の呼び声が聞こえません。
私たちは話すことで「修羅」の世界に縛り付けられているのです。私たちが「修羅」の世界を離れて自由になるためには、話すのをやめて耳を澄まさねばなりません。「話すのをやめて、耳を澄ませる」。それは、私たち門徒にとっては、「念仏行」を実践するということです。
「念仏行」には、わずか十数分しかかかりません。ですが私たちには、たいていこれができないんですね。「そんな暇があれば、掃除ができる、洗濯ができる、新聞が読める、あれもできる、これもできる」と思ってしまうのですね。
私たちは、「何もしない」ということが、それほど苦手なのです。常に何かをしていないと堪えられない。目が外を向いていて、外からの刺激が切れるとイライラする。刺激中毒になっている私たち。それが「修羅」なのです。ですが、その「修羅」を離れるためにあるのが、「念仏行」なのです。
「念仏行」というのは、静かなところに座ってそっと眼を閉じ、「ナム、ナム、ナム」と称え続けて、念仏という「他力」に任せるだけのことです。ですが、これは口で言うほど簡単なことではありません。
私たちは常に外の世界に目を向け、外の世界を自分の思い通りにコントロールしようとしてきました。コントロールするとは支配するということです。ですから、私たちは常に何かを支配していないと不安なのです。そんな私たちには、「任せる」ということがなかなかできません。そこで、「任せよう、任せよう」と努力してしまいます。
ですが、任せようと「努力」してはいけません。「努力」というのは、人間はほうっておくと怠けてダメになってしまうという考えから生まれています。つまり、「努力、努力」という「努力」を強調する考え方は、生命の自然な流れ、つまり「他力」に対する不信から生まれているのです。不信から信を得ることはできません。
では、どうするのか。ただ「念仏」するのです。「本当の自分に成りたい」「心の平安を手に入れたい」という、「成りたい」「手に入れたい」は「エゴ」です。本当の自分に成れても成れなくても、心の平安が得られても得られなくても、ただ「念仏」する。「他力」への信は、手に入れるものではありません。「他力」への信は、この「念仏」のなかから自然に生まれてくるものなのです。「努力」では「修羅」を離れられない、「修羅」を離れるには「念仏」しかないということ、お分り頂けましたでしょうか。
さて、私たちが「修羅」になった原因は、ひとことで言えば、教育にあります。教育に「一如」への気付きが欠けていることが原因です。教育というのは、なにも学校教育だけを言うのではありません。私たちは、社会全体に漂っている無数の情報を無意識のうちに学びとって、「修羅」になっていくのです。つまりは、「修羅」の社会に生まれることによって、「自他を区別する」という後天的煩悩が備わるわけです。
最近はやりの言葉で申しますと、私たちは社会から「マインドコントロール」を受けているということです。「マインドコントロール」などというと、新興宗教の御家芸のようにお考えかもしれませんが、そうではありません。
私たちはマインドコントロールによって社会の価値観を埋め込まれていくのです。「社会人」になるためには、このマインドコントロールを受けねばなりません。ですが、「社会人」を超えて、本当の自分になるためには、このマインドコントロールをはずさねばならないのです。
マインドコントロールをはずす。宗教の役目はここにあります。そこで次回は、このマインドコントロールをはずし、本当に自由になるというお話しをさせて頂きたいと思っております。
次回は10月15日の報恩講でして、今日から一月もありませんので多少慌ただしいのですが、どうぞお参り下さいませ。お待ち申し上げております。本日は長い間お付き合いを頂きまして、有り難うございました。
紫雲寺HPへ