本日は「永代経法要」でございますが、私が皆様の前でお話しをさせて頂くのも、今回で9回目になります。「9」という数は、一桁の数で最も大きな数ですから、中国では極数と申しまして、最も尊い数だとされております。「9」は、いわば究極の世界を表す数字なのです。
もちろん、9回目の法話と申しましても、そのような究極の境地をお話しできるわけではございませんが、これまで皆様とご一緒に考えさせて頂きました8回の法話を踏まえて、私の「ただいまの思い」ぎりぎりのところまでお話しさせていただければと、願っております。
本日は、先にご案内申し上げましたように、「身体と心と魂」という題でお話し申し上げますが、その要点をひとことで申しますと、「この身体と心と魂がひとつの全体に戻ったときに、命の意味が回復される」ということです。仏教的な言葉で申しますと、本日のテーマは「救いと信心」についてということになります。どうぞ、しばらくの間、お付き合いください。
さて、まず、本日の話の舞台となります私たちの「命」の全体像を、ご覧に入れておきます。どうぞ、こちらをご覧になって下さい。これまでに何度か話をお聞き頂いた方は、「ああ、またアレだな」とお思いになるかもしれませんが、これは唯識仏教でいう心の構造に基づいて描いた「命の全体像」です。別に、「命」がこういう形をしているというわけではありません。これは、あくまでモデルですので、そのおつもりでご覧下さい。
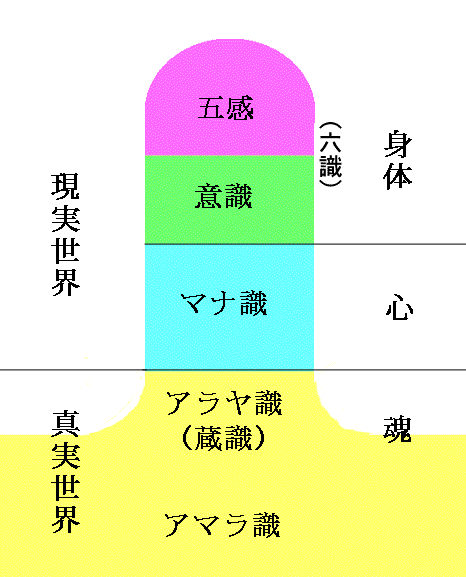 この小山のように盛り上がった形で描かれておりますもの、これが私たちの「命」の全体像です。上から順番に、五感と意識を合わせた「六識」、そして「マナ識」「アラヤ識」(「アマラ識」)という構造になっておりますが、一番上の「六識」が「身体」、次の「マナ識」が「心」、そして、その下の「アラヤ識」が「魂」に対応しております。「魂」という言葉がお嫌いな方は、「命の核心」だとお考え頂いても結構です。
この小山のように盛り上がった形で描かれておりますもの、これが私たちの「命」の全体像です。上から順番に、五感と意識を合わせた「六識」、そして「マナ識」「アラヤ識」(「アマラ識」)という構造になっておりますが、一番上の「六識」が「身体」、次の「マナ識」が「心」、そして、その下の「アラヤ識」が「魂」に対応しております。「魂」という言葉がお嫌いな方は、「命の核心」だとお考え頂いても結構です。
私たちの「命」は、本当は、こんなふうに分けることのできない「ひとつの全体」なのです。ですが、私たちは、この「命」を「ひとつの全体」としては見ていないのですね。私たちは、たいてい「身体」のレベルだけで「命」を考えているか、あるいは、せいぜいが「心」のレベルまでで「命」を考えています。
「命」というものを「身体」のレベルだけで考えていると「健康」が何よりも大切ということになってきます。また、「命」というものを「心」のレベルまでで考えていると、「生き甲斐」が何より大切ということになってきます。
私たちは、病気になれば「健康」を願い、健康になれば「生き甲斐」を望むものです。たしかに、「健康」も「生き甲斐」も、人生にとって大切なことだと思います。ですが、私たちの命の根底には、「健康」でも「生き甲斐」でも癒されない、「魂の渇き」がある。本当は、そこが問題なんですね。
と申しましても、お釈迦様のように、「自分とは何か、どこから来て、どこへ行くのか」といった実存的な悩みをつきつめて考える人は少ないでしょう。たいていは、現実的な幸せを求めるのに忙しくて、そんな「贅沢な悩み」とつきあっている暇はない。しかし、幸せはゆっくり近づいてきますが、不幸は突然やってきます。
たとえば、事故です。今年の2月には、北海道の豊浜トンネルで起こった岩盤崩落事故で、20人が亡くなっています。先月も、静岡県内の東名高速道路で大型トレーラーの事故がありました。この事故では、6人が亡くなっています。どちらも一瞬の間に起こった事故でした。亡くなった人たちは、その瞬間まで、いつもと変わりない生活をしていたのです。
また、病気もそうです。エイズウイルスに汚染された非加熱血液製剤を投与されて、400人もの方が亡くなっていますし、今年の夏の「病原性大腸菌O157」による食中毒でも、何人もの子供さんが亡くなっています。ご家族の誰もが、直前まで予想できなかった死だったと思います。医薬関係者が憎い。大腸菌が憎い。いや、それよりも何よりも、「どうして自分だけが、どうして自分の家族だけが」という思いに苦しんでおられるのではないかと思います。
以前、一人っ子さんを交通事故で亡くされた方のお話しをうかがったことがあります。「息子はいつものように「行ってきます」と学校に出かけました。それが元気な姿を見た最後です。息子は学校から帰ってきませんでした。息子の部屋は、今でも、そのときのままにしてあります。
机の上には、ノートが開いたまま。丸く減った消しゴム、短い鉛筆。電気スタンド。マンガの本。ゲームソフト。床の上には大切にしていたグローブとボールがころがっている。ベッドの上にはパジャマが脱いだままに丸めてある。みんな息子のものです。誰にもさわらせません。
最初は、時々、そっと子供部屋をのぞきにいきました。何を期待していたのでしょうね。今はもう、何か恐くて、部屋をのぞかなくなりましたが、それでも、子供の部屋の前を通るとき、思わず耳を澄ましている自分に気づくのです」と。
子供の死、老人のボケ、心身障害、進行性麻痺、膠原病、ガン、エイズ、脳溢血や心臓麻痺による突然の死。あるいは、いつまで続くか分からない病人や老人の介護。本人にとっても家族にとっても納得のいかないことばかりです。そのうえ、経済的な問題や様々な人間関係の問題もからんでくる。
苦しくて、辛くて、悲しくて、情けなくて、悔しくて仕方がない。そんなとき、人生が悲しみに塗りつぶされ、人生に疲れ切ったとき、人は誰も、「なぜ自分だけが、どうして自分の家族だけが」と思うのです。この問いに答えはあるのでしょうか。今日、ご一緒に考えてみたいと思っていますのは、このことです。
『雑阿含経』というお経に、こんな話がでてきます。舎衛城にキサー・ゴータミーという貧しい女がいました。キサーというのは「痩せた」という意味ですから、おそらく痩せた人だったのでしょう。このゴータミーが嫁いで男の子を産んだのですが、その子はほどなく死んでしまいます。ゴータミーは、愛しい子供が死んだことを認めず、亡骸を抱きかかえ、半狂乱になって叫びながら町中をさまよい歩きます。「だれか、この子をなおす薬をください、この子をなおす薬をください」と。そして最後に、お釈迦様のところにたどりつきました。
お釈迦様は、ゴータミーを哀れに思われ、「私が薬を作ってあげるから、よく聞きなさい。薬の材料としてケシの実がいる。ただ、普通のケシの実ではいけない。これまでに一度も死人を出したことのない家からもらったケシの実でないと効かない。そういう家からもらってきなさい」とおっしゃった。
そこで、ゴータミーは家々を尋ね歩くが、どの家もどの家も、全部、死者を出した家ばかりです。親に死なれた家、連れ合いに死なれた家、子供に死なれた家。死人を出していない家は一軒も無い。そうして家々を回るあいだに、ゴータミーの狂気は少しづつ鎮まっていきます。愛する人に死なれて悲しみ苦しんでいるのは「自分だけではないのだ」と気づいていきます。
ゴータミーは、お釈迦様のもとにもどります。お釈迦様が、「どうだ、ケシの実はもらえたか」とお尋ねになると、「いいえ。ですが、もうお薬は結構です」と応え、子供の亡骸を荼毘にふして、出家した、という話です。
ゴータミーは、お釈迦様の智慧によって、「自分だけが苦しんでいるのではない」と気づいて、正気を取り戻したわけですね。そこで、この物語を読んで、ゴータミーはお釈迦様に「救われた」のだとお考えになる方もおられます。ですが、私は、そうは思いません。ゴータミーは、「救われた」のではなく、「自分だけではない」と知って、「なぐさめられた」だけです。そして、「なぐさめ」では救われなかったからこそ、「救い」を求めて出家したのだと思います。
どんな苦しみでも、「自分だけではない」「自分と同じように苦しんでいる人がいる」「自分よりもっと不幸な人がいる」。これは事実です。ですが、「自分だけではない」という事実を知ることは、「なぐさめ」や「はげみ」にはなっても、「救い」にはなりません。不幸な人は自分だけではないと知っても、自分が不幸であることに変わりはないからです。私たちは「事実」では救われないのです。私たちは、「事実」によって救われるのではなく、「真実」によって救われるのです。
では、「真実」とは何か。それはです、私たちは「身体と心」だけでできているのではなく、私たちは「身体と心と魂」からできているが、本来は「一如」なのだということです。
「魂」などと申しますと、不愉快になられる方もおいでだと思います。なるほど、世間には、先祖の「魂」の御祓いをするとか、水子の「霊」を供養するとかいった、あやしげなことを商売にしている人々もいますし、そういった山師のような人々の吹く笛で踊り回る人々もたくさんいます。たしかに、愉快な眺めとは言いがたい。それに第一、現代科学が「魂」など認めていないのですから、そんな非科学的な馬鹿馬鹿しい話は聞きたくないと思われる方がおられても不思議ではありません。
科学を信仰する現代社会で、非科学的だと言われることは、気が狂っていると言われるようなものです。そのためでしょうか、もともと仏教は「魂」の存在を否定していないのですが、最近は坊さん方まで、「魂」を無視して人生を考えようとしているようです。ですが、私は、「魂」を抜きにして人生は理解できない、「魂」を抜きにしては人生に納得できないと思っています。
「身体」のレベルでは、見ての通り、自分と他人は違う。また、「心」のレベルでは、他人とは違う特別な自分がかわいい。仏教では、この、「自分と他人を区別して、自分の利益をはかろうとする心の働き」を「煩悩」と呼んでいます。別の言葉で言えば、「煩悩」とは「エゴ」のことです。
この「エゴ」が「心」を支配し、その「心」が「身体」を握りしめている。そのために、この図で申しますと、ここから上の「身体」と「心」のレベルでは、自分の思い通りでないことは、どうしても納得できないのです。私たちが「現実世界」と呼んでいるのは、この「煩悩」に支配された「身体と心」のレベルのことです。
ですが、本当は、私たちの「身体と心」からなる「現実世界」は、「真実の世界」によって支えられている。この図で申しますと、「真実の世界」というのは、この「魂」より下の世界です。これまでにも何度もお話ししてきたことですが、私たちは、「命」の底で、みんなつながっている。私たちは、「ひとつ」なのです。
30年ほど前のことですが、こんな体験をしたことを覚えています。近くの高校に通っていた頃のことです。昼ご飯を食べに帰って、午後の授業を受けるために、また学校に出かけました。大徳寺の裏あたりまで来たときに、北山通りの方からサイレンを鳴らして救急車が走ってくる。
救急車は、サイレンを鳴らしながら、私の側を走りすぎて行きました。その瞬間です。不思議なことですが、「あの救急車で運ばれている人は自分だ」という強烈な思いがしたのです。「あれは自分だ」。あるいは、「あの人は自分の一部なんだ、私はあの人の一部なんだ」という思いだったかもしれませんが、ともかく、それが他人ごとではなかったのです。
生々しい不安を感じました。まわりを見回すと、何人かの人が歩いている。ですが、誰も、「自分の一部が救急車で運ばれている」ことに不安を感じているようには見えません。その人たちは、「自分の一部が救急車で運ばれている」ことに気づいていない。こんどは、そのことが不安になりました。「おーい、僕らの一部が運ばれて行ったぞ、どうしよう」と、思わず声をかけそうになりました。
私は、そのときの経験を何度も思い直しました。あのときの、「あれは自分だ」という強烈な思いは何だったのかと。どうしても納得のいく説明が見つかりませんでしたが、何年もたって、ようやく分かった。
テレビで絞り染めの技法を紹介していたときです。絞り染めというのは、1枚の布のあちこちを糸で縛って、模様を染め出す技法です。糸で縛ったところは染まらない。ご存じだと思います。あの、糸で縛った小さな乳首のような突起が一面に並んでいるのを見て、ようやく分かったのです。あの糸で縛った一つの突起が「私」、別のもうひとつの突起が「あの人」だったのです。糸をほどけば同じ1枚の布だった。やっぱり、「あれは自分」だったのです。
お分かり頂けないかもしれませんが、別の「たとえ」でいえば、私は中指、あの人は人差指だった。ともに同じ手の一部だったのです。あの瞬間、何故かは分かりませんが、私の「心」は、「指」ではなく、「手」を見ていたらしいのです。こういう経験をしたおかげもあって、後年、唯識仏教の心の構造を学んだときに、非常によく分かりました。「ああ、これなんだ」と思いましたね。
この図でご覧になって頂けますように、私たちの個人的な「魂」は、みな「一如」の世界につながっています。そこには「自他」の区別がありません。「私」も「あなた」もない世界です。「人の喜びは、そのまま自分の喜び、人の悲しみは、そのまま自分の悲しみ」それが、この世界です。この世界を、仏教では「彼岸」と呼んでいます。この世界につながったとき、私たちは「ひとつの全体」としての「命の意味」を回復するのです。
思えば、「現実世界」で繰り広げられる日常生活の喜びも悲しみも、みなこの「彼岸」に支えられているのです。ですが、眼に見える「現実世界」が全てだと教えられ、「身体と心」の世界で溺れていると、なかなか、そのことに気づけないのですね。
もちろん、私たちは、「現実世界」にだけ固執して生きていても、ときには現実を超えた世界からの光に触れることがあります。たとえば、清らかな赤ん坊の寝顔に見入って微笑むとき、空に浮かぶ雲に我知らず涙するとき、安らかな死に顔に光を感じるとき、私たちは現実を超えた世界からの光に触れているのだと思います。
ですが、「身体と心」という「現実世界」しか認めないものには、その体験の意味が分からないのです。ですから、大切な体験がウヤムヤになって消えていくのです。仏教が教えているのは、その体験の意味なのです。
私たちは「身体」と「心」だけでできているわけではない。私たちは「身体」と「心」と「魂」でできているのです。そして、みんな、「あなた」も「私」もない「一如」の世界に支えられているのです。この「一如」の世界につながったとき、私たちは「ひとつの全体」としての「命の意味」を回復するのです。
皆さんは、星野富広という人をご存じでしょうか。星野さんは、群馬県の中学校の体育の教師でしたが、クラブ活動の指導中に起きた事故で、首の骨を折り、9年間の病院生活を送りました。結局、首から下の運動機能が回復しませんでしたが、今では、口に筆をくわえて、素晴らしい詩や絵を描きながら、静かな生活を送っておられます。
星野さんは、入院中、もう二度と手足が動かせないと知って、「死にたい、死にたい」と悩み苦しんでいたときにキリスト教の教えに出会い、徐々に癒され、救われていきました。この星野さんの絵も詩も素晴らしいものです。いちどご覧になって頂きたいと思いますが、私の好きな詩を、いくつかご紹介させて頂きます。どうぞ、これまでにお話しさせて頂きましたことと重ねて、お聞き下さい。
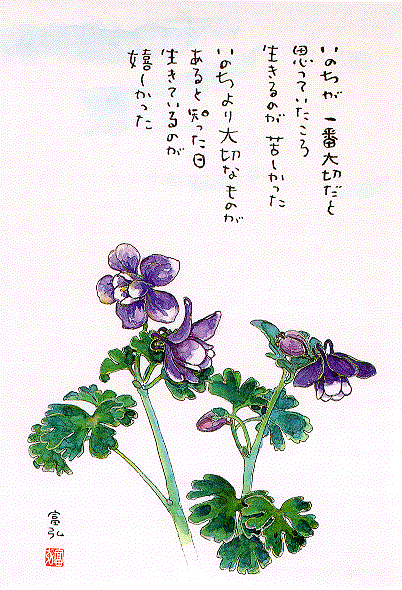 まずは、こういう詩です。
まずは、こういう詩です。
いのちが 一番大切だと
思っていたころ
生きるのが 苦しかった
いのちより大切なものが
あると知った日
生きているのが
嬉しかった
「いのちが一番大切だと 思っていたころ」という、この「いのち」は「身体と心」あるいは「今生」のことです。こんなことをするのはどうかと思いますが、一度、「いのち」という言葉を「身体と心」という言葉に入れ替えて、この詩を読んでみますね。
「身体と心」が 一番大切だと 思っていたころ
生きるのが 苦しかった
「身体と心」より大切なものが あると知った日
生きているのが 嬉しかった
いかがでしょうか。「いのち」というものを「身体」と「心」のことだと思っていたときには、「身体」の自由を失って取り返しのつかないことになったと、生きているのが苦しかった。でも、「いのち」の真実に気づいてみると、あの苦しみは、「身体」を自由にできなくなった「エゴ」の苦しみだったんだ。「身体」の自由を失って「死にたい」と思ったのは、あれは、本当の「私」ではなく、私の「身体」を握りしめていた「エゴ」だったんだ。この詩からは、そんな気づきが伝わってくるような気がします。
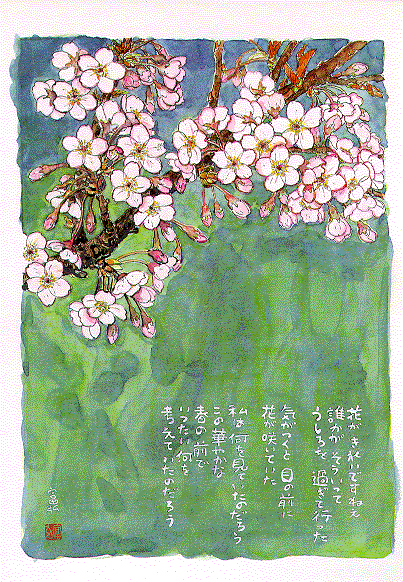 次は、こんな詩です。
次は、こんな詩です。
花が きれいですねえ
誰かが そういって
うしろを 過ぎて行った
気がつくと 目の前に
花が咲いていた
私は何を見ていたのだろう
この華やかな
春の前で
いったい何を
考えていたのだろう
「花が きれいですね」と言って通り過ぎて行ったのは、神様だと思いますね。神様の声を聞いて、「ひとつの全体」としての「命」を回復したとき、初めて、目の前に広がっていた世界の美しさに気づいたということではないでしょうか。
 また、こんな詩もあります。
また、こんな詩もあります。
わたしは傷を持っている
でも その傷のところから
あなたのやさしさがしみてくる
何も説明はいらないと思います。
「身体」は治る場合もあれば、治らない場合もあるでしょう。ですが、「身体」は治らなくとも、「真実の世界」に触れると、人は癒されていくのです。「癒し」という漢字は、もともと、「心のしこりがとれる」という意味だそうです。「心のしこり」とは、「エゴ」のことです。「現実世界が全てだ」と、「身体」にしがみついている「エゴ」がとれると、「一如」の光が「身体」にまで射し込み、「命」は本来の輝きを取り戻すのです。
人生には、喜びの絶頂から絶望の谷底に突き落とされるようなこともある。そんなとき、私たちは、「どうしてこんなことが起こるのか、なぜ自分だけが」と悩み苦しみます。
しかし、「どうして自分にこんなことが起こるのか」ということは、結局は、分からないのです。「目に見える現実世界が全てだ」と考えて、「心」を支配し、「身体」を握りしめている「エゴ」には分からないのです。
それでは、「救いは無いのか」と言えば、そうではありません。「命」の真実の姿を知り、「命」に無条件の信頼を寄せたとき、人は癒され、救われていくのです。
もうひとつ、別の人の詩をご紹介いたします。「心のチキンスープ」という本で読んだことですが、ニューヨークのあるリハビリ研究所の受け付けの壁に、南北戦争の頃の無名兵士が書いたという、こんな詩が掛かっているそうです。「苦しみを超えて」という題の詩です。
「苦しみを超えて」
大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、
謙遜を学ぶように弱い者とされた。
より偉大なことができるように健康を求めたのに、
よりよいことができるようにと病気を戴いた。
幸せになろうとして富を求めたのに、
賢明であるようにと貧しさを授かった。
世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、
神を求め続けるようにと弱さを授かった。
人生を享受しようとあらゆるものを求めたのに、
あらゆることを喜べるようにと命を授かった。
求めたものは一つとして与えられなかったが、
願いはすべて聞き届けられた。
神の意に添わぬものであるにも拘わらず、
心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。
私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。
大切なのは、この作者の気づきを詠った部分です。「謙遜を学ぶように弱い者とされた、よりよいことができるようにと病気を戴いた、賢明であるようにと貧しさを授かった、神を求め続けるようにと弱さを授かった、あらゆることを喜べるようにと命を授かった、願いはすべて聞き届けられた、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた、私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ」。
さきほどの星野さんも、この詩の作者も、お二人ともキリスト教徒ですが、キリスト教徒であれ仏教徒であれ、人はみな、同じなんですね。現実を超えた「真実」の世界に気づいて、初めて命が輝き、救われていくのだと思いますね。
「私が、私が」と言っている「私」は、「エゴ」なのです。「私がこれをする、私があれをする」と言うのをやめて、「おまかせします。何であれ、起こることが起こりますように」と、全てを受け入れる準備が整ったとき、そこに自然に癒しが始まり、救われていくのです。
「全てを受け入れる」。それは、「私が必要とすることではなく、私に必要なことが起こってくる。私が必要とするものではなく、私に必要なものが与えられる」という、「命」への無条件の信頼です。
ですが、「無条件の信」というものは、努力によって得られるものではありません。「無条件の信」というのは、「真実の世界」から訪れ来たるものなのです。そんな「信」を、真宗では、「賜わりたる信」と言っています。
親鸞聖人の御一代記であります『御伝鈔』に、親鸞聖人が吉水の法然上人のもとにおられたころのエピソードとして、こんな話しが伝わっております。
あるとき「信心」について法然上人のお弟子たちの間で議論が起こりました。そもそもの発端は、親鸞聖人が、「法然上人の御信心と、私の信心は、いささかもかわるところなく、同じものだ」とおっしゃったことにあります。
これに対して、他のお弟子たちは、「師匠の信心と弟子の信心が同じだなどと言うのは、はなはだ不遜だ」と非難する。ところが、親鸞聖人は、「なるほど、智慧や学識が師匠である法然上人と同じだと言ったのなら、これは不遜だ。だが、こと他力の信心に関しては、師匠の信心も私の信心も同じだ」と、譲らないのですね。
そこで、とうとうお師匠様に聞いてもらおうということになりました。他のお弟子がたは、「ひとつ、こいつの思い上がりを師匠にたしなめてもらおう」と思われたのでしょうが、案に相違して、法然上人は、こうおっしゃった。「自力の信心なら、人それぞれ智慧によって違いがあろうが、他力の信心は阿弥陀如来より賜わりたる信心であるから、弟子の信心も師匠の信心もなんら変わるところはない」と。
この事件を「信心一異の諍論」と言いますが、こういう議論が本当にあったかどうかは別といたしまして、信心とは、まさしく「賜わるもの」だと思います。それは、たとえば、こういうことです。
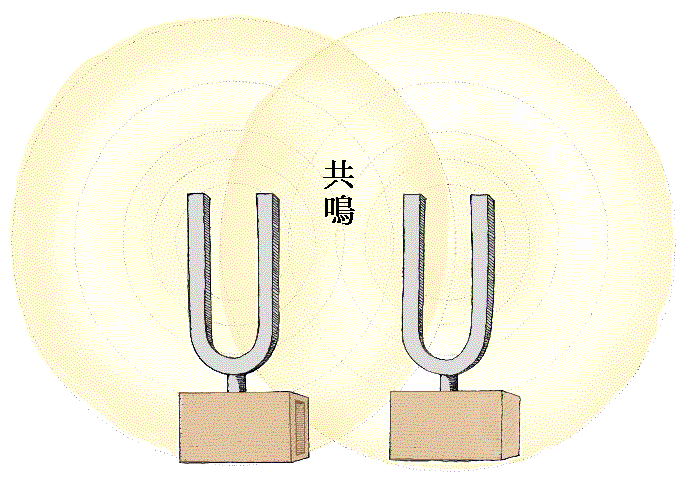 これは、以前にも一度使いましたが、理科の実験などで用いる「音叉」です。これをバチでたたくと固有の振動数で音を発します。同じ振動数の音叉を二つ並べてその一方をたたくと、もう一方が共鳴して音を発します。振動数の違うものなら共鳴を起こしません。
これは、以前にも一度使いましたが、理科の実験などで用いる「音叉」です。これをバチでたたくと固有の振動数で音を発します。同じ振動数の音叉を二つ並べてその一方をたたくと、もう一方が共鳴して音を発します。振動数の違うものなら共鳴を起こしません。
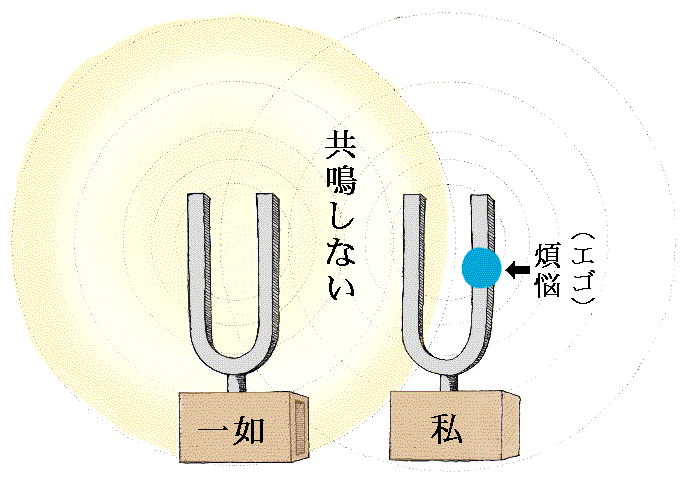 こちらの音叉が「一如」、もう一方の音叉が「私」だとしますね。人は本来「一如」ですから、みな「一如」と同じ振動数を持った音叉のようなものです。ですが、自他を区別する「エゴ」が「心」にくっついているものですから、本来なら起こるはずの「一如」との共鳴が、起きなくなっているのです。こんな具合にです。
こちらの音叉が「一如」、もう一方の音叉が「私」だとしますね。人は本来「一如」ですから、みな「一如」と同じ振動数を持った音叉のようなものです。ですが、自他を区別する「エゴ」が「心」にくっついているものですから、本来なら起こるはずの「一如」との共鳴が、起きなくなっているのです。こんな具合にです。
ですが、「お念仏」を唱える生活のなかで、「私」の「心」にくっついている、この「エゴ」が落ちていけば、必ずこんなふうに共鳴が起こります。「信心」というのは、この共鳴のことです。私の音叉の音は、この「一如」の音叉から賜ったものです。私は、信心を賜って、初めて「本当の自分」になるのです。そして、そのとき、「どうして自分だけが」という問いも、自然に消えていくのです。
私は、誰もが「心」の奥底では「本当の自分」を求めていると信じています。ですが、同時に、その「本当の自分」こそ、私たちが無意識のうちで最も恐れているものでもあるのです。というのは、私たちは、「エゴ」を「自分」だと思っているからです。私たちの「心」を乗っ取った「エゴ」は、本来の主である「本当の自分」が帰ってくることを恐れているのです。そんな「エゴ」と争わず、そんな「エゴ」を鎮める智慧が、「お念仏」です。
「エゴ」が鎮まっていくにつれて、「一如」からの呼び声が聞こえてきます。そのとき、自然に生まれてくるのが「信心」です。ですから、「信心」とは、「一如」から賜りたるものなのです。「賜りたる信心」に、師匠の信心も弟子の信心もありません。「一如」からの呼び声が聞こえてきたとき、人は永遠に変わります。それを、仏教では、「不退の位に入った」と言います。
ここから上の「身体と心」の世界には、自他の区別があります。つまり、「現実世界」には、自他の区別がある。自他の区別があるところで働くのは、「自力」です。「自力」で選び取る「信心」は、自分の利益のためのものです。
「私はあなたを信じます。宜しくお願いします」と言っても、結果が思うようにいかないと、「何だ、あいつを信じたのは馬鹿みたいだ」ということになる。しかし、神や仏というのは「一如」のことです。「一如」には、敵も身方もないのです。
「他力の信」「自力の信」というのは、仏教だけではなく、どの宗教でも言えることです。たとえば、第二次世界大戦のとき、沢山のユダヤ人が強制収容所で悲惨な体験を強いられましたが、その体験を通して、信仰を深めた人もいれば、信仰を捨てた人もいた。これもまた、「他力の信」「自力の信」に関わる問題だと思います。
ドイツのマイスター・エックハルトという人が、こういう言葉を残しています。「喜びに照らされた瞬間にだけ神を認めようとする人がいる。だが、彼らが見ているのは喜びや輝きだけであって、神ではない」。「じっさい人は、暗闇のなかにいるときこそ、光を見出すものだ。それゆえ悲しみの底に沈んでいるとき、私たちは光のもっとも近くにいるのである」と。
たしかに、健康なとき、裕福なとき、自分に都合のよいことが起こっているときに、神や仏を讃えることは誰にでもできます。ですが、その反対に、病気や貧困に苦しんでいるとき、自分に都合の悪いことが起こっているときに、神や仏の光を身近に感じることは、なかなかできないのですね。
そんなとき、たいていは、人から慰められ、励まされて、「人生って、こんなものだ」とあきらめ、「エゴ」が「現実」と折り合いをつけて終わっていくのです。ですが、まさに、そんな暗闇に覆われている「私」だからこそ、「人生って、こんなに素晴らしいものだったのか」と、気づかせてもらえる世界がある。それが、「信心」の世界なのです。
私は、「人は死んでも終わらない」「人生には意味がある」と信じております。「人は死んでも終わらない」「人生には意味がある」。この気づきが、私の信心の出発点でした。
ですが、実は、「人は死んでも終わらない」というだけでは、さほど意味がありません。というのは、「人は死んでも終わらない」と知っただけでは、「エゴ」は相変わらず元気だからです。それまでは、今生が全てだと、まるで運動場の鉄棒にしがみつくように「身体と心」にしがみついていた「エゴ」が、「また来世があるさ」と、力をゆるめて休憩するようになるだけです。これでは、救いではなく、慰めにすぎません。
大切なのは、「人生の意味」です。私は、「命の真実」に気づいていくこと、「本当の自分」になっていくことが、「人生の意味」だと信じています。ですがこれもまた、私が自分で気づいたことではなく、さまざまな「ご縁」によって、気づかせて頂いたことです。
「魂」というのは、私たちの「命」のなかで、私たちが「生まれてきた理由」を担っている部分です。私たちは、理由があって、この物質世界に生まれるべくして生まれてきたのです。ですから、この物質世界をしっかりと生きていかねばなりません。
ですが、以前にもお話しいたしましたように、私たちが生まれかわり死にかわり「輪廻転生」を繰り返しているのは、「命の真実」への気づきを深めながら、「一如」の世界へと帰っていくためです。
ですから、本当は、物質的なことも、社会的なことも、「身体」も「心」も、生まれることも、死ぬことも、そして「煩悩」さえも、全ては、私たちが「命の真実」に気づいていくための「ご縁」なのだと思います。「しっかり生きていく」というのは、その「ご縁」に、しっかり気づいていくことを言うのです。
私たちに共通して言えることは、誰かが気づいていけば、その気づいていく姿によって、必ず他の誰かが気づいていくということです。たとえば、さきほどの星野さんが、「命の真実」に気づいて、癒され、救われていく。その姿を見て、私たちもまた、気づき、癒され、救われていくのです。
「ご縁」を得て気づき、自分が「本当の自分」になっていく。生まれてきた役割を果たしていく。それが「ご縁」となって、また、他の人が気づき、救われていくのです。「ご縁」というのは、さまざまな思惑や感情で絡み合っていることを言うのではありません。「一如」をめざす一本の糸で結ばれていることを「ご縁」と言うのです。
私たちは、自分の力で気づいていくのではありません。「ご縁」を頂いて、気づかせてもらうのです。「一期一会」とは、その「ご縁」との出会いを言うのです。
「ご縁」によって自分が気づいていく姿を「往相」と言います。また、他の人が気づいていく「ご縁」になる姿のことを「還相」と言います。私たちは、みな、「一如」の世界をめざす「菩薩」として、この「往相」と「還相」のために生まれてくるのです。
しかし、ときには、今生での役割として「還相」だけを選んで生まれてくる人もいます。つまり、他の人が気づいていく「ご縁」になるためだけに生まれてくる尊い人です。そういう人を、「還相の菩薩」といいます。
こういう話をいたしますと、あるいは誤解を招くかもしれませんが、先日、こんな経験をしました。バイクで寺役に出ていたときのことです。小さな交差点で、赤信号で止まりました。そこへ、心身に障害を持った高校生くらいの男の子が、ジャージをはいた若い女の保護士さんに手を引かれて、目の前の横断歩道を渡っていく。いつもなら、「エゴ」が騒いで目をそらせていたかもしれませんが、その日は何故かじっと見つめていたのです。
目はうつろなんですが、顔は苦しみに満ちた恐ろしい表情をしている。「ああ、あの人は、何と苦しい人生を選んできたのだろう」と、心が暗くなった。その瞬間、その心の暗闇のなかに「還相の菩薩」という言葉がひらめきました。思わず、胸がいっぱいになって手を合わせそうになりましたが、そのとき、信号が青に変わり、車のクラクションの音で「現実」に引き戻されてしまいました。
交差点を渡ってからも、しばらく胸が熱かった。それまでにも、心身に障害を持った人々の姿には何度も接してきたはずです。ですが、私はその日、初めて「還相の菩薩」に出会ったのです。
思えば、高校への道で出会った救急車で運ばれていた人も菩薩です。星野さんに、「きれいな花ですね」と声をかけた人も菩薩です。人の出会いに偶然はない。出会いは、全て聖なるものです。ですが、そういう「ご縁」に気づかせてもらえるのも、また、「一如」の働き、「他力」のおかげなのですね。
病気のときに得た気づきは、健康になったときに、問い直される。健康なときに得た気づきは、病気になったときに、また、問い直される。そうして、気づきが深まっていく。そうやって深まっていく世界を支えているのが、「お念仏」です。この「お念仏」が無ければ、ただ、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」というだけに終わってしまいます。
「お念仏」は「本当の自分」を回復する智慧です。「お念仏」を唱える生活のなかで、私たちは「ひとつの全体」に戻るのです。「一如」の光が、「心」という煩悩の川を越えて「身体」を満たしつくし、「ひとつの全体」になる。そのとき私たちは、世界と「ひとつ」になり、対立するものを無くすのです。
「私が必要とすることではなく、私に必要なことが起こってくる。私が必要とするものではなく、私に必要なものが与えられる」。全てはおまかせなのだと気づいたとき、自然に肩から力が抜けて、晴れやかな明るい気持ちになるのです。
そして、その気づきをつきつめていくと、来世があろうと、無かろうと、それもまた、おまかせで、何の文句もないようにさえ思えてくるのです。
私たちは、いずれ死んでいきます。たとえ、今、「健康」で「生き甲斐」があったとしても、いずれ死んでいくのです。いくつまで生きたとしても、やはり死んでいく。そんな限りある命として、同じ限りある人の世を眺めたとき、対立している「あの人」さえも、いとおしいのです。
私たちの「命」の底には、感情とも呼べないような、それでいて感情としか呼べないような、深い「悲しみ」の感情が流れているように思います。
この「悲しみ」は、「ひとつの全体」になっていない悲しみです。この「悲しみ」に共感し、この「悲しみ」を共有することが「慈悲」だと、私は思います。仏教で言う「悲願」とは、この「悲しみ」の「願い」のことです。いや、「悲しみ」の「願い」といったのでは適切ではありません。この「悲しみ」が「願い」なんです。
「ひとつの全体」になっていない「悲しみ」は、「ひとつの全体」になりたい「願い」です。その「悲しみ」と「願い」は、私たちが意識できないほど深いのです。この深い「悲しみ」は、個人的な喜怒哀楽の感情を越えた、生きとし生けるものの共有する涙です。
たとえばそれは、何十年ぶりかに肉親との再会を果たした中国残留孤児の涙です。この「心」までのレベルでいえば、肉親との再会は喜びであるはずです。「心」は、嬉しくて嬉しくて仕方がない。ですが、そこに自然にあふれ出てくるのは「涙」です。私は、この涙は深い「悲しみ」から流れ出た涙、「悲願」の涙だと思います。
私が「本当の私」になっていない悲しみ、私があなたになっていない悲しみ。「ひとつの全体」になっていない悲しみ、それは、私が「私」になりたい願い、私があなたになりたい願い、「ひとつの全体」なりたい願い。それが「悲願」です。ですが、それは、「私」という「エゴ」の悲しみでも願いでもなく、「一如」の悲しみ、「一如」の願いなのです。私たちが「阿弥陀様」と呼ばせていただいていますのは、この「一如」のことです。
「人は、歳をとると涙もろくなる」と言いますが、歳をとると、それだけ、人の悲しみが分かるようになるということでしょうね。確かに、人には、歳をとらないと分からないことが沢山あります。ですが、「身体」と「心」にしがみついて歳をとっただけでは、分からないこともあるのです。そのことを教えているのが、仏教なのですね。
さて、本日の話は、ここまででございます。毎回、皆様の前で、分かったような顔をして、お話しさせて頂いておりますが、実は、私も分からないのです。そんな頼りない私ではございますが、「人生って、こんなに素晴らしいものだったのか」と、ともに頷きあえる日を願って、お同行の皆様とご一緒に「お念仏」の道を歩ませて頂ければと、心より念じております。
次回は、11月24日の「報恩講」でございます。どうぞ、また、お運び下さいますよう、お願い申しあげます。本日は、長い間、お付き合いくださいまして、有り難うございました。
【謝辞】
今回の法話には、「星野富弘詩画集絵はがき」より、作品3点を引用掲載させて頂きました。作者ならびに出版社に御礼申し上げます。星野富弘さんの作品(絵はがき等)をご希望の方は、下記の出版社にご連絡ください。合掌
グロリア・アーツ株式会社
213 川崎市高津区宇奈根 731-6
TEL 0120-33-5472, FAX 0120-833-044
紫雲寺HPへ