おそらく現在でも、「お釈迦さま」は物語のなかの登場人物であって歴史的人物だとは思っておられない方もおられるかと思います。ましてや、釈尊の御骨が現存していて、その一部が日本に在るなどという話は、容易には信じがたいかもしれません。実は学問の世界でもほんの百年ほど前まで、仏陀釈尊の歴史的実在が疑われておりました。その釈尊の歴史的実在を確証することになったのが、今回お話しします仏舎利(仏陀の遺骨)の発見です。
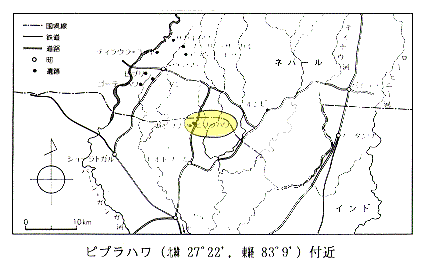 イギリスがインドでの覇権を確立し、ビクトリア女帝がインド女王として君臨していたころのことです。1898年、地方行政官であったイギリス人ウイリアム・C・ペッペが、インドのネパール国境近くに位置するピプラハワ村の自分の荘園内にあった仏塔を発掘し、一枚岩をくりぬいた砂岩製の大石櫃(132 x 82 x 66cm,696kg)を発見したのです。そのなかには水晶製舎利容器(1個)と滑石製舎利容器(4個)、それに数百点の金銀宝玉や装身具類が収められていました。
イギリスがインドでの覇権を確立し、ビクトリア女帝がインド女王として君臨していたころのことです。1898年、地方行政官であったイギリス人ウイリアム・C・ペッペが、インドのネパール国境近くに位置するピプラハワ村の自分の荘園内にあった仏塔を発掘し、一枚岩をくりぬいた砂岩製の大石櫃(132 x 82 x 66cm,696kg)を発見したのです。そのなかには水晶製舎利容器(1個)と滑石製舎利容器(4個)、それに数百点の金銀宝玉や装身具類が収められていました。
水晶製の舎利容器(高さ8.9cm,直径8.3cm)は、蓋の把手が魚の形をしていて、魚の胴体の中空部分に金箔製の装飾品が封入された、古代のものとは思えないほど見事な器でした。それだけなら単なる古代の仏塔の発掘で終わったのですが、骨片を収めた滑石製の舎利容器のひとつ(高さ15cm,直径10cm)に、西紀前数世紀の文字で「これは釈迦族の仏・世尊の遺骨の龕であって、名誉ある兄弟ならびに姉妹・妻子どもの奉祀せるものである」と刻まれていたものですから、学界に一大センセーションを引き起こすことになりました。それまでの学界では、『法華経』などの大乗仏典に記されている一種荒唐無稽な物語から、フランスのエミール・スナールの太陽神話起源説とか、キリストと仏陀を同一視した木村鷹太郎のギリシャ神話起源説など、仏陀を神話的産物と見てその実在を疑る向きもあったからです。これで仏陀の歴史的実在に疑問をはさむ者はいなくなりました。またこの発見によって、『大般涅槃経』等に見られる仏骨分配や造塔供養の記述がただの物語ではないことも明らかになったのです。
ペッペ氏はそれら発掘品をイギリス政府に寄贈することにしました。政府はその処置について審議を重ねたすえ、神聖なる釈尊の遺骨は仏教国であるシャムの王室に寄贈し、宝物は一部をカルカッタ博物館に、他の一部をロンドン博物館に、残りをペッペ氏に返還することにしました。かくして1898年(明治32年)、発掘された仏舎利がシャム王室の手に帰すると、時の国王は、その聖遺骨をさらにビルマ(現在のミャンマー)、セイロン(現在のスリランカ)、および日本の仏教徒に分与することに決めたのです。終始その斡旋の労をとったのは、時のシャム公使、稲垣満次郎氏でした。稲垣公使が仏教各宗派の管長にこの旨を伝えると、日本仏教界は大騒ぎになるのですが、この続きの仏舎利奉迎の様子次第に関しましては、次回にお話し申し上げようと思います。
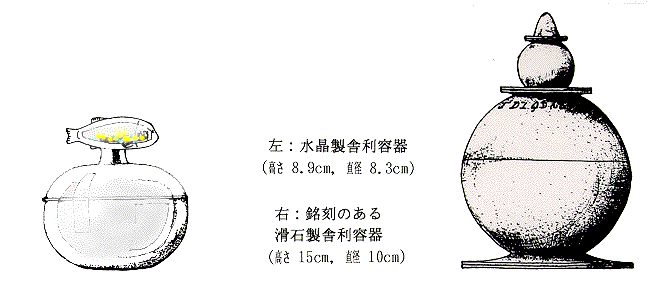
紫雲寺HPへ