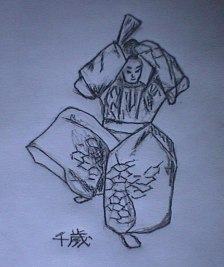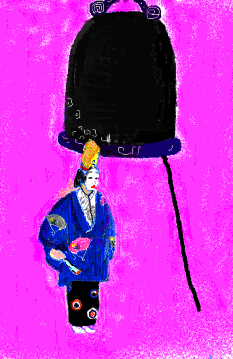謡曲について 能のことも
|
能楽鑑賞の手引き 1−−翁・岩船を例に
|
|
|
山姥の舞で名声を得た百万山姥(ひゃくまやまんば)という都の遊女が善光寺にお参りします。旅路の情景が美しく謡われ、旅行記を辿るように「有乳の山」、「玉江の橋」、「汐越」と近くの名所が出てきます。やがて越後越中の境界にある境川に着き、輿を下りて徒歩で「上げ路」の山に差し掛かりますと、急に日が暮れてきます。そこへ一人の女が現れ、宿をしようと申し出ます。女の庵に泊まりますと、女は山姥の歌を聴きたいから泊めたのだといいます。驚く旅人に、女はあなたは山姥クセ舞で有名になったのに、本当の山姥の事を考え、心に掛けたことがないだろう、その恨みを言いに来たのだと言うのです。遊女は恐れ直ぐにも歌おうとしますが、山姥は月の出るのを待てといい、その時には自分も舞うと言って消え失せます。 |