ギリシア語文献に見る
|
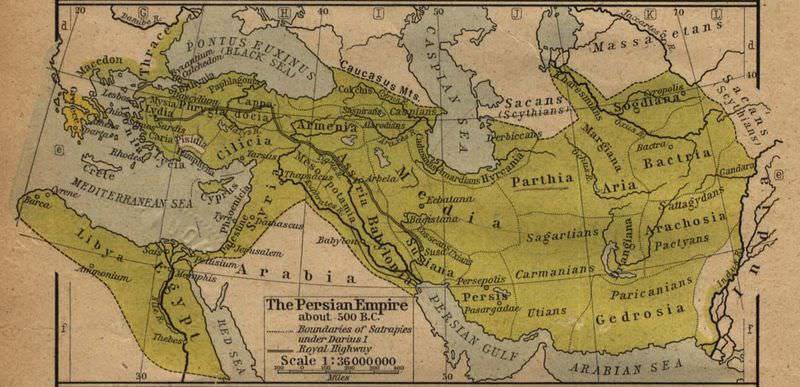
ゾロアスター教の故地
ゾロアスター教は、宗祖がはっきりしている世界最古の宗教である。
宗祖ゾロアスターの原形は、ザラスシュトラ。これをギリシア語でゾーロアストレースZwroavstrhVと音写した形の、さらに訛った形である。「ザラスシュトラ」の意味ははっきりしないが、伊藤義教は、「愚癡の法然坊」と自称した法然、「愚禿」と自称した親鸞を例に挙げながら、これを卑称「老いぼれ駱駝の持ち主」と解釈し、「ゾロアスターは敢えて自己を貧者の位置に引き下げ、結果としては彼らの代表となった」としている(「名詮自称『ゾロアスター』」、『ゾロアスター教論集』p.28)。
しかし、宗祖ゾロアスターが生きた年代そのものも、ゾロアスター教の伝承に基づいて、前630-553年とする研究者、紀元前1500-1200年紀とする研究者があり、一定しない(伊藤義教は、伝承どおり、前6世紀とする)。
ゾロアスター教の故地についても、諸説あって一定しないが、ゲラルド・ニョリは次のように云う。
さて、今日では、アルカイックな宇宙論の要素を再構成することができる。 とりわけ、ヴューダに見られる古代宇宙誌との比較、あるいはもっと広く考え て、インドの古代宇宙誌との比較によって再構成することができる。
近頃、ソ連の二人の学者G・M・ボンガルド=レヴィンとE・A・グラントフス キーは、非常に入念な著作を公刊したが、それによれば、「(北欧)的表象を ことごとくつなぐ文化圏が認められるが、その文化圏は……北極点に近い地域 に住んでいたこれらの北方民族とじかに接することによってのみ形成されえ た」という。
この二人の学者によれば、北欧がインド=イラン神話圏に入ることは、「ア ヴェスターのイラン人」と「ヴェーダのインド人」の祖先、すなわちアーリヤ 人が南東ヨーロッパでフィン=ウゴール語族の人々と隣接していたことによっ ても説明がつく。「このように、インド=イラン人の先祖たちは北欧の聖なる 山、北欧の海、(北極)のことなどについて話すのを聞いたのであった」。
したがって、本質的に神話的な地理をインド=イランの共通な考え方に帰す ることができよう。たとえば、アヴェスクーの中のハーラー山や、インドの メール山またはスメール山〔須弥山〕という考え方、イランのケシュワルやイ ンドのドゥヴィーパといった大地を七つの地域に分ける考え方、イランのカニラサやインドのジャンプードゥヴィーパといったある中心地域の考え方、イラ ンではハーラー山の南のウォルカシャ海中にある「すべての種の樹」、および インドのメール山の南にある(ジャンプーの樹)という考え方などである。こ こにはまさしく、ある共通するアルカイックな遺産にまで 遡る神話的要素や、インドとイランの比較の可能性を著しく増大させるような その他の細部に富んだ神話的要素が見られる。しかしながら、これらの要素 が、インダス河を境とするこのアーリヤ族の二支派〔イラン語族とインド語 族〕の移動から生じた二次的な混同現象が広まったことによって歴史的地理と 混ざり合うということもありえよう。
ヒンドゥークシュからパミール、ヒマラヤへと連なる巨大な山塊が、アヴェスターのイラン人とヴェーダのインド人、そして彼らの子孫にも等しく固有な このような現象を大いに促進することができたのは確かであろう。これらの大山脈の寒さといえばたいへん厳しいものであり、アーリヤ族の古代宇宙論と地理とを、北欧や北極の要素のいくつかと新たに同一視させることができた。
この最後の考察は、イランの(アイリヤナ・ワエージャフ)(Airyana Va[e]jah)を裏づけるという*難問*にとって、とても重要である。その十箇月におよぶ冬については、J・マルクヴァルトのような、古代および中世イラン の歴史地理の著名な専門家の説があるが、それでも、たとえばホラズミアの気候によるよりも、山の気候から説明する方がずっともっともらしく思える。つ まり現在のアフガニスタンの山の高さは、故国を想起するにはぴったりだった のである。(『ゾロアスター教論考』、p.105-106)
かのイランの予言者ゾロアスターが生き、活動した歴史的環境を再構成し ようとする場合、目を向けなければならないのは、ホラズミアよりもっと南で あろう。ゾロアスター教資料や、アヴェスター、パフラヴィー語資料およびギリシア語資料といった出所の異なる資料全体が、もし改めて分析され、的を射 た方法で調整されるなら、注意の目はヒンドゥークシュ周辺の地域とこの山脈 の南麓に広がる土地へ、要するに古代のドランギアナとアラコシアおよび古代 パクトリアとのあいだの地域へと向けられることになろう。
アヴェスターの歴史地理は、一まとまりになった範囲を一つだけ提示してい る。地理に関する資料を含む章節はさまざまであるが、そこに矛盾は見られな い。地域はだいたいにおいて一致している。東イラン高原の中南地帯がそれで ある。<……>ホラズミアのことをほのめかしているようなところはほとんどな い。加えて、ホラズミアというのは明らかに中世イラン語形の名称である。さ らに上記の四資料は、とりわけヒンドゥークシュ山脈地帯およびヘルマンド川 とその流域にっいて執拗に語っているだけでなく、そこにはかなり綿密な地理 の記述も見られる。そのような記述は、<……>パフラヴィー語資料の中にも同 じように指摘することができる。(同上、p.110)
ゾロアスター教の教義
ゾロアスター教は、それまでの伝統的な宗教を批判したところに成立した宗教改革の宗教であった。しかし、それが広く流布してゆくには、伝統的宗教と習合してゆかねばならなかった。ここに、ゾロアスター教の正体を見極めることを難しくしている。そこで、ゾロアスター教の要点を挙げれば、次のようになるであろう。
ザラスシュトラの新教の中心的な思想は、「ガーサー」にその輪郭をみるこ とができる。
第一はダエーワ(デーウ=邪悪なる偽りの神々)への祭祀、牛とハオマの供犠を禁じたことである。古き遊牧社会の経済の基礎をなしていた牛を、戦士的な支配集団はダエーワへの供犠として大量に屠っていたのである。彼らは牛を、「ヤスナ」の表現をかりれば「虐待と暴行でしめつけていた」のである。
牛の供犠はまたハオマ(酒)〔後述〕の供犠と 不可分のものであり、それらはアエーシュマ(酔乱)〔ギリシア語ではオルギ ア(狂宴)でしょう〕と結びついていた。「血染めの夜祭りを祝う陶酔的なハ オマ儀礼を特徴的に示す語がアエーシュマである」とヴィカンデルはいう (『アーリア人の男性結社』)。肉と酒と「血塗れの梶棒をもつ」酔乱は、戦士社会を支えた暴力的な「男性結社」の旗じるし であった。ダエーワ祭祀の禁止は、すなわちアーリア的な戦士社会の核を抜き 去ることを意味していたのである。つねに生き物のうちで最も危険なものとし て非難されてきた「両足の狼」こそ戦士結社の若者組の仮装の特徴であったの である。
<……>
第二はアフラ・マズダーを文字通り、いっさいを知り給う(マズダー)主 (アフラ)として、唯一の最高神として、その分神(大天使=アムシャ・スプ ンタ)とともに敬うことである。光と闇、天と地、世界の運動、昼夜のめぐり を創造し給うたのはこの神であり、アシャ(天則=正義)、ウォフ・マナフ (善思)、アールマティ(随心)の父なる神であった。
唯一神の信仰を説きながら七柱の分神(大天使)の存在を認めたのは、古い社会のインド=イラン的な多神教の信仰を内側から変革するためには、既存の 思考の塾を透写し、模倣しながら、神々の性格を、唯一神の意志と啓示にふさ わしい魂に置き換えることが有効であると考えられたゆえではなかったかとい う。デュメジルの意見(『大天使の誕生』一九四五年)である。
第三はアフラ・マズダーを双生の対立する二霊、スプンタ・マンユ(聖霊) とアンラ・マンユ(破壊霊)のうち前者の父としたことである。なぜならスプ ンタ・マンユは始元においてアシャ(正義)を選び、アンラ・マンユはドゥル ジ(不義)を選んだからである。人間も、そのいずれかを二霊にならって選び とるのである。二元論を一神論へと切り換えるのは選取する者の意志なのであ る。
第四に、人間は死ぬと、その魂はそのどちらを選び取って生きたかを調べら れる「検別者の橋」(チンワトの橋)へと送られるとした。検別者によって良 いと認められた魂塊が橋をこえて歌の館へと導かれ、不義と断ぜられた邪悪な 魂は不義の館へと、陪黒の中にびきずり落とされる。しかし「ガーサー」は、 その後の魂のゆくえについては暗喩にとどめている。すぎまじい地獄が出現す るのは、ササン朝以後のパフラヴィー語書においてである。
第五は、やがてダエーワ(偽りの神々)は打ち負かされ、救世主サオシュヤ ントが現われ、劫火による神判(神明審判)ののち人間の復活が行なわれ、生 まれ変わった新しい世界で一切智のアフラ・マズダーが勝利して輝くとする。(前田耕作『宗祖ゾロアスター』(ちくま新書108、1997.5.)、p.154-157)
ハオマ
 これはインドの「ソーマ」(おそらく同語源)に相当する。
これはインドの「ソーマ」(おそらく同語源)に相当する。
そのハオマがいかなる飲み物であったか、はっきりしないが、現在4種類ほどの薬草が推測されている。伊藤義教は、麻黄科麻黄属の一種 Ephedra gerardiana〔左図〕ではないかと推測している。(「ゾロアスターとハオマ」、『ゾロアスター教論集』p.467以下)
伊藤義教のあげた Ephedra gerardiana はパキスタン原産の麻黄で、東アジアには主として E. sinica, E. distachya などが分布する。<……>『本草綱目』には、味に麻性あり、色が黄色いのでその名があると書いてある。見たところはトクサに似た、高さ50センチメートルほどの多年生草本で、根が赤い。茎はほぼ直立し、菓はほとんど見えないほど小さい。初夏のころ黄色い花をつける。
<……>
薬理学的にいうと、中枢神経興奮、交感神経興奮様作用、発汗、利胆、抗炎症、抗アレルギー作用などが知られている。試みにマオウの水性エキスをマウスに飲ませると、マウスは自発運動を亢進させ、動きがはげしくなる。
マオウのエキスからは主成分エフェドリンが分離されており、エフェドリンを取り除いてしまったマオウエキスは、もはや上述したような作用を発現しない。だから、前述したようなマオウの薬理作用はほとんどエフェドリンの作用にあてはまる。
<……>エフェドリンは、側鎖にある水酸基(OH)をひとつ取り除くだけで、メタンフェタミンに変換される。この化合物は、メチル基の少ないアソフェタミンとともに、"白い粉の恐怖"として世間を騒がせている覚醒薬、薬の中の悪の親玉である。
これら覚醒薬の作用はまさにエフェドリンのそれと類似するが、最も著しい作用としては、交感神経興奮様作用よりもむしろ精神興奮作用があげられる。カフェインよりも少量で精神、運動性の興奮をもたらし、呼吸中枢も興奮させる。この作用は神経末端でノルアドレナリンを大量に放出させるために生ずるとされる。中枢系興奮のために眠気や疲労感を除去し、多幸感をもたらす。精神発揚につられて、つい耽溺し、中毒してしまう場合が多い。多用すると習慣性におちいり、必要量は10〜30倍にまでなる。慢性中毒としては精神分裂症状をひきおこし、幻覚をみる。狂暴、妄想、人格欠損が特徴とされる。いちどきに大量をとると、急性中毒症状として、めまい、ふるえ、不眠、幻覚、錯乱を生ずる。
ハオマ酒は、まさに古代の覚醒剤として、おそらくはあかあかと燃えあがるゾロアスターの炎の前で用いられたのにちがいない。(山崎幹夫『毒の話』中公新書781、p.89-91)
ハオマはいかにして作られるか。『アヴェスター』のヤスナ書には次のよう にあるよし。
1−8章(一切諸神を勧請する祭文から成る)を読誦するうちに、ハオマ液が作られる。いわゆるパラグラ儀式(Paragra)である。パラグラ儀式とはハオ マ液の最初の搾りとハオマ液の作成で、具体的に言うと、ハオマ草の枝を聖水で洗い、石榴の一枝といっしょに搗き砕いて漉し、その漉した液を一頭の牝山 羊だけの乳とまぜる。こうしてハオマ液ができあがる。
(伊藤義教『ペルシア文化渡来考』p.91からの孫引き)
伊藤義教は、ゾロアスターの否定したハオマと、アヴェスターの云うハオマとを同じものとして考えているらしい。
ヘーロドトス『歴史』第1巻132章によると、犠牲獣はギンバイカの床の上に寝かせられ、そしてマゴスが枝の束で犠牲獣に触れた後、その喉を切り裂く。その時、マゴスは讃歌を歌いながら、オリーヴ油と乳と蜂蜜を混ぜ合わせた潅奠を 大地に注ぐという。これらの行いがゾロアスター教的でないのはまったく明白である。にもかかわらず、新層アヴェスターの中に記述されている儀式とよく類似しているゆえに、これまで間違って解釈されてきたのである。すでに指摘したように、植物の葉の床はヴ ェーダのバルヒシュとよく類似している。他方、現代の解釈者たちは、アヴェ スターの〈ハオマ〉の地位を占めるこの不可思議とも言える供物を説明する段に至ると、ある種の難問にぶつかってしまうのだが、彼らはなんとしてもこれ がハオマと照応するものと考えようとする。
ところが、この不可思議な供物は 容易に説明がつく。乳とオリーヴ油と蜂蜜を混ぜ合わせた潅奠は、バビロニア人の祭儀における儀礼の一部であり、たとえば、バビロニアでアキートゥ祭〔バビロニアの国家的行事。新年祭ザグムックと習合して重要 な祭儀となった〕が祝われるときに、それが調合されるのである。(バンヴェニスト、p.50)
 Barbaroi!
Barbaroi!