公園づくりが共振し続ける |
これはだいぶ前の体験なのですが、ある都営住宅の建て替えに伴う公園改修の際に、近隣の小学生にも声かけをして「どんな公園が欲しいですか?」というやり取りをしたことがあります。「ブランコ」「ジャングルジム」「砂場」……子どもたちから返ってくる意向表明の味気ないことに驚いて、「エッ!そんなものでいいの?」と聞き返しました。すると「だっておじさん、さっき“公園”って言っていたじゃない?!」と言うのです。「あー、確かにそうだったよね」と言いつつも、「そうか、公園というのは、既にこういった規定の要素を組み替える程度の場としてしかイメージされていないのだ。……」と。コレは深刻だと思いました。つまり世の中で公園というものはあまり創造的な存在になっていないのです。
「公園はまだまだ数も面積も十分でない」と言いながらも、全国的にたくさん整備されてきています。ところがその持ちうる魅力が発揮されず、活かされていない公園を眼にすることも少なくありません。例えれば住まい手のいなくなった家屋が幽霊屋敷のように感じられるのと同じように、もぬけの殻のような公園があるのです。これは大いに問題にしていきたいところです。空間にとっても市民生活にとっても、まちづくりにとっても大変もったいないことだからです。
「みんなのものは誰のものでもないという公共」は、もうお仕舞いにしていきましょう。それぞれの使い手を意識したうえでの公共を構築していく時代を迎えています。こういった時代において参加型公園づくりは、公園を環境とする主体としての市民を形成していく取り組みとして期待されているのです。
1996年の川づくりのワークショップで「未来の絵日記」という方法を思いついて以来、わたしは「みんなで……」という参加型のまちづくりなどに「絵日記」を多用しています。絵、数値、文字という多様な表現手段が込められた絵日記は、「情景を表現することができる大変優れた意向表現手法」だからです。言葉だけで聞いていた「砂場」も、絵日記という情景表現の中では「具体的な形態」「周辺施設などとの位置関係」「イメージされている使われ方」などなど、たくさんの情報を伴って発信されます。そして絵日記によって共有される情報からは、形態としての具体像と共に関わりとしての生活像が見えてきます。
参加型公園づくりでは、その取り組みの熟度が上がり具体的な公園づくりのイメージが像を結んでくるようになると、「これをしたいという願いを実現できるものづくり」「これをすることのできるしくみづくり」、さらには「こういった暮らしの実現に向けた公園づくり」へと話題が徐々に広義に渡り、そして抽象化していきます。そして丁度専門家がコンセプトとか基本的な考え方と言っていることと同じように、公園づくりを価値として共有しはじめることになります。
それは生活者としての迫力が伴っているからであろうと思います。また、こういった基本的な考え方に辿り着いてからの公園づくりでは、これら2種類のデザインが共振していく可能性がとても高くなります。そして生活者である市民が見出した公園づくりの価値を大切にした生活を営み続ける限り、これら2種類のデザインならびに市民生活と公園づくりは共振し続けていくのではないでしょうか。
公園が関心を寄せられる存在になること
「住民参加の公園づくりとは、とてもすばらしいことですね」と多くの人が評価します。では一体何がすばらしいのでしょうか。民主主義のプロセスとして重要であるから、利用者からの情報や意向を把握できるから、開園後の運営管理体制づくりに繋げられるから……等々、いろいろな観点があります。きっとこれらは、取り組み方如何によっていずれにも可能性があると思います。
公園づくりを我がこととして受けとめる主体が生まれること
一体誰がまちづくりの主人公なのでしょうか?公園づくりでも同じです。全ての問いを一度ここ集約させないと次が始まらないと思っています。

ではどうしてこのようなことが繰り返されるのでしょうか?これまでの公園の使い手の想定が、大変ラフ(きめ細かさを欠いたもの)であったこと、また改修計画においてすらコレまでの使い手とやり取りをすることは希であったことが一因であると思います。法律の上で公園は、公共の福祉の増進に資する都市施設の一つになりますが、これからは都市生活者の施設と受け止め直していった方がよいと思います。「新しい公共」が唱えられ「協働」という言葉が定着し始めた昨今においては、量の確保から質の向上、そして公共の福祉の実現に向けて市民と行政とが協働で工夫する時代を迎えています。公園計画ならびにデザインにおいても、「標準」という言葉で表現される一般解としての整備理念や、一人当たりの整備面積という達成目標の世界から脱却して、もっと丁寧な姿勢、つまり具体的な使い手を意識して取り組む工夫が求められています。
情景をやり取りしながら共有される世界を紡ぎ出すこと
参加型の公園づくりで、「何がほしいですか」という問いかけが墓穴になることは先に挙げた通りです。「砂場」「滑り台」の話のように、公園づくりを「ものづくり」に終始させてしまうことのないように工夫することが大切です。

参加型公園づくりでは、現場を歩いてその特徴を語り合い「パークライフ絵日記」を一人で何枚も描いてもらいます。すると公園づくりイメージの交換という楽しいおしゃべりをしながら、だんだんとそこの場の限界や可能性や課題が共有されてきます。そしてはじめは、アレがほしい、コレがほしいと「ものの議論」をしていても、だんだんとアンナコトできたらいい、コンナコトもしてみたいと、「アクティビティの交換」にもなってきます。絵日記を通じて公園づくりを情景づくりとして交換することによって、「ものづくり」から「ことづくり」へと活用アイデアが拡がって、生活主体者としての公園活用イメージの楽しい連鎖反応が起こり始めます。共振に繋がる生活世界の共有化が参加型公園づくりで始まるのです。
生活に結びついた価値から営みがデザインされ続けること
公園づくりのデザインには2種類あってこれらの関係が上手く展開したときに公園づくりは生き生きとしてくると考えています。一つは、素材、形態や空間に関するハードウェアとしてのフィジカルデザインです。そしてもう一つが行為、ルール、システムなど、ソフトウェアに関するもので「営みのデザイン」と呼んでいます。
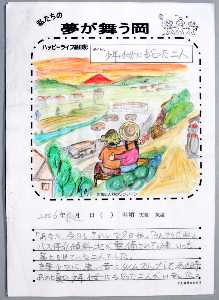
主体者である市民とのやりとりで見出された公園づくりの基本的な考え方(価値)には説得力があります。
菅博嗣(すが ひろつぐ)。
1959年東京都文京区生まれ。3児の父。千葉大学園芸学部造園学科卒業。登録ランドスケープアーキテクト(RLA)。技術士(都市及び地方計画)。
(社)日本造園学会学術委員。NPO法人日本冒険遊び場づくり協会理事。
「市民参加型事業に専門家はどのように参加すればよいのか?!」「参加者の少ない参加型事業での検討意義をどう評価するのか?!」等々、数々の参加型事業を通じて悩んできた経験を生かして、1999年より古河総合公園パークマスターに着任し公園づくりの新システムを構築する。
代表的なプロジェクトとして「立野公園の公園づくり(構想から実施設計、一部工事管理)」東京都練馬区、「「国分川の川づくり」千葉県松戸市など、「世田谷区公園配置計画(調査から計画)」東京都世田谷区など。
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
このページへのご意見はJUDIへ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
学芸出版社ホームページへ