参加型デザインの実践
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
参加型デザインの実践(レポート・トーク)を聞いて
榊原和彦(大阪産業大学)
 私は実践編を聞かせていただきました。 まず、 それぞれがご苦労されながらまちづくりを進めておられることに敬意を表したいと思います。 みなさんがされていることに学者的な立場から軽々しく論評するのはどうもと思うし、 やりにくい面もあるのですが、 しないわけにいかないので、 まずどう考えていけばいいのかを枠組みとして捉えてみました。
私は実践編を聞かせていただきました。 まず、 それぞれがご苦労されながらまちづくりを進めておられることに敬意を表したいと思います。 みなさんがされていることに学者的な立場から軽々しく論評するのはどうもと思うし、 やりにくい面もあるのですが、 しないわけにいかないので、 まずどう考えていけばいいのかを枠組みとして捉えてみました。
参加型環境デザインについて

|
|
図1
|
 まずは住民参加型のデザインとは何なのかをはっきりさせたいと思い、 図1の枠組みを用意しました。 この定義をご覧下さい(図1)。 ここでは参加型のデザインを行政機関(環境デザインにおける意思決定権者)のよりよい意志決定を目的とした、 住民、 専門家、 行政機関の情報共有およびコラボレーションにもとづく計画・デザインの営みのこととしています。
まずは住民参加型のデザインとは何なのかをはっきりさせたいと思い、 図1の枠組みを用意しました。 この定義をご覧下さい(図1)。 ここでは参加型のデザインを行政機関(環境デザインにおける意思決定権者)のよりよい意志決定を目的とした、 住民、 専門家、 行政機関の情報共有およびコラボレーションにもとづく計画・デザインの営みのこととしています。
 まずその目的自体が、 その主体を行政、 住民、 専門家、 あるいは市民社会全体に考えた場合では違ってきます。 例えば市民社会を主体に考えると、 環境デザインの目的は「公共の福祉」といった抽象的なものになりがちで、 どうも不明快だと思います。
まずその目的自体が、 その主体を行政、 住民、 専門家、 あるいは市民社会全体に考えた場合では違ってきます。 例えば市民社会を主体に考えると、 環境デザインの目的は「公共の福祉」といった抽象的なものになりがちで、 どうも不明快だと思います。
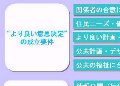
|
|
図2
|
 私はやはり、 行政を主体に考えた方がいいように思うのです。 そうすると、 おそらく住民参加には3つの要素があげられると思います。 「よりよい意思決定」「情報共有」「コラボレーション」です。 図2の「よりよい意思決定」の成立要件の中に「関係者の合意に基づいていること」「住民ニーズ・価値観を反映していること」等をあげていますが、 住民主体の目的はこの中に入れることができるだろうと考えます。 公共機関としては、 公共計画・デザインとしての整合性は重要でしょうし、 また、 こういうことが実際にはどうなっているかを、 実践事例で検証していくことは必要でしょう。
私はやはり、 行政を主体に考えた方がいいように思うのです。 そうすると、 おそらく住民参加には3つの要素があげられると思います。 「よりよい意思決定」「情報共有」「コラボレーション」です。 図2の「よりよい意思決定」の成立要件の中に「関係者の合意に基づいていること」「住民ニーズ・価値観を反映していること」等をあげていますが、 住民主体の目的はこの中に入れることができるだろうと考えます。 公共機関としては、 公共計画・デザインとしての整合性は重要でしょうし、 また、 こういうことが実際にはどうなっているかを、 実践事例で検証していくことは必要でしょう。
 それと情報共有に関しては「情報公開」という言葉がよく出ますが、 それは、 基本的には行政情報・専門家情報を住民に知らせることであって、 必要なのは、 それだけでなく、 住民情報を行政に持っていくことであり、 あるいは、 情報の相互交換も要ります。 それら全てを含めて情報共有と言うことにします。 それがどうなっているかの検証も必要でしょう。
それと情報共有に関しては「情報公開」という言葉がよく出ますが、 それは、 基本的には行政情報・専門家情報を住民に知らせることであって、 必要なのは、 それだけでなく、 住民情報を行政に持っていくことであり、 あるいは、 情報の相互交換も要ります。 それら全てを含めて情報共有と言うことにします。 それがどうなっているかの検証も必要でしょう。
 コラボレーションについては、 合意を形成する場面、 問題を定義・分析し解決策を探る場面、 それに加えて重要なのは良いデザインを創造する場面、 そういう諸場面から成り立っていることと考えています。
コラボレーションについては、 合意を形成する場面、 問題を定義・分析し解決策を探る場面、 それに加えて重要なのは良いデザインを創造する場面、 そういう諸場面から成り立っていることと考えています。
3つの実践事例について
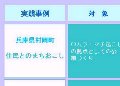
|
|
図3
|
 以上のようなことを考えながら、 今日の3つの事例を事前にインターネットで公表されていたレジュメを見て、 その対象とか目的・アプローチ・手法などが何なのかを考えたのが図3です。
以上のようなことを考えながら、 今日の3つの事例を事前にインターネットで公表されていたレジュメを見て、 その対象とか目的・アプローチ・手法などが何なのかを考えたのが図3です。
 村岡町の場合はムラ・マチ起こしの拠点としての公園づくり、 東灘区岡本地区の場合はまちづくりのルールを決めてからものづくりをする、 六甲道南地区の場合は震災復興の再開発計画を進めるなど、 が住民参加の対象であって、 その対象のもとに住民参加の目的がそれぞれあるわけです。 実際今日の生の声を聞くと、 それぞれの実践に特徴のある目的があって、 個性あるまちづくりをしていることが分かります。
村岡町の場合はムラ・マチ起こしの拠点としての公園づくり、 東灘区岡本地区の場合はまちづくりのルールを決めてからものづくりをする、 六甲道南地区の場合は震災復興の再開発計画を進めるなど、 が住民参加の対象であって、 その対象のもとに住民参加の目的がそれぞれあるわけです。 実際今日の生の声を聞くと、 それぞれの実践に特徴のある目的があって、 個性あるまちづくりをしていることが分かります。
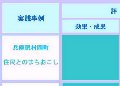
|
|
図4
|
 まとめとしては、 本来は実践の効果・成果や問題点は何なのか、 また住民参加の課題としてあげられたのは何かを述べ図4を埋めてゆくべきなのですが、 ここでは簡単に感じたことを申し上げます。
まとめとしては、 本来は実践の効果・成果や問題点は何なのか、 また住民参加の課題としてあげられたのは何かを述べ図4を埋めてゆくべきなのですが、 ここでは簡単に感じたことを申し上げます。
村岡町の実践
 まずは村岡町の実践について。 ここのポイントは住民自体の活性化であったろうと思います。 これは公共機関の側から住民を巻き込んでいくイベント型の事業ですから、 どれだけ住民を刺激することができたのかが、 私が興味深く思った点です。
まずは村岡町の実践について。 ここのポイントは住民自体の活性化であったろうと思います。 これは公共機関の側から住民を巻き込んでいくイベント型の事業ですから、 どれだけ住民を刺激することができたのかが、 私が興味深く思った点です。
 うかがったところ、 大成功だったという感じを受けました。
うかがったところ、 大成功だったという感じを受けました。
 また、 もうひとつ興味深かったのは、 参加したアーチストがこの共同作業を通して意識や制作に対する態度が変わったかどうかです。 コラボレーションの結果としてアーチスト自身も変わっていくのが本来の姿だろうと思うのですが、 その辺がどうだったのかに興味を持ちました。
また、 もうひとつ興味深かったのは、 参加したアーチストがこの共同作業を通して意識や制作に対する態度が変わったかどうかです。 コラボレーションの結果としてアーチスト自身も変わっていくのが本来の姿だろうと思うのですが、 その辺がどうだったのかに興味を持ちました。
岡本地区の実践
 続いて、 岡本地区の参加型まちづくりの手法について。 今朝、 日経新聞にまちづくりNPOの話題が掲載されていました。 岡本まちづくり協議会の活動は、 まさしくまちづくりNPOの先駆けだったんだなと思いながら話を聞きました。
続いて、 岡本地区の参加型まちづくりの手法について。 今朝、 日経新聞にまちづくりNPOの話題が掲載されていました。 岡本まちづくり協議会の活動は、 まさしくまちづくりNPOの先駆けだったんだなと思いながら話を聞きました。
 まちづくり協議会にもいろいろな問題点があるというお話でしたが、 あえて評論家風に言うなら、 住民参加のシステムそのものに問題がある、 あるいは、 意思決定システムに問題があり、 そうしたシステム作りの制度に問題があることが考えられます。
まちづくり協議会にもいろいろな問題点があるというお話でしたが、 あえて評論家風に言うなら、 住民参加のシステムそのものに問題がある、 あるいは、 意思決定システムに問題があり、 そうしたシステム作りの制度に問題があることが考えられます。
 現在の協議会はまちづくり条例という制度のもとでの活動にならざるをえないわけですが、 それで果たして十分なんだろうか。 やはり新しい時代に見合った新しいシステムなり制度なりがないと、 こういう住民参加は成功しないと思うのですが、 そのあたりはどうなんだろうと思いました。
現在の協議会はまちづくり条例という制度のもとでの活動にならざるをえないわけですが、 それで果たして十分なんだろうか。 やはり新しい時代に見合った新しいシステムなり制度なりがないと、 こういう住民参加は成功しないと思うのですが、 そのあたりはどうなんだろうと思いました。
六甲道南地区
 最後に六甲道南地区の震災復興再開発について。 結果としてこの再開発が良かったのか悪かったのかについて一番興味があったのですが、 私は良かったという結論なんだろうと推察しました。 全体として良かったのであれば、 他の再開発すべてに当てはめられてもいいわけです。 また、 これ以前の再開発でもここの場合と同じような問題、 問題点があったとおっしゃっていましたが、 だとするならば今のというか以前のというか再開発制度における住民参加のあり方がちょっとまずいのかもしれません。 震災があったからこそこんな風にうまくいったというのではなく、 通常の再開発でも通用できるやり方にしていく、 これも制度的な問題になるのですが、 そういう所に踏み込んでいかないと広がりが見えてこないだろうという感じがしました。
最後に六甲道南地区の震災復興再開発について。 結果としてこの再開発が良かったのか悪かったのかについて一番興味があったのですが、 私は良かったという結論なんだろうと推察しました。 全体として良かったのであれば、 他の再開発すべてに当てはめられてもいいわけです。 また、 これ以前の再開発でもここの場合と同じような問題、 問題点があったとおっしゃっていましたが、 だとするならば今のというか以前のというか再開発制度における住民参加のあり方がちょっとまずいのかもしれません。 震災があったからこそこんな風にうまくいったというのではなく、 通常の再開発でも通用できるやり方にしていく、 これも制度的な問題になるのですが、 そういう所に踏み込んでいかないと広がりが見えてこないだろうという感じがしました。
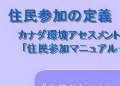
|
|
図5
|
 図5にあげましたように、 住民参加の課題は住民参加システムの成熟化あるいは住民参加プログラムの導入だろうと思います。 以前、 カナダの環境庁編「住民参加マニュアル」を訳した人たちが「参加プログラムをきっちりしておかないと成功しないものだ」と言っておりました。 今後は住民参加の制度をシステムとして整えていくことが必要になってくるだろうという気がします。 今日の日経新聞ではそうした住民参加のまちづくりについて面白い言い方をしていまして「まちづくりNPOは新しい公共である」と言っていました。 それは一体どういう仕組みなのかをもっと議論したいところです。
図5にあげましたように、 住民参加の課題は住民参加システムの成熟化あるいは住民参加プログラムの導入だろうと思います。 以前、 カナダの環境庁編「住民参加マニュアル」を訳した人たちが「参加プログラムをきっちりしておかないと成功しないものだ」と言っておりました。 今後は住民参加の制度をシステムとして整えていくことが必要になってくるだろうという気がします。 今日の日経新聞ではそうした住民参加のまちづくりについて面白い言い方をしていまして「まちづくりNPOは新しい公共である」と言っていました。 それは一体どういう仕組みなのかをもっと議論したいところです。
 私の話はここまでにしておきます。
私の話はここまでにしておきます。
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
このページへのご意見はJUDIへ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
フォーラムメインページへ
JUDIホームページへ
学芸出版社ホームページへ
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ![]() 私は実践編を聞かせていただきました。 まず、 それぞれがご苦労されながらまちづくりを進めておられることに敬意を表したいと思います。 みなさんがされていることに学者的な立場から軽々しく論評するのはどうもと思うし、 やりにくい面もあるのですが、 しないわけにいかないので、 まずどう考えていけばいいのかを枠組みとして捉えてみました。
私は実践編を聞かせていただきました。 まず、 それぞれがご苦労されながらまちづくりを進めておられることに敬意を表したいと思います。 みなさんがされていることに学者的な立場から軽々しく論評するのはどうもと思うし、 やりにくい面もあるのですが、 しないわけにいかないので、 まずどう考えていけばいいのかを枠組みとして捉えてみました。
![]() まずその目的自体が、 その主体を行政、 住民、 専門家、 あるいは市民社会全体に考えた場合では違ってきます。 例えば市民社会を主体に考えると、 環境デザインの目的は「公共の福祉」といった抽象的なものになりがちで、 どうも不明快だと思います。
まずその目的自体が、 その主体を行政、 住民、 専門家、 あるいは市民社会全体に考えた場合では違ってきます。 例えば市民社会を主体に考えると、 環境デザインの目的は「公共の福祉」といった抽象的なものになりがちで、 どうも不明快だと思います。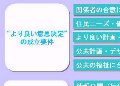
![]() それと情報共有に関しては「情報公開」という言葉がよく出ますが、 それは、 基本的には行政情報・専門家情報を住民に知らせることであって、 必要なのは、 それだけでなく、 住民情報を行政に持っていくことであり、 あるいは、 情報の相互交換も要ります。 それら全てを含めて情報共有と言うことにします。 それがどうなっているかの検証も必要でしょう。
それと情報共有に関しては「情報公開」という言葉がよく出ますが、 それは、 基本的には行政情報・専門家情報を住民に知らせることであって、 必要なのは、 それだけでなく、 住民情報を行政に持っていくことであり、 あるいは、 情報の相互交換も要ります。 それら全てを含めて情報共有と言うことにします。 それがどうなっているかの検証も必要でしょう。![]() コラボレーションについては、 合意を形成する場面、 問題を定義・分析し解決策を探る場面、 それに加えて重要なのは良いデザインを創造する場面、 そういう諸場面から成り立っていることと考えています。
コラボレーションについては、 合意を形成する場面、 問題を定義・分析し解決策を探る場面、 それに加えて重要なのは良いデザインを創造する場面、 そういう諸場面から成り立っていることと考えています。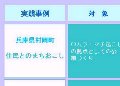
![]() 村岡町の場合はムラ・マチ起こしの拠点としての公園づくり、 東灘区岡本地区の場合はまちづくりのルールを決めてからものづくりをする、 六甲道南地区の場合は震災復興の再開発計画を進めるなど、 が住民参加の対象であって、 その対象のもとに住民参加の目的がそれぞれあるわけです。 実際今日の生の声を聞くと、 それぞれの実践に特徴のある目的があって、 個性あるまちづくりをしていることが分かります。
村岡町の場合はムラ・マチ起こしの拠点としての公園づくり、 東灘区岡本地区の場合はまちづくりのルールを決めてからものづくりをする、 六甲道南地区の場合は震災復興の再開発計画を進めるなど、 が住民参加の対象であって、 その対象のもとに住民参加の目的がそれぞれあるわけです。 実際今日の生の声を聞くと、 それぞれの実践に特徴のある目的があって、 個性あるまちづくりをしていることが分かります。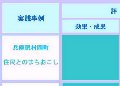
![]() うかがったところ、 大成功だったという感じを受けました。
うかがったところ、 大成功だったという感じを受けました。![]() また、 もうひとつ興味深かったのは、 参加したアーチストがこの共同作業を通して意識や制作に対する態度が変わったかどうかです。 コラボレーションの結果としてアーチスト自身も変わっていくのが本来の姿だろうと思うのですが、 その辺がどうだったのかに興味を持ちました。
また、 もうひとつ興味深かったのは、 参加したアーチストがこの共同作業を通して意識や制作に対する態度が変わったかどうかです。 コラボレーションの結果としてアーチスト自身も変わっていくのが本来の姿だろうと思うのですが、 その辺がどうだったのかに興味を持ちました。![]() まちづくり協議会にもいろいろな問題点があるというお話でしたが、 あえて評論家風に言うなら、 住民参加のシステムそのものに問題がある、 あるいは、 意思決定システムに問題があり、 そうしたシステム作りの制度に問題があることが考えられます。
まちづくり協議会にもいろいろな問題点があるというお話でしたが、 あえて評論家風に言うなら、 住民参加のシステムそのものに問題がある、 あるいは、 意思決定システムに問題があり、 そうしたシステム作りの制度に問題があることが考えられます。![]() 現在の協議会はまちづくり条例という制度のもとでの活動にならざるをえないわけですが、 それで果たして十分なんだろうか。 やはり新しい時代に見合った新しいシステムなり制度なりがないと、 こういう住民参加は成功しないと思うのですが、 そのあたりはどうなんだろうと思いました。
現在の協議会はまちづくり条例という制度のもとでの活動にならざるをえないわけですが、 それで果たして十分なんだろうか。 やはり新しい時代に見合った新しいシステムなり制度なりがないと、 こういう住民参加は成功しないと思うのですが、 そのあたりはどうなんだろうと思いました。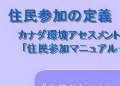
![]() 私の話はここまでにしておきます。
私の話はここまでにしておきます。