まちづくり実践ゼミ
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
共同化(大規模)に関する制度の概要
大塚映二 (神戸市住宅局)
1.共同化に関する補助・支援メニュー
 建築物を共同化する際の補助メニューは、 大きく分けると(1)面的整備事業区域における補助と(2)市内全域で適用可能な補助制度がある。
建築物を共同化する際の補助メニューは、 大きく分けると(1)面的整備事業区域における補助と(2)市内全域で適用可能な補助制度がある。
(1)面的整備事業区域内における補助制度
 第1の面的整備事業区域内における補助制度には、 「住宅市街地総合整備事業」(住市総)と「密集住宅市街地整備促進事業」(密集)の2つがある。
第1の面的整備事業区域内における補助制度には、 「住宅市街地総合整備事業」(住市総)と「密集住宅市街地整備促進事業」(密集)の2つがある。
1)住宅市街地総合整備事業
 住市総事業は、 拠点開発、 たとえば大規模工場跡地等の再開発と一体的に住宅供給を行い、 併せて周辺の住環境整備を行っていくことを目的としている。 神戸市内では、 現在8地区で事業中である。 キャナルタウン兵庫や東部新都心が典型的な地区である。
住市総事業は、 拠点開発、 たとえば大規模工場跡地等の再開発と一体的に住宅供給を行い、 併せて周辺の住環境整備を行っていくことを目的としている。 神戸市内では、 現在8地区で事業中である。 キャナルタウン兵庫や東部新都心が典型的な地区である。
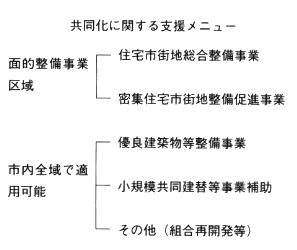
 共同化については、 この制度中「市街地住宅等整備」という項目で補助要件が規定されており、 一定の条件を満たす良好な共同住宅等に対して補助がある。 特に、 震災後の住宅再建にあたり、 合理的・効率的な土地利用を促進するため、 民間の共同化事業に対して手厚い補助となっている。
共同化については、 この制度中「市街地住宅等整備」という項目で補助要件が規定されており、 一定の条件を満たす良好な共同住宅等に対して補助がある。 特に、 震災後の住宅再建にあたり、 合理的・効率的な土地利用を促進するため、 民間の共同化事業に対して手厚い補助となっている。
2)密集住宅市街地整備促進事業
 密集事業は、 老朽化した木造住宅が密集している市街地の更新を図り、 併せて住環境整備を促進することを目的としている。 市内12地区で密集事業に取り組んでいる。 密集事業では、 老朽木造住宅の建て替えを促進することに重点を置いているが、 住市総事業同様に、 共同建替に手厚く補助するしくみになっている。
密集事業は、 老朽化した木造住宅が密集している市街地の更新を図り、 併せて住環境整備を促進することを目的としている。 市内12地区で密集事業に取り組んでいる。 密集事業では、 老朽木造住宅の建て替えを促進することに重点を置いているが、 住市総事業同様に、 共同建替に手厚く補助するしくみになっている。
(2)市内全域で適用可能な制度
 第2の市内全域で適用可能な制度には、 いくつかのメニューが用意されているが、 典型的なものは次の2つである。 一つは、 比較的大規模な共同化を対象とした「優良建築物等整備事業」(優建)であり、 もう一つはこの条件に合わない小規模な共同化を対象とした「小規模共同建替等事業補助」である。
第2の市内全域で適用可能な制度には、 いくつかのメニューが用意されているが、 典型的なものは次の2つである。 一つは、 比較的大規模な共同化を対象とした「優良建築物等整備事業」(優建)であり、 もう一つはこの条件に合わない小規模な共同化を対象とした「小規模共同建替等事業補助」である。
 「住市総」「密集」「優建」は、 いずれも建設省の制度要綱に根拠があるが、 「小規模共同建替等事業補助」は、 『阪神・淡路大震災復興基金』の中の補助制度のひとつであり、 小規模な共同建替・協調建替補助を通じて、 復興支援を行うものである。 補助限度額は、 戸当たり260万円と比較的少額だが、 共同化だけでなく、 隣近所同士で決めた協調建て替えルールにもとづく個別建て替えにも適用可能である。
「住市総」「密集」「優建」は、 いずれも建設省の制度要綱に根拠があるが、 「小規模共同建替等事業補助」は、 『阪神・淡路大震災復興基金』の中の補助制度のひとつであり、 小規模な共同建替・協調建替補助を通じて、 復興支援を行うものである。 補助限度額は、 戸当たり260万円と比較的少額だが、 共同化だけでなく、 隣近所同士で決めた協調建て替えルールにもとづく個別建て替えにも適用可能である。
2.優良建築物等整備事業
(1)事業のタイプ
 補助対象となる事業には、 次の5つのタイプがある。
補助対象となる事業には、 次の5つのタイプがある。
- 共同化タイプ(2人以上の権利者による土地の共同化)
- マンション建替タイプ(被災マンションの建て替え)
- 住宅複合利用タイプ(住宅のほか店舗、 事務所等と複合化したもの)
- 優良住宅供給タイプ(30戸以上の優良住宅供給)
- 市街地環境形成タイプ(敷地内に一定の空地を整備するもの)
 神戸市では被災住宅の再建支援を優先し、 震災後は原則として1)及び2)のタイプに限定している。 以下、 主として1)の共同化の場合について要件等をあげておく。
神戸市では被災住宅の再建支援を優先し、 震災後は原則として1)及び2)のタイプに限定している。 以下、 主として1)の共同化の場合について要件等をあげておく。
(2)採択要件
- 土地を共同利用すること
- 2人以上の土地所有者等(所有権、 借地権、 使用貸借権を含む)が共同で行うこと。
- 2以上の敷地を合わせて、 一の構えをなす建築物を建てること。
- ただし、 2人の場合は、 200m2未満または不整形な敷地を含むこと。
- 敷地面積(震災復興のための特例運用基準※)が一定規模以上あること
- 区域面積(敷地面積に、 接する道路の幅員の1/2の面積を加えたもの)が、 おおむね500m2以上(※通常は1000m2以上)。
- 敷地面積がおおむね300m2以上。
- 被災住宅を含むこと
- 震災により滅失した住宅が存した敷地を2以上含み、 かつ、 事業の実施によりこの住宅の再建を行う場合に限り対象となる。
- 新築建物に関する要件を満たすこと
- 規模:原則として3階建以上。
- 構造:耐火建築物または準耐火建築物。
- 空地:敷地内に一定規模以上の空地を設けること。
- 接道:幅員6m以上の道路に4m以上接すること。
- 建設基準に適合すること
(3)補助の内容
 共同化の場合の優建事業補助の内容は、 以下の通り。
共同化の場合の優建事業補助の内容は、 以下の通り。
土地所有者の同意状況
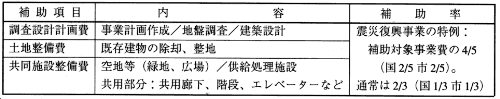
 全体事業費に占める補助金の割合は、 おおむね10〜20%程度である。
全体事業費に占める補助金の割合は、 おおむね10〜20%程度である。
3.終わりに
 共同化には大変なエネルギー=熱意と労力が必要であり、 共同化に参加する住民の方々はもちろん、 専門家の努力に負うところが大きい。 専門家のみなさんの活躍に期待したい。
共同化には大変なエネルギー=熱意と労力が必要であり、 共同化に参加する住民の方々はもちろん、 専門家の努力に負うところが大きい。 専門家のみなさんの活躍に期待したい。
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
このページへのご意見はいきいき下町推進協議会へ
(C) by いきいき下町推進協議会
阪神大震災復興市民まちづくりへ
学芸出版社ホームページへ
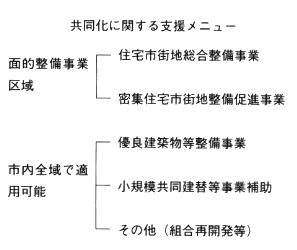
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ![]() 建築物を共同化する際の補助メニューは、 大きく分けると(1)面的整備事業区域における補助と(2)市内全域で適用可能な補助制度がある。
建築物を共同化する際の補助メニューは、 大きく分けると(1)面的整備事業区域における補助と(2)市内全域で適用可能な補助制度がある。![]() 第1の面的整備事業区域内における補助制度には、 「住宅市街地総合整備事業」(住市総)と「密集住宅市街地整備促進事業」(密集)の2つがある。
第1の面的整備事業区域内における補助制度には、 「住宅市街地総合整備事業」(住市総)と「密集住宅市街地整備促進事業」(密集)の2つがある。![]() 住市総事業は、 拠点開発、 たとえば大規模工場跡地等の再開発と一体的に住宅供給を行い、 併せて周辺の住環境整備を行っていくことを目的としている。 神戸市内では、 現在8地区で事業中である。 キャナルタウン兵庫や東部新都心が典型的な地区である。
住市総事業は、 拠点開発、 たとえば大規模工場跡地等の再開発と一体的に住宅供給を行い、 併せて周辺の住環境整備を行っていくことを目的としている。 神戸市内では、 現在8地区で事業中である。 キャナルタウン兵庫や東部新都心が典型的な地区である。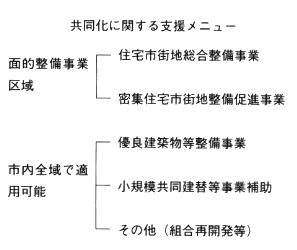
![]() 共同化については、 この制度中「市街地住宅等整備」という項目で補助要件が規定されており、 一定の条件を満たす良好な共同住宅等に対して補助がある。 特に、 震災後の住宅再建にあたり、 合理的・効率的な土地利用を促進するため、 民間の共同化事業に対して手厚い補助となっている。
共同化については、 この制度中「市街地住宅等整備」という項目で補助要件が規定されており、 一定の条件を満たす良好な共同住宅等に対して補助がある。 特に、 震災後の住宅再建にあたり、 合理的・効率的な土地利用を促進するため、 民間の共同化事業に対して手厚い補助となっている。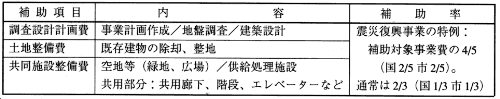
![]() 全体事業費に占める補助金の割合は、 おおむね10〜20%程度である。
全体事業費に占める補助金の割合は、 おおむね10〜20%程度である。![]() 共同化には大変なエネルギー=熱意と労力が必要であり、 共同化に参加する住民の方々はもちろん、 専門家の努力に負うところが大きい。 専門家のみなさんの活躍に期待したい。
共同化には大変なエネルギー=熱意と労力が必要であり、 共同化に参加する住民の方々はもちろん、 専門家の努力に負うところが大きい。 専門家のみなさんの活躍に期待したい。