(2)「命の構造」
さて、本日は、「念仏の道、浄土への道」という題で、お話し申しあげているわけですが、「念仏の道」は、「聞法」に始まり、「廻心」を経て、「浄土」へと続いております。「廻心」とは、一言で申しますと、信心が確立する体験のことです。
まれには、初めて仏法をお聞きになって、即座に信心が確立する方もおいでになるでしょうけれど、一般的に申しますと、「廻心」にまで信仰が深まっていくには、やはりそれなりの時間がかかるものです。蓮如様が、「仏法は若きころたしなむべし」とおっしゃっているのも、そのあたりの事情をふまえてのことではないかと思います。
「聞法」とは、仏の教えを聞くことですが、私たちは、まずは「耳」で聞いておりますね。この、耳で聞いておりますことを「たしなみ」と申します。「たしなみ」というのは、知識や教養として身につけることです。有り体に申しますと、知識や教養は信心ではありません。
ですが、聞法を重ねているうちに、耳で聞いていたものが、心で聞くようになってくる。つまり、自分の問題として、「聞こえる」ようになってくるわけですね。そこからが、信心の世界です。
正しい教えを、何度も何度も、繰り返し繰り返し、聞いておりますうちに、その教えが心の奥底までしみとおるようになる。このことを、仏教では「正聞熏習」と申しますが、では、教えが心の奥底までしみとおったら、どうなるのか。仏の教えが心の奥底までしみとおったら、心の奥底に眠っている「仏性」が目覚めます。この「仏性」が目覚める体験を、「廻心」と言うわけです。
たとえば、仏の教えが光だとしますと、「仏性」は種です。光があたると、種は芽をふきますが、ひとたび芽をふいた種は、二度と再び、もとの種には戻りません。このことを、「正定聚不退の位に入った」と申します。
「正定聚不退の位に入った」ということは、「往生」が保証されたということ、「往生」が保証されたということは、「成仏」が確約されたということです。これが、「聞法」から「成仏」までの大まかな道筋です。
「成仏」というのは「仏に成る」ということです。仏教というのは、「仏の説かれた教え」ですが、それは他ならぬ「仏に成るための教え」なのです。「真宗は往生の教えであって、成仏の教えではない」とおっしゃる方もおられますが、そんなことはありません。親鸞聖人の『浄土和讃』(大経意)にも、「念仏成仏これ真宗」というお言葉があります。
「仏」とは、「目覚めた人」のことを言います。「仏」とは、人間の完成された姿です。人と生まれたものが、人としての完成をめざして生きる。それこそが、人の道ですが、その、人としての完成をめざして生きることを、「信仰に生きる」というのですね。
どんな御宗旨の教えであっても、いやしくも仏教であるかぎり、「仏に成ること」、つまり「成仏」をめざさない教えはありません。とは申しましても、もし、この私に成仏の可能性がないと言うのなら、成仏をめざしても意味がないということになってまいります。ところが、誰にでも成仏の可能性があるのです。そのことを保証しているのが、『涅槃経』にある「一切衆生、悉有仏性」という言葉です。
「一切衆生、悉有仏性」とは、「あらゆる生き物には、ことごとく仏性が有る」という意味です。「仏性」とは「仏に成る可能性」のことです。もしも、私たちが瓦のようなものであるのなら、いくら磨いても宝石にはなりません。宝石の原石だからこそ、磨けば宝石になる。私たちに「仏性」があるというのは、ひとまずは、そういうことだとお考え頂いてよいかと思います。
私たちはみな、仏に成る可能性を、内に秘めているのです。ですが、内に秘めているというのは、これもまた、「目に見えない世界」のことです。ですから、身体のどこかを開いて、「はい、これが仏性です」と、お見せできるものではありません。仏教が分かり難い理由も、そのあたりにございます。
ですが、仏教の理論というものは、たいてい、この「目に見えない世界」で展開されておりますので、そういう世界を少しのぞいてみるのも、仏教を身近に感じるために、役に立つのではないかと思います。そこで、この時間は、その「目に見えない世界」を中心に、お話し申しあげようと思います。
「目に見えない世界」というものは、言うまでもありませんが、この肉眼で見ることはできません。それは、深い瞑想のなかで体験される世界です。「瞑想」というのは、仏教の言葉で申しますと、「禅定」です。
仏教のなかには、その禅定体験に基づいて、目に見えない「心の構造」を専門的に研究した学派がありまして、それを唯識仏教と申します。その唯識仏教によりますと、私たちの「心の構造」は、こんなふうになっていると言われております。
まず、一番表面にあるのは、私たちが見たり聞いたりする心の働き、いわゆる「五感」です。そして、その下に「意識」があります。私たちが通常自覚できるのは、ここまでですが、その下にはさらに、「マナ識」と「アラヤ識」というものがあると言われております。
「マナ識」というのは、私たちの心のなかで、煩悩に支配されている部分です。「煩悩」というのは、「他の誰よりも自分が可愛い」という心の働きを申します。現代の言葉で申しますと、「煩悩」とは、我が身大事の「エゴ」のことです。
その下の「アラヤ識」というのは、私たちのあらゆる経験が貯蔵される場所で、「蔵識」とも呼ばれます。「アーラヤ」というのは、「宿っている所」という意味です。たとえば、インドの北に、万年雪におおわれたヒマラヤという高い山がありますが、あのヒマラヤの「ヒマ」というのは「雪」のことでして、雪が宿っている場所ですから、ヒマーラヤと言うのです。
ちなみに、私たちの経験が貯蔵されているのは、「アラヤ識」の上の部分、ちょうどこの「マナ識」と接しているあたりだけでして、そこから下は煩悩に影響されておりません。そこで、その煩悩とは無関係な部分を「アマラ識」と呼び分けることもあります。「アマラ」とは、「汚れていない」という意味ですので、「アマラ識」は「無垢識」とも呼ばれます。これが、唯識仏教で言う、私たちの「心の全体像」です。
とは申しましても、別に、唯識仏教のお話しをするわけではありませんので、「アマラ識」とか「アラヤ識」といった言葉にこだわって頂く必要はございませんが、この唯識仏教で言われている「心の構造」を、私なりにアレンジして描き直したものがこれでございます。これは「心の構造」と言うよりも、「命の構造」と言ったほうがよいかと思っております。
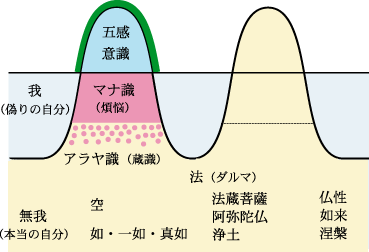 実は、この図は、以前、いろいろ考えておりますときに、思いついたものでして、もともとの唯識仏教とは、多少考え方が違っております。ただ、この図を用いると、仏教のいろいろな理屈がよく分かるものですから、こちらのほうが正しいのではないかと、秘かに自負しておりまして、法話でも、しばしばこれを用いてお話ししてまいりました。
実は、この図は、以前、いろいろ考えておりますときに、思いついたものでして、もともとの唯識仏教とは、多少考え方が違っております。ただ、この図を用いると、仏教のいろいろな理屈がよく分かるものですから、こちらのほうが正しいのではないかと、秘かに自負しておりまして、法話でも、しばしばこれを用いてお話ししてまいりました。
ところが、人の考えることに、それほど独創的なものはありませんで、先日、この図とほとんど同じものが、二十年ほど前にアメリカで出版された本に出ていることを知りました。鈴木大拙先生のお弟子で、フィリップ・カプローという禅の大家の本です。ですから、この図は、私の専売特許というわけではありませんが、なかなか便利なものですから、今回も、これを用いてお話しさせて頂きます。
また、念のために申し上げておきますと、これは、目に見えない「命の構造」を、仮に目に見える形を借りて描いた「モデル」ですので、私たちの「命」が、実際にこういう形をしているということではありません。いわば、この図そのものが、一種の「たとえ話」なのだと、お考え頂きますように、お願いいたしておきます。
さて、この小山のように盛り上がっておりますのが、たとえば「私」です。図全体では、波が並んでいるようにも見えますが、この波ひとつが一人の人間に相当いたします。
一つの波を、青、赤、黄と、三つの部分に色分けしてあります。一番上の青色の部分が、さきほど申しました「五感と意識」に相当します。ここに、水平線のような横線が引いてありますが、ここから上が、「目に見える物質世界」です。仏教の言葉で言えば、「娑婆」です。
この青色の「五感と意識」には、帽子のように緑色の膜が被せてありますが、これは、私たちの「身体」を表しております。「五感と意識」は目に見えません。見えているのは、その「五感と意識」を包んでいる「身体」の方です。ちなみに、この水平線から上の部分は、私たちが死ねば無くなってしまいます。私たちが通常自覚できるのは、ここまでです。
ここにある、私たちの「意識」は、自分と他人を区別する働きを持っております。見分けるということです。自分と他人の区別がつかないようでは、生きていくのに支障をきたしますから、区別できるというのは大切なことです。ですが、「意識」は、区別はしても、差別はしません。「差別」をするのは、その下の「マナ識」です。
さて、この水平線より下は、私たちには自覚できない、いわば無意識の世界です。ここにあります赤い色の「マナ識」は、さきほども申しましたように、私たちの心のなかで、煩悩に支配されている部分です。「煩悩」とは、「他の誰よりも自分が可愛い」という心の働き、我が身大事の「エゴ」のことです。誰の心にも、この「他の誰よりも自分が可愛い」という思いが、多少なりともあるものです。
あるところで、この話をしましたら、「ご院さん、私は自分のことより、孫が大事や」とおっしゃった方がおられます。お気持ちはよく分かりますが、孫が大事と言いましても、それは「我が孫」のことで、他人の孫のことではない。「我が家」であれ、「我が国」であれ、この「我が」という言葉がつくことを「エゴ」と申しますのですね。
「私が、私が」という思いは、みな、この「マナ識」から生まれます。「私が、私が」という、その「私」は、「煩悩に支配されている偽りの自分」のことなのです。私たちは、その「煩悩に支配されている偽りの自分」を、「自分」だと思っている。「本当の自分」ではないものを、「自分」だと思っているのです。それを仏教では、「我執」と申します。
私たちの悩みや苦しみや不安は、みな、この「我執」から生まれてくるわけですが、「煩悩」の話は、よくお聞きになっておられることと思いますので、ここでは、これ以上お話しせずに、先へ進みます。
さて、ではさらに、「目に見えない世界」の奥の院に入っていくことにいたします。「煩悩」に支配されている「マナ識」の下には、「アラヤ識」という、清らかで広大な世界が広がっております。この黄色の部分が、それです。
先にも申しあげましたが、この「アラヤ識」は「蔵識」とも呼ばれ、ここには、私たちのあらゆる経験が貯蔵されております。この図で申しますと、この赤い色の点々がそれです。これを唯識仏教では「種子」(ビージャ)と申しますが、私たちが「宿業」と言っておりますのも、これのことです。
しかし、「アラヤ識」そのものは、「煩悩」に汚されていない清らかな真実の世界です。仏教では、この清らかな真実世界のことを、いろいろな名前で呼んでおります。たとえば、「空」とか、「無我」とか、「如」とか、「一如」とか、「真如」とかいうのも、みな、この世界のことです。
「如」というのは、究極の真理のこと、「法」(ダルマ)のことです。ですから、「アラヤ識」とは、「法」(ダルマ)がいっぱい詰まっている所、つまりは、「法蔵」です。私たちが「法蔵菩薩」と呼んでおりますのは、この「アラヤ識」のことです。
「法蔵菩薩」は、すでに誓願を成就されて、「阿弥陀仏」となっておられる。その「阿弥陀仏」の世界を「浄土」と言うのです。ですから、つまりは、「阿弥陀仏」というのも、「浄土」というもの、また、この「アラヤ識」のことを言うわけです。
先ほども申しあげましたように、「アラヤ識」という言葉にこだわる必要はありません。仏教の目指している世界は、宗派にかかわりなく同じ所なのです。唯識仏教では、命の根底にある「清らかな世界」を「アラヤ識」という言葉で表現したわけですが、その同じ世界を、浄土の教えでは、「阿弥陀仏の西方極楽浄土」という言葉で表現しているのです。
また、私たちの心の奥底に眠っている、問題の「仏性」というのも、この「アラヤ識」のことを言うのです。「仏性」とは、「仏に成る可能性」のことですが、インドの言葉では「ブッダ・ダートゥ」とか「ブッダ・ゴートラ」とか申します。
「ブッダ・ダートゥ」というのは、文字通りに訳せば「仏界」となります。「仏界」とは「仏の世界」のことですから、つまりは、「浄土」です。
また、「ブッダ・ゴートラ」というのは、訳せば「仏種姓」となります。「種姓」というのは、簡単に申しますと、生まれた「血筋」のことです。私たちは、仏の家に生まれている。私たちの命の奥底には「仏の血」が流れている。それを、「仏性」というわけです。
私たちの命の根底には、「アラヤ識」がある、つまり「仏性」があるのです。それはつまり、誰もがみな「仏に成る」可能性を持っているということです。「一切衆生、悉有仏性」とは、このことです。
「仏性」とは、私たちの内にある「如来」のことです。親鸞聖人の『浄土和讃』(諸経意)にも、「如来すなはち涅槃なり、涅槃を仏性となづけたり」とあり、続けて、「大信心は仏性なり、仏性すなはち如来なり」とあります。
親鸞聖人は、「罪悪深重、煩悩熾盛の我が身」には「仏性」は無い、法蔵菩薩が誓願を成就されて阿弥陀如来となられたことが、自分の「仏性」なのだと、おっしゃっているわけですが、この図を見ましても、確かにそうですね。「罪悪深重、煩悩熾盛の我が身」とは、この「マナ識」のことですから、ここには「仏性」はない。「仏性」は、誓願が成就されている世界にある。つまりは、「仏性」とは、この「アラヤ識」のことを言うわけです。
「アラヤ識」とは、「煩悩に支配されていない本当の自分」のことです。つまりは、「本当の自分」は「仏」だということです。禅宗の言葉にも、「自ら自身を観よ。仏は内にあることを知れ。外に向かって尋ねず、即心即仏」とあります。「即心即仏」とは、「本来の心は、そのまま仏である」という意味です。
インドの有名な聖者で、サイババという人がおられます。ご存じかもしれませんね。あのサイババが、ある時、「あなたは神様ですか」とたずねられた。そうしたら、サイババが、こう応えたといいます。「そうです、私は神です。ですが、あなたも神なのです。私は自分が神であることを知っていますが、あなたはそうではない。私たちの違いは、それだけのことです」と。同じことを言っているのですね。私たちは、本当は仏なのです。私たちは、自分が仏であることを知らないだけなのですね。
まあ、ちょっと込み入った話が続きましたので、お疲れになったかと思いますが、もう少しだけお付き合いください。
仏教の話を聞いたり、本を読んだりいたしますと、「自力、他力」とか、「此岸、彼岸」とか、「色即是空」とかいった、分かったような分からないような、難しい言葉が沢山出てまいります。
皆様も、そんな難しい仏教用語のジャングルのなかで、頭を抱え込んでしまわれたことが、おありかもしれませんが、そんな時には、ちょっと、この図を思い出して頂きたいのです。言葉の本当の意味は、体験しないと分かりませんが、理屈だけなら、この図で結構見当がつくことがございます。
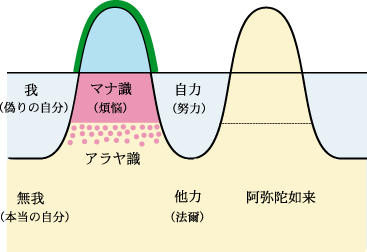 たとえば、「自力、他力」という言葉を例にとってみます。「自力」というのは、「自分の利益」のためにする「努力」のことですから、この「マナ識」の力だということになります。また、「他力」というのは、「阿弥陀如来の力」だと言われていますから、この「アラヤ識」の力のことです。となると、「自力」というのは、「煩悩に支配された偽りの自分」の力であり、「他力」というのは、「煩悩に支配されていない本当の自分」の力だということが分かるわけですね。
たとえば、「自力、他力」という言葉を例にとってみます。「自力」というのは、「自分の利益」のためにする「努力」のことですから、この「マナ識」の力だということになります。また、「他力」というのは、「阿弥陀如来の力」だと言われていますから、この「アラヤ識」の力のことです。となると、「自力」というのは、「煩悩に支配された偽りの自分」の力であり、「他力」というのは、「煩悩に支配されていない本当の自分」の力だということが分かるわけですね。
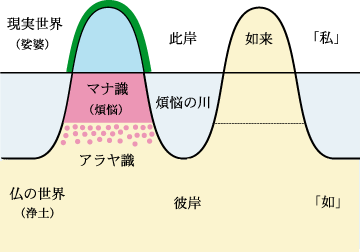 また、「此岸、彼岸」という言葉でも、同じように考えられます。「此岸」とは、私たちの目に見える現実世界のことですから、この図で言えば、この水平線より上の世界です。また、「彼岸」とは「仏の世界」のことですから、この「アラヤ識」のことです。そして、「此岸」と「彼岸」の間には、「煩悩」の川が流れている。となると、その川というのは、この「マナ識」のことですね。
また、「此岸、彼岸」という言葉でも、同じように考えられます。「此岸」とは、私たちの目に見える現実世界のことですから、この図で言えば、この水平線より上の世界です。また、「彼岸」とは「仏の世界」のことですから、この「アラヤ識」のことです。そして、「此岸」と「彼岸」の間には、「煩悩」の川が流れている。となると、その川というのは、この「マナ識」のことですね。
「悟る」というと、私たちは、この「此岸」から「彼岸」に渡ることのように考えがちですが、そうではありません。「煩悩」の流れが鎮まると、「彼岸」から「此岸」へと、「如」が流れ込んでくるのです。そして、「如」が命の全体を満たして「如来」となるわけです。それを、「如から来た」、「如来」というわけです。この横にあります「如来」の絵を見て頂きますと、「煩悩」の川を渡ったのは、「私」ではなくて、「如」の方だということが分かりますね。
こんなふうに、この図は、なかなか便利なものですが、この「命の構造」そのものは、学者が頭で考え出した理屈ではございません。これは、長い長い仏教の歴史のなかで、沢山の優れた仏教徒たちが、瞑想によって心の奥底まで探求し、いわば実際に確認したことなのです。
仏教は、本来、小難しい理論を重視する教えではなく、「禅定」つまり「瞑想」による真理の直接体験を重視した教えです。その禅定に秀でた人を「瑜伽師」と言いました。インドの言葉では、「ヨーガーチャーラ」とか「ヨーギン」とか申します。どちらも、「ヨーガを行ずる人」という意味です。
「ヨーガ」と言うと、一種の美容体操のようにお考えの方もおいでになりますが、そうではありません。「ヨーガ」というのは、瞑想の技術のことでして、もともとは「結び付ける」という意味の言葉です。「結び付ける」とは、何を結び付けるのかと申しますと、「現実」と「真実」、「此岸」と「彼岸」です。つまりは、「悟りの世界」に入るための技術が「ヨーガ」です。
「結び付ける」というと、「宗教」という言葉もそうですね。「宗教」という言葉は、明治時代に、英語の「レ=リジョン」という言葉を翻訳するためにできた言葉です。この「レ=リジョン」という言葉の、もともとの意味は、「再び結び付ける」というものです。つまり、「宗教」というのは、「人」と「神」、「現実」と「真実」の結び付きの回復をめざすものなのです。どんな宗教でも、目指している世界は同じなのです。
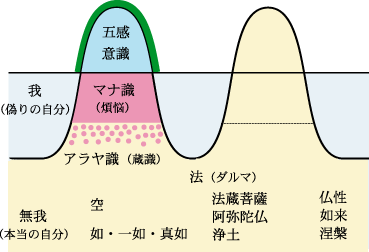 さて、最後に、この図をもう一度ご覧ください。ここから上の、目に見える世界だけで考えれば、私たちは、ちょうど海に浮かんでいる島のようなものです。ひとつひとつの島が、ばらばらに海に浮かんでいる。あなたはあなた、私は私。この「目に見える世界」が全てだとすれば、人生は孤独なものですね。
さて、最後に、この図をもう一度ご覧ください。ここから上の、目に見える世界だけで考えれば、私たちは、ちょうど海に浮かんでいる島のようなものです。ひとつひとつの島が、ばらばらに海に浮かんでいる。あなたはあなた、私は私。この「目に見える世界」が全てだとすれば、人生は孤独なものですね。
孤独というのは、何も、山の中に一人で暮らしていることを言うわけではありません。そうではなくて、日々、沢山の人に囲まれて暮らしていながらも、その誰とも本当の意味で心のつながりがない。何処まで行っても、あなたはあなた、私は私。それが孤独です。そんな孤独が、ときには家庭のなかにもある。現代社会を一言で言えば、そんな孤独な人が群れている社会ではないかと思いますが、いかがでしょうかね。
実際、現代は科学万能の時代ですから、そんな現代社会に生きる私たちは、この「目に見える世界」が全てだと考えるようになってしまいました。そのために、「命」というものの考え方も、全く変わってしまいました。
どう変わったかと申しますと、「目に見える世界」が全てだということなら、たとえば、この「私」という人間は、目に見えるこの「身体」のことだということになります。
科学の世界では、心とか魂とかいった、目に見えないものは、基本的に存在しないと考えられています。たとえば、嬉しいとか、悲しいとかいった感情も、全て、脳のなかを流れる電流や化学物質の働きに過ぎないというわけです。
では、目に見えるこの「身体」が私の全てだとすれば、どうなるのか。当然、「死ねば終わりだ」ということになります。前世もなければ、来世もない。「生まれてきたのは偶然で、死ねば終りだ」ということに、なってまいりますね。
ですが、もしも、「目に見えるものが全てだ」「生まれてきたのは偶然で、死ねば終わりだ」というのなら、そんな人生には、「もともと意味も目的もない」ということになりはしないでしょうかね。
実際、現代社会では、そう考えられていますね。「人生には、もともと意味や目的があるわけではない。だから、私たちは、自分で、人生の意味や目的を見つけだしていかねばならない。生き甲斐を見いだしていかねばならない」。いかがでしょうか。私たちは、たいてい、そんなふうに考えているのではないでしょうか。
しかし、仏教では、そうは申しません。仏教では、こう教えています。「人生には、意味も目的もある。あなたが生まれてきたのは、本当の自分に成るため、仏に成るためだ。それが、あなたの人生の目的なのだ。また、あなたが、あなたの命を生きていくことで、他の人が気づいていくご縁になる、それがあなたの人生の意味なのだ」と。それは、仏教の言葉で言えば、「往相」と「還相」ということになります。
「往相」「還相」の話は、今回はいたしませんが、私たちは、たいてい、そんな生まれてきたことの意味や目的に目覚めておりませんね。ですから、目に見える身体の「健康」が大事、死ぬまで退屈しないための「生き甲斐」が大切ということになるわけです。
確かに、「健康」も大事ですし、「生き甲斐」も大切です。ですが、それが全てではありません。実際、私たちは、健康であって、生き甲斐があっても、どこか満たされないものがある。魂のうずきがある。本当は、そこが大切なところです。
また、ご覧頂いてお分かりのように、私たちの心は、深いところで皆つながっています。つまり、この「アラヤ識」には「自分のアラヤ識」とか「他人のアラヤ識」といった区別はないのです。「自分も他人もない」ということは「無我」だということですが、この自分も他人もない「無我」が「本当の自分」なのです。
私たちはみな、命の根底で、「法」(ダルマ)に支えられている、「如来」に支えられている、「浄土」に支えられているのです。それが、私たちの生命の真実の姿なのです。
目に見える世界で言えば、確かに、私とあなたは、別の人間です。私が物を食べても、あなたのお腹がふくれるわけではない。ですが、目に見えない、命の奥底では、みんなつながっていて、ひとつなのですね。そのひとつの世界、「浄土」をめざして生きることを、「信仰に生きる」と言うのですね。
私たちの人生は、わずか数十年です。私たちは、いくつになっても、なかなか今日で最後かもしれないとは思えないものですけれど、たとえいくつまで生きたといたしましても、いずれは死んでいくのです。
そんな私たちの人生は、川面に浮かぶ「うたかた」のようにはかないものだと、よく言われます。確かに、私たちの人生は、川面に浮かぶアブクのようにはかないものかもしれません。ですが、川面に浮かぶアブクをよくご覧になってくださいね。川面に浮かぶアブクは無から生まれて無に帰っていくわけではありません。川面のアブクは、川の流れから生まれて、また、その川の流れに帰っていくのです。
私たちの人生もこれと同じです。私たちは、無から生まれて無に帰っていくわけではないのです。私たちは「大きな命の世界」から生まれて、また、その「大きな命の世界」に帰っていくのです。「死ぬ」というのは、「身体」という、この束の間の「あぶく」の姿を捨てて、「大きな命の世界」へと帰っていくことを言うのです。私たち門徒が「お浄土」と呼んでおりますのも、その「大きな命の世界」のことですね。
「目に見える世界」は「目に見えない世界」に支えられています。これが、私たちの「命の真実」の姿です。仏教は、この「命の真実」の姿を伝え、「命」の根底にある「目に見えない世界」を目指せと教えているのです。そこには「仏の世界」がある。「浄土」があるのです。
そこで、次の時間には、この「浄土」との二つの関わり方、「廻心」と「往生」について、最近よく話題になっております「臨死体験」の話をからめて、お話し申しあげたいと思います。午前中は、理屈っぽい話が続きましたので、昼からは、もう少し気楽にお聞き頂ける話にしたいと思っております。