C・G・ユング 「錬金術研究」III 精神現象としてのパラケルスス(2/4) |
2 『長寿論』:秘教的教説の解読
169
『長寿論』[001]は理解しにくいところも多少あるけれども、この問題についてある程度、解明の手掛かりを与えてくれる。もっとも、秘儀的用語に隠されている意味合いを掘り起こす努力が必要である。この論文はラテン語で書かれた数少ないものの一つで、文体は奇妙きわまるものではあるが、重要なヒントが数多く含まれているので、それだけいっそう綿密に検討する価値がある。
編者アダム・フォン・ボーデンシュタインは、バーデンヴァイラーの知事ルートヴィヒ・ヴォルフガンク・フォン・ハプスブルク宛の献呈文[002]のなかで、「パラケルススの語るところを口述筆記し慎重に修正を施した」と述べている。これがパラケルススの講義メモにもとづくもので、著者自身の文章でないことは明らかだろう。ボーデンシユタインは、この論文のラテン語とはおよそ異なる達意の文章を書くことのできる人であったところからして、ここで彼は文体上の配慮をいっさい行わず、平易な書き方をする努力をまったくしなかったと仮定しなければならない。でなければ彼自身の文体がもっと混入していたはずだ。彼は多少とも講義内容を原形のまま提示しようとしたと思われる。特に末尾のあたりにその形跡がはっきりうかがえる。講義内容が明確には理解できなかったようすであるが、これは論文の翻訳者とされるオポリーヌスについてもいえることだ。別に驚くにはあたらない。なにしろ師匠自身が、必要な明晰さをまことにしばしば欠いているからである。
そういう事情であるからには、どれだけが理解不能の部分であり、どれだけが思考力の未熟さに起因するものであるかは、なかなか決めにくい。のみならず筆写する際に書き誤りがあった可能性も無視できない[003]。したがって、われわれの解釈の土台となるテクストが最初から不確かなので、多くの問題は推定の域にとどまらざるをえない。しかし独創的な思想家であったとはいえ、パラケルススは錬金術的思考の影響を強く受けているので、過去と同時代の錬金術論文を渉猟し、また彼の弟子や信奉者の著述を参看すれば、いくつかの概念の解釈や脱落部分の復元がかなり可能となってくる。それゆえこの論文の注解・解釈の企ては、さまざまの困難が認められるにせよ、まったく絶望的とはいえないのである。
A イリアステル(星辰的賃料)
170
本論文の主眼は、千年以上の寿命が可能であるという考えに立ち、長寿を達成するのに必要な諸条件を考察することにある。まずここで、秘儀的教説に関連があり、その説明にも役立つ章節をいくつか拾い出しておこう[004]。
パラケルススは最初に生命を次のように定義する。「ヘラクレスによると、生命とはパルサムを含有する秘薬(Mumia)にほかならぬ。それは塩分の混融によって身体を蛆虫や腐敗から守る」[005]。ムーミア(Mumia)とは中世には広く知られていた医薬品であり、古代エジプトのミイラの粉末を成分とするもので、盛んに売買された。パラケルススは、身体が腐敗しないのは「バルサム」の特殊な力とか作用によるとする。これは天然の不老長寿薬のようなもので、身体が生命を維持するのも死体が腐敗しないのも、その働きによるという[006]。同じ論理に立てば、蠍や毒蛇にも必ず解毒の働きが備わっているはずであり、それがなければおのれの毒で死んでしまうだろう。
171
寿命を縮める病気はさまざまであり、これを治すのが先決問題であるから、パラケルススはおびただしい数の秘薬について論を展開する。秘薬のなかで特に重要なのは金と真珠であり、後者は<第五元素>に変成される可能性がある。<ケイリ>(Cheyri)[007]が独特の機能を発揮して、人体という小宇宙をきわめて強力なものにするが、その効能は「人体の生命を保持しつつ、四元素の普遍的構造のなかに一貫して生きつづつけているにちがいない」[008]。したがって、医師の心得ておくべきことは、四元素の「構造」が、「物質的なものによってではなく、物質的なものを保持する力によって単一の構造に集約されるようにする」ことである。これがパルサムであり、四元素を結びつける要であるところの第五元素よりいっそう高い位置におかれる。それは「身体の働き」から生ずるがゆえに、「自然そのものにまさる」[009]。
自然を超える何ものかを、人間の技術が作り出すことができるという思想は、まさしく錬金術的である。パルサムは生命原理であり、<メルクリウスの霊気>であって、これはパラケルススのいう星辰的質料の概念とほぼ一致する。後者は四元素より高位の存在で、人間の寿命を決定する。したがって、それはパルサムとほぼ同じものといってよいが、パルサムは星辰的質料の薬学的、化学的側面を指すとみなすこともできよう[010]。
星辰的質料には三つの形態がある。すなわち不変のもの(Iliaster sanctitus)[011]、調合されたもの(paratetus)[012]、最大のもの(magnus)の三つであり、それらはすべて「小宇宙たる人間に従属し」、「一つの合一体(gamonymus)」を形成しうる。パラケルススは星辰的質料が特殊な「結合力=合一のエネルギー」を持つと見なすので、gamonymus(gavmoV結婚+O{noma名前)という謹めいた概念は、一種の化学の結婚、すなわち両性の確固不動の合体をさすものと解釈しなければならない[013]。
星辰的質料は人間と同じ数だけ存在する。つまりすべての人間のなかに一つの星辰的質料が宿り、それが各個人の資質を独特の形で結合しているのである[014]。したがって、それは一種の普遍的形成原理であると同時に、個性化の原理でもあるように思われる。
B アクアステル(星辰的原水分)
172
星辰的質料(Iliaster)は長寿の秘薬を得るための出発点である。「この作業過程で最も必要なものを、星辰的質料に関して説明しよう。第一に、不純な生命体から元素を分離して浄化しなければならない。それは瞑想することによって行なわれる。この作業の目的は、あらゆる身体的・物理的作用をこえた精神の存在を確認するところにある」[015]。不純な身体は、これによって「一つの新しい形を刻みつけられる」。
173
ここで私はimaginatioを「瞑想」と訳した。パラケルスス的思想の伝統においては、<イマギナティオ>は星辰の能動的な力、すなわち星辰体(corpus coeleste)とか、天上体(corpus supracoeleste)と呼ばれるところの内なる高次の人間の能力を指す。ここに錬金術における心的要因が示されているのである。錬金術師の化学的作業が、同時に想像力にもとづく精神の活動を伴うからである。その目的は、不純物を浄化しつつ精神の存在を「確認(confirmation)することであるからだ。パラケルススの造語confirmamentumはおそらくfirmamentと無関係ではあるまい。この作業の間に、人間は「精神的に向上し、<エノク的半神>の域に達する」[016](エノク的半神とはエノクのように並みはずれた長寿に恵まれる者たちの意)。そのためには、人間の「内部構造」が最高度に熱せられねばならない[017]。そうすることにより不純物が焼き尽くされ、「腐食することのない」真正不動のものだけが残る。
錬金術師は溶鉱炉で化学的物質を熱しながら、精神的に火の苦悶と浄化をくぐることになる[018]。物質に自己を投射し無意識のうちにこれと一体化して、同じ過程を体験する。錬金術師の内なる火が溶鉱炉の火と同じものでないことを、パラケルススはぬかりなく読者に指摘している。この火は「火の精とかメルジーネ的形成原理」以外のいかなるものも含まず、むしろ「あらゆる現実の火のかなたにある生命の中心から、レトルトによって蒸溜されたものである」。<メルジーネ>は水棲生物であるから、「メルジーネ的形成原理」[019]とは、いわゆる「アクアステル」[020](星辰的原水分)を指す。アクアステルはイリアステル(星辰的質料〉の水性、水としての表れであり、身体内の水分に生命を与え、これを保持するからである。
イリアステルが不可視の霊的原理であることには疑いの余地がない。またそれは第一質料(prima materia)のごときものでもある。ただし第一質料は、錬金術用語としてはわれわれのいう物質に対応するものではないのである。錬金術師のいう第一質料とは、<根源的水分>[021]としての水[022]、<水の精気>[023]、<土の発散する蒸気>[024]である。それは事物の「魂」[025]とか「世界の精子」[026]とも呼ばれたし、海の上に生え、たくさんの花を咲かせる楽園のアダムの樹[027]とも呼ばれた。その他にも、中心から生ずる球状体[028]、アダムと呪われた人間[029]、両性具有の怪物[030]、<一>にしてそれ自体根源なるもの[031]、<全>なるもの[032]、などさまざまに呼ばれている。
第一質料に対する象徴的名称はすべて世界霊魂(anima mundi)を指す。すなわち、プラトンの<根源的人間>とか、原人(Anthropos)としての神秘的アダムであり、球体(=完全な全一性〉として形象される。球体は4つの部分から成り(四つの異なる相が統合されている)、両性を具有し(性の区別を超越している)、湿り気をおびている(心的である)。これは自己(self)という説明不可能な人間の全体性を図像として描き出している。
174
アクアステルは霊的原理でもある。たとえば、この力が錬金術師に「神的魔術を探り出す方法」を示唆する。錬金術師自体が、「アクアステルの力を秘めた魔術師」なのである。高度の霊的機能[033]を持つアクアステルは、精霊たち(Trarames)の助けを借りて「大いなる原因」を指し示す。キリストの身体は天上のアクアステルに由来し、マリアの身体は、「天から地に落ちてくる」[034]アクアステルの力を宿した。つまり彼女は星辰的質料の原水分から産み出された。彼女が月の上に立っていたことを、パラケルススは強調する(月はつねに水と関係つけられている)。キリストは天上のアクアステルをおびて誕生した。
人間の頭蓋骨には「アクアステルの裂け目」がある。男性については前額部に、女性については後頭部にある。女性はこの裂付自によって「堕落した(cagastric)アクアステルにさらされ、悪霊に侵されやすいが、男性はこの裂け目を通じて「堕落的な影響を受けるのではなく、超感覚的力を受け入れて、心臓のなかに超感覚的な生命の精気、いわゆるイリアステルの霊気を生起させる」。「心臓の中心に真実の魂、神の息吹が宿る」[035]のである。
175
以上の引用文に照らせば、アクアステルが何を意味するのかは容易に理解できる。イリアステルが力動的な生命の霊的原理として、善と悪をともに許容するように思われるのに対して、アクアステルは、物質に類似した属性を伴う「心的」原理としての色合いが強い(キリストとマリアの身体形成にはこの原理が関与しているからである〉。しかしその心的機能は、霊の世界にかかわる「超感覚的(necrocomic)」(=テレパシー的)働きであり、生命の精気を産み出す場所となるのである。したがってパラケルススの用いる諸概念のうち、アクアステルは無意識という近代的概念に最も近い。とすれば、パラケルススがこれを人格化して人造人間(homunculus)として表象し、かつ魂とは天上的アクアステルであるとする理由も、おのずと明らかになる。
真の錬金術師にふさわしく彼は、アクアステルとイリアステルの働きが、上向的であると同時に下向的でもあると考えた。それは霊的、天上的形態をとるとともに、物質に準ずる地上的形態をもとる。これは『エメラルド板』の次の公理と一致する。「下なるものは上なるもののごとし。されば<一>なるものの奇跡は実現さるべきものなり」。この<一>なるものが賢者の石とか賢者の子である[036]。第一質料の定義や名称からきわめて明白になってくるのは、錬金術における物質が、物質的かつ霊的なものであり、精神が、霊的かつ物質的なものであることだ。物質が「未熟にして不純」、「粗雑にして固く濃密な」のは第一の場合だけであり、第二の場合の物質は「純一繊細」である。パラケルススの考え方もまた、そういうものである。
C アレス
176
アダム・フォン・ボーデンシュタインは、「アレス」の概念をかなり表面的にとらえ、「事物の形態と種を決定する根本的性質」と解釈している[037]。ルランドスはこれをイリアステルや原生命(Archeus)と同じようなものと見なす。しかしイリアステルが存在一般の根本(「万物の発生因」)であるのに対して、原生命は「自然の調合者」(naturae dispensator)ないし「起爆剤」の役割を与えられている。けれどもアレスは「配当者であって、それぞれの種に特有の性質を割り当て、個別的形態を与える」[038]。したがって、それは厳密な意味での個性化原理と見なすことができる。それは超越的な天体から生ずる。
「無から瞬時にして身体的想像力(imaginationem corporalem)を産み出し、堅固な実体を生起せしめるのが、超越的な天体の属性であり本質であるからだ。アレスはかくのごとき働きを持つがゆえに、たとえば人が狼のことを想像すれば、狼が出現することになる[039]。この世界の構造は四元素によって構成される被造物に似ている。事物は四元素から生ずるが、生じた事物はその起源には少しも似ていない。しかもなお、アレス自体のなかに万物の起源がある」[040]。
それゆえアレスは、意識に先立つ生命の創造的形成原理を指す直観的概念であって、これは個々の被造物に生命を賦与する。したがって、イリアステルよりいっそう明確な個性化原理であり、さればこそ自然的人間を火によって浄化し、「エノク的半神」へと変容させる過程で重要な役割を果たすのである。すでに見たとおり、人間が熱せられる火は普通の火ではない。普通の火には「メルジーネ的形成原理(Melusinian Ares)」も「火の精」も含まれていないからである。火蜥蜴(salamander)(=火の精)は錬金術師の火を象徴する。それ自体が火の本質、火の精髄そのものだからである。パラケルススの用語でいえば、<サラマンドリーニ>や<サルディーニ>は火の人間、火の精、火の存在を指す。それらは燃える火のなかにあっても不可蝕不壊であるがゆえに、特に長寿に恵まれると古くから伝えられている。火断腸(=火の精)は「不燃性の硫黄」ともいわれるが、これは賢者の石とか子を産み出す秘儀的実体の別名である。錬金術の作業者を熱する火には、火の本質たる火蜥蜴以外のなにものも含まれていない。火蜥蜴とは、不易不壊の存在たる賢者の子の未成熟な過渡的形態であって、不易不壊の存在にかかわるさまざまの象徴は、結局、自己(self)を指示するものなのである。
178
パラケルススは、アレスに「メルジーネ的」属性を賦与する。メルジーネは水の領域、水の精
の支配下に属するので、この属性は、アレス(それ自体とLては霊的形成原理であるが)の概念の水性を移入することになる。その結果アレスは形而下の物質的領域と関係づけられ、身体と密接に結びつけられることになる。そこでアレスはアクアステルと酷似したものとなり、概念的に両者はほとんど区別できない。
パラケルススにかぎらず錬金術全般におよぶ思考の特色として、定義の明確な概念は何一つなく、ある概念は際限なく他の概念に置き換えられる。ところが、すべての概念が根本命題として打ち出されるので、どれ一つとして、ある概念のさす実体が、同時に他の実体でもありうるなどとは考えられないほどである。原始的思考の典型であるこういう現象は、古代インドの哲学にも見られる。そこでもさまざまの実体的概念がひしめきあっている。神々についての神話がその典型的な例であるが、ギリシア神話やエジプト神話の場合と同じように、同一の神についてまったく矛盾した事柄が語られている。しかしながら、矛盾する点はあるものの、それらの神話群が混乱をきたすことなく併存しているのである。
D メルジーネ
180
バラケルススの思想解釈を進めてゆくうえで、まだ何度かメルジーネを取り上げることになるので、この伝説的生物の本質をここでいま少し詳しく検討し、パラケルススにおいてそれが担う役割を明らかにしておかねばならない。
周知のとおり、女性に擬せられるこの生物はアクアステルの領域に属し、魚とか蛇の尾を持つ水の精である。元来フランスの古い伝説に、ルジニャン伯の始祖、「ルジニャンの太母」として現れる。彼女は土曜日ごとに魚の尾をつけなければならなかったが、ある時、夫がふと魚の尾をつけた彼女を目撃したことから秘密が露見し、ふたたび水中に姿を隠さざるをえなかった。以後ときおり姿を現すのは、災難を予兆する時だけであった。
メルジーネは「水の領域」に住む水の精や海の精と同じ範疇にある[041]。パラケルススは、「不滅の生命力について」[042]で水の精は「悪夢」であると明記し、それに対してメルジーネは血液のなかに宿るとしている[043]。また「小人族について」[044]では、メルジーネはもともと水の精であったが、ベゼルパブにそそのかされて魔力を行使するようになった、という。彼女は、予言者ヨナがその腹のなかで大いなる神秘を見たとされる鯨の子孫であった。この起源は重要な意味を持っている。メルジーネは神秘的なものを孕む子宮から生まれたわけで、それは明らかに今日無意識と呼ばれているものに相当する。
メルジーネは生殖器を持たない[045]。それは天国的存在であることを示す特徴である。楽園におけるアダムとイヴも性器を持たなかった[046]。そのうえ楽園は当時水の下にあったし、「今なおそうである」[047]。悪魔が楽園の木にしのび込んで、木は「悲しみを知り」、イヴは「地獄の蛇」に誘悪された[048]。アダムとイヴは「蛇のために堕落し」、「奇怪な」形になった。つまり蛇の誘事」よって過ちを犯し、その結果、性器を獲得したのである[049]。しかしメルジーネは水の中で生き、楽園的形状をとどめたまま人間の血液中に命脈を保ちつづけた。血液は魂を表す原始的象徴の一つであるから[050]、メルジーネは霊もしくは何らかの心的現象と解釈してさしつかえない。ゲラルド・ドルネウスは『長寿論』の注解のなかでこれを論証し、メルジーネは「人間の意識に現れる幻像」であるという[051]。意識下で行われる心的変容の過程を親しく知っている者であれば、メルジーネは無意識の魂(アニマ)の表象であることがはっきりとわかる。彼女はメルクリウスの蛇の一変形として現れるが、その場合、メルクリウスの怪物的二重性を表現するために、蛇女[052]の形で表されることもあった(図3、4、5参照)。この恐るべき怪物性からの救済は、聖母マリアの被昇天と戴冠の図として描かれてきた[053]。
図3
両性具有者(レーピス)。「聖三位一体と金属変成の秘伝の書」 (1420年)より。(『コデックス・ゲルマニクス』598、fol. l05V. ミュンヘン国立図書館)。この挿絵は『哲学者たちの薔薇園』における両性具有者のモデルになったのかもしれない。 |
図4
永遠の水としてのメルジーネが、ロンギノスの槍で子(キリストの寓意)の脇腹を裂いている。中央の人物はイヴ(大地)で、合ーによってアダム(キリスト)と再び合体する。この合体から両性具有の根源的人間が顕現する。右手に溶鉱炉(アタノール)があり、真ん中の容器から石(両性具有者)が生起する。両側の容器には<太陽>と<月>が入っている(ロイスナー『バンドラ:最も高貴な神の賜物、あるいは聖なる賢者の石』の木版画。パーゼル、1588年、P.249)。 |
図5 |
海(=無意識)から立ち現れる人間を抱擁するアニマとしてのメルジーネ。<魂と肉体との合一>。地の精たちは守護霊の形をとった遊星の霊である(大英博物館の『スローン写本』 5025)。リプレー『スクローレ』(1588年)の異形。 |
E 秘儀的実体としての王の子:ミヒャエル・マイアの教説
181
パラケルススにおけるメルジーネとメルクリウスの蛇との関係について、これ以上詳細に立ち入るつもりはない。ただここで、パラケルススに影響を与えたと思われる錬金術的元型のいくつかを指摘し、魂を求め救済を求めるメルジーネの願望は、海中に深くひそんで解放を求めて叫ぶあの王族の実体と類似していることを示唆しておきたい。この<王の子>についてミヒャエル・マイアはいう[054]。
「彼は海の深みにあって叫ぶ[055]。誰が海の底から私を救い出し、陸に引き上げてくれるというのか。この叫びがたとえ多くの者の耳に届いたとしても、誰ひとり憐みに駆られ、王を捜し出す仕事を引き受けはすまい。誰が海に飛び込むものか、誰がおのれの命を危険にさらしてまで、他人を窮地から救い出そうとするものか、と彼らはいう。悲嘆の叫びを聞き、信ずる者もわずかにはいるが、その声は、舟に襲いかかり難破させるスキュラとカリュブディスの咆哮であると考える。だから家のなかに座って動こうとはせず、王の秘宝にもおのれ自身の救済にも思いいたることがないのだ」。
182
ヒッポリュトスの『反証』(Philosophumena)は、長いあいだ失われたものと見なされていたので、マイアの目にふれたとは思われないが、彼にとってそれが王の嘆きのモデルになったとしても不思議ではないのである。ヒッポリュトスは、拝蛇派(ナーセネス)の秘密の教説を論じて、次のようにいう。
「天上の<無限定な者>(ajcarakthrivston)から下りきたるのが何者であるのか、誰も知らない。それは土くれのなかに見いだされるが、何であるかは誰にも見分けられない。だがこれは大水のなかに住む神なのだ[056]。『詩篇』ではその声が大水の上に響きわたる[057]。大水とは死すべき人間の群れであるとされている、が、そのなかから彼は、無限定な者神に向かって声高く呼びかける[058]、<わが一人娘なる魂>[059]を獅子たちから助け出したまえ[060]、と」。
それに対する答えはこうだ(イザヤ書』43・1以下)。
「ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを造られた主は今、こういわれる。恐れるな、わたしはあなたを贖う。わたしはあなたの名を呼ぶ。水のなかを通るときも、わたしはあなたと共にいる。大河のなかを通っても、あなたは押し流されない。火のなかを歩いても、焼かれず、炎はあなたに燃えつかない」。
ヒッポリュトスはさらに『詩篇』24・7以下を引いて、これをアダムの昇天(a[nodoV)と復活(ajnagevnhsiV)に関連づける。
「『城門よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。強く雄々しい主、雄々しく戦われる主……』。だが栄光に輝く王とは何者か、と拝蛇派は問う。そしてこれは回虫であって人間などではない、人間の忌むべきもの、一族から追放された者だ、というのである」[061]。
183
ミヒャエル・マイアの理解の仕方をたどるのはむずかしくはない。ここには引用しないが、本文のある一節からして明らかなように、彼にとって<王の子>とか<海の王>は、アンチモン[062]を意味する。もっとも彼の用語法では、この錬金術的概念は名称が化学的元素と同じであるにすぎない。実をいえば、アンチモンは神秘的変容を引き起こす実体であり、最高の天上界から降下し、暗い物質界の最深奥に潜んで解放を待っているのである。しかしこの深みに果敢に飛び込み、暗黒の闇のなかで火の業苦に焼かれ、自ら変容することによって王を救出しようとする者は誰ひとりいない。誰も王の声を聞き分けることができず、聞こえるのは破壊と混沌の轟きだと思い込んでいる。錬金術師のいわゆる「われらの海」とは、彼ら自身の暗部、すなわち無意識のことである。
エピファニウスは、「深い沼(limus profundi)」を「精神から産み出されたもの、つまり卑猥な想念や穢らわしい罪の意識」と解釈し、彼の立場から正確に意味づけた[063]。苦悶するダヴィデの言葉、「わたしは深い沼にはまり込み足がかりもありません」は、この見地から納得できるものとなる(『詩篇』69・3)この教父の解釈によれば、こういう暗く深い「沼」は悪そのものというほかなく、王がそれにとらわれているのは、おのれの罪深さのためである。
錬金術師の見解はもっと楽観的であった。魂の暗い背景に隠されているのはたんに悪だけでなく、救済を求めかつ救済される可能性のある王であるとして、たとえば『哲学者たちの薔薇園』では次のようにいう。「作業の最終段階にいたって王が出現する。それは王冠を戴き太陽のごとく輝き紅玉のごとき光を放ち、……火のなかにあっても不変の存在である」[064]。そして無用におわった第一質料については、「灰を軽蔑するなかれ。それは汝の心臓の戴く王冠にして、持続する事物の灰なればなり」[065]という。
184
以上の引用から、<王の子>という比喩的形象にまつわる神秘的雰囲気が、ある程度明らかになったと思う。哲学的錬金術の中心をなす諸観念が自由に検討されていた、あの遠いグノーシス派の時代に読者の注意を促したことは、無駄であったとは思わない。グノーシス派特有の類比的思考の真諦を知るうえで、ヒッポリュトスは最も完壁な資料となっているが、その思考法は錬金術師の方法と相似している。16世紀前半に錬金術を手がけた者であれば、必ずやグノーシス派のいくつかの観念に魅惑されたはずである。マイアが生きかつ著作にたずさわったのは、パラケルススより70年以上のちであったし、またパラケルススが異端的思想の研究家と交わっていたと想定できる理由は何一つないけれども、錬金術関係の文献、とりわけ彼のしばしば引用するヘルメス(図6)についての豊富な知識からして、王の子とか「母なる自然」讃美の表象が — これはキリスト教の立場と完全に一致するとはいえない表象であるが — 彼に強く印象づけられていたと考えてさしつかえない。
図6
山上の王の子と秘儀導師ヘルメス。明らかに「悪魔の誘惑」(ルカ 4章)への暗示がある。これに添えられた文は次のようにいう。「容器のなかにインドの山がもう一つあり、<霊>と<魂>は、子として、案内者としてそれに登った」。両者が霊と魂と呼ばれるのは、それらが第一質料を熱している間に立ち昇る揮発性の実体を象徴するからである(ラムプスプリンク「賢者の石について」図版XIIより。『ヘルメスの博物館』、フランクフルト a.M., 1678年)。 |
たとえば「へルメス黄金論説」にはこうある。「万物をつらぬく最強なる自然よ、汝は万物の最深奥に宿るいのちであり、かっそれをあまたの事物に分かち与える。光とともに来り、光とともに生まれ、また霧深き闇を生起せしめたるものよ、汝こそ万物の母なり」[066]。この祈願の調子には、自然に対する古典的な感情の響きがあり、文体は、デモクリトスに擬せられていた論文や『ギリシア魔術のパピルス』など、最古の錬金術文献のそれを思わせるところがある。
『パピルス』には、「王冠を戴くべき王の子」とか「王の血をひくわれらの子」という表現が出てくるが、それについては次のようにいわれている。「王の子は祝福されたる者にして、知恵ある者なり。知恵ある者の子らよ、きたれ。われらともに喜び楽しまん。死は克服され、すべて治むるは王の子なり。子は緋(chermes)の衣をまとえり」。王の子は「われらの火」から生まれ、自然が「小さき火」で「養育し、ととしえに生きるものとする」。この子が錬金術の作業によって生命を与えられると、「戦う火」あるいは「火の戦士」となる[067]。
F 蒸溜による<一>なる中心の産出
185
錬金術の基本的観念をいくつか取り上げて論じたので、イリアステルを変容させるためのパラケルススの方法がどういうものであるかという問題に、もう一度たちかえることにしよう。パラケルススは、この変容の過程を「レトルトによる蒸溜」と呼ぶ。錬金術においては、不純な身体から揮発性の霊という実体を抽出するのが蒸溜の目的であった。この過程は身体的経験であると同時に心的経験でもあった。「レトルトによる蒸溜」とは、専門用語として用いられていたわけではないが、おそらく蒸溜されたものが、何らかの形で蒸溜の過程自体に反作用する現象を意味するものであった。
この現象は、<ペリカン>と呼ばれる蒸溜器(図7)のなかで起こったのではないかと思われる。蒸溜物がレトルトのふくらんだ部分に逆流するのである。「循環的蒸溜」というこの方法は、錬金術師が大いに愛好し実践したものである。「千回もの蒸溜」を繰り返して、彼らは特に「純化された」ものを得ようとした[068]。パラケルススが目指したのも、そういうものであったといえなくもない。彼の目標は、人間の身体を極度に純化し、遂に最高の人間(maior homo)、すなわち内的・霊的人間との合一を達成して長寿にあずかることであったからだ。すでに述べたとおり、これは通常の化学的実験とは異なり、本質的に人間の心理的行動にかかわる。ここで用いられる火は象徴的な火であり、蒸溜は「人間の最深奥の中心から」(ex medio centri)始められなければならなかった。
図7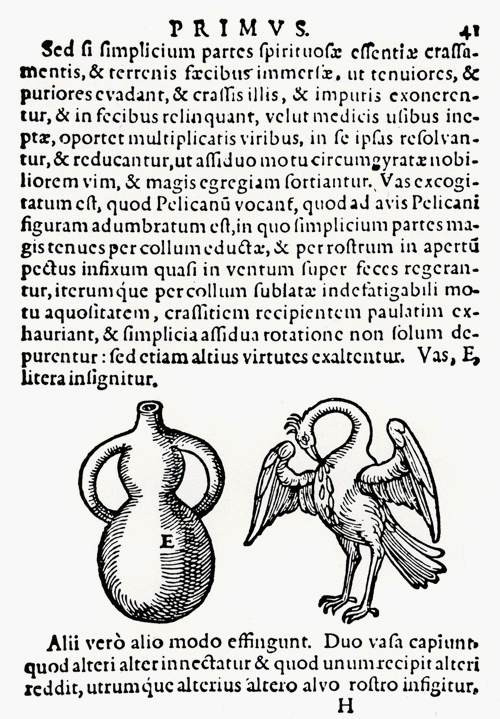
循環的蒸溜が起こる容骨=ペリカンの絵(レナヌス『容器の穴から太陽が出現する、あるいは金属鋳造の術』、フランクフルト a.M., 1613年)。 |
186
中心が強調されるのも錬金術の根本思想の一つである。ミヒャエル・マイアによれば、中心には「分割不可能な」原点があり、これは単純にして不壊の永遠の生命である。これに対応する物質が金であり、ゆえにそれは永遠を象徴する[069]。クリスティアノスにあっては、中心は楽園とその四つの河になぞらえられている。それは哲学的な意味での流動体(uJgrav)であり、中心からの流出物である[070]。「七つの遊星は地球の中心から生起したが、遊星の諸力はそこに残った。それゆえ地球の中心には、生命を胚胎する水がある」と『立ち昇る曙光』に書かれている[071]。またベネデイクトゥス・フィグルス[072]はこういっている。
地球の中心を訪れてみよ、
そこに球状の火があるだろう。
あらゆる穢れを除きこれを精留せよ、
愛と怒りをもってこれを駆り出せ……
彼はこの中心を「生命の家」とか「エノク」と名づけるが、後者は明らかにパラケルススからの借用語である。ドルネウスは、この中心を最も神に近い概念だという。いかなる空間を占めることもなく、人間の力で把握することも、見ることも、測ることも不可能だからである。したがって、中心とは、「神秘に満ちた無限の深淵」[073]である。中心に発する火はあらゆるものを上昇させるが、あらゆるものは熱が冷めると、また中心に落下する。「物理化学者はこの運動を循環的と呼び、作業の過程でそれを模倣する」。最高点に到達した諸元素は、下降する直前に「星辰の男精子を胚胎し」、下降中に諸元素の子宮(=昇華されていない元素)に入る。かくして、あらゆる被造物には四つの父性と四つの母性が関与していることになる。精子の胚胎は<太陽>と<月>の「流入と刻印」の結果である。それゆえ<太陽>と<月>は自然神として機能するといえるが、ドルネウスはそこまで明言していない[074]。
187
諸元素の創造、火力による諸元素の天への上昇は、錬金術的作業過程のモデルになる。地上的水は、慎重に火力を調整した火によって、まずあらゆる暗さを除去され、しかるのちに天上的水と分離されなければならない。「最終的には、この錬金術による胎児(foetus)は上昇によって天上的性質をおび、次に下降によって地球の中心の性質を具有して目に見える形をとるが、しかもなお上昇時に獲得した天上的性質は密かに保持されることになる」[075]。ここにいう錬金術による胎児(spagyrica foetura)こそ賢者の子にほかならない。それは死すべき人間の外殻の奥に潜む内的、永遠の人間である。賢者の子は、あらゆる身体的欠陥や病気を治す万能薬であるばかりではない。「人間の心のなかにある隠微な霊の病気」にも打ち勝つ。ドルネウスはこういう[076]。
「一者のなかに<一>にして<一>ならざるものがあるからだ。それは単一にして<四>から成る。これが太陽の火[077]によって浄化されると、純粋な水[078]が生ずるが、ふたたび単一の状態に返ると、それ〔四位一体〕[079]は錬金術の達人に神秘的なものの現成を証明するだろう。これが自然の英知の中心であるが、その周囲の領域はおのずと閉ざされて円を成している。すなわち測るべからざる巨大深遠な秩序がそこにあり、無限に通ずる」。「ここに<四>という数がある。その境界内で<三>が<二>と結合して<一>となり、かくして万物が現成するさまは、まさに奇跡的である」。
<四>、<三>、<二>と<一>とのこういう諸関係のうちに、「すべての知識と神秘的秘術の極致、すなわち万物の中心たる絶対不変の中心点が見いだされる」[080]とドルネウスはいう。一者が円の中心点であり、三つ一組をなすものの中心である。またそれは「第九の胎児」(foetus novenarius)、すなわち八つ一組をなすものに対しては<九>という数になり、四つ一組をなすものに対しては第五元素となる[081]。
188
中心部の中心点は火である。これを基点として、最も単純かつ完壁な形である円が形づくられる。この中心点は光の本質に最も近似し[082]、光は神の似姿(simulacrum Dei)である[083]。天上的水と地上的水のまんなかに天空が創造されたのとまったく同様に、人間のなかに輝く実体として根源的水分があり、これは天上界の水に由来する[084]。これは「恒星的バルサム」であり、動物の体温を維持する。天上界の水の精気が人間の脳髄に座を占め、そこにあって感覚器官を統御する。大宇宙における太陽のように、小宇宙にあってはパルサムが心臓に宿る[085]。輝く実体と星辰体(corpus astrale)であり、人間の内なる「星辰」、内なる「天空」である。天に輝く太陽のように、心臓に宿るパルサムは燃え輝く火の中心である。『賢者の群れ』[086]のなかにこの太陽的中心の観念が出てくるが、これは「卵の黄味のなかの原基」を指し、「原基が鶏の体温に温められて動き出す」。『合一の集い』では、卵の内部には四元素と「中心に赤い太陽点があり、これが鍵になる」[087]とされている。ミュリウスはこの鍵をヘルメスの鳥と解釈しているが[088]、これまたメルクリウスの蛇とほぼ同義の観念である。
189
以上の思想的脈絡からして、「レトルトによる中心点からの蒸溜」の結果、心的中心が活性化し、その働きが顕現してくることがわかる。心的中心という概念は、心理学的には自己の概念と
符合するものである。
G 春に達成される合一
190
パラケルススによれば、作業の最後にいたって「物理的稲妻」が走る。「土星の稲妻」が太陽の稲妻から分離するのだ。そして、この稲妻のなかに現れるものが、「長寿に関係し、疑うベくもなく偉大なあのイリアステルに固有の性質を持っている」[089]。この過程は身体の重みをいささかも奪うことがなく、ただ身体的な「動揺」のみを奪い去る。しかも「透明な色の働きによって」奪い去るのである[090]。他の錬金術師もまた、「精神の静謐」[091]を強調する。パラケルススは身体については何も語らない。身体は「悪く腐っている」。生きているといっても、ただ「ムーミア」のおかげで生きているにすぎない。その「絶えざる営み」は、腐敗し汚物となることだ。
「放浪する小宇宙(peregrinus microcosmus」はムーミアによって身体という物質を制御するが、そのためには秘薬が必要になる[092]。ここでパラケルススは(前には<ケイリ>を強調したが)、特に<テレニアビン>[093]とか<ノストック>[094]とか<メリッサ>の「恐るべき効力」を強調する。メリッサが特にここで称揚されているのは、古代医学において幸福の妙薬とされ、憂欝症の治療に、また身体内の「黒く焼けただれた血」を洗い清めるために用いられていたからである[095]。それ自体のなかに「天上的合一」の力が統合されていて、それは「イロク(Iloch)」であり、真のアニアドス(Aniadus)に由来する」。つい先ほどノストックについて語ったパラケルススの眼前で、イリアステルはすでにイロクに変化してしまっている。アニアドスという言葉が出てくると、今度はそれが合一の本質=イロクを構成するものとされる。
そもそも合一(coniunctio)とは何を指していわれているのか。これが言及されるに先立って、パラケルススは太陽と土星との分離について語っていた。土星の元素は冷たく暗く、また重く不純であり、太陽はその正反対である。この分離が達成され、メリッサによって身体が浄化されるとともに土星的憂鬱から解放されると、長寿を保つ内的人間との合一、つまり星辰的人間[096]との合一が可能になり、この合一から「エノク的半神」が生ずる。イロクとかアニアドスは永遠なる人間の神通力のようなものと思われる。この「驚異」は、「天と地の両世界に昂揚する力」の発現であり、「真の意味での五月」に起こる。「アニアドスの力の昂揚が始まるこの時期に、昂揚した諸力を結集すべきだ」。ここでもまたパラケルススは難解な語り方をする。けれども次の点だけははっきりとしている。つまりアニアドスは春のある状態を指示することで、ドルネウスの定義に従えば、それは「事物の霊能」であるということだ。
191
このモチーフはギリシア最古の文献の一つ、「祭司長コマリオスによるクレオパトラの教え」[097]と題された文献に出てくる。そのなかでオスタネス[098]とその仲間たちは、クレオパトラに次のよう
にいう。
教えて下さい、なにゆえに最高のものが最低のものに下降するのか、また中間にあるものが最高のものと最低のものとに近づき、それと一体になるのはなにゆえなのか[099]。祝福された水が天から落ちきたって、冥府のまんなかの暗闇につながれている死者たちを目ざめさせるのは、なにゆえなのか。不老長寿の霊薬が死者のもとにきたって、その眠りをさまし、彼らを目ざめさせるのは、なにゆえなのか。
192
クレオパトラは答える。
水が流れ込むと、閉じ込められた無力な死者たちの身体と霊を目ざめさせる……それらはやがてゆるやかに動きはじめ、立ち上がり、輝かしい色をおびてくる[100]、さながら春の花のように光り輝く色を。春は喜び、彼らが身にまとう豊かな花の成熟を楽しむ。
ルランドスの定義によれば、アニアーダ(Aniada)[101]とは「楽園的、天国的果実と力であり、またキリストの秘蹟でもある。……それは、思考、判断力、想像力の働きによってわれわれのなかの長寿を促進するもの」[102]といえよう。したがって、これに含まれる力は永遠の生命を授け、ケイリ、テレニアビン、ノストック、メリッサなどよりもさらに強力な不老長寿の霊薬(favrmakon ajqanasivaV)であるように思われる。それはコマリオスのいう祝福された水に対応し、また聖体拝領における神的実体に符合することも明らかである。
春はあらゆる生命力が祝祭的昂揚状態にある。そこで錬金術の作業も春に(しかも火星の支配する牡羊座(Aries)の月に、すでに)始めなければならない[103]。この時期にアニアドスの霊能的諸力を、あたかも薬草を集めるように「収集」しなければならない。ここには両義性がある。というのも、「収集」とは、あらゆる心的諸能力を結集するという意味にもなるからである。ポリフィロの聖なる結婚(hierosgamos)が実現するのも、同じく五月であるが[104]、これは神々の世界を具現する魂との合一を意味する。この結婚によって神的なものと人間的なものとが一体になる。それは「天と地の両世界の昂揚」である、とパラケルススはいう。
そして、次のようにつけ加えているところに重要な意味がある。「昂揚した刺草の生命もまた
燃え、小さな炎[105]の色がきらめき輝く」。刺草は治療のために(刺草の汁を調合して)用いられ、若葉の棘が最も鋭い五月に集められた。したがって、刺草は「情欲の火に最も駆られやすい」[106]青春の象徴であった。刺草とその燃える生命の小さな炎(flammula)という表現は、五月を支配するのがマリア
だけでなく、ウェヌスもそこに関与していることをそれとなく暗示する。その次の文では、この力は「別の何ものかに変化させる」ことが可能だ、と彼はいう。彼によれば、刺草よりはるかに強力かつ純粋な生命力、すなわちアニアドスに発する霊能的諸力があり、これは物質的元素界の子宮にではなく、天上的子宮に見いだされる。
原型的世界(Ideus)は、もし現象界より偉大なものを産み出すのでなかったならば、無に等しいだろう。だがそれは、現に天上的花々の咲き匂うもう一つの五月をすでに造りなしている。五月にアナクムス(Anachumus)[107]を抽出し保存しておかなければならない。「匂い玉[108]のなかに麝香が宿り、アヘンチンキ[109]のなかに金の効能が潜むように」。アナクムスの諸力が結集された時、はじめて人間は長寿にあずかることができる、とパラケルススはいう。私の知るかぎりでは、アナクムスとアニアドスを識別する方法は何もない。
 Barbaroi!
Barbaroi!