古代ギリシア案内古代ギリシアの軍制と戦術 |
[ ホメロス世界の戦闘形式]
ホメロス叙事詩の描く世界で、英雄(heros)と呼ばれるのは、族長としての貴族たちであった。
彼らは御者とともに二頭立ての戦車に乗り、あるいは徒歩で戦場に現れるが、戦闘の場合には前者も徒歩立ちになり、楯と槍とを主な武器として戦った。剣はクシポスと呼ばれる青銅の直刀を携えていたが、斬り合いにはあまり信頼性がなかったようで(『イリアス』第3書 361、第16書 337)、主にとどめをさすのに用いられたようである(『イリアス』第4書 530、第5書 146、第11書 146、第14書 496、第16書 332、第20書 459など)。
貴族戦士の楯は一般に頸から下をすっぽり覆うような、外見上8字形の大楯で、数枚の牡牛皮を張り重ねて金属で縁どられており、皮の部分だけでも重さ30キロと推定されている。したがって、片手で支えることかなわず、革紐で頸と左肩に懸けて用いられた。
槍は青銅の穂先を具え、投げ・突き両用の短いもので、ふつう1本だけ携行した。
戦車の利用は、手近に槍を用意するためにも、また重い楯を持って迅速に戦場を移動するためにも、輸送手段として不可欠であったと考えられる。
この完全武装の戦士貴族に対して、一般の将兵は粗毛を残した軽い皮楯(laiseion)で身を守り、槍や弓をその攻撃武器とする軽装兵で、氏族単位あるいは数氏族の集団をもって「墻壁(pyrgos)」と表現される密集戦列(phalanx)を構成した(『イリアス』第4書 335、347,第16書 280他)。しかし、ここでいう密集戦列は、古典期重装歩兵とは、その武器・装備、編成の均質性と戦闘行動の整一性を欠いている点で、いまだ大きな隔たりをもっていた。
戦闘の描写は、「砂塵の中でもみ合う」通常の接近戦(『イリアス』第11書148-152他)と、両軍が「青空のもと、おりおりは中休みしつつ遠く離れて」飛び道具で交戦する遠隔戦闘(『イリアス』第17書 370以下)とが交錯して見いだされる。
ホメロス詩において、貴族どうしの一騎討ちが戦闘の成り行きを決するかのように描かれているのは、もちろん、たんなる詩的誇張にすぎないが、一般将兵の集団戦闘も、個々の戦闘が戦局の全体を決定づけるような戦闘の統一性を欠いていたところに、当時の戦闘の特徴があったといえる。言ってみれば、いまだ「のどかな戦争」だったのである。
ところが、軽装兵集団がやがて軽装備から重装備へ、単純な集合体からより緊密な組織への転換を果たすことによって、軍組織の基幹部分として決定的な重要性を獲得するに至った。いわゆる重装歩兵(hoplites)による密集戦列(phalanx)の出現である。
その時期は明確ではないが、少なくとも前7世紀末ごろまでには、ほとんどすべてのポリスにおいて重装歩兵密集戦列が形成されたと見られる。この戦術・軍制上の変革は、同時に、貴族的国家体制からポリス的国家体制への社会意識の変革とも表裏一体をなすものであった。
[ アテナイの軍制]
アテナイの行政の根幹をなすのは「区(demos)」であるが、この区は、市域・沿岸・内陸の三地域に分けられ、それぞれがさらに10の区域に分割される。こうしてできた合計30の区域は、それぞれトリッテュス(trittys 「三分の一」の意)と呼ばれ、これを市部・沿岸部・内陸部からそれぞれ一つずつ選んで、合して一つの部族(phyle)を構成する。こうしてできた10部族が、アテナイの国制のみならず、軍制においても根幹をなした。
すなわち、軍隊は部族単位で編成され、これはtaxis(本文では「師団」と訳した)ないしphyleと呼ばれた(taxisは重装歩兵部隊、phyleは騎兵部隊というふうに使い分けられる場合もある)。また将軍も各部族から1名、計10人が選出された(後には、民会の挙手採決で選ばれるようになった)。といっても、将軍が自分の選出母胎の部族を指揮するわけではない。
(10人の将軍の役割分担については、アリストテレス『アテナイ人の国制』第61章を参照)。
各部族の重装歩兵を直接指揮するのは、同じく各部族から挙手選出された師団指揮官(taxiarchos)であり、師団指揮官は自分の部族の人々を率いるとともに、lochos(本文では「旅団」と訳した)の指揮官(lochagos)の任命権を有する。
同様に、騎兵を直接指揮するのは、各部族から挙手選出された部族騎兵指揮官(phylarchos)であった。これの上官は騎兵指揮官(hipparchos)で、こちらは民会で二人が挙手選出され、それぞれ5部族ずつの騎兵を分掌したという。
アテナイ市民の両親から生まれた男子は、18歳になると、区の集会で市民としての資格審査を受け、正式な市民として登録されると同時に、ムニキアにある兵舎で共同生活を送りながら、1年間の軍事訓練を受ける。これが終わると、アッティカ周辺の城砦に配属されて、さらに1年間の守備隊勤務に就かねばならなかった。(この2年間の年齢の若者は準-壮丁(hebe)すなわちephebosと呼ばれた)。
20歳から50歳までの市民は、重装歩兵や騎兵として現役軍に加入することが義務づけられ、50歳になると、60歳までは退役軍人として予備役に編入された。
[ スパルタの軍制]
スパルタの場合、諸々の制度も教育も、すべては「スパルタ人共同体を守るための戦士を育てる」というただ一つの目的に奉仕させられ、その徹底ぶりは、*野蛮なまでの合理性*に貫かれていた。
丈夫な子を産むために、娘たちも身体を鍛えることを求められ、その種目も徒競走や円盤投げといった陸上競技から、格闘技・槍投げといった軍事訓練にまで及んでいた。アルキダモス2世の娘キュニスカは、オリュムピア競技に女として初めて参加し、戦車競技で2度優勝したという。
生まれた子は国家の共有物であって、その子を育てるかどうかを決定する権限は父親にもなかった(プルタルコス「リュクルゴス伝」16)。そして7歳になると、男子は親元を離れて「少年隊(agelai)」に配属され、ここで共同生活を送りながら、少年監督官(paidonomoi)の統制のもとで厳しい教育を受ける。
スパルタでアテナイのephebosに相当するのはirenないしはeirenと呼ばれる若者で、徹底した軍事教育を施されて20歳になると、一人前の戦士として軍隊に編入されるが、依然として同期生と寝食を共にし、30歳になるまでは兵舎を離れることはなかった。
60歳以上の高年者と官職にある者、および3人の息子の父親は兵役を免除されたものの、60歳以上の年齢層にも国内防衛の義務だけは留保されていた。
アテナイの軍隊編成が10部族制に依拠していたのに対し、スパルタではこれを放棄し、地域偏差をなくした統一的な軍事組織を実現していたところにも、スパルタの合理主義が見て取れる。そこで、スパルタを例に、重装歩兵密集戦列の構造を見てみよう。
[ スパルタの重装歩兵密集戦列]
重装歩兵(hoplites)は、左手だけで支える直径約1メートルの青銅製の円楯(aspis)と胸甲とで武装し、長さ2メートル強の突き槍をその攻撃武器とした。楯の防御効果は主として左半身にあったが、右半身は同じ戦列の右隣に立つ兵士の楯で間接的に保護される。
密集戦列の構造は、横3列、縦深8層、これに指揮官1名がついて計25名で最小戦闘単位――これをenomotia(「結盟隊」の意)という――を形成した(自分の両横に立つ兵士をparastates、前に立つ兵士をprostates、後ろに立つ兵士をepistatesと呼ぶ)。
さらに、enomotia二つでpentekosteus(「五十人隊」の意)、pentekosteus二つ(したがって、enomotiaなら四つ)でlochosを構成していた。
といっても、これはあくまで基本であって、前418年夏のマンティネイアの戦いでは、ラケダイモンはenomotiaを4列8層に組んだと言うし(『戦史』第5巻 68節)、前371年のレウクトラの戦いの時には、enomotiaを3列12層で引率したという(『ヘレニカ』 第6巻 第4章 12節)。したがって、enomotiaの兵員は実際には32-36名といったところであったろう。
前4世紀になると、それまでのlochosはmora(本文では軍団と訳した)と改称されたようで、一つのmoraは4つのlochos、8つのpentekosteus、16のenomotiaから構成され、このような軍団が全軍で6個(前5世紀の初めには5個、ペロポンネソス戦争中には8個に増強されていた)、それぞれを軍令官(polemarchos)が指揮した模様である。
外征は概して中堅年齢層を中心に全軍の三分の一ないし二を動員して行われたが、非常事態の時には、たとえばレウクトラ戦(前371年)のように、最初から55歳までを動員し、その敗戦後さらに60歳までの市民と官職にある者を追派した例も見られる(『ヘレニカ』 第6巻 第4章 17節)。
[ 重装歩兵密集戦列の戦術]
重装歩兵の弱点は、装備の重さからくる機動力の欠如とともに、攻撃武器である槍を持った右側面の無防備さにあった。このことは密集戦列についても同様である。
このため、両勢力が戦闘に入ると、右翼の最先端にある兵士は、敵方が自分の無防備な右側に入り込むのを防ごうと急ぎ、戦列は右翼にむかって押し出されることになる。相手勢力も自軍の右翼でもって対する敵方の左翼をとり巻こうとする。
このせめぎ合いの中で、自軍の右翼が敵左翼を突き崩すことができれば、敵勢は自軍の左翼と右翼とによって挟撃され、文字通り殲滅されることになる。
かくして、右翼は最も危険度が高く、それゆえに最も名誉ある持ち場とされ、ギリシア連合軍が戦うときは、右翼はスパルタ兵の定位置であった(ヘロドトス『歴史』第9巻 第22章参照)。
この伝統的な戦法に改良を加えたのが、エパメイノンダス率いるテバイの斜陣隊形(loxe phalanx)であった。エパメイノンダスの改良は、従来の「全戦列を同じ縦深(8〜12層)にして同時に攻撃する」という原則を捨てたことにあった。
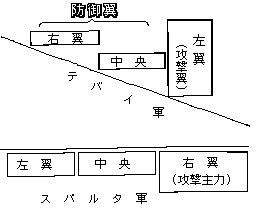 具体的に、不敗を誇ったスパルタ軍団を撃破したレウクトラ戦について見れば、縦深12層という伝統的な密集戦列を採用したスパルタ軍に対し、テバイ軍は前線を全体として左翼から右翼へと斜め右下がりに構えさせ、しかも、敵の攻撃主力である右翼に対置するに、縦深50層以上に及ぶ攻撃翼を集中的に配置し、自軍の右翼と中央部とは騎兵・軽装兵の援護のもとに堅固な防禦陣を組ませ、こうすることで、自軍の左翼が敵の攻撃主力である敵右翼と最初から衝突し、圧倒的な戦力でもってこれを破り、戦局を一気に決しようとしたものであった。
具体的に、不敗を誇ったスパルタ軍団を撃破したレウクトラ戦について見れば、縦深12層という伝統的な密集戦列を採用したスパルタ軍に対し、テバイ軍は前線を全体として左翼から右翼へと斜め右下がりに構えさせ、しかも、敵の攻撃主力である右翼に対置するに、縦深50層以上に及ぶ攻撃翼を集中的に配置し、自軍の右翼と中央部とは騎兵・軽装兵の援護のもとに堅固な防禦陣を組ませ、こうすることで、自軍の左翼が敵の攻撃主力である敵右翼と最初から衝突し、圧倒的な戦力でもってこれを破り、戦局を一気に決しようとしたものであった。 そして、この狙いは的中した。王を戦死させたことのなかったスパルタが、(レオニダス王以来初めて)クレオムブロトス王の戦死という屈辱をなめたのであった。
しかしながら、斜陣隊形は、防禦翼があまりに早く敵左翼と接触し、自軍の攻撃翼が相手陣を突き崩すまでもちこたえられないと、結局は相討ちになってしまうという指揮上の難しさがあったため、エパメイノンダスの戦死とともに、あまり見るべき成果をあげられなかった。しかし、ピリポス2世、アレクサンドロスという親子に確実に引き継がれていったのである。
【参考文献】
大牟田章「ギリシアの軍事組織――その形成と発展――」古代史講座5(学生社)
 Barbaroi!
Barbaroi!