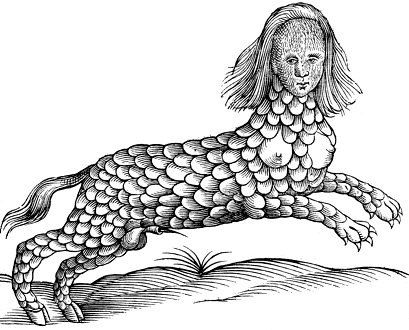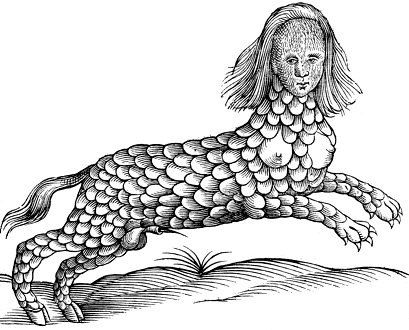第7話
メーデイア(medeia)について
参考図「ラミア」
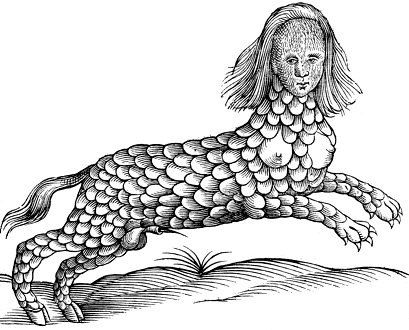
メーデイアと言われる動物がいるが、これが見出されるのはスキュティア地方つまりは北方で、そこにはゴットイ族、ダネイス族、(だからスキュタイ族をも、古の人たちは、すべて北方地区の住人と呼んでいた)。で、この動物はまったく獰猛このうえなく、このうえなく激情的、なおかつ最高に敵意に満ちた、つまりはまったくの裏切り者と言われている。というのは、書かれてきたところでは、自分の怒りにまかせて自分の仔どもを殺し、その後、一瞬も一時も反省することなく、殺害後も八つ裂きにして抹消した、しばしば子殺しメーデイアを云った人によれば……そうして彼女のみが、子どもたちを私的に裏切ることができる、ということである。
解釈。そういう次第で、メーデイアとは、このうえなく激情的で、このうえなく悪意に満ちた、無思慮このうえない、つまりは裏切り者の親たちの顔を意味するとは、古の書が聖人のために解釈するとおりである。他の箇所でも、「多衆は」— 使徒パウロスが…〔エペソにいるキリストに忠実な聖徒たち〕…に向かって謂う —「わたしたちの子どもを育て、主の訓戒と正義によって教育し、裏切ることのないよう」〔Cf. エペソ6:4〕。後には自然究理家が言った、「激情的な親たちは、自分自身の子どもたちを裏切る者たちでもある」と。ソロモーンも『箴言』の中で言う、「父親は子どもたちの誇り(kauvchma)」〔箴言17:6〕。わたしはこう思うのだが、父親を誇りと言うからには、勇気や希望がなければ他になく、慈悲を行ずるに勇気や希望によるのではなく、むしろ…〔欠損〕…人たちさえいるのだから、裏切ることこそ憐れむべきことである。なぜなら、メーデイアは動物である、そうして激情と野蛮な自然本性にしたがってこれをなす。ところが人間は、これをなすのは、自然本性に外れてであり、メーデイアより劣っているのである。なぜなら、自然本性にしたがったことは共通であり、よくあることだが、自然本性に外れたことは滅多になく、憐れむべき驚異である。哀れ、子どもらがしばしば悪評に陥り、なおそのうえに狂気や俘囚、あるいは彼らが弱さを遍歴し、無思慮のせいであれ、気が狂ってであれ、それらのことをこうむり、同様にピュトーンの息をもその上にしばしばこうむり、本来の〔親たち〕さえもはや彼らの世話をせず、それどころかむしろ無思慮に嘲弄するとしたら、いかなる言葉、あるいは、言葉の仕方によって、自分たちの身を神にゆだねるであろうか。されば、あなたも、人間この賢明なるものよ、メーデイアのごとく行ってはならない、むしろ福音と自余の神的な諸書の言辞にしたがって行え。
されば、美しくも自然究理家はメーデイアについて言った。
註
もちろん、ギリシア神話の「メーデイア」が下敷きになっているのであろうが、子殺しという点では「ラミア」と共通するところがあると考えられるので、「ラミア」について、ジョン・アシュトン『奇怪動物百科』(p.64-67)からの引用 —
ラミア
ラミアは今でこそ神話の怪物だが、かつては顔と胸が人間の女で、残りが蛇身というアフリカの怪獣であった。よそ者を誘惑して食らい、言語能力はなかったがシューシューという耳に快い音を出した。あるものの信ずるところによれば、ラミアは美しい女の姿で幼子を誘惑して食らう精霊であった。また、あるものによれば、ラミア伝説はジュピター〔ギリシア神話ではゼウス〕が美女のラミアと浮気したことに由来している。夫の浮気に怒ったジューノー〔へーラ〕がラミアを蛇身に変え、彼女の子供を皆殺しにした。それでラミアは気が狂い、自暴自棄になって手当たり次第に子供を食らうようになったというのである。
トプセルは怪物としてのラミアを語るまえに神話のラミアについて次のように述べている。
「リュキアの人メニッポスについてこんなことが伝えられている。彼はあるとき見知らぬ女に恋をした。女は美しく、やさしく、金持ちのように見えた。しかし事実はそうでなく、幻以外の何ものでもないのであった。彼女は次のようにして彼の親交に取り入ったということだ。彼がある日コリソトからセンロエへ歩いていると、美しい女性(じつは幻)と出会った。女は彼の手をとると、私はフェニキアの女ですが、これまで長いことあなたをお慕いもうしておりました、その胸のうちをお伝えしようと機会を求めておりましたが、今までかないませんでした。どうか私の家をお見知りおきください、といってコリントの郊外にあった家の方を指さし、彼の来訪を強く望んだ。メニッポスはかくも美しい女性から求愛され、その誘惑に簡単にまけて、しばしば女のもとへ通った。
ある賢者がいた。彼はメニッポスが女のもとへ通うのをみて、『美しい女に愛されているメニッポスよ、汝は蛇なのか、蛇を養っているのか?』といった。そのことばによって賢者はメニッポスに最初の諌め、あるいは非難の予告、をしたのである。しかし効き目はなく、メニッポスは幻の女にプロポーズした。というのも、彼女の家は豪華な家具が備わった豪邸に見えたからだ。そこで賢者は再びいった。『こうした金銀の装飾はタンタラスのリンゴのようなものじゃ。《華麗に見えるが実質は何もない》とホメロスのいっているあれじゃ。まさにそのように、汝がどのように思おうとも、汝の見ているものは幻なのだ。なぜなら、それらは汝が信ずるようにたくらまれた幻像、幻影にすぎないからじゃ。汝の花嫁はラミアあるいはモルと呼ばれている鬼女の一人なの心ゃ。彼女らは人間の男との交わりを望み、その肉をこよなく愛する。誘惑されたものは、その後はただ肉をむきぼり食らわれるだけなのじゃ』
賢者のそのことばで、金銀の皿も家具も料理人も召し使いもみな消え失せた。するとその鬼女はよよと泣き出し、どうか私を苦しめないでください、私の正体を告白させないでくださいと賢者に頼んだ。しかし賢者は情け容赦なく、本当のことをいわせたのである。それによると、彼女は精霊で、彼女の目的はメニッポスと交際し、彼に快楽を与えて肥えさせ、その後でたっぷり食しようというのであった。つまり、連中の親切な愛情というのは、ただ単に、美しい男を食べるためだけなのであった……」
「さて」とトプセルは続ける。「こうした架空のラミア伝から、手もとにある真実のラミア伝に向かうとしよう。『イザヤ書』34章から、我々はこれがへブライ語でリリトと呼ばれる怪獣であり、古代文明人からはパベルの都市を乗っ取るようにけしかけられたラミアと翻訳されたものであることを知る。同様に、『エレミア書』「哀歌」第4章の中の《ドラゴンが乳房をさしだす》と英訳されているところで、この《ドラゴン》がへプライ語ではEhannumとなっており、それは、釈義学者によると、ドラゴンではなく海の子牛のことであり、海の子牛とは怪獣一般をさす語だというのである。しかし、よく調べてみると、どうやらこの怪獣はラミアのことだと思えてくるのだ。それは、何よりもまずその大きな胸のせいで、そんな大きな胸はドラゴンのでも海の子牛のものでもないからだ。そしてこの怪獣が聖書に記録されているということで、それは確かに存在していたと認めてよいだろう。ディオンは、リピアにもそうした女面で美しい獣がいると述べている。それはいかなる絵かきもまねできない大きな美形の胸をもち、とくに前部の色が鮮やか。翼はなく、声もドラゴンのようなシューシューという声のみ。陸の獣の中で最も足が速く、何ものもそれから逃げのびることはできない。駿足によって獲物に追いつき、誘惑によって男どもを征服する。すなわち、男を見つけると胸を開いてみせ、その美しさによって男を引き寄せ、十分引きこんだときに食い殺すのである。
カエリウスとジェラル・ド・パリはそうした事柄に加えて、リビアのある奇怪な場所のことも語っている。そこは海岸の近くで、砂だらけの、まるで砂海といったところ。周辺はすべて砂漠である。たまたま難破などで人がこの岸に来ることがあると、これらの獣はその人間を見張り、この地を探険しようとしている人間であれ海に戻ろうとしている人間であれ、すべて食べてしまうという。また、付け加えて曰く、その獣は人間の男を見つけると、彼が来るまでじっと動かず — 自分の乳房を見つめたり、地面を見つめたりして — 待っている。男がこちらを見たら、自然の魔力によって引きつけられるように、その近くにやって来るのを計算してである。……プロプス皇帝がそれらを見世物として公にしたとき、それを見た人々のあるものが断言したように、この獣の後ろ身は山羊のごとくであり、前肢は熊、上半身は人間、そして体じゅうがドラゴンのように鱗でおおわれている。また、この獣は自分の子供も食らうので、そこから、すなわちラミアンドから、ラミアという名が出てくる、ともいわれている。この獣についてはこれくらいにしよう。」
イザヤ書34:14のヘブライ語は「リーリート」 Lilith.。
Lilith.。
これを音写したギリシア語は"Lilivq"、七十人訳では"ojnokevntauroV"となっている  セイレーンたちと馬身ケンタウロスたち.。が、シンマコス訳ではギリシア神話の"lamiva"に変えられた。
セイレーンたちと馬身ケンタウロスたち.。が、シンマコス訳ではギリシア神話の"lamiva"に変えられた。
欽定訳では「メンフクロウ(owl)」を充てている。
画像はトップセル『四足獣』から。