大阪大学 小浦久子地域とテーマ・コミュニティの連携パートナーシップ推進モデル事業:山手234番館活用実験 |
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
大阪大学 小浦久子
地域とテーマ・コミュニティの連携
パートナーシップ推進モデル事業:山手234番館活用実験
横浜市

|
| 修復中の山手234番館 |
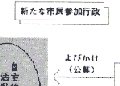
|
| パートナーシップ推進モデル事業のめざすもの |
![]() この委員会は22名で構成され、 地元住民、 地域活動団体とともに、 9名の一般公募(市外の人もある)が参加している。 1年間の検討会を経て、 日常管理マニュアルをつくり、 ボランティア(横浜シティガイド協会)によるインフォメーション機能と館内を整備し、 3ヶ月間の開館期間中に、 様々な展示や企画を行った。 行政スタッフと連携し、 多くの市民ボランティアの協力を得た。 この実験活用の経験が、 室内の改装や設備の計画に活かされており、 公開後の管理・企画の検討も実行委員会を中心に進められている。
この委員会は22名で構成され、 地元住民、 地域活動団体とともに、 9名の一般公募(市外の人もある)が参加している。 1年間の検討会を経て、 日常管理マニュアルをつくり、 ボランティア(横浜シティガイド協会)によるインフォメーション機能と館内を整備し、 3ヶ月間の開館期間中に、 様々な展示や企画を行った。 行政スタッフと連携し、 多くの市民ボランティアの協力を得た。 この実験活用の経験が、 室内の改装や設備の計画に活かされており、 公開後の管理・企画の検討も実行委員会を中心に進められている。
![]() 山手地区のまちづくりは「山手地区基本構想1982」が始まり。 平成4年に、 来街者の駐車場問題に対応する懇談会ができた。 住民、 学校関係者、 地元事業者はそれぞれ地域への思いが異なり、 市が主導してきた洋館の修復によるまちづくりは、 来街者に目が向いていると、 とられることも多かった。
山手地区のまちづくりは「山手地区基本構想1982」が始まり。 平成4年に、 来街者の駐車場問題に対応する懇談会ができた。 住民、 学校関係者、 地元事業者はそれぞれ地域への思いが異なり、 市が主導してきた洋館の修復によるまちづくりは、 来街者に目が向いていると、 とられることも多かった。
![]() このモデル事業は、 地域住民だけでなく、 公募参加や活動団体が参加することで、 山手の環境を守りつつ、 どのようなまちづくりをしていくかを考えるきっかけともなった。 まちの歴史や洋館に関心を持つ地域外の人々(テーマ・コミュニティ)の参加が、 地域内の利害をこえた活動を生む力になったという。
このモデル事業は、 地域住民だけでなく、 公募参加や活動団体が参加することで、 山手の環境を守りつつ、 どのようなまちづくりをしていくかを考えるきっかけともなった。 まちの歴史や洋館に関心を持つ地域外の人々(テーマ・コミュニティ)の参加が、 地域内の利害をこえた活動を生む力になったという。