いままでの都市計画とまちづくり都市計画兵庫県都市計画課 小松原祐二 |
1 都市計画
(1)都市基本計画
![]() 日本語としての「都市計画」の定義は、 「都市生活に必要な交通・区画・住宅・衛生・保安・経済・行政などに関し、 住民の福利を増進し公共の安寧を維持するための計画(広辞苑第3版)」、 「都市における交通の便利と住宅の整理と住民の幸福とを目的として改良を施す計画(広辞林第5版)」とされており、 都市部で何かをしようと企てることは全て都市計画の範疇に入ると考えて良い。
日本語としての「都市計画」の定義は、 「都市生活に必要な交通・区画・住宅・衛生・保安・経済・行政などに関し、 住民の福利を増進し公共の安寧を維持するための計画(広辞苑第3版)」、 「都市における交通の便利と住宅の整理と住民の幸福とを目的として改良を施す計画(広辞林第5版)」とされており、 都市部で何かをしようと企てることは全て都市計画の範疇に入ると考えて良い。![]() しかし、 専門家の間では、 都市計画は「都市というスケールの地域を対象とし、 将来の目標に従って、 経済的、 社会的活動を安全に、 快適に、 能率的に遂行せしめるために、 おのおの要求される空間を平面的、 立体的に調整して、 土地の利用と施設の配置と規模を想定し、 これらを独自の論理によって組成し、 その実現をはかる技術である。 (「都市計画」日笠端S52)」というような、 物的計画に限定されたものとされるが、 同書のなかでも「わが国では都市計画というと、 街路・公園・上下水道などの都市施設の建設事業と考えられてきた。 しかし、 都市計画は単なる建設技術や工学であってはならない」と喝破されているように、 単なる施設の建設計画ではない。
しかし、 専門家の間では、 都市計画は「都市というスケールの地域を対象とし、 将来の目標に従って、 経済的、 社会的活動を安全に、 快適に、 能率的に遂行せしめるために、 おのおの要求される空間を平面的、 立体的に調整して、 土地の利用と施設の配置と規模を想定し、 これらを独自の論理によって組成し、 その実現をはかる技術である。 (「都市計画」日笠端S52)」というような、 物的計画に限定されたものとされるが、 同書のなかでも「わが国では都市計画というと、 街路・公園・上下水道などの都市施設の建設事業と考えられてきた。 しかし、 都市計画は単なる建設技術や工学であってはならない」と喝破されているように、 単なる施設の建設計画ではない。
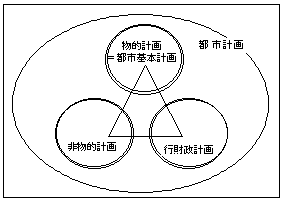
![]() なお、 広辞苑等による都市計画には、 経済計画などの非物的計画や行財政計画をも含んでいる。 非物的計画は都市における活動の計画、 物的計画はその活動が行われる場の設定、 行財政計画はそれらを実現するための行政の行動の裏付け、 という関係で3者を整理できる。 以下、 このメモでは誤解を避けるため、 物的計画の部分を「都市基本計画」といい、 これを扱うこととする(図1)。
なお、 広辞苑等による都市計画には、 経済計画などの非物的計画や行財政計画をも含んでいる。 非物的計画は都市における活動の計画、 物的計画はその活動が行われる場の設定、 行財政計画はそれらを実現するための行政の行動の裏付け、 という関係で3者を整理できる。 以下、 このメモでは誤解を避けるため、 物的計画の部分を「都市基本計画」といい、 これを扱うこととする(図1)。
(2)都市基本計画の構成(体系)
ア 土地・施設計画
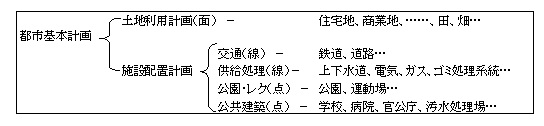
![]() 都市を形作る土地と施設に着目して、 物的な計画対象によって細分化する方法で、 われわれが一般的にイメージするのはこれである。 なお、 市街地開発事業は、 これらの個々の計画の実現を図るために、 あるまとまりのある区域について公的機関が直接、 または民間誘導により総合的な開発や保全をおこなうものであり、 再開発や区画整理それ自体が都市基本計画というものではない。
都市を形作る土地と施設に着目して、 物的な計画対象によって細分化する方法で、 われわれが一般的にイメージするのはこれである。 なお、 市街地開発事業は、 これらの個々の計画の実現を図るために、 あるまとまりのある区域について公的機関が直接、 または民間誘導により総合的な開発や保全をおこなうものであり、 再開発や区画整理それ自体が都市基本計画というものではない。イ 環境計画
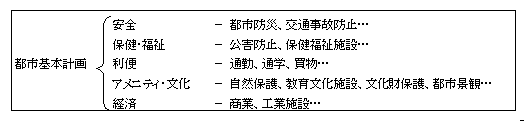
![]() 人間の生活を中心とする都市環境計画ともいうべき視点から細分化する方法。
人間の生活を中心とする都市環境計画ともいうべき視点から細分化する方法。ウ 地域計画
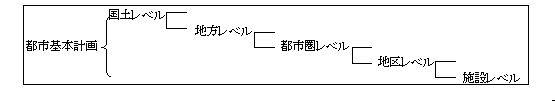
![]() 計画の設定エリアと計画密度によって細分化する方法。
計画の設定エリアと計画密度によって細分化する方法。
(3)都市基本計画の作成の標準となる考え方
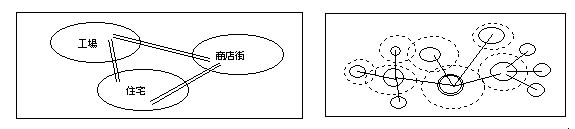
![]() 上記のア、 イは、 基本的には切り口が違うだけで同じものである(同じものであるべきである)。 また、 ウは、 ア・イのなかの考え方を示していると見ることもできる。 これらは都市を織りなす縦糸と横糸の関係といってもよいが、 現在の都市基本計画は、 一般的にはアの構成で作成される。 この場合の標準的な考え方を典型化して示したのが、 図5である。 左は、 機能の分化、 特化を行うため(例えば住宅地、 商業地等)にゾーニングをし、 各ゾーン間を必要な都市施設(道路、 鉄道等)で結ぶというものであり、 右は、 核と圏域という考え方で都市の構造を解析しようとするものある。
上記のア、 イは、 基本的には切り口が違うだけで同じものである(同じものであるべきである)。 また、 ウは、 ア・イのなかの考え方を示していると見ることもできる。 これらは都市を織りなす縦糸と横糸の関係といってもよいが、 現在の都市基本計画は、 一般的にはアの構成で作成される。 この場合の標準的な考え方を典型化して示したのが、 図5である。 左は、 機能の分化、 特化を行うため(例えば住宅地、 商業地等)にゾーニングをし、 各ゾーン間を必要な都市施設(道路、 鉄道等)で結ぶというものであり、 右は、 核と圏域という考え方で都市の構造を解析しようとするものある。
2 都市基本計画と都市計画決定(都市計画法)
(1)都市計画法
![]() 都市計画法にいう「都市計画」とは、 「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと(第2条)」を基本理念に、 「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、 都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、 第2章の規定に従い定められたもの(第4条)」と規定されている。
都市計画法にいう「都市計画」とは、 「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと(第2条)」を基本理念に、 「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、 都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、 第2章の規定に従い定められたもの(第4条)」と規定されている。![]() 第2章では整備・開発・保全の方針、 線引き、 地域地区、 都市施設、 市街地開発事業、 地区計画等、 都市計画基準などの内容と定めるべき事項等及び都市計画を決定する者、 案の縦覧等、 告示などの計画を決定する際の手続き等についての規定が記載されている。 従って、 これらの内容で、 このような手続きに従って定められた計画が、 法にいう「都市計画」である。 このうち、 整開保には都市基本計画のような機能を持たせることができるが、 その他については都市の環境形成の全てを目的とするものではない。 なお、 この計画(法定都市計画)を定めることが「都市計画決定」である。
第2章では整備・開発・保全の方針、 線引き、 地域地区、 都市施設、 市街地開発事業、 地区計画等、 都市計画基準などの内容と定めるべき事項等及び都市計画を決定する者、 案の縦覧等、 告示などの計画を決定する際の手続き等についての規定が記載されている。 従って、 これらの内容で、 このような手続きに従って定められた計画が、 法にいう「都市計画」である。 このうち、 整開保には都市基本計画のような機能を持たせることができるが、 その他については都市の環境形成の全てを目的とするものではない。 なお、 この計画(法定都市計画)を定めることが「都市計画決定」である。![]() なお、 法定都市計画の構成は都市基本計画の構成のうち1(2)アに示した土地・施設計画の体系によっていることは明らかである。
なお、 法定都市計画の構成は都市基本計画の構成のうち1(2)アに示した土地・施設計画の体系によっていることは明らかである。
(2)都市計画決定の内容
![]() 法定都市計画の最大の意味は、 基本理念にもうたわれているように、 私権の制限を伴うということにある。 ゾーニングにより土地利用の目的(建築物の用途)等が制限され、 都市施設が計画された場所では土地を利用することそのものが制限される場合もある。 しかし、 逆にそのことが法定都市計画の範囲を狭めている、 すなわち都市基本計画と同じものではなくなるという結果をもたらしているともいえる。
法定都市計画の最大の意味は、 基本理念にもうたわれているように、 私権の制限を伴うということにある。 ゾーニングにより土地利用の目的(建築物の用途)等が制限され、 都市施設が計画された場所では土地を利用することそのものが制限される場合もある。 しかし、 逆にそのことが法定都市計画の範囲を狭めている、 すなわち都市基本計画と同じものではなくなるという結果をもたらしているともいえる。![]() 「財産権はこれを侵してはならない。 財産権の内容は、 公共の福祉に適合するように、 法律でこれを定める」という憲法29条の規定により、 我が国では公共の福祉に適合する範囲でのみ私権を制限できることとなっており、 法定都市計画による制限もその例外ではない。 「公共の福祉」の範囲についての感じ方は時代によりまた人により異なるであろうが、 少なくとも都市基本計画に定められていること(定めるべきこと)の全てについて私権の制限を可とするまでの国民的な合意は得られていない。 (整開保については、 法定都市計画であるが都市基本計画と同様に私権の制限は伴わない。 以降、 私権の制限を伴うもののみ法定都市計画という)。
「財産権はこれを侵してはならない。 財産権の内容は、 公共の福祉に適合するように、 法律でこれを定める」という憲法29条の規定により、 我が国では公共の福祉に適合する範囲でのみ私権を制限できることとなっており、 法定都市計画による制限もその例外ではない。 「公共の福祉」の範囲についての感じ方は時代によりまた人により異なるであろうが、 少なくとも都市基本計画に定められていること(定めるべきこと)の全てについて私権の制限を可とするまでの国民的な合意は得られていない。 (整開保については、 法定都市計画であるが都市基本計画と同様に私権の制限は伴わない。 以降、 私権の制限を伴うもののみ法定都市計画という)。![]() ともあれ、 私権の制限を伴うが故に、 法定都市計画の内容はある範囲―公共の福祉のために個人の権利を制限してもやむを得ないと大多数の国民が認める部分―に限定されざるを得ないこととなる。
ともあれ、 私権の制限を伴うが故に、 法定都市計画の内容はある範囲―公共の福祉のために個人の権利を制限してもやむを得ないと大多数の国民が認める部分―に限定されざるを得ないこととなる。![]() また、 国による補助金交付や税制優遇措置等のなかにも都市計画決定が条件となるものも多い。 これも都市計画決定=公共の福祉に資する、 という図式から導かれるものである。
また、 国による補助金交付や税制優遇措置等のなかにも都市計画決定が条件となるものも多い。 これも都市計画決定=公共の福祉に資する、 という図式から導かれるものである。
(3)都市基本計画と法定都市計画
![]() 都市基本計画は、 当然に実現を目指したものであり、 そのための手だてを講じていく必要がある。 具体的な手だてとしては、 (1)規制(そこに○○を建ててはいけない、 下水が通ったら水洗便所にしなければならない)、 (2)誘導(○○を建てたら補助金をあげる、 税金まけたる)、 (3)事業(公共が土地を買って○○をつくる)など、 いくつかのものがあるが、 都市基本計画それ自体は直接にはこのような手だてを持たない。 このため、 計画の内容の一部を都市計画法に定める線引き、 地域地区、 都市施設、 市街地開発事業等の法定都市計画にそれぞれ組み替え、(2)に述べたような私権の制限等の力を借りるのが一般的である。
都市基本計画は、 当然に実現を目指したものであり、 そのための手だてを講じていく必要がある。 具体的な手だてとしては、 (1)規制(そこに○○を建ててはいけない、 下水が通ったら水洗便所にしなければならない)、 (2)誘導(○○を建てたら補助金をあげる、 税金まけたる)、 (3)事業(公共が土地を買って○○をつくる)など、 いくつかのものがあるが、 都市基本計画それ自体は直接にはこのような手だてを持たない。 このため、 計画の内容の一部を都市計画法に定める線引き、 地域地区、 都市施設、 市街地開発事業等の法定都市計画にそれぞれ組み替え、(2)に述べたような私権の制限等の力を借りるのが一般的である。![]() しかし、 くり返しになるが、 法定都市計画は私権の制限を可とする内容に限定されるため、 都市の環境形成全般について規定する都市基本計画と同じものには成り得ない。 このような関係をイメージ化したものが、 次の図6である。
しかし、 くり返しになるが、 法定都市計画は私権の制限を可とする内容に限定されるため、 都市の環境形成全般について規定する都市基本計画と同じものには成り得ない。 このような関係をイメージ化したものが、 次の図6である。
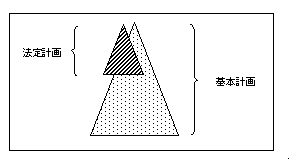
![]() 法定都市計画は都市基本計画の一部にすぎず、 さらに、 本当にやりたいこと(目標)からずれている場合もあり得る、 ということを示している。 例えば、 基本計画の中であるゾーンの目標を「戸建住宅地への純化」と規定したとしよう。 しかし、 法定都市計画のメニューには低層住宅地というものはあっても戸建に限定したものはない。 その場合、 次善の策として近いものを選択し法定計画として制限をかけるか、 あるいは法定計画とはせず規制とは別の方法(補助金や事業等)で実現を目指すか、 という選択を行うことになる。 都市施設においても同様のケースはあると思われる。
法定都市計画は都市基本計画の一部にすぎず、 さらに、 本当にやりたいこと(目標)からずれている場合もあり得る、 ということを示している。 例えば、 基本計画の中であるゾーンの目標を「戸建住宅地への純化」と規定したとしよう。 しかし、 法定都市計画のメニューには低層住宅地というものはあっても戸建に限定したものはない。 その場合、 次善の策として近いものを選択し法定計画として制限をかけるか、 あるいは法定計画とはせず規制とは別の方法(補助金や事業等)で実現を目指すか、 という選択を行うことになる。 都市施設においても同様のケースはあると思われる。![]() 都市計画法の条文上は、 特別用途地区や地区計画等を用いることにより、 上記のようなずれは生じないような定め方をすることは可能である。 しかし、 これはあくまで「条文上は」という条件付きの前提であり、 実際には「そのような定め=私権の制限が、 公共の福祉の名の下に許容されるか」という問いに耐えられるものばかりとは限らない。 もちろん都市基本計画全体は、 公共の福祉、 理想を追求して作成されるものであるが、 それを個のレベル、 計画のパーツのレベルで見たときには、 全てが私権の制限につながるものとは見なされていない。
都市計画法の条文上は、 特別用途地区や地区計画等を用いることにより、 上記のようなずれは生じないような定め方をすることは可能である。 しかし、 これはあくまで「条文上は」という条件付きの前提であり、 実際には「そのような定め=私権の制限が、 公共の福祉の名の下に許容されるか」という問いに耐えられるものばかりとは限らない。 もちろん都市基本計画全体は、 公共の福祉、 理想を追求して作成されるものであるが、 それを個のレベル、 計画のパーツのレベルで見たときには、 全てが私権の制限につながるものとは見なされていない。
3 人間サイズのまちづくり(まちづくり都市計画)
(1)いままでの都市計画
![]() 成熟社会の到来とともに、 いままでの都市計画のあり方について、 (1)自然領域へと都市が巨大化、 (2)生活よりも経済性・機能性を重視、 (3)個性に乏しく画一的、 という反省点が議論されるようになった。 これらの反省点を物的な面から振り返ってみれば、 (1)及び(2)は、 いわゆる高度成長社会―人口の急増、 右肩あがりの経済、 物質的な豊かさの希求―に応じた都市基本計画の策定と、 それの実現に向けた努力が実を結んだ結果ともいえる。 意に反して(1)、 (2)に責められるような都市(まち)ができたのではなく、 計画的につくってきたのである。
成熟社会の到来とともに、 いままでの都市計画のあり方について、 (1)自然領域へと都市が巨大化、 (2)生活よりも経済性・機能性を重視、 (3)個性に乏しく画一的、 という反省点が議論されるようになった。 これらの反省点を物的な面から振り返ってみれば、 (1)及び(2)は、 いわゆる高度成長社会―人口の急増、 右肩あがりの経済、 物質的な豊かさの希求―に応じた都市基本計画の策定と、 それの実現に向けた努力が実を結んだ結果ともいえる。 意に反して(1)、 (2)に責められるような都市(まち)ができたのではなく、 計画的につくってきたのである。![]() (3)については、 前述のように法定都市計画によるところが大きい。 都市基本計画で地域の特色を出しても、 それを大きな実効性が期待できる法定都市計画に落とし込む段階でほぼ全国一律に同じようなものとなるのであるから、 その結果としてのまちの姿もほぼ全国一律になる。 これも見方を変えれば都市計画法の成果である。
(3)については、 前述のように法定都市計画によるところが大きい。 都市基本計画で地域の特色を出しても、 それを大きな実効性が期待できる法定都市計画に落とし込む段階でほぼ全国一律に同じようなものとなるのであるから、 その結果としてのまちの姿もほぼ全国一律になる。 これも見方を変えれば都市計画法の成果である。
(2)人間サイズのまちづくりへ(まちづくり都市計画へ)
![]() 兵庫県では震災復興をとおして広く芽生えた住民による自発的かつ自律的なまちづくりへの取り組みに、 新しいまちづくりのあり方を見いだすことができた。 これが人間サイズのまちづくりという概念であり、 今後、 都市計画を策定し、 変更していく際のよりどころとなるものである。
兵庫県では震災復興をとおして広く芽生えた住民による自発的かつ自律的なまちづくりへの取り組みに、 新しいまちづくりのあり方を見いだすことができた。 これが人間サイズのまちづくりという概念であり、 今後、 都市計画を策定し、 変更していく際のよりどころとなるものである。![]() もちろん、 この概念は単に土地利用や都市施設のような物的なものに限らず、 経済や行財政など都市の活動をめぐるすべてに適用されるべきものであるが、 直接には物的なもの、 すなわち都市基本計画に大きく影響を与えるものとなる。 都市基本計画に人間サイズのまちづくりの概念を組み込んで変更したものを、 「まちづくり都市計画」という。
もちろん、 この概念は単に土地利用や都市施設のような物的なものに限らず、 経済や行財政など都市の活動をめぐるすべてに適用されるべきものであるが、 直接には物的なもの、 すなわち都市基本計画に大きく影響を与えるものとなる。 都市基本計画に人間サイズのまちづくりの概念を組み込んで変更したものを、 「まちづくり都市計画」という。
(3)まちづくり都市計画と法定都市計画
![]() 都市基本計画に人間サイズのまちづくりの概念を組み込み「まちづくり都市計画」として変更するとなれば、 法定都市計画との関係が問題となる。
都市基本計画に人間サイズのまちづくりの概念を組み込み「まちづくり都市計画」として変更するとなれば、 法定都市計画との関係が問題となる。
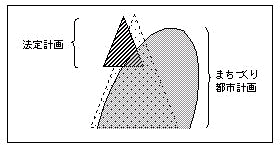
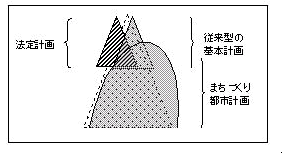
![]() 図7は、 まちづくり都市計画と法定都市計画との関係を大きく2つに分けて概念的に表したものである。 図7(a)は、 都市基本計画を純粋に人間サイズの観点からまちづくり都市計画に変更した場合である。 このときは、 現行の法定都市計画とまちづくり都市計画が乖離してくることが考えられる。 例えば、 極論すれば、 どんなに広域の、 国家的な観点から決定された都市施設(高速道路等)であってもその施設の近隣に住む者にとっては「我がまち」の一部であり、 人間サイズからのアセスメントを免れ得ないからである。
図7は、 まちづくり都市計画と法定都市計画との関係を大きく2つに分けて概念的に表したものである。 図7(a)は、 都市基本計画を純粋に人間サイズの観点からまちづくり都市計画に変更した場合である。 このときは、 現行の法定都市計画とまちづくり都市計画が乖離してくることが考えられる。 例えば、 極論すれば、 どんなに広域の、 国家的な観点から決定された都市施設(高速道路等)であってもその施設の近隣に住む者にとっては「我がまち」の一部であり、 人間サイズからのアセスメントを免れ得ないからである。![]() 一方、 図7(b)は、 法定都市計画にかかわる基本計画の部分は従来どおりの考え方により策定し(=変更しないで)、 それ以外の部分―私権の制限をするほどの公共の福祉は見いだせない部分―のみ人間サイズで見直しをする場合であり、 当然法定都市計画の変更の必要はない。 いままで法定都市計画をそのまま都市基本計画として施策展開をしていたが、 この度の人間サイズを契機に法定以外の計画を策定するような場合も、 このケースに含まれるだろう。
一方、 図7(b)は、 法定都市計画にかかわる基本計画の部分は従来どおりの考え方により策定し(=変更しないで)、 それ以外の部分―私権の制限をするほどの公共の福祉は見いだせない部分―のみ人間サイズで見直しをする場合であり、 当然法定都市計画の変更の必要はない。 いままで法定都市計画をそのまま都市基本計画として施策展開をしていたが、 この度の人間サイズを契機に法定以外の計画を策定するような場合も、 このケースに含まれるだろう。
(4)いま、 必要なこと
![]() いま、 必要なことは何であろうか。 今一度人間サイズのまちづくりを見てみよう。 都心における空洞化、 農山漁村における過疎化などにより脆弱化しつつある地域社会。 著しい経済の成長や人口の増加が終わり、 急速に少子高齢化が進む中で豊かな人間関係が形成されがたい地域社会。 投げかけられた様々な課題を解決するために、 地域の住民による主体的な創意工夫を生かしたまちづくりが求められている(まちづくり基本条例前文より)。
いま、 必要なことは何であろうか。 今一度人間サイズのまちづくりを見てみよう。 都心における空洞化、 農山漁村における過疎化などにより脆弱化しつつある地域社会。 著しい経済の成長や人口の増加が終わり、 急速に少子高齢化が進む中で豊かな人間関係が形成されがたい地域社会。 投げかけられた様々な課題を解決するために、 地域の住民による主体的な創意工夫を生かしたまちづくりが求められている(まちづくり基本条例前文より)。![]() そのような成熟社会におけるまちづくりの考え方を一言で表したものが「人間サイズのまちづくり」である。 まちづくりをリードしていくべき都市計画としては、 今後、 それに人間サイズのまちづくりの概念を組み込んだもので施策展開して行くべきであることは自明である。
そのような成熟社会におけるまちづくりの考え方を一言で表したものが「人間サイズのまちづくり」である。 まちづくりをリードしていくべき都市計画としては、 今後、 それに人間サイズのまちづくりの概念を組み込んだもので施策展開して行くべきであることは自明である。![]() 近く法定都市計画も国の管理下から一応は離れ、 県、 市町独自のものとなる。 従来は国からの通達と県の都市計画審議会のしばりによって実質的には全国一律の定め方しかできなかったものが、 自らの考えと自らの手で決めることができるようになるのである。 このような時期に新たな都市計画の考え方が芽生えたことは、 幸運である。 新しい考え方のもとで、 公共の福祉=私権の制限についてきっちり議論し、 成熟社会における都市計画決定のあり方を市町に示し、 また自らも実行することが県に求められている役割である。
近く法定都市計画も国の管理下から一応は離れ、 県、 市町独自のものとなる。 従来は国からの通達と県の都市計画審議会のしばりによって実質的には全国一律の定め方しかできなかったものが、 自らの考えと自らの手で決めることができるようになるのである。 このような時期に新たな都市計画の考え方が芽生えたことは、 幸運である。 新しい考え方のもとで、 公共の福祉=私権の制限についてきっちり議論し、 成熟社会における都市計画決定のあり方を市町に示し、 また自らも実行することが県に求められている役割である。![]() 仮に、 議論の結果、 まちづくり都市計画の実現を図るための私権の制限は難しい―制限してまでも実現を図るべきものとの県民的な合意は時期尚早―という結論になれば、 どうするのだろうか。 先の右図のように、 その部分のみ現在の法定都市計画の考えに則って(まちづくり都市計画の考えを離れて)私権の制限をかけていくのだろうか。 そうではないと思う。
仮に、 議論の結果、 まちづくり都市計画の実現を図るための私権の制限は難しい―制限してまでも実現を図るべきものとの県民的な合意は時期尚早―という結論になれば、 どうするのだろうか。 先の右図のように、 その部分のみ現在の法定都市計画の考えに則って(まちづくり都市計画の考えを離れて)私権の制限をかけていくのだろうか。 そうではないと思う。![]() 実現を図る手段は制限だけではない。 補助金等による誘導、 行政の直接事業等いくつかの手だてはある。 敢えて意に添わない内容の制限をかける必要はないだろう。 なにより、 そもそもまちづくりは権力の担保のもとで強制的に行われるべきものであろうか。 権力に担保され、 強制的に創り出された「人間サイズのまち」が果たして人々の生活の場となり得るのだろうか、 ということを考えてみるべきである。
実現を図る手段は制限だけではない。 補助金等による誘導、 行政の直接事業等いくつかの手だてはある。 敢えて意に添わない内容の制限をかける必要はないだろう。 なにより、 そもそもまちづくりは権力の担保のもとで強制的に行われるべきものであろうか。 権力に担保され、 強制的に創り出された「人間サイズのまち」が果たして人々の生活の場となり得るのだろうか、 ということを考えてみるべきである。
このページへのご意見はJUDIへ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
学芸出版社ホームページへ
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ