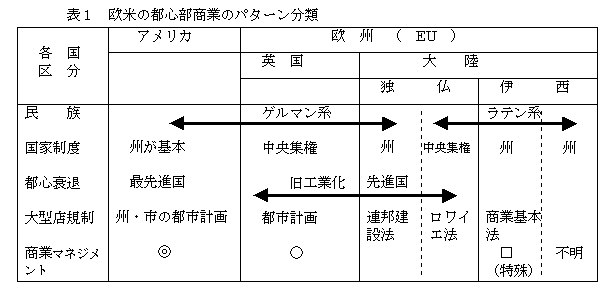コメント2まちづくり制度の各国比較DAN計画研究所所長 吉野国夫 |
資料:多様な個性発揮で活気づく欧州ラテン系都市
![]() 今日の資料は、 今年の2月に『福岡商工会議所欧州視察団』のコーディネーターとして渡欧した際の報告書の抜粋ですが、 これをもとにコメントしてみたいと思います。
今日の資料は、 今年の2月に『福岡商工会議所欧州視察団』のコーディネーターとして渡欧した際の報告書の抜粋ですが、 これをもとにコメントしてみたいと思います。![]() 今回の渡欧はイタリア(ローマ、 フィレンツェ)、 スペイン(バルセロナ)、 フランス(パリ)の中心市街地の現場を見ることが目的でした。 また、 1年前の2月にアメリカ東部のBID(ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト)の主なケースを見る機会がありました。 半年前には、 イギリス・ドイツの都市再生の現場を見てきましたし、 今日のテーマであるイタリアのまちづくりと他都市の比較をしてみるのも面白いかと思います。
今回の渡欧はイタリア(ローマ、 フィレンツェ)、 スペイン(バルセロナ)、 フランス(パリ)の中心市街地の現場を見ることが目的でした。 また、 1年前の2月にアメリカ東部のBID(ビジネス・インプルーブメント・ディストリクト)の主なケースを見る機会がありました。 半年前には、 イギリス・ドイツの都市再生の現場を見てきましたし、 今日のテーマであるイタリアのまちづくりと他都市の比較をしてみるのも面白いかと思います。
アメリカの制度(BID)と
それをモデルにした日本のTMO![]() 欧米の中心市街地活性化で、 一番進んでいるのはアメリカの制度です。 各市ごとにいろんな組織があるのですが、 ゆるやかなものから地区に税金をかけて環境整備や警備、 プロモーションまでするという本格的な組織まで様々に存在します。 テナントミックスまでまちづくりの現場では行なわれています。 そうした市街地活性化の試みがアメリカ全土で1200〜1500箇所行われているそうです。 成功しているところもあるのですが、 全部が成功というわけでもなく、 実際に見ても「これで成功か」と首を傾げてしまうところもありました。
欧米の中心市街地活性化で、 一番進んでいるのはアメリカの制度です。 各市ごとにいろんな組織があるのですが、 ゆるやかなものから地区に税金をかけて環境整備や警備、 プロモーションまでするという本格的な組織まで様々に存在します。 テナントミックスまでまちづくりの現場では行なわれています。 そうした市街地活性化の試みがアメリカ全土で1200〜1500箇所行われているそうです。 成功しているところもあるのですが、 全部が成功というわけでもなく、 実際に見ても「これで成功か」と首を傾げてしまうところもありました。![]() 日本でも中心市街地活性化の目玉としてTMO(タウン・マネジメント・オーガニゼイション)を導入しました。 TMOはアメリカのBIDをモデルにしたのですが、 実に中途半端な制度になりました。 BIDで行われているような権力も権限も財源もない形の制度ですから、 導入してから1年半も経たないうちに国でも「失敗だ」と言っている人もいます。 これから成功するかもしれないと言う人もいますが、 明らかに制度を修正する段階にきています。
日本でも中心市街地活性化の目玉としてTMO(タウン・マネジメント・オーガニゼイション)を導入しました。 TMOはアメリカのBIDをモデルにしたのですが、 実に中途半端な制度になりました。 BIDで行われているような権力も権限も財源もない形の制度ですから、 導入してから1年半も経たないうちに国でも「失敗だ」と言っている人もいます。 これから成功するかもしれないと言う人もいますが、 明らかに制度を修正する段階にきています。![]() 欧米、 特にアメリカでは中心市街地の衰退が悲惨なところまで行き着いています。 ロサンゼルスのダウンタウンは未だに歩けない状況です。 アメリカと比べたら、 ヨーロッパの都心は衰退したといってもまだ都心空間が機能していると言えるでしょう。
欧米、 特にアメリカでは中心市街地の衰退が悲惨なところまで行き着いています。 ロサンゼルスのダウンタウンは未だに歩けない状況です。 アメリカと比べたら、 ヨーロッパの都心は衰退したといってもまだ都心空間が機能していると言えるでしょう。
「行きたくなる商業ゾーン」に必要な要素は何か
![]() 中心市街地の活性化について、 先ほど井口さんは商業活性化というより文化のシンボルゾーン作りをするべきだとおっしゃいました。 確かに来てもらうのが商業の立場で、 行きたくなる街のひとつの解として文化のシンボルゾーンがあろうかと思いますが、 「行きたくなる商業ゾーン」というのもひとつの解としてあると思います。
中心市街地の活性化について、 先ほど井口さんは商業活性化というより文化のシンボルゾーン作りをするべきだとおっしゃいました。 確かに来てもらうのが商業の立場で、 行きたくなる街のひとつの解として文化のシンボルゾーンがあろうかと思いますが、 「行きたくなる商業ゾーン」というのもひとつの解としてあると思います。![]() その「行きたくなる商業ゾーン」をTMOでつくろうとしたのですが、 TMOの制度には財政的な裏付けがないのです。 中小企業庁の様々な高度化事業の枠組みにしても建設省の制度にしても、 市街地活性化のための新たな財政的な裏付けはありません。
その「行きたくなる商業ゾーン」をTMOでつくろうとしたのですが、 TMOの制度には財政的な裏付けがないのです。 中小企業庁の様々な高度化事業の枠組みにしても建設省の制度にしても、 市街地活性化のための新たな財政的な裏付けはありません。![]() TMOもひとつの組織ですからそれを支えるための財政的基盤が必要なのですが、 既存の商店街組織を残したまま新たにTMOを作っている状況ですので、 誰がお金を出して誰が利益を受けるのかという図式があいまいなままスタートしているのです。 うまく運営していけない状況にありますので、 今後どうしていけばいいのかという議論が盛んに行なわれています。
TMOもひとつの組織ですからそれを支えるための財政的基盤が必要なのですが、 既存の商店街組織を残したまま新たにTMOを作っている状況ですので、 誰がお金を出して誰が利益を受けるのかという図式があいまいなままスタートしているのです。 うまく運営していけない状況にありますので、 今後どうしていけばいいのかという議論が盛んに行なわれています。![]() 私はTMOという形を固定的に全国一律に考えるのではなく、 各都市で自由に枠組みを作っていけばいいと思っています。 その場合、 既存の商店街組合や組織をまとめてそれをTMOとしていくとか。 おそらくもう、 1都市1TMOでないとだめとか、 TMOはこうあるべしと国が指導していってもうまくいかないと思っています。
私はTMOという形を固定的に全国一律に考えるのではなく、 各都市で自由に枠組みを作っていけばいいと思っています。 その場合、 既存の商店街組合や組織をまとめてそれをTMOとしていくとか。 おそらくもう、 1都市1TMOでないとだめとか、 TMOはこうあるべしと国が指導していってもうまくいかないと思っています。![]() 福岡に唐人町という商店街があります。 そこは今、 再開発でとても面白い動きをしています。 法定再開発ではなくて、 建設省の優良建築物等整備事業という制度を使った開発ですが、 ひとつ完成して、 今は二つ目、 三つ目が動き出しているところです。 小さな商店街の中で、 再開発が連続して起きようとしているのですが、 それを動かしている組織がユニークなんです。 商店街組合、 非組合、 それぞれの事業組合などがあり、 これからの事業のあり方で参考になると思っているところです。
福岡に唐人町という商店街があります。 そこは今、 再開発でとても面白い動きをしています。 法定再開発ではなくて、 建設省の優良建築物等整備事業という制度を使った開発ですが、 ひとつ完成して、 今は二つ目、 三つ目が動き出しているところです。 小さな商店街の中で、 再開発が連続して起きようとしているのですが、 それを動かしている組織がユニークなんです。 商店街組合、 非組合、 それぞれの事業組合などがあり、 これからの事業のあり方で参考になると思っているところです。![]() 以上で私のコメントを終わります。
以上で私のコメントを終わります。
このページへのご意見はJUDIへ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
学芸出版社ホームページへ
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ