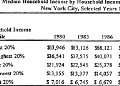
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
さて、 そういうグローバリゼーションのもとでは、 都市の中に住んでいる人の住宅問題が非常に厳しくなっています。
しかしニューヨークを見ていると、 住宅市場にグローバルな要因が大きく絡んでいるということに気がつきます。 こういう時代になると、 マーケット分析もドメスティックな因子だけではつかまえられないという印象です。
一言で言うと、 ニューヨークではアフォーダブルな住宅がものすごく足りなくなっています。 80年代から起こっている傾向ですが、 今になってどんどんひどくなっています。
「アフォーダブル住宅」とは、 きちっとした住宅がまあまあの負担で手に入るという、 いわゆる「低価格・低家賃のちゃんとした家」という程度の意味ですが、 それが全然足りないのです。
彼らは給料が高いので、 マーケットをホットにします。 あるいは、 うらぶれた街にどんどん入ってきてジェントリフィケーションを起します。 どんどん投資して、 かっこいい街に変化させるわけです。
また、 最近のニューヨークの論文を見ていて重要だと思ったのは、 グローバル企業の社員の給料は、 ローカルなマーケットと無関係に決まるという事です。
その地域の相場には関係なくべら棒な給料が出ますので、 地域の住宅の相場を気にせずに、 どんどんお金を使えます。 ですからローカルな相場とは関係が無い所で値段が吊り上がってしまうのです。 2。 世界都市の居住問題
アフォーダブル住宅の欠乏
これまで住宅問題について理解するために、 多くの専門家は国内のマーケットがどうなっているかを調査したり分析したりしていました。
ホットなハイ・エンド
何が起こっているかというと、 マーケットの上層の方ではファイアーのホットマーケットが形成されています。 ファイアーというのは、 finance、 insurance、 real estate、 つまり金融・保険・不動産といった脱工業都市の主要産業たるグローバル企業のエリート達の事で、 その雇用がものすごく増えているのです。
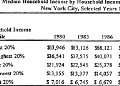
|
| 図表1 5分位階層別の平均的家計収入 |
グローバリゼーションによって、 トップにはものすごく裕福な階層が生まれるわけですが、 サービス経済の底辺では、 低賃金労働者がうごめいているわけです。
アフォーダブル住宅を減少させる要因の一つとして、 「アバンダンメント」があります。 これは住宅放棄の事です。
インナーシティの貧困地区では土地利用ができず、 地域がガラガラになっています。 低所得者ばかりになってくると、 家賃をもらってもペイしないので、 家主が物件を捨てて立ち去るわけです。
また80年代からホームレスが増えています。 最近は頭打ちになったものの、 10万人はいると推定されています。 公共部門のシェルターを利用しているのが、 そのうち6万人です。
日本でもちらほら増えてきましたが、 大阪では約1万人、 東京で約5千人ということですから、 やはり桁が違うという事が分かります。
HUD(ハッド)という日本の建設省住宅局みたいなところは、 どんどん小さくなってほとんど無くなりかけています。 公共住宅や補助付住宅の供給をやめ、 あるいは公共住宅を売り、 要するに公共介入を止めてしまって、 マーケットに任せようというわけです。
このような政策もあって、 先ほど申しましたようにニューヨークでは経済は今絶好調なんですが、 住宅事情はそれに反比例して、 どんどん厳しくなっています。
新自由主義の住宅政策
住宅が足りなくなった理由としては、 先ほど少しお話しましたが、 ネオ・リベラルな発想の住宅政策、 簡単に言うと住宅政策をやめようという政策があります。
このページへのご意見はJUDIへ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
学芸出版社ホームページへ