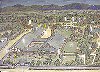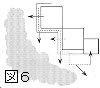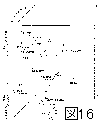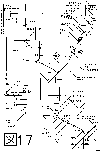シークエンスの基本単位
シークエンスを考える時に考慮すべきことには時間、 空間、 視点を中心とする人の行動、 そして人の記憶という要素があります。
 時間について言えば現実には現在という瞬間は捉えにくいものです。
時間について言えば現実には現在という瞬間は捉えにくいものです。
したがってここでは、 過去の時刻(ti-1)と現在の時刻(ti)との関係(ti/ti-1)を中心として捉え、 その時間での空間をそれぞれSi-1、 Siとして捉え、Si/Si-1を見ます。
次に、記憶を現在から見てすぐ前の記憶であるRi-1として扱います。
また視覚は先を見ますのでUi+1という様に未来も扱います(図1)。
シークエンスを考えるにあたっては区間が重要です。
例えば区間SiとSi+1と区切って、 その区間ごとの変化を捉えていくわけですが、 この区間をどうとるかについては、 いろいろと論があります。
庭園を研究されている進士氏は、 人間がゆったりと歩くときには5mおきくらいに変化がありそうだ、 とおっしゃっています。
私達の研究室でもベースとしては5mで考えているのですが、 狭い道ですともっと小さい単位で刻々と変化します。
脇に道があったり建物があったり変化するものが多いと、 もっと変化の間隔が狭まるのです。
一方広い道は変化が少なく、 間隔も広がると考えられます。
パノラマ性、 見通し性、 奥行き性
・東洋の庭園を例に
 寝殿造りのような視覚的に広角度に開かれた景観を、 パノラマ的景観と呼ぶと、 この場合は視座自体を動かすことなく、 広角の視野で眺めるわけですが、 シークエンスにとっては厄介なことです。
寝殿造りのような視覚的に広角度に開かれた景観を、 パノラマ的景観と呼ぶと、 この場合は視座自体を動かすことなく、 広角の視野で眺めるわけですが、 シークエンスにとっては厄介なことです。
それはシークエンスが区間ごとの変化性から成立するにもかかわらず、 少々首を左右に動かしてもあまり景観が変化しないからです。
イギリスの風景式庭園もパノラマ的なのですが、 それに加えて奥行き性が加わります。
例えば、 現在も見られる仁和寺の寝殿造りの南庭は奥行きの見通し性が弱く、 主にパノラマ性で支えられているのですが、 風景式庭園では大見通し性とパノラマ性が同時に存在しています(図2)。
一方書院造りの北の庭では、 部屋を分割してその中から庭を見ます。
視対象が同じようなものであっても見る場所が分割されていますと、 視野が限定されて額縁的空間となり、 結果として異なる部分が見えます。
 中国の頤和園(いわえん)はあまりに巨大すぎて遠景ばかりであり、 少々動いてもなかなかシークエンスが変わりません。
中国の頤和園(いわえん)はあまりに巨大すぎて遠景ばかりであり、 少々動いてもなかなかシークエンスが変わりません。
そこで手前に島を置いて中景をつくったりもしています(写真1)。
・西欧の場合―軸線性
 頤和園のようにワイドなパノラマ性と奥行き性の両方を持っていながら、 それらを別々に配している庭園として、 ヨーロッパの庭園ではヴェルサイユが挙げられます。
頤和園のようにワイドなパノラマ性と奥行き性の両方を持っていながら、 それらを別々に配している庭園として、 ヨーロッパの庭園ではヴェルサイユが挙げられます。 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ